解説記事2020年11月02日 税務マエストロ 令和2年度消費税改正(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限)(2020年11月2日号・№856)
税務マエストロ
令和2年度消費税改正(居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限)
#254
熊王征秀(税理士)
略歴
学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会調査研究部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員大原大学院大学教授
マエストロの解説
居住用賃貸住宅の取得費は、非課税となる住宅家賃に対応するため、本来仕入税額控除の対象とすることはできないのであるが、作為的に金の売買を継続して行うなどの手法により課税売上げを発生させ、物件取得時の消費税の還付を受けるとともに、課税売上割合の変動による税額調整の規定を回避しようとする事例が散見される。そこで、令和2年度改正では、建物の用途の実態に応じて計算するよう、「居住用賃貸建物」について、仕入税額控除制度を見直すこととしたものである。
今月は、令和2年度改正で創設された「居住用賃貸建物に対する仕入税額控除の制限」について確認する。
1 金の売買を利用した還付スキーム
(1)物件取得時の還付スキーム
居住用の賃貸物件であっても、建物が完成する課税期間における課税売上高が5億円以下であり、かつ、課税売上割合が95%以上となる場合には、その建築費の全額を仕入税額控除の対象とすることができる。そこで、課税売上割合を95%以上にするための様々な工作がなされているようである。
例えば、新設法人が設立事業年度中に賃貸マンションを新築するとしよう。この場合において、建物の完成を事業年度末に設定し、賃貸開始は翌事業年度からとする。さらに、建物が完成する事業年度において少額の金の売買を行った場合には、建物が完成する事業年度中の課税売上高は金の売上高だけとなり、結果、課税売上割合が100%(95%以上)となって、建物の建築費の全額を仕入税額控除の対象とすることができるのである。
(2)課税売上割合の変動による取戻し課税を回避するためのスキーム
本則課税の適用期間中に高額特定資産を取得した場合には、いわゆる「3年縛り」が強制適用となるために、課税売上割合が著しく減少した場合には、高額特定資産に係る当初の還付消費税額が、第3年度の課税期間で取戻し課税されることになる。
そこで、建物を取得した課税期間から第3年度の課税期間にかけて、変動率又は変動差のいずれかの要件を満たさなくなる程度に金を売買することにより、第3年度の課税期間における取戻し課税を回避しようとするものである。
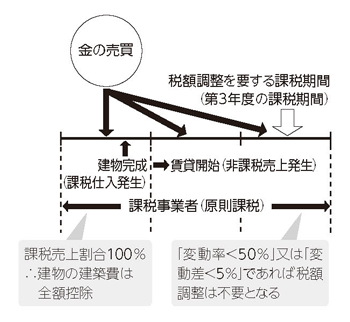
2 居住用賃貸建物と仕入税額控除の制限
(1)居住用賃貸建物とは?
仕入税額控除が制限される「居住用賃貸建物」とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物で、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に該当するものをいう。
(注)「居住用賃貸建物」には、その附属設備も含まれる(改消法30⑩)。
具体的には、建物の構造や設備の状況・その他の状況により住宅の貸付用でないことが客観的に明らかでない限りは居住用賃貸建物に該当することになる(消基通11−7−1)。
居住用賃貸建物の範囲について、建物の用途別に整理してみると次のようになる。
① 事業用の建物
店舗・工場などの事業用施設からは絶対に住宅家賃は発生しないため、居住用賃貸建物には該当しない。
② 賃貸用の建物
賃貸マンションやアパートなど、居住用の賃貸物件は居住用賃貸建物に該当する。
1階が貸店舗で2階が居住用の貸室となっているような物件は、1階から発生する家賃は消費税が課税されるものの、2階部分が居住用貸室となっていることから物件全体が居住用賃貸建物に該当することになる。
貸店舗・貸事務所・ホテルなど、すべてが事業用の賃貸物件からは絶対に住宅家賃は発生しないため、これらの物件は居住用賃貸建物には該当しない。
用途未定の賃貸物件は、居住用として賃貸することが想定されることから居住用賃貸建物に該当することになる。繰り返しになるが、『住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物でなければ居住用賃貸建物から除外することはできない』ということに注意しなければならない。
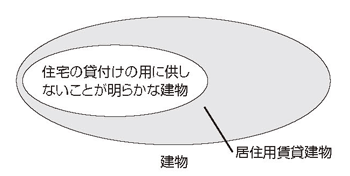
なお、用途未定の賃貸物件であっても、課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日において住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとすることができる(消基通11−7−2)。
③ 販売用の建物
いわゆる現住建造物(入居者が居住した状態の建物)として販売する目的で入居者付の建物を取得する場合には、取得と同時に住宅として賃貸していることとなるので、たとえ最終目的が販売用であったとしても、取得した物件は居住用賃貸建物に該当する。
ただし、店舗や事務所として賃貸中の現住建造物を販売目的で取得した場合には、住宅の貸付けの用に供しているものではないことから居住用賃貸建物には該当しない。
また、建売住宅や分譲マンションのような棚卸資産は、購入者が住宅として使用するものではあるが、販売者が住宅として貸付けるものではないことから、所有期間中に住宅として賃貸しないことを条件に、居住用賃貸建物に該当しないものとして取り扱うことができる。
(2)居住用賃貸建物の判定時期(消基通11−7−2)
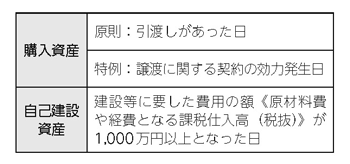
(3)仕入税額控除の制限(改消法30⑩)
現行法では、居住用の賃貸物件であっても、下表の①又は②に該当する場合には仕入税額控除が認められているところであるが、本年度の改正により、居住用賃貸物件の取得時における仕入税額控除はシャットアウトされることになった。

<留意点>
ⅰ 3年縛りの規定は、取得した居住用賃貸建物について、仕入税額控除が制限された場合であっても適用される(消基通1−5−30)。
ⅱ 居住用賃貸建物について、下記の取引が行われた場合にも、仕入税額控除は制限されることになる(改消令53の4③)。
① 代物弁済、負担付き贈与、現物出資などの資産の譲渡等に類する行為
② 土地収用法その他の法律の規定に基づく収用
(4)自己建設高額特定資産の取扱い
高額特定資産を自己建設する場合には、原材料費や経費となる課税仕入高(税抜)の累計額が1,000万円以上となった課税期間において、その「自己建設高額特定資産」を仕入れたものとして取り扱うこととされている(消法12の4①)。そこで、自己建設高額特定資産が居住用賃貸建物に該当する場合には、その仕入日の属する課税期間(原材料費や経費となる課税仕入高(税抜)の累計額が1,000万円以上となった課税期間)以後の課税期間中に発生した課税仕入れについてのみ、仕入税額控除を制限することとしている(改消令50の2②)。
よって、課税仕入高(税抜)の累計額が1,000万円以上となる課税期間より前に発生した課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の制限はない(消基通11−7−4)。
<具体例>
x1年中に居住用賃貸建物の建設を開始し、x2年において課税仕入れの累計が1,000万円以上となった場合には、x3年から物件が完成するx4年の翌々年であるx6年まで、本則課税が強制適用となる。
この場合において、x2年〜x4年中に発生した課税仕入れ(□の金額)については仕入税額控除はできない(x1年中に発生した課税仕入れ600は、仕入控除税額の計算に取り込むことができる)。
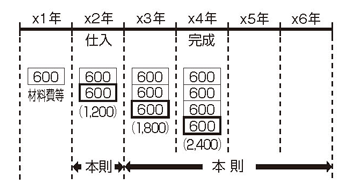
3 建物の取得価額
(1)店舗兼用賃貸住宅などの取扱い
居住用賃貸建物を、建物の構造や設備の状況・その他の状況により、商業用(賃貸)部分と居住用賃貸部分とに合理的に区分しているときは、居住用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除が制限される(改消令50の2①)。
具体的には、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物などについて、使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、その建物の実態に応じた合理的な基準により区分することになる(消基通11−7−3)。
(2)資本的支出
居住用賃貸建物に対する資本的支出がある場合には、その金額も「居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額」に含まれる。ただし、以下の場合のように、その資本的支出自体が居住用賃貸建物の課税仕入れ等に該当しない場合には、仕入税額控除の制限はない(消基通11−7−5)。
① 建物に係る資本的支出の金額が1,000万円未満であることなどの理由により、高額特定資産に該当しない場合
② 店舗のように、居住用賃貸部分でない建物に対する支出であることが明らかな場合
※資本的支出……事業の用に供されている資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その資産の価値を高め、又はその資産の耐久性を増すことになると認められる部分に対応する金額をいう。
4 調整税額の計算
(1)調整税額の計算方法
居住用賃貸建物の仕入日から第3年度の課税期間の末日までの間(調整期間)に、居住用賃貸建物の全部又は一部を課税賃貸用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの賃貸料収入と売却価額を基礎として計算した額を、第3年度の課税期間又は譲渡日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整することとされている(改消法35の2)。
<留意点>
ⅰ 「第3年度の課税期間」とは、「居住用賃貸建物の仕入日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間」をいう(改消法35の2③)。
ⅱ 居住用賃貸建物の仕入日から第3年度の課税期間の末日までの期間を「調整期間」という(改消法35の2①)。
ⅲ 居住用賃貸建物の仕入日から物件の売却日までの期間を「課税譲渡等調整期間」という(改消法35の2③)。
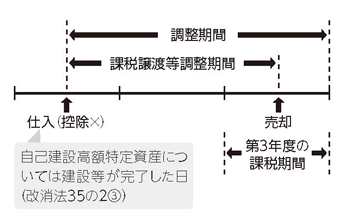
ⅳ 下記に該当する場合(みなし譲渡)にも税額調整の規定が適用される(改消法35の2②後段かっこ書)。
① 個人事業者が居住用賃貸建物を家事用に転用したとき
② 法人が居住用賃貸建物を役員に贈与したとき
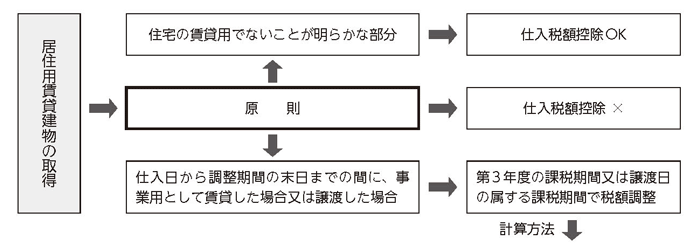
○ 居住用賃貸建物を調整期間中に課税賃貸用に供した場合(改消法35の2①③)
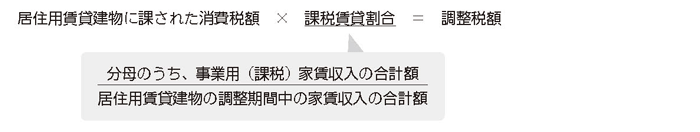
(注)「課税賃貸割合」は、調整期間中に発生した家賃収入の値引額等を控除して計算する(改消令53の2①)。
○ 居住用賃貸建物を調整期間中に売却した場合(改消法35の2②③)
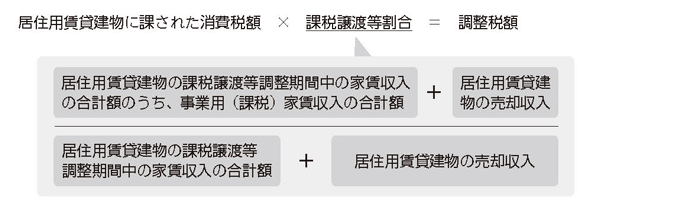
(注)「課税譲渡等割合」は、課税譲渡等調整期間中に発生した家賃収入と居住用賃貸建物の売却収入の値引額等を控除して計算する(改消令53の2②)。
(2)居住用賃貸建物を合理的に区分した場合
上記3(1)により、居住用賃貸建物を合理的に区分した場合には、居住用賃貸部分についてのみ、仕入税額控除が制限されることとなるので、調整税額の計算も、居住用賃貸部分についてだけすることになる(改消令53の4①)。
(3)自己建設高額特定資産の取扱い
自己建設高額特定資産が居住用賃貸建物に該当する場合には、原材料費や経費となる課税仕入高(税抜)の累計額が1,000万円以上となった課税期間以後の課税期間中に発生した課税仕入れについてのみ、仕入税額控除を制限することとしている(改消令50の2②)。
したがって、調整税額の計算についても、その制限された税額についてだけすることになる(改消令53の4②)。
(4)課税賃貸用の意義
居住用賃貸建物に対する税額調整は、居住用賃貸建物を住宅以外の用途で貸付けた場合でなければ適用できない。したがって、居住用賃貸建物に関連する駐車場の賃貸収入や水道代収入などの課税収入があったとしても、建物を住宅以外の用途で貸し付けたという事実がない限り、税額調整はできないことになる(消基通12−6−1)。
(5)課税業務用に転用した場合の取扱い
貸店舗などの課税業務用調整対象固定資産を3年以内に居住用(非課税業務用)に転用した場合には、転用日の属する課税期間で税額調整が必要となる。
これに対し、非課税業務用調整対象固定資産(居住用賃貸建物)を3年以内に課税業務用に転用したとしても、居住用賃貸建物についてはそもそも仕入税額控除の規定が適用されないので、非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入税額控除の調整もできないことになる。
居住用賃貸建物を取得して、第3年度の課税期間の末日までに課税業務用に転用した場合には、転用日以後に発生する課税家賃収入をベースに計算した「課税賃貸割合」により調整税額を計算することになる。
(6)中途で売却した場合の取扱い
居住用賃貸建物に対する「課税賃貸割合」による税額調整は、居住用賃貸建物を第3年度の課税期間の末日において保有していなければ適用できない。よって、居住用賃貸建物を売却したことにより第3年度の課税期間の末日に保有していない場合には、「課税賃貸割合」による税額調整ではなく、「課税譲渡等割合」により調整税額を計算する(消基通12−6−2)。
なお、居住用賃貸建物を中途で除却した場合には、「課税賃貸割合」と「課税譲渡等割合」のいずれの割合による税額調整もできないこととなる。
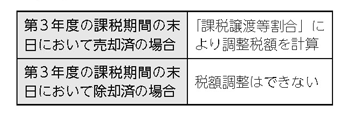
5 計算例
x1年度中に1,100,000(税込)で賃貸物件を取得した場合のx3年度における調整税額は次のように計算する(単位:省略)。
なお、x1年度からx3年度までの家賃収入(税抜)は下記のようになっており、入居者の募集広告は「居住用・事務所……」としていることから、当該物件についてはx1年度において仕入税額控除の対象とはしていない。
(年度) (課税される家賃収入) (家賃収入合計)
x1年度 1,600,000 2,000,000
x2年度 3,000,000 10,000,000
x3年度 800,000 8,000,000
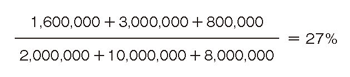
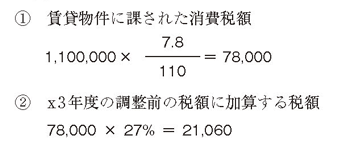
x1年度中に1,100,000(税込)で販売用の居住用現住建造物を取得し、x2年度において1,320,000(税込)で売却した場合のx2年度における調整税額は次のように計算する(単位:省略)。
なお、物件の取得時から売却時までの家賃収入は300,000である。
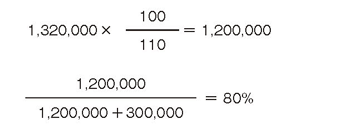
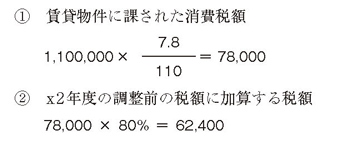
6 改正法の効果
販売目的で居住用の現住建造物を取得した場合には、その取得費は、非課税となる家賃収入と物件売却時に発生する建物売却金額のいずれにも対応するため、現行法では課税非課税共通用の課税仕入れに区分することとなる。
結果、取得費のうち、課税売上割合分しか仕入税額控除が認められていなかったのであるが、本改正により、建物の売却金額を反映させたところで税額調整ができることとなった。よって、取引の実態に即した改正であると評価することができそうである。
(注)販売目的で取得した現住建造物は課税売上対応分に区分すべきであるとの提訴に対し、東京地裁では、ムゲンエステート社については令和元年10月11日付で原告敗訴の判決を下したものの、エー・ディー・ワークス社については令和2年9月3日付で原告勝訴の判決を下している。本誌執筆の時点では、上告審の結果が出ていないことから、上記の解説は、あくまでも筆者の私見であることをお断りしておきたい。
7 適用時期
本改正は令和2年10月1日以後の取得物件について適用される。ただし、令和2年3月31日までに契約した物件については適用しないこととされている(令和2年改正法附則44)。
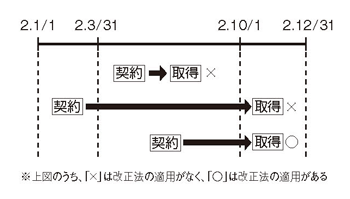
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















