解説記事2020年11月30日 税務マエストロ 居住用賃貸建物と控除対象外消費税額等との関係について(2020年11月30日号・№860)
居住用賃貸建物と控除対象外消費税額等との関係について
#255
熊王征秀(税理士)
略歴
学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会調査研究部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員大原大学院大学教授
マエストロの解説
令和2年度消費税改正により、居住用賃貸建物についてはその全額が仕入税額控除の計算から除外されることになった(No.856−2020.11.2号参照)。
では、税抜方式を採用した場合の居住用賃貸建物に対する仮払消費税等は、その全額が控除対象外消費税額等として認識され、繰延消費税額等として均等償却をすることができるのであろうか……?
とある支部での会員研修に参加された先生から、『法人税法施行令第139条の4(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)第5項を読む限り、居住用賃貸建物についてはそもそも仮払消費税等の計上が認められないのではないか?』という質問を頂いたことから、居住用賃貸建物と控除対象外消費税額等との関係について、本コーナーで検討することとしたものである。
1 控除対象外消費税額等の取扱い
税抜方式を採用している原則課税適用事業者の課税売上割合が40%で、一括比例配分方式を適用したケースについて考えてみる。この場合、仮払消費税等の40%だけが仕入税額控除の対象とされることから、残額の60%は控除されずに残ってしまうことになる。この残ってしまう部分のことを「控除対象外消費税額等」という。
したがって、税込方式を採用した場合はもちろんのこと、税抜方式を採用した場合であっても、課税期間中の課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上であることにより、課税仕入れ等の全額を控除した場合には、「控除対象外消費税額等」という概念はでてこないことになる。
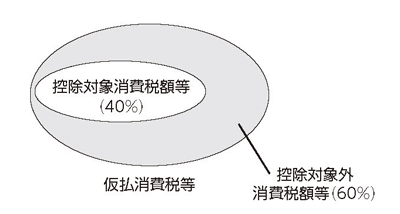
(1)交際費等に関する控除対象外消費税額等の取扱い
法人税法上、交際費等については資本金の額により、損金算入額が制限されている。この損金算入額の計算の基礎となる支出交際費等については、税込方式の場合には税込金額で、税抜方式の場合には税抜金額で計算することとなっている。
税抜方式を採用した場合で、控除対象外消費税額等のうちに交際費等に関するものがある場合には、その金額は、支出交際費等の額に含めたところで損金不算入額を計算することに注意されたい。
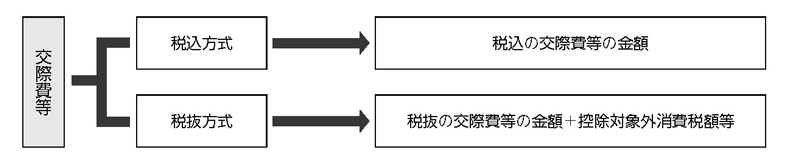
(2)繰延消費税額等の処理方法
資産に係る控除対象外消費税額等のうち、下記①〜③のいずれかに該当するものについては、支出時に費用処理することができる。
① 課税売上割合が80%以上の場合
② 個々の資産に係る控除対象外消費税額等の金額が20万円未満のもの
③ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等
控除対象外消費税額等について注意を要するのは、固定資産を購入した期の課税売上割合が80%未満で、かつ、その固定資産に係る控除対象外消費税額等が20万円以上の場合である。
この場合には、その控除対象外消費税額等については、次のいずれかの方法により処理することとされている(所令182の2、法令139の4)。
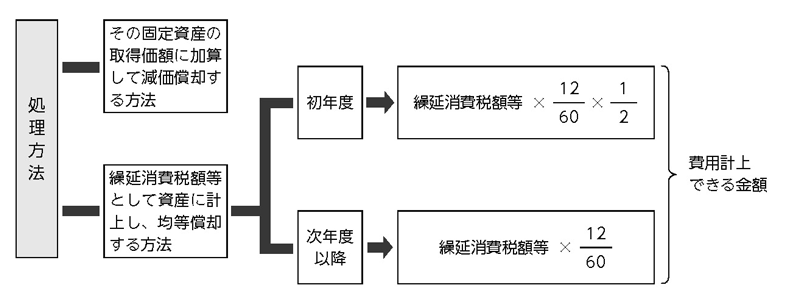
2 本則課税による計算例
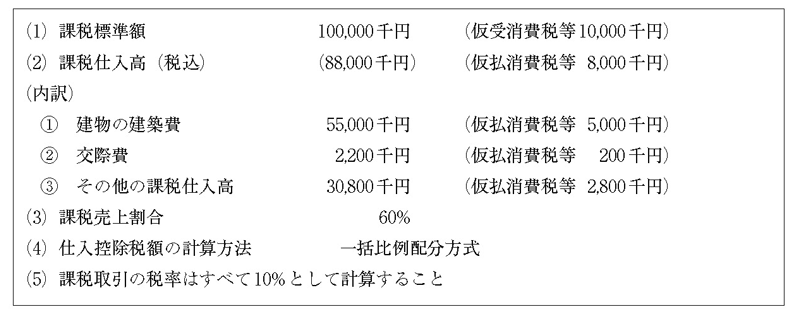
<納付消費税額及び地方消費税額の計算>
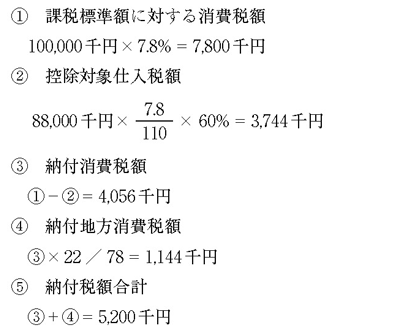
≪控除対象外消費税額等の計算≫
① 交際費等に係る控除対象外消費税額等は支出交際費等に加算する。
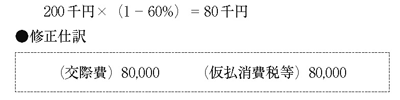
(注)修正仕訳をおこさずに、法人税法別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)で加算することもできる。
② 資産(建物)に係る控除対象外消費税額等については、課税売上割合が80%未満であり、その金額が20万円以上であることから繰延処理が必要となる。
(注)固定資産の取得価額に加算して減価償却することもできる。
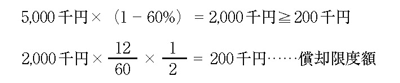
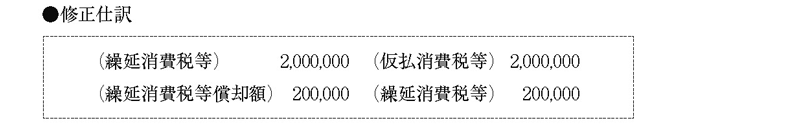
③ 仮払消費税等の残額については費用処理ができるので、仮受消費税等の残額を借方に、仮払消費税等の残額と未払消費税等の金額を貸方に計上し、貸借の差額(その他の課税仕入高に係る控除対象外消費税額等)を雑損失として処理する。
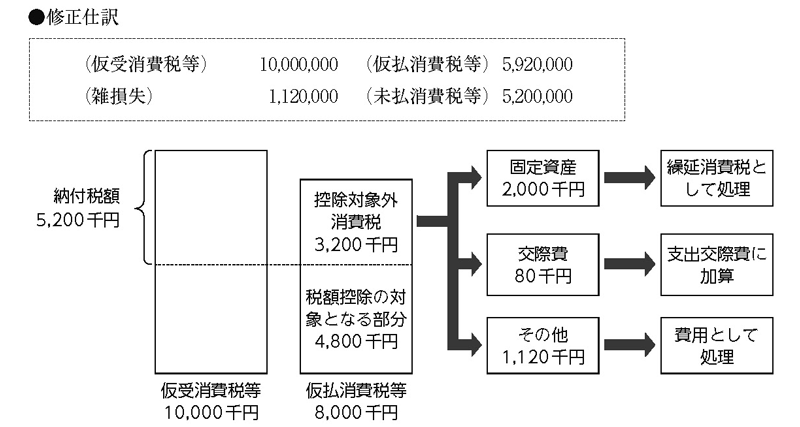
3 簡易課税と税抜方式の関係
簡易課税制度による場合であっても、税抜方式を採用することは何ら問題ない。
税抜方式を採用することにより、建物に課された消費税を繰延消費税額等として均等償却すれば、建物の取得価額を早期に費用化することが可能となる。よって、簡易課税制度の適用を受ける場合であっても、税抜方式の採用を検討する必要があろう。
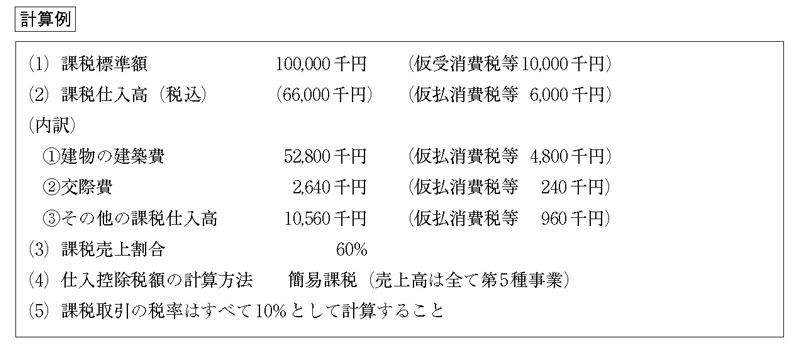
<納付消費税額及び地方消費税額の計算>
① 課税標準額に対する消費税額
100,000千円×7.8%=7,800千円
② 控除対象仕入税額
7,800千円×50%=3,900千円
③ 納付消費税額
①−②=3,900千円
④ 納付地方消費税額
③×22/78=1,100千円
⑤ 納付税額合計
③+④=5,000千円
≪控除対象外消費税額等の計算≫
① 控除対象外消費税額等の金額は、仮払消費税等の金額から、簡易課税の適用による控除対象仕入税額(3,900千円)と、地方消費税のうち控除対象仕入税額に相当する金額(3,900千円×22/78=1,100千円)を控除して計算する。
6,000千円−(3,900千円+1,100千円)=1,000千円……控除対象外消費税額等の金額
交際費等及び固定資産の取得に係る控除対象外消費税額等については、控除対象外消費税額等の合計額に仮払消費税額等の割合を乗じて算出する。
② 交際費等に加算される控除対象外消費税額等
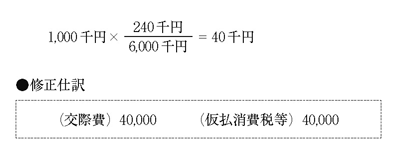
(注)修正仕訳をおこさずに、法人税法別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)で加算することもできる。
③ 繰延消費税額等
課税売上割合が80%未満であり、建物(固定資産)に係る控除対象外消費税額等が20万円以上であることから繰延処理が必要となる。
(注)固定資産の取得価額に加算して減価償却することもできる。
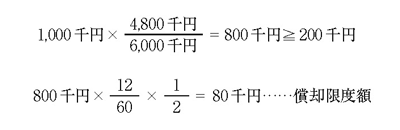
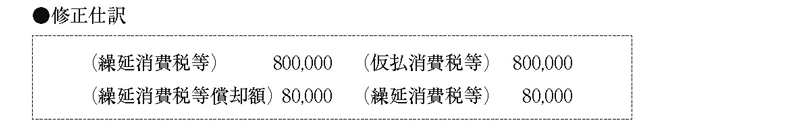
④ 消費税等の精算
仮受消費税等の残額を借方に、仮払消費税等の残額と未払消費税等の金額を貸方に計上し、差額を雑損失として処理する。
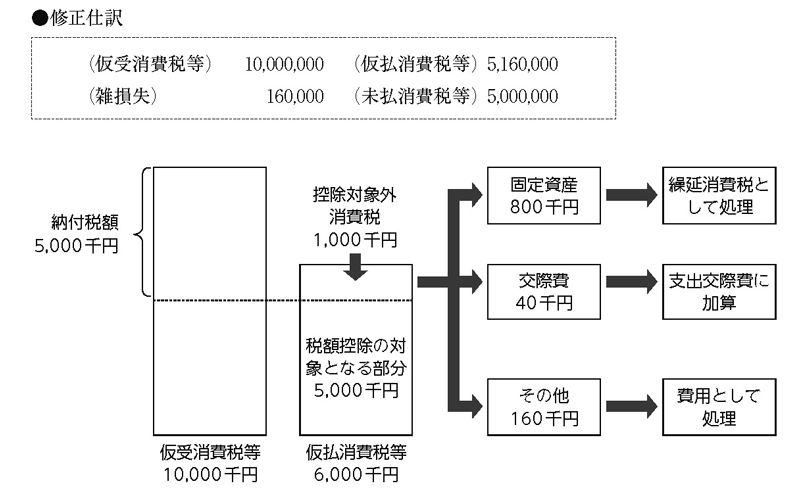
4 資産に係る控除対象外消費税額等の意義
控除対象外消費税額等とは、一般的には税抜方式を採用した場合において、仕入税額控除の対象とならなかった仮払消費税等と理解されているが、正しくは、法人税法施行令において次のように定義されている。
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
:
5 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない金額及び当該控除をすることができない金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額でそれぞれの資産に係るものをいう。
つまり、資産に係る控除対象外消費税額等とは、消費税法第30条第1項(仕入れに係る消費税額の控除)の規定の適用を受ける場合で、仕入金額を取引の対価(税抜価格)と仮払消費税額等(課税仕入れ等の税額+地方消費税の額に相当する金額)に区分する経理(税抜方式)をしたときにおける控除をすることができない仮払消費税等で資産に係るものをいうことになる。
ここで、「課税仕入れ等の税額」については、消費税法第30条第2項に規定されており、次の①〜③の税額をいうこととされている。
①課税仕入れに係る支払対価の額×7.8/110(6.24/108)
②特定課税仕入れに係る支払対価の額×7.8/100
③保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課された又は課されるべき消費税額
また、「地方消費税の額に相当する金額」は、課税仕入れ等の税額に22/78を乗じて算出することとされている(地法72の82〜83)。
消費税法第30条 仕入れに係る消費税額の控除
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、国内において行う課税仕入れ(特定課税仕入れに該当するものを除く。以下この条及び第32条から第36条までにおいて同じ。)若しくは特定課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の属する課税期間の第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額(以下この章において「課税標準額に対する消費税額」という。)から、当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れに係る消費税額(当該課税仕入れに係る支払対価の額に110分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)、当該課税期間中に国内において行つた特定課税仕入れに係る消費税額(当該特定課税仕入れに係る支払対価の額に100分の7.8を乗じて算出した金額をいう。以下この章において同じ。)及び当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物(他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この章において同じ。)につき課された又は課されるべき消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。次項において同じ。)の合計額を控除する。
:
2 前項の場合において、同項に規定する課税期間における課税売上高が5億円を超えるとき、又は当該課税期間における課税売上割合が100分の95に満たないときは、同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額、特定課税仕入れに係る消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額(以下この章において「課税仕入れ等の税額」という。)の合計額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により計算した金額とする。
:
10 第1項の規定は、事業者が国内において行う別表第一第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この項において同じ。)以外の建物(第12条の4第1項に規定する高額特定資産又は同条第2項に規定する調整対象自己建設高額資産に該当するものに限る。第35条の2において「居住用賃貸建物」という。)に係る課税仕入れ等の税額については、適用しない。
5 居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額の取扱い
(1)仮払消費税等を計上できないものとする考え方
控除対象外消費税額等については、法人税法施行令において次のように規定している。
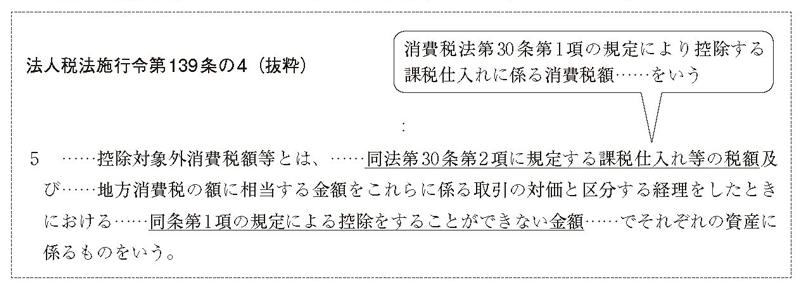
消費税法第30条第10項では、「第1項の規定は、……居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については適用しない。」と規定している。そうすると、法人税法施行令(上記)の「同条『第1項の規定による』控除をすることができない金額(下線の箇所)」には、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額は含まれないことになるのであろうか?
居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額について、『同条第1項の規定』が適用されないのであるならば、「同条第1項の規定による控除をすることができない金額」すなわち「同条第1項の規定を適用したことにより、控除することができないこととなる金額」もないこととなり、結果として、仕入税額控除の対象とならないだけでなく、そもそもが控除対象外消費税額等に該当しないようにも読めるのである。
この解釈によると、税抜方式を採用した場合の居住用賃貸建物に係る仮払消費税等は永久に償却できないこととなってしまう。したがって、居住用賃貸建物に課された消費税額等を費用計上するためには、固定資産と繰延資産については税込処理をしたうえで、居住用賃貸建物の税込取得価額を基に減価償却費を計上することになるように思えるのである。
(注)売上げ等の収益に係る取引につき税抜方式を採用している場合には、固定資産と繰延資産の取得についてだけ税込方式を採用することができる(消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて3(税抜経理方式と税込経理方式の選択適用))。
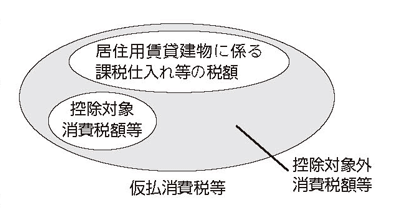
<改正案>
居住用賃貸建物について、消費税法が改正されたにも関わらず、法人税法施行令を改正しなかったことにそもそもの問題があるように思われる。法人税法施行令第139条の4第5項を次のように改正すれば、居住用賃貸建物に課された消費税等の全額を控除対象外消費税額等として計上することができるのではないだろうか?(下線が変更又は追加箇所)。
法人税法施行令第139条の4 資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入
:
5 第1項から第3項までに規定する資産に係る控除対象外消費税額等とは、内国法人が消費税法第19条第1項(課税期間)に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、当該課税期間中に行つた同法第2条第1項第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税の額及び当該消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税の額に相当する金額並びに同法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額をこれらに係る取引の対価と区分する経理をしたときにおける当該課税仕入れ等の税額及び当該課税仕入れ等の税額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができる金額及び当該控除をすることができる金額に係る地方消費税の額に相当する金額の合計額以外の金額でそれぞれの資産に係るものをいう。
上記のような改正ができないのであるならば、せめて、後半の「……同条第1項の規定による控除をすることができない金額……」という文言を「……同条第1項の規定により控除をすることができない金額……」と改めるべきである。
「る」と「り」でその意味合いは大きく異なるように思えるのである。立案担当者に改正(修正)の検討を促したい。
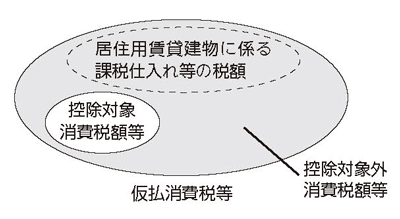
(2)仮払消費税等を計上できるものとする考え方
居住用賃貸建物であっても消費税が課されていることは紛れもない事実である。法人税法施行令第139条の4第5項に規定する「同条第1項の規定による控除をすることができない金額」という文言には、「『同条第1項の規定』が適用されない」ことにより、結果として控除することができないこととなった居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額も含まれるものと解釈すべきである。
よって、居住用賃貸建物に課された消費税等の全額を仮払消費税等として計上したうえで繰延消費税等として資産に計上し、均等償却することができるものと思われる。
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























