解説記事2021年03月01日 特別解説 我が国の上場企業による不正〜第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析〜(2021年3月1日号・№872)
特別解説
我が国の上場企業による不正
〜第三者委員会報告書を提出した企業の調査分析〜
はじめに
本稿では、2014年4月から2020年12月末日までの期間で、不適切な会計処理や不適切な行為について、第三者委員会報告書(第三者を含んだ社内調査報告書等を含む)を公表した企業を題材として、不正の発生原因や類型、特徴点を分析するとともに、2020年度下半期(7月〜12月)に発生した特徴的な不正事例として、理研ビタミンの事例を取り上げて紹介することとしたい。
調査の対象とした企業
今回調査の対象としたのは、2014年4月1日から2020年12月31日までの期間に、不適切な会計処理や不適切な行為等について第三者委員会報告書(第三者を含んだ社内調査委員会報告書を含む)を公表した企業(以下、「報告書公表企業」という。)である(表1を参照。)。

これまでは、年間にほぼ30件のペースで不適切な会計処理に関する調査報告書が公表されてきたが、2019年度は41件と大幅に増加し、2020年度は29件となっている。なお、調査報告書が公表された事例のうち、得意先が要求するスペックを満たしていない製品を偽って納入していた等の会計処理とは直接関係しない不適切な事例は、調査の対象からは除いている。
次に、報告書公表企業の195社を、上場している市場等の区分ごとに分類すると、表2のとおりであった。現在、東証における市場区分の見直しや銘柄の整理等が検討課題として挙げられているが、3,700社強の上場企業のうち、6割弱が東証1部上場となっている。当然のことながら、絶対数でみると東証1部に上場している企業(又はその子会社等)による不適切な会計処理が最も多いが、各市場の上場企業数の合計で除して比率を算出すると、東証1部が4.5%であるのに対して東証2部は5.9%、ジャスダック6.2%、マザーズが5.5%と、いわゆる新興市場に上場している企業のほうが、相対的に見て不適切な会計処理が起こりやすい傾向にあるという結果となった。
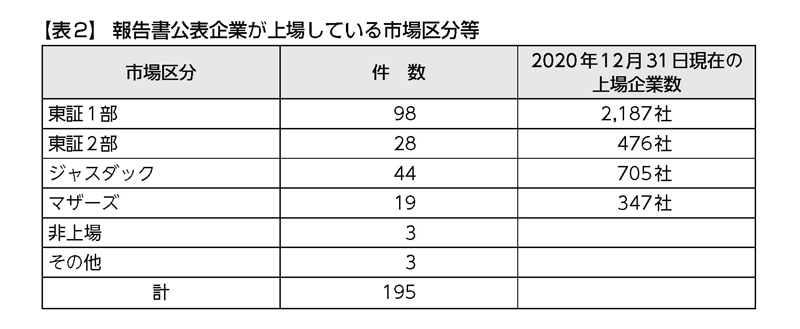
不適切な会計処理の分類と発覚の原因等
不適切な会計処理を生じさせた当事者を分類すると、表3のとおりであった。なお、表3の「元役員・従業員」の区分には、組織的ではない、個人的な不正行為(横領、着服等)を分類している。
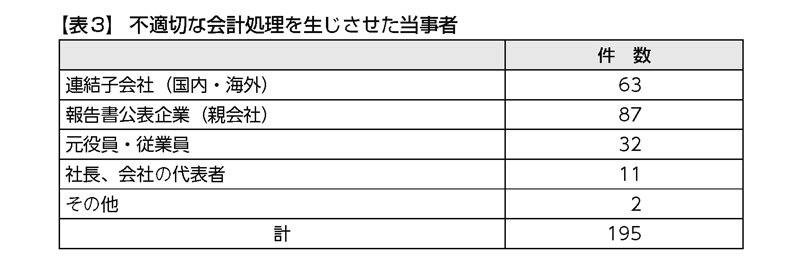
新聞報道等でもよく取り上げられているが、親会社に比べてガバナンスが効きにくく、監視の目が届きにくいとされる連結子会社(特に中国をはじめとする海外の子会社)で不適切な会計処理が発生した事例が多かった。
次に、不適切な会計処理を形態別に分類すると、表4のとおりとなった。
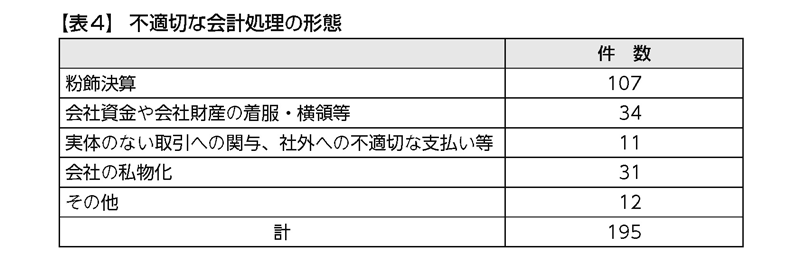
企業の業績、特に売上高や利益を実力以上によく見せることを狙ったいわゆる粉飾決算が過半数を占めていたが、その一方で、個人的な動機(ギャンブル等にのめりこんだ末の借金返済や、個人的な遊興費への充当等)による資金の横領や着服等も少なからず存在していた。また、国内外の連結子会社において、本社が十分に管理監督をしないままに現地の担当者に業務を任せきりにしていたり、未知の土地で取引の拡大を拙速に進めようとしたりした結果、不透明な取引や循環取引等に巻き込まれて多額の不良債権や損失が発生したような事例もあった。さらに、「企業の私物化」には、オーナー経営者や創業者が、取締役会の決議等を経ぬままに私情が絡んだ投資を行ったり、公私混同を行ったりしていたような事例が含まれている。
さらに、不正の具体的な内容を分類すると、表5のとおりであった。
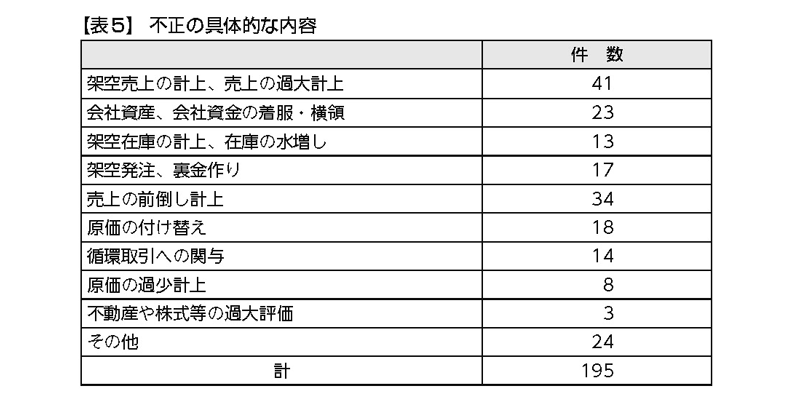
一つの不適切な会計処理事案の中に、表5の項目が複数含まれることはよくあり、むしろそのような事例のほうが多いが、ここでは便宜的に、それぞれの事案をどれか一つの項目に絞って分類している。
最後に、不適切な会計処理が発覚した契機を分類すると、表6のようになった。
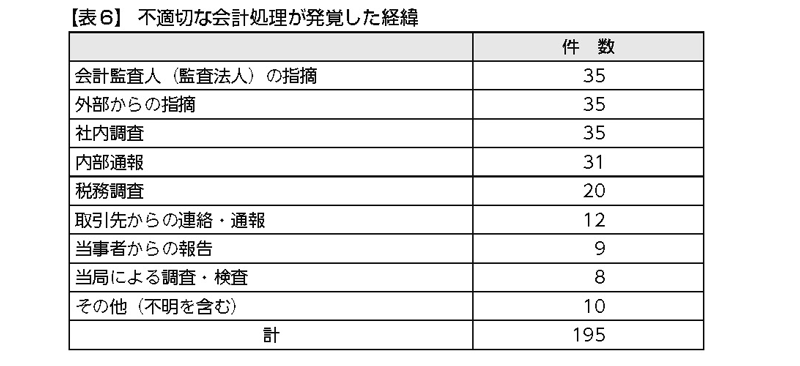
調査報告書上は必ずしも明記されていないが、表6の「社内調査」には、企業が自ら異変に気付いて行った自発的な社内調査のほかに、内部・外部から内密の情報提供を受けた上での社内調査も相当数、含まれているものと思われる。一般的には、不適切な会計処理を外部者が発見することは難しく、したがって不適切な会計処理を発見するためには内部通報のほうが有効であると言われることもあるが、今回の調査結果を見る限り、会計監査人(監査法人)や外部からの指摘、あるいは税務調査における指摘など、外部の第三者が介在したことをきっかけとして不適切な会計処理が発覚したケースがかなりの部分を占めていた。また、会計監査人が不適切な会計処理の兆候を発見して企業側に未然に是正を求めたようなケースや、不適切な会計処理が行われはしたものの、第三者委員会を設置しての調査が必要となるほどの規模になるまでの拡大は防いだようなケースも少なからず存在すると思われる。内部統制や内部的な自浄作用に加え、会計監査人等による外部からのけん制も、不適切な会計処理の抑止に一定の効果があるものと思われる。
2020年度下半期に発生した特徴的な不適切な会計処理の事例
表1で紹介しているように、2020年1月1日から12月31日までの間に第三者委員会報告書が公表された不適切な会計処理にかかる事例は29件あったが、本稿では、2020年度の下半期(7月〜12月)に生じた不適切な会計処理のうち、コロナウイルス感染症が爆発的に拡大した2020年をある意味で象徴しているといえる理研ビタミンの事例を取り上げてみたい。
理研ビタミン(以下「会社」という。)の事例は、コロナウイルス感染症の広がりにより、海外(中国)子会社の決算・監査業務が滞っていたところに、会計上の不祥事が追い打ちをかけて大混乱となった事例である。
会社は、2020年9月23日と11月13日の2回、外部調査委員会による調査報告書を公表している。
(決算及び監査業務の遅延)
会社は、乾燥わかめやドレッシングなどを製造販売する食品大手である。中国に所在する会社の100%子会社(以下「連結子会社」)では、例年2月中旬より、会社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人(以下「あずさ監査法人」という。)から連結監査の一環として業務の委託を受けたKPMG(中国)が監査指示書に基づく監査を実施しているところ、2020年3月期の期末監査は同年1月以降の中国国内における新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、通常より1か月強遅れた3月下旬から開始されていた。また、中国国内での移動制限や、日中間の実質的な渡航制限により会社から連結子会社に対する監査対応支援が不可能であったこと、連結子会社が取引や契約に関する書類(取引先からの提供分を含む。)の提出に時間を要していることも影響し、監査手続に著しく時間を要していた。
このような中、会社は、2020年5月中旬にあずさ監査法人から、連結子会社におけるエビの加工販売の取引について、取引の実在性を確認するために追加手続を実施する必要があり、会社法上の監査報告書を当初の予定どおりに提出することができない旨の通知を受けた。
また、会社は、同年7月20日にあずさ監査法人から、KPMG(中国)が実施した追加手続では取引の実在性を確認するに足る外部証憑を入手することができず、また連結子会社から十分な協力を得られなかったことなどにより、現時点において監査意見を表明するに足る十分な監査証拠を得られておらず、無限定適正意見を表明できない可能性がある旨の通知を受けた。
会社は、最終的に9月に、連結子会社の取引において、取引の全容および実在性が確認できなかった特定の顧客向けの売上高及び売上原価を取り消し、120億円を特別損失として計上した。
なお、あずさ監査法人は、2020年3月期の有価証券報告書については限定付適正意見を表明し、2020年6月期、及び2020年9月期の四半期報告書については、結論を不表明とした。
(追加調査)
連結子会社は、2020年7月15日、新型コロナウイルス感染症に関する保健衛生の観点から行われた中国山東省膠州市の市場監督管理局の立入り検査において、倉庫内に賞味期限を超えて滞留していた在庫が発見され、処分を命じられたことから、滞留在庫を飼料として廉価で販売して処分した。会社は、2020年9月30日に連結子会社から受領した2020年8月度月次決算報告において、当該廉価販売に伴い約26億円の営業損失が計上されていたことから、連結子会社に対し事実関係の説明及び関連書類の提出を求めたところ、連結子会社からは、滞留していた原材料及び製品の一部について、飼料用途として廉価販売していたとの報告を受けた。この報告により、会社と連結子会社との間で、在庫の仕入・製造時期についての認識に相違があることが判明し、過年度においてそれらの評価が適切に行われていなかった疑い、及びその結果として過年度の連結貸借対照表上の棚卸資産が過大に計上されていた疑いが生じた。そのため、再度調査委員会が組織されて追加調査が行われた。
会社は、コロナ感染症拡大に対応する提出期限の一律延長措置にも助けられ、提出期日ぎりぎりの9月30日に2020年3月期の有価証券報告書を提出することができたが、2021年3月期第一四半期の四半期報告書については締め切りより1か月遅れの10月28日に提出し、上場廃止措置を寸前で回避した。第二四半期報告書については、提出期限の延長申請等をすることなく、11月16日に提出を終えたが、会計監査人の四半期レビュー報告書の結論は不表明が続いており、混乱が収束したとは言えない状況にある。
調査上の制約
会社が設置した「特別調査委員会」による連結子会社への実地調査に対し、面談や資料の提出を拒むなど、当事者たちが一貫して非協力的な姿勢であったことに加えて、以下のような様々な制約が存在したことも、本事例で特筆すべき事項であろう。
・デジタルフォレンジック調査について、連結子会社では会社のサーバーが存在せず役職員はフリーメールを業務利用しており、また、業務で利用するPCについてIT担当者による管理もされていないため、個々の業務用PCについて役職員の同意を得てデータを保全する必要があった。責任者のA氏はデジタルフォレンジック調査の実施に一旦は同意したものの、同氏不在中の総経理代行として調査対応の責任者となった副総経理であるE氏から実施を拒絶された。同氏によれば、国家機密が存在する可能性、社内の共産党委員会に関係する情報の存在、従業員のプライバシー等の問題があり、これらに関する懸念が払拭できないためとのことである。
・コロナウイルス感染症拡大防止策の観点から、当委員会の委員又は日本の調査チームは連結子会社を訪問することができず、また、会社からも連結子会社に対して調査対応支援のための役職員を派遣することができなかった。
・当委員会の調査によって連結子会社における証憑を十分に取得できなかった理由の一つとして、同社のシステムのIT化が進んでおらず、手書きの証憑類を探索・収集せざるを得なかったことが挙げられる。連結子会社においては、業務上使用するPCの管理は各従業員に任されており、メールアドレスは各従業員が独自に取得したフリーメールを使用しているなど会社としてのIT管理がなされていない。また、基幹システムが整備されていないほか、会計システムを利用していないとのことであり、経理関係書類が手書きで管理・集計されている場合もある。
海外子会社の管理の難しさ
調査委員会報告書によると、連結子会社がエビ加工品の架空取引をするようになったのは同社の決算月にあたる2018年12月からで、同月は8億円余りの架空取引が行われた。さらに2019年12月期は架空取引が1年を通じて行われ、その額は116億円に上った。2019年12月期のエビ加工品の販売総額は124億円であるため、その取引のほとんどが架空であり、同社の売上高全体の実に7割以上に及んだという。
こうした経営がまかり通ってきた背景として、会社の完全子会社であるにもかかわらず事業上の関係が希薄であり、連結子会社の人事に会社が関与してこなかったことなどが指摘されている。その他に、調査報告書においては、連結子会社へのガバナンスの根本的な問題点として、次のような点が指摘されている。
・管理強化を伴わない支援強化等が、連結子会社でモラルハザードを生じさせた可能性が否めない。
・事実上、現会長のB氏と前会長のA氏の間の属人的信頼関係に基づく単線のラインしか機能しておらず、組織的に行われるべき子会社管理においては異常な状態であった。
・会社内においても子会社管理の脆弱性の懸念は持たれていたが、中国の国営企業を買収したという特殊な経緯、買収を主導した前会長のA氏や現会長のB氏への高い評価、連結子会社は中国政府により「三同企業(「輸出対応生産設備」「輸出対応製造標準管理」及び「輸出対応品質管理」を備えた企業)」として認定されるなど、品質面では高い評価を受けていたこと、黒字経営を維持していたこと、事業上の関係が深まらなかったことなどの事情から、改善されることはなかった。
・このようなおざなりな管理体制が既成事実化してしまい、2016年以降の連結子会社の業績悪化に際して資金繰り支援の強化・事業構造転換の指示(輸出中心から中国国内市場へ、簡易加工品から高付加価値品への転換)等が行われてきたものの、経営責任を取らせることや、管理面の強化を図ることはできないままとなっていた。
・前回調査報告書の公表後、会社が付帯的な業務改善策を策定している期間においてさえ、連結子会社は会社に何らの相談も報告もすることなく、独断でかつ適切な管理もなされないままPCのハードディスクのリプレースを行っていた。
終わりに
海外子会社の管理の難しさや、中国という我が国とは体制が大きく異なる国家が抱えるリスクについては、前々から各方面から指摘がなされてきていたが、今回のコロナウイルス感染症の感染拡大を契機に、問題点が一気に表面化した感がある。
物理的な距離に加えて、カントリーリスクがあると、日本からのグリップは非常に難しくなる。また、コロナウイルス感染症の拡大が続いている昨今は(中国に限らず)特に外国の拠点を直接訪問することが非常に困難であるため、多くの海外子会社で潜在的なリスクは高まっていると考えるべきであると思われる。海外に子会社を保有する我が国の多くの企業にとって、決して他人事では済まされない事案であろう。
11月13日付の調査委員会報告書の最後に、「グループ・ガバナンスの抜本的見直し」として記載されている下記の文章に、会社としてなすべきことが言い尽くされていると言えよう。
本件のような事態を二度と生じさせないためには、連結子会社において滞留在庫を適切に管理せず、会社に対して適時に適切な報告も行わなかったことなどについて、経営陣の責任を明確化する必要があることは当然である。さらに、連結子会社がこのような事態を発生させる状況にあることを許してきた会社側での親会社としての管理監督上の責任についても検討すべきである。そもそも、買収後25年以上経過しているにも関わらず、長年にわたり連結子会社のマネジメントをA氏に強く依存させ、親会社としてあるべきガバナンス・管理体制の構築ができないままとなっており、その結果、会社は、前回調査においては子会社の取引の実在性を確認することができず、有価証券報告書等の提出期限延長をした上で過年度訂正をすることとなり、さらに本件により、再度の訂正をした上で四半期報告書の提出を遅延して監理銘柄(確認中)指定を受け、監査人の監査報告書又は四半期レビュー報告書は意見不表明又は結論の不表明となるという極めて重大な事態を招くに至っている。会社としてもこの責任を深く自覚しなければならない。本件を受けて、会社・連結子会社双方において、過去のしがらみを断ち切って経営体制の再構築を行うことも検討に値する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























