解説記事2019年12月16日 特別解説 IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点~IFRS解釈指針設定のためのデュー・プロセス~(2019年12月16日号・№815)
特別解説
IFRS解釈指針委員会での議題から却下された論点
~IFRS解釈指針設定のためのデュー・プロセス~
はじめに
国際財務報告基準(IFRS)を開発する国際会計基準審議会(IASB)の上部機関であるIFRS財団は、2019年4月に、「デュー・プロセス・ハンドブックの修正案」を公表した。デュー・プロセス・ハンドブックとは、IASB及びIFRS解釈指針委員会に適用されるデュー(適切な)・プロセス手続を示すものである。
我が国におけるIFRSに関連する記事や書籍等では、IFRSの基準書やIASBにおける審議の状況等に主に焦点があてられることが多く、IFRS解釈指針委員会や解釈指針の開発プロセス等について説明しているものは極めて少ない。本稿では、IFRS基準書適用の「縁の下の力持ち」ともいえるIFRS解釈指針委員会の活動を取り上げ、世界各国から寄せられる様々な論点が、どのようにして基準書や解釈指針策定の議論に織り込まれていくのか(あるいは、却下されていくのか)のプロセスを紹介した後、最終的に解釈指針やIFRS基準書の修正等といった形で、「日の目を見ることがなかった」論点について、それらがアジェンダとして取り上げられなかった理由を探っていくことにより、取り上げることとしたい。
IFRS解釈指針委員会におけるアジェンダ決定のプロセス
まず最初に、我が国ではなじみが薄いと思われる、IFRS解釈指針委員会におけるアジェンダ決定のプロセスを簡単に示すこととする。
(1)論点の提出(サブミッション)
IFRS解釈指針委員会の議題は、世界中の様々な関係者から提出される論点に基づいて決定される。論点を提出する場合、提出者は論点がIASB及びIFRS解釈指針委員会デュー・プロセス・ハンドブックに記載されている、「議題(アジェンダ)となるための要件【表1】参照」を満たしているかどうかを評価しなければならない。そのうえで、IFRS解釈指針委員会が当該論点を検討すべきと考えた論拠を、論点の説明や現行の会計実務及び関連する基準書等とともに記載して論点を提出する。
【表1】IFRS解釈指針委員会で議題となるための要件
(デュー・プロセス・ハンドブック5.16、5.17及び5.21項)
| ① 広がりのある影響を有し、影響を受ける人々に重要性のある影響を与えているか又は与えると予 想されること。 ② 多様な報告方法の解消または削減を通じて、財務報告が改善されること。 ③ 既存のIFRS基準及び「財務報告に関する概念フレームワーク」の枠内で効率的に解決できること。 ④ 論点は解釈指針委員会が効率的な方法で対処できる十分な狭さであるべきであるが、解釈指針委 員会及び関心のある関係者にとってIFRS基準の変更を行う場合に必要となるデュー・プロセスの実 施が費用に見合う効果がないほど狭いものとすべきではないこと。 ⑤ 解釈指針委員会が開発する解決策は、合理的な期間にわたり効力を有するべきであること。 |
(2)論点の評価と分析
IASBのスタッフは、提出された論点について提出者にコンタクトし、内容の詳細(関連する取引事実や状況を含む)や背景・懸念等を把握する。また、議題となるための要件を満たすか(例えば当該論点・取引が広く存在するか、実務に多様性(会計処理のばらつき)が生じているか)を評価・分析するため、通常、各国の会計基準設定主体や規制当局等から情報を収集する。スタッフは、入手した各種情報や関連する基準等をもとに分析を行い、分析結果と提案をペーパーにまとめて、IFRS解釈指針委員会の会議に提起する。
(3)IFRS解釈指針委員会での議論と議決
基本的に、提出されたすべての論点がIFRS解釈指針委員会の公開の会議で検討される。IFRS解釈指針委員会では、通常、IASBのスタッフによる分析や提案が記載されたペーパーに沿って、論点を議題に追加すべきかどうかについて議論する。議論の結果、論点が議題要件を満たさないとIFRS解釈指針委員会が判断すると、当該論点の却下が、出席したメンバーの多数決によって暫定的に決定される。
(4)暫定の却下通知と意見募集
IFRS解釈指針委員会が議題にしないと一度決議したことが、即座に正式な決定事項となるわけではない。まず、IFRS解釈指針委員会は、暫定の却下通知を公表する。当該却下通知では、論点の概要と、IFRS解釈指針委員会が議題に追加しないと判断した根拠が説明される。そして、IFRS解釈指針委員会は、当該却下通知について、最低60日間の意見募集を実施する。その後、受領したコメントについてのIASBスタッフの分析に基づいて、IFRS解釈指針委員会は、再度公開の審議を実施し、正式な却下通知を公表するかどうかを決議する。
(5)却下通知
IFRS解釈指針委員会の公開の場での会議での二度の決議の結果、議題としないことが正式に決定されたものについて、最終的な却下通知が公表される。これらのIFRS解釈指針委員会としての議論と決定は、すべてIASBのホームページに公開されている。次節以降では、公表物である「IFRIC UPDATE」の記載に基づいて、これまでに却下された論点を、却下された理由とともに紹介していくこととする。
IFRS解釈指針委員会が議題として取り上げないことを決定した論点
IFRS解釈指針委員会(以下「委員会」という。)の会議は年に6回あり、委員会が公開の会議で至った決定の要約がIFRIC UPDATEとして公表されている(わが国の企業会計基準委員会(ASBJ)のホームページから、和訳を入手できる。)。
IFRIC UPDATEは、「現在のアジェンダにある項目」、「委員会の暫定的なアジェンダ決定」、「委員会のアジェンダ決定」及び「その他の事項」に分かれており、本稿では、「委員会のアジェンダ決定」に記載されている内容を紹介する。「委員会のアジェンダ決定」では、委員会が基準設定アジェンダに追加しないことを決定した論点について、その概要と関連する基準書の説明、並びに委員会が基準設定アジェンダに追加しないことを決定した根拠が(特に最近の数年は)かなり詳細に記載されている。
これまでの議論の結果として、委員会が基準設定アジェンダに追加しないことを決定した論点は300強あり、そのうち、現時点では、IAS第17号「リース」やIAS第18号「収益」等の、すでに廃止された基準書に係るものを除いた280件ほどがIFRS財団のホームページに掲載されている。これらについて、最終的に基準設定アジェンダに追加されなかった理由別に分類し、事例の紹介及び簡単な分析をすることとしたい。
論点が最終的に基準設定アジェンダに追加されなかった理由
利害関係者から提出された論点が、最終的に基準設定アジェンダに追加されなかった理由を示すと、表2のとおりであった。
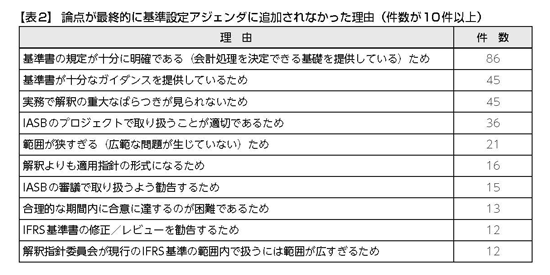
このほかに、「国際財務報告基準(IFRS)の年次改善プロセスの中で解決されることが最善であるため」「解釈指針の開発により、コストを上回る便益をもたらさないため」「ケースバイケースの判断が要求されるため、解釈指針を開発すべきではない」などの理由がみられた。以後で、それぞれの理由について、適宜実例を交えつつ簡単に触れることとする。なお、それぞれの事例の中の記述は、アジェンダ提案がなされた当時の基準書に基づいて記載されているため、その後の年次改善等により、現時点においては問題点が解消されている(基準書の記載内容等も変更されている)可能性があることにご留意いただきたい。
(1)「基準書の規定が十分に明確である(会計処理を決定できる基礎を提供している)ため」及び「基準書が十分なガイダンスを提供しているため」
この2つの理由で、全体の却下理由の4割強を占めていたが、最近の1~2年だけでみると、却下理由のほとんどがこの2つである。その背景には、IFRS第9号「金融商品」、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びIFRS第16号「リース」といった大型の基準書が相次いで完成し、適用開始されたことがあると考えられる。IASBの前身のIASC(国際会計基準委員会)が作成したIAS(国際会計基準)は、IAS第19号「従業員給付」やIAS第39号「金融商品:認識及び測定」といった一部の例外を除くとページ数が少なく、要求事項やガイドラインの数なども限られていたため、解釈の余地が大きかったと考えられる。しかし、IFRS第9号、第15号や第16号は要求事項の数が多いうえ、適用指針や設例等も多く用意されており、基準書作成の趣旨や議論の背景等を書き込んだ「結論の根拠」パートも非常に充実している。また、会計基準書策定の過程において、アウトリーチ活動等によって数多くの利害関係者の声を聴いて基準に反映させているため、基準書の記述もかなりきめ細かくなっているためではないかと考えられる。
(2)実務で解釈の重大なばらつきが見られないため
表1の②の要件を満たさないためとされたものである。下記(5)の事例も参照。
(3)IASBのプロジェクトで取り扱うことが適切であるため
この理由は、委員会の初期の5年間(2002年~2007年)によく見られた却下の理由である。当時は、IASBにおいて、企業結合(IFRS第3号)、金融商品、収益など、新基準の作成に向けたプロジェクトが目白押しであった。解釈指針を作成すべきとして提出された論点も、解釈指針ではなく新基準作成のためのプロセスに組み入れられ、IASBでの議論を経て、最終的にIFRS第3号、第9号、第15号、第16号といった新しい基準書に織り込まれていったものと考えられる。
(4)範囲が狭すぎる(広範な問題が生じていない)ため
表1の①の要件を満たさないためとされたものである。
2014年4月の会議で、委員会は、期限延長オプション、早期決済オプション及び利息支払停止オプション(すべて発行者側のオプション)を含んだ複合金融商品の保有者による分類を明確化するように要望を受けた。これに対して委員会は利害関係者にアウトリーチによる情報提供を要請し、その回答に基づいて、この論点は一般的な広がりがないと考えた。また、委員会は提出された要望書に述べられている金融商品は個別的なものであり、この特定の論点に関するガイダンスを設けることは適切ではないと考えて、この論点をアジェンダに追加しないことを決定したとしている。
(5)解釈よりも適用指針の形式になるため
2009年5月の会議で、委員会は、IAS第41号「農業」が非常に限定されたガイダンスしか提供していないとして、生物資産の公正価値が将来正味キャッシュ・フローの現在価値として見積られるときに、企業が適切な割引率をいかに決定すべきかについてガイダンス提供を質問者から求められた。
これに対して委員会は、以下の点に注目した。
・IAS第41号における公正価値測定の目的は、他の基準と整合していること。
・IAS第41号が2008年5月に改訂され、そこでは、正味キャッシュ・フローの現在価値決定に当たり、市場参加者により生物資産が生み出すと期待される正味キャッシュ・フローを勘案することが明確化されたこと。
・IAS第41号第24項は、最初にコストが発生してからほとんど生物的変化が生じていない場合、取得原価は公正価値に近似することがあるとしていること。
・IAS第39号及びIASBが最近公表してきた金融危機関連のマテリアルが、活発でない公正価値見積りに関して広範なガイダンスを提供しており、生物資産の測定においても関連性を有すること。
これらを踏まえ、委員会は、本論点に関するさらなるガイダンスは、解釈というよりは性質上適用ガイダンスであると認識した。また、現在利用可能なIFRSのガイダンスにより実務の著しいばらつきが予想されないことから、本論点をアジェンダに追加しないことを決定したとしている。
(6)IASBの審議で取り扱うよう勧告するため、及びIFRS基準書の修正/レビューを勧告するため及びIFRSの年次改善プロセスの中で解決されることが最善であるため
我が国の会計基準設定においてはこのような手続は行われていないが、IASBは毎年、年次改善(Annual improvement)という手続を行っている。年次改善は、IASBのIFRS基準の維持管理のためのプロセスの一部であり、軽微又は範囲の狭い解釈を含んでいる。このプロセスの一部として行われる修正は、IFRS基準の文言の明確化又は比較的軽微な見落し若しくはIFRS基準の既存の要求事項の間の矛盾点の訂正のいずれかである。年次改善は、2017年度分、2018年度サイクルというように、年ごとにまとめて、複数の基準書にまたがって行われる。一から解釈指針を作成するとなると非常に時間も労力もかかるため、最近は、この年次改善手続の一環としてIFRS基準書等の微修正を行うことにより、問題点の改善を図るケースが増えている。
(7)合理的な期間内に合意に達するのが困難であるため
2010年5月の会議で、委員会は、のれんについて認識された減損損失の戻入れについて、処分グループの減損損失を戻し入れることができるかどうかについて、ガイダンスの提供を要望された。処分グループ中ののれんに対する減損損失の戻入れは認められないとする見解の根拠は、のれんに対する減損損失の戻入れは認められないことによる(IAS第36号「資産の減損」第124項)。一方で、処分グループ中ののれんに対する減損損失の戻入れは認められるとする見解の根拠は、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」の第22項が、特段にIAS第36号第124項に対する参照をしていないことによる。
委員会は、処分グループの減損損失(のれんに関するもの)の戻入れの認識と配分に関連して、IFRS第5号第22項と第23項との間に潜在的な矛盾を認識したが、既存のIFRSとフレームワークの枠内で効率的に解決することが困難であること、また、タイムリーに合意に至ることが困難であることを認識したため、この論点をアジェンダに追加しないことを決定したとしている。
(8)解釈指針委員会が現行のIFRS基準の範囲内で扱うには範囲が広すぎるため
表1の③の要件を満たさないためとされたものである。(7)の事例も参照。
我が国から提出された論点
最後に、我が国から提出された論点(最終的にIFRS解釈指針委員会の議題としては取り上げられなかった)を1つ紹介したい(この論点は、現時点では、IASBのホームページから削除されている)。
2003年の4月とかなり昔になるが、「日本政府の代行部分返上に係る負債の会計処理」が論点として委員会に提出された。
論点の概要としては、「この論点は、従業員の年金制度(日本の厚生年金保険法に基づいて設立された確定給付型年金制度)に係る給付債務のうち、代行部分を企業が負担する部分から分離し、代行部分及び関連する負債を日本政府に移転する取引を、雇用者がどのように会計処理するかという点である。」とされており、議題として取り上げられなかった理由としては、「本論点は広範なものではなく、IFRSの文脈において実務的な目的適合性はないため、IFRS解釈指針委員会の議題として取り上げるには範囲が狭すぎる。また、実務において、本論点に関する解釈上の疑問点が提起されていない。」とされている。
終わりに
2019年10月18日付で、IFRS財団は、2019年1月から9月までの間に行われたアジェンダディシジョンをまとめた資料(Compilation of 2019 agenda decisions)を公表した。ここには、本稿でも取り上げた、IFRS解釈指針委員会において行われたアジェンダ決定も含まれている。IFRS財団は、今後も年に2回、4月と10月にこういったまとめ資料を公表していくとしている。このような資料が公表されるのは初めてであるが、これらの資料によって、さまざまな事象・論点に対して、基準書における該当する原則と要求事項とがどのように適用されるのかが説明され、実務上の疑問点の解消が促進されることが期待される。
参考文献
あらた有限責任監査法人 PwC's View2016年2月号 「IFRS解釈指針委員会による却下通知」
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























