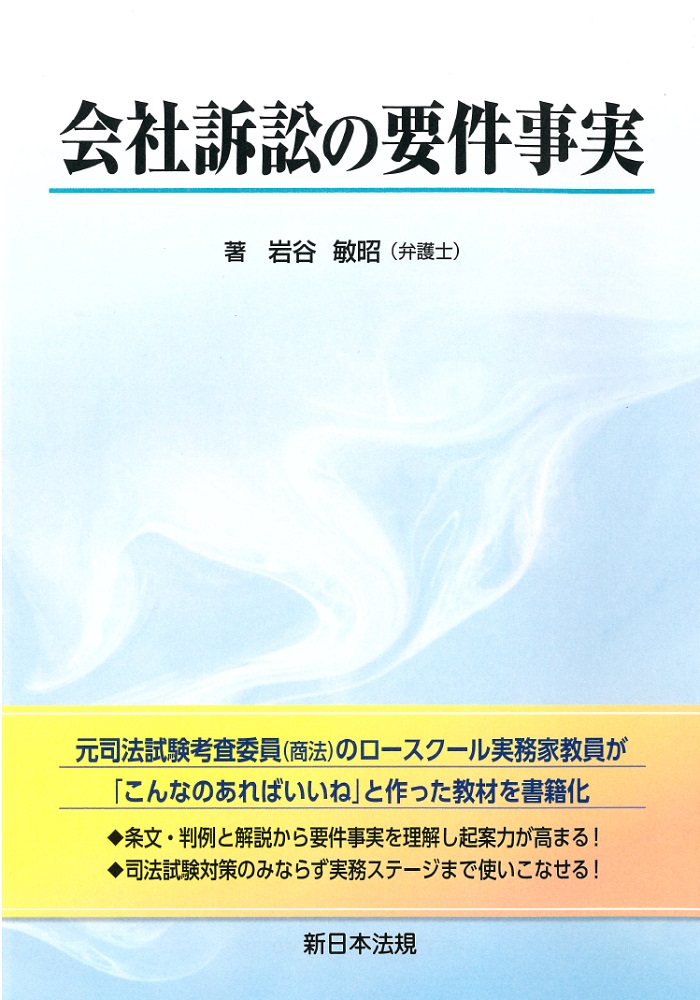解説記事2022年09月12日 論考 簿外経費等の必要経費・損金不算入の論拠と問題点(2022年9月12日号・№946)
論考
簿外経費等の必要経費・損金不算入の論拠と問題点
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
1 はじめに −問題の所在−
令和4年度の税制改正は、租税政策上の重要項目が乏しいが故に、一般的には、小粒な税制改正であると評価されている。しかし、このように、世間からそれ程注目されていない年には、得てして重要な税制改正が行われるものである。令和4年度の税制改正も、正にそのとおりであり、注目すべきは、納税環境整備関係である。納税環境整備というと、納税者側の納税の便宜が図られるという、ソフトイメージに捉えられることもあるが、反面、納税の適正化の面を有している。この納税の適正化は、税法が定めるとおりに税金が納付されることを意味し、税金逃れを防ぐことから、課税の強化につながることになる。
このような観点から平成4年度の納税環境整備税制を見ると、①悪質な納税者等に対する措置(簿外経費等の必要経費・損金不算入)、②死亡届の情報等の通知、③税理士に対する懲戒処分の拡大、④帳簿不提出等の加算税の加重、⑤財産債務調書の見直し等が挙げられる(注1)。これらの中で、特に、①については、租税法における理論上の問題、租税法における他の制度の関係、実務への影響等が大きいので、本稿では、改正された所得税法及び法人税法の規定の基に、それぞれの論点を検討する(注2)。
2 必要経費不算入規定の概要と趣旨
(1)令和5年1月1日から施行される所得税法45条3項は、収入金額が300万円を超える事業所得者等につき、「隠蔽仮装行為(その所得の金額又は所得税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。)に基づき確定申告書(〈略〉)を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用(〈略〉)及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額(〈略〉)は、その者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額及び雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。ただし、次に掲げる場合に該当する当該売上原価の額又は費用の額については、この限りでない。」と定めている。
そして、上記のただし書に該当するものとして、次の場合を掲げている(所法45③一、二)。
① 保存している帳簿書類等により、当該売上原価等の基因となる取引が行われたこと及びこれらの額が明らかである場合
② 売上原価等の額の基因となる取引の相手方が明らかである場合その他当該取引が行われたことが明らかであり、又は推測される場合であって、当該相手方に対する調査その他の方法により税務署長が、当該取引が行われ、これらの額が生じたと認める場合
上記と同様な規定は、法人税法55条3項においても定められている(以下これらの規定を「必要経費不算入規定」という。)。
(2)以上のような必要経費不算入規定の立法の趣旨について、立法担当者は、次のように説明している(注3)。
「所得課税においては、裁判例によって示されているように「所得金額」や「必要経費の存否及び額」については、原則として課税当局の側に立証責任があるとしつつ、「簿外経費」については、納税者側に立証責任があると解する場合が多いとされています。
しかしながら、実際の事案として、所得税の税務調査において家事関連費の計上を発見した後に、納税者が簿外経費の存在を後から主張し、課税当局が多大な事務量を投入してその簿外経費が全て存在しないことを立証して更正に至ったという悪質な事案があり、政府税制調査会の「納税環境整備に関する専門家会合」において議論が行われました。同会合においては、特に悪質な納税者への対応として、「課税の公平性を確保するために、税務調査時に簿外経費を主張する納税者、虚偽の書類を提出する等調査妨害的な対応を行う納税者への対応策や、調査等の働きかけに応じない納税者、到底当初より申告の意図を有していたとは思われない納税者等、既存のけん制措置では必ずしも対応できていない悪質な納税者への有効な対応策の検討を行う。」旨が政府税制調査会に報告されました(納税環境整備に関する専門家会合の議論の報告(令和3年11月19日))。これを踏まえ、納税者が事実の仮装・隠蔽がある年分又は無申告の年分において主張する簿外経費の存在が帳簿書類等から明らかでなく、課税当局による反面調査等によってもその簿外経費の基因となる取引が行われたと認められない場合には、その簿外経費は必要経費に算入しないこととする措置を講ずることとされました。」
3 「所得」の意義と立証責任
(1)所得税法及び法人税法における各税の課税標準は、所定の期間ごとの所得金額である。この「所得」の意義については、租税法上の固有概念であり、制限的所得概念と包括的所得概念に区分されるが、現行法の下では、後者によっている。包括的所得概念は、全ての経済的利得を所得として認識するものである。よって、この概念に基づいて所得金額を計算する場合には、所得税法であれば、別段の定めのない限り、当該年分の全ての収入金額から全ての必要経費の額を控除することとなり、法人税法であれば、別段の定めのない限り、当該事業年度分の全ての益金の額から全ての損金の額を控除することになる。この点につき、昭和44年改正前の法人税基本通達は、「総益金とは、……純資産増加の原因となるべき一切の事実をいう。」(同通達51)と規定し、「総損金とは……純資産減少の原因となるべき一切の事実をいう。」(同52)と規定していた(注4)。
(2)かくして、このような所得金額の多寡が争われた場合に、納税者又は課税庁のいずれかが主張・立証責任を負うべきかが問題となる。この点につき、最高裁昭和38年3月3日第二小法廷判決(訟務月報9巻5号668頁)が、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである。」と判示しているところ、この判示については、学説、判例とも異論はない。そのため、課税処分の取消訴訟においては、課税庁としては、全ての収入金額と益金の額を調査するだけではなく、全ての必要経費と損金の額を調査する必要があり、それらができなければ、当該課税処分が違法性を帯びることになる。もっとも、推計課税における特別経費の存在等特別の場合には、納税者側が立証責任を負うことがある(注5)。
この点につき、今回の必要経費不算入規定は、簿外経費等の必要経費不算入及び損金不算入の別段の定めを設けたわけであるから、上記の課税庁側に課せられた立証責任の一部を立法によって納税者側に転嫁したものと言える。しかし、この転嫁方法の是非については、他の関連する法理との関係において検討を要することになる。
4 推計課税との関係
(1)前述の立証責任の例外の一つとして、推計課税がある。すなわち、所得税法156条は、所得金額の実額計算が困難なとき(推計の必要性があるとき)には、「税務署長は、居住者に係る所得税につき更正又は決定する場合には、その者の財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況又は生産量、販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額(〈略〉)を推計して、これをすることができる。」と定めている。この規定と同旨の規定は、法人税法131条にも定められている。
(2)このような推計課税の規定は、最高裁昭和39年11月13日第二小法廷判決(訟務月報11巻2号312頁)が、推計課税の規定が昭和25年に設けられたにもかかわらず、昭和23年分及び24年分の所得税について推計課税した事案に関し、「所得税法が、信頼しうる調査資料を欠くために実額調査のできない場合に、適当な合理的な推計の方法をもって所得額を算定することを禁止するものでないことは、納税義務者の所得を捕捉するのに十分な資料がないだけで課税を見合わせることの許されないことからいっても、当然の事由であ」ると判示したこと等から、創設的規定ではなく確認的規定であると解されている。したがって、現行の消費税法には推計課税の規定はないが、所得税等の推計に連動して消費税についても推計課税が可能になる(注6)。
そうであれば、本件のような簿外経費等に関しても、例えば、所得税法156条に2項を設け、「前項の推計に必要性と合理性があれば、当該推計の額を所得金額とみなす」旨の規定を設ければ、今回のような必要経費不算入規定を設ける必要はないことになる。その点では、今回の措置は、立法政策上問題を残すことになる。
(3)なお、推計課税の取消訴訟においては、審理の段階で、収入金額を確定した後に、簿外経費等の証拠を提出する手法(いわゆる後出しじゃんけん)が見受けられたが、その弊害を是正するために、昭和59年度税制改正において国税通則法116条が改正された(注7)。同条1項は、訴えを提起した者が、「国が当該課税処分の基礎となった事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。」と定め、同条2項は、訴えを提起した者が前項の規定に違反して主張又は証拠の申出をしたときには、民事訴訟法157条1項に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御とみなす旨定めている。しかし、このような規定は、その後の推計課税の取消訴訟等においても訓示的な規定にとどまっているようである。
5 調査規定との関係
(1)必要経費不算入規定を設けた趣旨は、立法担当者の説明によると、調査非協力者等の悪質な納税者に対処するためであるという。しかし、そのような問題は今に始まったことではなく古くから存在していたからこそ、前述のような推計課税の規定が設けられており、課税当局に質問検査権の権限が与えられているところである。そこで、質問検査権の行使が十分に機能しているか否かの見地から検討する。
まず、国税通則法24条は、「税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。」と定めている(無申告者に対する決定については、同法25条に同旨を定めている。)。
また、上記の調査に係る質問検査権の行使につき、国税通則法74条の2第1項は、「(税務署等の)当該職員(〈略〉)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(〈略〉)を検査し、又は当該物件(〈略〉)の提示若しくは提出を求めることができる。」と定めている(平成23年の改正までは、各税法に同旨を定めていた。)。
(2)このような調査規定において、解釈上、問題となるのが、「調査」の意義と程度である。「調査」の意義については、かつては、大阪地裁昭和45年5月22日判決(訟務月報17巻1号91頁)が、「……課税標準等または税額等を認定するに至る一連の判断過程の一切を意味すると解せられる。すなわち、課税庁の証拠資料の収集証拠の評価あるいは経験則を通じての要件事実の認定、租税法その他の法令の解釈適用を経て更正処分に至るまでの思考、判断を含むきわめて包括的な概念である。」と判示したところに拠っていた。また、「調査」の程度については、最高裁昭和48年7月10日第三小法廷決定(刑集27巻7号1205頁)が、「この場合の質問検査の範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目については、右にいう質問検査の必要があり、かつ、これと相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまるかぎり、権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられているものと解すべく、また、暦年終了前または確定申告期間経過前といえども質問検査が法律上許されないものではなく、実施の日時場所の事前通知、調査の理由および必要性の個別的、具体的な告知ごときも、質問検査を行なううえの法律上一律の要件とされているものではない。」と判示したところに拠っていた。これらの解釈論は、適正課税を願う当時の国税職員の努力によって勝ち取られたものである。
(3)ところが、平成23年の国税通則法の改正による「第7章の2 国税の調査」の創設とそれに迎合する「国税通則法第7章の2(国税の調査)関連通達の制定について(法令解釈通達)」(平成24年、以下「調査通達」という。)の発出によって、前述の「調査」の意義、程度に関する解釈論は葬られることになった(注8)。それによって、予期されたように、国税当局の調査能力は弱体化し、簿外経費の捕捉も覚束無くなっているのかも知れない。そのために、今回のような必要経費不算入規定の措置が必要であるというのであれば、かつての立法・通達制定の際の誤りを別の方法で塞ごうとするもので首肯し難いものを残すことになる。
6 必要経費不算入規定の位置付け
(1)前記3で述べたように、所得税法及び法人税法の課税標準は、「所得」金額であるから、その計算においては全ての収入金額から全ての経費の額を控除することが原則である。しかし、両法とも、「別段の定め」を設けてその例外を設けているが、それが立法政策であるからと言っても、当該「別段の定め」には自ずから合理性が求められることになる。
この点につき、今回の改正は、既に、別段の定めとして、他の費用項目につき必要経費又は損金の不算入規定を定めている所得税法45条と法人税法55条に、今回問題にしている簿外経費等を加える方法を採用している。そうすると、同じ条文に規定するのであるから、当該各条に定めている既存の不算入項目に類似していることが望ましいことになる。しかし、当該各条の既存の不算入項目は、家事関連費、各種の附帯税額、いわゆる脱税工作費用、罰科金等であって、それらの必要経費性又は損金性に元々疑義があったものであるから、それらの取扱いを明確にしたものと評価できる。他方、今回の簿外経費等については、それらの存在が明確になれば、それらの必要経費性又は損金性は否定できないものである。その点では、既存のものとは異質のものを所得税法45条等に加えたということで、立法政策上疑義が生じることになる。
(2)また、法人税法に関しては、法人が賄賂性の高い費用を支出した場合にその支出先を明らかにしないことが多いので、そのような費途不明金を損金の額に算入しない旨の取扱いを定めている(法基通9−7−20)。しかし、それでは不正工作に対する制裁が不十分であるということで、租税特別措置法62条が、所定の使途秘匿金を支出している場合には、通常の法人税額に使途秘匿金額の40%を加算した金額を納付させることにしている。そのほか、企業経営上損金性があっても、所定の「交際費等」に該当するものについては、租税特別措置法61条の4が、損金不算入規定を設けている。このような立法手続上の観点からすると、今回の簿外経費等の損金不算入規定も、法人税法等の本法ではなく、租税特別措置法で定める方法も考えられるはずである。
7 隠蔽仮装行為の意義
(1)次に、改正規定の解釈については、最も問題となるのが、「隠蔽仮装行為」の意義(解釈)である。元々、今回の税制改正の趣旨は、「隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出している者」を対象に簿外経費等の必要経費不算入等を行うということで、悪質納税者対策のイメージ作りをしている。そのため、今回の必要経費不算入規定が悪質納税者に限られるということで、一般の納税者には関係がないように思われている。しかし、そもそも「隠蔽仮装行為」とは何を意味するかについては、大きな問題がある。
元々、「隠蔽・仮装」の用語は、国税通則法68条に定める重加算税の賦課要件に端を発しているが、当該賦課要件の解釈上も種々の問題を有しているところ、当該賦課要件と必要経費・損金不算入との関係も問題になるところである。
(2)まず、重加算税の賦課要件としての「隠蔽・仮装」の解釈については、次のことが問題とされている(注9)。
① 納税者がその不正手段を行うに当たって、それを認識した上で、税を免れようとする意思すなわち故意が明らかにされている(立証する)必要があるか否かである。
② 無記帳、不申告、虚偽申告、つまみ申告、申告書上の虚偽記載等のように積極的な不正工作を伴わない行為が「隠蔽又は仮装」といえるか否か。
③ 「隠蔽又は仮装」を行った者(行為者)が納税者本人に限定されるか、また、限定されない場合にどの範囲まで行為者を拡大できるのか。
④ 重加算税の納税義務の成立との関係で、納税義務成立後の税務調査等の段階での虚偽答弁等の不正工作が賦課要件を充足することになるのか。
⑤ 脱税等について刑事罰が適用されることとなる場合又は課税権の期間制限等が延長されることとなる場合の「偽りその他の行為」又は「偽り」との異同はどうなるのか。
以上の解釈上の問題点については、関係裁判例等において、一応定まっているが、まだまだ多くの論点が残されている。そのため、それらの解釈論をそのまま所得税等の本税に係る必要経費不算入規定の解釈に持ち込むことには、いささか無理があるように考えられるから、更に検討を要するところである。
8 実務への影響
(1)以上のように、今回の必要経費不算入規定は、立法政策上種々の問題があるところであり、かつ、解釈上も難しい問題を惹起することが予測される。その中で、必要経費不算入規定は、令和5年1月1日から施行されることになる。また、他の納税環境整備の改正事項(注10)と併せて考慮すると、国税当局は、青色申告制度に代表される納税者の記帳制度と申告納税制度を一層徹底させ、そのような記帳制度や申告納税制度に未熟な納税者を「悪質」扱いしようとしているようでもある。そして、税務調査の現場においても、一通りの調査を済ませた上で、帳簿や証拠がないという理由だけで、推計課税もせず、経費否認を行うという乱暴な調査が行われるということも予測される。その背景には、消費税におけるインボイス導入を含め、IT技術の発展がそれらを可能にするという、思い込みもあるのかも知れない。
しかしながら、申告納税制度が発足して75年、青色申告制度が発足して72年経過しているが、それらの歴史の流れと両制度の現況を考慮すると、国税当局の上記のような思い込みがあるとすれば、時期尚早であるように考えられる。
(2)特に、近年、働き方改革の一環として、フリーランサーやサラリーマンのサイドビジネスが増加してくると、それらの者が、最初から、所得計算のための帳簿の記帳や証拠の保存を徹底しているとは考えられない。他方、従来からの事業所得者であっても、青色申告制度を利用する者もいれば、特定の団体に属して税務当局と対峙するために帳簿や証拠書類を秘匿している者もいるはずである。このような雑多な納税者に対して、今回の必要経費不算入規定を一律に適用しようとすると、無用な混乱が生じることも考えられる。
このような混乱を回避するためには、担当調査官の熟練した調査能力と判断が求められるところであるが、前記5で述べた現状からみて、それも全ての調査官に期待することができないものと思われる。そうであれば、納税者(税理士)側も相応の対処方法を考えておく必要がある。
(注1)このような税制改正の趣旨については、松汐利悟(主税局企画官)「納税環境整備関係改正の趣旨」資産承継2022年6月号21頁等参照。
(注2)それぞれの論点については、品川芳宣「納税環境整備(納税の適正化関係)改正の論点」資産承継2022年4月号18頁、同「改正税法の法解釈・法制度の論点」資産承継2022年6月号53頁、石井亮・折原昭寿「税務調査等の実務の対応」資産承継2022年6月号65頁等参照。
(注3)「改正税法のすべて 令和4年版」(大蔵財務協会 令和4年)82頁、同旨320頁参照。
(注4)これらの規定は、法人税法上の解釈上当然のことであるとして、昭和44年の法人税基本通達の改正において削除された。
(注5)大阪高裁昭和46年12月21日判決(税資63号1233頁)、最高裁昭和39年2月7日第二小法廷判決(訟務月報10巻4号669頁)等参照。
(注6)消費税について推計課税したことを適法と認めた裁判例として、大阪地裁平成14年3月1日判決(税資252号順号9081)等参照。
(注7)同条の趣旨については、品川芳宣「国税通則法の理論と実務」(ぎょうせい 平成29年)448頁等参照。
(注8)当時の国税通則法の改正と調査通達の発出を適正課税を願う立場から批判したものとして、品川芳宣「国税通則法改正後の税務調査手続等の問題点」税経通信2013年4月号17頁等参照。
(注9)詳細については、品川芳宣「附帯税の事例研究 第4版」(財経詳報社 平成24年)302頁、前出(注7)290頁等参照。
(注10)前出(注2)各書参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.