解説記事2022年10月17日 ニュース特集 インボイス制度における登録申請の留意点(2022年10月17日号・№950)
ニュース特集
登録申請期限まで残り半年、現時点の登録は課税事業者の38%
インボイス制度における登録申請の留意点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入まで残り1年を切った。令和5年10月1日から登録事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請を行う必要がある。令和4年9月末時点における適格請求書発行事業者として登録された件数は120万5,091件であり、課税事業者である約300万者における登録割合は38%となっている。インボイスへの登録は任意ではあるものの、課税事業者の多くはインボイスに登録することが見込まれる。来年3月末の駆け込み申請も予想されるところだが、登録申請はインボイス制度導入の第1歩にすぎない。年明けは確定申告が待っている。登録後は、取引先への番号通知やインボイスの交付方法の決定など、登録申請後に準備しなければならないことも多いことからすると、早めの登録申請が必要といえよう。本特集では、インボイス制度における登録申請の留意点について解説する。
課税事業者の多くがインボイスの登録が必要に
令和5年10月1日からインボイス制度が導入される。インボイス制度では、課税事業者が消費税を一般課税で申告する際、インボイス(適格請求書)の保存がなければ、仕入税額控除が認められなくなる。このため、インボイスの発行が求められた場合に、インボイスを交付できなければ、取引先は仕入税額控除をすることができない。
国税庁が10月7日に公表したところによると、令和4年9月末時点における適格請求書発行事業者として登録された件数は120万5,091件にとどまる。課税事業者である約300万者における登録割合は38%だ。インボイスへの登録は任意ではあるものの、現在、課税事業者の多くがインボイスに登録することを考えると、少し物足りない数値といえよう。
とはいってもすべての取引でインボイスの交付が必要になるわけではない。事業者同士の取引でも取引先(売上先)が免税事業者であればインボイスの交付は求められず、課税事業者であっても取引先が簡易課税制度を選択していれば、インボイスの交付を受けなくてもみなし仕入率による仕入税額控除が認められるため、インボイスの交付は求められない。また、相手が消費者の場合はそもそもインボイスの交付は求められない。したがって、業種によっても大きく左右されるが、取引の相手のほとんどが消費者だけであればインボイスに登録する必要性は低い。逆に取引の相手のほとんどが一般事業者であれば、現在、免税事業者であってもインボイスに登録するか否かの検討が必要になってくる。
なお、インボイス発行事業者への登録の有無に関する効果と留意事項は図表1のとおりである。
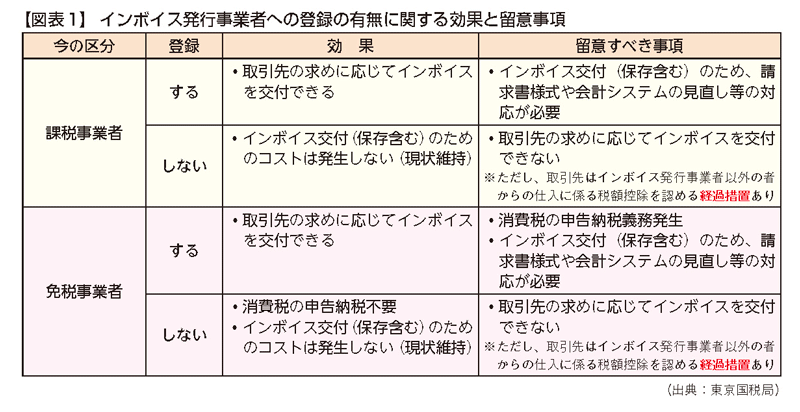
インボイス登録後も準備期間が必要
インボイス制度は令和5年10月1日からスタートするが、インボイス制度を導入するためには、まずは適格請求書発行事業者に登録する必要がある。ご承知のとおり、すでに登録申請の受付は令和3年10月1日から始まっており、インボイス制度開始から登録を受けるには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要がある(図表2参照)。
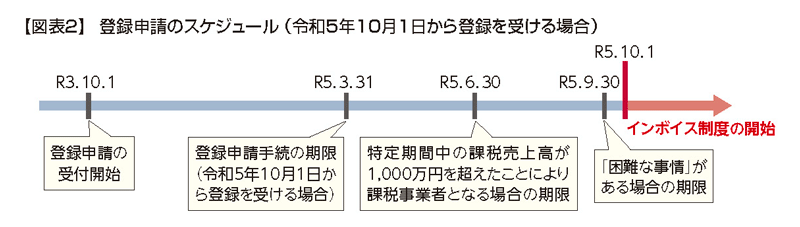
登録申請の8割がe-Tax
登録申請書を提出してから登録番号が通知されるまでには一定の期間が必要とされており、現在、登録申請書を提出してから登録通知までの期間は、e-Taxの場合で約3週間、書面の場合で約1か月半となっている(10月11日時点)。
なお、登録申請件数の約8割がe-Taxによる申請という。e-Taxの場合であれば、税務署における登録とほぼ同時に通知を受け取ることができるほか、紛失リスクがないなどのメリットがある(登録通知書は、原則として再発行は行われない)。
来年3月末での駆け込み申請となった場合には、登録通知期間はさらに長くなることが想定される。インボイスへの登録申請は導入までへの第1歩にすぎない。登録後は、インボイス交付のため、請求書様式や会計システムを見直しなどの準備期間があるため、可能な限り早めの登録申請が必要だろう。
登録番号通知とともに相手先の登録の有無の確認も
例えば、売手としては、売上先には登録を受けた旨(登録番号)を連絡し、何を適格請求書とするか、その交付方法等について認識を共有することが必要。適格請求書の写しの保存方法や売上税額の計算方法などの検討が必要になる。
また、買手としては、仕入先には適格請求書発行事業者の登録予定の有無の確認が必要になる。インボイスの発行がなければ仕入税額控除ができないからだが、仕入先に課税事業者か免税事業者か聞きにくいケースもあろう。この場合には、まず自らが登録申請を行い、相手先に登録番号を通知するとともに、登録の有無などを聞くということから準備を進めるとスムーズにいくかもしれない。また、登録の予定がなければ取引価格の見直しなどの交渉も必要になる(本誌923号・940号参照)。そのほか、請求書等を登録番号の有無で区分して管理することや、自社の仕入れや経費について、インボイスが必要な取引かなどの検討も必要になってこよう。
この点、国税庁では「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」を公表しており、参考になる(図表3、8頁参照)。
登録申請できない場合における一定の救済措置
令和5年10月1日から登録事業者になるためには令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があるが、一定の救済措置も設けられている(図表2参照)。
まずは、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えたことにより課税事業者となる場合だ。この場合には、令和5年3月31日までに登録申請できないケースがあるため、登録申請の提出期限は令和5年6月30日まで延長されている(平成28年改正消法附則44条1項)。また、どうしても令和5年3月31日までに登録申請できない「困難な事情」がある場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる(改正消令附則15条)。この場合の「困難な事情」とは、困難の度合いを問わないとされている(インボイス通達5−2)(次頁コラム参照)。
免税事業者は令和11年9月末まで経過措置
なお、インボイス制度開始後は、免税事業者から行った課税仕入れは仕入税額控除をすることができないが、免税事業者との取引への影響を緩和するため、インボイス制度導入後3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日まで)は、免税事業者からの仕入れに係る消費税の8割相当額、その後の3年間(令和8年10月1日から令和11年9月30日まで)は5割相当額の仕入税額控除を可能とする経過措置が設けられている。
また、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられている。経過措置の適用を受けて登録申請手続を行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はないこととされている。免税事業者の場合、経過措置の適用を受けつつ、この期間にインボイス制度を導入するか否か検討することが必要だろう。
免税事業者の登録はいまだ進まず
ただ、これまでインボイスに登録した免税事業者はおよそ5万5,000件にすぎない。免税事業者がどの程度課税事業者になるかは未知数だが、この数値は約500万者といわれる免税事業者全体の1.1%にすぎない。日本商工会議所が9月8日に公表したアンケート調査では、免税事業者の約3割が「課税事業者になる予定」とし、約2割は「要請があれば課税事業者になる予定」と回答していることからすれば、登録申請自体がほとんど進んでいないことがわかる。インボイス制度導入が迫る中、何らかの法制度などの見直しを求める声もあり、今後の動向が注目される。
登録申請できない「困難な事情」とは?
令和5年3月31日までに登録申請できない「困難な事情」がある場合には、困難な事情を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる。登録申請書を提出できなかったことの事情を記載すればよいとされており、国税庁によれば、「インボイス制度導入の検討をしたが結論が出なかった」「取引先と協議したが提出期限までに検討が進まなかった」など、理由についての困難の度合いは問わないとしている。
インボイス制度については、新しい制度なだけに理解するまでにはある程度の時間は必要になろう。万が一、令和5年3月31日までに登録申請ができなかったとしても、「困難な事情」を登録申請書に記載することにより、制度開始時からインボイス制度を導入することができるので覚えておきたい点だ。
ただ、期限間際での登録申請は可能な限り避けておきたいところ。すでに述べているように、登録申請はあくまでもインボイス制度導入までの第1歩であり、その後、様々な準備が必要だからだ。また、登録申請したからといってすぐに登録が完了するわけではない。実際に通知までのタイムラグもある。当然、令和5年10月1日までに番号が通知されなければ登録番号を請求書等に記載することはできない。仮に通知が令和5年10月1日を超えてしまった場合には、改めて相手先に令和5年10月1日に登録した旨を通知することが必要になり、二度手間になってしまう。注意したい点だ。
また、令和5年4月1日以降に「困難な事情」を記載せずに登録申請書を提出してしまった場合も留意したい。令和5年10月1日までに登録を受けることができればよいが、登録までに時間がかかり場合によっては登録日が10月2日以降になってしまうことも想定される。この場合は特に令和5年10月1日を登録日とする救済措置は設けられていない。
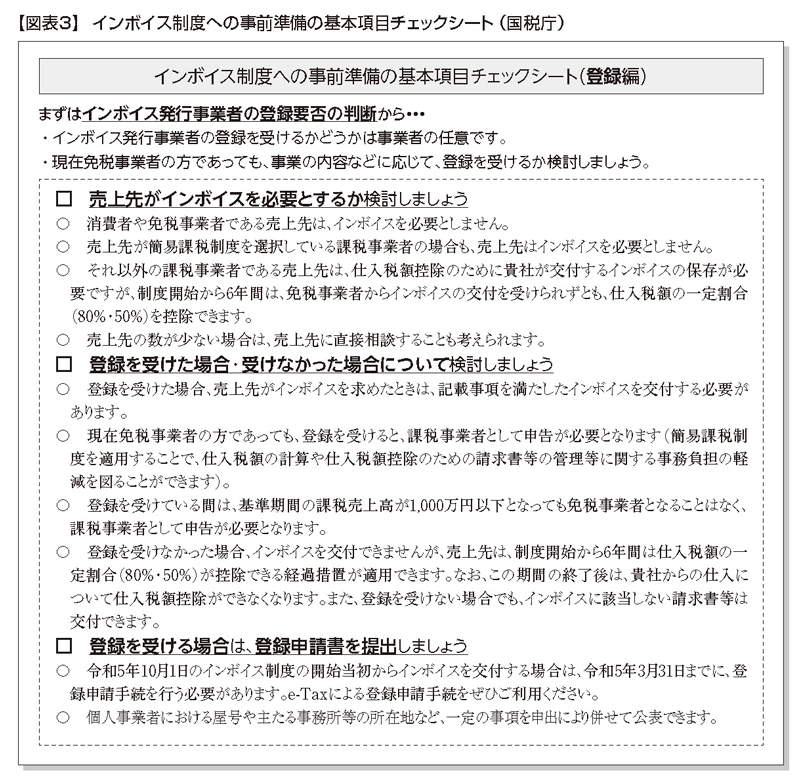
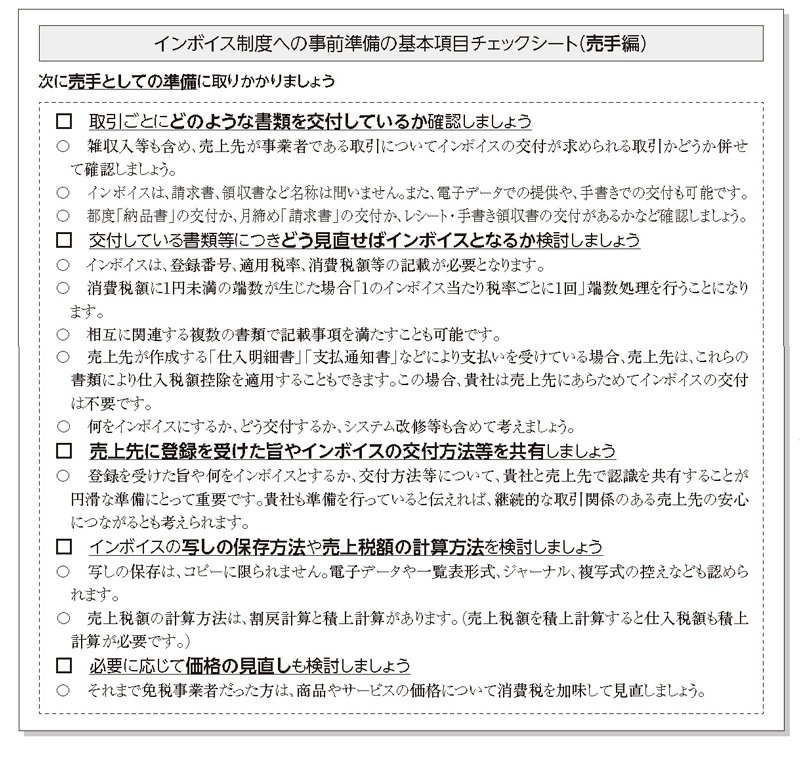
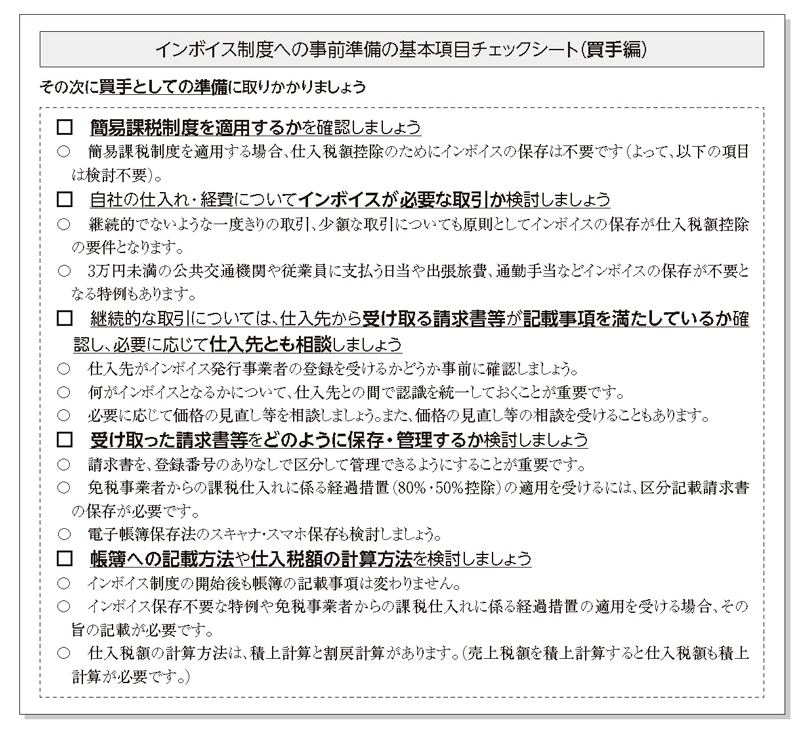
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























