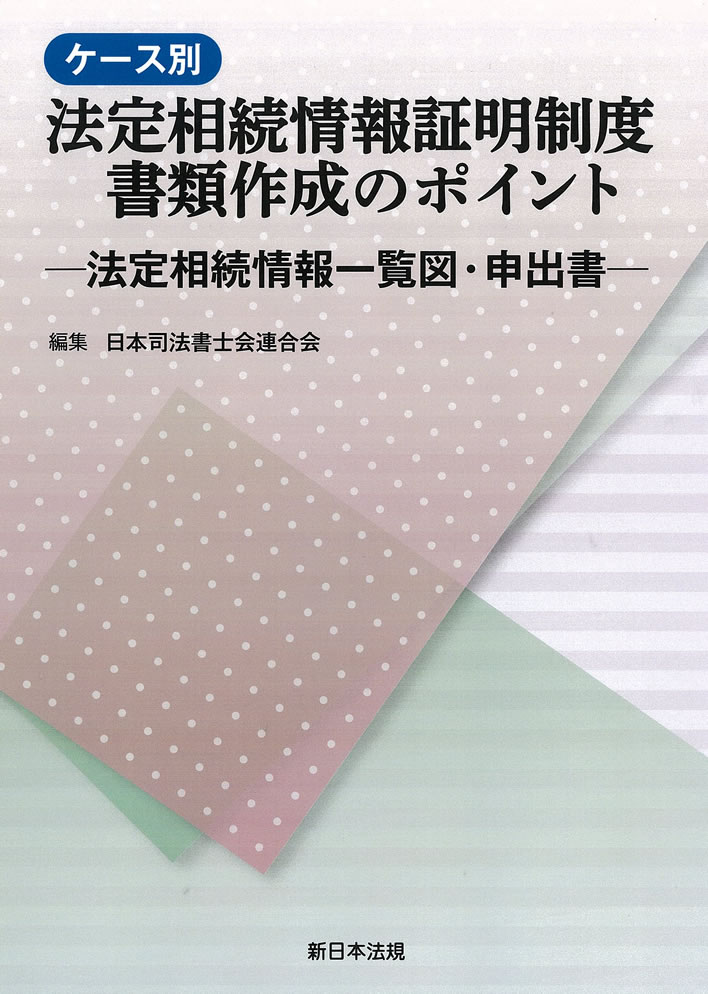解説記事2022年12月05日 ニュース特集 改正要望からは見えない重要改正事項の行方(2022年12月5日号・№957)
ニュース特集
見えてきた令和5年度法人関係税制改正の全貌
改正要望からは見えない重要改正事項の行方
例年より若干遅い12月15日または16日における(令和5年度)税制改正大綱の公表に向けた議論が佳境を迎えつつある。令和5年度税制改正の論点の多くは、8月末に各省庁がとりまとめた税制改正要望に盛り込まれているが、11月から本格化した税調の議論の中では、税制改正要望のみでは不明確だった論点、税制改正要望に付随する論点のほか、これまでにはなかった論点も浮上している。その中には、事業用資産の買換え特例の規律強化など企業にとって厳しい内容のものもあるが、中小事業者等をターゲットとしたインボイス制度の緩和、電子帳簿保存法における「電子取引の保存」要件の緩和、スキャナ保存制度における「承認要件」の緩和など企業にとって有利なものもある。このほか、“外形標準課税外し”への対応、防衛費増額に伴う法人税増税など、先行きが不透明な論点も議論の対象となっている。
本特集では各省の税制改正要望だけでは把握できない論点を中心に、直近の改正議論の動向をお伝えする。
買換え特例
申告時の“事後的紐づけ”に、税務当局が問題意識
長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例(事業用資産の買換え特例)が今年度末で期限切れを迎える中、国交省が中心となり、経産省が共同要望を行う形で期限延長等が議論されているが、令和5年度税制改正では同特例の規律強化も検討されていることが本誌取材により判明した。
事業用資産の買換え特例は創設が昭和44年度税制改正と古く、減税額も令和2年度で約718億円(国交省の推計)と租税特別措置の中でも比較的規模が大きいことから、適用期限切れの度に縮減議論が提起されてきたが、税務当局にとっては、減税額の大きさのみならず、企業が実際の買換えのタイミングではなく、法人税の申告時に事後的に譲渡資産と買換資産の紐づけを行っているのではないかとの問題意識がある。例えばある事業年度において甲社が資産A及びBを譲渡し、資産C及びDを取得したとする。甲社にとって、Aを譲渡したからCを取得した、あるいは、Bを譲渡したからDを取得したという事業上の因果関係はないが、買換え特例の適用を受けるため、法人税の申告時にAからCへの買換え、BからDへの買換えを行った旨を別表十三(五)に記入した場合、税務当局からすれば、甲社は申告時にAとC、BとDへと“事後的紐づけ”を行っているに等しい。
期限延長されるとしても適用要件強化は不可避
このような行為が常態化しているとなれば、買換え特例は政策効果(買換えの喚起による事業再構築等の推進)を十分に発揮しているとは言えず、規律強化の議論につながりやすい。例えば、譲渡資産の譲渡又は買換え資産の取得の時点で、買換え資産の取得又は譲渡資産の譲渡との「紐づけ」がある程度明確にできるものに限って、買換え特例を認める必要があるのではないか、といったものだ。具体的にどのような決着となるかは大綱を確認する必要があるが、仮に期限延長されるとしても、適用要件の強化は避けられない情勢となっている。
インボイス
小規模事業者に納税額・事務負担軽減措置を導入
2023年10月からのインボイス制度開始を控え小規模事業者等の対応が遅れる中、中小・小規模事業者等への負担軽減や影響最小化のために必要な税制措置の導入を求める声が高まっているが、まず小規模事業者に対する納税額の負担軽減措置として、免税事業者(基準期間の課税売上高が1,000万円以下である者)が課税事業者を選択した場合には、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間(インボイス制度の開始から令和8年9月30日の属する課税期間まで)講じることとなった。
また、事務負担の軽減措置としては、基準期間における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくても「帳簿のみ」で仕入税額控除を可能とする。なお、基準期間における課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は前事業年度の日以後6か月の期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は本特例の対象となる。
このほか、インボイス制度においては、値引き等を行った際には、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票(返還インボイス)の交付義務が課されるが、事務負担に配慮し、「1万円未満」の少額な値引き等については返還インボイスの交付を不要とする。
電子帳簿保存法関係
8月の経産省要望にはなかった「電子取引の保存」が見直しの対象に
電子取引を含む電子帳簿保存法については、比較的大規模な改正が行われる。
注目すべきは、下記の通り、経済産業部会要望で電子帳簿保存法について「電子取引の保存」との記載が入ったことだ。電子帳簿保存法のうち電子取引に係る部分は、令和3年度改正で紙保存が封じられ、令和4年度改正では一転して2年間の宥恕措置が講じられるという複雑な経緯を辿ったが(本誌913号参照)、「電子取引の保存」との文言の追加は、宥恕措置を再改正することを示している。具体的には、現行の宥恕措置(令和5年12月31日まで)を期限の到来をもって廃止し、相当の理由によりシステム対応を行うことができなかった事業者については、従前行われていた出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の確保の要件等を不要としてそのデータの保存を可能とする新たな猶予措置を「本則」として整備する。なお、改正案ではあくまで「データでの保存」が必要である点、留意したい。すなわち、データ及び出力書面について、税務調査期間にわたって保存が必要となる。
また、現行制度上、「売上高が1千万円以下である事業者」は、すべての検索機能の確保が不要とされているが、このバーを「売上高が5千万円以下である事業者」に引き上げる。さらに、データを出力したことにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力され、取引年月日等及び取引先ごとに整理されたものに限る)の提示・提出の求め、及びそのデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは、検索機能要件を充足しているものとする。
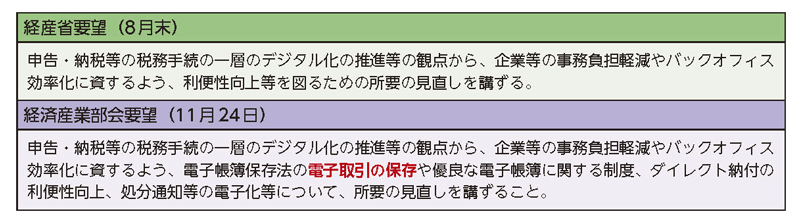
人事部の保管下にある賃金台帳にも「優良な電子帳簿」の保存要件
上記経済産業部会の「優良な電子帳簿……所要の見直し」との税制改正要望を巡っては、企業から「優良な電子帳簿の保存要件の緩和」への期待が寄せられている。
令和3年度税制改正では、優良な電子帳簿を推進する観点から、加算税軽減のインセンティブ措置が講じられたところ。具体的には、一定の国税関係帳簿について優良な電子帳簿の要件を満たして電磁的記録による備付け及び保存を行い、本インセンティブ措置の適用を受ける旨等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出している保存義務者について、その国税関係帳簿に記録された事項に関し申告漏れがあった場合には、その申告漏れに課される過少申告加算税が5%軽減される(電帳法8④)。
一定の国税関係帳簿とは、法人税についていえば青色申告法人が保存しなければならないこととされている仕訳帳、総勘定元帳、その他の必要な帳簿をいい、青色申告法人は、(これらの帳簿については)別表二十一に定めるところにより、取引に関する事項を記載しなければならない(電帳法施行規則8、法規54)。その上で、国税庁が公表している電帳法一問一答では、「法第8条第4項の規定によって過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるためには、……青色申告法人が作成しなければならない帳簿の全てについて、優良な電子帳簿の保存要件を満たして保存等を行う必要があります。」とされている(電子帳簿保存法一問一答 問41参照)。
そこで企業としては「別表二十一」の内容が気になるところだが、当該別表には、例えば、(十四)として「賃金、給料手当」との項目がある。賃金は個人情報の塊であり、通常、企業の人事部の保管下にある。このため、ただでさえ経理部の統制が効きにくい状況であり、電子化はできていても「優良な電子帳簿の要件を満たして保存等」ができている可能性は著しく低い。こうした中、加算税軽減の特例措置を享受するために、通常は企業の人事部の保管下にある賃金台帳等も含め、全ての帳簿について優良な電子帳簿の保存要件を満たす必要があるとされており、企業にとって酷との声が挙がっている。
このインセンティブ措置自体は企業に好評だが、同措置の適用を受けるためには、同措置をより実効性のある制度に見直すよう、令和5年度税制改正で電子帳簿保存法の更なる改正を期待する声が高まっている。
スキャナ保存制度
スキャナ保存制度について更なる要件緩和
同じく経産省の令和5年度税制改正要望の一部として、スキャナ保存制度の更なる要件緩和が実施される可能性があることが本誌の取材により判明している。
スキャナ保存にはいくつか要件があり、入力者等情報の確認要件もその1つとされている。平成27年度税制改正以前は、本要件は電子署名要件とされていたが、電子署名要件の目的である①入力者を特定する機能、②電磁的記録の非改ざんの証明機能のうち、②については、別途講じられているタイムスタンプ要件でも足りるとの判断により、①のみが残ることとなった。現行制度の下でのスキャナ保存に際しては、「当該国税関係書類に係る記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと」が必要となる(電帳法施行規則2⑥三)。ただし、この入力者等情報は、企業の通常の文書作成・保管プロセスにおいては必要不可欠なものではない。
入力者等確認要件、読み取り情報保存要件の存在意義を問う声
こうした中、企業からは、スキャナ保存制度に適合するためだけに入力者等情報の確認に対応するのは不合理との声がある。例えばタクシーの領収書を例にとると、経費を支出した者(=タクシーに乗った者)ではなく、当該領収書に係る入力担当者の情報を保存しておくことが、適正課税の確保の観点からどれだけ効果があるのか、ということである。
また、同じく適正課税の確保という観点からは、読み取り情報(解像度、階調、大きさ)の保存要件(電帳法施行規則2⑥二ハ)も、必要性が乏しいとの指摘がある。すなわち、スキャナ保存制度の適正な制度運用に不可避なのは、あくまでも解像度が200dpi相当以上である(=鮮明である)こと、赤・青・緑の階調が256階調以上である(=カラーが明瞭である)こと(電帳法施行規則2⑥二イ)といったスキャン・データのクオリティを維持することであって、わざわざ解像度・階調等のデータを保存することにどれだけの意義あるのか、ということである。実際、市中でも、一部の市販システムでなければ解像度が容易に判明しないとの指摘もあり、使い勝手の悪さが指摘されている。
こうした声を受け、入力担当者の情報の確認を不要とする(電子取引についても同様)とともに、読み取り情報の保存要件も不要とする。このほか、帳簿の記録事項との間に、相互にその関連性を確認することができるよう求める書類を、契約書、領収書、納品書、請求書など、資金や物の移動に直結・連動する「重要書類」に限定する(見積書、注文書、検収書などは重要書類に該当しない)。
税務手続きの電子化
源泉徴収票、給与明細の電子交付、承諾要件がネックに
所得税においては、マイナポータルとの連携により、住宅ローンの年末残高証明書や生命保険料控除証明書などの各種申告書への電子的な取り込みなど、年末調整のデジタル化が進められてきた。ただ、年末調整以外の分野では、電子化が不十分な手続きがある。
その1つが給与所得の源泉徴収票や給与支払明細書だ。会社員であれば会社から定期的にこれらの書類の交付を受けているはずだ。いずれも法定書類であり、原則として紙で交付する必要があるが、給与の支払いを受ける者の承諾が得られれば、会社は電子交付することができる(所法226①④、231①②)。承諾を得る際には、会社側が「その用いる電磁的方法の種類および内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない」とされている(所令353①、356①)。
この「承諾要件」が、これら書類につき書面から電子交付に移行する際のネックになっている。仮に会社が全社員に対し、一律で電子交付に移行したい旨を通知し、書面又は電子により承諾するよう求めたとしても、必ず返事をしない(意思表明をしない)社員が存在する。会社側としては、税法に則れば、意思表明しない社員は「承諾しなかった」とみなさざるを得ない。そのため、大多数の社員が電子交付を希望している場合であっても、会社による社員の意思確認に長期間を要し、会社単位での電子交付への移行が進展しないという事態が生じている。
「運用」での問題解決には限界も
この確認作業は、社員が数万人以上等の規模の会社にとっては、計り知れない負担となる。税務手続きのうち、法人税関連のものは経理部、所得税関連のものは人事部と、役割分担が決まっている企業もあり、このような企業では人事部が対応に苦慮するのは間違いない。経済社会のデジタル化に反するどころか、働き方改革にも反するとの指摘もある。
この課題に対応するため、社員が明示的に承諾しない場合であっても承諾があったものとみなすなど「税法解釈の柔軟化」があり得るのではないかとのアイデアも聞かれる。しかし、税法で「承諾を得て」と明記されている以上、運用レベルで解決できる問題なのかとの指摘もあり、課題解決には税制改正が必要となる可能性は十分にある。
外形標準課税
「資本金1億円超」という現行基準は基本的に維持
総務省は8月、地方財政審議会に「地方法人課税に関する検討会」を設置し、デジタル課税のほか、かねてから減資等による課税逃れが問題視されている外形標準課税について議論を重ねてきたが、11月16日に「中間整理」を公表するとともに、自民党税調にも議論の状況を報告している。
「中間整理」では、外形標準課税の対象法人数の減少について、「資本金1億円以下への減資を行う法人が多いこと及び資本金1億円超への増資を見送ることが主な原因ではないかと推測できる」との分析結果を示す一方で、「(3)課題への対応の必要性と方向性」には以下の記述がある。
外形標準課税の対象法人の基準として、制度創設以来資本金が用いられてきていることも踏まえ、この問題への対応策としては、小規模な企業への影響に配慮するとともに、必要以上に多くの法人に制度見直しの影響が及ばないよう、現行基準(「資本金1億円超」の法人)を基本的に維持しつつ、公平性等の観点から、減資・組織再編の動きに対応するための追加的な基準を付け加えることが考えられる。
「小規模な企業への影響に配慮するとともに」「必要以上に多くの法人に制度見直しの影響が及ばないよう」「現行基準(「資本金1億円超」の法人)を基本的に維持しつつ」との表現からは、中小企業への配慮が色濃く伺われる。ただでさえ、中小企業は来年10月から開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)への対応に懸念を強めている。こうした中、「減資対策」との名の下、資本金1億円のバーを引き下げることなどにより外形標準課税の対象を中小企業にも拡大するのであれば混乱は必至。中小企業団体から表明された強い懸念が上記記述の背後にあったことが本誌の取材により確認されている。
減資・組織再編に対応するための追加的基準については結論出ず
もっとも、中間整理では“外形外し”を容認すると言っていない。上記記述の後段では「減資・組織再編の動きに対応するための追加的な基準を付け加える」としている。
中間整理には、減資・組織再編に対応する「追加的な基準」について、「減資については、資本金を資本剰余金に振り替える項目振替型減資への対応を中心として検討」とある。すなわち、総務省は、振替によっても数値に変動がない法人税法/地方税法上の資本金等の額を何らかの形で用いることも選択肢の1つとして検討しているということだ。
ただし、資本金等の額は、そもそも計算が複雑であることに加え、自己株式の取得を行う場合には減少するため、納税者による操作の可能性がないとは言えない。平成27年度改正では、外形標準課税資本割の課税ベースの計算上、資本金等の額が「資本金+資本準備金の額」を下回る場合、「資本金+資本準備金」を用いることとされたが、この方式を外形標準課税の適用の有無の判定に組み込めば、判定プロセスはかなり複雑なものとなる。外形標準課税を巡っては、現状でも付加価値割の計算等が複雑で実務負担が大きいとして簡素化を求める声が企業側から上がっており、こうした簡素化の流れにも逆行する。
結局、地方法人課税に関する検討会では「資本金+資本剰余金」を用いる案も含め、様々なオプションが提示はされたが、決着に至るほど議論が深まったわけではなく、結論は来年以降に持ち越しとなる。
組織再編、典型的には「分社化による持株会社+事業会社」への再編の問題は、法人税におけるグループ法人税制を参考に、100%支配関係のあるグループについては、親法人が大法人であれば、子法人が資本金1億円以下であっても大法人とみなして外形標準課税を適用する案もオプションの1つとして示唆されたが、この案では分社化以外の通常のグループ会社も捕捉してしまうのではないか、外形標準課税の対象法人が逆に増えすぎるのではないか、都道府県がグループの資本関係をタイムリーに把握できるのか、“100%外し”の可能性への対応など、様々な課題があり、こちらも結論は出ていない。
このように、制度改正に向けて対応すべき課題は多い。しかし、ここまで検討した以上、総務省としては将来的に何もしないわけにはいかなくなったと言える。企業にあっては、大綱の表現を確認するとともに、自社及び資本金1億円以下の子法人への影響について確認しておく必要があろう。
法人税増税
「法人増税を明記」との大手紙の過熱報道合戦は“勇み足”に
令和5年度税制改正における法人税関係改正の“裏テーマ”として、防衛費の増加に伴う法人税増税の可能性が指摘されていたが、政府の「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」が11月22日にとりまとめ岸田総理に提出した報告書を読むと、風向きが変わりつつあることがうかがえる。
報告書では、防衛費増に伴う財源問題について、増税の可能性を含め提言を行っており、具体的な検討は政府・与党が引き継いでいる。提言の結論部分(抜粋)は以下の通りとなっている。
国を守るのは国民全体の課題であり、国民全体の協力が不可欠であることを政治が真正面から説き、負担が偏りすぎないよう幅広い税目による負担が必要なことを明確にして、理解を得る努力を行うべきである。持続的な経済成長実現と財政基盤確保とを同時に達成するという視点に立ち、国民各層の負担能力や現下の経済情勢へ配慮しつつ、財源確保の具体的な道筋をつける必要がある。
その際、高齢化が進むなかで今後も社会保険料等の負担が増すことを踏まえるとともに、成長と分配の好循環の実現に向け、多くの企業が国内投資や賃上げに取り組んでいるなか、こうした企業の努力に水を差すことのないよう、議論を深めていくべきである。
政府は、多角的な検討を速やかに行い、本年末に方針が決定される令和5年度予算編成・税制改正において成案を得て、具体的な措置を速やかに実行に移すべきである。
まず注目すべきポイントは、「法人税」に関する記述が落ちたことだ。原案では、「財源の一つとしての法人税については、成長と分配の好循環の実現に向けて……」とされていたが、あたかも法人税が財源として決まっているかのような書きぶりは、他税目との関係においてバランスを欠くとの指摘もあり、取りまとめの過程で修正された。
ただ、法人税との表現を落としても、「多くの企業が国内投資や賃上げに取り組んでいるなか」との表現は残っている。そこで、この表現とバランスをとるため、原案にはなかった「高齢化が進む中で今後も社会保険料等の負担が増すことを踏まえるとともに」との一文を加えることで、現役世代に対する所得税についても、過剰な負担は好ましくないというニュアンスを出すことになったという経緯が本誌の取材により確認されている。「法人増税を明記」などと連日のように過熱報道合戦を繰り返していた大手紙は、誤報とは言わないまでも“勇み足”という結果となった。もっとも、法人増税の可能性は消えていない。
令和5年度予算編成・税制改正での「成案」へ
また、令和5年度予算編成・税制改正において「成案」を得るとの表現が用いられていることも注目される。ちなみに、岸田総理は11月9日の有識者会議で「令和5年度予算編成・税制改正において所要の結論を得られるよう、与党と連携して、引き続き検討を深めてください」と指示しており、「成案」との表現は用いていない。
その後、岸田総理は11月28日、財務大臣に対し、年末に、緊急的に整備すべき5年間の中期防衛力計画の規模、また、将来にわたり強化された防衛力を安定的に維持するための、令和9年度に向けての歳出歳入両面での財源確保の措置、これを一体的に決定することを指示している。
増税問題については、今後、与党の税制調査会が引き取ることになるが、防衛費問題に関する議論の本格化は今週後半からであり、12月12日の週に一気に政治的に決着するとの見方が出ている。この短期間でどのような「成案」を得ることになるのか、議論の行方が注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.