解説記事2022年12月05日 SCOPE 非営利型一般財団法人が行ったグループ内金銭貸付は収益事業(2022年12月5日号・№957)
利子配当等非課税も先行事案同様認められず
非営利型一般財団法人が行ったグループ内金銭貸付は収益事業
非営利型の一般財団法人である原告が、収益事業以外の事業に属する資産から生じた預貯金利子等に係る源泉所得税は非課税とすべきであり、また、グループ内の別法人に対する金銭の貸付けは収益事業に該当せず、貸付利息に法人税は課されないとして争っていた事案で、東京地裁民事3部(市原義孝裁判長)は令和4年11月18日、納税者敗訴の判決を下した。
東京地裁は、先の同種事案同様、公益法人と非営利型法人との間の源泉所得税の課税・非課税の取扱いの区別を設けた平成20年改正は合理的であると判断した。
また、法人税法施行令5条1項3号に規定する金銭貸付業は、必ずしも貸金業法等にいう『貸金業』のような登録を受けて営業を行う者に限る必要はなく、特定又は少数の者に対して貸し付けるものであっても、その貸付けが継続している限りは金銭貸付業に当たるとして、貸付利息に法人税を課した本件課税処分を適法とした。
約定利息を付した多額の金銭貸付けは、金融機関の融資と変わらず収益事業
非営利型の一般財団法人が、収益事業以外の事業に属する資産から生じた配当及び利子等については非課税とされるべきとして、源泉徴収された所得税の還付を求めた事案(以下、先行事案)で、控訴審でも敗訴したのは既報のとおり(本誌944号)。
本件は、当該一般財団法人が、①その一つ前の事業年度分についても同様の訴えを起こすとともに、②グループ内の別法人A社に対する金銭の貸付けが収益事業に該当し、貸付利息が法人税の課税対象になるかについても争った事案である。
原告は、上記①の争点について、先行事案と同様に、公益法人制度改革に伴う平成20年税制改正前には、旧公益法人が支払を受ける利子及び配当等が非課税とされていたことから、非営利型の一般法人に非課税規定が適用されなくなった当該改正は違憲であると主張していた。
これに対し東京地裁は、「仮に、原告の主張するように本件税制改正が違憲であったとしても、これにより本件預貯金利子等に対する所得税の額を法人税の額から控除し、それでも控除しきれない部分について還付を受けることができることになる法律上の根拠はない」とした上で、本件税制改正が違憲かどうかについても検討した。
東京地裁は、先行事案同様、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決を引用し、「公益法人については、高い公益性を確保するための制度上の担保があるのに対し、非営利型法人については、公益目的事業の受け皿となる反面、公益性を担保する制度上の仕組みがなく準則主義により簡便に設立することが可能であり行為規範や事業に対する監督が最小限度にとどまっているという違いがあることや、非営利型法人の中にも営利法人に近い事業活動を行っているものもあることから、公益法人に比して適正な課税を確保する必要性がある」点を指摘、利子及び配当等について、公益法人は非課税であるのに対し、非営利型法人は課税するという区別は、正当なものであり著しく不合理とはいえないとの判断を下した。
特定・少数の者への貸付けでも金銭貸付業
続いて原告は、上記②の、グループ内の法人に対する金銭の貸付けが収益事業に該当するか否かという争点については、「店舗その他の事業活動の拠点となる一定の場所は設けておらず、『事業場を設けて行われるもの』に該当しない」として、法人税法2条13号に定める収益事業には該当しないと主張した。
しかし、東京地裁は、「『事業場』を設けるとは、その収益事業を行うために特別の施設を設けることを要するものではないと解され、原告が本件所在地において事務所を設けて事業活動を行い、その一環として本件金銭貸付を行っている以上、『事業場を設けて行われるもの』に該当する」として、原告の主張を斥けた。
また原告は、「本件金銭貸付は、グループ企業であるI社に対する貸付けであり、不特定多数の者を相手方とするものではないから、法人税法施行令5条1項3号に掲げられた金銭貸付業に該当しない」とも主張したが、東京地裁は、「多額の金銭を約定利息を付して貸し付ける金銭の貸付けは、銀行などの金融機関が一般企業に対して通常業務として行う融資と何ら異ならないものであり、公益法人等以外の法人が一般的に行う事業と競合するもの」と指摘。
「貸付行為を反復継続しているものでも、業として貸付行為を行っているものでもない」との原告の主張に対しては、法人税法施行令5条1項3号に規定する金銭貸付業は、営利企業との競合関係の有無のみならず課税上の公平の維持等の専ら税制固有の理由から収益事業として規定されたものであるから、必ずしも貸金業法等にいう『貸金業』のような登録を受けて営業を行う者に限る必要はなく、特定又は少数の者に対して貸し付けるものであっても、その貸付けが継続している限りは金銭貸付業に当たるとの考えを示した。
そして、原告がI社に対し3年間継続して本件金銭貸付を含む多額の金銭の貸付けを行っていることに照らせば、本件金銭貸付は法人税法施行令5条1項3号に規定する金銭貸付業に該当するとし、原告がI社以外の不特定多数の者に対し金銭の貸付けを行っていないとしても、そのことによって前記認定判断が左右されるものではないとした。
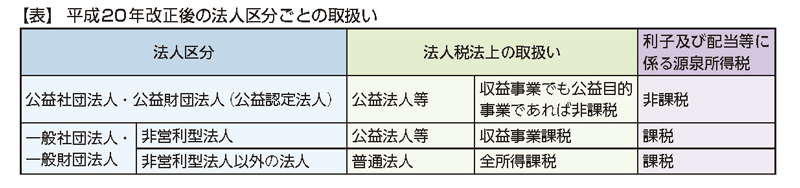
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























