解説記事2022年12月19日 ニュース特集 相続前贈与の加算期間を7年に延長、資産移転時期の選択に中立的な税制へ(2022年12月19日号・№959)
ニュース特集
相続時精算課税に基礎控除を創設
相続前贈与の加算期間を7年に延長、資産移転時期の選択に中立的な税制へ
令和5年度税制改正では、資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築が図られることになった(図1参照)。暦年課税と相続時精算課税制度の選択制は引き続き維持した上で、相続時精算課税制度で受けた贈与については、暦年課税の基礎控除とは別途、毎年、110万円までは課税しないこととするなど、同制度をより適用しやすいものにすることで利用を促す。また、暦年課税における相続前贈与の加算期間を現行の3年から7年に延長する。制度の廃止を含めた検討が行われていた「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」及び「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については、一部見直しを行った上で適用期限を前者は3年、後者は2年延長することで決着した。
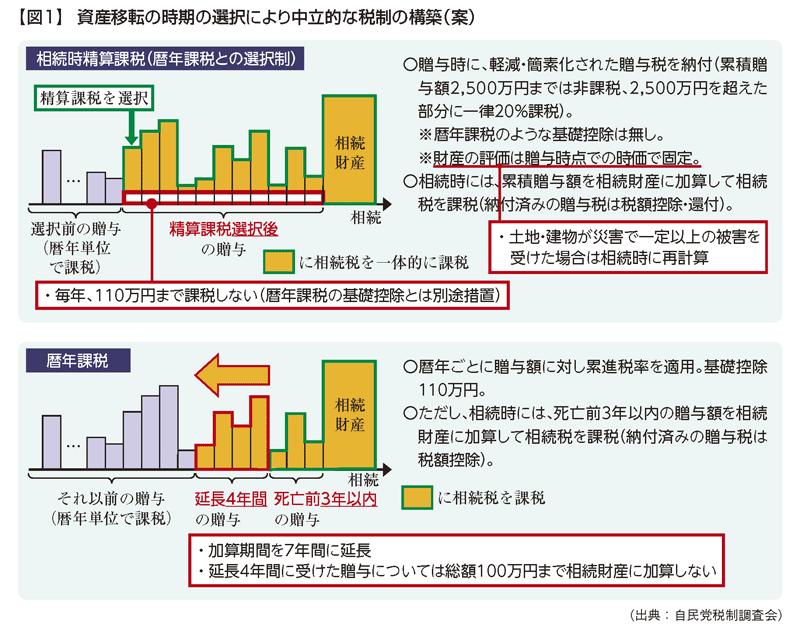
引き続き暦年課税と相続時精算課税の選択制
政府税制調査会に設置された「相続税・贈与税に関する専門家会合」が11月8日に取りまとめた「資産移転の時期に中立的な税制の構築に向けた論点整理」と題する論点整理では、法定相続分課税方式の見直しについては中期的な課題とした上で、当面の対応すべき課題として①相続時精算課税制度、②暦年課税における相続前贈与の加算、③経済対策等として時限的に講じられている贈与税の非課税措置の3点が掲げられており、令和5年度税制改正でどのような見直しが行われるのか注目されていた。結果的には廃止すべきと提言されていた贈与税の非課税措置以外は基本的に専門家会合の提言に近い改正内容となっている。また、中里実政府税制調査会会長が明言していたとおり、暦年課税の廃止は行わず、引き続き暦年課税と相続時精算課税制度の選択制となっている。
「法定相続分課税方式」の見直しは中期的な課題
資産移転の時期に中立的な税制の最終的な形は相続税・贈与税の一体化ということになる。この場合、贈与者は税負担を意識して財産の移転のタイミングを計る必要がなく、その一方で税率の格差を狙った意図的な税負担の回避も防止することができる。
日本の場合は、「法定相続分課税方式」が採用されているが、贈与税は相続税とは別体系であり、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制となっている。暦年課税は、資産移転の時期に中立的ではないとされているため、最終的には「暦年課税」の廃止を含めた「法定相続分課税方式」の見直しの検討が必要になる。現行の法定相続分課税方式から諸外国のような遺産課税方式や、遺産取得課税方式に移行すべきとの意見もあるが、中期的な検討課題となっている。
110万円までは課税せず
では、今回の改正内容についてみてみることにしよう。まず、相続時精算課税制度についてだ。相続時精算課税制度は、生前贈与と相続で税負担が大きく異なる暦年課税とは違い、選択後は生前贈与と相続税で税負担は一定であり、資産移転の時期の選択に中立的であるとされている。
しかし、令和2年分のデータでみると、申告件数は暦年課税の36.4万件に対して相続時精算課税は4.0万件と低調にとどまっている。申告件数が低調にとどまる理由としては、暦年課税とは異なり、110万円以下の少額の贈与であっても申告しなければならないことや、贈与財産の価額が贈与者の相続開始時までに下落した場合であっても、贈与時の価額で相続税を課税することとされているため、贈与財産の価額が下落したときは相続時精算課税制度を選択したことで不利益が生ずることなどがネックとなっていた。
このため、今回の税制改正では、毎年、110万円までは課税しない措置を導入する(図2参照)。暦年課税と同様、110万円までは確定申告を要しないことになる。複数の特定贈与者から贈与を受けた場合には、それぞれの贈与額に応じ按分する。
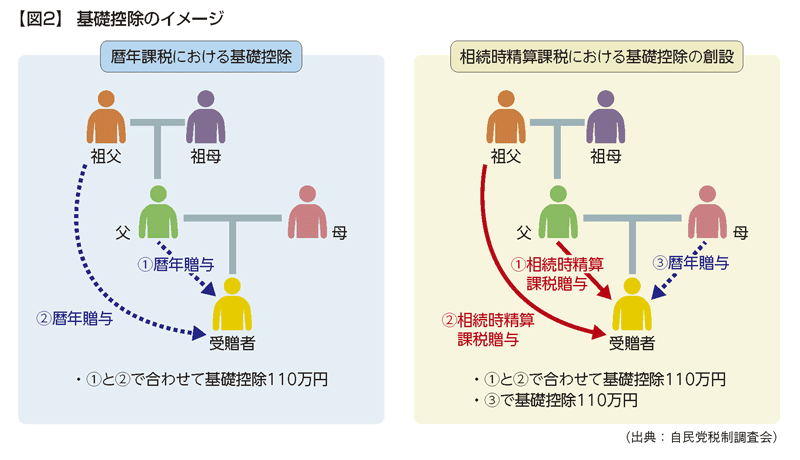
また、財産の評価は贈与時点の時価で固定されているため、土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合には相続時に再計算できる仕組みを取り入れることとした。
相続前贈与の加算期間、完全移行は令和13年1月以降
暦年課税における相続前贈与の加算については、現行の3年から7年に延長する。加算期間を延長することにより、現行制度よりも「資産移転の時期の選択に中立的な税制」に少し近づくことになる。
令和6年(2024年)1月以降に受けた贈与について加算期間の延長を適用するが、令和9年(2027年)1月以降、加算期間は順次延長されることになり、加算期間が7年となるのは令和13年(2031年)1月以降となる(図3参照)。
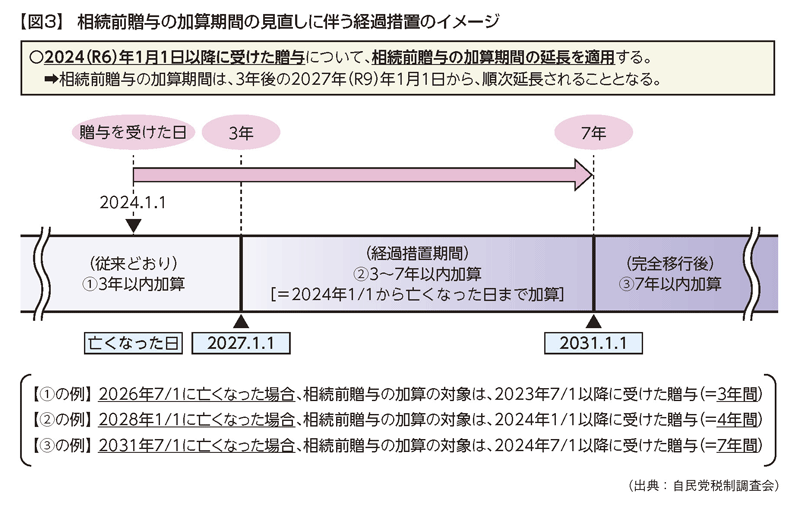
100万円までは相続財産に加算せず
また、延長した4年間に受けた贈与については、総額100万円までは相続財産に加算しないこととする。
贈与税の非課税措置、次の適用期限には廃止も含めて検討
富裕層を優遇し、格差の是正に逆行する制度であるとの批判の声がある「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については、令和4年度税制改正大綱においても「格差の固定化防止等の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある」と明記されていたことから、制度の廃止を含めた検討が行われたが、こども家庭庁が設置されることもあり、結果的には一部見直しを行った上で適用期限が延長されることになった。
契約終了時の残高には贈与税の本則税率
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については、現行の1,500万円とされている非課税限度額を維持し、適用期限を令和8年3月31日まで3年延長する。ただし、契約終了時の残高に贈与税が課される際の税率は、特例税率ではなく贈与税の本則税率とする(下表参照)。また、契約期間中に贈与者が死亡した際、贈与者に係る相続税の課税価格の合計(≒小規模宅地特例等の適用後の遺産総額)が5億円を超える場合には、受贈者の年齢等に関わらず、残高を相続財産に加算することとする。
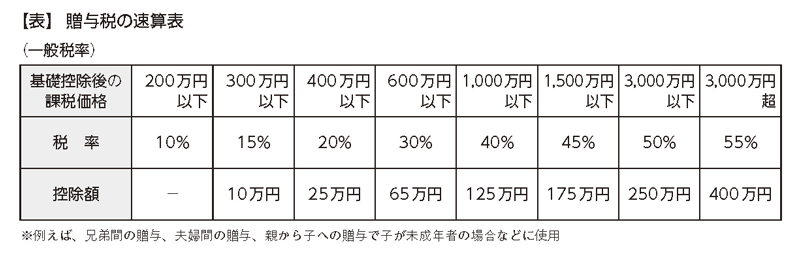
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」については、現行の1,000万円とされている非課税限度額を維持し、適用期限を令和7年3月31日まで2年延長する。ただし、契約終了時の残高に贈与税が課される際の税率は、こちらも贈与税の本則税率とする。
なお、次の適用期限の到来時には、利用件数や利用実態等を踏まえ、制度の廃止も含め改めて検討が行われる模様だ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























