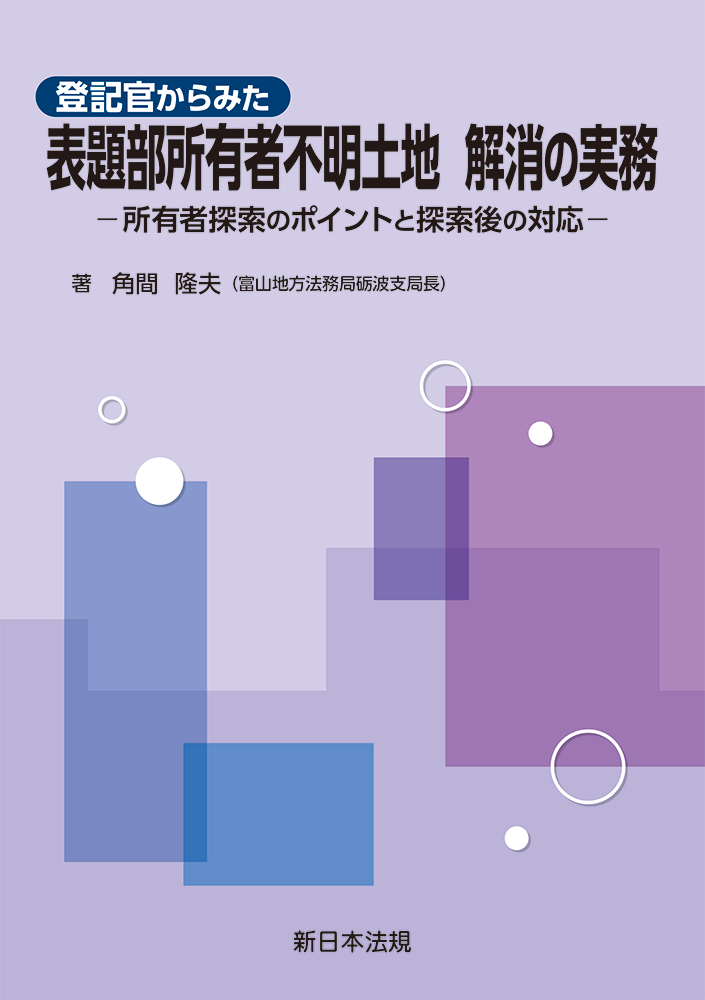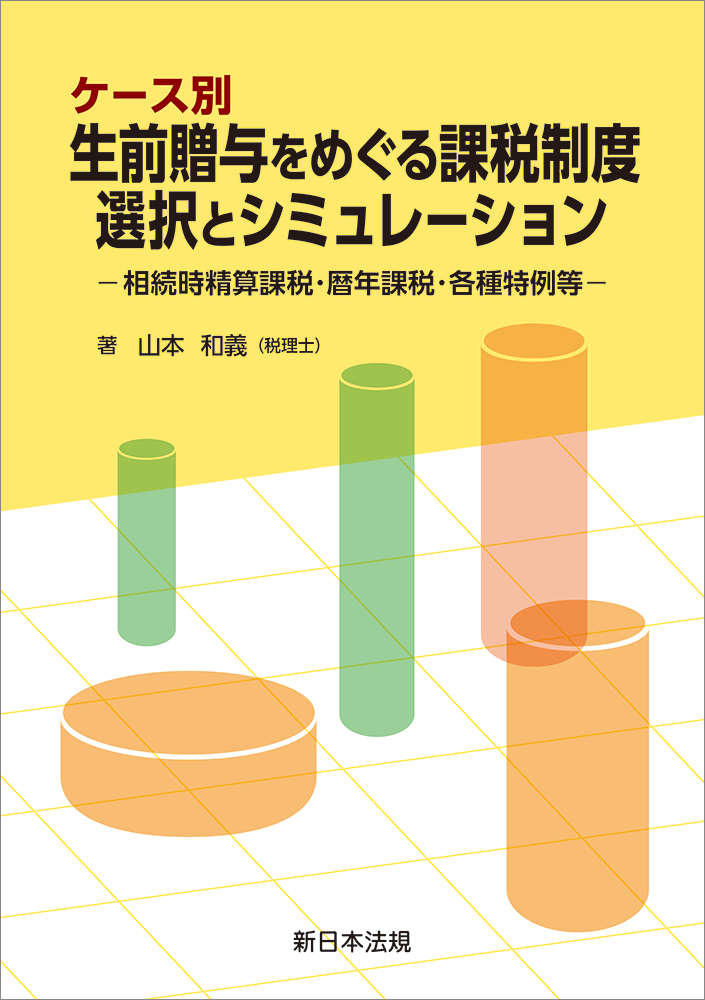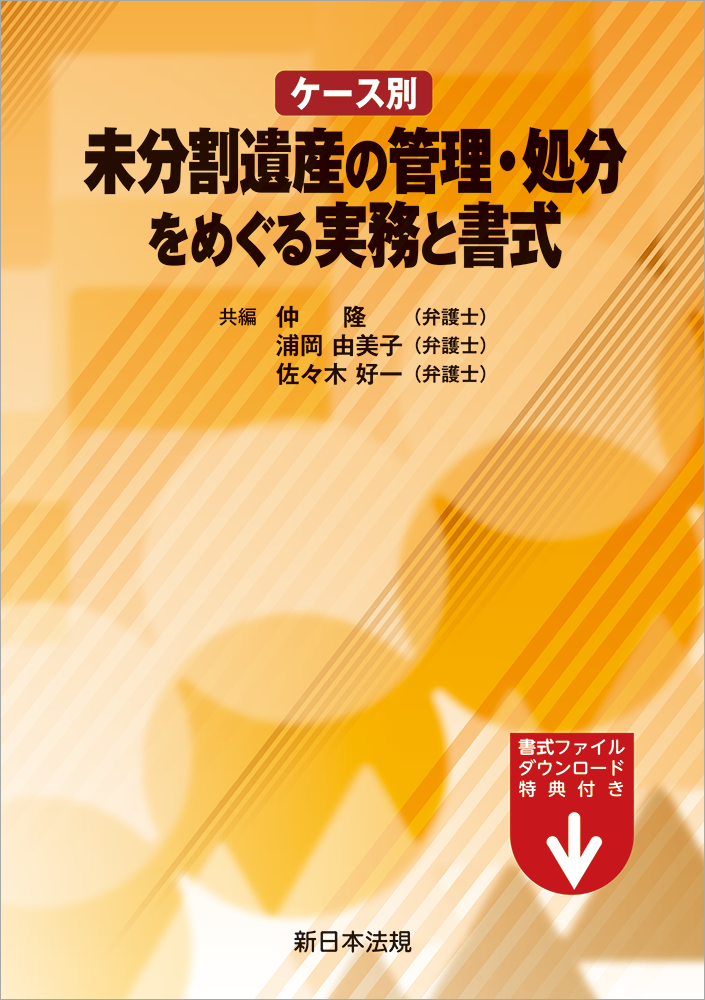資料2022年12月23日 【税制改正関連資料】 第19回税制調査会 議事録
税制調査会 2022年度
2022年10月18日 第19回 ・個人所得課税について
議事録 (PDF形式:476KB)
会議資料
記者会見録 (PDF形式:111KB)
税制調査会(第19回総会)議事録
日 時:令和4年10月18日(水)14時30分
場 所:WEB会議(財務省第3特別会議室を含む)
○中里会長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから第19回「税制調査会」を開始いた
します。
本日の出席者一覧は、お手元にお配りさせていただいているとおりです。オンライ
ンで御出席の方につきましても、現在、全員の方との接続が確認できております。
オンラインで御出席の方におかれましては、会議の途中でパソコン操作などに支障
が生じましたら、あらかじめお伝えしております事務局の電話番号に御連絡をいただ
ければと思います。
なお、プレスの方々には、密回避のため、別室にてリアルタイムで会議の模様を御
覧いただくこととしております。
加えて、これまでと同様に、インターネットでのリアルタイム中継も行っておりま
すので、その点、お含みおきください。
それでは、議事に入りたいと思います。
本日も、税目ごとの議論ということで、10月4日に引き続いて2回目となりますけ
れども、「個人所得課税」を議題にして議論を進めたいと思います。
本日の議事の流れに関しましては、最初に事務局から資料の御説明をいただき、そ
の後に委員の皆様で意見交換を行う時間を設けたいと思います。
早速、主税局税制第一課の関課長、続いて、自治税務局市町村税課の植田課長の順
に御説明をよろしくお願いいたします。
○関主税局税制第一課長
税制第一課長の関でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料総19-1に沿いまして御説明いたします。
前回は、どちらかといいますとマクロの所得税負担の状況について御議論いただき
ましたけれども、今回は諸控除の見直しなど比較的ミクロのテーマを中心に御説明申
し上げたいと思います。
まず、現行制度の概観ということで、3ページ目です。この資料は、総合課税分に
つきまして、課税ベースがどの程度あり、どの程度の税額が生じているかということ
を図示したものでございます。恩給や失業等給付という非課税所得を除きました約
270兆円の収入のうち、まず給与所得控除・公的年金等控除といった各種所得につい
ての控除、その次に基礎控除・配偶者控除といった人的控除や社会保険料控除などの
所得控除を適用した後に、課税所得が約120兆円になり、そこに累進税率を適用する
ことで税額は13.6兆円となるというのが現状でございます。
4ページ目でございます。この資料は、前のページで整理いたしました所得控除と
いう欄のうち、人的控除というところに整理させていただいた部分の詳細をまとめた
ものです。基礎控除・配偶者控除・扶養控除といった基礎的な人的控除と、障害者控
除や寡婦控除といった特別な人的控除に大別できます。
5ページ目でございます。この資料は、人的控除以外の所得控除をまとめてござい
ます。社会保険料控除や生命保険料控除などが代表例となってございます。
6ページ目でございます。こちらから、これまでの税制調査会の議論において、
「働き方やライフコースの多様化等への対応」として議論が行われてきました幾つか
の論点を御紹介申し上げたいと思います。
7ページ目をお願いいたします。この資料は、令和元年9月の取りまとめ文書の記
述を抜粋させていただいたものです。最後の方に下線を引かせていただきましたとお
り、「働き方の違いによって不利に扱われることのない、個人の選択に中立的な税制
の実現に向け、所得再分配機能が適切に発揮されているかといった観点も踏まえなが
ら、諸控除の更なる見直しを進めることが重要」といった御指摘をいただいてきてい
るところです。
8ページ目から、1つ目の所得の種類ごとの負担調整から納税者の人的な事情に配
慮した負担調整への見直しという論点をまず取り上げさせていただきたいと思います。
9ページ目でございます。これまで議論いただいてまいりました、経済社会の構造
変化のキーワードの一つが「働き方の多様化」でございます。この資料では、自営業
主の中で、士業や小売店主といった伝統的自営業から、建築技術者・保険外交員とい
った使用従属性の高い自営業者の割合が高まっているという状況を左側にまとめてご
ざいます。また、フリーランスの人口が増加傾向にございまして、内閣官房の調査で
は足元で約462万人といった分析がなされております。
10ページ目でございます。こちらの資料は、昨年6月の専門家会合でフリーランス
協会から御提出いただいた資料を引用させていただいております。正規雇用から派
遣・契約・パートといった非正規雇用、さらにはギグワーカーや請負等のフリーラン
スといったように、職種・就労形態が多様化していることが見てとれます。
11ページ目でございます。こういった状況に対応いたしまして、税負担の調整の在
り方につきましては、収入の稼得形態によって税制上の取扱いが大きく異なることに
なる所得の種類ごとの負担調整、グリーンで塗らせていただいたところですけれども、
こういった調整から、所得の種類と関係なく収入の稼得形態に中立的な、人的な事情
による負担調整、赤く塗らせていただいているところですけれども、こういった方へ
重点を移していくことが指摘されてきたところでございます。
12・13ページ目につきましては、平成27年11月の論点整理におきまして、今、御説
明したような内容が触れられている箇所を抜粋させていただいております。
14ページ目をお願いいたします。こういった御議論を踏まえまして、平成30年度の
税制改正におきまして、給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替え
るといった見直しが行われてきているところでございます。
15ページ目からは、2つ目の配偶者控除に関する論点の御紹介でございます。
まず、16ページ目でございます。配偶者控除につきましては、政府税制調査会の中
で議論が重ねられてまいりまして、見直しの必要性が指摘されてきております。平成
26年11月の論点整理の中では、共働きよりも片働きの優遇になっている、あるいはパ
ート世帯の優遇になっている、配偶者特別控除の導入により、配偶者の収入が103万
円を超えても世帯の手取りが逆転しない仕組みとなっていて、税制上の103万円の壁
は解消しているけれども、企業の家族手当の支給基準として援用されている実態があ
る、こういった御指摘をいただいております。
17ページ目でございます。この資料は、平成26年11月の論点整理で示されました配
偶者控除の見直しの選択肢、それから、その後の議論を踏まえました平成28年11月の
「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」、この2つの文書
におきまして整理いただいた内容をまとめております。
選択肢につきましては、Aとございますけれども、配偶者控除を廃止しつつ、廃止
により生ずる財源を子育て支援の拡充に充てるという案。それから、Bのところです
けれども、配偶者控除に代えまして、配偶者の所得計算において控除し切れなかった
基礎控除を納税者本人の方に移転する移転的基礎控除を導入して、夫婦二人で受けら
れる控除額を一定とする案。それから、Cとございますけれども、配偶者控除に代え
まして、若い世代の結婚・子育てに配慮する観点から、夫婦世帯に対して配偶者の収
入にかかわらず適用される新たな控除を導入する案。こういったものが挙げられてき
たところでございます。
一方で、それぞれの案につきましては、このページの中にも書かせていただいたよ
うな論点も指摘されまして、意見の収れんには至らなかったところでございます。
そうした中で、一番下の箱にございますように、企業の手当の支給基準として援用
されている喫緊の課題への対応という観点からも、「103万円」を引き上げることも
一案との意見も出されていたところでございます。
18ページ目では、こうした最後の点も踏まえまして、平成29年度税制改正におきま
して、所得控除38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、103万円から、矢印
にございますように150万円に引き上げるという見直しが行われたところでございま
す。
19ページ目は、いわゆる「103万円の壁」という御指摘について整理をしておりま
す。配偶者特別控除の導入により、配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手
取り収入が逆転しない仕組みとなってございます。税制上、いわゆる「103万円の壁」
は解消しているということでございます。
他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することにより、
103万円以内にパート収入を抑える傾向があり、こうした傾向の要因としては、103万
円という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用されているためではないか、
また、いわゆる「103万円の壁」が引き続き心理的な壁として作用しているためでは
ないか、こういった御指摘がなされているところでございます。
20ページ目の資料は、民間企業の家族手当の支給状況をまとめさせていただいてお
ります。①のところにございますように、少しずつ、家族手当自体を廃止する、ある
いは配偶者に着目した形での家族手当は行わないといった企業は増えつつございます。
ただ、②にございますように、配偶者の収入による制限の額につきましては、真ん中
に103万円という欄があるかと思いますけれども、この基準を採る企業が少しずつ減
少しておりますが、一定数存在してございます。
なお、この点に関しましては、64ページ目に参考資料を付けておりますけれども、
全世代型社会保障構築会議の中でも御議論があり、その中で、企業の配偶者手当に関
しましては、労使において改廃・縮小に向けた議論が進められるべきといった御指摘
もいただいているところです。
21ページ目から、3つ目の論点でございます退職所得に関する論点を御紹介いたし
ます。
まず、22ページ目は、平成12年の答申を引用してございます。退職金の性格につき
ましては、賃金の後払いという性格、あるいは退職後の生活保障といった性格が指摘
されてございます。そのほか、功労報償といった点も指摘されているところでござい
ます。
23ページ目でございます。こちらは、その後の税調の答申を引用しておりますが、
令和元年9月の取りまとめ文書の下の方ですが、退職給付に係る税制は、一時金払い
か年金払いかで異なるなど、給付の在り方に対して中立的ではなく、また、転職の増
加など働き方の多様化を想定していないとの御指摘が書かれております。
24ページ目でございます。こちらは退職所得の課税方式でございます。特徴といた
しましては、一時にまとめて相当額を受給することなどを踏まえまして、平準化の観
点から「2分の1課税」の仕組みが取られていること、それから、勤続年数が長いほ
ど厚く支給される退職金の支給形態も反映して、勤続年数20年超になりますと、1年
当たりの退職所得控除額が40万円から70万円に増加する形になっている、こういった
特徴がございます。この点につきまして、長期継続雇用を特に優遇することが労働移
動に与える影響があるのではないかといった指摘をする声が存在するところでござい
ます。
25ページ目でございます。こちらは、令和3年度改正で行われました直近の改正内
容をまとめてございます。退職給付の実態を踏まえまして、5年以下の勤務の役員以
外の従業員への退職金の一定金額以上の部分につきまして、「2分の1課税」の適用
から外すという改正を行っております。
26ページ目から、現在の退職金の支給状況をまとめてございます。まず、退職金の
支給形態でございますけれども、「退職一時金制度のみを有する」企業の割合が増加
傾向にございます。
27ページ目は、雇用の流動化の状況ということで、従業員の平均勤続年数を国際比
較しております。特に左側の男性の従業員の平均勤続年数が直近10年間でほぼ変わっ
ておらず、国際的に見ても最も長くなっているというのが現状でございます。
28ページ目は、勤続年数別の賃金水準を国際比較いたしますと、勤続20年目以降の
賃金水準が大幅に上昇する傾向にございます。
29ページ目です。実際の退職手当の額のイメージとしてモデルケースをお示しした
ものです。20年前、平成13年のブルーの線が、勤続年数20年を超えますと退職手当の
額の上がり幅がきつくなるという傾向がございましたけれども、それと比較しますと、
令和3年の、黒い実線のところに関しましては、以前ほどその傾向が顕著ではなくな
っているのが見てとれます。
30ページ目は、前のページの令和3年分の支給額に対応いたしまして、退職所得控
除額が灰色でございますが、どの程度適用になって、課税対象は黒色の部分ですけれ
ども、そこがどの程度あるかということを図示したものでございます。
31ページ目から、引き続いて、私的年金等に係る税制について御説明いたします。
32ページ目ですけれども、令和元年9月の取りまとめの関連箇所の抜粋でございま
す。まず、働き方の違いにより、私的年金に関する税制の適用関係が異なり、非課税
拠出枠の限度額管理も制度ごとに行われている、これに対して、諸外国では拠出・運
用段階では一定の限度額まで非課税としつつ、給付段階においては、大きな控除を有
する我が国と異なり、基本的には課税となっている、こういったファクトが指摘され
ているところでございます。
33ページ目、この資料は横軸に正規雇用労働者から始まり、自営業主、専業主婦と
いった方などの働き方の類型を並べており、上から下に、投資・貯蓄促進から公的年
金までの老後に向けた資産形成のためのツールを一覧表にしてまとめてございます。
特に、黒の太枠で囲んでいるところが私的年金の世界でございます。
34ページ目でございます。こちらの資料は、私的年金に関する税制措置の原則的な
取扱いをまとめております。イギリス・カナダのところを御覧いただくと、拠出段階
で共通の非課税枠を設定し、給付段階で課税を行うことになっておりますけれども、
左側の日本の場合は、拠出段階では、例えばDB、確定給付年金の場合には拠出上限額
はないなど、企業年金制度次第で差が生じる一方で、給付段階、下の方ですけれども、
公的年金等控除が適用されて、高所得者ほどメリットを受けやすい上に、相当程度の
控除額が適用になっているため、一部課税にとどまっているというのが現状でござい
ます。
35ページ目は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額についての整理です。
右側の欄で、例えばDBのところについては拠出限度額なしというように、もともと年
金制度の中で差が生じているわけですけれども、iDeCoの赤いところの拠出限度額に
つきましては、少しずつ制度間の差異をそろえようということで努力を重ねていると
ころでございます。
36ページ目は、主要国における公的年金税制の概要をまとめてございます。一番上
にありますように、日本はEET型ということで、給付段階での課税という考え方を
採っておりますけれども、次の37ページ目で、公的年金等控除が適用される結果、T
の部分が一部の課税にとどまるというのが実態でございます。
38ページ目でございます。もともと政府税調の取りまとめでは、給与・退職一時
金・年金給付の間の税負担のバランスといった論点が提示されてございます。その点
に関連して、年金受給者と給与所得者の課税最低限を比較してございます。年金受給
者の課税最低限は、給与所得者の課税最低限より高くなっていますが、その理由は、
公的年金等控除の額が高いことが要因になってございます。
39ページ目では、私的年金制度におきまして、確定給付企業年金では7割程度、確
定拠出年金では9割程度が一時金での受取りという方式を選択しているということで、
年金と一時金を比べた場合には、一時金が選択されるケースが多いという状況を示し
ているところでございます。
この点につきまして、付随する論点になりますけれども、参考資料として59ページ
目に関連の資料をお付けしております。給与所得と年金所得を同時に得ている方につ
きまして、合計で同じ所得を得ていても、給与所得と年金所得の内訳次第で税負担額
に差が出ている現状があるということも資料としてお示ししております。
40ページ目からは、所得再分配機能に係るこれまでの対応についての整理です。
41ページ目は、所得控除と税額控除の性格の差を整理しております。これまで、納
税者の担税力の減少に配慮するという考え方から、所得控除による対応が基本としつ
つも、高所得者ほど税負担軽減額が大きくなるという特徴がございます。一方で、税
額控除につきましては、財政的支援としての性格が強いといった整理が行われており
ます。
42ページ目、所得控除方式に代わります負担調整の方式といたしましては、ここに
挙げられているとおり、ゼロ税率、税額控除、逓減・消失型の所得控除があるという
ことでございます。
43ページ目、日本の場合は、平成29年度税制改正で、配偶者控除につきまして逓
減・消失の仕組みを導入したということでございます。
44ページ目、平成30年度改正で、基礎控除につきまして逓減・消失の仕組みを導入
してございます。
45ページ目は、所得制限のある所得控除を一覧にしております。例えば、下の方で
すけれども、寡婦控除、ひとり親控除は、右下を御覧いただくと、所得金額500万円
以下という形で所得制限を設けております。
46ページ目は、給与所得控除の適正化ということで、控除額の水準自体の見直しの
話でございます。給与所得控除につきましては、主要国並みに適正化するとの考え方
で引下げが累次行われてきておりますけれども、現状は、下の真ん中の方を御覧いた
だきますと、国際比較ではまだまだ高水準という状況にございます。
47ページ目、公的年金等控除につきましても、平成30年度改正で一部適正化を図っ
てございます。年金収入が高額な方、あるいは年金以外の収入が高額な方に上限を設
定いたしましたけれども、やはり国際比較ではまだまだ高い水準でございます。
48ページ目から、個人事業主の記帳水準の向上というテーマでございます。
49ページ目にございますように、個人事業主の記帳水準をめぐりましては、会計ソ
フトの普及などの技術進歩も背景に、複式簿記による記帳をさらに普及・一般化させ
る方向で施策を検討していく必要があると考えてございます。
50ページ目は、現行の記帳制度を整理してございます。一番左側にございます青色
申告の正規の簿記の世界をいかに広めていくかという観点が重要かと考えてございま
す。
51・52ページ目で実態を整理しております。51ページ目は、事業収入1,000万円以
下の小規模事業者の方に白色申告が多い、52ページ目では、60代以上の個人事業主の
方に白色申告が多くなっているという現状でございます。実態をよく踏まえる必要が
ございますけれども、少しでも正規の簿記による申告が行われるように環境整備に努
めてまいりたいと考えてございます。
資料総19-1に関しては以上でございます。
引き続き、資料総19-2についても御説明いたします。こちらは、前回10月4日の
所得税のセッションの中で、委員の先生から御指摘・御意見をいただいた点について、
幾つか資料を調えさせていただいたので、その御報告です。
まず、2ページ目の資料になりますけれども、林特別委員から、申告納税者の所得
税負担率や資本所得に関する前回お示ししたデータについて、例えば過去に遡った分
析や今後も継続的な分析を求める御指摘をいただいたところです。
その中で、現時点で対応可能なデータといたしまして、2ページ目にございますよ
うに、前回お示しした令和2年分の所得税負担率のデータに加えまして、令和元年分
の負担率のデータをお配りしております。こちらも3ページ目にございます令和2年
分と構図は変わってございません。1億円超の所得の中心は非上場株式の譲渡所得だ
という傾向でございます。
4ページ目ですけれども、佐藤委員から、譲渡所得に関しては、長期間にわたる値
上がり益が一時に実現するので、平準化という要素を考える必要があるのではないか
という御指摘がございました。
こちらの点につきまして、簡便な方法ではあるのですけれども、横軸に譲渡所得を
採り、その金額の譲渡所得が単年、5年、10年、20年、30年という形で一律に生じる
とした場合に、現行の累進課税の税率を適用しますと、それぞれどの程度の税負担率
になるかということを計算してカーブを描かせていただいております。譲渡所得の金
額が10億円を超えてまいりますと、平準化した場合においても30パーセントを超える
ような負担率になっているという絵姿になってございます。
5ページ目でございます。こちらは、前回、6・7ページ目にございますような資
料をお示しして、アメリカ・イギリスの分離課税について、段階的課税の仕組みを採
っていると御説明申し上げた際に、ちょっとイメージが分かりにくいのではないかと
いった御指摘をいただきました。
それで、一つの試みといたしまして、株式譲渡所得の額を横軸に採って、各国で適
用される負担率をカーブの形で整理させていただいております。日本は譲渡所得の金
額に関係なく一律なので赤い横線になりますけれども、例えばアメリカの場合には、
譲渡所得の金額が大きくなりますと33.5パーセントの税率に達することが見てとれる
といったところでございます。
私からの説明は以上です。
○中里会長
ありがとうございました。
続いて、総務省の植田課長、よろしくお願いいたします。
○植田自治税務局市町村税課長
総務省市町村税課長の植田でございます。
私からは、資料総19-3によりまして、個人住民税についての追加的な説明をさせ
ていただきます。所得控除制度の中でも、所得税とは異なる点を中心に、また、個人
住民税独自の仕組みでございます非課税限度額等について資料を用意させていただき
ました。
まず3ページ目、こちらは前回10月4日のときにも出させていただきましたけれど
も、給与所得者の個人住民税額計算のフローチャートでございます。左側の合計所得
金額を算出するための給与所得控除については、所得税と同じ計算をする。そこから
が個人住民税の独自の計算ということで、右上の所得控除の額が所得税よりも低く設
定されていること、課税ベースが若干広がっているということと、あとは税額控除に
ついても収入や控除額に違いがあって、国が政策的に行う控除についてはできる限り
そのまま個人住民税に適用しないよう、控除別に判断されてきているということでご
ざいます。
4ページ目も前回に続いての資料ですけれども、今回、主に御議論いただく所得控
除につきましては、個人住民税についても、所得税より若干低く設定されております
けれども、それでも約70兆円という規模感になってございます。
5ページ目は、平成12年の答申の抜粋でございますけれども、上に「個人住民税の
意義」がございますように、「地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分
任する」という負担分任の性格ということで、課税最低限は所得税よりも低く設定さ
れているとされております。当時は緩やかな累進構造でしたけれども、税源移譲後、
10パーセントの比例税率になっているということでございます。
また、一番下のところですけれども、「個人住民税の課題」の②のところで、「所
得割の所得控除及び課税最低限のあり方については、個人住民税の負担分任の性格か
ら所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かち合うべきものであ
るため、所得税と一致させる必要はない」と記述されております。
6・7ページ目は所得控除の概要ですけれども、6ページ目は人的控除、7ページ
目がその他ということでございます。
6ページ目の人的控除につきましては、基礎控除・配偶者控除・扶養控除など、所
得税と同様の体系になっておりますけれども、右の方の控除額の金額にありますよう
に、その金額は所得税よりも低く設定されているということでございます。
7ページ目でございます。その他の所得控除ということで、上の4つには※印をつ
けてございますけれども、それらについては所得税と全く同様の計算方式です。下の
生命保険料、地震保険料の控除につきましては、赤線を引いておりますけれども、所
得税よりも若干額が小さくなっています。例えば、一番上の2万8千円のところは、
所得税では4万円といった形になっております。
8ページ目です。こちらも所得税の方でも御説明がございましたけれども、平成29
年度改正で行われた配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてのグラフでござい
ます。ほぼ同じ形になっておりますけれども、金額が若干違っておりまして、配偶者
の給与収入が155万円のところから控除額が階段で減額されていく形になってござい
ます。
また、納税者本人の所得制限につきましても、合計所得金額は900万円から1,000万
円にかけて逓減するということは同じですけれども、対応する給与収入が若干少なく
なっているということでございます。
続きまして、9ページ目でございます。8ページ目の控除額を階段で逓減させてい
く仕組みをより詳しく説明したものです。配偶者に係る所得制限、納税者本人に係る
所得制限は、片方または両方適用されるということで、下の表のように両方適用され
る場合にそれぞれ左上から右下にかけて逓減していくという形になってございます。
10ページ目です。こちらも御説明がございましたけれども、基礎控除についても平
成30年度改正で見直されて、生活に十分余裕のある高所得者には措置する必要はない
という考え方に基づいて、控除を逓減・消失させるということでございます。
続きまして、11ページ目は令和元年の答申の抜粋でございます。下から2つ目の段
落のところに、働き方に関する個人の選択に中立的な税制の実現に向けて、諸控除の
更なる見直しが重要だとされておりますけれども、最後の段落に、前回も御紹介いた
しましたけれども、こうした見直しの検討を進める際にも、個人住民税の負担分任の
性格、また、応益課税としての性格等を踏まえる必要があるとされております。
12ページ目は、所得控除と税額控除の効果の比較についてでございます。所得税と
異なるところでございますけれども、所得税は累進税率でございますので、同じ額の
所得控除を行った場合に、高所得者ほど負担軽減が大きくなりますが、個人住民税の
場合は比例税率ですので、所得の大きさにかかわらず所得控除が税額に与える影響は
一定でございます。また、負担調整効果の観点から見れば、所得控除と税額控除につ
いては、いずれも同じ効果になります。
13ページ目以降は、非課税限度額について、また、こうした所得とか税の情報と社
会保障制度の関係についての資料を付けさせていただいております。
14ページ目は、非課税限度額の概要でございます。1つ目の○にございますように、
地域社会の会費的な性格、つまり、できるだけ幅広く御負担いただくという性格がご
ざいますが、低所得者層の負担を考慮し、生活保護基準額程度の所得の方をできるだ
け非課税としようとする制度でございます。均等割は昭和51年度、所得割は昭和56年
度の創設ということになっております。
下に計算式がございますけれども、非課税限度額の基準は、均等割については前年
の生活扶助の基準額、所得割については前年度の生活保護基準額を勘案して設定され
ているということで、世帯の人員数に応じて増額されるという計算式になってござい
ます。
15ページ目では、具体的なイメージとして、単身の給与所得者のケースについて図
示しております。左の四角囲いのところに拡大図が付いておりますけれども、生活扶
助基準が97万円であるのに対して、個人住民税の均等割については非課税限度額が
100万円に設定されています。さらに、所得割の課税最低限が115万円ということで、
所得税については121万円。これらの額の設定について、典型的なパターンが御理解
いただけるかと思います。
16ページ目でございますけれども、この非課税限度額を含めまして、個人住民税等
の課税等によって把握しております合計所得金額等の金額、また、個人住民税につい
て所得割なり均等割が非課税であることが、広い意味での社会保障に関する多くの制
度に活用されているということを示しております。令和2年の段階で関係省庁に照会
した結果を集約しております。
近年、こうした恒久的な制度のみならず、コロナ禍における様々な給付金等におい
て、個人住民税の非課税といった条件が用いられることが増えているという状況でご
ざいます。
最後、17ページ目でございます。今申し上げたようなことが平成27年の税調の論点
整理にも書かれてございまして、下線部分にございますように、様々な社会保障や福
祉の制度の適用基準等に、こうした個人住民税制度における課税・非課税の別や、個
11
人住民税制度における非課税限度額の基準が広く用いられていることと、非課税限度
額の基準が生活保護基準額を勘案して設定されていることなど、社会保障制度と個人
住民税制度が実質的にリンクしていることにも留意が必要ということで、非課税限度
額や税額に影響のあるような制度改正を行う際に、社会保障制度への影響についても
考慮しながら検討していく必要があるものと考えております。
説明は以上とさせていただきます。
○中里会長
ありがとうございます。
それでは、ここからは委員の皆様から御意見をいただければと思います。御意見が
ございます方は、会場で御出席の方も含め、画面上の「挙手」ボタンを押してくださ
い。発言順につきましては私から指名させていただきますので、指名された方は、会
場に御出席の方は卓上マイクをオンにしていただき、オンラインで御出席の方は「ミ
ュート」ボタンを解除して御発言ください。挙手いただいた順に指名をさせていただ
きますが、おのおのの委員の出席可能な時間の関係で前後する場合がございますので、
あらかじめ御了承ください。
また、本日欠席の岡﨑特別委員から意見書が提出されております。政府税調のホー
ムページにも後ほど掲載予定ですので、適時御覧いただければと思います。
なお、事務局資料に言及する場合には、当該資料のページをおっしゃっていただけ
れば、スクリーン上にも表示いたします。
佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員
まず、所得控除の再編成という観点から、御指摘のとおり、給与所得控除・公的年
金等控除などの所得計算上の控除から人的控除への移行というのは重要だと思います
が、併せて、給与所得控除と公的年金等控除の統合という観点があっていいかなと思
います。ある意味、働きながら公的年金をもらっている人は控除を二重取りしてしま
っているので、こういう状況を解消したほうがいいかなと思います。
それから、財務省資料の41・42ページ目に関わりますが、これは長年の課題であり
ますが、そろそろ所得控除の税額控除化を真摯に考えたほうがいいのではないかとい
うことです。それはもちろん所得再分配機能の強化というのもあります。
既に、財務省的にはといいますか、税調的には、消失型控除で対応しているという
向きもあるかもしれませんけれども、そもそも消失型控除というのもおかしな仕組み
で、本来、所得控除の趣旨は、生活最低限を保障するためだったのですけれども、所
得の高い人には生活最低限の費用は保障しなくていいのかという議論になってしまい
ますし、もっとプラクティカルに言うと税制を複雑にするという点もありますので、
それはむしろ税額控除化した方がすっきりすると思います。
また、個人的な属性、例えば扶養家族がいる・いないとか、こういったことは税額
控除に反映させればいいということになります。
もう一つ、私が個人的に気になっているのは、個人所得課税上の所得という定義と、
法人所得課税上の所得の定義が実は違うのですね。法人所得課税は利益ですが、個人
所得課税は、今申し上げたとおり、所得控除があるものですから利益ではないのです。
なので、この辺りの平仄を合わせた方がいいのではないかと思います。つまり、客観
的な基準で所得というのを定義するべきではないかという考え方です。
もう一つ、これも長年の課題の一つで、財務省資料の9・10ページ目に関わる議論
ですが、所得区分の見直しが本来考えなければいけないことかなと思います。既に税
調的には、例えば副業とか雇用的人員への対応というのは、記帳の促進という形でや
っているということになっていますが、納税環境の整備だけではなく、税制上の対応
が求められるかなと思います。具体的には、事業所得にも給与所得と同じような概算
控除、今で言うところの給与所得控除に相当するものを採り入れていく必要があるか
なと思います。
それから、退職所得について、前回も生涯所得ベースで課税するという考え方があ
っていいのではないかということを指摘したのですけれども、退職金も一時的所得で
すよね。だから、一時的な所得に累進課税を課すと課税額が急増するので、それを平
準化するという観点から課税ベースを2分の1に圧縮するという措置を採っています
が、そういうことをやると、39ページ目にあったように、企業年金についても一時金
で受け取る誘因につながってしまっているというのもあります。なので、本当はキャ
ピタルゲインも含めてですけれども、一時的な所得については、退職金であれ、企業
年金の一時金であれ、こういったものについても生涯ベースでの課税、具体的に言う
と、公年所得に平準化させていくという手法が検討されていいのかなと思いました。
次は、総務省の報告に関わる話として二点です。
個人所得課税について、今日はお話がありませんでしたけれども、そろそろ現年所
得課税化を本気で考えた方がいいかなと思います。最近、外国人労働者の方が、例え
ば今年日本で暮らしているのだけれども、来年帰国してしまったとき、課税に1年タ
イムラグがあるものですから、来年、住民税を課そうと思ってももういらっしゃらな
いといった問題もありますし、そもそも担税力の発生と徴税のタイミングを合わせた
方がいいと思うのです。今回のコロナのようなときにも、去年までは順調に仕事をし
ていた人が、今年仕事がなくなっても原理的には個人住民税の納税義務が発生してし
まうのです。なので、担税力の発生と徴税のタイミングを合わせるという観点からも、
現年所得課税化を進めるということ。
これは、税務行政的に言うと、賦課課税から申告納税の転換に当たると思うのです
が、実はこれ自体が自治体の徴税業務の負担軽減にもなると思いますので、そういう
観点からも検討されてはいかがでしょうかということです。
それから、これは一般論に近いのですけれども、課税と給付の連動というのをもっ
と意識した方がいいかなと思います。既に配偶者控除の見直しのとき、今日の資料で
いえば、財務省資料の17ページ目の選択肢A-1ですけれども、配偶者控除をやめて
給付に切り替えるべきだという議論があったとおり、税と給付を一体に考えなければ
いけない時期になってきていると思います。これは何度も言っているのですけれども、
リアルタイムで所得情報を活用して、それでプッシュ型を含む給付の実現をやってい
くことが必要かなと思います。
それとの関係なのですが、今日、総務省から最後の方でお話のあった非課税限度額
についてですが、この仕組みはちょっと変だなと思うのですね。もちろん、生活保護
とのバランスを取るというのは分かるのですが、日本は、課税というのは本来個人単
位でやっているのに、課税所得限度額の計算は世帯の人数を考慮しますので、事実上、
世帯単位になっているような設定の仕方なのですね。もちろん、生活保護とのバラン
スをどうするのだということがあるかもしれません。例えば今申し上げた、給付付き
勤労所得税額控除というものに対応していくことが求められるかと思います。
あと、今回も非課税世帯に5万円を給付してブーイングが起きていましたけれども、
非課税かどうかで給付を受け取れたり、受け取れなかったりするというのは実態に合
わないと思いますので、所得に応じた給付を進めていく視点が税制の観点からも重要
かと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
清家委員、お願いいたします。
○清家委員
関課長、植田課長、とても丁寧な御説明をありがとうございました。大変よく理解
できる説明だったと思います。それで、お二人にそれぞれ御質問というか、コメント
をさせて頂ければと存じます。
関課長の御説明になった個人所得課税について、これまで何度も申し上げたことで
すけれども、改めて申し上げたいのは、今同時に進んでいる全世代型社会保障の構築
と整合的な形になるようにしていただければと思っています。
その一つのポイントは、やはり働き方に中立的な制度にすること。これも社会保障
制度改革の中心命題ですので、その意味で、配偶者控除の問題、公的年金等控除の問
題であります。配偶者控除の問題はフルタイムで働くか、パートタイムで働くかとい
った選択に中立的ではないですし、公的年金等控除は高齢になってから就業を続ける
のか、年金を受け取るのかということによって税制上の扱いが違ってくるという意味
で中立的ではありませんので、繰り返しになりますけれども、ここは抜本的な見直し
が必要だと思います。
もう一つは、全世代型ということの意味は、年齢に関係なく収入に応じて負担をし、
必要に応じて給付を受けるということですので、その面では、38ページ目にも資料が
出ていますけれども、公的年金等控除がある場合、年金給付の場合と勤労収入の場合
で、例えば課税所得の下限が違ってくるというのは中立的ではありません。
特に、これは年金と給与所得の違いですけれども、実際に年金を受け取るのは高齢
者ですから、実態から言えば、年齢によって税制上の扱いが中立的ではないというこ
とになりますので、公的年金等控除についても抜本的に見直す必要があると思います。
それから、植田課長が御説明になった点について、これはコメントですけれども、
先ほど佐藤委員が言われたように、この御説明資料の最後のところにもありますけれ
ども、いわゆる住民税非課税ということが、様々な給付、例えば私も少し関係してい
る事例でいいますと、この2年半ぐらいの間、ものすごい勢いで行われた特例貸付の
制度、短期の貸付あるいは総合貸付という、パンデミック下で生活の厳しくなった人
たちに対する貸付の償還免除の基準などにも使われようとしています。そういう点か
ら申しますと、植田課長が言われたように、住民税というのが様々な給付とか償還免
除等の基準になっているということを考慮しつつ住民税非課税という問題を考えてい
くということはまことに大切だと思いますし、同時に、そもそも住民税非課税という
のは税の仕組みとしてあるわけですから、住民税非課税ということを基準に様々な給
付金とか償還免除の基準にすることが良いのかどうかということ。これはよく言われ
るわけですけれども、これも実は年齢によって中立的ではないわけです。住民税非課
税の計算をする場合にも、公的年金等控除の影響があるということがしばしば指摘さ
れていますので、そういう面ではむしろ社会保障制度あるいは給付の制度の方も、住
民税非課税というのを基準にするのが良いのかどうかというのを考える必要もあるの
ではないかと思いました。これは税制に対する要望というよりは、社会保障制度に対
する要望になるかもしれません。
○中里会長
ありがとうございます。
土居委員、お願いいたします。
○土居委員
私からは四点の意見と一点質問があります。
まず、給与所得控除についてであります。公的年金等控除との関係でいいますと、
資料19-1の47ページ目にありますように、公的年金等控除は2020年の所得から上限
が設けられるようにはなりましたけれども、実際にその上限に直面しておられる方は
たったの0.5パーセントしかおられないということに対して、給与所得控除は今850万
円よりも多い給与収入ですと上限になる、そういう標準的な上限ですけれども、これ
でおおよそ7~8パーセントの方がこの上限に直面しているということのバランスを
考えると、やはり公的年金等控除の上限が高過ぎると言わざるを得ないと思います。
少なくとも、給与所得控除の上限適用者並みの7~8パーセントの上位の年金収入の
方々に対して、この上限控除がこれ以上増えない形になるような仕組みに変えていく
必要があると思います。
また、59ページ目では、両控除が併用できることによる弊害が如実にこのグラフに
表れていて、両控除をうまく使えば、同じ課税前収入にもかかわらず負担が違うとい
う、水平的公平にも差し障るような控除が併用されているということですから、両控
除の統合を含めて今後検討する必要があるのではないかと思います。
それから、43ページ目に配偶者控除の例がありますけれども、逓減・消失化という
のは非常に複雑な仕組みをもたらしてしまう。特に、下の表でありますけれども、結
局、自分が納税者として配偶者控除ないし配偶者特別控除が一体幾ら受けられるのか
ということは、このマトリックスの中から探し出さなければいけない。しかも、それ
は単に控除であって、税負担軽減額が幾らになるかというのは、さらに税額等の計算
を経てからでないと税負担軽減効果が分からないという非常に複雑な仕組みになって
いるということですから、むしろ税額控除などを分かりやすい仕組みにして、働き方
に中立なものにしていくことが必要だと思います。
それから、資料19-3の14ページ目で、先ほど佐藤委員、清家委員からも御指摘が
ありましたけれども、非課税限度額は私も問題があると思います。実際、個人住民税
を納税されている方は6,000万人ほどしかおられないわけです。全人口の半分ぐらい
しかいないにもかかわらず地域社会の会費と言えるのだろうかということはあるわけ
です。均等割、所得割、それぞれあるわけですから、均等割だけはお支払いいただく。
それは数千円ですから、そんなに重い負担と言えるわけではない。所得割は、もちろ
ん所得が高くなければ、負担はそんなに重くならないということでありますから、地
域社会の会費と言うならば、せめて少しは納税していただく工夫が必要なのではない
かと思います。
最後の意見は、退職所得課税と私的年金及び非課税貯蓄のiDeCo、NISAに関連する
ところであります。資料19-1の39ページ目に、特に確定給付企業年金・確定拠出年
金で一時金払いが多いということが示されております。これは多分に税制が影響して
いると私は思います。つまり、一時金払いにし方が年金払いにするよりも税負担が軽
くなる。それは退職所得課税の話とも密接に関係しているということですから、退職
所得課税の負担が軽くなり過ぎているのではないかという批判があることは承知して
いますけれども、目のかたきにするよりかは、ひとまず一時金払い、年金払いのどち
らの受け取り方であっても税負担が同じになるような仕組みに移行していく。もちろ
ん一時金払いのときに住宅ローンの返済に充当するということがあれば、その分だけ
考慮した上で、どちらの受け取り方でも同じ税負担になるような仕組みに変えていく
ことに取り組むことがあってもいいのではないか。
それから、NISAとiDeCoは、老後の資産形成という意味では非課税枠を両者併せて
考えるべきではないか。その金額が低所得層でも十分投資ができるような枠にすると
いうことであって、高所得層だけがその枠が使えるということにならないような範囲
で、両者を併せ持って非課税枠を考える必要があるのではないかと思います。
今申し上げた点に関して、事務局に質問がございます。政府税制調査会で、まさに
iDeCo、NISAが俎上に載っているということではあるのですが、新たに「新しい資本
主義実現会議 資産所得倍増分科会」でこの議論をするというお話になっているやに
聞いております。
政府税制調査会は様々な政策決定に資するような材料を提供すべく議論するという
ことではないかと思っておりますが、あちらの議論の方が先に結論が出るということ
になりますと、我々は一体何の議論をしているのだろうかという疑問にもさいなまれ
るわけでありまして、両会議の役割分担というか、立てつけというか、その辺りはど
ういうふうにお考えなのかをお伺いしたいと思います。
以上です。
○中里会長
それでは、調査課長、お願いいたします。
○河本主税局調査課長
政府税制調査会は、おっしゃるとおり中長期的な視点から税制の現状と今後につい
て検討いただく場でございますけれども、政府税制調査会だけが税の議論をする場で
はもちろんございませんで、政府の様々な他の会議とか、あるいは国会の中で様々な
議論がなされていく。そのどこの段階で何の税の改正が決まるかということは、それ
ぞれのタイミングによって決まってくるものだと思います。
いずれにしましても、様々な幅広い観点から政府税制調査会は中長期的な視点から
あるべき税制を議論するということでございまして、特に何かの議論をしてはいけな
いとか、何かの議論はここでやるということが決まっているわけではございません。
○中里会長
それでは、田近特別委員、お願いします。
○田近特別委員
前回から、調査課長が今まさにおっしゃったように、中長期的な視点で所得税の問
題を考えるということで議論をしているわけですけれども、そういう線に沿って所得
税改革の流れから始めたいのですけれども、まさに中長期な点です。バブル崩壊後、
いろいろ議論はあったのですけれども、私は、定率減税の議論はその発端として重要
だったと思います。
アジア危機が1998年にあって、時は小渕内閣ですけれども、99年に恒久的減税とし
て定率減税をした。簡素にやらなければいけないということで、払った税金の一定割
合を負担軽減してあげるという仕組みが定率減税ですけれども、それが99年で、その
後、小泉内閣になって景気が良くなって、2007年からそれがなくなった。つまり、恒
久的減税は長い期間、ほぼ10年たって、それを廃止できた。それは一つのアチーブメ
ントだったと思います。
第2のアチーブメントは、いろいろあるかもしれませんけれども、私が思う範囲で、
今日は関課長から御説明のあった所得計算上の控除、つまり、給与所得に対して、公
的年金に対して、退職金に対して、そういう所得計算上の控除から人的控除に控除を
改めようと。これも一つの大変な成果だったと思います。端的に言えば、給与所得控
除・公的年金等控除から、基礎年金控除に振り替えた。これが第2のアチーブメント
だった。
では、今、何が問題か。前回の1億円の壁というのも問題の一つでしょうけれども、
今日は財務省・総務省から非常にいい資料を出していただいて、中長期的な観点から
何がイシューなのかということで、今のことを踏まえて議論したいのです。
私は、圧倒的に重要な問題は、社会保障と税制の関係をどうするか、具体的に言う
と社会保険料をどうするか。実態的に言えば、普通の人の8割以上あるいは9割近く
の人は社会保険料の方が大きいわけですよね。それをどう考えるかということです。
具体的に申し上げると、配偶者控除の問題があって、19ページ目を見ていただきた
いのですけれども、これももう長年にわたって議論して、いわゆる103万円の壁で、
この紙は歴史的な紙みたいな感じですけれども、要するに、配偶者特別控除で消失控
除をするので103万円の壁はありませんというのはそのとおりだと思います。でも、
なぜこれがまだ問題になっているかというと、実は106万円の辺りから社会保険料が
始まるわけです。そうすると、働く人が社会保険料も税負担と同じようにみなせば、
相変わらずデントというか、へっこみは起きるわけです。一つの例を申し上げました
けれども、社会保険料と同時に考えないと問題は解けない。
それを言い出したら切りがないと思うのですけれども、もう一つです。次に、公的
年金等控除も改革はしてきましたけれども、これも年金所得をどう考えるかというこ
とで、社会保険の問題と切り離せない。割り切って言えば、EETの仕組みですから、
それはもうしっかり取る。特に必要な配慮があるとすれば、それは高齢者に対する配
慮なので、公的年金の配慮ではなくて老齢者への配慮だろう。
退職所得も、34ページ目を見ていただきたいのですけれども、これは賃金の後払い
なので、それをどう平準化するかで、2分の1が良い・悪いということになるわけで
すけれども、考えてみたら、34ページ目の大きな枠があるのですけれども、DC年金じ
ゃないかと。DC年金で、それをそれぞれの人のアカウントで管理すればいいのではな
いか。
何が言いたかったかというと、今まで所得税に関して幾つか大きな改革があった。
しかし、社会保険料の問題を今考える、社会保険を考えないと所得税の問題が解けな
い。
次は、働き方の問題で、多様な働き方の問題もさんざん議論しました。持続化給付
金に至っては、働いている人というのは事業所得だと思ったら給与所得であったと。
その働き方の問題です。
それから、負担調整では、既に出ているように、所得控除というのは消失控除で対
応していますけれども、それだけではなくて、タックスクレジットをどう考えるか。
全部を包摂するものとしてデジタル化にどう備えるかということで、申し上げたかっ
たのは、今までの歩みはそれなりに踏まえて、今の問題をもっと概念化するというか、
全体の現状と問題を抽出して、それぞれにどう対応するか。
その中で私が一番申し上げたかったのは、社会保険料と所得税を同時に考えないと
今の問題は解けない。それを一番申し上げたいと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
神津特別委員、お願いいたします。
○神津特別委員
既に、佐藤委員をはじめとして何人かの委員がおっしゃったことと大分かぶるので、
たくさん言いたいことはございますが、1つだけに整理させていただきます。
所得控除でございますけれども、基礎控除が逓減消失してしまうことで、高額所得
者は課税最低限も保障されないという制度は明らかにおかしな制度だと思います。
そこで、給与所得控除を縮減、公的年金等控除も減らして、基礎控除は平等に増額
するというスタイルで行っていただきたいと思います。それが働き方の多様化とかい
ろいろなことにも耐えられる、正しい所得税の対応だと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
熊谷特別委員、お願いします。
○熊谷特別委員
本日御説明いただいた論点に関しましては、全て改革の基本的な方向性に賛成いた
します。
清家委員からも御指摘がございましたけれども、働き方やライフコースが多様化す
る中で、働き方の違いによって不利に扱われることのないよう、個人の選択に中立的
な税制という観点から、とりわけ配偶者控除や退職金税制、そして、公的年金等控除
等の見直しは、いずれも極めて重要な改革のメニューであると考えます。
そのことを申し上げた上で、具体的に三点だけコメントをさせていただきます。
まず一点目として、公的年金等控除でございます。公的年金と給与所得の両方を得
る者について、公的年金等控除と給与所得控除がダブルで控除されるため、課税最低
限が低くなり過ぎている面があります。課税最低限、住民税非課税ラインは、経済対
策の給付対象者や社会保障給付の自己負担割合などを決定する際にも利用されており
ますので、所得の種類ごとの控除からなるべく基礎控除に振り替えて、負担能力を適
切に反映した税制に近づけていくべきであると考えます。
二点目といたしましては、退職所得控除でございますけれども、労働移動の障害と
ならないように、働き方に中立的な税制とする観点から、勤続年数1年当たりの控除
額を同額にする、あるいは退職時に得た退職金をiDeCoなどに拠出してプールすれば、
その分は課税を繰り延べられるといった制度改正などが必要ではないかと考えます。
三点目として、先ほど土居委員から御指摘があった内容に賛同いたします。やはり
税というのは地域社会の会費のような性格がございますので、広く薄く負担するとい
うことが基本です。諸外国ではある程度納税しているような所得レベルの方々であっ
ても、我が国ではほとんど納税していないという、このカーブのゆがみが本質的な問
題の一つでございますので、もちろんこれは政治的には非常に困難なものではあると
は思いますが、こういった問題についても正面からしっかり議論することが必要では
ないかと考えます。
私からは以上でございます。ありがとうございました。
○中里会長
ありがとうございます。
芳野特別委員、お願いいたします。
○芳野特別委員
初めに、所得控除制度について、働き方などに中立な税制構築の観点から、検討の
方向性について五点申し述べたいと思います。
一点目は、人的控除についてです。高所得者ほど税負担の軽減額が大きくなる現行
の所得控除方式から、所得水準にかかわらず軽減額が一定の税額控除方式に改めてい
く必要があります。
二点目は、給与所得控除についてです。勤務費用の概算控除に加え、給与所得者と
自営業者などとの捕捉率の差などを総合的に加味して設けられている控除ですので、
検討を行う場合は慎重の上にも慎重を期すべきと考えています。
三点目は、配偶者控除についてです。扶養関係と一定収入のみを基準とする扶養控
除に整理・統合した上で、現行の配偶者特別控除に準じた措置を講じる必要があると
考えます。
四点目は、退職所得控除についてです。就業形態が多様化しており、勤続年数で差
を設ける意義も薄れていることを踏まえ、勤続年数にかかわらず一律とし、水準は60
万円程度を念頭に検討すべきと考えます。
五点目は、フリーランスについてです。税制の議論とは異なりますが、コロナ禍を
機にギグワーカーの法的保護に向けて、世界的に労働者性を認める方向で検討がなさ
れています。日本においても、税制を見直す前に労働者性の見直しを行うべきです。
次に、企業年金などに係る税制について申し述べたいと思います。企業年金は後払
い賃金としての性格と公的年金の補完機能を持っており、労使合意の積み重ねによっ
て実施されてきた経緯を重く受け止めるべきです。万が一にも、税制や法制度の見直
しによって企業年金の設計や給与水準の変更を余儀なくされることがあってはなりま
せん。また、企業年金と個人年金は制度の性格が異なり、掛金の拠出者も異なります。
両者を確定拠出年金制度として一元的に限度額管理をしている点は、企業年金の個人
年金による置き換えの懸念があり、労働組合として問題意識を持っています。
なお、この点について仮に検討を行うとしても、各制度の性格に十分留意した上で、
高所得者優遇とならないよう丁寧に検討していく必要があります。あわせて、公的年
金等控除については、年金以外の所得を含めた高所得層における応能負担の在り方の
検討も必要と考えます。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
足立特別委員、お願いします。
○足立特別委員
私の方からは、働き方、そして、ライフコースの多様化に即した中立な税制の在り
方についての意見としまして、個人所得課税について二点、個人住民税について一点
ございます。
まず一点目、個人所得課税におきましては、14ページ目にありますように、COVID19以降、フリーランスやギグワーカー等の働き方、そして、令和3年の高齢者雇用安
定法改正におきます70歳までを選択肢に含めました業務委託や社会貢献などの稼得方
法などから、多様な働き方を想定した所得計算が求められています。具体的には、給
与所得控除や公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることで、働き方をゆがめ
ない中立な税制の在り方は引き続き検討が必要かと思います。この点につきまして、
女性の就労の促進につながる形で配偶者控除の検討を併せてお願いいたします。
二点目につきましては、高齢期におきます課税の在り方です。58ページ目にありま
したように、確かに高齢期の経済的稼得力が減退すると、公的年金による負担調整と
税制の配慮は重要です。しかしながら、高齢者雇用の進展によって所得形態の多様化
を踏まえ、年齢ではなくて、稼得能力に応じた税負担の在り方の検討が求められてお
ります。具体的には、諸先生方におっしゃっていただきましたように、給与所得を得
ながらも年金受給者が増えている状況を鑑みた場合に、給与所得控除と公的年金等控
除それぞれの適用による課税ベースの脱漏が課題になる中で、令和4年には65歳未満
の在職老齢年金制度による見直しが行われています。したがいまして、高齢期におき
ます課税の在り方において、高齢者の働き方をゆがめない中立な税制も検討が重要か
と思います。
これら二点の多様な働き方におきます税制の中立性につきましては、個人住民税に
おいても同様になります。
最後に、16ページ目にありました個人住民税と社会保障制度の適用基準との関係に
ついての意見になります。社会保障制度の適用基準として、個人住民税の非課税限度
額や総所得金額が使用されています。ですので、本来、個人住民税とは地域社会の費
用を住民が広く負担を分任するという応益負担という性格を踏まえますと、社会保障
制度の適用基準としてリンクしていますけれども、ここは給付と税を区別して考えて
いくことが重要であると考えます。
私の方から、以上三点になります。
○中里会長
ありがとうございます。
赤井特別委員、お願いいたします。
○赤井特別委員
細かいところは他の委員の方がかなり言っていただいていますので、大きな考え方
としては、中立性、垂直的な公平性というところをキーワードに、徹底的に議論をし
て進めるべきところを優先順位をつけて進めていくべきかと思います。
中立性に関しては、フリーランスも含めて多様な働き方に対応できるような税制、
あとは女性の働き方に関しても中立性、制度を優先順位をつけながら確実に停滞する
ことなく進めていくことが大事かなと思います。
公平性に関しては、いろいろ議論されているように垂直的な公平性をもう少し考え
ていくべきではないか。要するに、累進化をもう少し進めるべきではないかというと
ころで、所得税・住民税、統一的な視点から控除の在り方を議論すべきと思います。
住民税の基礎控除の見直しということで、10ページ目にありますけれども、かなり
高所得者の人しか減少していないということもありますし、こういうところももう少
し累進性を強化するということがあってもいいでしょうし、ちょっと戻りますけれど
も、中立性のところでいえば、あまり出ていない、例えば退職金も、資料総19-1の
24ページ目で、いまだに長く働けば退職金の控除も増えるということで、これも中立
性かもしれませんけれども、あまり頻繁に会社を替えるような今の働き方だと一つの
企業でずっと働くわけではないですから、長く働いた方が控除額が増えるという制度
を含めて、中立性と公平性を順に徹底的に見直していくべきだと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
諸富特別委員、お願いします。
○諸富特別委員
今回の所得税の議論は、経済社会の変化の中でどういうふうにして21世紀型の所得
税制をつくっていくかという点で非常に重要な論点が幾つも出されたと思います。既
に幾つかの指摘がなされましたが、所得税制の基本的な考え方で多くの委員の皆様が
指摘されたのは、所得控除は高額所得者により大きな便益をもたらすやり方であり、
一定の所得を課税対象から外すということに歴史的な意義があったとしても、現段階
で見れば、税制の所得再分配の機能を損なうことになりますし、また、税収を損なう
ことになりますので、これを税額控除に切り替えていくという点で大きなコンセンサ
スが形成されているのではないかという印象を私も持ちました。
さらに、税控除というのは、基本的には課税最低限以上の方々に税額を減じるとい
う恩恵が行き渡るわけですけれども、さらにこれを手当に切り替えることによって課
税最低限以下の世帯にも恩恵が及びます。そういう意味では、今日の財務省資料の17
ページ目に3つの選択肢ということで議論されている中では、こういった改革をやっ
たときに、それぞれどの世帯にどれだけのプラスマイナスがあるのかということが明
示的に計算してみると恐らく出てくると思いますが、所得控除を廃止して手当を乗せ
るという形にするものが、恐らく一番所得再分配上は改善に資するような改革になっ
ていくのではないかなと思います。
そうしますと、税率の構造を変えなくても、控除の仕組みを切り替えることによっ
て、所得税制の所得再分配機能を向上させることができますし、また、控除の改革と
手当の創設ないしは増額をセットにすることによって、より効果的な所得再分配機能
の発揮がなされるのではないかと思います。
そういう観点で、年金の課税についても、今日の資料の34ページ目とか36ページ目
のところで、これはかつて海外調査の報告でも詳細になされた点でありますが、例え
ば34ページ目で気になるのは、日本の場合は拠出と運用の段階では課税せず、給付の
段階で課税するという形ですが、一部課税という形で図に描かれてありますし、また、
36ページ目の公的年金についても、日本のところはEETと書かれているのですが、給
付の段階では他国では課税となっているところが日本は一部課税にすぎない。ここは
先ほど御説明にあったとおりです。この辺りは、日本の所得税制として、拠出と運用
の段階で非課税とするなら、給付の段階での課税をしっかりやっていくような仕組み
に切り替えていくべきではないか。
そもそも私は知識がなくて、なぜ年金に関してこのような控除制度が認められてき
たのかというのは存じ上げていないので、この辺りを御教授いただければと思います。
恐らく年金がそれほど分厚くなかった頃に、なけなしの年金に対して年金所得を課税
に組み入れるのは忍びないということから、これを課税しないというところで始まっ
たのではないかと思うのですけれども、年金制度のその後の発達につれて、こういっ
たやり方が現代的なのかどうかということについて疑問に思いますし、ここを見直し
ていくべきではないかと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
武田委員、お願いします。
○武田委員
本日は、事務局に大変丁寧に重要な論点を御提示いただきまして、ありがとうござ
いました。
結論としまして、経済社会の構造をしっかりと踏まえた税制へ、そして、働き方や
個人の選択に中立な税制へと見直していくこと、これが最重要課題であると考えます。
その上で、時間の関係で二点に絞って意見を申し上げます。
一点目は、配偶者控除についてです。経済社会の構造変化として、もはや共働き世
帯が過半を上回っております。また、配偶者の働き方に中立的でない税制度を維持す
ることの弊害も増していると思います。
制度的には壁がなくなっているとの御説明がございましたが、本日御説明いただき
ましたとおり、現実には家族手当がある企業の45パーセントが103万円で収入制限を
行っておりますほか、心理面でも行動に影響している事実がございます。税制は社会
の慣習や、心理要因として人々の行動を変えていく、あるいは根づかせていくことの
表れと思います。
田近特別委員が御指摘されましたとおり、社会保障も併せて考えることは大切で、
また、全世代型社会保障と整合的であることも必要と思いますが、本税制調査会とし
ては、配偶者控除を廃止し、働き方に中立な税制を実現することが大切ではないかと
考えます。
二点目は、退職金税制に関してです。今後の日本経済を考えますと、企業が構造転
換のスピードを上げて付加価値向上を伴う生産性の上昇につなげていけるのか、生産
性が低い分野から生産性が高い分野に資本や人をスムースに移動できるのか、ここに
かかっていると考えます。
この実現に向けては、個人の意欲や挑戦が、少なくとも税制で妨げられない中立な
制度にする必要がございます。つまり、経済社会の構造変化を踏まえた労働移動に中
立という観点から、また、個人の多様な働き方、選択に中立という観点からも、退職
所得控除は勤続年数で差を設けずに、一律とする制度へ早急に改めるべきと考えます。
二点に絞って意見を申し上げましたが、それぞれ歴史的にはその意義や役割はあっ
たと思います。しかし、経済社会の変化とともに制度も見直していくことが重要と考
えます。同時に、日本の国際競争力、産業構造の転換の遅れをこれ以上放置してはな
らない。そうした危機感が税制調査会として必要ではないかと考えます。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
寺井委員、お願いします。
○寺井委員
非常に丁寧な御説明をありがとうございました。
私からは、既に他の委員の方々もコメントされていますが、退職所得税制について
二点意見を述べさせていただきたいと思います。
退職金・企業年金は賃金の後払いの性質を持つというお話がありました。後払い賃
金体系には、労働者の離職をできるだけ防いで、採用や訓練のコストを抑えたいとい
う企業の意図が反映されていると思っており、その企業の合理的な判断を否定するこ
とはありませんが、それだけでなくて、長期就労に有利な退職所得への税制が雇用の
流動性を抑制する効果を持っているとしたら、それは修正されるべきだと考えます。
労働者がより高い生産性を発揮できる産業・企業に移動しようとするときに、退職
金・企業年金の受取りに不利にならない制度設計が望ましいと考えます。
二点目ですが、現行の退職所得税制が、企業が後払い賃金体系を選択しやすくして、
労働者がそれを受け入れやすくしていないかを注意深く考える必要があろうかと思い
ます。資料総19-1の23ページ目で、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け
取ることによって税負担を回避した事例に言及がありました。非常に単純で極端な例
えで恐縮ですが、労働者の賃金支払の割引現在価値、つまり、生涯賃金が同じであっ
ても、若いときに賃金を抑制して、キャリアの後半で賃金を高くする賃金体系の方が
税制上有利になるのであれば、払わなくて済んだ税金分、労働者は得をしますし、ま
た、それを見越して企業はその分賃金を抑制することができるかもしれません。先ほ
ど資料で御説明いただいた例は、これに当てはまるのかなと思います。すごく目立っ
た例なので資料に載っていたと思うのですけれども、その他にもこのような例に該当
するものがないか。今、私が申し上げたのは理論的な可能性ですので、それにとどま
らず、きちんとしたエビデンスを踏まえて考えるべきということを申し添えたいと思
います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
辻󠄀委員、お願いします。
○辻󠄀委員
私は、今回の参加者の中では比較的少ない政治学も専攻している人間です。政治学
の立場からこれまでの議論を聞いていますと、今までいろいろな事情でこれだけ複雑
な制度になってきていて、税額控除や所得控除などがさまざまな経緯から複雑にから
みあって、今の制度でやっと合意が形成されてきているという側面があります。
そうした中で、税額控除だけでさっぱりシンプルにというのは理論的にはできるの
かもしれませんが、現実問題としては、ほんとうに合意形成が可能なのでしょうか。
現実的に考えると、税額控除と所得控除を両方考えながら、現実的に筋が通ってい
るものを求めていかざるをえないと思いました。
これを前提に具体的には三点あります。
一点目は、今回の税調の議論の中で、EBPMということで、なるべく政策の効果を検
証していこうと一生懸命やってきたことです。これからすると、今日話題になってい
るのは、所得税の控除の部分とか個人住民税の控除の部分が結果的に単に税収の多寡
に影響しているだけなのか、翻って住民行動に影響を与えて、政策的な副反応も出て
いるのかを検証すべきです。また、同じようなことを給付でやるよりは、政策費用は
税額控除でやった方が低いはずです。
こういうことを考えた場合に、特に所得税控除と個人住民税控除は微妙に額も違い
ます。これらを比較してみたときに、何か住民行動に対して異なる影響を与えている
か。こうした点を、少し検証してみる必要があるのではないかというのが一点目です。
二点目に、個人住民税が非課税かどうかという基準は、他のところでもたくさん援
用されています。今でも非課税なのか、ぎりぎり課税なのか、そこのところの公平性
が問われていますが、個人住民税の非課税基準にかわる明確な基準がないので、どう
してもこの基準がよく用いられています。
したがいまして、仮に個人住民税の非課税世帯を変更した場合に、サンプルでいい
のですけれども、この基準を援用している他の部分の影響も含めて、どうなるか慎重
に議論する必要があると思いました。
三点目に、他の給付と併せて個人で見るか、世帯で見るかという話が一部でありま
した。昔に比べて家族の絆は非常に緩くなっていて、そういう意味では個人で見た方
がいいということがあって、奨学金の認定に際しても世帯で見ていたのを個人の要素
を入れるように変わってきたところもあります。しかし、現実問題でいうと、まだ世
帯単位で行っているものが、たくさんあります。それを個人に分解すると給付増につ
ながる場合もあり、伝統的に世帯単位で行ってきたものについては、世帯単位の良さ
も十分残していくということを考えながら、税制改革していく必要があると思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
岡村委員、お願いします。
○岡村委員
三点申し上げます。
一点目は、本日、土居委員から非常に貴重なお言葉をいただきましたが、それは受
け取り方に中立的だということでございます。私もこの考え方には全面的に賛成でご
ざいまして、退職所得、年金、退職所得が基になるような金融資産性所得といったも
のについては、受け取り方に中立的な、言葉を換えて言えば、支出に対して中立的な
税制を一体的に組んでいくべきではないかと考えます。
もともと所得とは何かと言われると、それは純資産の増加と消費であると言われて
いますけれども、特に、あまり豊かでないような人たちについては、消費、支出の部
分を重視して税制をつくっていくことが大事だと思います。
しかし、これに対して高所得者層、例えば1億円の山の向こう側にいる人たちにつ
いては、貯蓄の部分、純資産増加の部分に対してある程度の負担をお願いする。それ
は、やはり累進性のあるもの、つまり、EETということで言えばTです。しっかりと
した累進課税を金融資産性所得であっても行うべきである。その点では、賦課税とか
いろいろな形が考えられると思うのですけれども、多少はそこのところを入れていた
だくということがいいのではないかと思います。
二点目は、それに伴う住民税の問題です。これも以前申し上げたかもしれませんけ
れども、現在、住民税は金融資産性所得については減免課税をやっていると思います。
ですから、さらにもう少し進んで、ここのところが絶対に比例税率でなければならな
いのか、応益課税だから比例税率だというところが論理必然的に結びつくのかどうか
というところも検討の余地があり、もし国税の方で極めて高い金融資産性所得につい
てはもう少し御負担をお願いすることが可能になるのであれば、住民税もそちらで行
かれるのがいいのではないかと思います。
三点目は、10月4日に出されている資料総17-1の22ページ目、納税者の分布(所
得税の限界税率ブラケット別)をじっくり見ていると、地方税のことは横に置かせて
いただくと、5パーセントの人たちが相当部分を占めているのですけれども、5パー
セントの所得税がいいのか、それとも、もう少し違う、私は支出ということを申し上
げましたが、例えば消費の方がむしろスムースなのかということは、国全体の政策と
してよく考えていく必要があるのではないか。
そして、今日は税額控除なのか所得控除なのかという話が出ていますけれども、ゼ
ロ税率という話もあったと思います。確かに、税額控除だと累進課税の下で同じ価値
を持つとか、累進性の下で所得控除を消失させるといったアイデアでやっているので
すけれども、基本的にはこれは税負担の累進性の問題であり、本来は累進税率上にお
いて対処すべき問題ではないかと思います。
そうだとすると、現在の様々な基礎的、人的控除と呼ばれているものは、ゼロ税率
といった形で処理をし、ゼロ税率の範囲をもうちょっと延ばす。そして、そこのとこ
ろは所得税ではないような形で処理をした方が、国全体の税制としてはより合理的で
効率的かもしれないと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
田中特別委員、お願いいたします。
○田中特別委員
幾つか商工会議所で検討していることもあるのですけれどもお話をしたいと思いま
す。
まず、103万円の壁がなくなったというお話をいただき、確かにグラフを見るとス
ムースになっているような気がするのですが、現場からは、やはり150万円の壁があ
る、全額最大限に控除を受け取れるというところについて非常に意識をしていると。
さらに、田近特別委員がおっしゃるとおり、社会保険料の壁が130万円にあります。
ですから、やはり社会保険料と税金を一緒に考えて、その壁をどうしていったらいい
のかということが一つのポイントではないかなと思います。そういった壁を意識して
労働時間の調整を行うことは引き続き続いていると言われており、なおかつ人材の確
保に苦慮していると言われています。
もう一つ、法人と個人事業との境目があまり議論されたことがないのですが、いつ
も小規模な法人と大企業との間で軽減税率によって不公平ではないかと言われるので
すけれども、実際には、個人事業主が法人になるか、個人事業主のままやるかについ
ては、税金だけでなくて社会保険料も効いていて、負担は法人になった方が多いので
すね。今、15パーセントの軽減税率を適用したとしても、負担は法人の方が多いです。
これは全体の議論をするときにすごく大事なポイントだと思います。
先ほど佐藤委員が自営業にも給与所得控除をすべきではないかと発言がありました。
僕は自営業の負担をなるべく軽くしてあげることについては反対ではないのですが、
実際に個人事業主と法人との間の境目がどうなっているのかということを検証して対
策を立てていただきたいと思います。
3つ目は、先ほども配偶者控除の話が出ました。辻󠄀委員の言うとおり、合意形成を
することは、実際の各個人にとってどういうプラスマイナスがあるかということにか
かってくるので難しいと思うのですけれども、商工会議所では、配偶者控除について、
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を所得に寄らない人的な控除に統一して、夫
婦であれば消化し切れない部分は片一方にシフトするようなことができると分かりや
すいのではないかと主張しています。
税額控除についても、そういう意味では若い人にとって厚くなる支援ができるよう
な税額控除の方がいいかもしれないというところが今の議論にはあります。
もう一つ、1億円の壁について、3ページ目の表にあるとおり、この内容について
もう少し知りたいと前回お話があったと思うのですが、私も同様で、非上場株式の譲
渡所得等が27.4パーセントで非常に大きなシェアを占めているのですけれども、これ
は金融資産ではないので、それなりの事情・背景があるような気がするので、要注意
かなと思っていて、この表についてももう少しレイヤーを分離して分析をすることが
必要ではないかと感じました。
○中里会長
ありがとうございます。
林特別委員、お願いします。
○林特別委員
二点コメントと、一点質問があります。
まず、参考資料の御準備ありがとうございました。御準備いただいた方々によろし
くお伝えください。
コメントですけれども、二点とも所得控除に係ると思います。間違っていたら御指
摘いただきたいのですが、配偶者控除は、そもそも扶養控除から分離・独立したもの
だと記憶しています。配偶者控除をなくすとなると、そもそも扶養控除をどう考える
かという問題に波及せざるを得ないかと思います。したがって、特定の控除をなくす
という御議論は、担税力をそろえるという所得控除の観点から、合理的かつ筋の通っ
た理論的な検討が必要かなと思います。
もう一つ、これも退職金に係る控除のお話になると思いますが、退職金は給与を後
払いするという考え方をすれば、考えようによっては積立の年金のようなイメージに
なるのかなと思います。高額所得者は特別配慮する必要はないのかもしれませんけれ
ども、年金給付が厚生年金も下がるかもしれないという状況の中で、退職金は老後資
金として捉える必要があるので、それに応じた控除の仕組みもあってもいいのかなと
思いました。
最後は住民税の非課税限度額についての質問です。生活保護とのバランスで決まっ
ているという御説明があったような気がしたのですけれども、生活保護基準は級地に
よってかなり違います。となると、バランスで決めるということになれば、地域によ
って住民税の非課税限度は変わらないといけなくなると思うのですけれども、そこら
辺はどうなっているのかなというのが興味を持ちました。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
それでは、植田市町村税課長、お願いします。
○植田自治税務局市町村税課長
14ページ目に非課税限度額の計算の資料がございますけれども、注4のところに、
基本額及び加算額に級地区分に応じて率を乗じた額を基準として条例で設定とされて
おりまして、先ほどおっしゃられました、生活保護を受けている方々がここの非課税
限度額に当たって課税されることが基本的にないような形に勘案して設定するという
形にしておりますので、この級地区分についても勘案したような制度になっていると
いうことでございます。
○中里会長
それでは、梶川特別委員、お願いいたします。
○梶川特別委員
今までの委員の方々の御意見とほとんど同じでございますけれども、一点だけ、働
き方改革の中のお話で、資料の10ページ目ですけれども、控除のお話が中心ではあっ
たのですが、そもそも所得区分の考え方の整理も議論をしていってもいいのかなとい
う気がいたしました。そこの裏返しで、給与所得控除であるとか、実額控除というか、
当然必要経費というお話が出てくるのですが、冒頭、佐藤委員がおっしゃったように、
所得という概念が、片方では収入であり、片方では利益という部分が、事業所得の場
合には当然利益という世界だと思いますけれども、本来的な意味の給与所得と事業所
得が完全にグラデーション化しているので、そちらの方の御議論もしていただいた上
で、所得による控除というくくり、各種所得による控除というのが3ページ目にある
のですけれども、どっちが先かみたいなところはあるのかなという気がいたしました。
それと、田中特別委員がおっしゃった法人と個人事業というところに関係して、実
務というか何とかの話になるのですが、法人で経費を取った上に給与所得を取るとい
うのは個人事業では考え得る方法論ではあるのですね。これは、言い方を変えると控
除が2回取れるみたいな、実額経費を取った上で給与にしてしまうということもない
ではない話になって、それが全体としての事業の収益から見ると、効率のいい手取り
に持っていくこともないではないので、その辺も、これだけグラデーション化して、
それが悪いということではなくて、本当にそれなりの法人事業としてしながら動かし
ていくということも当然あると思いますし、保険料が社会保険の方がいいねというこ
とで雇用に何とかできないかという話も、私などの専門職業なんかの場合には時々出
てきます。それから、雇用の方も、相当変形労働で、逆に個人事業に近いような労働
環境でもあまり問題にしないという業種もおありになると思うので、所得区分をどう
お考えになるかという話は、御議論いただければなという気はいたしました。
○中里会長
ありがとうございます。
林特別委員、お願いします。
○林特別委員
先ほどの質問の続きで、総務省の資料の14ページ目の注4ですけれども、非課税限
度額は均等割と書いてあるのですが、所得割も同じという考えでよろしいでしょうか。
○中里会長
植田市町村税課長、お願いします。
○植田自治税務局市町村税課長
所得割についてはそのような制度にはなってございません。
○林特別委員
ということは、給付でよく問題になる非課税限度額というのは、均等割の方で決ま
っているという理解でよろしいですか。
○植田自治税務局市町村税課長
個人住民税非課税と単純に言われている場合は、均等割の方がより低いものですか
ら、これを基準にされているということでございます。
○林特別委員
了解いたしました。どうもありがとうございます。
○中里会長
今の点は実務的にも重要な点だと思いますが、クリアにしていただいてありがとう
ございます。
前回に続いて、本日も多くの委員の方からとても貴重な御意見、御指摘あるいは御
質問をいただき、大変充実した会議になったと思います。ありがとうございました。
本日の議事はこれで終了となります。
次回総会の開催日時や議題などは、決まり次第、改めて事務局から皆様に御連絡を
申し上げます。
なお、本日の会議の内容は、この後、私から記者会見で御紹介したいと思います。
お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。
[閉会]
PDFファイルを表示(221223_4zen19kaigiji.pdf)
2022年10月18日 第19回 ・個人所得課税について
議事録 (PDF形式:476KB)
会議資料
記者会見録 (PDF形式:111KB)
税制調査会(第19回総会)議事録
日 時:令和4年10月18日(水)14時30分
場 所:WEB会議(財務省第3特別会議室を含む)
○中里会長
それでは、定刻となりましたので、ただいまから第19回「税制調査会」を開始いた
します。
本日の出席者一覧は、お手元にお配りさせていただいているとおりです。オンライ
ンで御出席の方につきましても、現在、全員の方との接続が確認できております。
オンラインで御出席の方におかれましては、会議の途中でパソコン操作などに支障
が生じましたら、あらかじめお伝えしております事務局の電話番号に御連絡をいただ
ければと思います。
なお、プレスの方々には、密回避のため、別室にてリアルタイムで会議の模様を御
覧いただくこととしております。
加えて、これまでと同様に、インターネットでのリアルタイム中継も行っておりま
すので、その点、お含みおきください。
それでは、議事に入りたいと思います。
本日も、税目ごとの議論ということで、10月4日に引き続いて2回目となりますけ
れども、「個人所得課税」を議題にして議論を進めたいと思います。
本日の議事の流れに関しましては、最初に事務局から資料の御説明をいただき、そ
の後に委員の皆様で意見交換を行う時間を設けたいと思います。
早速、主税局税制第一課の関課長、続いて、自治税務局市町村税課の植田課長の順
に御説明をよろしくお願いいたします。
○関主税局税制第一課長
税制第一課長の関でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、資料総19-1に沿いまして御説明いたします。
前回は、どちらかといいますとマクロの所得税負担の状況について御議論いただき
ましたけれども、今回は諸控除の見直しなど比較的ミクロのテーマを中心に御説明申
し上げたいと思います。
まず、現行制度の概観ということで、3ページ目です。この資料は、総合課税分に
つきまして、課税ベースがどの程度あり、どの程度の税額が生じているかということ
を図示したものでございます。恩給や失業等給付という非課税所得を除きました約
270兆円の収入のうち、まず給与所得控除・公的年金等控除といった各種所得につい
ての控除、その次に基礎控除・配偶者控除といった人的控除や社会保険料控除などの
所得控除を適用した後に、課税所得が約120兆円になり、そこに累進税率を適用する
ことで税額は13.6兆円となるというのが現状でございます。
4ページ目でございます。この資料は、前のページで整理いたしました所得控除と
いう欄のうち、人的控除というところに整理させていただいた部分の詳細をまとめた
ものです。基礎控除・配偶者控除・扶養控除といった基礎的な人的控除と、障害者控
除や寡婦控除といった特別な人的控除に大別できます。
5ページ目でございます。この資料は、人的控除以外の所得控除をまとめてござい
ます。社会保険料控除や生命保険料控除などが代表例となってございます。
6ページ目でございます。こちらから、これまでの税制調査会の議論において、
「働き方やライフコースの多様化等への対応」として議論が行われてきました幾つか
の論点を御紹介申し上げたいと思います。
7ページ目をお願いいたします。この資料は、令和元年9月の取りまとめ文書の記
述を抜粋させていただいたものです。最後の方に下線を引かせていただきましたとお
り、「働き方の違いによって不利に扱われることのない、個人の選択に中立的な税制
の実現に向け、所得再分配機能が適切に発揮されているかといった観点も踏まえなが
ら、諸控除の更なる見直しを進めることが重要」といった御指摘をいただいてきてい
るところです。
8ページ目から、1つ目の所得の種類ごとの負担調整から納税者の人的な事情に配
慮した負担調整への見直しという論点をまず取り上げさせていただきたいと思います。
9ページ目でございます。これまで議論いただいてまいりました、経済社会の構造
変化のキーワードの一つが「働き方の多様化」でございます。この資料では、自営業
主の中で、士業や小売店主といった伝統的自営業から、建築技術者・保険外交員とい
った使用従属性の高い自営業者の割合が高まっているという状況を左側にまとめてご
ざいます。また、フリーランスの人口が増加傾向にございまして、内閣官房の調査で
は足元で約462万人といった分析がなされております。
10ページ目でございます。こちらの資料は、昨年6月の専門家会合でフリーランス
協会から御提出いただいた資料を引用させていただいております。正規雇用から派
遣・契約・パートといった非正規雇用、さらにはギグワーカーや請負等のフリーラン
スといったように、職種・就労形態が多様化していることが見てとれます。
11ページ目でございます。こういった状況に対応いたしまして、税負担の調整の在
り方につきましては、収入の稼得形態によって税制上の取扱いが大きく異なることに
なる所得の種類ごとの負担調整、グリーンで塗らせていただいたところですけれども、
こういった調整から、所得の種類と関係なく収入の稼得形態に中立的な、人的な事情
による負担調整、赤く塗らせていただいているところですけれども、こういった方へ
重点を移していくことが指摘されてきたところでございます。
12・13ページ目につきましては、平成27年11月の論点整理におきまして、今、御説
明したような内容が触れられている箇所を抜粋させていただいております。
14ページ目をお願いいたします。こういった御議論を踏まえまして、平成30年度の
税制改正におきまして、給与所得控除・公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替え
るといった見直しが行われてきているところでございます。
15ページ目からは、2つ目の配偶者控除に関する論点の御紹介でございます。
まず、16ページ目でございます。配偶者控除につきましては、政府税制調査会の中
で議論が重ねられてまいりまして、見直しの必要性が指摘されてきております。平成
26年11月の論点整理の中では、共働きよりも片働きの優遇になっている、あるいはパ
ート世帯の優遇になっている、配偶者特別控除の導入により、配偶者の収入が103万
円を超えても世帯の手取りが逆転しない仕組みとなっていて、税制上の103万円の壁
は解消しているけれども、企業の家族手当の支給基準として援用されている実態があ
る、こういった御指摘をいただいております。
17ページ目でございます。この資料は、平成26年11月の論点整理で示されました配
偶者控除の見直しの選択肢、それから、その後の議論を踏まえました平成28年11月の
「経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告」、この2つの文書
におきまして整理いただいた内容をまとめております。
選択肢につきましては、Aとございますけれども、配偶者控除を廃止しつつ、廃止
により生ずる財源を子育て支援の拡充に充てるという案。それから、Bのところです
けれども、配偶者控除に代えまして、配偶者の所得計算において控除し切れなかった
基礎控除を納税者本人の方に移転する移転的基礎控除を導入して、夫婦二人で受けら
れる控除額を一定とする案。それから、Cとございますけれども、配偶者控除に代え
まして、若い世代の結婚・子育てに配慮する観点から、夫婦世帯に対して配偶者の収
入にかかわらず適用される新たな控除を導入する案。こういったものが挙げられてき
たところでございます。
一方で、それぞれの案につきましては、このページの中にも書かせていただいたよ
うな論点も指摘されまして、意見の収れんには至らなかったところでございます。
そうした中で、一番下の箱にございますように、企業の手当の支給基準として援用
されている喫緊の課題への対応という観点からも、「103万円」を引き上げることも
一案との意見も出されていたところでございます。
18ページ目では、こうした最後の点も踏まえまして、平成29年度税制改正におきま
して、所得控除38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、103万円から、矢印
にございますように150万円に引き上げるという見直しが行われたところでございま
す。
19ページ目は、いわゆる「103万円の壁」という御指摘について整理をしておりま
す。配偶者特別控除の導入により、配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手
取り収入が逆転しない仕組みとなってございます。税制上、いわゆる「103万円の壁」
は解消しているということでございます。
他方で、配偶者特別控除の導入後も、配偶者が就業時間を調整することにより、
103万円以内にパート収入を抑える傾向があり、こうした傾向の要因としては、103万
円という水準が企業の配偶者手当の支給基準として援用されているためではないか、
また、いわゆる「103万円の壁」が引き続き心理的な壁として作用しているためでは
ないか、こういった御指摘がなされているところでございます。
20ページ目の資料は、民間企業の家族手当の支給状況をまとめさせていただいてお
ります。①のところにございますように、少しずつ、家族手当自体を廃止する、ある
いは配偶者に着目した形での家族手当は行わないといった企業は増えつつございます。
ただ、②にございますように、配偶者の収入による制限の額につきましては、真ん中
に103万円という欄があるかと思いますけれども、この基準を採る企業が少しずつ減
少しておりますが、一定数存在してございます。
なお、この点に関しましては、64ページ目に参考資料を付けておりますけれども、
全世代型社会保障構築会議の中でも御議論があり、その中で、企業の配偶者手当に関
しましては、労使において改廃・縮小に向けた議論が進められるべきといった御指摘
もいただいているところです。
21ページ目から、3つ目の論点でございます退職所得に関する論点を御紹介いたし
ます。
まず、22ページ目は、平成12年の答申を引用してございます。退職金の性格につき
ましては、賃金の後払いという性格、あるいは退職後の生活保障といった性格が指摘
されてございます。そのほか、功労報償といった点も指摘されているところでござい
ます。
23ページ目でございます。こちらは、その後の税調の答申を引用しておりますが、
令和元年9月の取りまとめ文書の下の方ですが、退職給付に係る税制は、一時金払い
か年金払いかで異なるなど、給付の在り方に対して中立的ではなく、また、転職の増
加など働き方の多様化を想定していないとの御指摘が書かれております。
24ページ目でございます。こちらは退職所得の課税方式でございます。特徴といた
しましては、一時にまとめて相当額を受給することなどを踏まえまして、平準化の観
点から「2分の1課税」の仕組みが取られていること、それから、勤続年数が長いほ
ど厚く支給される退職金の支給形態も反映して、勤続年数20年超になりますと、1年
当たりの退職所得控除額が40万円から70万円に増加する形になっている、こういった
特徴がございます。この点につきまして、長期継続雇用を特に優遇することが労働移
動に与える影響があるのではないかといった指摘をする声が存在するところでござい
ます。
25ページ目でございます。こちらは、令和3年度改正で行われました直近の改正内
容をまとめてございます。退職給付の実態を踏まえまして、5年以下の勤務の役員以
外の従業員への退職金の一定金額以上の部分につきまして、「2分の1課税」の適用
から外すという改正を行っております。
26ページ目から、現在の退職金の支給状況をまとめてございます。まず、退職金の
支給形態でございますけれども、「退職一時金制度のみを有する」企業の割合が増加
傾向にございます。
27ページ目は、雇用の流動化の状況ということで、従業員の平均勤続年数を国際比
較しております。特に左側の男性の従業員の平均勤続年数が直近10年間でほぼ変わっ
ておらず、国際的に見ても最も長くなっているというのが現状でございます。
28ページ目は、勤続年数別の賃金水準を国際比較いたしますと、勤続20年目以降の
賃金水準が大幅に上昇する傾向にございます。
29ページ目です。実際の退職手当の額のイメージとしてモデルケースをお示しした
ものです。20年前、平成13年のブルーの線が、勤続年数20年を超えますと退職手当の
額の上がり幅がきつくなるという傾向がございましたけれども、それと比較しますと、
令和3年の、黒い実線のところに関しましては、以前ほどその傾向が顕著ではなくな
っているのが見てとれます。
30ページ目は、前のページの令和3年分の支給額に対応いたしまして、退職所得控
除額が灰色でございますが、どの程度適用になって、課税対象は黒色の部分ですけれ
ども、そこがどの程度あるかということを図示したものでございます。
31ページ目から、引き続いて、私的年金等に係る税制について御説明いたします。
32ページ目ですけれども、令和元年9月の取りまとめの関連箇所の抜粋でございま
す。まず、働き方の違いにより、私的年金に関する税制の適用関係が異なり、非課税
拠出枠の限度額管理も制度ごとに行われている、これに対して、諸外国では拠出・運
用段階では一定の限度額まで非課税としつつ、給付段階においては、大きな控除を有
する我が国と異なり、基本的には課税となっている、こういったファクトが指摘され
ているところでございます。
33ページ目、この資料は横軸に正規雇用労働者から始まり、自営業主、専業主婦と
いった方などの働き方の類型を並べており、上から下に、投資・貯蓄促進から公的年
金までの老後に向けた資産形成のためのツールを一覧表にしてまとめてございます。
特に、黒の太枠で囲んでいるところが私的年金の世界でございます。
34ページ目でございます。こちらの資料は、私的年金に関する税制措置の原則的な
取扱いをまとめております。イギリス・カナダのところを御覧いただくと、拠出段階
で共通の非課税枠を設定し、給付段階で課税を行うことになっておりますけれども、
左側の日本の場合は、拠出段階では、例えばDB、確定給付年金の場合には拠出上限額
はないなど、企業年金制度次第で差が生じる一方で、給付段階、下の方ですけれども、
公的年金等控除が適用されて、高所得者ほどメリットを受けやすい上に、相当程度の
控除額が適用になっているため、一部課税にとどまっているというのが現状でござい
ます。
35ページ目は、個人型確定拠出年金(iDeCo)の拠出限度額についての整理です。
右側の欄で、例えばDBのところについては拠出限度額なしというように、もともと年
金制度の中で差が生じているわけですけれども、iDeCoの赤いところの拠出限度額に
つきましては、少しずつ制度間の差異をそろえようということで努力を重ねていると
ころでございます。
36ページ目は、主要国における公的年金税制の概要をまとめてございます。一番上
にありますように、日本はEET型ということで、給付段階での課税という考え方を
採っておりますけれども、次の37ページ目で、公的年金等控除が適用される結果、T
の部分が一部の課税にとどまるというのが実態でございます。
38ページ目でございます。もともと政府税調の取りまとめでは、給与・退職一時
金・年金給付の間の税負担のバランスといった論点が提示されてございます。その点
に関連して、年金受給者と給与所得者の課税最低限を比較してございます。年金受給
者の課税最低限は、給与所得者の課税最低限より高くなっていますが、その理由は、
公的年金等控除の額が高いことが要因になってございます。
39ページ目では、私的年金制度におきまして、確定給付企業年金では7割程度、確
定拠出年金では9割程度が一時金での受取りという方式を選択しているということで、
年金と一時金を比べた場合には、一時金が選択されるケースが多いという状況を示し
ているところでございます。
この点につきまして、付随する論点になりますけれども、参考資料として59ページ
目に関連の資料をお付けしております。給与所得と年金所得を同時に得ている方につ
きまして、合計で同じ所得を得ていても、給与所得と年金所得の内訳次第で税負担額
に差が出ている現状があるということも資料としてお示ししております。
40ページ目からは、所得再分配機能に係るこれまでの対応についての整理です。
41ページ目は、所得控除と税額控除の性格の差を整理しております。これまで、納
税者の担税力の減少に配慮するという考え方から、所得控除による対応が基本としつ
つも、高所得者ほど税負担軽減額が大きくなるという特徴がございます。一方で、税
額控除につきましては、財政的支援としての性格が強いといった整理が行われており
ます。
42ページ目、所得控除方式に代わります負担調整の方式といたしましては、ここに
挙げられているとおり、ゼロ税率、税額控除、逓減・消失型の所得控除があるという
ことでございます。
43ページ目、日本の場合は、平成29年度税制改正で、配偶者控除につきまして逓
減・消失の仕組みを導入したということでございます。
44ページ目、平成30年度改正で、基礎控除につきまして逓減・消失の仕組みを導入
してございます。
45ページ目は、所得制限のある所得控除を一覧にしております。例えば、下の方で
すけれども、寡婦控除、ひとり親控除は、右下を御覧いただくと、所得金額500万円
以下という形で所得制限を設けております。
46ページ目は、給与所得控除の適正化ということで、控除額の水準自体の見直しの
話でございます。給与所得控除につきましては、主要国並みに適正化するとの考え方
で引下げが累次行われてきておりますけれども、現状は、下の真ん中の方を御覧いた
だきますと、国際比較ではまだまだ高水準という状況にございます。
47ページ目、公的年金等控除につきましても、平成30年度改正で一部適正化を図っ
てございます。年金収入が高額な方、あるいは年金以外の収入が高額な方に上限を設
定いたしましたけれども、やはり国際比較ではまだまだ高い水準でございます。
48ページ目から、個人事業主の記帳水準の向上というテーマでございます。
49ページ目にございますように、個人事業主の記帳水準をめぐりましては、会計ソ
フトの普及などの技術進歩も背景に、複式簿記による記帳をさらに普及・一般化させ
る方向で施策を検討していく必要があると考えてございます。
50ページ目は、現行の記帳制度を整理してございます。一番左側にございます青色
申告の正規の簿記の世界をいかに広めていくかという観点が重要かと考えてございま
す。
51・52ページ目で実態を整理しております。51ページ目は、事業収入1,000万円以
下の小規模事業者の方に白色申告が多い、52ページ目では、60代以上の個人事業主の
方に白色申告が多くなっているという現状でございます。実態をよく踏まえる必要が
ございますけれども、少しでも正規の簿記による申告が行われるように環境整備に努
めてまいりたいと考えてございます。
資料総19-1に関しては以上でございます。
引き続き、資料総19-2についても御説明いたします。こちらは、前回10月4日の
所得税のセッションの中で、委員の先生から御指摘・御意見をいただいた点について、
幾つか資料を調えさせていただいたので、その御報告です。
まず、2ページ目の資料になりますけれども、林特別委員から、申告納税者の所得
税負担率や資本所得に関する前回お示ししたデータについて、例えば過去に遡った分
析や今後も継続的な分析を求める御指摘をいただいたところです。
その中で、現時点で対応可能なデータといたしまして、2ページ目にございますよ
うに、前回お示しした令和2年分の所得税負担率のデータに加えまして、令和元年分
の負担率のデータをお配りしております。こちらも3ページ目にございます令和2年
分と構図は変わってございません。1億円超の所得の中心は非上場株式の譲渡所得だ
という傾向でございます。
4ページ目ですけれども、佐藤委員から、譲渡所得に関しては、長期間にわたる値
上がり益が一時に実現するので、平準化という要素を考える必要があるのではないか
という御指摘がございました。
こちらの点につきまして、簡便な方法ではあるのですけれども、横軸に譲渡所得を
採り、その金額の譲渡所得が単年、5年、10年、20年、30年という形で一律に生じる
とした場合に、現行の累進課税の税率を適用しますと、それぞれどの程度の税負担率
になるかということを計算してカーブを描かせていただいております。譲渡所得の金
額が10億円を超えてまいりますと、平準化した場合においても30パーセントを超える
ような負担率になっているという絵姿になってございます。
5ページ目でございます。こちらは、前回、6・7ページ目にございますような資
料をお示しして、アメリカ・イギリスの分離課税について、段階的課税の仕組みを採
っていると御説明申し上げた際に、ちょっとイメージが分かりにくいのではないかと
いった御指摘をいただきました。
それで、一つの試みといたしまして、株式譲渡所得の額を横軸に採って、各国で適
用される負担率をカーブの形で整理させていただいております。日本は譲渡所得の金
額に関係なく一律なので赤い横線になりますけれども、例えばアメリカの場合には、
譲渡所得の金額が大きくなりますと33.5パーセントの税率に達することが見てとれる
といったところでございます。
私からの説明は以上です。
○中里会長
ありがとうございました。
続いて、総務省の植田課長、よろしくお願いいたします。
○植田自治税務局市町村税課長
総務省市町村税課長の植田でございます。
私からは、資料総19-3によりまして、個人住民税についての追加的な説明をさせ
ていただきます。所得控除制度の中でも、所得税とは異なる点を中心に、また、個人
住民税独自の仕組みでございます非課税限度額等について資料を用意させていただき
ました。
まず3ページ目、こちらは前回10月4日のときにも出させていただきましたけれど
も、給与所得者の個人住民税額計算のフローチャートでございます。左側の合計所得
金額を算出するための給与所得控除については、所得税と同じ計算をする。そこから
が個人住民税の独自の計算ということで、右上の所得控除の額が所得税よりも低く設
定されていること、課税ベースが若干広がっているということと、あとは税額控除に
ついても収入や控除額に違いがあって、国が政策的に行う控除についてはできる限り
そのまま個人住民税に適用しないよう、控除別に判断されてきているということでご
ざいます。
4ページ目も前回に続いての資料ですけれども、今回、主に御議論いただく所得控
除につきましては、個人住民税についても、所得税より若干低く設定されております
けれども、それでも約70兆円という規模感になってございます。
5ページ目は、平成12年の答申の抜粋でございますけれども、上に「個人住民税の
意義」がございますように、「地域社会の費用を住民がその能力に応じ広く負担を分
任する」という負担分任の性格ということで、課税最低限は所得税よりも低く設定さ
れているとされております。当時は緩やかな累進構造でしたけれども、税源移譲後、
10パーセントの比例税率になっているということでございます。
また、一番下のところですけれども、「個人住民税の課題」の②のところで、「所
得割の所得控除及び課税最低限のあり方については、個人住民税の負担分任の性格か
ら所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かち合うべきものであ
るため、所得税と一致させる必要はない」と記述されております。
6・7ページ目は所得控除の概要ですけれども、6ページ目は人的控除、7ページ
目がその他ということでございます。
6ページ目の人的控除につきましては、基礎控除・配偶者控除・扶養控除など、所
得税と同様の体系になっておりますけれども、右の方の控除額の金額にありますよう
に、その金額は所得税よりも低く設定されているということでございます。
7ページ目でございます。その他の所得控除ということで、上の4つには※印をつ
けてございますけれども、それらについては所得税と全く同様の計算方式です。下の
生命保険料、地震保険料の控除につきましては、赤線を引いておりますけれども、所
得税よりも若干額が小さくなっています。例えば、一番上の2万8千円のところは、
所得税では4万円といった形になっております。
8ページ目です。こちらも所得税の方でも御説明がございましたけれども、平成29
年度改正で行われた配偶者控除・配偶者特別控除の見直しについてのグラフでござい
ます。ほぼ同じ形になっておりますけれども、金額が若干違っておりまして、配偶者
の給与収入が155万円のところから控除額が階段で減額されていく形になってござい
ます。
また、納税者本人の所得制限につきましても、合計所得金額は900万円から1,000万
円にかけて逓減するということは同じですけれども、対応する給与収入が若干少なく
なっているということでございます。
続きまして、9ページ目でございます。8ページ目の控除額を階段で逓減させてい
く仕組みをより詳しく説明したものです。配偶者に係る所得制限、納税者本人に係る
所得制限は、片方または両方適用されるということで、下の表のように両方適用され
る場合にそれぞれ左上から右下にかけて逓減していくという形になってございます。
10ページ目です。こちらも御説明がございましたけれども、基礎控除についても平
成30年度改正で見直されて、生活に十分余裕のある高所得者には措置する必要はない
という考え方に基づいて、控除を逓減・消失させるということでございます。
続きまして、11ページ目は令和元年の答申の抜粋でございます。下から2つ目の段
落のところに、働き方に関する個人の選択に中立的な税制の実現に向けて、諸控除の
更なる見直しが重要だとされておりますけれども、最後の段落に、前回も御紹介いた
しましたけれども、こうした見直しの検討を進める際にも、個人住民税の負担分任の
性格、また、応益課税としての性格等を踏まえる必要があるとされております。
12ページ目は、所得控除と税額控除の効果の比較についてでございます。所得税と
異なるところでございますけれども、所得税は累進税率でございますので、同じ額の
所得控除を行った場合に、高所得者ほど負担軽減が大きくなりますが、個人住民税の
場合は比例税率ですので、所得の大きさにかかわらず所得控除が税額に与える影響は
一定でございます。また、負担調整効果の観点から見れば、所得控除と税額控除につ
いては、いずれも同じ効果になります。
13ページ目以降は、非課税限度額について、また、こうした所得とか税の情報と社
会保障制度の関係についての資料を付けさせていただいております。
14ページ目は、非課税限度額の概要でございます。1つ目の○にございますように、
地域社会の会費的な性格、つまり、できるだけ幅広く御負担いただくという性格がご
ざいますが、低所得者層の負担を考慮し、生活保護基準額程度の所得の方をできるだ
け非課税としようとする制度でございます。均等割は昭和51年度、所得割は昭和56年
度の創設ということになっております。
下に計算式がございますけれども、非課税限度額の基準は、均等割については前年
の生活扶助の基準額、所得割については前年度の生活保護基準額を勘案して設定され
ているということで、世帯の人員数に応じて増額されるという計算式になってござい
ます。
15ページ目では、具体的なイメージとして、単身の給与所得者のケースについて図
示しております。左の四角囲いのところに拡大図が付いておりますけれども、生活扶
助基準が97万円であるのに対して、個人住民税の均等割については非課税限度額が
100万円に設定されています。さらに、所得割の課税最低限が115万円ということで、
所得税については121万円。これらの額の設定について、典型的なパターンが御理解
いただけるかと思います。
16ページ目でございますけれども、この非課税限度額を含めまして、個人住民税等
の課税等によって把握しております合計所得金額等の金額、また、個人住民税につい
て所得割なり均等割が非課税であることが、広い意味での社会保障に関する多くの制
度に活用されているということを示しております。令和2年の段階で関係省庁に照会
した結果を集約しております。
近年、こうした恒久的な制度のみならず、コロナ禍における様々な給付金等におい
て、個人住民税の非課税といった条件が用いられることが増えているという状況でご
ざいます。
最後、17ページ目でございます。今申し上げたようなことが平成27年の税調の論点
整理にも書かれてございまして、下線部分にございますように、様々な社会保障や福
祉の制度の適用基準等に、こうした個人住民税制度における課税・非課税の別や、個
11
人住民税制度における非課税限度額の基準が広く用いられていることと、非課税限度
額の基準が生活保護基準額を勘案して設定されていることなど、社会保障制度と個人
住民税制度が実質的にリンクしていることにも留意が必要ということで、非課税限度
額や税額に影響のあるような制度改正を行う際に、社会保障制度への影響についても
考慮しながら検討していく必要があるものと考えております。
説明は以上とさせていただきます。
○中里会長
ありがとうございます。
それでは、ここからは委員の皆様から御意見をいただければと思います。御意見が
ございます方は、会場で御出席の方も含め、画面上の「挙手」ボタンを押してくださ
い。発言順につきましては私から指名させていただきますので、指名された方は、会
場に御出席の方は卓上マイクをオンにしていただき、オンラインで御出席の方は「ミ
ュート」ボタンを解除して御発言ください。挙手いただいた順に指名をさせていただ
きますが、おのおのの委員の出席可能な時間の関係で前後する場合がございますので、
あらかじめ御了承ください。
また、本日欠席の岡﨑特別委員から意見書が提出されております。政府税調のホー
ムページにも後ほど掲載予定ですので、適時御覧いただければと思います。
なお、事務局資料に言及する場合には、当該資料のページをおっしゃっていただけ
れば、スクリーン上にも表示いたします。
佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員
まず、所得控除の再編成という観点から、御指摘のとおり、給与所得控除・公的年
金等控除などの所得計算上の控除から人的控除への移行というのは重要だと思います
が、併せて、給与所得控除と公的年金等控除の統合という観点があっていいかなと思
います。ある意味、働きながら公的年金をもらっている人は控除を二重取りしてしま
っているので、こういう状況を解消したほうがいいかなと思います。
それから、財務省資料の41・42ページ目に関わりますが、これは長年の課題であり
ますが、そろそろ所得控除の税額控除化を真摯に考えたほうがいいのではないかとい
うことです。それはもちろん所得再分配機能の強化というのもあります。
既に、財務省的にはといいますか、税調的には、消失型控除で対応しているという
向きもあるかもしれませんけれども、そもそも消失型控除というのもおかしな仕組み
で、本来、所得控除の趣旨は、生活最低限を保障するためだったのですけれども、所
得の高い人には生活最低限の費用は保障しなくていいのかという議論になってしまい
ますし、もっとプラクティカルに言うと税制を複雑にするという点もありますので、
それはむしろ税額控除化した方がすっきりすると思います。
また、個人的な属性、例えば扶養家族がいる・いないとか、こういったことは税額
控除に反映させればいいということになります。
もう一つ、私が個人的に気になっているのは、個人所得課税上の所得という定義と、
法人所得課税上の所得の定義が実は違うのですね。法人所得課税は利益ですが、個人
所得課税は、今申し上げたとおり、所得控除があるものですから利益ではないのです。
なので、この辺りの平仄を合わせた方がいいのではないかと思います。つまり、客観
的な基準で所得というのを定義するべきではないかという考え方です。
もう一つ、これも長年の課題の一つで、財務省資料の9・10ページ目に関わる議論
ですが、所得区分の見直しが本来考えなければいけないことかなと思います。既に税
調的には、例えば副業とか雇用的人員への対応というのは、記帳の促進という形でや
っているということになっていますが、納税環境の整備だけではなく、税制上の対応
が求められるかなと思います。具体的には、事業所得にも給与所得と同じような概算
控除、今で言うところの給与所得控除に相当するものを採り入れていく必要があるか
なと思います。
それから、退職所得について、前回も生涯所得ベースで課税するという考え方があ
っていいのではないかということを指摘したのですけれども、退職金も一時的所得で
すよね。だから、一時的な所得に累進課税を課すと課税額が急増するので、それを平
準化するという観点から課税ベースを2分の1に圧縮するという措置を採っています
が、そういうことをやると、39ページ目にあったように、企業年金についても一時金
で受け取る誘因につながってしまっているというのもあります。なので、本当はキャ
ピタルゲインも含めてですけれども、一時的な所得については、退職金であれ、企業
年金の一時金であれ、こういったものについても生涯ベースでの課税、具体的に言う
と、公年所得に平準化させていくという手法が検討されていいのかなと思いました。
次は、総務省の報告に関わる話として二点です。
個人所得課税について、今日はお話がありませんでしたけれども、そろそろ現年所
得課税化を本気で考えた方がいいかなと思います。最近、外国人労働者の方が、例え
ば今年日本で暮らしているのだけれども、来年帰国してしまったとき、課税に1年タ
イムラグがあるものですから、来年、住民税を課そうと思ってももういらっしゃらな
いといった問題もありますし、そもそも担税力の発生と徴税のタイミングを合わせた
方がいいと思うのです。今回のコロナのようなときにも、去年までは順調に仕事をし
ていた人が、今年仕事がなくなっても原理的には個人住民税の納税義務が発生してし
まうのです。なので、担税力の発生と徴税のタイミングを合わせるという観点からも、
現年所得課税化を進めるということ。
これは、税務行政的に言うと、賦課課税から申告納税の転換に当たると思うのです
が、実はこれ自体が自治体の徴税業務の負担軽減にもなると思いますので、そういう
観点からも検討されてはいかがでしょうかということです。
それから、これは一般論に近いのですけれども、課税と給付の連動というのをもっ
と意識した方がいいかなと思います。既に配偶者控除の見直しのとき、今日の資料で
いえば、財務省資料の17ページ目の選択肢A-1ですけれども、配偶者控除をやめて
給付に切り替えるべきだという議論があったとおり、税と給付を一体に考えなければ
いけない時期になってきていると思います。これは何度も言っているのですけれども、
リアルタイムで所得情報を活用して、それでプッシュ型を含む給付の実現をやってい
くことが必要かなと思います。
それとの関係なのですが、今日、総務省から最後の方でお話のあった非課税限度額
についてですが、この仕組みはちょっと変だなと思うのですね。もちろん、生活保護
とのバランスを取るというのは分かるのですが、日本は、課税というのは本来個人単
位でやっているのに、課税所得限度額の計算は世帯の人数を考慮しますので、事実上、
世帯単位になっているような設定の仕方なのですね。もちろん、生活保護とのバラン
スをどうするのだということがあるかもしれません。例えば今申し上げた、給付付き
勤労所得税額控除というものに対応していくことが求められるかと思います。
あと、今回も非課税世帯に5万円を給付してブーイングが起きていましたけれども、
非課税かどうかで給付を受け取れたり、受け取れなかったりするというのは実態に合
わないと思いますので、所得に応じた給付を進めていく視点が税制の観点からも重要
かと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
清家委員、お願いいたします。
○清家委員
関課長、植田課長、とても丁寧な御説明をありがとうございました。大変よく理解
できる説明だったと思います。それで、お二人にそれぞれ御質問というか、コメント
をさせて頂ければと存じます。
関課長の御説明になった個人所得課税について、これまで何度も申し上げたことで
すけれども、改めて申し上げたいのは、今同時に進んでいる全世代型社会保障の構築
と整合的な形になるようにしていただければと思っています。
その一つのポイントは、やはり働き方に中立的な制度にすること。これも社会保障
制度改革の中心命題ですので、その意味で、配偶者控除の問題、公的年金等控除の問
題であります。配偶者控除の問題はフルタイムで働くか、パートタイムで働くかとい
った選択に中立的ではないですし、公的年金等控除は高齢になってから就業を続ける
のか、年金を受け取るのかということによって税制上の扱いが違ってくるという意味
で中立的ではありませんので、繰り返しになりますけれども、ここは抜本的な見直し
が必要だと思います。
もう一つは、全世代型ということの意味は、年齢に関係なく収入に応じて負担をし、
必要に応じて給付を受けるということですので、その面では、38ページ目にも資料が
出ていますけれども、公的年金等控除がある場合、年金給付の場合と勤労収入の場合
で、例えば課税所得の下限が違ってくるというのは中立的ではありません。
特に、これは年金と給与所得の違いですけれども、実際に年金を受け取るのは高齢
者ですから、実態から言えば、年齢によって税制上の扱いが中立的ではないというこ
とになりますので、公的年金等控除についても抜本的に見直す必要があると思います。
それから、植田課長が御説明になった点について、これはコメントですけれども、
先ほど佐藤委員が言われたように、この御説明資料の最後のところにもありますけれ
ども、いわゆる住民税非課税ということが、様々な給付、例えば私も少し関係してい
る事例でいいますと、この2年半ぐらいの間、ものすごい勢いで行われた特例貸付の
制度、短期の貸付あるいは総合貸付という、パンデミック下で生活の厳しくなった人
たちに対する貸付の償還免除の基準などにも使われようとしています。そういう点か
ら申しますと、植田課長が言われたように、住民税というのが様々な給付とか償還免
除等の基準になっているということを考慮しつつ住民税非課税という問題を考えてい
くということはまことに大切だと思いますし、同時に、そもそも住民税非課税という
のは税の仕組みとしてあるわけですから、住民税非課税ということを基準に様々な給
付金とか償還免除の基準にすることが良いのかどうかということ。これはよく言われ
るわけですけれども、これも実は年齢によって中立的ではないわけです。住民税非課
税の計算をする場合にも、公的年金等控除の影響があるということがしばしば指摘さ
れていますので、そういう面ではむしろ社会保障制度あるいは給付の制度の方も、住
民税非課税というのを基準にするのが良いのかどうかというのを考える必要もあるの
ではないかと思いました。これは税制に対する要望というよりは、社会保障制度に対
する要望になるかもしれません。
○中里会長
ありがとうございます。
土居委員、お願いいたします。
○土居委員
私からは四点の意見と一点質問があります。
まず、給与所得控除についてであります。公的年金等控除との関係でいいますと、
資料19-1の47ページ目にありますように、公的年金等控除は2020年の所得から上限
が設けられるようにはなりましたけれども、実際にその上限に直面しておられる方は
たったの0.5パーセントしかおられないということに対して、給与所得控除は今850万
円よりも多い給与収入ですと上限になる、そういう標準的な上限ですけれども、これ
でおおよそ7~8パーセントの方がこの上限に直面しているということのバランスを
考えると、やはり公的年金等控除の上限が高過ぎると言わざるを得ないと思います。
少なくとも、給与所得控除の上限適用者並みの7~8パーセントの上位の年金収入の
方々に対して、この上限控除がこれ以上増えない形になるような仕組みに変えていく
必要があると思います。
また、59ページ目では、両控除が併用できることによる弊害が如実にこのグラフに
表れていて、両控除をうまく使えば、同じ課税前収入にもかかわらず負担が違うとい
う、水平的公平にも差し障るような控除が併用されているということですから、両控
除の統合を含めて今後検討する必要があるのではないかと思います。
それから、43ページ目に配偶者控除の例がありますけれども、逓減・消失化という
のは非常に複雑な仕組みをもたらしてしまう。特に、下の表でありますけれども、結
局、自分が納税者として配偶者控除ないし配偶者特別控除が一体幾ら受けられるのか
ということは、このマトリックスの中から探し出さなければいけない。しかも、それ
は単に控除であって、税負担軽減額が幾らになるかというのは、さらに税額等の計算
を経てからでないと税負担軽減効果が分からないという非常に複雑な仕組みになって
いるということですから、むしろ税額控除などを分かりやすい仕組みにして、働き方
に中立なものにしていくことが必要だと思います。
それから、資料19-3の14ページ目で、先ほど佐藤委員、清家委員からも御指摘が
ありましたけれども、非課税限度額は私も問題があると思います。実際、個人住民税
を納税されている方は6,000万人ほどしかおられないわけです。全人口の半分ぐらい
しかいないにもかかわらず地域社会の会費と言えるのだろうかということはあるわけ
です。均等割、所得割、それぞれあるわけですから、均等割だけはお支払いいただく。
それは数千円ですから、そんなに重い負担と言えるわけではない。所得割は、もちろ
ん所得が高くなければ、負担はそんなに重くならないということでありますから、地
域社会の会費と言うならば、せめて少しは納税していただく工夫が必要なのではない
かと思います。
最後の意見は、退職所得課税と私的年金及び非課税貯蓄のiDeCo、NISAに関連する
ところであります。資料19-1の39ページ目に、特に確定給付企業年金・確定拠出年
金で一時金払いが多いということが示されております。これは多分に税制が影響して
いると私は思います。つまり、一時金払いにし方が年金払いにするよりも税負担が軽
くなる。それは退職所得課税の話とも密接に関係しているということですから、退職
所得課税の負担が軽くなり過ぎているのではないかという批判があることは承知して
いますけれども、目のかたきにするよりかは、ひとまず一時金払い、年金払いのどち
らの受け取り方であっても税負担が同じになるような仕組みに移行していく。もちろ
ん一時金払いのときに住宅ローンの返済に充当するということがあれば、その分だけ
考慮した上で、どちらの受け取り方でも同じ税負担になるような仕組みに変えていく
ことに取り組むことがあってもいいのではないか。
それから、NISAとiDeCoは、老後の資産形成という意味では非課税枠を両者併せて
考えるべきではないか。その金額が低所得層でも十分投資ができるような枠にすると
いうことであって、高所得層だけがその枠が使えるということにならないような範囲
で、両者を併せ持って非課税枠を考える必要があるのではないかと思います。
今申し上げた点に関して、事務局に質問がございます。政府税制調査会で、まさに
iDeCo、NISAが俎上に載っているということではあるのですが、新たに「新しい資本
主義実現会議 資産所得倍増分科会」でこの議論をするというお話になっているやに
聞いております。
政府税制調査会は様々な政策決定に資するような材料を提供すべく議論するという
ことではないかと思っておりますが、あちらの議論の方が先に結論が出るということ
になりますと、我々は一体何の議論をしているのだろうかという疑問にもさいなまれ
るわけでありまして、両会議の役割分担というか、立てつけというか、その辺りはど
ういうふうにお考えなのかをお伺いしたいと思います。
以上です。
○中里会長
それでは、調査課長、お願いいたします。
○河本主税局調査課長
政府税制調査会は、おっしゃるとおり中長期的な視点から税制の現状と今後につい
て検討いただく場でございますけれども、政府税制調査会だけが税の議論をする場で
はもちろんございませんで、政府の様々な他の会議とか、あるいは国会の中で様々な
議論がなされていく。そのどこの段階で何の税の改正が決まるかということは、それ
ぞれのタイミングによって決まってくるものだと思います。
いずれにしましても、様々な幅広い観点から政府税制調査会は中長期的な視点から
あるべき税制を議論するということでございまして、特に何かの議論をしてはいけな
いとか、何かの議論はここでやるということが決まっているわけではございません。
○中里会長
それでは、田近特別委員、お願いします。
○田近特別委員
前回から、調査課長が今まさにおっしゃったように、中長期的な視点で所得税の問
題を考えるということで議論をしているわけですけれども、そういう線に沿って所得
税改革の流れから始めたいのですけれども、まさに中長期な点です。バブル崩壊後、
いろいろ議論はあったのですけれども、私は、定率減税の議論はその発端として重要
だったと思います。
アジア危機が1998年にあって、時は小渕内閣ですけれども、99年に恒久的減税とし
て定率減税をした。簡素にやらなければいけないということで、払った税金の一定割
合を負担軽減してあげるという仕組みが定率減税ですけれども、それが99年で、その
後、小泉内閣になって景気が良くなって、2007年からそれがなくなった。つまり、恒
久的減税は長い期間、ほぼ10年たって、それを廃止できた。それは一つのアチーブメ
ントだったと思います。
第2のアチーブメントは、いろいろあるかもしれませんけれども、私が思う範囲で、
今日は関課長から御説明のあった所得計算上の控除、つまり、給与所得に対して、公
的年金に対して、退職金に対して、そういう所得計算上の控除から人的控除に控除を
改めようと。これも一つの大変な成果だったと思います。端的に言えば、給与所得控
除・公的年金等控除から、基礎年金控除に振り替えた。これが第2のアチーブメント
だった。
では、今、何が問題か。前回の1億円の壁というのも問題の一つでしょうけれども、
今日は財務省・総務省から非常にいい資料を出していただいて、中長期的な観点から
何がイシューなのかということで、今のことを踏まえて議論したいのです。
私は、圧倒的に重要な問題は、社会保障と税制の関係をどうするか、具体的に言う
と社会保険料をどうするか。実態的に言えば、普通の人の8割以上あるいは9割近く
の人は社会保険料の方が大きいわけですよね。それをどう考えるかということです。
具体的に申し上げると、配偶者控除の問題があって、19ページ目を見ていただきた
いのですけれども、これももう長年にわたって議論して、いわゆる103万円の壁で、
この紙は歴史的な紙みたいな感じですけれども、要するに、配偶者特別控除で消失控
除をするので103万円の壁はありませんというのはそのとおりだと思います。でも、
なぜこれがまだ問題になっているかというと、実は106万円の辺りから社会保険料が
始まるわけです。そうすると、働く人が社会保険料も税負担と同じようにみなせば、
相変わらずデントというか、へっこみは起きるわけです。一つの例を申し上げました
けれども、社会保険料と同時に考えないと問題は解けない。
それを言い出したら切りがないと思うのですけれども、もう一つです。次に、公的
年金等控除も改革はしてきましたけれども、これも年金所得をどう考えるかというこ
とで、社会保険の問題と切り離せない。割り切って言えば、EETの仕組みですから、
それはもうしっかり取る。特に必要な配慮があるとすれば、それは高齢者に対する配
慮なので、公的年金の配慮ではなくて老齢者への配慮だろう。
退職所得も、34ページ目を見ていただきたいのですけれども、これは賃金の後払い
なので、それをどう平準化するかで、2分の1が良い・悪いということになるわけで
すけれども、考えてみたら、34ページ目の大きな枠があるのですけれども、DC年金じ
ゃないかと。DC年金で、それをそれぞれの人のアカウントで管理すればいいのではな
いか。
何が言いたかったかというと、今まで所得税に関して幾つか大きな改革があった。
しかし、社会保険料の問題を今考える、社会保険を考えないと所得税の問題が解けな
い。
次は、働き方の問題で、多様な働き方の問題もさんざん議論しました。持続化給付
金に至っては、働いている人というのは事業所得だと思ったら給与所得であったと。
その働き方の問題です。
それから、負担調整では、既に出ているように、所得控除というのは消失控除で対
応していますけれども、それだけではなくて、タックスクレジットをどう考えるか。
全部を包摂するものとしてデジタル化にどう備えるかということで、申し上げたかっ
たのは、今までの歩みはそれなりに踏まえて、今の問題をもっと概念化するというか、
全体の現状と問題を抽出して、それぞれにどう対応するか。
その中で私が一番申し上げたかったのは、社会保険料と所得税を同時に考えないと
今の問題は解けない。それを一番申し上げたいと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
神津特別委員、お願いいたします。
○神津特別委員
既に、佐藤委員をはじめとして何人かの委員がおっしゃったことと大分かぶるので、
たくさん言いたいことはございますが、1つだけに整理させていただきます。
所得控除でございますけれども、基礎控除が逓減消失してしまうことで、高額所得
者は課税最低限も保障されないという制度は明らかにおかしな制度だと思います。
そこで、給与所得控除を縮減、公的年金等控除も減らして、基礎控除は平等に増額
するというスタイルで行っていただきたいと思います。それが働き方の多様化とかい
ろいろなことにも耐えられる、正しい所得税の対応だと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
熊谷特別委員、お願いします。
○熊谷特別委員
本日御説明いただいた論点に関しましては、全て改革の基本的な方向性に賛成いた
します。
清家委員からも御指摘がございましたけれども、働き方やライフコースが多様化す
る中で、働き方の違いによって不利に扱われることのないよう、個人の選択に中立的
な税制という観点から、とりわけ配偶者控除や退職金税制、そして、公的年金等控除
等の見直しは、いずれも極めて重要な改革のメニューであると考えます。
そのことを申し上げた上で、具体的に三点だけコメントをさせていただきます。
まず一点目として、公的年金等控除でございます。公的年金と給与所得の両方を得
る者について、公的年金等控除と給与所得控除がダブルで控除されるため、課税最低
限が低くなり過ぎている面があります。課税最低限、住民税非課税ラインは、経済対
策の給付対象者や社会保障給付の自己負担割合などを決定する際にも利用されており
ますので、所得の種類ごとの控除からなるべく基礎控除に振り替えて、負担能力を適
切に反映した税制に近づけていくべきであると考えます。
二点目といたしましては、退職所得控除でございますけれども、労働移動の障害と
ならないように、働き方に中立的な税制とする観点から、勤続年数1年当たりの控除
額を同額にする、あるいは退職時に得た退職金をiDeCoなどに拠出してプールすれば、
その分は課税を繰り延べられるといった制度改正などが必要ではないかと考えます。
三点目として、先ほど土居委員から御指摘があった内容に賛同いたします。やはり
税というのは地域社会の会費のような性格がございますので、広く薄く負担するとい
うことが基本です。諸外国ではある程度納税しているような所得レベルの方々であっ
ても、我が国ではほとんど納税していないという、このカーブのゆがみが本質的な問
題の一つでございますので、もちろんこれは政治的には非常に困難なものではあると
は思いますが、こういった問題についても正面からしっかり議論することが必要では
ないかと考えます。
私からは以上でございます。ありがとうございました。
○中里会長
ありがとうございます。
芳野特別委員、お願いいたします。
○芳野特別委員
初めに、所得控除制度について、働き方などに中立な税制構築の観点から、検討の
方向性について五点申し述べたいと思います。
一点目は、人的控除についてです。高所得者ほど税負担の軽減額が大きくなる現行
の所得控除方式から、所得水準にかかわらず軽減額が一定の税額控除方式に改めてい
く必要があります。
二点目は、給与所得控除についてです。勤務費用の概算控除に加え、給与所得者と
自営業者などとの捕捉率の差などを総合的に加味して設けられている控除ですので、
検討を行う場合は慎重の上にも慎重を期すべきと考えています。
三点目は、配偶者控除についてです。扶養関係と一定収入のみを基準とする扶養控
除に整理・統合した上で、現行の配偶者特別控除に準じた措置を講じる必要があると
考えます。
四点目は、退職所得控除についてです。就業形態が多様化しており、勤続年数で差
を設ける意義も薄れていることを踏まえ、勤続年数にかかわらず一律とし、水準は60
万円程度を念頭に検討すべきと考えます。
五点目は、フリーランスについてです。税制の議論とは異なりますが、コロナ禍を
機にギグワーカーの法的保護に向けて、世界的に労働者性を認める方向で検討がなさ
れています。日本においても、税制を見直す前に労働者性の見直しを行うべきです。
次に、企業年金などに係る税制について申し述べたいと思います。企業年金は後払
い賃金としての性格と公的年金の補完機能を持っており、労使合意の積み重ねによっ
て実施されてきた経緯を重く受け止めるべきです。万が一にも、税制や法制度の見直
しによって企業年金の設計や給与水準の変更を余儀なくされることがあってはなりま
せん。また、企業年金と個人年金は制度の性格が異なり、掛金の拠出者も異なります。
両者を確定拠出年金制度として一元的に限度額管理をしている点は、企業年金の個人
年金による置き換えの懸念があり、労働組合として問題意識を持っています。
なお、この点について仮に検討を行うとしても、各制度の性格に十分留意した上で、
高所得者優遇とならないよう丁寧に検討していく必要があります。あわせて、公的年
金等控除については、年金以外の所得を含めた高所得層における応能負担の在り方の
検討も必要と考えます。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
足立特別委員、お願いします。
○足立特別委員
私の方からは、働き方、そして、ライフコースの多様化に即した中立な税制の在り
方についての意見としまして、個人所得課税について二点、個人住民税について一点
ございます。
まず一点目、個人所得課税におきましては、14ページ目にありますように、COVID19以降、フリーランスやギグワーカー等の働き方、そして、令和3年の高齢者雇用安
定法改正におきます70歳までを選択肢に含めました業務委託や社会貢献などの稼得方
法などから、多様な働き方を想定した所得計算が求められています。具体的には、給
与所得控除や公的年金等控除の一部を基礎控除に振り替えることで、働き方をゆがめ
ない中立な税制の在り方は引き続き検討が必要かと思います。この点につきまして、
女性の就労の促進につながる形で配偶者控除の検討を併せてお願いいたします。
二点目につきましては、高齢期におきます課税の在り方です。58ページ目にありま
したように、確かに高齢期の経済的稼得力が減退すると、公的年金による負担調整と
税制の配慮は重要です。しかしながら、高齢者雇用の進展によって所得形態の多様化
を踏まえ、年齢ではなくて、稼得能力に応じた税負担の在り方の検討が求められてお
ります。具体的には、諸先生方におっしゃっていただきましたように、給与所得を得
ながらも年金受給者が増えている状況を鑑みた場合に、給与所得控除と公的年金等控
除それぞれの適用による課税ベースの脱漏が課題になる中で、令和4年には65歳未満
の在職老齢年金制度による見直しが行われています。したがいまして、高齢期におき
ます課税の在り方において、高齢者の働き方をゆがめない中立な税制も検討が重要か
と思います。
これら二点の多様な働き方におきます税制の中立性につきましては、個人住民税に
おいても同様になります。
最後に、16ページ目にありました個人住民税と社会保障制度の適用基準との関係に
ついての意見になります。社会保障制度の適用基準として、個人住民税の非課税限度
額や総所得金額が使用されています。ですので、本来、個人住民税とは地域社会の費
用を住民が広く負担を分任するという応益負担という性格を踏まえますと、社会保障
制度の適用基準としてリンクしていますけれども、ここは給付と税を区別して考えて
いくことが重要であると考えます。
私の方から、以上三点になります。
○中里会長
ありがとうございます。
赤井特別委員、お願いいたします。
○赤井特別委員
細かいところは他の委員の方がかなり言っていただいていますので、大きな考え方
としては、中立性、垂直的な公平性というところをキーワードに、徹底的に議論をし
て進めるべきところを優先順位をつけて進めていくべきかと思います。
中立性に関しては、フリーランスも含めて多様な働き方に対応できるような税制、
あとは女性の働き方に関しても中立性、制度を優先順位をつけながら確実に停滞する
ことなく進めていくことが大事かなと思います。
公平性に関しては、いろいろ議論されているように垂直的な公平性をもう少し考え
ていくべきではないか。要するに、累進化をもう少し進めるべきではないかというと
ころで、所得税・住民税、統一的な視点から控除の在り方を議論すべきと思います。
住民税の基礎控除の見直しということで、10ページ目にありますけれども、かなり
高所得者の人しか減少していないということもありますし、こういうところももう少
し累進性を強化するということがあってもいいでしょうし、ちょっと戻りますけれど
も、中立性のところでいえば、あまり出ていない、例えば退職金も、資料総19-1の
24ページ目で、いまだに長く働けば退職金の控除も増えるということで、これも中立
性かもしれませんけれども、あまり頻繁に会社を替えるような今の働き方だと一つの
企業でずっと働くわけではないですから、長く働いた方が控除額が増えるという制度
を含めて、中立性と公平性を順に徹底的に見直していくべきだと思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
諸富特別委員、お願いします。
○諸富特別委員
今回の所得税の議論は、経済社会の変化の中でどういうふうにして21世紀型の所得
税制をつくっていくかという点で非常に重要な論点が幾つも出されたと思います。既
に幾つかの指摘がなされましたが、所得税制の基本的な考え方で多くの委員の皆様が
指摘されたのは、所得控除は高額所得者により大きな便益をもたらすやり方であり、
一定の所得を課税対象から外すということに歴史的な意義があったとしても、現段階
で見れば、税制の所得再分配の機能を損なうことになりますし、また、税収を損なう
ことになりますので、これを税額控除に切り替えていくという点で大きなコンセンサ
スが形成されているのではないかという印象を私も持ちました。
さらに、税控除というのは、基本的には課税最低限以上の方々に税額を減じるとい
う恩恵が行き渡るわけですけれども、さらにこれを手当に切り替えることによって課
税最低限以下の世帯にも恩恵が及びます。そういう意味では、今日の財務省資料の17
ページ目に3つの選択肢ということで議論されている中では、こういった改革をやっ
たときに、それぞれどの世帯にどれだけのプラスマイナスがあるのかということが明
示的に計算してみると恐らく出てくると思いますが、所得控除を廃止して手当を乗せ
るという形にするものが、恐らく一番所得再分配上は改善に資するような改革になっ
ていくのではないかなと思います。
そうしますと、税率の構造を変えなくても、控除の仕組みを切り替えることによっ
て、所得税制の所得再分配機能を向上させることができますし、また、控除の改革と
手当の創設ないしは増額をセットにすることによって、より効果的な所得再分配機能
の発揮がなされるのではないかと思います。
そういう観点で、年金の課税についても、今日の資料の34ページ目とか36ページ目
のところで、これはかつて海外調査の報告でも詳細になされた点でありますが、例え
ば34ページ目で気になるのは、日本の場合は拠出と運用の段階では課税せず、給付の
段階で課税するという形ですが、一部課税という形で図に描かれてありますし、また、
36ページ目の公的年金についても、日本のところはEETと書かれているのですが、給
付の段階では他国では課税となっているところが日本は一部課税にすぎない。ここは
先ほど御説明にあったとおりです。この辺りは、日本の所得税制として、拠出と運用
の段階で非課税とするなら、給付の段階での課税をしっかりやっていくような仕組み
に切り替えていくべきではないか。
そもそも私は知識がなくて、なぜ年金に関してこのような控除制度が認められてき
たのかというのは存じ上げていないので、この辺りを御教授いただければと思います。
恐らく年金がそれほど分厚くなかった頃に、なけなしの年金に対して年金所得を課税
に組み入れるのは忍びないということから、これを課税しないというところで始まっ
たのではないかと思うのですけれども、年金制度のその後の発達につれて、こういっ
たやり方が現代的なのかどうかということについて疑問に思いますし、ここを見直し
ていくべきではないかと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
武田委員、お願いします。
○武田委員
本日は、事務局に大変丁寧に重要な論点を御提示いただきまして、ありがとうござ
いました。
結論としまして、経済社会の構造をしっかりと踏まえた税制へ、そして、働き方や
個人の選択に中立な税制へと見直していくこと、これが最重要課題であると考えます。
その上で、時間の関係で二点に絞って意見を申し上げます。
一点目は、配偶者控除についてです。経済社会の構造変化として、もはや共働き世
帯が過半を上回っております。また、配偶者の働き方に中立的でない税制度を維持す
ることの弊害も増していると思います。
制度的には壁がなくなっているとの御説明がございましたが、本日御説明いただき
ましたとおり、現実には家族手当がある企業の45パーセントが103万円で収入制限を
行っておりますほか、心理面でも行動に影響している事実がございます。税制は社会
の慣習や、心理要因として人々の行動を変えていく、あるいは根づかせていくことの
表れと思います。
田近特別委員が御指摘されましたとおり、社会保障も併せて考えることは大切で、
また、全世代型社会保障と整合的であることも必要と思いますが、本税制調査会とし
ては、配偶者控除を廃止し、働き方に中立な税制を実現することが大切ではないかと
考えます。
二点目は、退職金税制に関してです。今後の日本経済を考えますと、企業が構造転
換のスピードを上げて付加価値向上を伴う生産性の上昇につなげていけるのか、生産
性が低い分野から生産性が高い分野に資本や人をスムースに移動できるのか、ここに
かかっていると考えます。
この実現に向けては、個人の意欲や挑戦が、少なくとも税制で妨げられない中立な
制度にする必要がございます。つまり、経済社会の構造変化を踏まえた労働移動に中
立という観点から、また、個人の多様な働き方、選択に中立という観点からも、退職
所得控除は勤続年数で差を設けずに、一律とする制度へ早急に改めるべきと考えます。
二点に絞って意見を申し上げましたが、それぞれ歴史的にはその意義や役割はあっ
たと思います。しかし、経済社会の変化とともに制度も見直していくことが重要と考
えます。同時に、日本の国際競争力、産業構造の転換の遅れをこれ以上放置してはな
らない。そうした危機感が税制調査会として必要ではないかと考えます。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
寺井委員、お願いします。
○寺井委員
非常に丁寧な御説明をありがとうございました。
私からは、既に他の委員の方々もコメントされていますが、退職所得税制について
二点意見を述べさせていただきたいと思います。
退職金・企業年金は賃金の後払いの性質を持つというお話がありました。後払い賃
金体系には、労働者の離職をできるだけ防いで、採用や訓練のコストを抑えたいとい
う企業の意図が反映されていると思っており、その企業の合理的な判断を否定するこ
とはありませんが、それだけでなくて、長期就労に有利な退職所得への税制が雇用の
流動性を抑制する効果を持っているとしたら、それは修正されるべきだと考えます。
労働者がより高い生産性を発揮できる産業・企業に移動しようとするときに、退職
金・企業年金の受取りに不利にならない制度設計が望ましいと考えます。
二点目ですが、現行の退職所得税制が、企業が後払い賃金体系を選択しやすくして、
労働者がそれを受け入れやすくしていないかを注意深く考える必要があろうかと思い
ます。資料総19-1の23ページ目で、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け
取ることによって税負担を回避した事例に言及がありました。非常に単純で極端な例
えで恐縮ですが、労働者の賃金支払の割引現在価値、つまり、生涯賃金が同じであっ
ても、若いときに賃金を抑制して、キャリアの後半で賃金を高くする賃金体系の方が
税制上有利になるのであれば、払わなくて済んだ税金分、労働者は得をしますし、ま
た、それを見越して企業はその分賃金を抑制することができるかもしれません。先ほ
ど資料で御説明いただいた例は、これに当てはまるのかなと思います。すごく目立っ
た例なので資料に載っていたと思うのですけれども、その他にもこのような例に該当
するものがないか。今、私が申し上げたのは理論的な可能性ですので、それにとどま
らず、きちんとしたエビデンスを踏まえて考えるべきということを申し添えたいと思
います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
辻󠄀委員、お願いします。
○辻󠄀委員
私は、今回の参加者の中では比較的少ない政治学も専攻している人間です。政治学
の立場からこれまでの議論を聞いていますと、今までいろいろな事情でこれだけ複雑
な制度になってきていて、税額控除や所得控除などがさまざまな経緯から複雑にから
みあって、今の制度でやっと合意が形成されてきているという側面があります。
そうした中で、税額控除だけでさっぱりシンプルにというのは理論的にはできるの
かもしれませんが、現実問題としては、ほんとうに合意形成が可能なのでしょうか。
現実的に考えると、税額控除と所得控除を両方考えながら、現実的に筋が通ってい
るものを求めていかざるをえないと思いました。
これを前提に具体的には三点あります。
一点目は、今回の税調の議論の中で、EBPMということで、なるべく政策の効果を検
証していこうと一生懸命やってきたことです。これからすると、今日話題になってい
るのは、所得税の控除の部分とか個人住民税の控除の部分が結果的に単に税収の多寡
に影響しているだけなのか、翻って住民行動に影響を与えて、政策的な副反応も出て
いるのかを検証すべきです。また、同じようなことを給付でやるよりは、政策費用は
税額控除でやった方が低いはずです。
こういうことを考えた場合に、特に所得税控除と個人住民税控除は微妙に額も違い
ます。これらを比較してみたときに、何か住民行動に対して異なる影響を与えている
か。こうした点を、少し検証してみる必要があるのではないかというのが一点目です。
二点目に、個人住民税が非課税かどうかという基準は、他のところでもたくさん援
用されています。今でも非課税なのか、ぎりぎり課税なのか、そこのところの公平性
が問われていますが、個人住民税の非課税基準にかわる明確な基準がないので、どう
してもこの基準がよく用いられています。
したがいまして、仮に個人住民税の非課税世帯を変更した場合に、サンプルでいい
のですけれども、この基準を援用している他の部分の影響も含めて、どうなるか慎重
に議論する必要があると思いました。
三点目に、他の給付と併せて個人で見るか、世帯で見るかという話が一部でありま
した。昔に比べて家族の絆は非常に緩くなっていて、そういう意味では個人で見た方
がいいということがあって、奨学金の認定に際しても世帯で見ていたのを個人の要素
を入れるように変わってきたところもあります。しかし、現実問題でいうと、まだ世
帯単位で行っているものが、たくさんあります。それを個人に分解すると給付増につ
ながる場合もあり、伝統的に世帯単位で行ってきたものについては、世帯単位の良さ
も十分残していくということを考えながら、税制改革していく必要があると思います。
以上です。
○中里会長
ありがとうございます。
岡村委員、お願いします。
○岡村委員
三点申し上げます。
一点目は、本日、土居委員から非常に貴重なお言葉をいただきましたが、それは受
け取り方に中立的だということでございます。私もこの考え方には全面的に賛成でご
ざいまして、退職所得、年金、退職所得が基になるような金融資産性所得といったも
のについては、受け取り方に中立的な、言葉を換えて言えば、支出に対して中立的な
税制を一体的に組んでいくべきではないかと考えます。
もともと所得とは何かと言われると、それは純資産の増加と消費であると言われて
いますけれども、特に、あまり豊かでないような人たちについては、消費、支出の部
分を重視して税制をつくっていくことが大事だと思います。
しかし、これに対して高所得者層、例えば1億円の山の向こう側にいる人たちにつ
いては、貯蓄の部分、純資産増加の部分に対してある程度の負担をお願いする。それ
は、やはり累進性のあるもの、つまり、EETということで言えばTです。しっかりと
した累進課税を金融資産性所得であっても行うべきである。その点では、賦課税とか
いろいろな形が考えられると思うのですけれども、多少はそこのところを入れていた
だくということがいいのではないかと思います。
二点目は、それに伴う住民税の問題です。これも以前申し上げたかもしれませんけ
れども、現在、住民税は金融資産性所得については減免課税をやっていると思います。
ですから、さらにもう少し進んで、ここのところが絶対に比例税率でなければならな
いのか、応益課税だから比例税率だというところが論理必然的に結びつくのかどうか
というところも検討の余地があり、もし国税の方で極めて高い金融資産性所得につい
てはもう少し御負担をお願いすることが可能になるのであれば、住民税もそちらで行
かれるのがいいのではないかと思います。
三点目は、10月4日に出されている資料総17-1の22ページ目、納税者の分布(所
得税の限界税率ブラケット別)をじっくり見ていると、地方税のことは横に置かせて
いただくと、5パーセントの人たちが相当部分を占めているのですけれども、5パー
セントの所得税がいいのか、それとも、もう少し違う、私は支出ということを申し上
げましたが、例えば消費の方がむしろスムースなのかということは、国全体の政策と
してよく考えていく必要があるのではないか。
そして、今日は税額控除なのか所得控除なのかという話が出ていますけれども、ゼ
ロ税率という話もあったと思います。確かに、税額控除だと累進課税の下で同じ価値
を持つとか、累進性の下で所得控除を消失させるといったアイデアでやっているので
すけれども、基本的にはこれは税負担の累進性の問題であり、本来は累進税率上にお
いて対処すべき問題ではないかと思います。
そうだとすると、現在の様々な基礎的、人的控除と呼ばれているものは、ゼロ税率
といった形で処理をし、ゼロ税率の範囲をもうちょっと延ばす。そして、そこのとこ
ろは所得税ではないような形で処理をした方が、国全体の税制としてはより合理的で
効率的かもしれないと思います。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
田中特別委員、お願いいたします。
○田中特別委員
幾つか商工会議所で検討していることもあるのですけれどもお話をしたいと思いま
す。
まず、103万円の壁がなくなったというお話をいただき、確かにグラフを見るとス
ムースになっているような気がするのですが、現場からは、やはり150万円の壁があ
る、全額最大限に控除を受け取れるというところについて非常に意識をしていると。
さらに、田近特別委員がおっしゃるとおり、社会保険料の壁が130万円にあります。
ですから、やはり社会保険料と税金を一緒に考えて、その壁をどうしていったらいい
のかということが一つのポイントではないかなと思います。そういった壁を意識して
労働時間の調整を行うことは引き続き続いていると言われており、なおかつ人材の確
保に苦慮していると言われています。
もう一つ、法人と個人事業との境目があまり議論されたことがないのですが、いつ
も小規模な法人と大企業との間で軽減税率によって不公平ではないかと言われるので
すけれども、実際には、個人事業主が法人になるか、個人事業主のままやるかについ
ては、税金だけでなくて社会保険料も効いていて、負担は法人になった方が多いので
すね。今、15パーセントの軽減税率を適用したとしても、負担は法人の方が多いです。
これは全体の議論をするときにすごく大事なポイントだと思います。
先ほど佐藤委員が自営業にも給与所得控除をすべきではないかと発言がありました。
僕は自営業の負担をなるべく軽くしてあげることについては反対ではないのですが、
実際に個人事業主と法人との間の境目がどうなっているのかということを検証して対
策を立てていただきたいと思います。
3つ目は、先ほども配偶者控除の話が出ました。辻󠄀委員の言うとおり、合意形成を
することは、実際の各個人にとってどういうプラスマイナスがあるかということにか
かってくるので難しいと思うのですけれども、商工会議所では、配偶者控除について、
基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除を所得に寄らない人的な控除に統一して、夫
婦であれば消化し切れない部分は片一方にシフトするようなことができると分かりや
すいのではないかと主張しています。
税額控除についても、そういう意味では若い人にとって厚くなる支援ができるよう
な税額控除の方がいいかもしれないというところが今の議論にはあります。
もう一つ、1億円の壁について、3ページ目の表にあるとおり、この内容について
もう少し知りたいと前回お話があったと思うのですが、私も同様で、非上場株式の譲
渡所得等が27.4パーセントで非常に大きなシェアを占めているのですけれども、これ
は金融資産ではないので、それなりの事情・背景があるような気がするので、要注意
かなと思っていて、この表についてももう少しレイヤーを分離して分析をすることが
必要ではないかと感じました。
○中里会長
ありがとうございます。
林特別委員、お願いします。
○林特別委員
二点コメントと、一点質問があります。
まず、参考資料の御準備ありがとうございました。御準備いただいた方々によろし
くお伝えください。
コメントですけれども、二点とも所得控除に係ると思います。間違っていたら御指
摘いただきたいのですが、配偶者控除は、そもそも扶養控除から分離・独立したもの
だと記憶しています。配偶者控除をなくすとなると、そもそも扶養控除をどう考える
かという問題に波及せざるを得ないかと思います。したがって、特定の控除をなくす
という御議論は、担税力をそろえるという所得控除の観点から、合理的かつ筋の通っ
た理論的な検討が必要かなと思います。
もう一つ、これも退職金に係る控除のお話になると思いますが、退職金は給与を後
払いするという考え方をすれば、考えようによっては積立の年金のようなイメージに
なるのかなと思います。高額所得者は特別配慮する必要はないのかもしれませんけれ
ども、年金給付が厚生年金も下がるかもしれないという状況の中で、退職金は老後資
金として捉える必要があるので、それに応じた控除の仕組みもあってもいいのかなと
思いました。
最後は住民税の非課税限度額についての質問です。生活保護とのバランスで決まっ
ているという御説明があったような気がしたのですけれども、生活保護基準は級地に
よってかなり違います。となると、バランスで決めるということになれば、地域によ
って住民税の非課税限度は変わらないといけなくなると思うのですけれども、そこら
辺はどうなっているのかなというのが興味を持ちました。
以上でございます。
○中里会長
ありがとうございます。
それでは、植田市町村税課長、お願いします。
○植田自治税務局市町村税課長
14ページ目に非課税限度額の計算の資料がございますけれども、注4のところに、
基本額及び加算額に級地区分に応じて率を乗じた額を基準として条例で設定とされて
おりまして、先ほどおっしゃられました、生活保護を受けている方々がここの非課税
限度額に当たって課税されることが基本的にないような形に勘案して設定するという
形にしておりますので、この級地区分についても勘案したような制度になっていると
いうことでございます。
○中里会長
それでは、梶川特別委員、お願いいたします。
○梶川特別委員
今までの委員の方々の御意見とほとんど同じでございますけれども、一点だけ、働
き方改革の中のお話で、資料の10ページ目ですけれども、控除のお話が中心ではあっ
たのですが、そもそも所得区分の考え方の整理も議論をしていってもいいのかなとい
う気がいたしました。そこの裏返しで、給与所得控除であるとか、実額控除というか、
当然必要経費というお話が出てくるのですが、冒頭、佐藤委員がおっしゃったように、
所得という概念が、片方では収入であり、片方では利益という部分が、事業所得の場
合には当然利益という世界だと思いますけれども、本来的な意味の給与所得と事業所
得が完全にグラデーション化しているので、そちらの方の御議論もしていただいた上
で、所得による控除というくくり、各種所得による控除というのが3ページ目にある
のですけれども、どっちが先かみたいなところはあるのかなという気がいたしました。
それと、田中特別委員がおっしゃった法人と個人事業というところに関係して、実
務というか何とかの話になるのですが、法人で経費を取った上に給与所得を取るとい
うのは個人事業では考え得る方法論ではあるのですね。これは、言い方を変えると控
除が2回取れるみたいな、実額経費を取った上で給与にしてしまうということもない
ではない話になって、それが全体としての事業の収益から見ると、効率のいい手取り
に持っていくこともないではないので、その辺も、これだけグラデーション化して、
それが悪いということではなくて、本当にそれなりの法人事業としてしながら動かし
ていくということも当然あると思いますし、保険料が社会保険の方がいいねというこ
とで雇用に何とかできないかという話も、私などの専門職業なんかの場合には時々出
てきます。それから、雇用の方も、相当変形労働で、逆に個人事業に近いような労働
環境でもあまり問題にしないという業種もおありになると思うので、所得区分をどう
お考えになるかという話は、御議論いただければなという気はいたしました。
○中里会長
ありがとうございます。
林特別委員、お願いします。
○林特別委員
先ほどの質問の続きで、総務省の資料の14ページ目の注4ですけれども、非課税限
度額は均等割と書いてあるのですが、所得割も同じという考えでよろしいでしょうか。
○中里会長
植田市町村税課長、お願いします。
○植田自治税務局市町村税課長
所得割についてはそのような制度にはなってございません。
○林特別委員
ということは、給付でよく問題になる非課税限度額というのは、均等割の方で決ま
っているという理解でよろしいですか。
○植田自治税務局市町村税課長
個人住民税非課税と単純に言われている場合は、均等割の方がより低いものですか
ら、これを基準にされているということでございます。
○林特別委員
了解いたしました。どうもありがとうございます。
○中里会長
今の点は実務的にも重要な点だと思いますが、クリアにしていただいてありがとう
ございます。
前回に続いて、本日も多くの委員の方からとても貴重な御意見、御指摘あるいは御
質問をいただき、大変充実した会議になったと思います。ありがとうございました。
本日の議事はこれで終了となります。
次回総会の開催日時や議題などは、決まり次第、改めて事務局から皆様に御連絡を
申し上げます。
なお、本日の会議の内容は、この後、私から記者会見で御紹介したいと思います。
お忙しい中、本当にどうもありがとうございました。
[閉会]
PDFファイルを表示(221223_4zen19kaigiji.pdf)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -