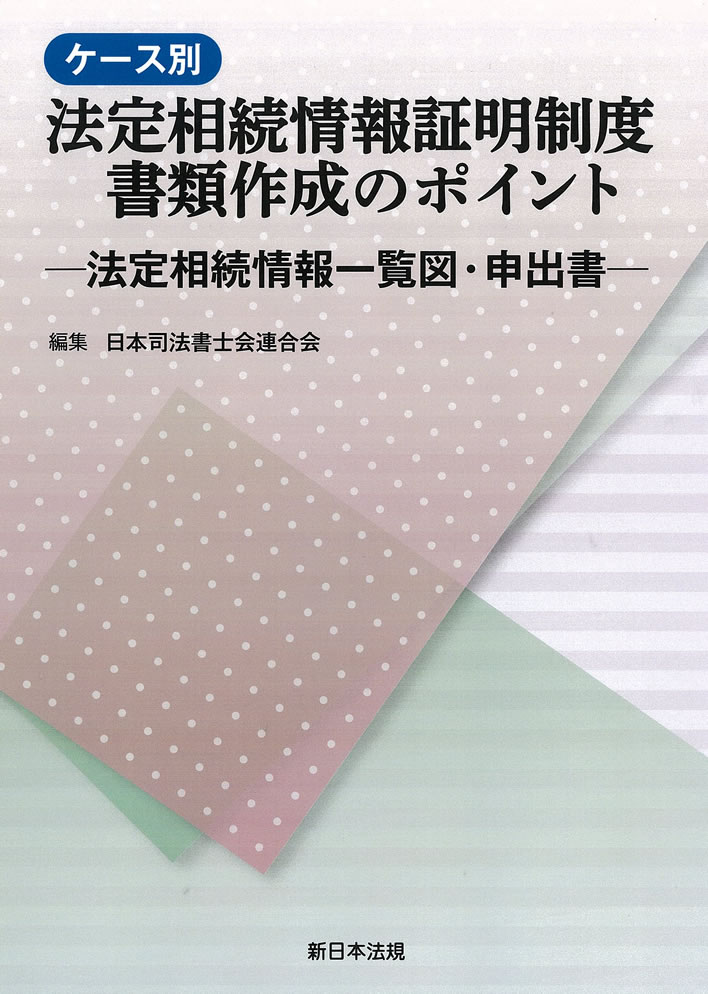解説記事2023年02月06日 巻頭特集 令和5年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント(2023年2月6日号・№965)
巻頭特集
令和5年度与党税制改正大綱の主要事項のポイント
−−激動の改正を振り返り、令和6年度税制改正を展望する
一般社団法人 日本経済団体連合会 経済基盤本部 秋本潤一郞
昨年末、岸田政権2度目となる税制改正大綱が取りまとめられた。同政権の重要な政策テーマである「成長と分配の好循環」の実現や、成長のエンジンと目されるスタートアップ振興等に即する形で、例年にも増して数々の重要改正事項があった。これに加えて、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置についても、与党大綱とりまとめまでの約1週間という短期間で大まかな方向性が示されたことも特筆に値すべきであろう。
本稿においては、主要改正事項を概観した上で、令和6年度税制改正以降を展望していくこととしたい。なお、本稿の記載事項は、2023年1月25日時点の情報に基づいており、今後法令等により変更が生じうる。全ては筆者個人の見解であり、所属組織を代表したものではないことを予めお断りしておく。
1.主要改正事項の解説
(1)法人税制
① 研究開発税制
令和2年度租税特別措置の適用実態調査報告書によれば、研究開発税制の適用額は約5,000億円に上り、税額控除系の租税特別措置の中でも、最大規模の減収額となっている。企業のイノベーション創出力の維持・強化という政策目標に照らして、制度が「適切な」インセンティブを有しているか否かを巡って、当局との間で毎々厳しい調整が行われている。
令和5年度税制改正では、一般型の控除上限や、控除率カーブのあり方を巡る「伝統的な」議論に加えて、オープンイノベーション(OI)型の裾野の拡大、ビジネスモデルの変化に即した試験研究費の範囲の見直しという新たな議論も行われた。
a)一般型−インセンティブ強化と制度の予見可能性のバランスが焦点に
まず、一般型の見直しに向けては、「メリハリ付け」をキーワードに議論が展開された。その意味するところは、試験研究費を頑張って増大させた企業には、より大きなインセンティブを、そうではない企業に対しては当該税制のインセンティブ付けの度合いを抑制するということである。昨年9月の経団連提言においては、インセンティブ機能の確保に向けて、令和3年度税制改正で創設された「コロナ特例」(一定の要件を満たす場合には、一般型の控除上限に+5%を加算する時限措置)について、要件を見直す形での延長を求めていた。しかしながら、実際の適用件数が少ないこと、そして「メリハリ付け」の観点を踏まえて、期限通り廃止されることとなった。
その代わりとして、一般型の控除上限について、増減試験研究費割合に応じて、20%〜30%のレンジで変動する仕組みが新たに導入されることとなった(変動型の控除上限は3年間の時限措置)。増減試験研究費割合は、ある事業年度の試験研究費の当該事業年度の前の3事業年度の試験研究費の平均額(比較試験研究費)からの増減率を指す。このため、「メリハリ付け」の趣旨に照らして、試験研究費を増加させ続けることが当該税制の最大限の恩恵を受けるための最適な企業行動となる。裏を返せば、増減試験研究費割合の分母となる比較試験研究費が既に巨額である場合や、経営環境の変化等の一時的な要因により試験研究費が減少する場合には、控除上限そのものにも下押し圧力がかかる。これは、研究開発税制を所与として、どのように複数年度に渡って研究開発投資を行うのかという企業判断にも影響を与えかねないものである。このため、インセンティブ設計のあり方と納税者側の制度の予見可能性のバランスをどのように確保するかが最大の焦点となった。
結果として、増減試験研究費割合が−4%から+4%のレンジであれば、これまでと同様に25%の控除上限が維持される仕上がりとなった(図表1参照)。企業サイドからは、増減試験研究費割合の閾値は±5%程度が望ましいのではないかという声も聞かれたが、政策意図をより色濃く打ち出したいという当局の意向が優先されることとなった。なお、増減試験研究費割合が+12%の場合に控除上限30%に達するという設計は、後述の通り、控除率カーブの屈曲点との整合性が図られたためである。なお、売上高試験研究費割合が10%超の場合における控除上限の最大10%上乗せは、令和7年度末まで3年間延長となった。同上乗せ措置と変動型の控除上限のいずれか大きい方が適用される。
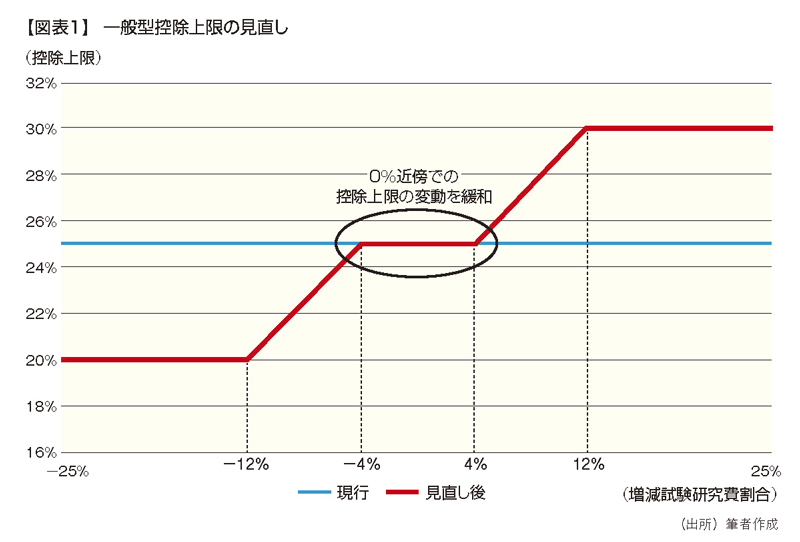
一般型の控除率カーブについては、「増減試験研究費割合0%⇒控除率8.5%」という「基準点」の維持、そして控除率の上限を10%から14%に引き上げる特例措置の延長(令和7年度末までの時限措置)が行われた上で、下限の引き下げ及び傾きを急にする見直しが行われた。調整過程では、企業サイドからは「基準点」の維持を前提としつつ、傾きの急峻化を可能な限り緩やかなものとすべきという意見が強かった。上述の変動型の控除上限と同様に増減試験研究費割合の0%近傍での変動による影響を最小化することが念頭にあったためである。結果として、財源規模との見合いで、図表2の通りの見直しが行われた。なお、屈曲点の閾値となる「増減試験研究費割合12%」は、「第6期科学技術・イノベーション基本計画」における民間の研究開発投資の総額目標の達成に必要な伸び率とみられる。
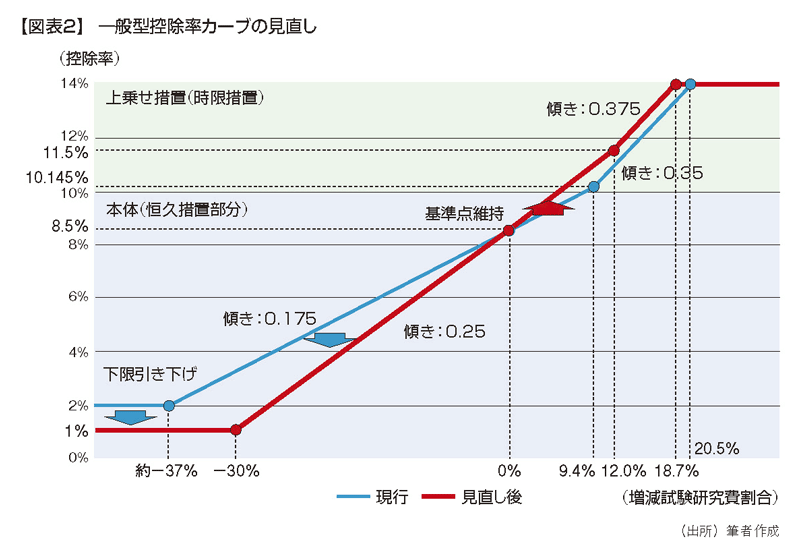
b)OI型−イノベーションの担い手の裾野の拡大が図られる
OI型は、大学や、スタートアップ等との共同研究・委託試験研究等を行う場合に、一般型よりも高い控除率が適用される。例えば、相手方がいわゆるスタートアップ等(新事業開拓事業者等)である場合には、税額控除率20%が適用される。しかしながら、「新事業開拓事業者等」は、産業競争力強化法により経済産業大臣が認定したベンチャーファンドの出資先や、一定の要件を満たす大学発ベンチャー企業等に範囲が限定されている。経済産業省によれば、該当するスタートアップ等は約200社である。
こうした状況を踏まえ、OI型の相手方としてのスタートアップ等を再定義するとともに控除率を25%に引き上げることとなった。一定の要件を満たし、かつ経済産業省の証明書が交付された、研究開発型スタートアップに定義が拡張されることとなった。その要件とは、①設立15年未満(設立10年以上の場合は営業赤字)、②売上高研究開発費割合10%以上、③スタートアップに対する投資を目的とする投資事業有限責任組合又は研究開発法人の出資先、④未上場の株式会社かつ他の会社の子会社ではないもの等である。要件設定に際しては、OI型を適用しようとする企業側の不正行為等を防止するという当局側の意図があったと考えられる。この見直しの下で、2,000社超がスタートアップ等に該当することとなるが(経産省調べ)、OI型の適用が進むか否かは今後の要注目事項であろう。
また、「人への投資」の文脈から、新たな類型が追加された。試験研究に際し、一定の「博士号取得者」及び「外部研究者」に支出する人件費(工業化研究を除く)の「『試験研究を行う者』の人件費」に占める割合が対前年度比で3%以上増加する場合に、同人件費の20%を税額控除できることとなった。具体的な要件は、図表3の通りとなる。一定の「博士号取得者」等の試験研究費における人件費の増加を単純に要求している訳ではないことが実務上の適用可否のポイントとなるだろう。
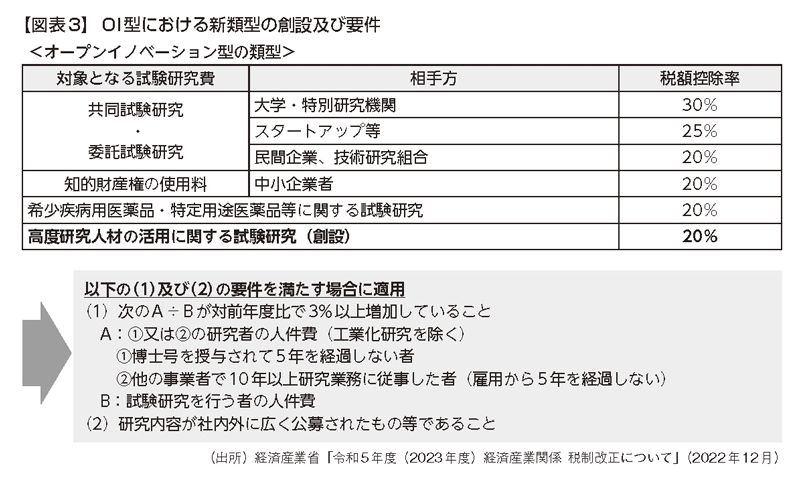
c)試験研究費の定義等−ビジネスモデルの変革に即した形へ
まず、新たな「サービス開発」に際し、現行制度ではデータの収集・分析、サービスの設計・適用の各ステップにおいて充足すべき行為が定められている。このうち、一連の工程の入り口となるデータ収集は、「大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によつて行われた情報の収集又はその方法によつて収集された情報の取得」(措令27の4⑥一)とされ、既存データの利用自体は想定されていない。このため、既存のビックデータを利活用して行う「サービス開発」も対象に追加されることとなった。
次に、試験研究費の適正化の文脈から、性能向上を目的としない開発業務のうち、考案されたデザインに基づく設計・試作は対象外とされることとなった。
② スタートアップ振興税制
経団連は、必要な税制措置のあり方を含む「スタートアップ躍進ビジョン」(2022年3月)をとりまとめた。これを受ける形で政府でも検討が進められ、「スタートアップ育成5か年計画」(2022年11月28日)が策定され、今回の税制改正に向けても大きな追い風となった。以降各税制措置の内容をごく簡潔に見ていくこととしたい。
a)オープンイノベーション促進税制の拡充
スタートアップの出口戦略としてのM&Aを促進することを視野に入れて、M&A時の発行済株式の取得に対しても所得控除25%を講じる拡充が行われる。同税制の創設時には、単に創業者を利することになるとの懸念から、新規発行株式に対象を限定するとされてきただけに、大胆な見直しが講じられることとなった。もっとも、拡充の趣旨を踏まえ、発行済み株式は50%超の取得時に限定されることに加えて、海外スタートアップも対象からは除外される。これに加えて、5年以内に図表4の成長投資・事業成長の要件を充足しなかった場合等は、所得控除分を一括で取り戻すという制約も加えられている。
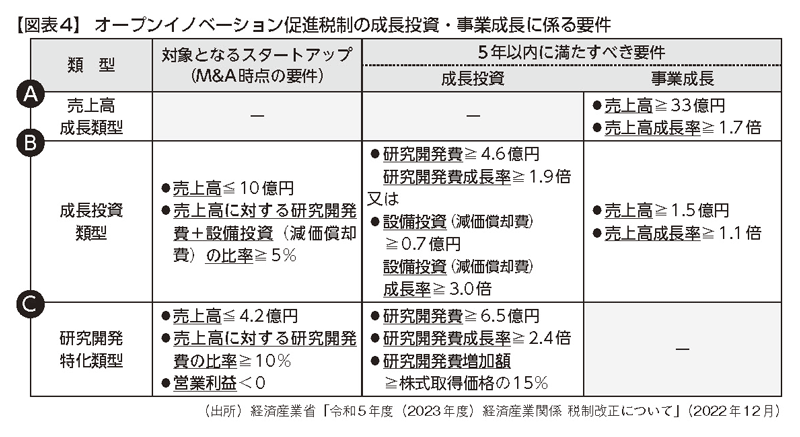
b)スピンオフ税制の拡充
元親会社に一部持分を残すパーシャルスピンオフについても、一定の要件を満たせば、再編時の譲渡損益や、配当に対する課税を対象外とする1年限りの租税特別措置が講じられることとなった(図表5参照)。組織再編税制における独立性の観点から、持分一部残しがどのように説明され得るかが論点となり、与党税調の「○×(マルバツ)等審議」の場面では、当初厳しい判定が行われていた模様である。結果として、1年限りの租税特別措置として各種要件付きでの異例の決着となった。令和6年度税制改正においては、企業側のニーズ等も踏まえつつ、単純延長を要望するのか、それとも本則化にチャレンジするかが1つの焦点となるだろう。
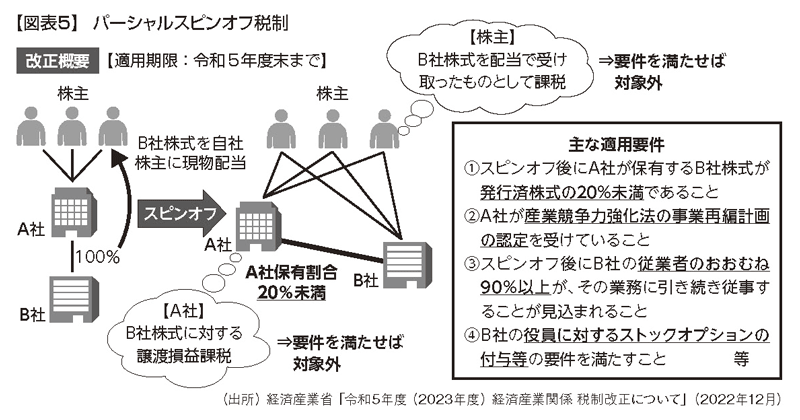
c)ストックオプション税制の拡充
スタートアップの人材獲得を一層後押しする観点から、設立から5年未満の未上場企業においては、権利行使期間は付与決議から2〜15年へと延長された。また、適格ストックオプションを行使して取得した株式は金融商品取引業者に保管委託することが要件となっているが、未上場株の保管委託先が極めて限定的という声も上がっていた。これを踏まえ、保管委託の運用の見直しを行い、利便性の向上が行われる。
d)自己保有・自己発行の暗号資産に係る期末時価評価課税の見直し
内国法人が有する暗号資産は、期末時価評価課税の対象となるため、ブロックチェーン関連企業の海外流出が一部から提起された。これを受けて、自己が発行した暗号資産で継続して保有しているもののうち、一定の要件を満たすものについては、期末時価評価課税の対象外とすることとされた。なお、資金調達のために第三者に売却した暗号資産は引き続き時価評価課税の対象であり、令和6年度税制改正以降でも論点となると考えられる。
e)エンジェル税制の拡充・手続きの簡素化
事業化前の段階における個人によるエンジェル投資の重要性が高まっていること、そしてわが国における起業促進の必要性等を背景として、エンジェル税制の抜本的な拡充が行われた。すなわち、20億円を上限として、事業化前段階のスタートアップへの投資を課税繰延から非課税措置にするとともに、起業家による会社設立のための出資も非課税措置とすることとされた。
この他、エンジェル投資の裾野を拡大する観点から、申請手続きの簡素化も行われた。
(2)自動車関係諸税−エコカー減税等は本年末まで据え置き
エコカー減税等の各種措置の適用期限が到来しようとする中、厳しい物価高に加えて、半導体等関連製品の供給制約を背景とした納期の長期化という消費者サイドの負担感への対応が大きな論点となった。
結果として、自動車重量税のエコカー減税、自動車税・軽自動車税の環境性能割について、「異例の措置」として現行制度は2023年末までの据え置きとなった。クリーンディーゼル車に対する現行の取扱いも同年末まで延長される。据え置き期間後は、燃費性能の向上等を踏まえつつ、現行の優遇規模を維持する形で、2025年度までの見直しを実施することとされた(図表6参照)。
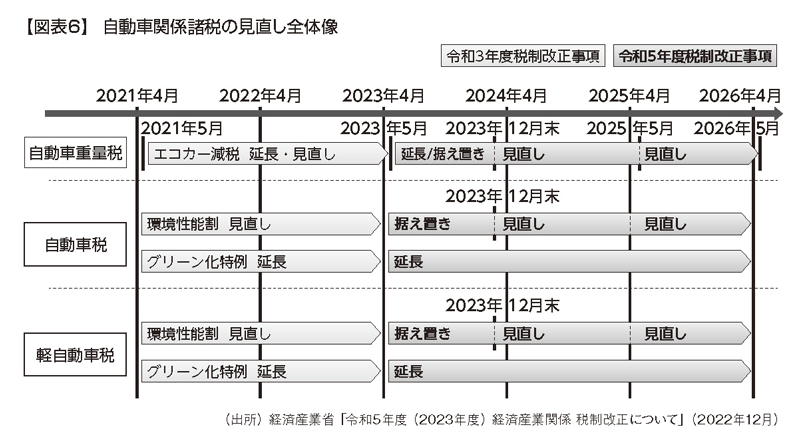
(3)「資産所得倍増」に向けた税制措置等
令和5年度税制改正では、「資産所得倍増プラン」(2022年11月)を受ける形で、図表7の通り、NISA制度の抜本的拡充及び恒久化が図られた。

報道自体はあまり行われなかったものの、申告納税者の負担率に係る「1億円の壁」問題にも一定の決着が図られた。すなわち、令和7年分の所得からの適用に向けて、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化のための措置が設けられる。具体的には、①合計所得金額から3.3億円を控除した金額に22.5%を乗じた金額が②通常の所得税額を上回る場合に限り、差額分を申告納税することとされた。この結果、追加負担が生じる平均的な所得水準は約30億円とみられる。
この他、従前より政府税制調査会等で指摘がなされてきた通り、資産移転の時期の選択により中立的な税制を構築する観点から、相続時精算課税や、暦年課税に係る見直し等が行われた。
(4)国際課税−いよいよグローバル・ミニマム課税が国内法制化へ
OECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」では、経済のデジタル化に伴う課税上の課題について検討が行われてきた。その対応策の「第1の柱(市場国への新たな課税権の配分)」については、2023年前半の署名開放に向けて、引き続き制度の詳細について議論が継続中である。その一方で、「第2の柱(グローバル・ミニマム課税)」については、実施に向けて、EUをはじめとして世界各国で国内法制化が進捗している。
こうした中、日本でも、令和5年度税制改正でグローバル・ミニマム課税のうち所得合算ルール(IIR:Income Inclusion Rule)を導入することとなった。
IIRは、年間総収入金額が7.5億ユーロ(約1,100億円)以上の多国籍企業を対象とし、有形資産や給与に着目した一定の適用除外後の所得について各国・地域(法域)ごとに最低税率15%以上の課税を確保する仕組みである。具体的には、子会社所在法域毎に計算した子会社(複数の場合は、その合計)の実効税率(会計上の数値を基礎に所定の調整計算を施し算出)がミニマム税率15%に満たない場合には、ミニマム税率に達するまでの税額(トップアップ税額)を親会社所在法域で課税するものである。法人税率の引き下げを巡る各国の底辺への競争を防止するとともに、企業間の競争条件の公平化を企図している。
なお、グローバル・ミニマム課税のうち、軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)と国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)は、令和6年度改正以降の課題とされている。
今回の税制改正大綱では、IIRの内容が【付記】として示されている。また、IIRと制度趣旨が異なるとは言え、既存の外国子会社合算税制(CFC税制)についてもIIR導入に伴う事務負担の軽減の観点から、一部事務負担の見直しが行われることとなった。以降、IIRの内容及びCFC税制の見直し事項を概観する。
① IIR概要
IIRのトップアップ税額は、国税として「各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税」(仮称)及び「特定基準法人税額に対する地方法人税」(仮称)として創設される。外国子会社の所得をもとに課税を行うため、地方自治体の行政サービスとの応益関係はなく、法人住民税や法人事業税による課税は行われない。
IIRは、国際合意に基づく恒久措置であることも踏まえ、租税特別措置法ではなく、法人税法や地方法人税法の本則で導入されると見られ、通常の法人税・地方法人税とは区別される。
a)各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)
ⅰ)納税義務者
内国法人は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)を納める義務がある。ただし、公共法人については、その義務がない。
ⅱ)課税の範囲
特定多国籍企業グループ等(企業グループ等のうち、各対象会計年度の直前の4対象会計年度のうち2以上の対象会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ相当額以上であるもの)に属する内国法人に対して、各対象会計年度の国際最低課税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)が課される。
ⅲ)税額の計算
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の額は、各対象会計年度の国際最低課税額(課税標準)に100分の90.7の税率を乗じて計算した金額とされる。なお、法人住民税の計算の基礎となる法人税額には、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の額は含まない。
なお、税率は、トップアップ税額につき、現行の税率を基に法人税による税額と地方法人税による税額が907:93の比率となるよう制度設計されている。
ⅳ)申告及び納付等
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に行うものとされる。ただし、当該対象会計年度の国際最低課税額(課税標準)がない場合は、当該申告を要しない。
一定の場合とは、IIRの適用初年度を指す。日本では、IIRは令和6年度から施行されることから、3月決算法人の場合、最初のIIRの申告・納付は、2026年9月となる。
なお、「(課税標準)がない場合は、当該申告は要しない」とされているが、下記c)の「情報申告制度」による申告義務は免れない。電子申告の特例等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とされる。
ⅴ)その他
質問検査、罰則等については、各事業年度の所得に対する法人税と同様とされる。
なお、OECDの「セーフハーバー(SH)及び罰則緩和」の文書では、経過期間(2026年(令和8年)12月31日以前に開始し、かつ、2028年(令和10年)6月30日以前に終了する対象会計年度)における罰則緩和について記載されている。具体的には、「税務当局は、納税者がグローバル・ミニマム課税の正確な適用を保証するため『合理的な手段』をとったと考える場合には、経過期間においては情報申告の提出に関連し、罰則や制裁は課さないこととすべきである」とされている。
導入当初は納税者としても脱税や租税回避等の意図なく、記入誤りや、計算間違いをする可能性があること等に配慮した記載と考えられる。後述のb)、c)における「罰則」とも合わせて、OECD文書の意図がどのように執行上配慮されるかが今後の要注目事項となる。
ⅵ)適用関係
各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度から適用される。
b)特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)
ⅰ)課税の対象
特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各課税対象会計年度の特定基準法人税額には、特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)が課される。
ⅱ)税額の計算
特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)の額は、各課税対象会計年度の特定基準法人税額(課税標準)に907分の93の税率を乗じて計算した金額とされる。特定基準法人税額は、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の額とし、附帯税の額を除いたものである。
ⅲ)申告及び納付等
特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)の申告及び納付は、各課税対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に行う。電子申告の特例等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様である。
ⅳ)その他
質問検査、罰則等については、基準法人税額に対する地方法人税と同様となる。
ⅴ)適用関係
特定基準法人税額に対する地方法人税(仮称)は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する課税対象会計年度から適用される。
c)情報申告制度の創設
特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在法域毎の法域別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必要な事項等(特定多国籍企業グループ等報告事項等)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月(一定の場合には、1年6月)以内に、電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、納税地の所轄税務署長に提供しなければならない。
また、特定多国籍企業グループ等報告事項等の不提供及び虚偽報告に対する罰則が設けられる。
この改正は、内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)について適用される。
d)今後予想される動き
2022年12月、OECDから「セーフハーバー(SH)及び罰則緩和」、「情報申告」、「税の安定性」と題する3文書が公表された。
まず、「SH及び罰則の緩和」の文書では、経過措置としてのCbCRを利用したセーフハーバーの詳細が明らかとなった。すなわち、2026年(令和8年)12月31日以前に開始し、かつ、2028年(令和10年)6月30日以前に終了する対象会計年度が対象となる。①デミニマス要件、②簡素な実効税率要件、③通常利益要件のいずれかを満たした法域における多国籍企業グループのトップアップ税額は零となる。セーフハーバーの適用有無は、納税者の選択制であるが、選択しない場合、後続年度では適用ができない。
上記①〜③については、令和5年度税制改正事項として、法律・政省令に盛り込まれる予定であり、今後、具体的な条文を確認する必要がある。
次に、「情報申告」は公開市中協議の対象となっており、情報申告において必要となるデータが一覧化されている。各子会社等についての詳細な情報提供が求められており、事務負担軽減の観点から、記入項目の削減等は可能か否かが論点となっている。
最後に、「税の安定性」も公開市中協議の対象となっている。グローバル・ミニマム課税制度は、租税条約に基づく措置ではなく、各国が国内法として導入する。このため、各国によるルール等の解釈の相違があれば、同一の法域に所在する子会社に対して、異なる国からIIRやUTPRが重複して適用される可能性がある。これを受けて、紛争予防・解決を通じて税の安定性を向上させる必要性が指摘されている。文書では、紛争予防のツール、紛争の解決メカニズム等に係るオプションが示されており、国内法や、執行面への反映についても注目が必要である。
上記の他、グローバル・ミニマム課税の執行を補助するための行政ガイダンスが現在議論中である。準備が整ったものから順次公表されると見込まれ、例えばCFC税額のプッシュ・ダウンの取り扱い等、企業の実務関係者から関心の高い論点について一定の方向性が示されるとみられる。
② 外国子会社合算税制
前述の通り、グローバル・ミニマム課税の導入に伴う追加的な事務負担の増加に加えて、CFC税制そのものに係る事務負担自体が既に膨大であるという企業側の切実な声を受ける形で、一部事務負担の簡素化が実現した。
a)判定対象となる特定外国関係会社の絞り込み
平成29年度税制改正では、日本の法人実効税率29.74%を参照しつつ、租税負担割合30%を適用免除基準とした。これにより、租税負担割合20%以上30%未満の判定対象となる外国関係会社が大幅に増加した。しかしながら、そのうち合算税額が発生している企業数及び合算税額の規模は決して大きいものではないという企業側の声が強まっていた。
こうした背景を踏まえ、連結財務諸表の数字等を用いた適用免除基準のあり方も検討の俎上に上がったが、租税負担割合30%を27%に引き下げることで決着した。27%の閾値は、図表8の通り、どのような税率の下で真に租税回避へのインセンティブが生じるかを計算した結果と考えられる。
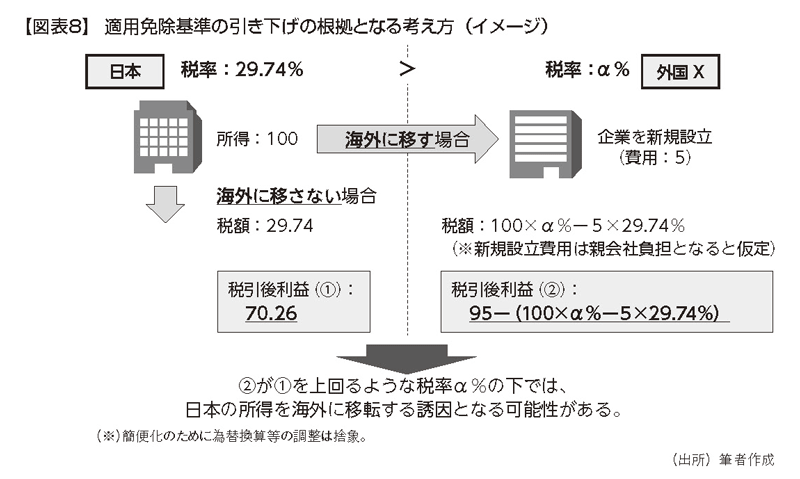
実質的には、租税負担割合27%以上の特定外国関係会社が適用免除となることから、例えば米国、ドイツ等に所在するペーパーカンパニー等は判定対象から除外され、事務負担の一部簡素化に資することが期待される。
b)添付対象となる外国関係会社の範囲の見直し
各種書類の添付に要する事務負担を緩和する観点で、次に掲げる部分対象外国関係会社については、書類の添付義務ではなく保存義務を課すという見直しが行われた(図表9参照)。
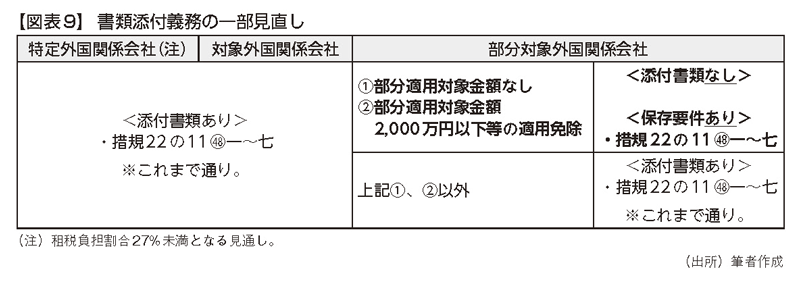
1.部分適用対象金額がない部分対象外国関係会社
2.部分適用対象金額が2,000万円以下であること等の要件を満たすことにより本制度が適用されない部分対象外国関係会社
c)添付対象となる書類の一部見直し
申告書に添付することとされている外国関係会社に関する書類(外国関係会社の株式等を直接又は間接に保有する者(株主等)に関する事項を記載するものに限る。)の記載事項について、その書類に代えてその外国関係会社と株主等との関係を系統的に示した図にその記載事項の全部又は一部を記載することができることとなった。これにより、例えば出資関係図(図表10、11はイメージ)を既に作成している場合には、申告時に必要な添付資料に代替して提出することが可能となり、一定の事務負担軽減に資することが期待される。
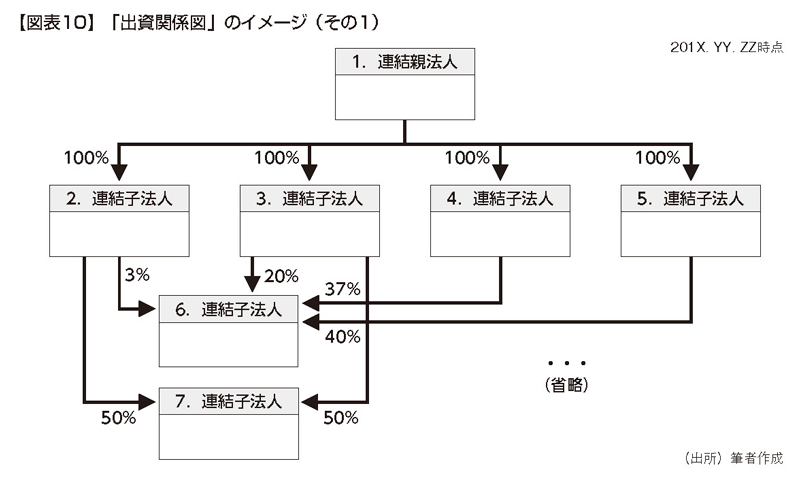
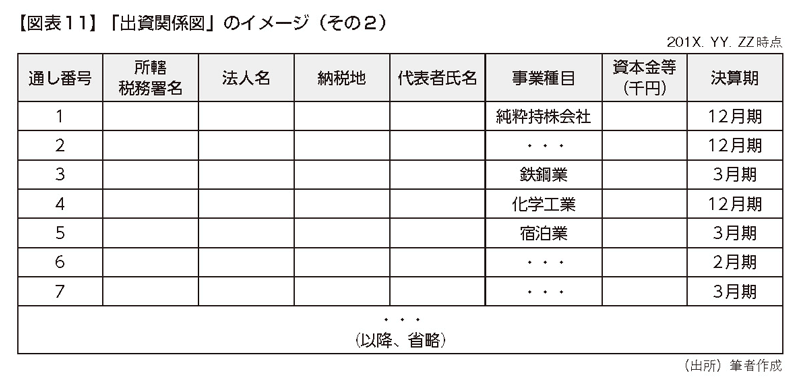
d)その他
これらの見直しに併せて、居住者に係る外国子会社合算税制、特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例等の関連制度についても所要の見直しが行われる。
また、地方税について、法人住民税及び法人事業税について、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例等の見直しに関する国税の取り扱いに準じて所要の措置が講じられる。
e)適用時期
内国法人の令和6年4月1日以後に開始する事業年度について適用が行われる見通しである。令和5年度からの適用開始ではないのは、CFC税制の見直しは、「第2の柱」の導入により、追加的な事務負担が生じることを前提として行うものであることから、見直し後のCFC税制の適用自体も「第2の柱」の施行時期との整合性の確保が意識されたと見られる。「外国法人」ではなく「内国法人」とされたのは、「第2の柱」の下でトップアップ税額を負うのは内国法人であり、事務負担軽減効果の早めの発現を期したものと解釈される。なお、見直し後の制度の全体像は図表12の通りである。
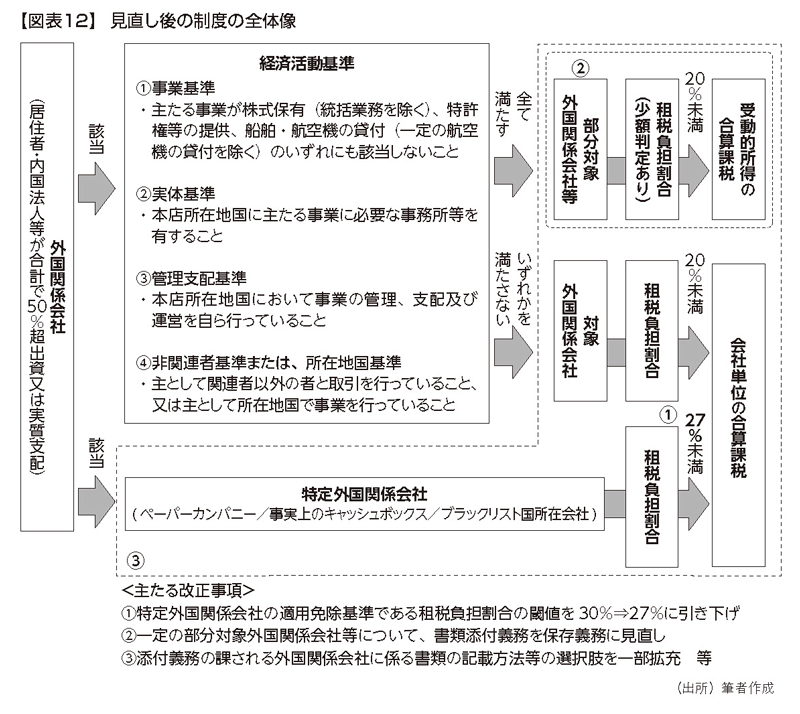
2.防衛力強化に向けた財源としての税制措置−「法人恒久増税」へ
ロシアによるウクライナ侵攻や、中台関係の緊張の高まり、そして北朝鮮による挑発行為の頻発化等、わが国を取り巻く安全保障環境は厳しさを増している。政府・与党サイドの危機感は、2022年6月閣議決定の「骨太方針2022」で早くも鮮明に打ち出され、防衛費を対GDP比2%以上とするという絵姿の下での財源確保のあり方が最大の論点であった。昨年夏の時点では、防衛費増分の全てではないにせよ、税制措置の「出番」が出てくるのであれば、法人税負担自体は不可避であり、その規模感がどの程度に落ち着くのかが企業・経済界の一大関心事だった。
巨額の歳出増加局面における臨時の税制措置について、歴史を紐解くと、湾岸戦争時(平成3年)の法人臨時特別税、石油臨時特別税、そして平成23年の東日本大震災後の復興特別法人税・所得税等を挙げることができる。これらの臨時措置は、期限の定めがあり、かつその使途が明確に規定されたものであった。法人税については、いずれも税額に一定の率を乗じる等の付加税方式が採られた。
今回の防衛力強化自体は、基本的には恒久的性質を有するものであるが、仮に法人税負担が生じるのであれば、過去例にならった付加税方式が基本となるということが関係者の共通の見立てだった。もっとも、昨秋の段階では、防衛という「公共財」に国民全員が裨益することから、税制措置による負担は、各種税目あるいは法人税においても、「薄く、広く、偏らず」を基本とすべきと考えられていた。
こうした中、政府は、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」を設置し、わが国防衛力の5年以内の抜本的な強化に向けた基本的な考え方を提示した。同会議の報告書(2022年11月22日)では、財源の確保についても紙幅が割かれた。具体の税目への言及こそなされなかったものの、「令和5年度予算編成・税制改正において成案を得て、具体的な措置を速やかに実行に移すべき」との一文がその後の政府・与党の検討のピン止めを果たすこととなった。
更に、政府与党政策懇談会の場で、岸田総理から防衛力整備計画の規模感の想定、そして税制措置を含む財源確保の方針が表明され(2022年12月8日)、約1週間程度の極めて集中的な与党での検討プロセスの「号砲」となった。総理発言には、「個人の所得税の負担が増加するような措置は行わない」という文言も含まれ、候補となる税目は自ずと絞り込まれた。
その後、類例を見ないスピードで与党大綱の記載に決着した。法人税に着目すると、税額にして500万円、所得にして約2,400万円(=120万円÷中小法人等の軽減税率15%+(500万円−120万円)/法人税率(本則)23.2%)以下の企業は付加税の対象外となった。これは、国税庁「会社標本調査(令和2年度分)」に基づけば、中小企業のうち欠損法人を含めて約9割の企業に付加税が課されないことを意味する。また、所得税については、復興特別所得税の税率1%分の引き下げと課税期間の延長を行った上で、税率引き下げ分に相当する付加税が課される(図表13参照)。
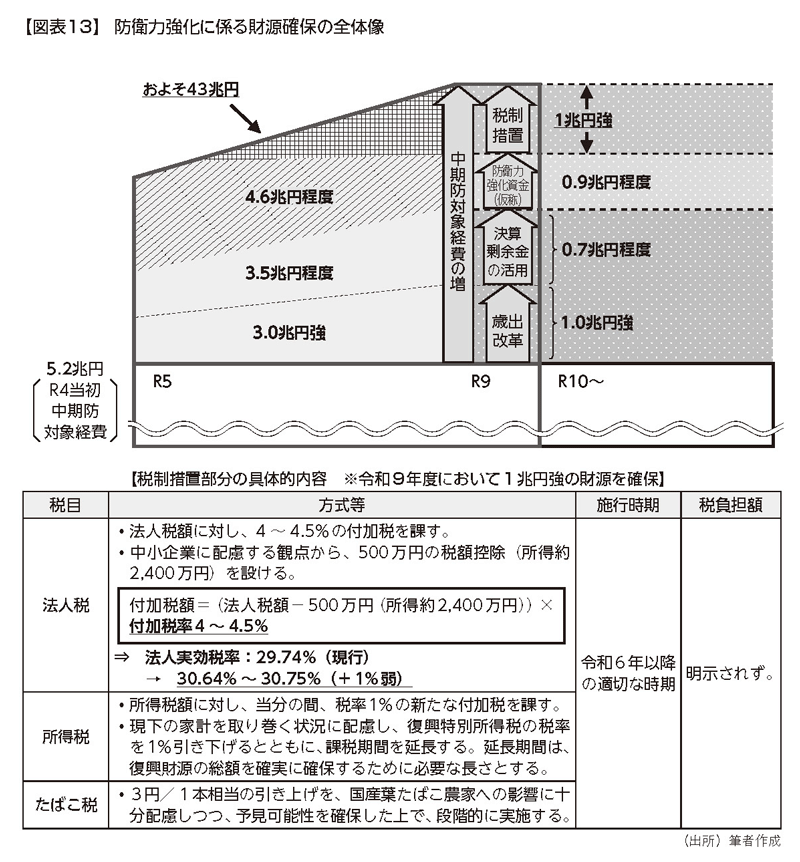
与党大綱には明記されなかったものの、各種報道によれば、法人税、所得税、たばこ税による負担額の比率は、約6:2:2と言われている。法人税による負担額が過半を占め、かつその主体は大企業という結果となった。令和9年度時点での税制措置による負担額を約1兆円と仮定すれば、約6,000〜7,000億円が法人税付加税により賄われなければいけない。なお、法人税収は令和5年度概算額で14.6兆円と見込まれているが、与党大綱に明記された税率を簡易的に乗じると、約5,800〜約6,600億円となり所要額との若干の乖離が生まれる。今後の制度設計に着目する必要があるが、その要因としては、実際の税収額は、所得税額控除及び外国税額控除の後の数字であることが考えられる。上述の「会社標本調査」を参照すると、所得税額控除の合計額は約4兆円、外国税額控除は約4,000億円にのぼる。図表14の通り、復興特別法人税や、地方法人税の基準法人税を念頭に制度設計が検討されているのだろう(なお、使途秘匿金課税、土地重課、留保金課税を含むという意味で、地方法人税の基準法人税額は復興特別法人税よりも「広い」)。「令和6年以降の適切な時期」とされた施行時期を含めて、制度の詳細は今後の政治プロセスに委ねられることとなる。
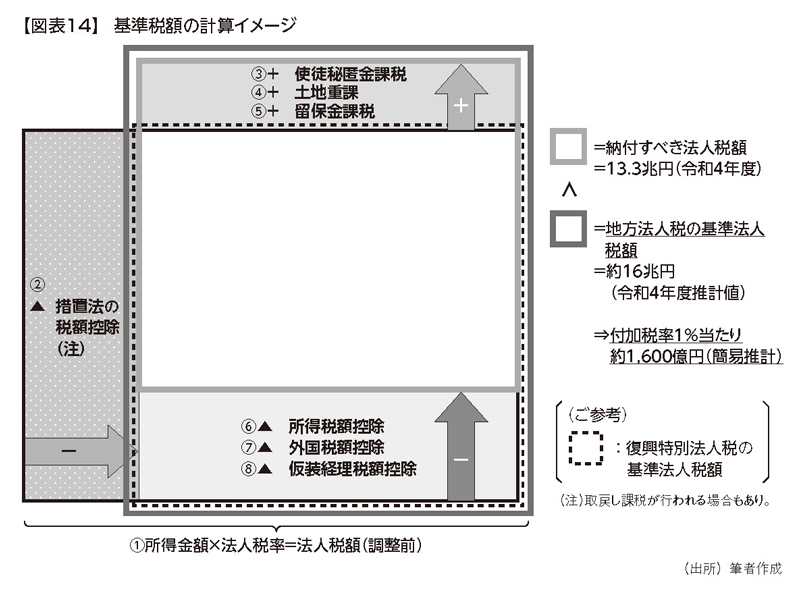
3.令和6年度税制改正に向けて
令和6年度税制改正を展望するに際して、経済環境の変化について若干の考察を述べたい。わが国を含む世界は、新型コロナウイルス感染症との共存、その脅威の克服に向けて、着実に歩みを進めている。他方で、ロシアによるウクライナ侵攻の停止は本稿執筆時点においても依然として見通しがたく、国際政治経済秩序の大きな揺らぎがわが国の家計や、企業の経済活動に影を落とし続ける可能性は大きい。とりわけ、歴史的な物価上昇の波が押し寄せる中では、企業の大胆な賃金引上げと投資こそがわが国経済を下支えする上での不可欠な取り組みとなることは言うまでもない。他方で、それらが経済の好転に本格的な影響を及ぼすまでには一定の期間を要しうることも忘れてはならないと考える。令和6年度税制改正においては、企業が社会的な責務としての賃金引上げや、投資の拡大を続けていく上でも、相応の対応を講じていくことが求められるだろう。
ここで、令和5年度末で期限切れの租税特別措置を概観すると、賃上げ促進税制、カーボンニュートラル(CN)投資促進税制、オープンイノベーション促進税制等を挙げることができる。前章で述べた防衛力強化のための法人付加税の開始が令和6年度となるか否かは不詳であるものの、賃上げや、投資を積極的に行う大企業に対する増税分を一定程度相殺できるような仕組みを講じることが必要となるだろう。
とりわけ、CN投資促進税制は、グリーントランスフォーメーション(GX)の推進という現政権の目標とも整合的であることに加えて、企業からの拡充要望の強い税制措置である。昨年9月の経団連提言では、次の通り要望している。
既存の需要開拓商品、生産工程効率化等設備に係る類型について、例えば、各種素材関係設備の追加を行う等、対象設備の拡充を検討すべきである。併せて、新たな類型を設けて、CNへの貢献度合いを踏まえて、当該税制の対象に他の取得資産を加えることも検討すべきである。例えば、電気自動車に係る充電設備及びその他構成機器関連設備、蓄電池、鉄道車両、航空機等を追加することが考えられる。
産業競争力強化法の改正も見込まれる中、CN投資促進税制の延長・拡充が焦点の1つとなるだろう。GXの推進という観点からは、関連する投資により取得した償却資産に係る固定資産税について減免措置を講じることも一案である。
「人への投資」という文脈での対応も注目すべきポイントの1つだろう。令和5年度税制改正においても、研究開発税制OI型における新類型の創設の他、教育への企業の積極的な関与を促進するための税制措置の新設、そしてDX投資促進税制における人材育成・確保等に資する要件の見直しが行われたところである。生産性を高め、イノベーションの創出の起爆剤となる人材育成・確保は引き続き社会的な要請も高いことから、企業側のニーズ等も踏まえた対応が今後も必要不可欠である。
令和6年度以降も見据えれば、与党大綱検討事項に記載の通り、自動車関係諸税の中長期的なあり方についても、検討が行われることとなるだろう。モビリティ産業の裾野の広さや、CASEに代表される環境変化に対応するインフラの維持管理・機能強化等に即した形で、「次のエコカー減税の期限到来時までに検討を進める」ことが記載されている。経団連は、昨年モビリティ委員会を設置しており、今後のモビリティ産業のデザインを含めて、検討を本格化することとなるだろう。
これまでは、企業活動の後押しを念頭に置いた税制措置のあり方について私見を書き連ねたが、同時に企業はルールに則って、適正な税負担を負わなければいけない。与党大綱においては、令和6年度以降の企業の税負担等の適正化に向けても、いくつかの「頭出し」が行われている。
1つ目は、法人事業税の外形標準課税のあり方である。総務省の「地方法人課税に関する検討会」の第3回会合(2022年10月7日)資料では、外形標準課税の対象企業数の減少要因についての分析がなされている。同資料では、資本の減資額が資本剰余金に振り替えられている可能性があること、そして分社化・ホールディングス化に伴い、外形標準課税の対象範囲が実質的に縮小する事例が取り上げられている。これらを踏まえた見直しに際しては、法人の規模を表す指標のあり方の検討に加えて、グループの範囲と外形標準課税の対象のバランスに係る精緻な検討が求められる。企業・経済界からは、外形標準課税付加価値割の計算等の複雑さがかねてより指摘されていることから、事務負担にも配慮した形での議論が必要不可欠となるだろう。
2つ目は、国境を越えた役務の提供に係る消費課税のあり方である。デジタルプラットフォーム運営事業者が仲介する、国外サプライヤーのオンラインゲーム等の販売に係る消費課税のあり方が焦点となる。
3つ目は、「出産・子育て応援交付金」の安定財源確保である。同交付金は、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と妊娠・出産時の10万円の経済的支援を一体的に行うものであり、令和6年度以降の継続実施が焦点となっている。政治状況に応じては検討できる選択肢は限定されることとなるが、動向を注視することが必要だろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.