解説記事2023年02月27日 巻頭特集 鼎談 令和5年度税制改正の背景と今後の税制のあり方(2023年2月27日号・№968)
巻頭特集
鼎談
令和5年度税制改正の背景と今後の税制のあり方
自由民主党 税制調査会会長 宮沢洋一
日本経済団体連合会 経済基盤本部長 小畑良晴
公認会計士・税理士 緑川正博
令和5年度税制改正は、防衛費財源を確保するため法人税が約30年前の法人臨時特別税以来の純然たる増税になるなど、税制改正史に1ページを刻むこととなった。そこで本誌では、税務会計の専門家であるとともにビジネス界でも幅広く活躍する公認会計士の緑川正博氏を進行役として、難しい税制改正の舵取り役を務めた自民党の宮沢洋一 税制調査会会長、そのカウンターパートとなった経団連・経済基盤本部長の小畑良晴氏に、それぞれの視点から令和5年度税制改正、さらには今後の税制のあり方について語っていただいた。
本鼎談は、防衛費財源決定の舞台裏、「税率4~4.5%、令和6年以降の適切な時期に施行する」という形で不確定要素を残したまま決着した付加税の行方、日本経済の鍵を握る物価上昇及び賃上げ、人的資本投資とそれを後押しする高専等の設立準備法人への寄附金の全額損金算入制度、こども予算倍増の財源といったマクロ的なテーマから、令和5年度税制改正で小規模事業者に対する複数の負担軽減措置が講じられたインボイス制度のさらなる見直しの可能性、相続税におけるマンションの評価方法の適正化、外形標準課税の見直しの方向性、ふるさと納税の行方など税理士等の実務家にとって関心が高いテーマに至るまで、多岐な話題について税制改正のキーパーソンの本音を聞く貴重な機会となった。(本文中、敬称略)
防衛財源
本格的な議論は12月第1週からという“短期決戦”に
緑川:まずは、令和5年度税制改正の中で最も注目を浴び、企業の関心も高い防衛力強化財源から始めたいと思います。宮沢先生、防衛力強化財源決定の舞台裏について、可能な範囲でお聞かせいただけないでしょうか。
宮沢:防衛費については、既に夏の終わり頃から政府内で議論が始まっていたのですが、この5年間で何をやるかという「防衛力整備計画」がまとまらなければ、それによってどの程度の歳出が必要になるかも見えませんので、防衛力整備計画の議論が先行して行われていました。防衛費を当面は赤字国債で、という意見も党内にはありましたが、このような恒常的な支出を赤字国債で賄うわけにはいきませんので、他の歳出をどれだけ削減できるか、また、税以外の収入がどの程度見込めるかを検証した上で、ようやく税という財源を考えることになります。税調は11月20日前には始めましたが、あらゆる税目について、白紙からしっかり検討しなければならないということで、結論に至ったのは大綱を世に出す直前でした。
緑川:ただ、あらゆる税目について白紙で検討すると言っても、主なものは所得税、法人税、消費税あたりに限られますよね。
宮沢:今挙げていただいた税目のうち消費税については、まさにこれからの増大する社会保障費に対応するための大切な財源であって、はじめから議論の対象外でした。したがって、正確に言えば、所得税、法人税、主要税を含むあらゆる税目を白紙で検討した、ということになります。
緑川:税について本格的に検討を始めたのはいつ頃からだったのでしょうか。
宮沢:防衛力整備計画及びそれに伴う歳出についての議論に相当時間がかかってしまったということ、自民党の中にも色々な考えの方の人がいるということもあって、私の手元に、税でどのくらい確保して欲しいという資料が来たのが12月の第1週でした。
小畑:12月8日の夕方に政府与党政策懇談会が開かれた後、岸田総理が、増税で1兆円強、所得税の負担は増やさない、と会見で表明されたところから税の議論が本格化しましたね。
宮沢:大綱を公表するまでのわずかな期間でこのような重いテーマをまとめるのは大変だなあというのが正直なところでしたね。もっとも、税調が始まる前から、短期決戦での議論になる可能性が極めて高いということは分かっていました。しかも、こういう増税の議論というのは、消費税を除いて、極めて短期間で決めてきたというのがこれまでの歴史なんです。

緑川:増税となると当然反対意見が出てきますが、短期間で決着がついてきたのは何故でしょうか。
宮沢:減税は時間をかけて議論すれば相応のところに落ち着きますが、増税の議論は、それに反対する人とあまりにも溝が深いところから始めなくてはならないんです。だからこそ、短期決戦でやらざるを得ない。まあ、今回はこれほど短期間になるとは思っていませんでしたが(笑)。もちろん、その前から財務省等々とは頭の整理は色々やっており、それの中で、法人税が一つ大きな候補であることは間違いないと思っていました。
緑川:やはりそうならざるを得ないでしょうね。この点について小畑さんはどうお考えでしょうか。
小畑:防衛力強化は国民全体の問題であることから、法人の負担を否定するものではありませんが、法人に偏ることなく薄く広く国民全体で税負担を求めるのが適切なのではないかと申し上げてまいりました。また、法人については、GX経済移行債の償還財源に係るカーボンプライシングの議論も併行して行われていたことから、決着の仕方によっては経済活動に大きな影響を及ぼしかねない懸念もありました。
期待通りとはいかなかった法人税率の引下げ効果
宮沢:小畑さんの前でこんなことを言うのは若干気が引けるのですが、私が経産大臣をやっていた時には、私がイニシアティブを取って法人税率を相当下げましたし、下げることによる効果も期待していました。その一つはやはり賃上げであり、また、投資を増やして内部留保を活用してもらうということや、税率を下げることによって日本があまり強くないサービス産業が活性化してくれないかというのが当時の我々の目論見でしたが、残念ながら期待していたような結果にはなりませんでした。逆に言うと、多少税率を上げたからといって、我々が期待していた効果を阻害する要因にはならないのではないか、という判断になったわけです。

小畑:賃上げについて言えば、2014年以降9年連続でベアが実現しており、この賃上げのモメンタムを維持・強化していくことが重要ですが、働き手の7割を雇用する中小企業における賃金引上げとそのための環境整備、雇用者の約4割に上る有期雇用等労働者の処遇改善が課題です。
付加税導入が賃上げを加速する可能性も
緑川:付加税の課税ベースとなるのは、地方法人税と同じく租税特別措置の「税額控除後」の税額となるのではないかと推測しています。そうすると、例えば賃上げや投資に積極的な企業においては、賃上げ税制等により付加税の発射台を低くすることができることになりますね。
宮沢:仮に法人税の付加税を4%とすると、簡単に言えば法人税率で約1%(23.2%×0.04)です。したがって、例えば労働分配率が50%だとすると、2%賃上げすれば法人税の負担は現在と変わらないことになります。
緑川:今回の付加税も「賃上げ」を後押しすることを意識したのかな、と思いながらお話をうかがっていました。結果として、付加税が導入された際には企業では賃上げが加速することになるのではないでしょうか。
最近では、衣料品チェーンのユニクロを運営するファーストリテイリングが、国内の従業員の給与を最大で40%引き上げるとの報道がありました。他の大企業も賃上げするという話をよく耳にしますが、これは令和4年度税制改正で強化した、宣言税制たる賃上げ税制の良い影響が出ているということでしょうか。
宮沢:そうですね。税調や政権の幹部の間でも、良い経済のサイクルを作るためにはやはり賃上げがどうしても必要だという意識は大変強いものがあります。これだけ物価が上がってきている状況で、ますますその意識は強まっていますね。
緑川:賃上げ税制あり、何より現実に物価が上がっている。企業の選択としては、給料を上げるしかないんじゃないでしょうか。
小畑:賃金と物価の好循環を回さないといけませんね。物価が上がらない時代が30年間続いてきたわけですから、賃上げの良い機会ではないでしょうか。物価が上がることをある意味チャンスと捉えて、物価動向を特に重視しつついかに賃上げができるかということが企業に問われているのではないかと思います。
税調内の3分の1は「反対」、3分の1は「拙速」との意見
緑川:一方、今回の防衛力強化財源として相続税という選択肢はなかったのでしょうね。恐らくそれほど大きな税収にはつながらないでしょうから。
宮沢:おっしゃる通りです。結果的に使うことになった復興特別所得税、たばこ税のほか、その他の税についても様々な可能性を相当なレベルでシミュレーションしていました。相続税についても高額な相続財産を相続される方を含め色々シミュレーションはしましたが、金額的に大きなものにはなりませんでした。また、相続税は基礎控除を抜本的に見直してからまだ10年位ですし(平成25年度税制改正、平成27年1月施行)、この見直しによって従来は約4%しかいなかった相続税の申告対象者がその2倍の約8%まで増えていますので。
緑川:所得税も普通に増税していれば、相当ハレーションがキツかったでしょうね。復興特別所得税を活用することで、少なくとも現在の負担を増やさないというのは上手いやり方だったと思います。
宮沢:所得税についてもいろいろなケースを想定しましたけれども、緑川先生のおっしゃる通り、これは相当ハレーションがキツいだろうなと。実は復興特別所得税を活用することについては、12月の始めの段階までに頭の整理はしてありました。法人税、たばこ税についても、私のところでは早い段階から様々なシミュレーションはしていました。
緑川:それでも大綱のとりまとめ直前まで決着がもつれ込んだということにはどのような背景があるのでしょうか。

宮沢:それだけ税調内にも様々な意見があったということです。大綱のとりまとめ期限が迫る中で防衛力強化財源のための増税についての議論を開始して、結果的には3日連続で税調を開催することになりました。1日目は、国税の主要な税目の中で議論の対象になりうる税を羅列してそれぞれの税収の規模感を示した上で自由に発言していただいたのですが、「国債でもいいんじゃないか」という意見もあれば、「あまりにも拙速」という意見もありました。かなり多くの方が発言されましたが、大まかに言うと、3分の1は「反対」、3分の1は「拙速」、3分の1は「やむをえない」というものでした。2日目は、先ほど申し上げた主要3税目について議論したのですが、2日目までは、1日目とそれほど違わない議論が多かった印象です。そして3日目には、最終的な結論となるような議論をして、法人税については税率4~4.5%の付加税、復興特別所得税、たばこ税を財源として示しつつ、ただし実施時期については状況を見ながら決めますよというようなことを書いたペーパーを出しました。ポイントは、法人税の付加税率に幅があるということと、実施時期を決めていないということです。つまり、少なくとも2023年の通常国会に税制改正法案を出すことはできないということになります。この説明をして、あとは私に一任ということになりました。
税率と施行時期は税調を前倒し開催して決定する可能性も
緑川:条文には当然できないわけですが、一応まとまったということは、これを前提にして今後の議論が進むという理解でよろしいでしょうか。
宮沢:はい、そういうことです。これはもう総務会まで通して、自民党として決定したことです。
緑川:施行は「令和6年以降の適切な時期」とされていますが、最終決着はいつ頃になるのでしょうか。
宮沢:今年年末の税調なのか、それとも、もう少し早めに税調を開いて決めるのか。法律として書くことの95%は決まってるわけですから、残りの5%についてどうするかということになろうかと思います。
産業構造の変革
サービス産業の付加価値をどれだけ上げられるかが内需のカギに
緑川:今回の大綱の「基本的考え方」では、「マーケット」「産業」「人材」への成長投資を一体的に強化することが強調され、とりわけ、資産所得倍増やスタートアップ・エコシステムの強化に向けた措置が目に付きます。これらを実現するためには、産業構造の変革、特に、内需ビジネスから外需ビジネスへのシフトが重要だと思われますが、この点についてはどのようにお考えでしょうか。新規IPOにおける日本企業は未だに内需ビジネスばかりだと感じています。外需ビジネス、要は海外でも稼げる企業を徹底的に応援するような税制というのは考えられないでしょうか。
宮沢:外需については、大企業ばかりでなく、この10年、20年で中小企業、中堅企業も相当積極的になっています。日本企業が外需に対しチャンスを作れるようにしていくことは大変重要なことと考えています。ただ、内需も重要であり、おそらく内需を喚起するには、特にサービス産業の付加価値をどれだけ上げられるかということがカギだと思っています。
緑川:日本のサービス産業は基本的に非常に遅れていて、海外で利益を出している日本の製造業以外の企業というとほとんどないのが現状ではないでしょうか。やはりモノ作りなんですよね。
小畑:もっとも、製造業、鉱業、建設業、農林水産業以外をサービス産業とすれば、日本の名目GDPの実に7割を占めているので、サービス産業の労働生産性の向上は重要な課題です。サービス産業の多くは労働集約型で、人材の質が売上や付加価値に直結するので、人材育成が重要ですね。
宮沢:飲食産業については、例えばカレーのCoCo壱番屋はかなり世界に進出していますし、中国には日本のラーメンチェーンが進出しています。日本の飲食産業はクオリティでは世界に冠たるものを持っていますが、値段が非常に安い。だから付加価値が低いんです。
緑川:中小企業の根本的な問題ですね。また、私が「外需ビジネスがダメだ」といったのは、海外に進出はしているけれども利益が出てないっていう意味でダメだということです。ですから、海外でも稼げて事業拡大が期待できる企業を徹底的に応援するような税制というものはできないかと。企業にはお金が余っているわけですから。
アルゴリズムを書ける人材をどれだけ育成できるか
宮沢:内部留保の水準が高いという点については、国内市場に目を向けると何に投資するのかという問題がありますね。国内で投資しようにも、市場が大きくなるということが見通せなければ、なかなか投資に踏み出せません。
緑川:その問題を解決するためにはどうしたらよいと思われますか。
宮沢:人への投資しかないですね。人への投資をこれから徹底的にやることによって、日本の市場が大きくなる雰囲気が出てこなければいけないと思っています。我々も経団連の皆さんには、賃上げだけではなくて、人への投資をやって欲しいということはお願いしているのですが、はかばかしい返事が来ないんですよ(笑)。最も重要なのは、アルゴリズムを書けるような人材をどれだけ育成できるのかということです。ここが日本にとって勝負どころなんですよ。
緑川:そこには経団連としても協力的なわけですよね。
小畑:アルゴリズムを書ける人材をどれだけ増やすかということについては、最後は賃金という話になるのではないかと思っています。能力・スキルに報いられなければ、やはり人は増えないですよね。
宮沢:特にアルゴリズムについては教える人材すらいないんですよ。まずは教えられる人材を確保して、しっかりした教育体制を作り上げていく。高専等の設立準備法人への寄附金の全額損金算入措置の対象には専門学校まで入れたのですが、これは、教育内容について文科省の規制を受けないようにするためです。各学校が自由に独自の教育を行っていただきたい。また、その学校を卒業したというだけで企業が採用したがるような教育をしていただきたいと思っています。
緑川:その点は私も賛成です。若干気になったのは、本措置の対象はなぜ新設法人だけなのでしょうか。既設の学校法人が、例えば新たな技術系の専門学校を設置する場合にも、現行の「受配者指定寄付金」ではなく、学校法人において全額が寄付金として受け入れられる今回の措置を拡大して認めてもよいのではないでしょうか。なぜなら、「既設」ということは、文字通り既に人材教育に成功しているわけですよ。そういうところに新たな人材教育の機会を与えれば確実性が高いですし、本措置の活用もより機動的になるのではないかと思います。
宮沢:なるほど。それは一理ありますね。次の宿題としましょう。
インボイス制度
インボイス制度開始後に新たな問題が生じれば、さらなる法律改正も
緑川:今年10月からのインボイス制度開始を控え、令和5年度税制改正では小規模事業者に対する複数の負担軽減措置が講じられましたが、依然として小規模事業者等の対応は相当遅れているようです。この点について、宮沢先生はどのようにお考えでしょうか。
宮沢:インボイス制度は平成28年度税制改正で導入しているので、制度の仕組み自体はずいぶん前から分かっているわけです。日本人の性格なのか、直前になって自分のこととして考え始めると、商工会議所、税理士会など色々なところから様々な意見が出て来ました。こうした中で、免税業者が課税業者になった場合の事務手続についても相当簡素化しましたし、免税業者でい続ける者についてもそれなりに簡素化をするなど、いただいた意見のうち対応できるものは概ね制度の中に入れ込んだというのが令和5年度税制改正です。さらに、関係者の皆さんには、インボイス制度が開始した後、また何か新たな問題が生じた場合には、法律改正も含めて今年の年末以降しっかり対応していくということは申し上げています。
小畑:この辺りは基本的には経団連というよりは商工会議所の話ですが、昨年9月の日本商工会議所の消費税インボイス制度に関する実態調査によると、「売上高1,000万円以下の事業者」に限ると60.5%が特段の準備をしていない状況にありました。ただ、年間売上高が1,000万円以下とされる免税事業者の30.8%が「課税事業者になる」、20.4%が「要請があれば課税事業者になる」と回答しており、免税事業者の過半数は課税事業者への転換を考えていることも明らかになっています。

宮沢:特に小規模事業者にとっては、やってみなければ分からないという面はあると思いますが、今後事業を拡大していこうと考えているのであれば、青色申告でしっかり経理をした上で、インボイス制度にも対応していただくということが、将来の成長につながるのだろうと思います。
緑川:インボイス制度をきっかけに経理体制が整備され、企業の成長につながるという良い循環を生むことになればいいですね。
宮沢:そうですね。もちろん無理に課税転換をしていただく必要はありませんが、将来事業を広げたいという場合には視野に入れていただければいいなと思います。
相続税評価
マンションの相続税評価、見直しは必須の情勢
緑川:令和5年度税制改正大綱では、マンションの売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているとして、相続税におけるマンションの評価方法の適正化を検討する旨が明記されましたが、マンション評価は以前から問題になっていますし、昨年には評価通達総則6項の適用を認める最高裁判決も出ています。
宮沢:その最高裁判決については承知しています。
緑川:本判決について、土地の評価が問題になっていると考えている実務家も多いと思うのですが、実は建物の評価もおかしいんですね。また、マンションは高い階層や角部屋ほど価格が高いことは当たり前にもかかわらず、税評価が対応していないため、変な税目的の売買がなされていることに違和感を感じています。今回の最高裁判決をきっかけに、相続・贈与税、固定資産税の評価も税調で議論していただけないかと思っています。
宮沢:おっしゃる通り、大綱でも相続税におけるマンションの評価方法の適正化を検討するということが明記されましたし、国税庁からも、租税法学者や不動産鑑定士、不動産業界など関係者などを集めて、マンションの評価に関する有識者会議を始めるという報告を受けています。したがって、少なくとも相続税におけるマンションの評価方法については議論が進むはずです。
緑川:おかしな評価を利用したいわゆる節税商品によって一番得をしているのは、結局は富裕層なんですよ。「一億円の壁」といった話よりも、評価の問題の方が議論のテーマとしては優先度が高いと思います。国税庁ではなく税調でもこの問題には切り込んでいただきたいですね。
宮沢:具体案を出していただければ、検討しますよ。
緑川:いっぱいありますので是非よろしくお願いします(一同笑)。
外形標準課税
節税以外の目的で減資等を行う法人への“副作用”に配慮
緑川:令和5年度税制改正大綱では、減資や組織再編による外形標準課税の対象法人数の減少を問題視し、外形標準課税の対象から外れている実質的に大規模な法人を対象に制度的な見直しを検討することが明記されましたが、実際に外形標準課税の見直しを視野に入れているのでしょうか。
宮沢:そうですね。外形標準課税の対象企業数は導入当時と比べて3分の2くらいにまで減少しています。ここまで減っていることに対しては、驚きとともに強い問題意識を持っていますし、総務省も様々な検討を重ねているわけですが、本来であれば今回の税制改正である程度手を付けられれば良かったと思っています。減資をして資本準備金に振り替えても、実態としてはその企業は何も変わりません。そのような企業を対象に制度の見直しを色々考えたのですが、関係者からいくつか問題点を指摘され、税調でそれらをまとめるところまでの合意が取れなかったというのが昨年末の状況です。ただ、この問題には対応しなければならないと思っています。
緑川:一部の企業が外形標準課税を逃れるためにやったことをきっかけに適用範囲が拡大されれば、とばっちりを受ける企業も出てきますね。
宮沢:おっしゃる通りです。そうならないようにするためには、節税を目的とする法人に対してどのような方法をとるべきかということだけでなく、節税以外の目的で減資等を行う法人に“副作用”が及ばないようにすることもテーマになりますので、もう少し検討する時間が必要です。そういう意味では、昨年末は「あえて決めなかった」とも言えます。
小畑:外形標準課税の適用を避けるために減資した企業と、分社化により結果的に外形標準課税の適用がない企業とでは、問題の状況はまた別な感じもしますが、本来外形標準課税が適用されてしかるべき企業をいかにして制度的に切り出せるかが技術的な課題ですね。
ふるさと納税
ふるさと納税で行政経費の無駄遣いが発生
緑川:話を個人課税に移したいと思います。個人的には、ふるさと納税はそろそろ終わりにしてもよいのではないかと思っているのですが、ふるさと納税を抜本的に見直すお考えはありますでしょうか。
宮沢:私もふるさと納税は基本的にはあまり好きな制度ではないんですよ。「合成の誤謬」という言葉がありますが、ふるさと納税はその典型みたいなものと言えるかもしれません。要するに、地方自治体が税収をきちんと行政目的に使っているということを前提にすると、少なくとも返礼品に要する税収の3割位のコストと発送や人件費等の経費を含めた5割位の部分は、本来は行政経費として文字通り行政に使われるべきものです。それが食品などに変わってしまい、その分だけ行政経費が無駄遣いされていることになります。
緑川:ふるさと納税は、税という言葉は付いていますが税ではないですね。やはり、地方税の対応策だったら地方税法の中に明確に位置付けて欲しいと思います。
宮沢:そうですね。“物付き”というのは違和感がありますし、ふるさと納税はもはや本来の趣旨とは異なったものになってきていると感じています。
こども予算と社会保険料
社会保険料の増額は賃上げに“冷や水”をかけることに
緑川:こども予算倍増の財源についてはどのようにお考えでしょうか。消費税は早々に封印されていますが、どこに財源を求めるべきだと思われますか。最後は社会保険料なのか税なのかという議論に行くのではないかと思っているのですが。
宮沢:社会保険料になると、やはり働く現役世代の負担になるんですよね。
緑川:給与所得者が中心になりますしね。
小畑:せっかく賃上げしても、そちらに吸い取られてしまっては賃上げによる活力が生まれません。物価上昇に対応して賃上げが浸透しつつある中で社会保険料が上がるとなれば、この流れに冷や水をかけられる格好になるおそれもあると思います。
宮沢:「もし税でやるとしたら、これとこれしかないよな」ぐらいのことは頭の中にありますが、いずれも政治的にはキツいでしょうね。
緑川:さすがに消費税というわけにはいかないでしょうしね。「子ども手当促進税制」でも作るのはいかがでしょうか(笑)。
宮沢:例えば、配偶者控除を見直して、そこで生まれた財源を子どもに振り分けるという案がありますが、これはおそらく政治的にもの凄く大変だと思います。やはり高齢者夫婦の世帯が年金プラスアルファで暮らしているところで、配偶者控除がなくなるというのは酷ですから。
緑川:高齢者層に影響が及ぶことはなかなかできないということですね。
宮沢:やるとしても、鉋(カンナ)をかけるように少しずつ、ギリギリの範囲でということです。
緑川:時間がかかるということですね。やはり、先ほどもお話が出た人材育成も含めたところで、賃上げから上手く景気を好循環させ、良い企業が育っていくという流れを作っていく必要があると思いますね。
小畑:社会保険料も半分は企業負担です。法人税よりも、法人が払っている社会保険料の方が多いですから。限界に来ていると思います。
緑川:新たなもので広く薄く取るしかないと思いますが、それを社会保険料でやったら、賃上げの流れに冷や水をかけることになる。要するに何らかの税でやるしかないということですかね。
宮沢:難しい問題ですね。社会保険料は僕の仕事じゃないなと思っているのですが(笑)。
緑川:社会保険料と税はやっぱり一体なんですよね。この話は簡単に結論が出ることではないと思いますので、また議論できる機会があることを期待します。宮沢先生、小畑さん、本日はお忙しい中、ありがとうございました。
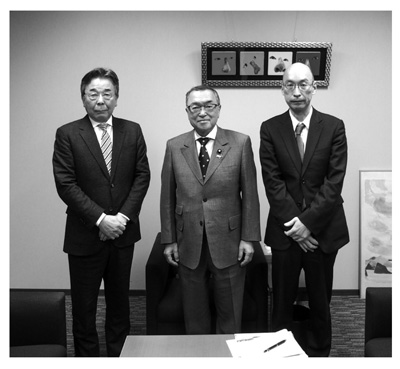
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























