解説記事2023年02月27日 税務マエストロ 還付請求手続の実践演習(個人事業者編)(2023年2月27日号・№968)
税務マエストロ
還付請求手続の実践演習(個人事業者編)
#283
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
免税事業者は、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間においてインボイスの登録申請をする場合、「課税事業者選択届出書」を提出しなくてよいこととされている(平成28年改正法附則44④)。また、令和5年度税制改正大綱によると、免税事業者がインボイスの登録申請をする場合には、いわゆる「15日ルール」により登録希望日を選定できることとなるようだ。
免税事業者が消費税の還付を受けるためには、期限までに「課税事業者選択届出書」を提出することが実務における常識とされていたところであるが、今後はインボイスの登録申請による消費税の還付請求という新たなスキームを検討する必要があるように思われる。
そこで、令和5年度改正の成立を前提に、消費税の還付請求手続について実務上のポイントを確認することにした。今回は個人事業者に関する事例を検証する。
なお、「2割特例」や「少額特例」など、インボイス関係の令和5年度改正については、改正法の政省令と通達が公表された後に本コーナーで取り上げる予定である。
また、令和5年度において改正が予定されている申請書(届出書)の期限に関する取扱いについては、政省令と通達の公表により解釈が変更になる可能性もあることをご承知おき戴きたい。
以下の各事例について、いつまでにどのような手続きが必要であるか、届出書の種類とその届出書を提出すべき課税期間およびその届出書の適用開始課税期間について解答されたい。
(前提条件)
令和5年の9月中に税務相談を受けたという前提で解答すること。
また、課税期間の短縮制度については、消費税の還付を受けるために必要な場合に限り、 活用するものとする。
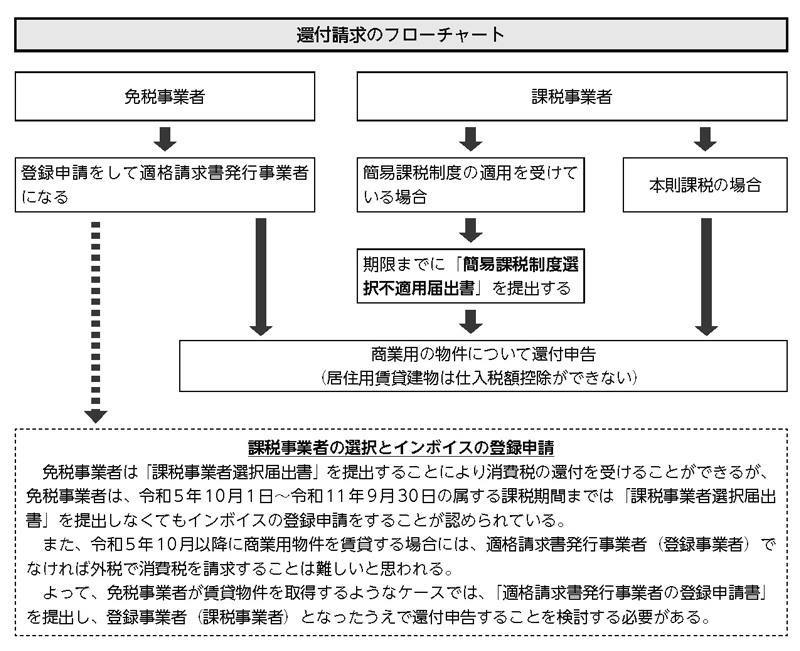
事例1 当年中に建物(高額特定資産)を取得する場合−令和5年9月取得のケース
給与所得者であるA氏は、遊休地を有効活用すべく、ここに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和5年9月30日であり、同年1月中に建築会社と請負金額1億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については840万円、令和5年中は210万円である。
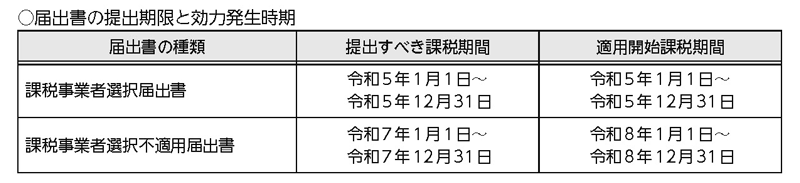
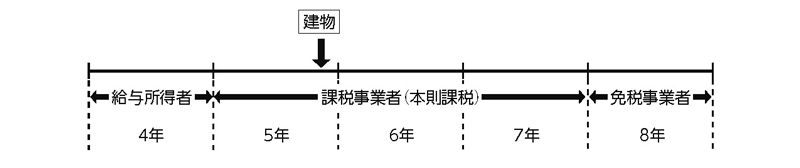
<ポイント>
① 旧3年縛り(平成22年度改正法)により、課税事業者の拘束期間は3年間となる。また、令和6年と令和7年の申告で簡易課税制度の適用を受けることはできない。
② 課税事業者を選択しようとする場合には、原則として、適用を受けようとする課税期間が始まる前までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければならないが、「新規開業」の場合には、事前に提出することが不可能なので、届出書を提出した日の属する課税期間から課税事業者となることが例外的に認められている。
③ 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出を検討する必要がある。
④ 建築請負契約を締結したのが令和4年以前の場合、「新規開業」に該当しないことから還付を受けることはできない。
<スケジュール>
① 令和5年12月31日までに「課税事業者選択届出書」を提出する。
これにより、令和5年から課税事業者となることができる。
② 令和5年分の確定申告で消費税の還付を受けることができる。
③ 課税事業者となった課税期間の初日(令和5年1月1日)から3年を経過する日(令和7年12月31日)の属する課税期間の初日(令和7年1月1日)以降に「課税事業者選択不適用届出書」を提出することができるので、これを令和7年中に提出する。
「課税事業者選択不適用届出書」の提出により、令和8年から免税事業者になることができる。
新規開業とは?
新規開業の場合には、届出書の提出日の属する課税期間から課税事業者になることができるわけであるが、この「新規開業」については、消費税法施行令20条一号で「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」と規定している。
注意してほしいのは、「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」というのは、「課税資産の譲渡等を開始した日」つまり課税売上げが発生した日を意味するものではないということである。DHCコンメンタール(第一法規出版)によれば、「事業に必要な事務所、店舗等の賃貸借契約の締結や資材、商品の仕入などの開業準備行為を行った日もこれに該当する」とされているので、その翌課税期間から課税事業者になろうとする場合には、これらの開業準備行為を行った日の属する課税期間中に届出書を提出する必要がある。
また、事業の規模は「新規開業」の判断には関係ないので、たとえ貸駐車場1台だけであっても、これを賃貸し、賃貸収入を得ているような場合には「新規開業」には該当しないことになるので注意が必要だ。
事例1−1 建築請負契約が前年の場合
給与所得者であるA−1氏は、遊休地を有効活用すべく、ここに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和5年9月30日であり、令和4年10月中に建築会社と請負金額1億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については840万円、令和5年中は210万円である。
<コメント>
建築請負契約を締結したのが令和4年中であることから、令和5年は「新規開業」の年に該当しない。
また、相談を受けた月(令和5年9月)の月末に物件が完成することから、課税期間を1か月に短縮しても「課税事業者選択届出書」を事前に提出することはできない。よって、還付を受けることはできないことになる。
事例1−2 貸駐車場の賃貸収入がある場合
給与所得者であるA−2氏は、遊休地を有効活用すべく、ここに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和5年9月30日であり、令和5年1月中に建築会社と請負金額1億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については840万円、令和5年中は210万円である。
なお、A−2氏は、給与収入の他に年額60万円の貸駐車場(アスファルト舗装及び区画整理のしてあるもの)の収入がある。
<コメント>
以前から貸駐車場の賃貸による賃貸収入があるので「新規開業」には該当しない。よって、「事例1−1」と同様に還付を受けることはできない。
税抜経理の節税効果
税込経理の場合には、消費税の還付金は、不動産所得の計算上総収入金額に算入することになっている。
税抜経理の場合には、仮払消費税等と仮受消費税等の差額を未収入金として計上する。結果、建物の取得価額が消費税相当額だけ減少し、減価償却費は税込経理に比べて少なくなるが、消費税の還付金は所得金額の計算に影響しないことになる。したがって、還付申告になるような場合には、不動産所得の計算は、面倒でも税抜経理によることをお勧めしたい。
事例
不動産賃貸業を営む個人事業者が、新築した貸店舗について消費税の還付を受けるためにx1年から課税事業者を選択した場合
[x1年の収支]
① 賃貸料収入 2,200,000円 (非課税となる居住用物件はない)
② 貸店舗の建築費 55,000,000円
(1/10取得 償却率0.020 定額法)
③ ②の償却費以外の必要経費 1,000,000円 (うち課税仕入高 110,000円)
[x2年の収支]
① 賃貸料収入 2,420,000円 (非課税となる居住用物件はない)
② 貸店舗の償却費以外の必要経費 1,000,000円 (うち課税仕入高 132,000円)
※便宜上、消費税と地方消費税の合計税率10%により試算する。
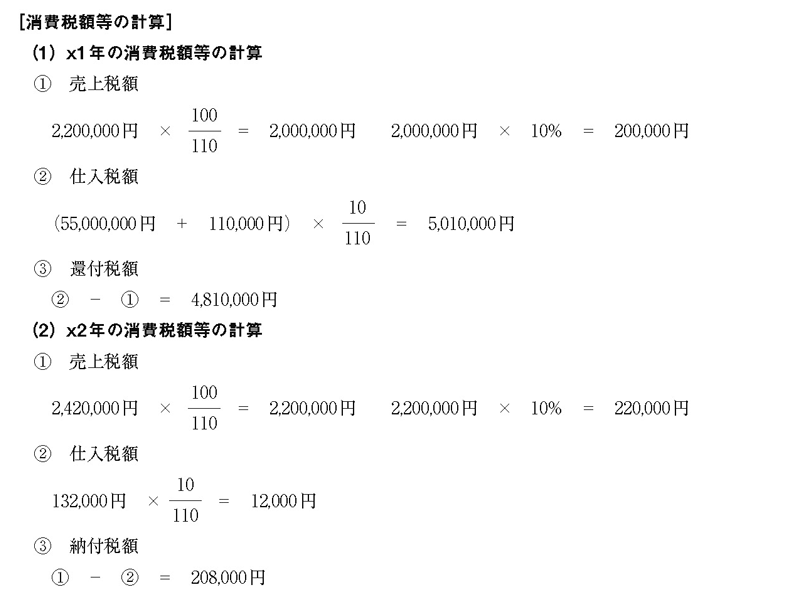
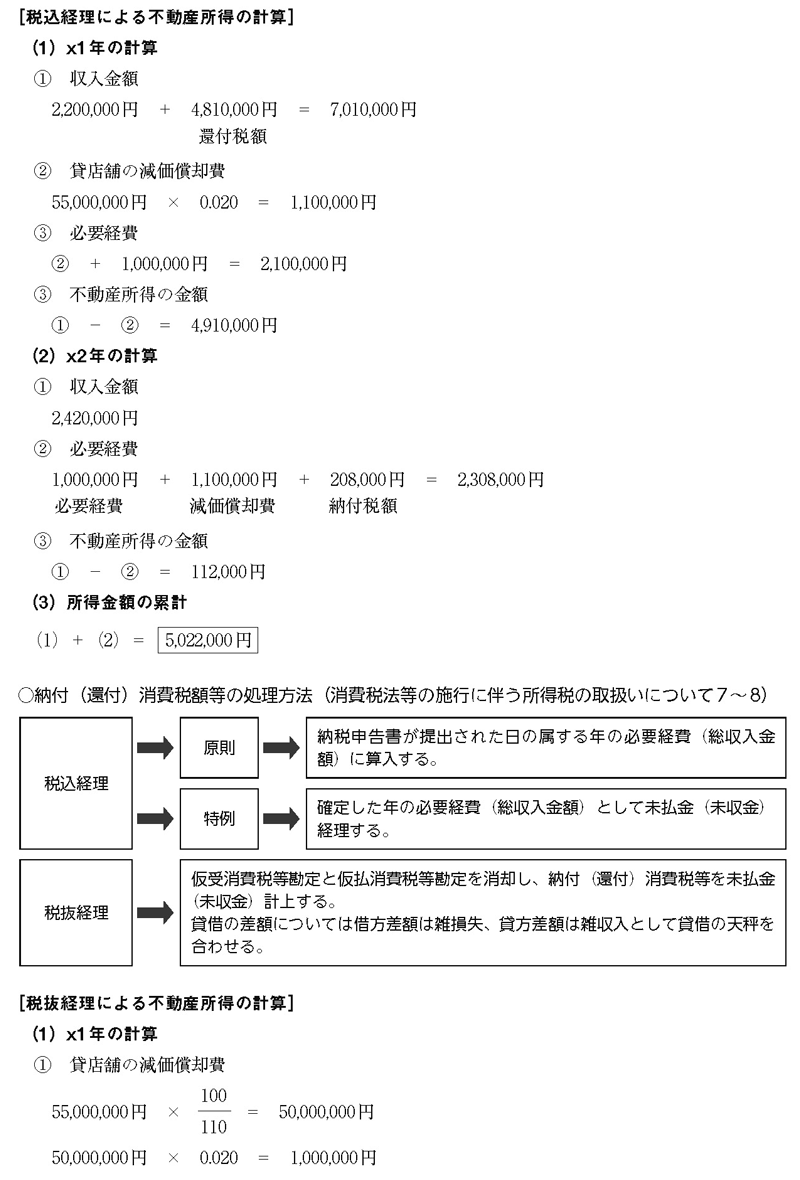
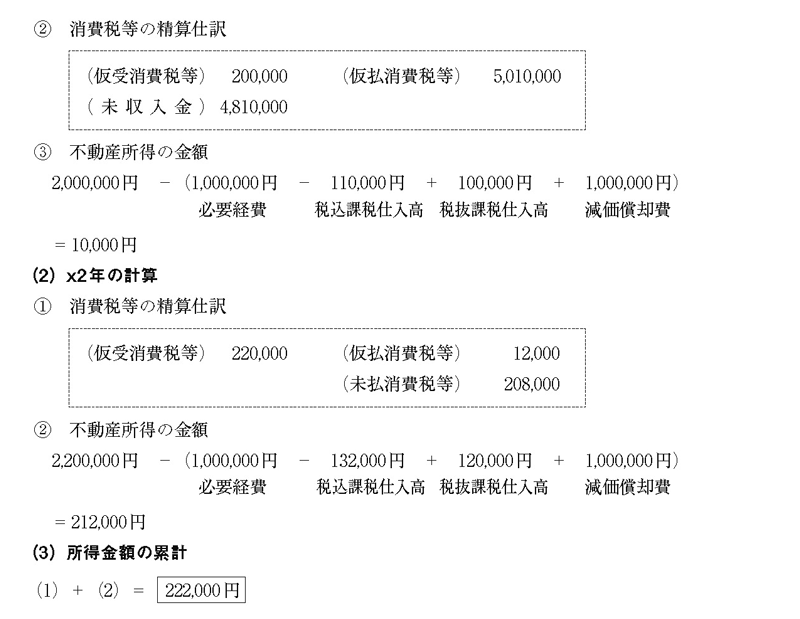
税抜経理によった場合、税込経理に比べて毎年の減価償却費は少なくなるが、還付消費税額等が損益に影響しないため、課税所得を平準化させることができる。税抜計算にさほど手間がかからないような場合には、積極的に税抜経理を活用することも必要である。
事例2 当年中に建物(調整対象固定資産)を取得する場合−令和5年10月取得のケース
給与所得者であるB氏は、中古の貸倉庫を購入して賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の購入金額は900万円(税抜)で、令和5年10月31日に引渡しを受ける予定である。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については240万円、令和5年中は40万円である。
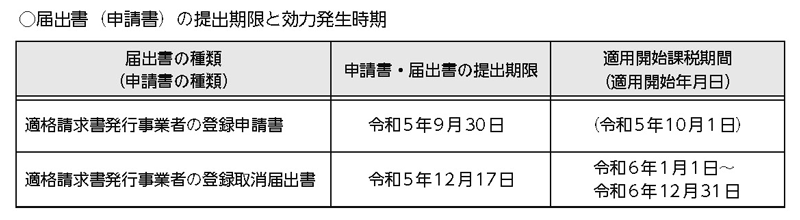
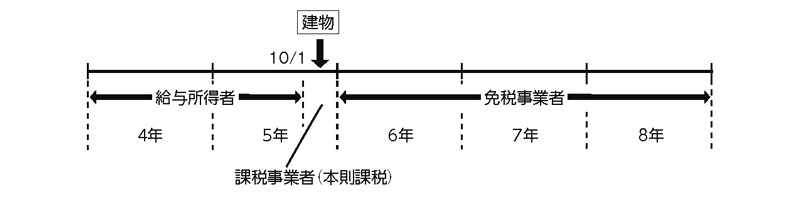
<ポイント>
① 令和5年10月1日から登録事業者になるためには、登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要がある。
ただし、期限までに申請書を提出できなかったことにつき、困難な事情がある場合には、9月30日までに登録申請書を提出することにより、困難の度合いを問わず、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)となることができる。
※ワンポイントアドバイス
令和5年10月2日以後に登録を受ける場合、登録申請書に記載する「登録希望日」は、登録申請書の提出日から15日を経過する日以後の日を記載することとされている。よって、令和5年10月31日に間に合わせるためには、登録申請書は遅くとも令和5年10月16日までに提出する必要がある。
② 登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者になることができる。ただし、インボイスの登録をしていないと消費税相当額を家賃に上乗せして請求するのが困難と思われるので、引き続き登録事業者として申告することを検討する必要がある。
※ワンポイントアドバイス
インボイスの登録を受けた登録事業者は、登録取消届出書(適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書)を提出しない限りは課税事業者として申告義務が発生する。
登録事業者が翌年又は翌事業年度から登録を取り止めようとする場合には、その課税期間の初日から起算して15日前の日までに登録取消届出書を提出する必要がある。
③ 「課税事業者選択届出書」を提出していないので旧3年縛り(平成22年度改正法)の適用はない。よって、令和6年以降も登録事業者として申告する場合には、簡易課税制度又は「2割特例」の適用を受けることができる。
<スケジュール>
① 登録申請書を令和5年9月30日までに提出し、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)になる。
登録申請書(次葉)の「免税事業者の確認欄」にある「登録希望日」の欄は、令和5年10月1日から登録する場合には記載する必要はない。
なお、登録申請書は早めに提出するように心掛けて戴きたい。
② 令和5年分の確定申告で消費税の還付を受けることができる。
③ 令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者になることができる。
事例3 期間短縮のケース
不動産賃貸業を営むC氏は、簡易課税制度の適用を受け、消費税の確定申告をしているが、遊休地を有効活用すべく、新たに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和5年10月31日であり、令和5年の1月中に建築会社と請負金額1億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については840万円、令和5年中は140万円である。
また、C氏の令和4年までの課税家賃収入(税抜)は2,000万円前後で推移しており、「適格請求書発行事業者の登録申請書」は令和4年中に提出済である。
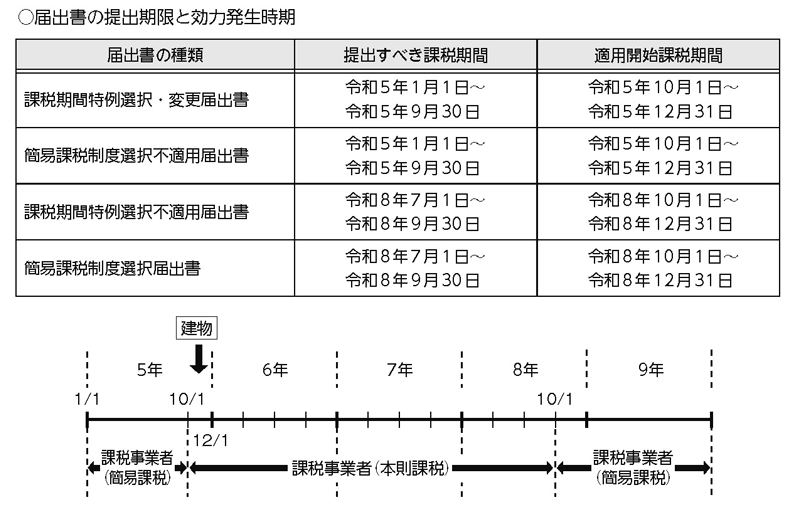
<ポイント>
① 令和5年10月中に完成する建物の建築費について消費税の還付を受けるためには年の中途より本則課税に変更する必要があるので、課税期間を短縮したうえで、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要がある。
② 簡易課税から本則課税に変更しても、旧3年縛り(平成22年度改正法)の適用はない。ただし、高額特定資産を取得するので、新3年縛り(平成28年度改正法)の適用により、本則課税による拘束期間は3年間となる。
<スケジュール>
① 令和5年9月30日までに「課税期間特例選択・変更届出書」を提出し、課税期間を10月1日から3か月ごとに区分する。
② 令和5年9月30日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することにより、10月1日から本則課税に変更することができる。
③ 令和5年10月1日~12月31日課税期間の確定申告で消費税の還付を受けることができる。
④ 「簡易課税制度選択届出書」は、令和8年7月1日~9月30日課税期間以後に提出することができるので、この課税期間中に届出書を提出することにより、令和8年10月1日より簡易課税により申告することができる。
⑤ 「課税期間特例選択不適用届出書」は、令和7年7月1日~9月30日課税期間以後に提出することができるのであるが、本則課税が強制適用となる令和8年7月1日~9月30日課税期間までは、期間短縮を継続する必要がある。
(注)令和7年中に「課税期間特例選択不適用届出書」を提出した場合には、令和8年から暦年単位の課税期間に戻ることになるが、この場合、「簡易課税制度選択届出書」の効力は令和9年から生ずることとなり、上記④に比べて不利になってしまう。
事例4 法人成りをした個人事業者が建物を取得するケース
同族法人の代表者であるD氏は、遊休地を有効活用すべく、ここに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和6年3月31日であり、令和5年の8月中に建築会社と請負金額3億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、平年については2,400万円、令和6年中は1,800万円である。
D氏は、令和3年までは個人で物品販売業を営んでいたが、令和3年12月中に法人成りをし、その事業の全部を法人が引き継いでいる。
D氏は、個人事業者としての消費税の確定申告にあたり、簡易課税制度の適用を受けていたが、法人成りに伴い、個人事業を廃業した際に、個人事業者としての消費税に関する届出書、申請書等の提出は一切行っていない。
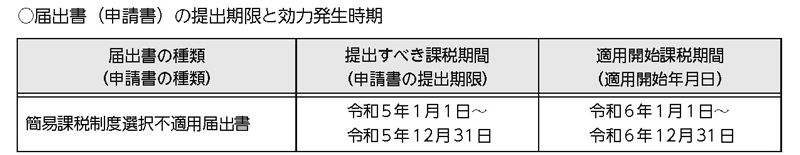
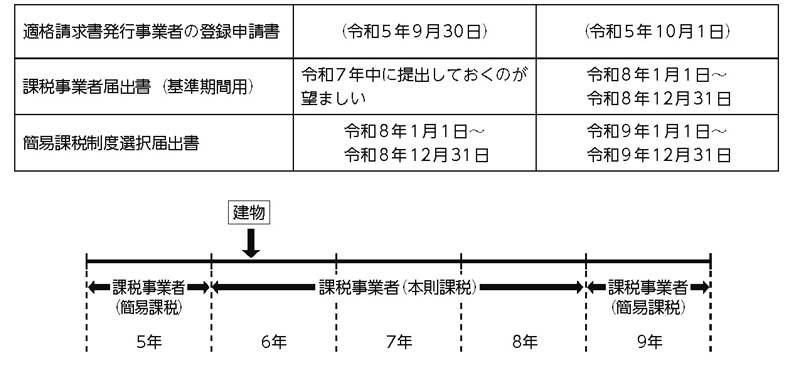
<ポイント>
① 令和5年10月1日から登録事業者になるためには、登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要がある。
ただし、期限までに申請書を提出できなかったことにつき、困難な事情がある場合には、9月30日までに登録申請書を提出することにより、困難の度合いを問わず、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)となることができる。
※令和6年3月31日に間に合わせるためには、登録申請書は遅くとも令和6年3月16日までに提出する必要がある。
② 「簡易課税制度選択届出書」の効力は、たとえ業種が変わっても継続されるので、簡易課税を適用している個人事業者が事業を廃止したような場合には、「事業廃止届出書」又は「簡易課税制度選択不適用届出書」のいずれかを提出する必要がある。
※ワンポイントアドバイス
「事業廃止届出書」の提出があった場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間から簡易課税の効力は失効することとされている。
また、「簡易課税制度選択不適用届出書」に事業を廃止した日が記載されている場合には、「事業廃止届出書」の提出は必要ない。
③ 「課税事業者選択届出書」を提出していないので旧3年縛り(平成22年度改正法)の適用はない。ただし、高額特定資産を取得するので、新3年縛り(平成28年度改正法)の適用により、課税事業者の拘束期間は3年間となる。また、令和7年と令和8年の申告で簡易課税制度の適用を受けることはできない。
④ 令和5年は課税事業者であるが、課税売上高も確定消費税額もないことから確定申告は不要となる(消法45①前文ただし書)。
<スケジュール>
① 本事例の場合には、廃業時に何ら届出書が提出されていないので、「簡易課税制度選択届出書」の効力は存続していることになる。
よって、令和5年12月31日までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、令和6年から本則課税に変更する必要がある。
② 登録申請書を令和5年9月30日までに提出し、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)になる。
登録申請書(次葉)の「免税事業者の確認欄」にある「登録希望日」の欄は、令和5年10月1日から登録する場合には記載する必要はない。
なお、登録申請書は早めに提出するように心掛けて戴きたい。
③ 令和6年分の確定申告で消費税の還付を受けることができる。
④ 令和8年以降は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えることから「課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要がある。
⑤ 令和9年から簡易課税で計算するためには、「簡易課税制度選択届出書」を令和8年中に提出する必要がある。
事例5 翌年から貸付を開始する場合
給与所得者であるE氏は、遊休地を有効活用すべく、ここに貸倉庫を建築し、賃貸の用に供することを計画している。
貸倉庫の完成予定日は令和5年12月31日であり、令和5年の1月中に建築会社と請負金額3億円(税抜)で契約を締結した。
この貸倉庫の賃貸により見込まれる家賃収入(税抜)は、年額2,400万円であるが、貸付を開始するのは令和6年からとなっており、令和5年中に家賃収入は発生しない。
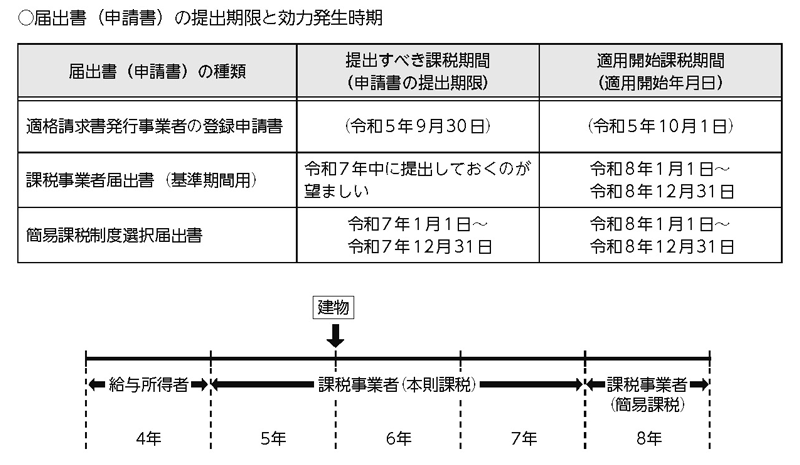
<ポイント>
① 令和5年10月1日から登録事業者になるためには、登録申請書を令和5年3月31日までに提出する必要がある。
ただし、期限までに申請書を提出できなかったことにつき、困難な事情がある場合には、9月30日までに登録申請書を提出することにより、困難の度合いを問わず、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)となることができる。
※令和5年12月31日に間に合わせるためには、登録申請書は遅くとも令和5年12月16日までに提出する必要がある。
② 「課税事業者選択届出書」を提出していないので旧3年縛り(平成22年度改正法)の適用はない。ただし、高額特定資産を取得するので、新3年縛り(平成28年度改正法)の適用により、課税事業者の拘束期間は3年間となる。
また、令和6年と令和7年の申告で簡易課税制度の適用を受けることはできない。
③ 令和5年中は売上げが発生していないので、課税売上割合は0%(95%未満)となるのであるが、個別対応方式で計算することにより、建物の建築費については課税業務用として全額を仕入税額控除の対象とすることができる。
<スケジュール>
① 登録申請書を令和5年9月30日までに提出し、令和5年10月1日から登録事業者(課税事業者)になる。
登録申請書(次葉)の「免税事業者の確認欄」にある「登録希望日」の欄は、令和5年10月1日から登録する場合には記載する必要はない。
なお、登録申請書は早めに提出するように心掛けて戴きたい。
② 令和5年分の確定申告で消費税の還付を受けることができる。
③ 令和8年以降は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えることから「課税事業者届出書(基準期間用)」を提出する必要がある。
④ 令和8年から簡易課税で計算するためには、「簡易課税制度選択届出書」を令和7年中に提出する必要がある。
本記事につきましては、一部誤りがございましたのでお詫びして訂正いたします(本誌975号(2023.4.17)39頁参照)。
なお、本記事は、令和5年4月27日付けで訂正後のものを掲載しております。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























