解説記事2023年04月10日 ニュース特集 D課税第2の柱 R5改正・R6以降改正の動向(2023年4月10日号・№974)
ニュース特集
改正政省令の内容、QDMTTの導入に伴う事務負担・紛争リスクは
D課税第2の柱 R5改正・R6以降改正の動向
令和5年度税制改正では、デジタル課税第2の柱「所得合算ルール(IIR)」の導入が決まり、その一部が令和5年度税制改正法にも盛り込まれたが、第2の柱の国内立法化がこれで完結するわけではない。現状、第2の柱に係る政省令は遅延しており、本誌取材によると、6月頃の公布となる可能性がある。さらに令和5年度税制改正の与党大綱には、「軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)と国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)について、令和6年度税制改正以降の法制化を検討する旨が明記されている。
そこで本特集では、令和5年度税制改正で国内法制化された所得合算ルール(IIR)のうち、邦貨換算の方法や情報申告制度の詳細など政省令に委任された事項に関する企業の疑問のほか、本誌取材によると最速で令和7年4月1日以降に開始する事業年度からの適用が見込まれるQDMTTの導入に伴う事務負担、日本と異なるQDMTTを導入する子会社所在地国との紛争に巻き込まれるリスクなど、企業が関心を寄せる事項について、Q&A形式でレポートする。
令和5年度改正
閾値の邦貨換算が省令委任となった理由
Q
令和5年度税制改正で国内法制化が図られたデジタル課税第2の柱「所得合算ルール(IIR)」では、特定多国籍企業グループについて、「直前の4会計年度のうち2以上の会計年度」の総収入金額が「7億5,000万ユーロ相当額以上」という閾値が設けられていますが、その邦貨換算が省令に委任されています。対象グループの閾値が類似する国別報告事項(CbCR)では法律段階で邦貨換算するにもかかわらず、なぜIIRは省令委任されているのでしょうか?
A
OECDが策定する第2の柱に関する行政ガイダンスによるインストラクションを待つ必要があったためだと推測されます。
IIRでは「国際的な制度の整合性」が不可欠
特定多国籍企業グループの閾値である「7億5,000万ユーロ相当額以上」における「相当額」の意義をこの度成立した令和5年度税制改正法案で確認すると、「7億5,000万ユーロ……を財務省令で定めるところにより本邦通貨表示の金額に換算した金額以上であるもの……」とされています(改正法法82四)。一方、対象グループの閾値が類似する国別報告事項(CbCR)については、周知の通り、7億5,000万ユーロを法律段階で邦貨に換算し、総収入金額が1,000億円以上である場合に提出義務が生じます(措法66の4の4①、④三)。現状、1ユーロは140円強となっていますが、閾値近辺の企業(1ユーロ=140円と仮定すると総収入金額が1,050億円近辺の企業グループ)としては、どの時点の為替レートを使うのか気になるところでしょう。
なぜCbCRと異なり、IIRでは閾値の詳細が省令に委任されているのかという疑問に対する答えは、2月1日にOECDが公表した第2の柱に関する行政ガイダンス(Administrative Guidance)によって明らかとなっています。要するに、税制当局としては、同ガイダンスによるインストラクションを待つ必要があった、ということだと推測されます。
ECBの12月平均レートを翌年開始事業年度に適用
IIRは各国で導入されることから、国際的な制度の整合性が不可欠であり、ユーロを各国通貨に換算する際も「統一基準」が求められます。
行政ガイダンスによれば、各国は毎年ユーロを自国通貨に置き直す(rebase)必要があり、その際に使用するのは、欧州中央銀行(ECB)の外貨参照レートに基づく12月の平均レートとなります。その平均レートを、翌暦年に属する日に開始する事業年度に適用します。
日本円はECBの外貨参照レートの対象になっているため、ECBのデータに基づき、毎年客観的に計算することが可能です。納税者である企業にとっては、省令又は通達、Q&A等で、換算後の円貨が毎年、早期かつ明確に表示されることが期待されるところです。
過去4会計年度の全てに前年の12月の平均レートを用いることは不可
行政ガイダンスでは事例も示されています。
例えば2026年において、ある企業グループがIIRの対象であるかどうかを判定する場合には、直前の4会計年度(すなわち、2022年、2023年、2024年、2025年)のうち2以上の会計年度の総収入金額が7億5,000万ユーロ以上となるかどうかを確認することとなります。外貨換算においては右図のデータを使用します。
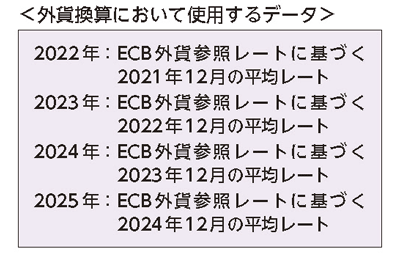
ポイントは、1年ごとにその前年12月の平均レートを見るということです。2026年に判定を行うからといって、過去4会計年度の全てについて2025年12月の平均レートを用いることは認められません。
デミニマス基準の閾値の邦貨換算も省令委任
ところで、IIRについて定めた改正法人税法では、上記の対象グループの閾値の他、トップアップ税額が零とみなされるデミニマス基準においても、収入金額や利益又は損失の額について、それぞれ1,000万円ユーロ、100万ユーロという閾値が設定されており、やはり邦貨換算は省令に委任されています(改正法法82の2⑥)。
行政ガイダンスでは、デミニマス基準についても、各国は同様の方式により平均レートを当てはめるべき、としています。
なお、同ガイダンスには、これらはあくまでもIIRに係るいくつかの閾値のための為替換算の方法を示したものであって、IIRの計算において、連結財務諸表の数値を自国通貨に換算する際のレートに用いるものではないことが確認的に記載されています。
情報申告制度と税務申告の違い
Q
デジタル課税第2の柱・所得合算ルール(IIR)における情報申告制度は、要するに税額の計算過程を詳述するためのものであり、税務申告との違いが分かりません。OECDの市中協議文書でも、実効税率の分母・分子に係る各種の調整計算の過程、トップアップ税額の計算過程等に関する記載が「数値込み」で求められており、情報申告書は税務申告の別表のようなものとなっています。税務申告との差分がないのに別の制度とすれば、企業の負担が増えるだけではないでしょうか?
A
令和5年度税制改正法においてIIRは法人税法本則に位置付けられ、かつ、申告納付と情報申告制度は条項の記載位置からして全く別の制度として創設されました。例えるなら、両者は、移転価格税制におけるローカル・ファイルと国別報告事項(CbCR)の関係のようなものであると言えます。
情報申告書が税務申告の別表と酷似したものになる可能性
令和5年度税制改正大綱によると、デジタル課税第2の柱・所得合算ルール(IIR)における申告及び納付の部分は、「特定多国籍企業グループ等に属する内国法人の各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税(仮称)の申告及び納付は、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月……以内に行うものとする」とされています。一方、情報申告制度の部分でも、「特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の名称、当該構成会社等の所在地国ごとの国別実効税率、当該特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税額その他必要な事項等(特定多国籍企業グループ等報告事項等)を、各対象会計年度終了の日の翌日から1年3月……以内に……納税地の所轄税務署長に提供しなければならない」とされています。確かに、これらの大綱の記述からすると、企業から「税務申告と情報申告制度の違いが分からない」という指摘が出てくるのもやむを得ないかもしれません。
また、情報申告制度では「国別実効税率」、「国際最低課税額(すなわちトップアップ税額)」等を記述するとされ、税額の計算過程を詳述する書類に見えます。実際、昨年末に公表された「GloBE情報申告」と題するOECDの市中協議文書には、日本の情報申告制度のひな型ともいうべきものが掲載されていますが、そこでも、実効税率の分母・分子に係る各種の調整計算の過程、トップアップ税額の計算過程等に関する記載が「数値込み」で求められています。そうなると、情報申告書は税務申告の別表のようなものであり、「税務申告との差分がないのに、なぜ別の制度となっているのか」という疑問が生じます。
トップアップ税額がなくても、特定多国籍企業グループ等報告事項等は要提出
この点については、例えるなら、移転価格税制におけるローカル・ファイルと国別報告事項(CbCR)の関係のようなものであると理解するのが適当と言えます。
国外関連取引に係る基本的な事項を記載したローカル・ファイルは、平成28年度税制改正を踏まえ、税務申告の期限までに準備することとされたところです(同時文書化)。税務当局の求めに応じ、提出する必要があります。ただし、ローカル・ファイルはあくまでも取引の「点」の情報であり、グループ全体のリスク・アセスメントという観点からは、「面」の情報であるCbCR(あるいはマスターファイル)が別途必要とされました。CbCRは同じく平成28年度税制改正で導入され、事業年度終了後12か月以内に提出することとされています。税務当局に提供されたCbCRは、租税条約により関係する国に連携されます。
税務申告は、基本的にトップアップ税額及びそれに対応する法人税額の記載を求めるものです(点としての最終結果)。トップアップ税額がなければ提出を要しません(新法法82の6一)。これに対し、情報申告制度は、IIR等に係るグループの「全体情報」を求めるもの(面としての情報)です(新法法150の3)。本誌の取材によれば、トップアップ税額が生じない場合でも、情報申告制度に基づく「特定多国籍企業グループ等報告事項等」は税務当局に提出する必要があります。IIRは法人税法本則として位置づけられ、かつ、申告納付と情報申告制度は条項の記載位置からして全く別の制度として創設されることとなるなど、両者は全く別の制度と位置付けられています。
情報申告書で他国に連携される情報は当該他国に必要な範囲に限定すべき
また、上述のOECD市中協議では、情報申告制度の枠組み自体が協議の対象となっています。しかし、グループの構成事業体に関する各種情報は機密情報であり、条約方式により守秘義務は課されるものの、企業としては、むやみやたらと詳細な情報を子会社所在地国の当局と連携したいとは考えていないでしょう。
そもそも、情報申告書に個別の構成事業体の情報を1つ1つ書き込むことが現実的なのか、という問題もありますが、企業からは、少なくとも、他国に連携される情報については、当該他国に必要な範囲のみとすること、ミニマム課税以外の目的に使用しないこと、問い合わせ・税務調査も、現地子会社に対してバラバラと行うのではなく、親会社に一元化すべきことなどの意見が出ています。
令和5年度税制改正法では、情報申告制度の詳細にまでは踏み込んでいません。OECDでの議論の結末が、そのまま政省令で規定される事項に反映されることが予想されます。
令和6年度以降の改正
QDMTTの導入に伴う事務負担
Q
令和5年度税制改正の与党大綱には、国内ミニマム課税である「QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)」について令和6年度税制改正以降の法制化を検討する旨が盛り込まれましたが、日本の子会社等の実効税率が15%を割り込むことは考えにくい中、多数の日本の子会社の実効税率を計算するのは非常に効率が悪く、QDMTTの導入に伴う事務負担の増加に大きな懸念を抱いています。これを回避するための対応はとられるのでしょうか?
A
計算の簡素化、すなわちセーフ・ハーバー(SH)の導入が必須であると考えられます。
高税率国の日本で、膨大な数の子会社の実効税率を計算するという非効率
令和5年度税制改正ではデジタル課税第2の柱「所得合算ルール(IIR)」の導入が決まりましたが、第2の柱の国内立法化がこれで完結するわけではありません。
与党大綱には以下の記述があります。
軽課税所得ルール(UTPR:Undertaxed Profits Rule)と国内ミニマム課税(QDMTT:Qualified Domestic Minimum Top-up Tax)を含め、OECDにおいて来年以降に実施細目が議論される見込みであるものについては、国際的な議論を踏まえ、令和6年度税制改正以降の法制化を検討する。
本誌取材によると、税制当局は今のところUTPRとQDMTTについて、最速で令和7年4月1日以降に開始する事業年度から適用することを念頭においています。
日本で適格IIRが導入されるならば、日本の多国籍企業グループが他国で導入されたUTPRの対象となるケースは基本的にありません。このため、日本企業の関心は目下、QDMTTがどのようなものになるかに集まっています。
QDMTTはその名の通り国内におけるミニマム課税であり、例えば日本がQDMTTを導入した場合、多国籍企業グループのうち連結財務諸表を構成する日本の子会社等が対象となります。日本は高税率国であり、研究開発税制等の租税特別措置の適用を勘案したとしても、日本の子会社等の実効税率が15%を割り込むことは考えにくいにもかかわらず、場合によっては三桁にものぼる日本の子会社等の実効税率を計算するのは非常に効率が悪いと言えます。そこで企業側からは、QDMTTについても、計算の簡素化、すなわちセーフ・ハーバー(SH)が必須、との声が挙がっています。
行政ガイダンスではCbCRを活用した時限的SH及び恒久SHを認めるべき旨を明記
この問題については、2月にOECDが公表した行政ガイダンス(Administrative Guidance)で明確化が図られており、「SH及び罰則緩和」(2022年12月、OECD)で示された時限的SH(既存のCbCRを活用して簡易に実効税率を計算する等の措置)及び恒久SHが、QDMTTでも認められるべきことが記載されています(パラ118.45、109頁)。令和6年度税制改正においてQDMTTを導入するならば、企業にとってはこれらの措置も併せて確実に導入される必要があるでしょう。
子会社所在地国とのQDMTTの相違による紛争への懸念
Q
QDMTTが他国でも導入された場合、親会社がQDMTTを導入する子会社所在地国との紛争に巻き込まれるリスクはないでしょうか?
A
OECDの行政ガイダンスによると、QDMTTは日本のみならず他国でも導入され、しかも、各国によるカスタマイズが可能とされているため、親会社(日本企業)は、日本と異なるQDMTTを導入する子会社所在地国との紛争に巻き込まれるリスクがあります。
企業からは「QDMTTはモデル・ルールに完全に準拠すべき」との声
最近ではシンガポールがQDMTTに相当する制度を導入することを発表しています。IIRの計算式は概ね次頁の通りとなっており、他国におけるQDMTTは、親会社所在地国におけるトップアップ税額の計算上、控除項目となります。これは、他国においてQDMTTが課されるならば、それを親会社所在地国におけるIIRの計算上、除外しないと、二重カウントになってしまうからです。
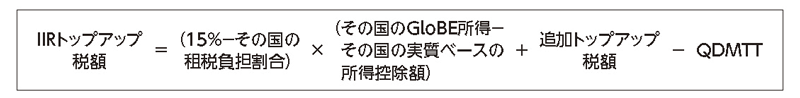
次頁の計算式から分かる通り、親会社所在地国の税務当局としては、税収の逸失を防止する観点から、他国のQDMTTについて、本当に「適格」(Qualified)なのか、その金額は妥当なのか(過剰ではないか)ということに目を光らせることになります。
納税者である日本企業の間では、こうした論点を巡って親会社所在地国やQDMTTを導入する子会社所在地国を交えた紛争に巻き込まれるリスクへの強い懸念が広がるとともに、「QDMTTはモデル・ルールに完全に準拠すべきであり、各国によるカスタマイズを許すべきではない」との声が挙がっています。
こうした声もあり、OECDの行政ガイダンスでQDMTTの制度設計についてどのような言及がなされるか注目が集まっていましたが、企業にとってはやや失望を禁じ得ない内容となっています。行政ガイダンスによれば、QDMTTは「GloBEルールの設計と整合しなければならない」「GloBEルールの結果と整合しなければならない」との2大原則を掲げつつ(パラ5、99頁)、個別の項目を見ると、「QDMTTでは、実質ベースの所得控除(有形資産や給与の一定割合をGloBE所得から控除する仕組み)を講じる必要はない」(パラ118.37、107頁)、「デミニマス除外を講じる必要はない」(パラ118.39、107頁)といった任意の規定が目立ちます。要するに、各国によるカスタマイズが可能ということです。
会計基準の相違に起因するQDMTT相当額の乖離
Q
最終親会社所在地国とQDMM導入国の間で会計基準の相違によりQDMTT相当額に乖離が生じた場合、いずれが採用されるのでしょうか?
A
QDMTT相当額として算出される額に一定の乖離が生じれば、これが紛争の原因となる恐れがあります。
会計上のQDMTTの乖離の“許容範囲”を行政ガイダンスで整備へ
IIRは最終親会社の使用する特定財務会計基準(日本企業で言えば日本基準やIFRS等)、QDMTTは場合によっては適格財務会計基準(その国において一般的に公正妥当とされる会計処理の基準であり、特定財務会計基準を除く)を使用してトップアップ税額の計算を行うことが通常想定されます。その結果、最終親会社所在地国とQDMM導入国で、使用する会計基準の相違によって、QDMTT相当額として算出される額に一定の乖離が生じる可能性があり、これが紛争の原因となる恐れがあります。この問題について行政ガイダンスには、どの程度の乖離であれば許容されるのかについて、QDMTT特有のガイダンスを整備する旨の記載がありますが(パラ118.15、103頁)、現状ではその内容は明らかになっていません。
3月16日、OECDは第2の柱に関する公聴会を開催し、企業・実務家等からGloBE情報申告書や税の安定性について意見を募ったところ、企業からはQDMTTについて、異なる制度の乱立への懸念や、制度設計の詳細についての関心が数多く示されました。OECDは、QDMTTについては今後も作業を継続するとしており、引き続き動向に注目しておく必要があります。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















