解説記事2023年04月24日 最新判決研究 1年当たり平均額法により役員退職給与適正額が算定された事例(2023年4月24日号・№976)
最新判決研究
1年当たり平均額法により役員退職給与適正額が算定された事例
東京地裁令和2年3月24日判決(平成28年(行ウ)第589号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、栃木県内に所在し、肉用牛の飼育、販売等を営む株式会社(昭和62年4月設立時には有限会社、平成21年6月に株式会社移行)であるが、平成24年12月25日に同社の取締役を退任した甲に対して、平成25年3月1日、退職慰労金2億円及び特別功労金7000万円合計2億7000万円(以下「本件役員退職給与」という。)を支給し、同金額を損金の額に算入して平成25年3月期分法人税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)をした。これに対し、所轄税務署長は、本件役員退職給与につき、役員退職給与適正額は6250万円余(以下「本件役員退職給与適正額」という。)であるとして、同金額を超える2億749万円余は損金の額に算入できないとし、翌期へ繰り越す欠損金額(申告額4億2081万円余)から当該損金不算入額を減額する更正処分(以下「本件更正」という。)をした。
Xは、本件更正を不服とし、前審手続を経て、国(被告)に対し、その取消しを求めて本訴を提起した。
(2)甲は、Xの設立と同時に同社の代表取締役に就任し、以後代表取締役を務めていたが、平成8年3月9日、代表取締役及び取締役を退任(以下「平成8年退任」という。)し、同日、甲の子乙が代表取締役に就任して現在に至っている。しかし、甲は、平成15年11月13日、Xの取締役に就任(以下「平成15年就任」という。また、平成8年退任から平成15年までの間を「本件役員退任期間」という。)し、平成24年まで取締役を務めた(平成24年の退任を以下「平成24年退任」という。)。なお、甲は、肉用牛の繁殖、販売等を業とするY(昭和54年8月24日有限会社として設立、平成21年6月17日に株式会社に移行)の代表取締役を設立から平成24年12月25日まで務めていた。
また、Xは、平成19年4月頃以降、甲に対し、役員報酬を月額25万円を支給していたが、平成25年1月11日、甲に対し、平成24年6月から同年12月までの役員報酬として合計525万円(月額75万円)を追加支給した(以下同追加支給額を「本件遡及増額」という。)。そして、Xは、この本件遡及増額を基にして、本件役員退職給与のうち、退職慰労金2億円については、いわゆる功績倍率法により、最終報酬月額100万円、勤続年数25年、功績倍率8倍として算定した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、本件役員退職給与における不相当に高額な部分の金額の有無及びその額であり、具体的には、国が主張する本件役員退職給与適正額の算定(以下「本件算定」という。)の合理性の有無である。
2 国の主張
(1)役員退職給与適正額の算定方法については、一般に、平均功績倍率、1年当たり平均額法及び最高功績倍率法がある。他方、1年当たり平均額法は、平均功績倍率法を用いることが不合理であると認められる特段の事情がある場合には、同業類似法人の抽出が合理的に行われる限り、合理的な方法というべきである。そして、本件においても、本件遡及増額が不自然であるなど、功績倍率法を用いることに合理性が認められないので、1年当たり平均額法によって甲の役員退職給与適正額を算定すべきである。
本件算定に用いた類似法人の本件各抽出基準等は、①抽出対象地域について、Xの所在地である栃木県と経済事情が類似する地域である関東信越国税局及び隣接局の管内を対象とし、②事業の類似性を判断する要素である業種について、Xと同種の事業である日本標準産業分類における大分類「A−農業、林業」の中分類「01−農業」の小分類「012−畜産農業」とし、③事業規模の類似性を判断する要素である売上金額について、Xの平成25年3月期の売上金額の2分の1から2倍の範囲内(売上金額の倍半基準)とし、④代表取締役等に対し退職給与の支給があり、かつ、その退任理由を甲と同じく普通退職としており、業種の同一性、規模等の近似性等のいずれの点においても、同業者の類似性の基礎的要素を欠くものではなく、合理的なものである。そして、本件役員退職給与の適正額は、類似法人の本件各支給事例(10件)の1年当たり役員退職給与の平均額150万7897円に、甲の勤続年数10年(平成15年11月13日から同24年12月25日まで)を乗じて算定すると、1507万8970円となる。
(2)国が本件同業類似法人を抽出の基準とした日本標準産業分類は、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として設定された統計基準であるから、同業類似法人の業種の同一性を確保する上で、十分な合理性、客観性を有している。
(3)次に、類似法人抽象の地域の範囲については、本件において、抽出対象地域を、順次、Xの本店所在地である真岡税務署管内から、栃木県内、関東信越国税局の管内、隣接局の仙台国税局、東京国税局及び名古屋国税局の管内にまで拡大した結果、小分類「畜産農業」に該当する同業類似法人における役員退職給与の支給事例を10事例抽出したのである。
3 Xの主張
(1)本件同業類似法人は、いずれも細分類「養鶏業」又は細分類「養豚業」を営むものであるが、後記に述べるとおり、小分類「畜産農業」のうち、細分類「養鶏業」及び細分類「養豚業」と、Xが営む細分類「肉用牛生産業」とは、その事業の特質等を大きく異にする以上、小分類「畜産農業」を営む法人であることを抽出基準としなければXの同業類似法人を得られないなどの特段の事情がない限り、細分類「肉用牛生産業」を営む法人であることを抽出基準とすべきである。
(2)役員給与が不相当に高額である場合の課税は、概算課税ではなく、納税者が訴訟等において推計課税のような実額反証をする余地もないのであるから、役員給与が不相当に高額であるか否かを判断するための同種の事業を営む法人の業種の類似性についても、当然にかなり厳格なものが要求されるものと解すべきである。
(3)形式的には役員に就任していない者であっても、実質的に法人の経営に従事している者については、法人税法2条15号に規定する「役員」とみなされることになるから、同施行令70条2号に規定する「業務に従事した期間」には、実質的に法人の経営に従事していることにより「役員」とみなされる期間も当然に含むものと解される。
甲は、本件役員退任期間において、Xの経営管理、経理に関する決裁及び判断、決算書及び税務申告書の承認、事業投資の意思決定、事業投資に必要な資金調達等を行っていたものであり、実質的にXの経営に従事していたといえる。
(4)平均功績倍率又は1年当たり役員退職給与額の平均額により役員退職給与適正額を算定することとした場合には、同業類似法人の平均的な退職給与の額を超える部分が不相当に高額な部分の金額であるということになるが、そのような解釈は、「不相当に高額」という法人税法34条2項の文言に合致しない。
(5)以上のとおり、①本件各抽出基準等がXの同業類似法人を抽出するための基準等として合理的なものとは認められないこと、②本件指示等に対する税務署長等による調査が適切に行われたものとは認められないこと、③本件元取締役が実質的にXの代表取締役としての職責を果たしていたこと、④本件算定が、功績倍率を用いた算定方法によることがXにとって有利となるか否かの検討なく、1年当たり役員退職給与額を用いた算定方法によっていることからすれば、1年当たり平均額法により算定された金額を、本件役員退職給与適正額と認めることはできない。
三、判決要旨
請求棄却。
(1)役員退職給与適正額の算定に当たっては、複数の方法が考えれるものの、そのいずれを選択するかにかかわらず、同業類似法人の役員退職給与の支給事例が適切に抽出及び選択され、かつ、役員の勤続年数が適正に認定及び評価されることが前提となるものである。まず、中でも、甲と退職の事情又は役職を異にする役員に対する支給事例を用いていることの適否は、当該支給事例それ自体から、その適否を判断し得るものであり、かつ、その適否がその後の検討の前提ともなることから、これをまず検討することとする。
(2)本件支給事例8は、Sファームの取締役であったAに対する退職給与の支給事例であり、当該支給に係る同人の取締役の退職は、Sファームによる解任を原因とするものであったことがうかがわれ、本件においてはこれに反する積極的な証拠はない。法人税法施行令70条2号は、役員退職給与適正額の算定に当たって「退職の事情」を考慮すべきことを明文で定めており、本件のような辞任の場合と株主総会による決議を要する解任の場合とでは、退職の事情が異なると認められる上、一般に、解任手続が採られた場合に、役員退職給与が支給されないか又は役員退職給与の額が支給規程の定めにより算出された額よりも減額されることがあることは、当裁判所に顕著である。
また、本件支給事例2及び本件支給事例10はいずれも監査役に対する退職給与の支給事例であるが、取締役と監査役とではその職務内容に明らかな相違があることに照らし、仮に、同程度の最終月額報酬額や勤務年数の者であったとしても、一般に、取締役と監査役とで支給される役員退職給与の額が異なることがあることも、当裁判所に顕著である(このことは、本件支給事例2に係る法人において、同一の事業年度での役員退職給与の支払につき、ほぼ同じ勤続年数であるとされているにもかかわらず、代表取締役に対するものと監査役に対するもの(本件支給事例2)とで、その金額に3倍を超える差が生じていることからも、うかがわれるところである。)。
以上によれば、本件役員退職給与適正額の算定に当たって、本件支給事例2、本件支給事例8及び本件支給事例10を用いることは合理性を欠くというべきである。これに反する国の主張は採用することができない。
(3)法人税法施行令70条2号は、同業類似法人について、「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するもの」とのみ規定しており、「同種の事業を営む法人」を抽出するに当たって、産業分類上の同種性を厳格に確保しなければならないと解すべき法令上の根拠は見当たらない。また、法人間における業種、業態等の相違の程度が、各法人における役員退職給与の支給額にいかなる差異をもたらすかについては、その性質上、一般的かつ明確な基準を設けることは困難であるといわざるを得ない上、役員退職給与適正額の算定に当たっては、同業類似法人の役員退職給与の支給事例が複数抽出された上で、その功績倍率の平均値又は1年当たり役員退職給与額の平均額の形で用いられることにより、同業類似法人間の業種、業態等の相違による役員退職給与の支給額に対する影響が平準化される結果、当該法人と同業類似法人との間の業種、業態等の相違による影響も相対的に緩和されるということができる。そして、事業規模等の他の条件との兼ね合いや、十分な数の同業類似法人及び支給事例を確保すべき必要性等にも照らし、ある事業につき、当該法人の事業との間に、社会通念上、業種の共通性が相応にあるということができれば、その事業を営む法人は、「同種の事業」を営むものとして同業類似法人となり得るものと解するのが相当である。
本件についてみると、Xは、肉用牛生産業に該当する肉用牛の飼育、肥育及び販売事業を主たる事業として行う株式会社である。他方、本件各支給事例のうち、前記(2)において判断を示した本件支給事例2、8及び10を除いた各支給事例についてみると、①本件支給事例1は、養豚業を主たる事業とするM牧場の取締役であったAに対する退職給与の支給事例、②本件支給事例3は、養豚業を主たる事業とするP千葉の取締役であったSに対する退職給与の支給事例、③本件支給事例4は、養鶏業を主たる事業とするYファームの取締役であったKに対する退職給与の支給事例、④本件支給事例5及び6は、養鶏業を主たる事業とするN養鶏の取締役であったN及びTに対する退職給与の各支給事例、⑤本件支給事例7は、養鶏業を主たる事業とするT養鶏場の取締役であったTに対する退職給与の支給事例、⑥本件支給事例9は、養鶏業を主たる事業とするA産業の取締役であったSに対する退職給与の支給事例であるとそれぞれうかがわれ、本件においては、これに反する積極的な証拠はない(以下、本件支給事例1、3、4、5、6、7及び9を総称して「裁判所選定支給事例」といい、裁判所選定支給事例に係るS牧場、P千葉、Yファーム、N養鶏、T養鶏場及びA産業を総称して「裁判所選定法人」という。)。
そうすると、裁判所選定法人が主たる事業とするものとうかがわれる養豚業および養鶏業と、Xが主たる事業とする肉用牛生産業とを比較すると、共に日本標準産業分類において小分類「畜産農業」の下に位置付けられているとおり、いずれも、家畜を飼養・飼育して必要な物資を得る事業として、社会通念上、業種の共通性があるということができる。
したがって、本件各抽出基準等は、本件の事実関係の下においては、相応の合理性を有するものであると認められる。
(4)役員退職給与適正額の算定において考慮されるべき退職役員の法人に対する功績は、当該退職役員の役員としての地位に基づく活動により生じるものであるから、役員退職給与適正額の算定において用いられるべき当該退職役員の勤続年数は、原則として、役員の在任期間と一致するものであるが、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。)以外の者でその法人の経営に従事しているものが法人税法上の役員に該当することに鑑みれば、役員の在任期間の他に、その者の法人内における地位や行う職務等からみて、その者が他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事している期間があった場合には、当該期間も通算し勤続年数を算定しなければならないというべきである。
この点、証拠によれば、T養鶏場及びA産業は、それぞれ同族経営による会社であるとうかがわれ、これらの取締役であったT及びSが、それぞれ取締役就任以前から、当該法人を経営する一族に属する者として実質的に法人の経営に従事していた可能性は認め得るものの、Tが昭和37年頃から、Sが平成2年又は平成3年頃から、それぞれ実質的に法人の経営に従事していたと認めるに足りる的確な証拠はない。
そうすると、平均功績倍率法、1年当たり平均額法等に用いるに当たって、本件支給事例7及び9の勤続年数を、それぞれ52年、24年とすることは、役員退職給与の支給を受けた取締役につき職制上使用人としての地位のみを有する使用人として就業していたにすぎない可能性のある期間についても、実質的に法人の経営に従事した期間であったものとして取扱い、1年当たり役員退職給与額を算定する点で、合理的な理由なくXに不利な取扱いをすることとなる可能性を排除することができないから、合理性を欠くというべきである。もっとも、それぞれ、前記認定した商業登記簿の記載から認定できる取締役の在任期間である21年、14年とする限りでは、職制上使用人としての地位のみを有する使用人としての退職給与の支給である可能性がある部分も含めて役員退職給与として取り扱い、1年当たり役員退職給与額を算定するという意味で、Xに有利な取扱いをすることになるから、その限度でなお、Xの同業類似法人における役員退職給与の支給事例としての合理性を認めることができるというべきである。
(5)Xは、少なくとも総資産額がXの総資産額の2分の1を大幅に下回る法人を、Xと法人税法施行令70条2号にいう「その事業規模が類似するもの」と認めることができないとした上で、本件支給事例3に係る法人を除く裁判所選定法人については、総資産額がXの総資産額の2分の1を大幅に下回ることが推認されるから、Xと「その事業規模が類似するもの」と認めることはできず、Xの同業類似法人ということはできない旨主張する。
しかし、本件全証拠によっても、法人間の総資産額の差異が、当該各法人における役員退職給与の支給額に有意な影響を及ぼす旨の知見又は経験則は見当たらない。また、総資産額が、売上げから生じた利益が集積して増加する側面を有するものであって、ある事業年度における事業活動の規模を直ちに示すものではなく、当該法人の事業年度における事業活動の規模を端的に示す指標である売上金額と重ねて考慮しなければ、「事業規模が類似するもの」の抽出において直ちに合理性を欠くことになるとは解し難い。
(6)認定事実によれば、甲は、本件役員退任期間において、①継続してX内部における決算書や申告書の修正の指示や承認を行い、Xの税務申告業務に関与していた税理士とのやり取りや、XのメインバンクであるA銀行との間でXが受ける融資に関する交渉及び毎年の決算報告の説明を行うなど、Xの経理面の重要な業務に関する行為を行っていたほか、②継続的に、Xの年度の予算を作成し、実績と比較した上でX代表者乙やXの従業員に対し改善の指示をするなど、Xの予算管理に係る行為も行っていたものであり、さらに、③S農場及びK牧場の各購入並びにO牧場の新設稼働という三度にわたるXの事業拡大の場面において、それぞれ、購入等の意思決定を行うとともに、資金の借入れの実現のため交渉等を行っており、Xの重要な経営判断やその実務処理に実質的に参与したといえる。
そうすると、甲は、本件役員退任期間において、上記①及び②のとおり、継続的に、Xの経理や予算管理に係る業務を担っていたということができ、さらに、本件役員退任期間の中では散発的に行われたものではあるものの、上記③にみたとおり甲がXの重要な経営判断やその実務処理に実質的に参与したことがあったことも併せ勘案すれば、甲は、本件役員退任期間において、継続して、実質的に原告の経営に従事していたと認めるのが相当であり、本件役員退職給与適正額の算定における平均功績倍率法、1年当たり平均額法等において用いられるべき甲の勤続年数には本件役員退任期間も通算されるべきである。
なお、平成8年の退任は、当時問題を起した取締役Kの退任に連座して、甲自身の責任も取る形で退任していると認められるから、平成8年の退任までの間の本件元取締役のXに対する功績については、平成8年の退任の際に既に評価し尽くされて清算されたものと認められる。
以上によれば、本件役員退職給与適正額の算定において用いられるべき甲の勤続年数は17年(平成8年3月9日から平成24年12月25日。以下、同期間を「本件評価期間」という。)とすべきであり、これを10年とした本件算定は、その限度で合理性を欠くというべきである。
(7)法人税法施行令70条2号は、法人税法34条2項に規定する「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」につき、「その退任した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額(役員退職給与適正額)を超える場合におけるその超える部分の金額」を定めているのであるが、平均功績倍率法又は1年当たり平均額法における役員退職給与適正額の算定においては、同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象された、より平準化された数値である、平均功績倍率又は1年当たり役員退職給与額の平均額のみならず、当該退職役員又は当該法人に係る事情である、最終月額報酬額や当該退職役員の勤続年数も併せ考慮されているのであるから、これらにより求められた金額を「その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」とし、これを超える部分を「不相当に高額な部分の金額」と解することが、法人税法34条2項の文言や、役員に対する退職給与のうち隠れた利益処分としての性質を有する部分について損金算入を認めないこととした同項の趣旨に合致しないものとはいえない。
そして、最高功績倍率法及び1年当たり最高額法の算定過程には、用いられる役員退職給与の支給事例に係る同業類似法人間に通常存在する諸要素の差異やその個々の特殊性が捨象される過程が存在せず、平均功績倍率法及び1年当たり平均額法と比較して合理性において劣ることは前記に説示したとおりである。
本件においては、前提事実のとおり、甲は、遅くとも平成19年4月以降、役員報酬として月額25万円の支給を受けていたが、平成24年の退任の後である平成25年1月11日に、役員報酬の遡及的な追加支給がされ、その最終月額報酬額は、月額25万円の4倍に上る月額100万円とされたものである(本件遡及増額)。そして、Xは、本件遡及増額につき、会社法361条1項の趣旨に反しない旨を主張するのみで、大幅に増額する必要があった合理的な理由を何ら主張せず、本件において、これを認めるに足りる証拠もない。したがって、本件役員退職給与適正額の算定については、功績倍率を用いた方法によることが不合理であると認められる特段の事情があるといえ、1年当たり平均額法が合理的な方法となるというべきである。
(8)以上によれば、本件算定は、①1年当たり役員退職給与額の平均額の算定に当たって本件支給事例2、8及び10を用いている点、②本件支給事例7の勤続年数を21年とすべきところを52年とし、本件支給事例9の勤続年数を14年とすべきところを24年としている点及び③本件元取締役の勤続年数を17年とすべきところを10年としている点について、合理性を欠くものの、その他の算定過程はいずれも合理性を肯定できるから、各1年当たり役員退職給与額の平均額を基に、甲の勤続年数を17年として1年当たり平均額により算定した額を、本件役員退職給与適正額と認めることができる。
これを計算すると、1年当たり役員退職給与額の平均額及び本件役員退職給与適正額は、それぞれ、192万2528円(1円未満切上げ)、3268万円余となり、本件役員退職給与の額2億7000万円のうち、上記の本件役員退職給与適正額を超える2億3731万円余が不相当に高額な部分の金額となる。
四、解説
はじめに
法人税法では、役員給与について、それが年次給与であれ、退職給与であれ、「不相当に高額」の部分を損金不算入としている。この場合の「相当性」の判断については、本来、当該役員の役務提供の価値によって判断されるべきであろうが、実務的には、当該価値の判断が困難であるということで、いわゆる類似法人の支給状況と比較して判断している。本件においても、Xが支給した役員退職給与が不相当に高額であるとした本件更正につき、国側は、類似法人10件の支給事例に基づいて、1年当たり平均額法を適用すれば本件更正は適法である旨主張している。これに対し、Xは、当該支給事例の全てが適切でない旨争うこととなった。このように、本件においては、類似法人の適否と具体的な算定方法の適否が争われたものである。
なお、本判決は、3年程前のものではあるが、事案の内容と本判決の判示が実務に参考になるものと考えられたので、紹介することにした。
1 過大役員給与の損金不算入
(1)法人税法34条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(〈略〉)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。そして、法人税法施行令70条1項1号イは、当該相当性の判定については、まず、年次給与につき、原則として「当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額」と定めている。
他方、役員退職給与については、法人税法施行令70条1項2号は、「当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額」と定めている。
(2)以上のように、同じ給与でありながら、年次給与と退職給与とでは、その相当性の判断要素について若干の差異を設けている。すなわち、年次給与においては、①当該役員の職務の内容、②その内国法人の収益状況及び③使用人に対する給与の支給状況が定められているが、退職給与に関しては、それらは明記されずに、①当該役員のその内国法人の業務に従事した期間及び②その退職の事情が明記されている。これらを対比して、退職給与側から考察してみると、①当該退職役員の職務の内容(職務上の功績)よりも勤務期間の方が評価されるのか(勤務期間が長ければ良いのか)、②その内国法人の収益状況(退職時の経営状態や利益剰余金の基準度合)は無視してよいのか、③使用人との支給バランスは関係はないのか、等の疑問が生ずる。しかし、これらの事情は、実際の役員退職給与の支給に当たっては、何らかの形で検討されるはずである。
このような状況において、類似法人との比較、すなわち、「その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模に類似するもののその役員に対する支給状態」と対比することについては、両者とも共通している。しかし、この場合、「同種の事業を営む法人でその事業規模の類似するもの」すなわち類似法人をどのようにして選定するのか、そして、その類似法人における支給状況と対比して判定する具体的な算定方法が問題となる。このような選定方法なり算定方法は、決め手となるような方法がないので、結局、裁判例の動向によって判断せざるを得ないことになる。そこで、以下、この二つの方法と現状の問題点について、検討する。
2 類似法人の選定と問題点
(1)類似法人の選定については、通常、一時的には、法人が支給した役員退職給与の額を不相当に高額であるとして課税処分を行う課税庁が行うことになる。この場合、課税庁の選定基準については、一般的に、本訴において国も主張しているように、①抽出対象地域については、当該法人と経済事情が類似するということで、同一の税務署管内又は当該税務署を管轄する国税局の管内、更には、当該国税局に隣接する国税局の管内に及ぶこともある、②事業の類似性を判断に要する業種については、当該法人と同種の事業である日本標準産業分類における大分類の中分類の小分類にすることとし、③当該法人と事業規模の類似性を判断する要素については、売上金額について、当該法人の売上金額の2分の1から2倍の範囲内(倍半基準)とし、④当該類似法人において、代表取締役等に対して退職給与の支給があり、かつ、当該法人の退任役員とその退任事由と同じくするもの、等である。
(2)このような外形的な選定基準については、一応の合理性があるものと考えられる。しかし、幾つかの問題を抱えている。そもそも、このように抽出される類似法人のデータは、それぞれの税務署に提出された法人税申告書等の内容に基づくものであろうが、納税者側はその存在と内容自体は確認できないのである。特に、争訟の段階においては、争う相手である国側のみが知っているデータを対立する納税者側が信頼できないというのも無理からぬ所がある(注1)。この点、裁判所(裁判官)は、国同士の機関であるから相互の信頼関係もあろうし、あるいは、裁判所(裁判官)に対しては、類似法人の実名等の詳細なデータが提出されている場合もあろう。もちろん、裁判所(裁判官)も、本件でもそうであるが、国側が主張する類似法人のデータを鵜呑みにしているわけではない(注2)。
このような問題はともかくとして、このような類似法人のデータによる比較は、あくまでも外形的なものに過ぎず、類似法人の役員がどの程度当該法人の経営に貢献してきたのか(あるいは貢献しているのか)、そして、争う側の法人の役員の貢献がどの程度であって、類似法人の役員の貢献度との差異はどの程度であるのか、という役員の経営に対する役務提供の対価がどの程度であるべきかという本質的な比較は期待し難いものと言える。もっとも、そのような本質的な比較は、実務上困難であるということで、前述のような外形的な比較に頼らざるを得ないというのであれば、そのような外形的比較に何らかのアローアンスを加えるべきであろう。
例えば、後述する具体的な算定方法である効率倍率法なり1年当たり平均額法を採用するにしても、類似法人における最高値を採用するとか、あるいは、平均値に2~3割加算するとか、という方法も考えて然るべきであると考えられる。
3 適正額の算定方法と問題点
(1)前述した類似法人における役員退職給与の支給状況等との比較を前提にして、役員退職給与の適正額についての具体的な算定方法には、一般的に、次の方法が採用されている。
① 功績倍率法
次の算式によって、適正額を算定する方法である。
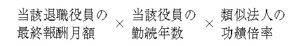
この功績倍率については、類似法人の平均値を採用したものを平均功績倍率法と言い、類似法人の中で最高値を採用したものを最高功績倍率法という。
② 1年当たり平均額法
次の算式によって、適正額を算定する方法である。
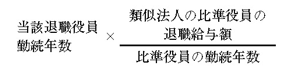
この方法の場合にも、1年当たり平均額につき、類似法人における平均値を採用する方法と最高値を採用する方法がある。
そのほかにも、従前の裁判例においては、統計的手法によって役員退職給与の適正額を算定する方法(注3)、国家公務員の退職手当の額に準じて適正額を算定する方法(注4)等が採用されているが、いずれも、一般的ではない。
(2)前述の功績倍率法の中でも、平均功績倍率法が最も合理的であると解されており、裁判例においても最も多くが支持されている。例えば、前記1で述べたように、納税者側は類似法人における役員退職給与の支給について正確な情報を得ることができないところ、巷間言われている適正功績倍率3.0を適用して役員退職給与を支給したが、所轄税務署長が類似法人の平均功績倍率2.1を適用した課税処分の適否が争われた事案がある。この事案につき、東京地裁昭和46年6月29日判決(行裁例集22巻6号885頁)は、税務署長が選定した類似法人11社にはそれぞれ原告との類似性に問題があり、かつ、11社の功績倍率の平均値(2.1)を上回る類似法人の功績倍率の数値に比しても、原告が採用した3.0は不当とは言えないとして、当該課税処分を取り消した。ところが、控訴審の東京高裁昭和49年1月31日判決(税資74号293頁)は、平均功績倍率法を適用して役員退職給与適正額を算定することこそ法人税法の趣旨に合致する旨判示して、当該課税処分を適法として、上告審の最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決(税資80号259頁)も、原判決を支持している。
このような事案と各判決の考え方を考察すると、平均功績倍率法には、種々の問題はあるが、結局、裁判官も、平均功績倍率法に頼らざるを得ないという裁判上の限界を示すことにもなる。かくして、その後の裁判例においても、平均功績倍率法が多用されることとなり、例外的に、最高功績倍率法が採用されることにもなる(注5)。
なお、功績倍率法については、他の算定要素である退職役員の最終報酬月額及び勤続年数についても、本件でも問題になっているように、それぞれの個別事案の事情によって問題が生じることになる(注6)。
(3)他方、1年当たり平均額については、その算定要素が退職役員の勤続年数に限られているので、勤続年数が長い程適正額が増加することになる。その点では、功績倍率法の算定要素である退職役員の最終報酬月額が当該役員の会社に対する貢献度の指標となるというのであれば、適正額を算定する上で、功績倍率法よりも劣ることになる。しかし、最終報酬月額は、常に、当該会社に対する貢献度の指標になるとは限らない。例えば、会社代表者が、滅私奉公的に自身の報酬を押えてまでも会社に尽してきたような場合には、それが徒になって、退職給与額も不当に安くなるであろうし、その逆であれば、退職給与額が不当に高額に算定されることになる。また、前掲(注6)の高松地裁平成5年6月29日判決のように、何らかの事情によって最終報酬月額が不当に低額である場合もある。
そのため、1年当たり平均額についても、類似法人の平均値を採用する場合と最高値を利用する場合もあるが、いずれを選択するかは、当該事案の事情を総合判断して決定すべきものと考えられる(注7)。
4 本件役員退職給与の適正額
(1)本件においては、Xの取締役を退任した甲に対する役員退職給与の適正額につき、Xが、退職慰労金2億円及び特別功労金7000万円合計2億7000万円(本件役員退職給与)支払ったことが法人税法34条2項に定める「不相当に高額」に該当するか否かが争われたものである。Xは、本件役員退職給与の支給に当たって、甲の退職時に、それまで月額25万円の報酬を月額100万円に引き上げ、勤続年数25年、功績倍率8倍とし、功績倍率法によって退職慰労金を2億円と算定し、それに特別功労金7000万円を加算したものである。
これに対し、所轄税務署長は、甲の役員退職給与適正額を6250万円余とし、それを上回る2億749万円余は損金の額に算入できないとする課税処分(本件更正)を行った。そして、本訴において、国は、本件のように、役員退任時に報酬の額を増額している場合には功績倍率法は適用できないとし、類似法人の本件各支給事例10件の1年当たり平均額150万7897円を基とし、甲の勤続年数を10年に修正し、1年当たり平均額を適用し、その適正額は1507万8970円になると算定し(本件算定)、本件更正は適法である旨主張した。
かくして、本訴の審理の段階では、主として、①本件同業類似法人の抽出の合理性等、②本件役員退職給与適正額の算定に用いるべき支給事例の適格性、③甲の勤続年数及び④1年当たり平均額を用いることの合理性等が争われることになった。
(2)かくして、本判決は、上記の具体的な各争点について具に検討し、判断を下している。まず、本判決は、本件支給事例10件のうち、「8」は、当該退職の事情が解任を原因とするものであるから、「退職の事情」が異なるとし、「2」及び「10」は、監査役に対するものであるから、取締役とは異なるとし、残りの7事例(裁判所選定支給事例)に基づいて判断すべきとした。そして、本判決は、日本標準産業分類における小分類「畜産農業」の中に養豚業及び養鶏業も含まれ、しかもXが営む肉用牛生産業の本件支給事例が含まれていないことにつき、「社会通念上、業種の共通性がある」として、不問にした。また、本判決は、本件支給事例7及び9の勤続年数のそれぞれの52年及び24年について、使用人時代も含まれているとし、それぞれ21年と14年に修正した。
次いで、本判決は、甲の役員勤続年数につき、平成8年の退任については、不祥事を起こした役員と連座して退任したものであるからそれまでの期間は含まれないとし、平成8年以降から24年までの17年間は実質的に経営に関与した期間もあるのでその年数も含むべきとすべき旨判示した。そして、本判決は、役員退職給与適正額の算定方法については、平均功績倍率法又は1年当たり平均額(平均値)法の方が最高功績倍率法又は1年当たり平均額法の最高値よりも優れている旨判示し、本件においては甲の最終報酬月額を25万円から100万円に引き上げたことが不合理であるから、1年当たり平均額(平均値)法により算定すべき旨判示した。その結果、裁判所選定支給事例7件に基づくそれらの1年当たり平均額が192万2528円となり、甲の勤続年数17年を乗じると、適正額は3268万円となり、2億3731万円余が不相当に高額な部分の金額となるから、その範囲内の本件更正は適法である旨判示した。
(3)前記1及び2で述べたように、法人税法が役員退職給与の「不相当に高額」の部分の損金性を否定しているところ、その「相当性」の判断については、本来であれば、当該退職役員の法人に対する貢献度について実質的に判断すべきであるが、実際には、類似法人における役員退職給与の支給事例と比較して、判断されている。そして、この場合、問題となるのが、当該類似法人の選定と比較する場合の具体的な算定方法であり、後者については、平均功績倍率法が最も重視されており、それを補完する形で1年当たり平均額が採用されている。
本訴においても、これらの問題が多面的にかつ厳しく争われたのであるが、本判決は、それらの争点について具に検討し、判断を示している。その点では、本判決は、類似の事件に関して参考になるものである。しかしながら、それらの個々の判断については、やや難点も見受けられる。まず、類似法人の選定について、本判決は、国が選定した本件支給事例10件のうち、3件については、退職事由が解任であることや監査役の対するものであるということで除外したことについては首肯できるとしても、類似法人を日本標準産業分類の小分類「畜産農業」から抽出したことにつき、10件全てが養豚業や養鶏業であってXが営む肉用牛産業が1件も含まれていないことの合理性を安易に容認したことには首肯し難いところがある。筆者自身、農業高校で学び農林省に勤めた経験に照らすと、同じ畜産でも、牛と豚・鶏では飼育、経営方法等に相当の差異があるので、本件支給事例の中に1件もXと同じ同業者が選定されていないことに違和感がある。この場合、選定上無理であるというのであれば、適正額の判定上何らかの斟酌(例えば、最高値を採用)があって然るべきであろう。
また、役員の勤続年数について、本件支給事例の2件について使用人時代も含まれているとして修正したことと、甲の勤続年数を実質的に経営に従事していた期間を含めて17年としたことは首肯し得るとしても、甲の平成8年退任時までの8年間について退職給与の算定の根拠としなかったことについては、当該退任の事由をもっと精査する必要があったように考えられる。次に、適正額の算定方法について、国も本判決も、甲の最終報酬月額が遡及増額されたことの一事をもって平均功績倍率法の適用は認められないと判断しているが、元々、当時の社会通念上、創業者である役員の報酬月額が25万円というのも異常に低いわけであるし、かつて月額120万円の報酬を支払っていた旨のXの主張もあるわけであるし、前掲高松地裁判決((注6)参照)の例にも照らし、もっと弾力的な判断があって然るべきであると考えられる。また、1年当たり平均額法(平均値)によるにしても、前述のような諸事情を考慮した場合には、裁判所選定事例の中で最高値を採用する余地もあったものと考えられる。
5 本判決の意義と問題点
以上のように、本件は、役員退職給与の適正額が争われたものであるが、事案の内容としては、対象役員の甲が、会社の創業者ではあったが、中途での退任、その退任から復職までの経営の関与等が「役員」としてみなされるかどうかという、勤続年数それ自体が問題となっており、最終報酬月額を遡及増額するという問題もあり、更には、Xが肉用牛生産業という特別の事業を営んでいたこともあって類似法人の選定にも問題を有していた。
本判決は、これらの諸問題について、当事者の各主張に照らし、詳細に事実認定を行い、それらを踏まえた判断を下している。その点では、類似事案の参考となるものであって、参考判決として重視されるべきであろう。しかしながら、前述してきた役員退職給与の適正額の判定方法論に照らし、また、本件の事実関係に照らし本判決の個々の判断については、前記4で述べたような問題を残しているものと考えられる。
(注1)この場合、争訟段階で、国側又は原処分庁が抽出したデータの内容を当該納税者に開示する方法も考えられるが、それも、守秘義務の問題があるから困難であろう。また、それが可能であったとしても、当該納税者としては、抽出されたもの以外に自己に有利なデータがあるかも知れないと考えるであろう。
(注2)本判決においても、比準事例における一部の類似法人が除外されているが、訴訟の段階で類似法人の選定替え、否定等が行われた事例として、札幌地裁平成11年12月10日判決(税資245号703頁)、東京地裁昭和46年6月29日判決(行裁例集22巻6号885頁)等参照。
(注3)大阪地裁昭和44年3月27日判決(税資56号316頁)参照。
(注4)大阪高裁昭和54年2月28日判決(税資104号531頁)参照。
(注5)最高功績倍率法が適用された事例として、岐阜地裁平成2年12月26日判決(税資181号1104頁)、東京地裁昭和51年5月26日判決(税資88号862頁)、東京高裁昭和52年9月26日判決(税資95号597頁)、東京地裁昭和55年5月26日判決(訟務月報26巻8号1452頁)、仙台高裁平成10年4月7日判決(税資231号470頁)等参照。
(注6)例えば、最終報酬月額につき、高松地裁平成5年6月29日判決(税資195号709頁)は、退職役員の退職時の最終報酬月額が低額過ぎるとし、同役員が従前受領していた報酬月額を修正した金額を最終報酬月額として平均功績倍率法を適用するのが相当である旨判示している。
(注7)1年当たり平均額(平均値)を適用した事例として、札幌地裁昭和58年5月27日判決(行裁例集34巻5号930頁)、岡山地裁平成元年8月9日判決(税資173号432頁)、昭和61年9月1日裁決(裁決事例集32号231頁)等参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























