解説記事2023年12月11日 ニュース特集 実務に直結する令和6年度の納税環境整備(2023年12月11日号・№1006)
ニュース特集
不正行為に基づく更正の請求も罰則の対象に
実務に直結する令和6年度の納税環境整備
与党の税制調査会は早ければ12月14日にも令和6年度税制改正大綱を取りまとめる予定だが、実務に直結する見直しである納税環境整備の概要が明らかとなった。課税や徴収関係の整備・適正化の観点からは、法人が廃業しても、不正申告を行った法人の代表者に第二次納税義務を課す措置を講じるほか、仮装・隠ぺいした「更正の請求書」を提出した場合も重加算税の賦課対象に加えるなどの見直しが行われる。また、諸外国と同様、日本でもプラットフォーム課税を導入し、本来の制度趣旨に沿わない形で事業者免税点制度の特例や簡易課税制度を適用する国外事業者に対し、各制度の見直しを行う。円滑な申告・納税のための環境整備では、納税者の事前の同意を前提に、すべての処分通知等の電子交付を可能にすることや、法定調書のe-Tax等による提出義務基準を現行の「100枚以上」から「30枚以上」に引き下げる。
廃業も不正申告を行った法人の代表者に第二次納税義務
令和5年度税制改正に引き続き、令和6年度でも課税や徴収関係の整備・適正化が行われる。すでに本誌でお伝えしている通り、仮装・隠ぺい行為に基づき納税申告書を提出した場合だけでなく、「更正の請求書」を提出した場合についても重加算税の対象とする(本誌999号12頁参照)こととしたほか、更正の請求による消費税還付に係る受還付犯の適用を見直す。現行、不正行為に基づき申告書を提出して消費税の還付を受けた者(未遂を含む)については、消費税法において、10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金が科せられることになっている(受還付犯)。しかし、不正行為に基づき「更正の請求書」を提出し消費税の還付を受けた者については、申告書の提出による不正還付と実質的な違いはないにもかかわらず、消費税法において罰則を科すこととされていない。このため、不正行為に基づき「更正の請求書」を提出して消費税の還付を受けた場合(未遂を含む)についても受還付犯と同様の罰則を消費税法において科すこととなった。
また、不正申告を行った法人の代表者等に対する徴収手続が整備される。現状、法人が財産を散逸させた上で廃業する等により納税義務を免れようとする事案が散見されており、税務調査や滞納処分を行う段階では、既にその法人の財産が残存していない場合が多く、滞納国税の徴収が困難になっていることが問題点として指摘されている。また、仮に代表者等が簿外財産や不正還付金といった不正行為に係る財産を創出し、自らが当該財産の移転を受けた場合や、自ら実行して法人外部へ散逸させた場合であっても代表者等に追及できないのがネックとなっている。
このため、不正行為により国税を免れた法人(株式会社・合資会社・合同会社)がその不正行為に係る財産の移転を行っており、かつ、その国税を納付していない場合には、その法人財産から滞納国税の全額を徴収することができないときに限定した措置として、株式50%超(親族等の一定の者と合わせて50%超を含む)を保有する等によりその法人を支配し、不正行為を実行し、及び移転を受け、又は法人外部への移転を実行した代表者等(役員)に対して、「その移転を受けた財産」及び「移転がされた財産(代表者等が移転を実行したものに限り、通常の営業経費の支払等に係る移転は除く)」の価額を限度として不正行為により免れた国税の第二次納税義務を課すこととしている(図表1参照)。
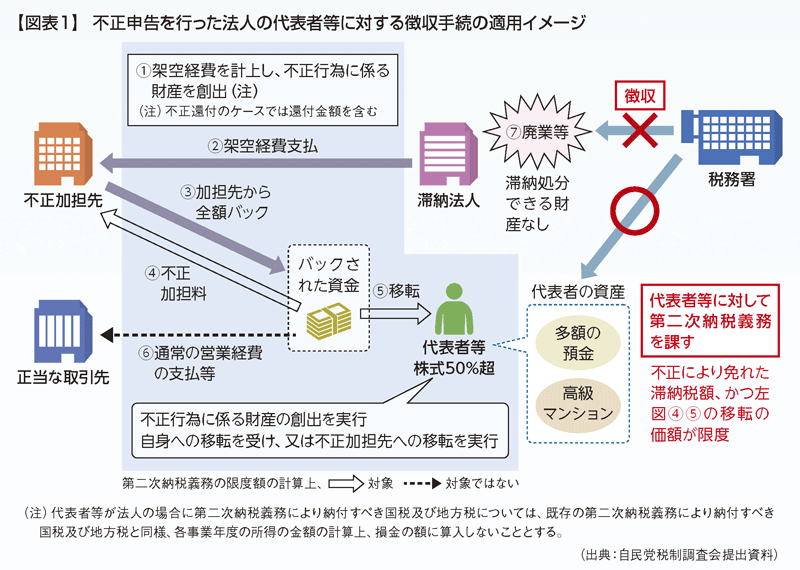
保全差押えの解除期間を6月から2年以内に
そのほか、査察調査の実態を踏まえ、保全差押えの解除までの期間を、2年以内の国税局長が相当と認める期間とする。現行、一定の査察調査等において、国税の税額確定手続(申告・更正等)が行われた後に徴収を確保することができないと認められるときは、国税の税額確定前に、一定の保全差押金額を決定し、直ちに財産の保全のための差押えを行うことができる(金額の決定には国税局長の承認が必要)。ただし、保全差押金額の通知をした日から6月を経過した日までに、その差押えなどに係る国税につき納付すべき額の確定がないときは、保全差押えを解除しなければならないとされている。この点、昨今の査察調査が事案の複雑化に伴い長期化しており、調査の終了前に保全差押えが解除され、徴収手続に支障が生じる可能性があることから、この保全差押えはほとんど活用されていないのが現状だ。このため、保全差押えの解除までの期間を延長することでこの問題を解消する。また、この見直しに併せ、強制換価手続や査察調査が行われた場合等において法定申告期限前に行う繰上保全差押えの解除までの期間(現行:10月)についても、対象となる査察調査の進捗度合や税目等に応じた適切な期間を設定できるようにする。
取引高50億円超のプラットフォーム事業者に課税
デジタル市場が拡大している中、プラットフォームを介して数多くの国外事業者が国内市場に参入しているが、国外事業者の捕捉や調査・徴収が大きな課題となっている。すでに多くの国では、プラットフォームを運営する事業者の役割に着目して付加価値税の納税義務を課す制度(プラットフォーム課税)が導入されており、令和5年度税制改正大綱では、プラットフォーム課税について、「国境を越えた役務の提供に係る消費課税のあり方については、諸外国での制度面の対応や執行上の課題、プラットフォーム運営事業者の役割等を踏まえ、国内外の競争条件の公平性も考慮しつつ、適正な課税を確保するための方策を検討する。」と明記されていた。これを踏まえ、財務省は、「国境を越えたデジタルサービスに対する消費税課税のあり方に関する研究会」を設置し、報告書を取りまとめていた。
令和6年度税制改正では、この報告書を踏まえ、日本においてもプラットフォーム課税を導入することとする。制度の対象を国外事業者が国内向けに行うデジタルサービスに限り、国外事業者が自身のプラットフォームを介して行うデジタルサービスの取引高が50億円を超えるプラットフォーム事業者を対象とする(図表2参照)。
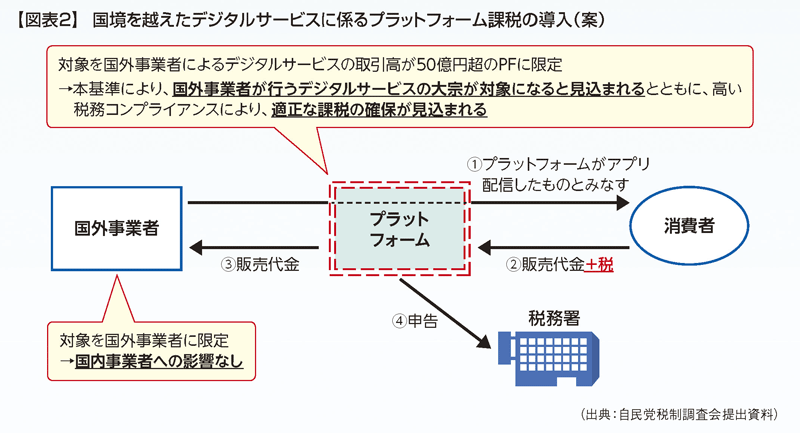
国外事業者の事業者免税点制度特例を見直し
また、消費税法においては、小規模な事業者の事務負担や税務執行コストへの配慮から事業者免税点制度が設けられているのは周知の通りだ。しかし、国外事業者により、本来の趣旨に沿わない形で事業者免税点制度の特例や簡易課税制度などを適用し、売手が納税せず買手が控除を行う、いわゆる「納税なき控除」による租税回避が行われている現状がある。このため、令和6年度税制改正では、①事業者免税点制度の特例の適用の見直し、②簡易課税制度の適用の見直し、③免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の見直しを行うとしている。
前記①では、国外事業者については「給与(居住者分)の合計額」による判定を認めないなどの見直しを行うこととしている(図表3参照)。②に関しては、恒久的施設を有しない国外事業者については、国内における課税仕入れ等が一般的に想定されず、業種ごとのみなし仕入率による控除が適切とはいえないため、簡易課税制度の適用を認めないことに変更する。加えて適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(いわゆる2割特例)の適用についても同様とする。③では、一の免税事業者からの仕入額が、1年間で10億円を超える場合、その超えた部分については、インボイス制度導入に伴う8割控除・5割控除の経過措置の適用を認めないこととしている。
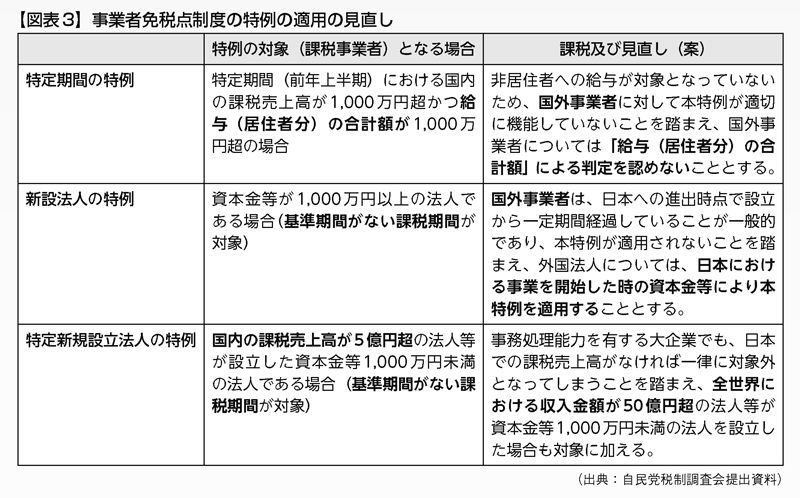
金地金等が200万円以上の場合を追加
そのほか、消費税法では、事業者免税点制度及び簡易課税制度の恣意的な適用を防ぐため、一定の高額な資産を仕入れて仕入税額控除の適用を受けた場合には、その後の2年間、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けることができないこととされている。この高額特定資産は、「1の取引単位につきその税抜き対価の額が1,000万円以上」のものとされているが、金地金等は、1の取引単位の金額の調整が容易であり、同制度の適用を回避することが可能になっている。
このため、令和6年度税制改正では、その課税期間中に仕入れた金又は白金の地金等の合計額が200万円以上である場合を特例の対象として追加し、事業者免税点制度の適用を制限するとしている。
GビズIDならe-TaxのID等は不要
円滑な申告・納税のための環境整備としては、GビズIDとの連携によるe-Taxの利便性向上が挙げられる。現行、e-Taxにより申請等を行う場合には、e-Taxの「ID(識別符号)・パスワード(暗証符号)」を入力して、「電子署名・電子証明書」を付して送信しなければならないとされている。この点、法人がGビズIDを用いて、e-Taxにログインをする場合には、e-Taxの「ID(識別符号)・パスワード(暗証符号)」の入力及びその申請等の際の「電子署名・電子証明書」の送信を要しないこととする。
事前同意ですべての処分通知の電子交付可能
また、現在は9手続とされている処分通知等の電子交付について、納税者の事前の同意を前提に、すべての処分通知等の電子交付を行うことができることとする。その際には、納税者が事前の同意を行う場合のメールアドレスの登録を必須(現行:任意)とするほか、事前の同意を行う方式は、e-Tax上で一括して行う方式へ変更する(現行:個々の処分通知等ごとに同意)。
法定調書の電子提出義務基準を引下げ
法定調書のe-Tax等による提出義務基準の引下げが行われる。現行では、法定調書の種類ごとに、基準年(前々年)の提出枚数が「100枚以上」である法定調書については、e-Tax若しくはクラウド等又は光ディスク等により提出しなければならないとされているが、電子提出の促進に向け、この提出義務基準を「30枚以上」に引き下げる。
自動販売機等の取引は住所の記載不要
消費税の仕入税額控除の適用は、一定の帳簿と請求書等の保存が要件とされているが、一定の取引については、帳簿に①課税仕入れの相手方の住所・所在地及び②特例対象である旨の記載をすることで、請求書等の保存がなくても仕入税額控除を可能とする特例が設けられている。この点、自動販売機による取引や入場券等のように使用時に証票が回収される取引(3万円未満)については、事業者の実務に配慮し、住所等の記載を不要とする。
簡易課税適用者の経理処理方法を一部見直し
また、税抜経理方式を採用する簡易課税適用者が、課税仕入れを行った場合の経理処理方法の明確化を図る。具体的には、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の者からの仕入れについては、原則、仮払消費税額等は生じないが、簡易課税適用者は、インボイスの保存が仕入税額控除の要件とされていないことを踏まえ、継続適用を要件に支払対価の額の110分の10(108分の8)相当額を仮払消費税額等として計上できることとする(2割特例適用者も同様)。これにより、仕入先が免税事業者かどうかを把握する必要はなく、インボイス制度導入前と同じ取扱いとなる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























