解説記事2024年01月22日 最新判決研究 法人税法34条2項の違憲性と役員給与適正額の算定方法(2024年1月22日号・№1011)
最新判決研究
法人税法34条2項の違憲性と役員給与適正額の算定方法
東京地裁令和5年3月23日判決(令和2年(行ウ)第456号)
筑波大学名誉教授・弁護士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする有限会社であるが、平成25年9月期、平成26年9月期、平成27年9月期及び平成28年9月期(以下「本件各事業年度」という。)分の法人税について、兄弟で同社の役員をしている甲、乙及び丙(以下「本件各役員」という。)に対し、後記【表】のとおり、役員給与を支給し(以下「本件各給与」という。)、その全額を損金の額に算入して確定申告をした。これに対し、処分行政庁は、本件各給与の適正額は後記(2)のとおりであり、それを上回る部分は不相当に高額であるとして、本件各事業年度分法人税についての更正等(以下「本件各更正等」という。)をした。処分行政庁の役員給与適正額の算定方式(以下「本件算式」という。)は、次のとおりである。
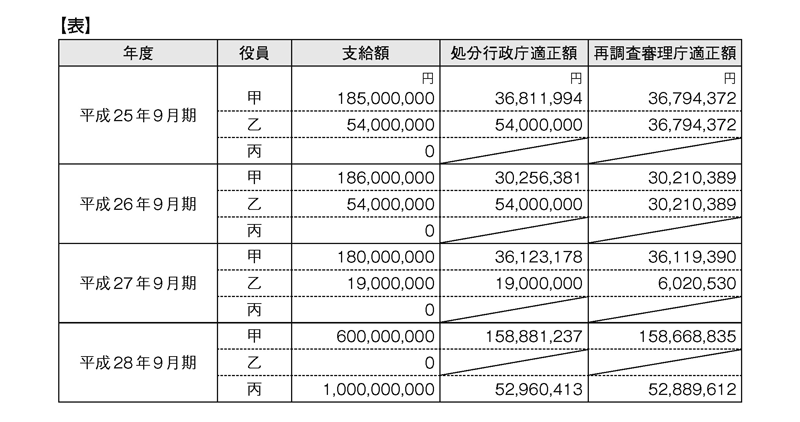
Xの適正な役員給与額=(当該年度の類似法人の役員給与最高額の平均値)×{①(当該年度のXの売上額)/(当該年度の類似法人における売上高の平均値)+②(当該年度のXの改定営業利益)/(当該年度の類似法人における改定営業利益の平均値)+③(当該年度のXの個人換算所得)/(当該年度の類似法人における個人換算所得の平均値)}×1/3
なお、類似法人は、①Xと同県内から抽出し、②事業の類似性は日本標準産業分類の小分類とし、③事業規模の類似性は売上高の倍半基準を採用し、④Xの同じ青色申告者から集計し、計10社(以下「本件類似法人」という。)を選定した。
(2)本件各給与、処分行政庁が算定した適正額及び再調査審理庁が算定した適正額は、後記【表】のとおりである。なお、Xの本件各事業年度の申告所得金額は、各年度順に、△5,919万円余、△1億308万円余、零円、△3,964万円余であった。
かくして、Xは国(被告)に対し、本件各更正等の取消しを求めて、前審手続を経て、本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
(1)法人税法34条2項の違憲性及び法人税法施行令70条1号イの違法性(争点1)
(2)本件各更正等認定の適正給与額と本件訴法における国主張の適正給与額との相違に係る違法性の有無(争点2)
(3)本件各給与における不相当に高額な部分の金額の有無及びその額(争点3)
2 Xの主張
(1)憲法84条の求める課税要件明確主義は、課税庁の行為規範として、各税法規定が課税庁にとっても一義的に明確なものとして当然要請しているとみるべきである。しかるに、法人税法34条2項が、課税庁にとっての一義的な法規範として現実に機能しているのであれば、課税庁の考える「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」の内容に処分時と裁判時で異なるという現象は起きないはずである。したがって、同項は、課税庁にとっての一義的に明確な規範として現実には機能していない。また、法人税法施行令70条1号イの内容は、税務署長ないし裁判所の機能を超える認定・判断を求めており、法人税法の委任の範囲を超えるものである。
(2)本件各更正等において認定された適正給与額と、本訴において国が主張する適正額とが相違しているのは、理由の差し替えに該当する。理由の差し替えが適法といえるには、差し替え前に摘示していた課税要件事実と差し替え後に摘示していた課税要件事実との間に同一性がある必要があるところ、当該理由の差し替えには、課税要件事実の同一性がない。
(3)法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額」は、同項の委任を受けた法人税法施行令70条1号において、同号イに掲げる金額と同号ロに掲げる金額のいずれか多い金額とするものと規定されている。前記のとおり、Xは役員給与の限度規定を株主(社員)総会等の決議により定めておらず、同号ロに規定する基準は存在していないから、同号イに掲げる金額を超える部分の有無及びその金額が具体的な争点となる。そして、国の各役員に対する適正給与額の認定には、次のような不合理性がある。
① 類似法人の抽象基準が不合理である。すなわち、Xの主たる経済活動は商品の企画・開発・販売であるにもかかわらず、それらが考慮されておらず、Xの業務の拠点は香港をはじめ海外であるから兵庫県内から類似法人を抽出できないはずであり、売上高倍半基準は売上高の高低と役員給与の高低との間に何らの関係がないから不合理であり、売上高経常利益率や自己資本比率が採用されていないのが不合理である。
② 本件各役員の職務内容を考慮しないという不合理性がある。すなわち、Xが平成28年9月期に着手したベトナム新規事業は、初年度から30億円の収益が見込まれ、5年後には年間100億円の収益が見込まれる。そして、丙は、腕利きの経営者であり、Xに招聘する前は月額4400万円の報酬を得ていた人物であるから、平成28年9月期に丙に対し月額2億5000万円の支払いをしても過大ではない。
③ Xの中長期的な業績について考慮されていない。すなわち、本件各更正等における本件類似法人との比較は、単に単年度ごとに行われているに過ぎない。
④ 本件算式には誤りがある。すなわち、本件算式において用いられている売上高数値に基づく比率は、倍半基準を始め改定営業利益や改定営業利益に基づく比率や個人換算所得に基づく比率にも反映されるなど、偏重し過ぎている。
3 国の主張
(1)法人税法34条2項は、課税の公平性を確保する観点から、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図るという考え方によるものである。そして、その委任を受けた法人税法施行令70条1号イは、法人の支給する役員給与につき、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入することが認められるべき役員の職務執行の対価としての相当性を判断するための具体的基準であり、法人税法34条2項の趣旨にも即したものである。したがって、法人税法34条2項は、課税要件明確主義に反するものではない。また、法人税法施行令70条1号イの規定も、法律の委任に反するものではない。
(2)国は、Xに対して法人税法34条2項を適用して行われた本件各法人税更正処分の適法性、具体的には、同項の適用によりXの損金の額に算入されない額である「不相当に高額な部分の金額」の適否につき、各条件下における適正給与額を攻撃防御の一つとして主張したものにすぎず、同じ課税要件の範囲内の主張であるから、理由の差し替えの場面に当たらない。
(3)Xの基本的な収益の状況を表す各項目は、いずれも横ばいないし減少傾向にあり、特に、収益のうち最も重要な指標である売上高や売上総利益の減少が、Xの主たる営業活動の成果の縮小を顕著に表しているにもかかわらず、本件各役員に対する給与は、Xの収益や純資産の額の状況からすれば支給を継続することが困難というべき水準にまで増額され、Xの収益の状況の更なる圧迫要因になっていた。上記事情に鑑みると、Xの適正給与額について、本件類似法人の数値に比してより高額に認定すべき差異は認められない。
三、判決要旨
請求棄却。
1 法人税法34条2項の違憲性等(争点1)
(1)法人税法34条2項は、内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと規定している。同項の趣旨は、法人の役員に対する給与が法人の利益処分たる性質を有する場合があることから、法人所得の金額の計算上、一般に相当と認められる金額に限り必要経費として損金算入を認め、それを超える部分の金額については損金算入を認めないことによって、職務執行の対価としての相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図り、課税の公平性を確保することにあると解される。
そして、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条1号イは、法人税法34条2項所定の「不相当に高額な部分の金額」を役員給与について算定するに当たり考慮すべき事項を、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に類似化して具体的に定めたものということができる。
(2)租税法規が憲法84条の規定に反しないか否かについては、当該法規の趣旨、目的とするところを合理的、客観的に解釈し、その法規が課税の根拠、要件を規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるか否かという観点から判断するのが相当である。
そこで検討するに、一般に、個々の法人における役員に対する給与の額について、「不相当に高額な部分の金額」の上限を確定的に定めることは、その性質上、極めて困難であり、かえって課税の公平性を害するおそれが高いものである。他方、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条1号イの掲げる考慮すべき事項のうち、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況については納税者において把握している事項であり、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等については、一般に公表された統計等、入手可能な資料等から一定程度の予測は可能であるというべきであって、これらの各事項を法人税法34条2項の規定の趣旨に照らして考慮すれば、納税申告の時点において、「不相当に高額な部分の金額」について、必ずしも確定的な金額までは判明しないとしても、相応の予測は可能であるというべきである。したがって、法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条1号イの規定は、法律により委任された課税要件と規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるというべきであるから、法人税法34条2項は憲法84条の規定に違反するものということはできない。
また、法人税法施行令70条1号イが職務執行の対価としての基準を定めたことは法人税法の委任の趣旨に沿うものといえる。
2 本件各更正等の適正給与額と本件訴法における国主張の適正給与額の相違に係る違法性(争点2)
本件訴訟における国の主張は、本件各更正等が適法であるとの攻撃防御方法を追加する趣旨のものにすぎず、本件各更正等を争うにつきXに格別の不利益を与えるものではないというべきである。以上によれば、本件各更正等認定の適正給与額と本件訴訟における国主張の適正給与額と相違をもって違法であるということはできない。
3 本件各給与の適正額(争点3)
(1)認定事実
イ Xの沿革と事業内容
甲は、父が家業としていた味噌製造事業を営むM味噌の経営に昭和55年(当時14才)頃から参画し、平成3年頃から中国に進出し、2つの工場を新設し、平成14年に法人成りした。また、平成27年頃ベトナムにも進出しようとしたが、課税上の問題もありその実施を留保することになった。Xの主な取扱商品は、冷凍食品、インスタント食品、味噌、瓶詰、缶詰、天かす等であり、その売上高は、他社から仕入れた商品を他社に売却することにより生じているものである。
ロ 本件各役員の職務内容
甲は、本件各事業年度において、X及び関連会社全体の業務として商品開発、営業活動等業務全般に従事していた。
乙は、Xの経理事務、経費等の銀行支払業務に従事していた。
丙は、X設立以来Xの取締役であったが、平成27年11月まではXの業務を担当せず、同年12月から、ベトナムに赴任した上で、ベトナム新規事業に係る業務全般を担うことになっていたが、当該業務に見込みが立たなかったこと等もあり、平成28年3月Xの取締役を辞任した。
ハ Xの収益等の概況
Xの売上高及び売上総利益は、平成24年9月期をピークに減少している。すなわち、①売上高は、平成24年9月期と比較して、平成25年9月期は約0.97倍(売上高10億3800万円余)、平成26年9月期は約0.7倍、平成27年9月期は約0.82倍、平成28年9月期は約0.62倍となっており、②売上総利益は、平成24年9月期と比較して、平成25年9月期は約0.87倍、平成26年9月期は約0.5倍、平成27年9月期は約0.4倍、平成28年9月期は約0.42倍となっている。
経常利益は、平成24年9月期は約4600万円であったが、平成25年9月期にはマイナス約9500万円、平成26年9月期にはマイナス約1億9600万円、平成27年9月期にはマイナス約9700万円、平成28年9月期にはマイナス約32億0500万円となっている。改定経常利益は、平成24年9月期は約1億3000万円であり、平成25年9月期は約1億4400万円に微増したが、平成26年9月期には約4400万円(平成24年9月期比で約0.34倍)、平成27年9月期には約1億0200万円(平成24年9月期比で約0.78倍)、平成28年9月期には約マイナス16億0500万円(平成24年9月期比でマイナス約12.36倍)と減少した。
純資産の額は、平成24年9月30日時点においては約9億3000万円、平成25年9月30日時点においては約8億7400万円、平成26年9月30日時点においては約7億7200万円、平成27年9月30日時点においては約8億4400万円、平成28年9月30日時点においては約4億6000万円であった。
(2)類似法人の抽出基準の合理性
認定事実からすると、Xの売上総利益の大部分は、K物産が取り扱う商品を、Xが企画及び開発して製造委託先に製造させ、完成した製品を購入した上でMソフトに販売することによって生じており、Mソフトはその後K物産の小売店に当該製品を販売する卸売業者であったこと、Mソフト以外の取引先との関係においても、反復継続的に仕入れ・販売することによって売上総利益が生じていることからすると、Xの主たる事業は、日本標準産業分類上、有体的商品を購入して販売する事業所、すなわち「卸売業」に該当すると認めるのが相当である。そして、日本標準産業分類は、統計の正確性と客観性を保持し、統計の相互比較性と利用の向上を図ることを目的として設定された統計基準であり、全ての経済活動を産業別に分類したものであるから、同業類似法人の抽出に当たって同基準を用いることは合理的であるといえる。
その他、抽出地域を兵庫県内としたこと、売上高倍半基準を採用したこと等いずれも合理性が認められる。
(3)本件各給与の不相当に高額金額の有無とその金額
イ 前判示のとおり、Xの売上高及び売上総利益が、本件各事業年度を通じて大幅に減少傾向にある中で、本件各役員給与は、平成24年9月期は合計8300万円(うち甲は3000万円)であったのが、平成25年9月期には合計2億3900万円(うち甲は1億8500万円)と約2.9倍(甲については約6.2倍)に急増し、その3事業年度後である平成28年9月期には16億円(うち甲は6億円)(平成24年9月期と比較して約19倍(甲については20倍))と大幅に増額しているところ、本件各役員給与は、本件各事業年度において各売上総利益の額を上回っており、また、Xの各改定営業利益の大部分を占めてXの営業利益を大きく圧迫するに至っていることからすると、本件各役員給与の額の高さ及び増加率は著しく不自然である。
本件類似法人の役員給与最高額の支給状況は、甲の役員給与の支給状況と比較すると、平成25年9月期から平成27年9月期までの最高額と比較しても12.5倍から18倍、金額にして1億7000万円以上高額となっており、平成28年9月期の甲の役員給与額(6億円)は、本件類似法人の最高額の約64倍、金額にして5億9000万円以上高額となっている。このような役員給与の支給状況の格差は、認定事実のような甲の職務内容や職責等を踏まえても、合理的な範囲を超えるものといわざるを得ない。
また、平成28年9月期における丙の役員給与額は10億円となっており、同月期の本件類似法人の最高額の約107倍、金額にして9億9000万円以上高額となるに至っており、認定事実のような丙の職務内容や職責等を踏まえると、合理的な範囲を超えるものというほかない。
上記のとおり、Xの売上高等からすると本件各役員給与の高さ及び増加率は不自然であり、本件類似法人の役員給与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲を超えるものとなっている。
ロ 前提事実のとおり、処分行政庁は、平成25年9月期法人税更正処分ないし平成28年9月期更正処分において、甲及び丙の適正給与額を算定するに当たり、本件類似法人の役員給与最高額の平均額に、売上高、改定営業利益及び個人換算所得を勘案すべき要素として等分の重みづけをして乗じて算出する方法(本件算式)により適正な役員給与額を算定したものである。本件算式において本件類似法人の役員給与最高額の平均額が基準値とされたことについては、甲及び丙がXの代表権を有する取締役であったこと、Xの事業内容及びXの収益状況に鑑みると、合理的といえる。そして、甲がXの売上げを得るために果たした職責や達成した業績に鑑みると、処分行政庁が、本件類似法人の役員給与最高額の平均額に一定の加重をすることが相当であると判断して、Xと本件類似法人との間に存する偏差を調整するために、法人税法施行令70条1号イにおいて適正給与額の判断要素として規定している「事業規模」の指標に当たるものとして売上高、「収益」に当たるものとして改定営業利益及び個人換算所得(同族会社における実質的な所得金額と解される。)を勘案要素として考慮した本件算式を用いて算出したことは合理的であり、乙がXの売上げを得るために果たした職責や業績に鑑みると、乙についても、同様に、本件算式を用いるのが相当である。したがって、甲及び乙については、本件算式により算出される金額が適正給与額に該当し、それを超える金額が「不相当に高額な部分の金額」に該当すると認めるのが相当である。
これに対し、丙については、平成27年11月まではXの業務を担っておらず、Xから給与の支給がされていた平成27年12月から平成28年3月までの4か月間に果たした職務の内容等に鑑みても、本件類似法人の役員給与最高額の平均額に一定の加重をすることが相当とは認められない。したがって、本件類似法人の役員給与最高額の平均額の4か月分(3分の1を乗じた金額)が適正給与額に該当し、それを超える金額が、「不相当に高額な部分の金額」に該当すると認めるのが相当である。
ただし、平成27年9月期の乙の適正給与額は、認定事実のとおり乙の担当している商品の売上高及び利益の金額が減少していることからすると、X支給額の1900万円が相当であり、丙の適正給与額は、平成28年9月期類似法人の役員給与最高額の平均額(844万6000円)に3分の1を乗じた金額(281万5334円)(本訴における国の主張額と同じ。)である。
四、解説
はじめに
本件は、兵庫県内で味噌等の製造、卸、販売等を目的とする有限会社が、その役員3名(兄、妹、弟の関係)に対して、4事業年度にわたって支給した役員給与(本件各給与)が法人税法34条2項に定める「不相当に高額」であるということで課税処分(本件各更正等)を受けたので、その適否が争われたものである。法人税法34条2項の規定に反する旨の課税処分は、役員退職給与に係るものが多く、本件のような年次給与に係るものが少ないだけに注目されるところである。
本訴においては、Xは、法人税法34条2項の規定自体が課税要件明確主義に反するということで、当該条項の憲法違反を主張するとともに、処分行政庁が算定し、また、本訴において国が主張する「不相当に高額」の算定方法の合理性を真っ向から否定している。そこで、このようなXの主張とそれを否定する本判決の判断の当否を検討する。もっとも、本件におけるXの本件各給与の支給は、Xの営業利益を相当上回るという異例なものであるだけに、役員給与の支給戦略の見地からも考えさせられるところがある。以下、それらの問題点を論じることとする。
1 課税要件明確主義と不確定概念
(1)憲法84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定め、租税法律主義を宣明している。換言すれば、「法律の根拠に基づくことなしには、国家は租税を賦課・徴収することはできず、国民は租税の納付を要求されることはない。」(注1)ことになる。
このような租税法律主義の理念は、現代の国民の経済生活に法的安定性と予測可能性(両者は租税法律主義の機能である。)を与えることに極めて重要である。すなわち、経済取引においては、当該経済取引が幾許の租税負担をもたらすかが法令の規定によって明確にされていないと、当該取引において合理的な判断ができないことになる。しかしながら、現実の国民の租税負担を律する法令の定め(又は定め方)には、種々の問題があり、前述のような法的安定性と予測可能性が保障されるとは言い難い問題がある。その問題は、租税法律主義の内容(注2)のそれぞれからもたらされることがある。
(2)その中で、本件に即すると、課税要件明確主義が挙げられる。課税要件明確主義は、法律又はその委任のもとに政令や省令において課税要件及び租税の賦課・徴収の手続は一義的で明確でなければならないことを意味する。けだし、法令上の定めが一義的で明確でなければ、結局、租税行政庁に一般的・白紙的委任するのと同じ結果になり、納税者の経済活動における法的安定性と予測可能性を害することになるからである。
しかしながら、この課税要件明確主義の中で最も問題となるのは、法令の定めの中で、抽象的、多義的概念を有する不確定概念が用いられることである。このような不確定概念と称されるものには、本件で問題となっている「不相当に高額」(法法34②、36)のほか、「不適当であると認められる」(所法18)、「相当の理由」(所法145二、150①三、法法123二、127①三)、「必要があるとき」(法法153、154、通法74の2~74の6各1項等)、「正当な理由」(通法65⑤、66①、67①)等数多く存在する。
もっとも、このような不確定概念については、一般的には、租税行政庁に自由裁量を認めるものではなく、法の解釈の問題であり、裁判所の審査に服する問題であると解されるから、その必要性と合理性が認められる限り、この種の不確定概念を用いることは課税要件明確主義に反しないものと解されている(注3)。しかしながら、本件においてもそうであるが、前述のような不確定概念を適用した課税処分の違法性を争う事件は数多く見られるところである。したがって、立法技術的に前述のような不確定概念を用いざるを得ないにしても、その運用(執行、解釈)においては、慎重でかつ一定の幅を持った解釈が行われるべきであろう。
例えば、東京地裁昭和46年6月29日判決(行裁例集22巻6号885頁)、東京高裁昭和49年1月31日判決(税資74号293頁)及び最高裁昭和50年2月25日第三小法廷判決(同80号259頁)(注4)の事案では、役員退職給与の適正額につき、当時、巷間、功績倍率3.0程度であれば税務上も認められる、と言われていたこともあり、当該会社が、その旨役員退職給与規定を整備して役員退職給与を支給したところ、類似法人3件の平均功績倍率2.1によるべきとする課税処分が行われ、その適否が争われた。前掲の東京地裁判決は、当該役員退職給与が法令の規定の趣旨等に照らし不相当に高額とは認められない旨判示して、当該課税処分を取り消した。しかし、上訴審の前掲各判決は、平均功績倍率を厳格に適用すべき旨判示し、当該課税処分を適法と認めた。このような各判決をみて、前述の「不相当に高額」の解釈のあるべき方向を考えると、上訴審の各判断は頑なであり、東京地裁判決の方が妥当であると考えられる。
2 役員給与の支給戦略
(1)ところで、我が国では、中小企業の法人成りが非常に多いが、その最大のメリットは、事業主やその家族使用人の事業への役務提供に対して支給される給与に係る税負担の軽減にある(注5)。その中でも、法人成り後の代表者(同族役員を含む。)に対する年次の役員給与については、当該法人の法人税負担と当該役員の年次給与に係る所得税額の合計額を最小にすることが得策である。そのためには、当該役員に対する年次給与について法人税法上の損金不算入の規制を受けないようにした上で、当該役員の所得税の限界税率と法人税の比例税率(最高税率)が等しいようにすれば良いことになる。この仮説が成立するには、当該役員の所得(財産)と当該法人の所得(財産)が一体であることが必要である。通常の同族会社であれば、このような仮説は成立するはずである。
(2)ところが、本件の場合には、Xに多額な欠損を残しながら、本件各役員に対する年次給与だけは異常に高額になっている。このような高額な年次給与については、大部分について、所得税の最高税率(45%、住民税等を加算すると、最高55.954%となる。)が適用され、前述のような仮説が成立しなくなる。しかし、当該役員が所得税法上の非居住者(注6)に該当することになると、上記のような最高税率が適用されないで、源泉所得税率20%で済ますことができることになる。本件においては、その事実関係から定かではないが、Xが中国に進出していることやベトナムに進出しようとしていることからすると、甲及び丙は居住者ではなく非居住者であることも考えられる。
この点に関し、東京地裁令和2年1月30日判決(平成29年(行ウ)第371号)(注7)の事案では、代表取締役に対し、5事業年度にわたって、各年度の利益金額の数倍、金額にして、2億7200万円ないし5億2000万円の役員給与を支払った場合に、当該各支給額の約9割を損金不算入とする課税処分の適否が争われ、当該課税処分が適法とされている。この事案の場合にも、当該代表取締役は、マレーシアに居住していたため、非居住者として、我が国の所得税の累進課税を受けていない。
3 「不相当に高額」の判定基準
(1)法人税法34条2項は、「内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と定めている。そして、「政令で定める金額」について、法人税法施行令70条1項1号は、年次給与につき、次のように定めている。
「一、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
イ 内国法人が各事業年度おいてその役員に対して支給した給与(〈略〉)の額(〈略〉)が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(その役員の数が2以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額)
ロ 定款の規定又は株主総会、社員総会若しくはこれらに準ずるものの決議により、役員に対する給与として支給することができる金銭その他の資産について、金銭の額の限度額若しくは算定方法、その内国法人の株式若しくは新株予約権の数の上限又は金銭以外の資産の内容を定めている内国法人が、各事業年度においてその役員(〈略〉)に対して支給した給与の額(〈略〉)の合計額が当該事業年度に係る当該限度額及び当該算定方法により算定された金額、当該株式又は新株予約権(〈略〉)の当該上限及びその支給の時(〈略〉)における1単位当たりの価額により算定された金額並びに当該支給対象資産(〈略〉)の支給の時における価額(〈略〉)に相当する金額の合計額を超える場合におけるその超える部分の金額(〈略〉)」
(2)以上のように、法人税法施行令70条1項1号は、年次給与の「不相当に高額」の判定につき、イの実質基準に基づく高額部分とロの形式基準に基づく高額部分のいずれか多い金額と定めている。この場合、形式基準については、会社側の議事録等の記載が問題とされる等正に形式的なミス等が問題となる。例えば、山形地裁昭和41年2月21日判決(税資44号94頁)(注8)の事案では、昭和30年設立時の創立総会議事録に「取締役及び監査役の報酬は、年額50万円以内」と記載していたが故に、その3年後から3事業年度にわたって取締役3名に対し、年63万円余から94万円余の報酬を支払ったところ、それらの50万円を超える部分が「不相当に高額」であるということで課税処分を受けている。当該訴訟において、会社側は、「年額50万円」は「各自年額50万円」とすべきところ記載ミスである旨主張したが、前掲判決は、その主張を認めなかった。
また、岐阜地裁昭和56年7月1日判決(税資120号1頁)(注9)でも、株主総会議事録に、「役員報酬支給限度額は、1900万円」と記載していたところ、当該係争年度において、3名の役員に対して、合計2180万円支給したため、その差額の280万円が「不相当に高額」であると認定されている。
これらの事例にみられるように、一見、事務上の誤りであっても、それらの記載を盾に当該役員報酬が「不相当に高額」であると認定される場合があるので留意する必要がある。この点、本件のXは、それらの記載がなかったというのであるから、関係条文の形式どおり、実質基準のみで「不相当に高額」か否かが判断されることになる。
(3)ところで、実質基準については、「当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等」を判断基準とされているが、本来、役員給与は、当該役員の経営手腕の対価として支給されるべきであるので、「当該役員の職務の内容」が最も重視されるべきである。しかし、筆者の実務経験に照らしても、そのような真の実質判断(人が人の能力を判断すること)は極めて困難である(注10)。そのため、実務的には、「同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況」すなわち、類似法人の支給との比較が最も重視されている(むしろ、このような判定基準しかないのが実態である。)。
しかしながら、このような類似法人との比較については、たとえ、当該会社と類似法人との間に、業種、地域、売上規模等に類似性があったとしても、それらの類似性は、当該各役員の経営手腕とは直接関係がないはずである。そのため、それぞれの比較項目について、何らかの加重方法がとられて然るべきである。それについては、本件においても、本件算式の中で相応の配慮がされている。しかし、その妥当性については、追って検討する。
4 本件各給与の相当性等
(1)本件におけるXは、兵庫県内に所在し、味噌等の製造、卸、販売等を目的とする有限会社ではあるが、中国に進出して味噌工場を二か所設立し、ベトナムにも進出しようとし、国内で売上高の大部分が味噌等の商品を他社から購入して他社に転売するという特殊な経営形態を採用している。しかも、会社役員は、兄弟3名であり、Xの主張によると、従業員もほとんどいないようである。そういう経営状況の中で、本件各係争年度において、申告所得金額が零円又は多額な欠損金でありながら億単位の極めて高額な役員給与(本件各給与)を支給してきた、というものである。このような役員給与の支給方法は、前記2で述べた通常の役員給与の支給戦略に照らし異例なものであり、仮に、甲及び丙が非居住者であって所得税について我が国の高率な累進税率の適用を免れるものとしても、Xに多額な欠損金を残したまま多額な役員給与を支払うことには、通常の経営戦略では解せないところがある。
これに対し、処分行政庁は、例によって、類似法人の役員給与の支給状況と比較して、本件各給与の適正額を算定し、それを上回る部分を不相当に高額であるとして、本件各更正等をしたのであるが、当該支給状況との比較において若干の工夫をしている。すなわち、単純に平均値とか最高値によって比較するのではなく、類似法人の役員給与最高額の平均値に、売上額、改定営業利益及び個人換算所得について、Xの数値と類似法人の平均値をそれぞれ比較するという、加重方式を適用して適正額を算定している(本件算式)。また、類似法人の抽出については、Xと同県の兵庫県内から抽出し、類似業種は日本標準産業分類の小分類(卸売業)から抽出し、事業規模は売上高の倍半基準を採用し、Xと同じ青色申告者の中から10社を採用している。このような類似法人の選定や本件算式には、相応の工夫が見られるのであるが、その結果として、本件類似法人中の年次給与の最高額の平均値が各期900万円前後であるが、いかに中小企業の役員とはいえ、年間の役員給与としては低過ぎるように考えられる。
かくして、Xは、このような課税処分をもたらす法人税法34条2項自体の違憲性と同項の委任を受けた同法施行令70条1号イの違法性を主張し、かつ、本件各更正の違法性(「不相当に高額」の認定誤り。)を主張することとなった。
(2)本判決は、まず、法人税法34条2項の違憲性については、同項が、役員の職務執行の対価として相当性を確保し、役員給与の金額決定の背後にある恣意性の排除を図り、課税の公平性を確保することにある旨判示し、「法人税法34条2項の委任を受けた法人税法施行令70条1号イの規定は、法律により委任された課税要件を規定したものとして一般的に是認し得る程度に具体的で客観的なものであるというべきであるから、法人税法34条2項は憲法84条の規定に違反するものということはできない。」と結論付けた。また、「法人税法施行令70条1号イが職務執行の対価としての基準を定めたことは法人税法の委任の趣旨に沿うものといえる。」と判示した。
また、本判決は、本件各更正等の適正給与額と本件訴法における国主張の適正給与額が異なることの違法性については、前述のように、攻撃防御方法を追加したにすぎない旨判示し、Xの主張を一蹴している。
次に、本件各給与の適正額に関しては、本判決は、前述のように、本件の事実関係を詳細に認定し、まず、類似法人の抽出基準については、対象地域、類似業種、売上高の倍半基準等、処分行政庁が採用したものに合理性がある旨判示した。そして、本件各給与の「不相当に高額」の該当性について、本件各給与が、Xの売上高や売上総利益に比し、また、類似法人の役員給与最高額の支給状況に比し、異常に高いことを指摘し、「Xの売上高等からすると本件各役員給与の高さ及び増加率は不自然であり、本件類似法人の役員給与の最高額と比較しても、その較差は合理的な範囲を超えるものとなっている。」と判示し、本件各給与が「不相当に高額」であるとしている。次いで、本判決は、本件各給与の適正額については、前述のように、概ね本件算式の合理性を認めている。ただし、平成28年9月期の丙に対する役員給与については、丙が4か月間しか勤務していないことから、本件類似法人の役員給与最高額の平均額の4か月分が適正給与額である旨判示している。
(3)このような本判決の判示については、次のことが指摘できる。まず、法人税法34条2項の規定の合憲性であるが、そもそも、平成18年改正後の法人税法34条がそのタイトルを「役員給与の損金不算入」として役員給与それ自体に損金性がないような不合理な定め方をしている(注11)。また、同条2項に定める役員給与の「不相当に高額」の解釈についても、それが不確定概念の最たるものであるが故に、非常に多くの争訟事件を惹起している。そのため、納税者側が、Xのような違憲主張をすることも理解できないわけではない。しかしながら、租税法規の違憲問題については、最高裁昭和60年3月27日大法廷判決(民集39巻2号247頁)(注12)が、「租税法の定立については、国家財政、社会経済、国民所得、国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的、技術的な判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ないものというべきである。」と判示して以降、それが判例法となり、各裁判所は、租税法規の違憲性について極めて消極的になっている(注13)。よって、本件においても、合憲判断がされたのも、その延長線上にあると言える。もっとも、「不相当に高額」という不確定概念の運用(執行)については、前記1で述べたように、一定の幅をもって弾力的に行われるべきであろう。
次いで、本判決は、本件の主題である本件各給与について相当性の判断をするのであるが、前述のように、本件各給与が、Xの業績等に比しても、異常に高額である旨を認定した上で、処分行政庁による本件算式の合理性を概ね容認した上で、本件各更正等の適法性を容認している。このような判断については、本件各給与が異常に高額であることや処分行政庁が認定した適正額が類似法人の平均値の数倍になるなど相応のアローアンスを見込んでいることを考慮すれば、妥当なものと考えられる。いずれにしても、本判決については、役員給与の年次給与の適正額を争う争訟事件が比較的少ないだけに、一つの先例として参考になる。
(注1)金子宏「租税法 第24版」(弘文堂 令和5年)78頁。
(注2)租税法律主義の内容としては、課税要件法定主義、課税要件明確主義、合法性の原則、適正手続保障原則及び遡及立法禁止の原則が挙げられる。
(注3)前出(注1)85頁等参照。
(注4)品川芳宣「役員報酬の税務事例研究」(財経詳報社 平成14年)304頁参照。
(注5)法人成りの税務メリットの詳細については、品川芳宣「非上場会社(中小企業)における役員報酬等の支給戦略」資産承継2022年12月号6頁等参照。
(注6)非居住者とは、「居住者以外の個人をいう。」(所法2①五)が、居住者とは、「国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。」(所法2①三)ことになる。
(注7)品川芳宣「重要租税判決の実務研究 第四版」(大蔵財務協会 令和5年)608頁。
(注8)前出(注4)104頁参照。
(注9)前出(注4)124頁参照。
(注10)品川芳宣「傍流の正論」(大蔵財務協会 令和5年)62頁参照。
(注11)平成18年改正の役員給与課税の問題点については、品川芳宣「役員給与課税の本質を衝く!(前)(後)」本誌2008年4月14日号27頁、同2008年4月21日号24頁参照。
(注12)同判決は、大島訴訟(判決)と称されるものであるが、同志社大学の大島教授が、昭和39年分所得税(給与所得)について、給与所得控除による必要経費の取扱いが事業所得に比して不平等であるとして、給与所得課税規定の憲法14条違反を争ったものである。
(注13)例えば、大阪地裁平成7年10月17日判決(行裁例集46巻10・11号942頁)、大阪高裁平成10年4月14日判決(訟務月報45巻6号1112頁)及び最高裁平成11年6月11日第二小法廷判決(税資243号270頁)は、旧租税特別措置法69条の4の違憲性につき、当該規定は合憲であるが、当該規定を適用した課税処分は違憲状態になるとして、当該課税処分を取り消している(詳細については、前出(注7)1262頁参照)。しかし、当該69条の4は、違憲問題を多発しかねないということで、平成8年3月廃止している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















