解説記事2024年02月12日 税務マエストロ 立替金とインボイス制度(2024年2月12日号・№1014)
税務マエストロ
立替金とインボイス制度
#297
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
記載要件を満たさないインボイスもどきの書類が横行しているようである。制度が定着するまで、今後様々な問題点が浮上してくるものと思われるが、実務の現場では、とりわけ立替金の取扱いに関する質問が多いようだ。そこで、本稿では国税庁のインボイスQ&A問94(立替金)の内容を確認した上で、国税庁の質疑応答事例などを参考に注意すべき立替金に関する事例を検討する。
Ⅰ 国税庁のインボイスQ&A 問94(立替金)
当社(A社)は、取引先のB社に経費を立て替えてもらう場合があります。
この場合、経費の支払先であるC社から交付される適格請求書には立替払をしたB社の名称が記載されますが、B社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。【令和5年10月改訂】
※問については筆者が一部アレンジしている
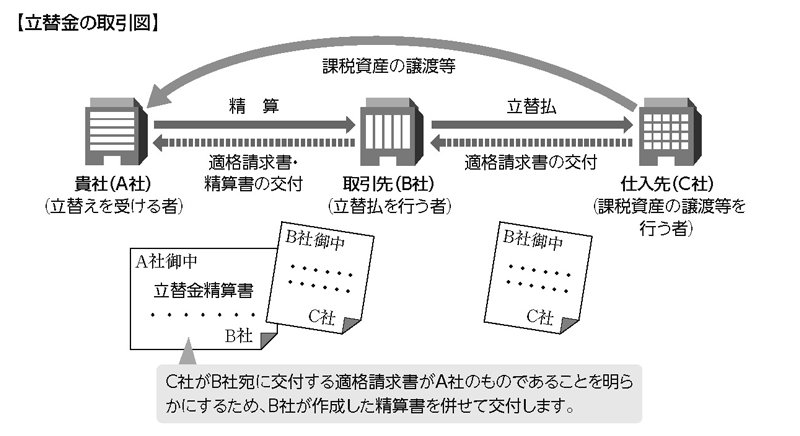
1 立替を受けた経費の処理方法
次頁【立替金の取引図】にあるように、貴社(A社)がB社において立替払がされた経費を仕入税額控除の対象とするためには、次の①と②の書類を保存する必要がある(消基通11−6−2)。
① B社が当社の仕入先(C社)から交付を受けたインボイス
② B社が作成した立替金精算書
ただし、3万円未満の公共交通料金のように、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるような立替の場合には、法定事項を記載した帳簿を保存することにより、前頁①及び②の書類を保存せずとも仕入税額控除を行うことができる。
また、立替払の精算に当たっては、立替者であるB社が登録事業者である必要はない。
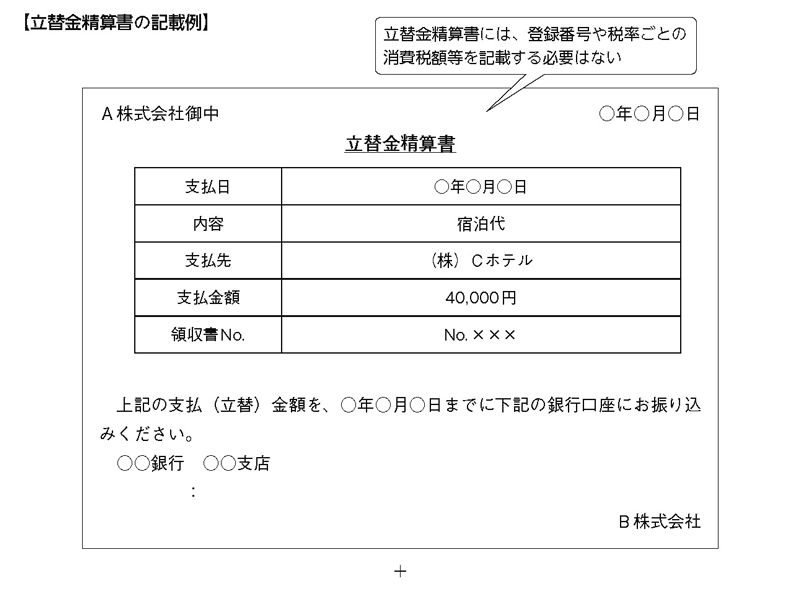
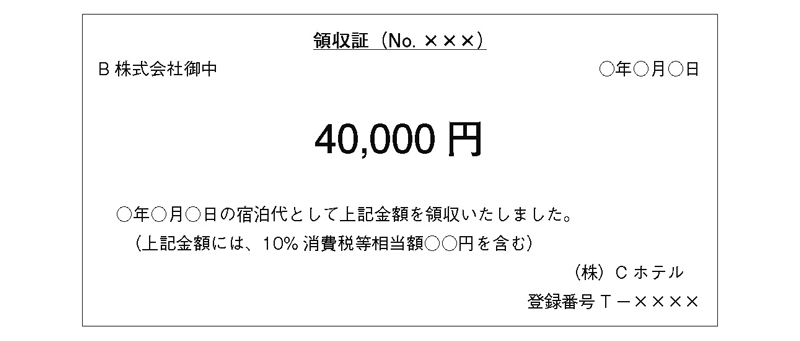
2 複数者分の経費を一括して立替払している場合
(1)原則
B社が複数者分の経費を一括して立替払している場合でも、B社は、上記①及び②の書類をA社をはじめとする立替を受けた者に交付する必要がある。
<ポイント>
・立替払を行ったB社はインボイスの原本をコピーして交付する。
・A社はB社から交付を受けたインボイスのコピーと立替金精算書を保存することにより、仕入税額控除を行うことができる。
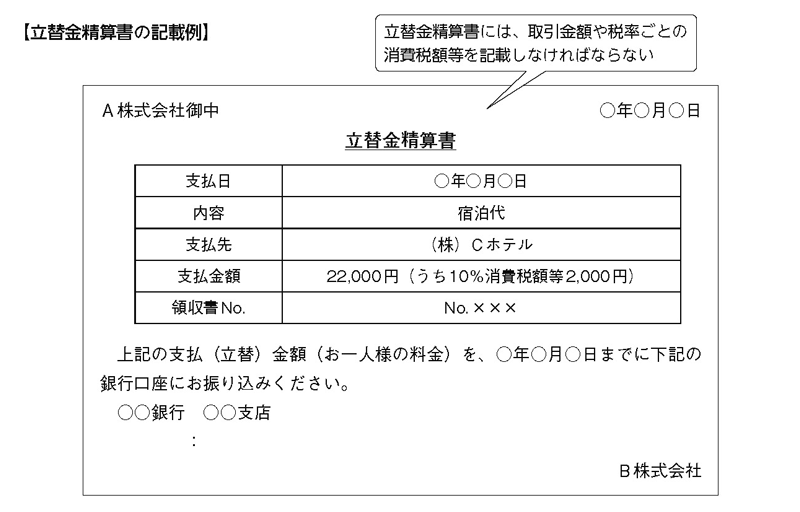
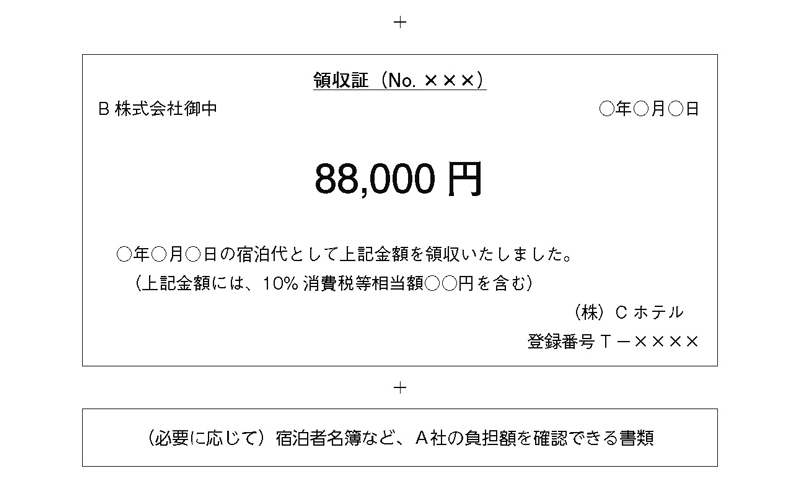
(2)例外
インボイスのコピーが大量になるなどの事情により、B社がコピーの交付が困難なときは、B社はインボイス(コピー)の交付を省略し、A社をはじめとする立替を受けた者に立替金精算書だけを交付することができる。
<ポイント>
・立替払を行ったB社は、A社が仕入税額控除を受けるために必要な事項を立替金精算書に記載しなければならない。
・B社は当社の仕入先(C社)から交付を受けたインボイスを保存する。
・A社はB社が作成した立替金精算書を保存することにより、仕入税額控除を行うことができる。
・B社とA社の間で、その課税仕入れ(経費)が登録事業者からのものかどうかを確認できるようにしておく必要がある。
確認の方法としては、書面等で通知する場合のほか、継続取引に係る契約書等で別途明らかにされている場合には、精算書にこれらの事項を明記する必要はない。
(3)例外による場合の端数処理
立替金精算書に記載する「消費税額等」については、立替払いを受ける者の負担割合を乗じてあん分するなどの合理的な方法で計算した金額を記載する必要がある。
<ポイント>
・立替金精算書に記載する複数の事業者ごとの消費税額等の合計額が適格請求書に記載された「消費税額等」と一致しない場合でも、合理的な方法で計算されたものである限り問題はない。
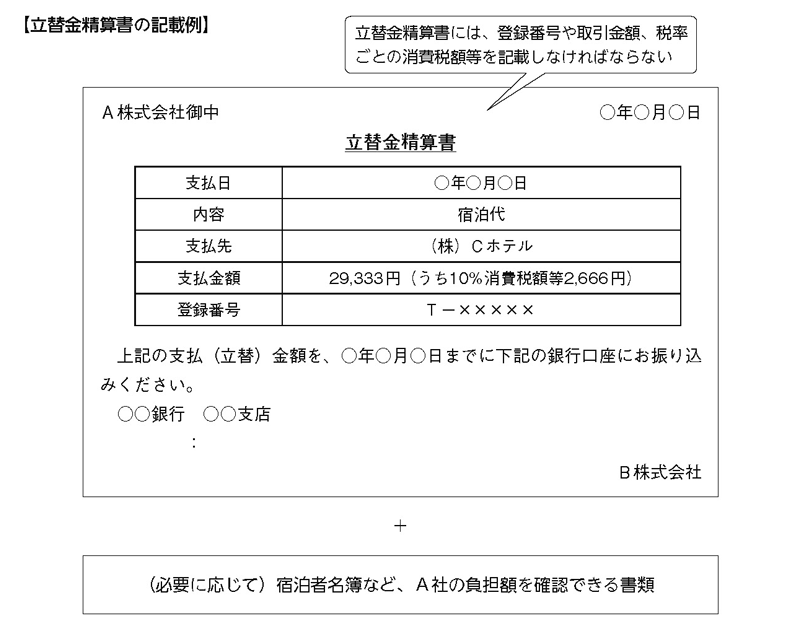
※支払金額の計算方法
A社、M社、L社の宿泊代(各1名)の合計金額88,000円をB社が立て替えた場合、各社への立替金の請求額を次のように計算することができる。
A社 88,000円÷3≒29,333円(端数切捨)
29,333円×10/110≒2,666円(端数切捨)
M社 88,000円÷3≒29,333円(端数切捨)
29,333円×10/110≒2,666円(端数切捨)
L社 88,000−(29,333+29,333)=29,334円
29,334円×10/110≒2,666円(端数切捨)
Ⅱ 国税庁の質疑応答事例
1 テナントから領収するビルの共益費(資産の譲渡の範囲10)
【照会要旨】
ビル管理会社等がテナントから受け入れる水道光熱費等の共益費等は、いわゆる「通過勘定」という実費精算的な性格を有することから、課税の対象外としてよいでしょうか。
【回答要旨】
ビル管理会社等が、水道光熱費、管理人人件費、清掃費等を共益費等と称して各テナントから毎月一定額で領収し、その金額の中からそれぞれの経費を支払う方法をとっている場合には、ビル管理会社等が領収する共益費等は課税の対象となります。
また、水道光熱費等の費用がメーター等によりもともと各テナントごとに区分されており、かつ、ビル管理会社等がテナント等から集金した金銭を預り金として処理し、ビル管理会社等は本来テナント等が支払うべき金銭を預かって電力会社等に支払うにすぎないと認められる場合には、当該預り金はビル管理会社等の課税売上げには該当しません。
<ポイント>
(1)共益費を定額で収受する場合
ビルの賃貸において、賃借人である各テナントが負担すべき光熱費などの共益費を家賃とは別に請求することがある。この場合の共益費は、賃貸人が電力会社などから光熱費を仕入れ、賃借人に供給(販売)していることとなるので、家賃と区分して光熱費などの名目で一定額を請求する限り、消費税が課税されることになる。管理人人件費などについても、ビルのオーナーが行う役務提供の対価として取り扱うこととなるので、たとえ共益費の内訳が区分されていたとしても不課税とはならず、その全額に消費税が課税されることになる。
(2)実測により請求する場合
メーター等により賃借人の光熱費の使用量を個別管理しているような場合には、立替金又は預り金として処理した請求額は賃貸人の課税売上高として計上する必要はない。
また、賃借人は、賃貸人から交付を受けた立替金精算書を保存することにより、負担した光熱費を仕入税額控除の対象とすることができる。
この場合の立替金精査書の作成と光熱費の精算方法は、上記Ⅰの【立替金精算書の記載例】を参照されたい。
2 ホテルの客のタクシー代の立替払(資産の譲渡の範囲25)
【照会要旨】
ホテルにおいて客のタクシー代や宴会のコンパニオン派遣料等を立替払した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
ホテル等が客の依頼を受けて、又は客が自らタクシーや宴会のコンパニオンを呼んだ場合においては、本来それらの役務の提供の対価は客が直接役務の提供者に支払うべきものですから、ホテルが当該対価を客に代わって立替払をし、その旨を明確に区分している場合には、その代金を客から領収しても課税の対象とはなりません。また、その支払はホテルの課税仕入れにも該当しません。
なお、タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客から領収する場合には、単なる立替えとは異なりますので、その全額が課税の対象となります。
<ポイント>
(1)立替払の場合
ホテル等が客(利用者)の経費を立替払しているような場合には、立替金又は預り金として処理した金額はホテルの課税売上高として計上する必要はない。
また、客(利用者)は、ホテル等から交付を受けた立替金精算書を保存することにより、経費を仕入税額控除の対象とすることができる。
この場合の立替金精査書の作成と経費の精算方法は、上記Ⅰの【立替金精算書の記載例】を参照されたい。
(2)マージンを上乗せする場合
タクシー代やコンパニオン代の実費にホテル等のマージンを上乗せして客(利用者)から領収する場合には、単なる立替えとは異なることからその全額が課税売上高となる。領収金額の内訳を実額とマージンに区分して提示しない限り、マージンだけを課税売上高に計上することは認められないものと思われる。
3 実費弁償金の課税(資産の譲渡の範囲26)
【照会要旨】
弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に充てるものとして受け取った金銭については、それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、課税の対象となりません(基通10−1−4(注))。
<ポイント>
(1)立替払の場合
弁護士が負担すべき宿泊費や旅費などの経費を依頼者が立替払している場合には、立替金又は預り金として処理した金額は弁護士の課税売上高として計上する必要はない。
また、弁護士は、依頼者から交付を受けた立替金精算書を保存することにより、経費を仕入税額控除の対象とすることができる。
この場合の立替金精査書の作成と経費の精算方法は、上記Ⅰの【立替金精算書の記載例】を参照されたい。
(2)実額を請求する場合
弁護士が宿泊費や旅費などの経費を支払い、その実額を依頼者に請求しているような場合には、たとえ実額を請求している場合であっても立替金として処理することはできない。
弁護士は、依頼者に請求した弁護士報酬と経費の合計額を課税売上高として認識するとともに、支払った経費については仕入税額控除の対象とすることになる。
【インボイスの記載例】
弁護士報酬が100,000円(税抜)で、旅費・交通費が5,500円の場合の請求書は下記のような記載方法になるものと思われる。
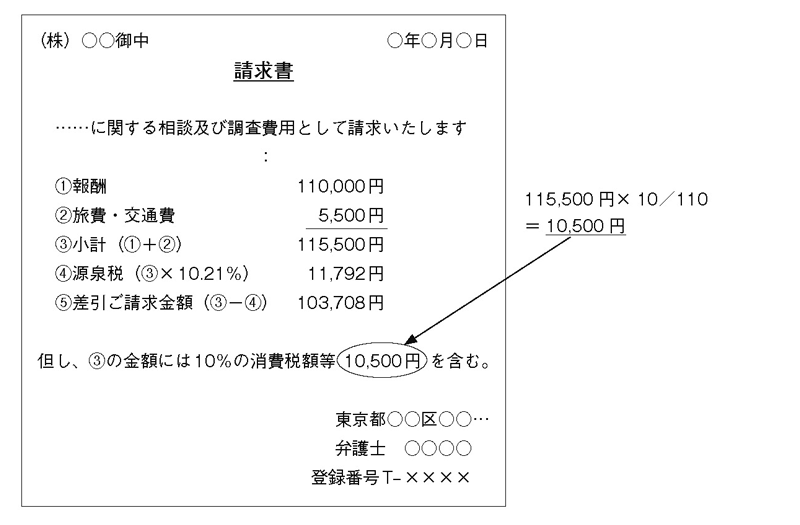
【回答要旨】に記載のとおり、旅費・交通費も弁護士報酬に含まれることとなるため、インボイスに消費税額等10,000円と記載することはできない。
また、次頁のように旅費・交通費などを除外して源泉税を計算している請求書が巷で見受けられるようであるが、旅費・交通費が弁護士報酬に含まれることを考えると、このような計算は誤りではないかと思われる。
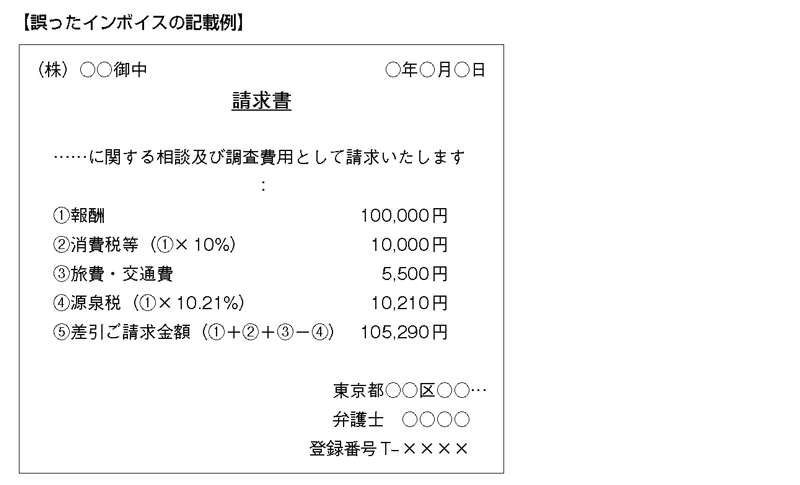
ただし、本体価格105,000円(115,500円×100/110)と消費税等10,500円を区分している場合には、下記のように源泉税を計算することが認められている(消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて3)。
105,000円×10.21%=10,720円
Ⅲ その他のトラブル事例(筆者オリジナル作品)
1 実費で請求する保険料の取扱い
運送業者が貨物の配送にあたり、保険会社と損害保険契約を締結した。
この場合において、運送業者は荷送人に対し、配送料とは別に荷送人に請求した保険料(実費)を課税売上高には計上せずに、立替金として処理することができるか。
Answer
本事例の場合には、保険契約を締結したのは荷送人ではなく、当社である。つまり、当社が荷送人に請求した保険料は、あくまでも「配送」という役務提供に関するコストの一部であり、これを「保険料」という名目で請求したに過ぎないものである。
したがって、当社が荷送人に対して請求した保険料は、配送料(売上高)の一部分として扱われることになるため、運送業者は、保険料も含めた全額を課税売上高に計上しなければならない(荷送人は保険料も含めた全額を仕入税額控除の対象とすることができる)。
<ポイント>
(1)実費で請求する保険料の取扱い
上記のように、保険契約を締結したのが運送会社である場合には、運送会社が負担する保険料は運送会社のコストであり、これを荷送人に請求するかどうかということは、あくまでも運送会社の判断により決定するものである。この場合において、荷送人に保険料を実費で請求するかどうかということは運送会社が判断することであり、これにより税務上の取扱いが変わるわけではない。「実費で請求したのだから立替金である」という理屈は通用しないので注意が必要だ。
保険料を立替金として処理した場合、インボイスには正しい消費税相当額が記載されていないことになる。結果、荷送人は仕入税額控除ができないこととなるので注意が必要だ。
(2)荷送人が保険契約を締結する場合
荷送人本人が保険会社と契約する場合には、荷送人が保険会社に支払う保険料は非課税となり、仕入税額控除の対象とはならない。この場合において、運送業者が荷送人から依頼を受けた上で保険会社に保険料を支払い、これを立替金として処理した上で荷送人に請求したような場合には、その保険料は運送業者にしてみればまさに立替金であり、このようなものについてまで売上高に計上する必要はない。
(3)荷主に代わって運送業者が付保する場合
貨物運送の場合の運送保険は、荷送人から付保の委任を受けた運送業者名で保険契約を結ぶことが認められている。この場合には、たとえ運送業者名で保険契約を結んでいたとしても、保険の効果は荷送人に帰属するので、事故があった場合には、荷送人に保険金が支払われることになる。
このような実態にある運送保険の保険料について、運送業者が立替金または仮払金として処理している場合には、荷送人から保険料相当額として収受する立替金または仮払金は売上高に含める必要はない。
2 配送料の預り金処理
商品の販売にあたり、購入者から商品の販売代金とは別に配送料を収受しているが、この配送料は、運送業者に支払う配送料にマージンを上乗せして購入者に請求している。
この場合において、購入者から収受した配送料と運送業者に支払う配送料を相殺し、残額のマージンを手数料として収益に計上することはできるか。
Answer
(1)別途収受する配送料の取扱い
課税商品などの販売にあたり、購入者から商品の販売代金とは別に配送料を収受する場合には、原則として商品の販売価格に配送料も含めた金額が課税標準(対価の額)となる。
一方、消費税法基本通達では、課税商品などの販売にあたり、配送を運送業者に委託するような場合には、購入者から商品の販売代金と配送料を明確に区分して収受し、その配送料を預り金又は仮受金等として処理しておけば、その配送料は対価に含めなくてよい旨が明記されている(消基通10−1−16)。
つまり、購入者から収受する配送料は、本来購入者が支払うべき配送料を単に預かり、これを運送業者に代理支払をしているに過ぎないため、これを預り金または仮受金等として明確に区分した経理処理を行っているならば、その配送料は対価の額には含まれないということである。
(2)本事例の問題点
本事例のケースでは、消費税法基本通達10−1−16を適用するために、収受する配送料を預り金として処理し、運送業者に支払う配送料は預り金勘定を取り崩して支払っているものと思われる。
この場合には、当然のことながらマージンの部分が預り金勘定に残高として滞留することになる。
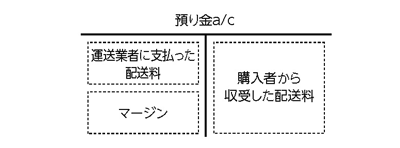
この場合において、預り金の残高を決算修正で雑収入勘定に振り替えたとしても、そのような処理自体がそもそも認められていないわけであるから、収受した預り金の全額が対価の額として認識されるものと考えるべきである。
(借方)預り金×× (貸方)雑収入××
↑
この部分だけを売上計上することは認められない
なお、簡易課税制度の適用を受ける場合には、購入者から収受した配送料収入は「運輸業」の売上げとして第5種事業に区分することになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























