解説記事2024年03月04日 巻頭特集 緊急特集 相続開始前にM&Aによる買収予定価額が示されていた株式の評価について(2024年3月4日号・№1017) ~総則6項の適否が争われた東京地裁令和6年1月18日判決を踏まえて~
巻頭特集
緊急特集
相続開始前にM&Aによる買収予定価額が示されていた株式の評価について
~総則6項の適否が争われた東京地裁令和6年1月18日判決を踏まえて~
税理士 香取 稔(元高松国税不服審判所長・埼玉学園大学大学院客員教授)
Ⅰ はじめに
評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》(以下「総則6項」という。)の適用に関して最高裁令和4年4月19日判決(以下「最高裁令和4年判決」という。)は、直接その適否を判断しなかったものの、相続財産の価額を評価通達に定める方法により評価した価額(以下「通達評価額」という。)を上回る価額で評価して課税処分を行うことは、「評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合」には違法性がない旨判示している。しかしながら、最高裁令和4年判決は、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」としてどのようなものが挙げられるかについて一般論として明示していなかった。
こうした中、非上場株式の評価について総則6項を適用した更正処分等の取消しを求めた訴訟において東京地裁令和6年1月18日判決(以下「本判決」という。)は、「相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が通達評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利益があるという評価をすることは相当でない」として、平等原則を理由に総則6項の適用を認めず、当該更正処分等を取り消した。
本判決は、課税庁が控訴したことから確定はしていないものの、本判決の判断プロセスは今後の総則6項の適用リスク等を検討する上で参考になると考えられることから、本稿では、本判決を踏まえた総則6項の適用の判断プロセスについて検討する。
Ⅱ 本判決についての検討
1 事案の概要
納税者(以下「本件相続人ら」という。)は、被相続人(以下「本件被相続人」という。)から相続(以下「本件相続」という。)により取得したO社の株式(以下「本件相続株式」という。)を評価通達に定める類似業種比準方式により1株当たり8,186円(以下「本件通達評価額」という。)と算定して相続税を申告した。
これに対し、課税庁は、本件相続株式は本件被相続人の生前にV社との間で本件相続株式を含むO社の全株式を1株当たり105,068円(以下「譲渡予定価格」という。)で譲渡することで基本合意(以下「本件基本合意」という。)しており、かつ、本件相続開始後に譲渡予定価格と同額の金額(以下「本件売却価格」という。)でV社にO社の全株式を譲渡する契約(以下「本件株式譲渡契約」という。)が締結されていたことなどから、総則6項を適用し、本件相続株式をDCF法によって1株当たり80,373円(以下「本件算定報告額」という。)と算定して更正処分等(以下「本件各更正処分等」という。)を行ったことから、本件相続人らがその処分の取消しを求めた事案である。
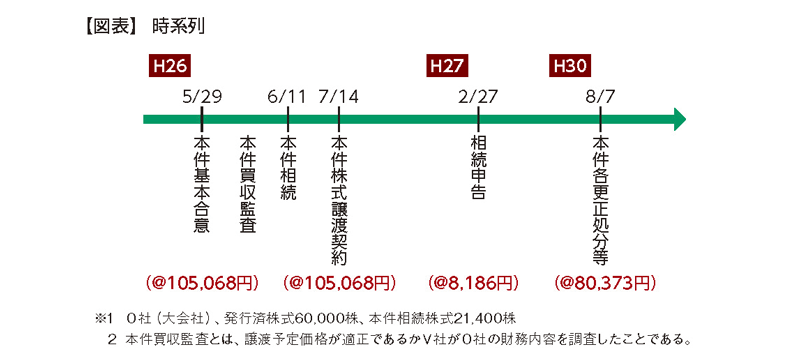
2 最高裁令和4年判決
本判決は、最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って総則6項の適否を判断していることから、本判決の内容を検討する前に、最高裁令和4年判決の内容を確認する(重要な判示部分を抜粋。下線は筆者による。)。
4(1)相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。
そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである。
そうであるところ、本件各更正処分に係る課税価格に算入された本件各鑑定評価額は、本件各不動産の客観的な交換価値としての時価であると認められるというのであるから、これが本件各通達評価額を上回るからといって、相続税法22条に違反するものということはできない。
(2)ア 他方、租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法よる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。
イ これを本件各不動産についてみると、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間には大きなかい離があるということができるものの、このことをもって上記事情があるということはできない。
もっとも、本件購入・借入れが行わなければ本件相続に係る課税価格の合計額は6億円を超えるものであったにもかかわらず、これが行われたことにより、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は2826.1万円にとどまり、基礎控除の結果、相続税の総額が0円になるというのであるから、上告人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。そして、被相続人及び上告人らは、本件購入・借入れが近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において上告人らの相続税の負担を減じ又は免れさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件購入・借入れを企画して実行したというのであるから、租税負担の軽減をも意図してこれを行ったものといえる。そうすると、本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、上記事情があるものということができる。
ウ したがって、本件各不動産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するということはできない。
3 本判決のポイントと解説
本判決は、総則6項の適用が認められる特段の事情(最高裁令和4年判決が判示するところの「実質的に租税負担の公平に反するというべき事情」をいう。以下同じ。)の有無について、最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って丁寧に判示していることから、以下、順次、その判示のポイントを示した上で、その内容を考察する(下線は筆者による。)。
(1)最高裁令和4年判決の解釈について
ア 最高裁令和4年判決は、実質的には、特段の事情がある場合に総則6項を適用することを肯定しているものと解されるが、当該特段の事情としてどのようなものが挙げられるかについて一般論として明示はしておらず、被相続人側の租税回避目的による租税回避行為がない場合について直接判示したものとは解されない。もっとも、最高裁令和4年判決が租税回避行為をしなかった他の納税者との不均衡、租税負担の公平に言及している点に鑑みると、租税回避行為をしたことによって納税者が不当ないし不公平な利益を得ている点を問題にしていることがうかがわれる。
☞ 最高裁令和4年判決は、現行の行政事件訴訟法のもとにおいて、取消訴訟の対象となるものは、直接に国民の権利義務を変動させる法的効果を持つものに限定されるのが原則(宇賀克也「行政法概説Ⅰ」319頁・(株)有斐閣)であるから、国民ないし裁判所を拘束しない評価通達の適用に関して判断をしていない。
しかしながら、最高裁令和4年判決は「実質的租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合には、通達評価額を上回る更正処分を行ったとしても平等原則には反しないと判断しており、この点は総則6項の適用を巡って争われた原審(東京高裁令和2年6月24日判決)及び従前の裁判例(東京地裁平成4年3月11日判決(控訴審:東京高裁平成5年1月26日判決、上告審:最高裁平成5年10月28日判決)、東京地裁平成4年7月29日判決(控訴審:東京高裁平成5年3月15日判決)、東京地裁平成5年2月16日判決(控訴審:東京高裁平成5年12月21日判決)、東京地裁令和2年11月12日判決(控訴審:東京高裁令和3年4月27日判決)の判断を概ね踏襲している。したがって、本判決が判示するとおり、実質的には、最高裁令和4年判決は特段の事情がある場合に総則6項の適用を肯定していると解される。
なお、本判決では、「租税回避行為」という言葉を使用しているが、最高裁令和4年判決は、それに代わるものとして「租税負担の軽減をも意図してこれを行った」という言葉を使用し、この点について最高裁令和4年判決に係る最高裁判所調査官は、「ここで問題となっているのは、時価に係る事実の(平等な)認定であり、いわゆる租税回避行為の否認ではない。本判決が『租税負担の軽減をも意図』した点についての判断に当たり、否認の根拠規定の有無や本件購入・借入れの経済的合理性等を全く問題としていないのはそのためである」旨述べている(山本拓「ジュリスト1581号」96頁・(株)有斐閣)。そして、本判決(後記(3)の判示部分参照)では、「相続税を軽減するために被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産などを購入して評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評価額の差異を利用する」ことを租税回避行為といっていることから、本判決中の「租税回避行為」とは、講学上の租税回避行為、すなわち租税法規が予定していない異常ないし変則的な法形式を用いて租税負担の減少を図るという行為を指すのではなく、最高裁令和4年判決と同様にもっと一般的な租税負担の軽減行為を指すものと解される。
(2)実質的な租税負担の公平に反する事情があるか否かの判断の仕方
イ 本件においては、最高裁令和4年判決の事案とは異なり、本件被相続人及び本件相続人らが相続税その他の租税回避の目的でO社株式の売却を行ったとは認められない。そうすると、本件各更正処分等の適否は、本件相続開始日以前に本件通達評価額を大きく超える金額での売却予定があったO社株式について、実際に本件相続開始日直後に当該金額で予定どおりの売却ができ、その代金を本件相続人らが得たことをもって、この事実を評価しなければ、「(取引相場のない大会社の株式を相続しながら通達評価額を大幅に超えるこのような売却による利益を得ることができなかった)他の納税者と原告らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反する」(最高裁令和4年判決)といえるかどうかによって判断すべきことになる。
☞ 本判決は、最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って総則6項の適用が許される特段の事情の有無について、相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が通達評価額を著しく超えていたという事実が、他の納税者と本件相続人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するといえるかどうかによって判断したものであるが、最高裁令和4年判決は相続税の負担の軽減行為が認められた事案であったのに対し、本判決は同行為が認められなかった事案であるから、直ちに最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って当該審理を進めるのが相当であるか否か疑義が生じないでもない。
しかしながら、最高裁令和4年判決では、「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」がある場合には、通達評価額を上回る価額による更正処分を容認しており、同判決に係る最高裁判所調査官は、「実質的な租税負担の公平を問題とする以上、これに影響する当該財産の取得の経緯等の事情が含まれる一方、通達評価額によることが他の納税者との間の租税負担の均衡を害することになる事情に限られるというべきであり、そのような事情に当たるか否かを検討する必要がある」とし、同判決中の「本件各不動産の価額について評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件購入・借入れのような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と上告人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべきであるから、平等原則が適用されない合理的理由がある。」旨の判示部分について「事例判断ではあるが、その考え方は不動産以外の相続財産が問題となる事案においても参考になる」とし、同判決は「具体的な事例に即した判断を示したものであり、同種事案における審理判断の枠組みを明らかにするものとして、理論上も実務上も重要な意義を有する」旨述べている(山本拓・前掲書95頁以下)。
したがって、総則6項の適用が許される特段の事情の有無は、原則として最高裁令和4年判決の判断枠組み、すなわち、相続財産の評価を通達評価額によることが他の納税者との間の租税負担の均衡を害することになるか否かによって判断するのが相当であるといえる。
(3)相続開始後に相続財産を通達評価額よりも著しく高い価額で売却できた場合にその売却額で申告しないことは実質的な租税負担の公平に反する事情といえるか
ウ 相続開始後に納税等の理由により、相続財産の一部を売却して現金化することは特別稀有な事情ではないが、かかる際に通達評価額よりも相当高額で現金化することができたとしても、当該売却やそれに向けて交渉すること自体は何ら不当ないし不公平なことではなく、仮にそのような売却を行うことができたとしても、売却価額ではなく通達評価額で当該財産を評価して相続税を申告することが問題視されることは一般的でない。また、相続開始後に相続財産を通達評価額よりも著しく高い価格で売却することができたとしても、当該売却による利益は譲渡所得税による納税対象とされることになるし、これによって相続時と売却時に二度納税することになる。こうした点を考慮すれば、相続税を軽減するために被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産などを購入して評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評価額の差異を利用する租税回避行為をしているような場合でない限り、当該相続対象財産を通達評価額を超える価格で評価して課税しなければ相続開始後に相続財産の売却をしなかった又はすることができなかった他の納税者と比較してその租税負担に看過し難い不均衡があるとまでいうことは困難である。
逆に、ある財産を相続して通達評価額で相続税を納税した上で、一定期間経過後に当該財産を通達評価額と比して著しく高い価格で売却することができた者を想定すると、本件更正処分等のように相続直近の時期に売却した者のみ当該売却価格に着目されて通達評価額を超える財産評価を受けて高額の相続税納税義務を負うという不利益が生ずることも想定される。そうすると、相続直後に相続財産を通達評価額を著しく超える価額で売却した(又はすることができた)者が売却しなかった(又はすることができなかった)者に比して常に有利とも限らず、むしろ、相続財産を相続開始直後に売却した場合にのみ通達評価額を超える財産評価を受けることは、明らかに前者にとって不利であるともいえる。このように考えると、相続開始直後に相続財産の一部を高額で売却することができたとしても、その事実に着目して相続課税をしなければ他の納税者との間で租税負担に看過し難い不均衡があるとは必ずしも断じ得ない。
☞ 最高裁令和4年判決では、本件各通達評価額と本件各鑑定評価額との間に大きなかい離があるが、そのことをもって「実質的な租税負担の公平に反するというべき事情」があるということはできないと判示している。この点に関して最高裁令和4年判決に係る最高裁判所調査官は、「実質的な租税負担の公平という観点からは、同様のかい離は類似の不動産にも広く存在し得る以上、これを相続する潜在的な他の納税者と同じく通達評価額によったとしても租税負担の均衡が害されることはなく、むしろ、当該納税者についてのみ通達評価額を上回る価額によることは不合理というべきである(このようなかい離は、本来、評価通達の見直し等によって解消されるべきものといえる)。」旨述べている(山本拓・前掲書95頁)。
そうすると、一般的に相続財産の通達評価額と時価(客観的な交換価値)との間にかい離が生じていることは公知の事実であるから、本件のように本件相続株式が本件相続開始後に売却されたことによって、そのかい離が顕在化したことをもって、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情に当たるとはいえない。
なお、本判決では、総則6項の適用が許される場合について「相続税を軽減するために被相続人の生前に多額の借金をした上であらかじめ不動産などを購入して評価通達の定める方法における現金と不動産など他の財産に係る評価額の差異を利用する租税回避行為をしているような場合でない限り」と限定的に解しているが、東京地裁平成5年2月16日判決においても、総則6項の適用が実質的な税負担の公平を図るという見地から正当として是認されるのは、「被相続人が敢えて銀行から資金を借り入れて債務を負担し、その借入金によって不動産を取得することにより、その債務を相続債務として計上し、結果としてその債務額を他の積極財産の価額から控除されるという利益を享受することとなる場合であることを要するものである。したがって、銀行からの借入金によって購入されたものではなく、他の不動産を売却して得た代金を資金として取得されたため、右のような方法による相続税の節減に何ら寄与しない物件については、その相続財産としての価額を右通達以外の客観的な交換価格によって評価することを正当化する理由はなく、その評価は、通常の場合と同様に、右通達に定める方法によって行われるべきものである。」旨判示している。
(4)本件基本合意をもって実質的な租税負担の公平に反する事情といえるか
エ 本件では、本件相続開始日直後に本件売却価格という通達評価額を大幅に上回る高値で本件相続株式を売却することができたという事実に加え、本件相続開始日以前から本件被相続人がO社株式の売却の交渉をしており、かつ、その生前の段階でV社との間で譲渡予定価格まで基本合意していたという事情が認められる。しかしながら、一般にM&Aが終了しても前オーナーがしばらく会長や顧問等の職に就き、引継ぎを円滑に行うようにすることが多く、逆にM&Aの途中で前オーナーが死亡した場合には(引継ぎが困難になるため)買い手側が手を引く例があるところ、本件においても、本件被相続人はO社のカリスマ的なオーナーであったため、V社(本件基本合意以前から本件被相続人に対し、平成26年度の定時株主総会までは取締役会長に、その後も相談役又は顧問に留まって欲しい意向を表明していた。)が本件相続開始によって本件相続株式の買取りを取りやめる可能性もあったことがうかがわれるのであって、本件基本合意が本件相続の後も本件相続人らとの間でそのまま存続するか否か自体、本件相続開始日において不透明な状況であったといわざるを得ない。なお、上記の点に加え、本件基本合意が譲渡予定価格等について本件被相続人及びV社を法的に拘束するものではないとした点や本件被相続人においてO社株式の全部を取りまとめ又は買い集めることが前提条件とされていた点などに鑑みれば、譲渡予定価格による本件相続株式の売買代金債権を相続財産と同視することも困難である。したがって、本件相続開始日以前からO社株式の譲渡予定価格が本件被相続人とV社との間で事実上合意されていたという事情を殊更重視するのは相当でない。
加えて、相続開始後に通達評価額より著しく高い価額での売却によってほぼ同額の利益を得た納税者を想定した場合においても、上記売却に向けた交渉が相続の前後にまたがっている納税者に対して当該売却額に着目した相続課税をしなければ、相続開始後に売却に向けた交渉を開始した納税者との間に租税負担の点で看過し難い不均衡があるともいえない(むしろ、前者に対しのみ高額の課税をすることの方が不公平とも考えられる。)。
以上によれば、本件相続開始前からO社株式の譲渡予定価格が事実上合意されていたという事情をもって、特段の事情(の一部)ということはできない。
☞ 相続開始時において売買契約中の土地(売主側)の評価について東京高裁昭和56年1月28日判決は総則6項の適用を認めたが、上告審の最高裁昭和61年12月5日判決は、原審の判断を採用することなく相続財産は土地そのものではなく売買契約に係る残代金請求権であるとして評価した。したがって、本件のように相続開始時点において相続財産となる株式について売買契約が成立していない場合は、原則として売主側の相続財産は株式として通達評価額により評価されることになる。
また、贈与土地の評価について課税庁が、当該土地は、贈与者が当該土地の買取り等の申出を受けた後に贈与をしていることから、当該土地の評価は通達評価額によることなく当該買取り等の申出に基づく売却予定価額であるとして決定処分等をした事案の取消しを求めた審査請求において、平成20年7月8日裁決・TAINSコードF0-3-692は、大要「贈与により取得した財産の価額は、特別な事情がない場合には、評価通達により定められた評価方法によって画一的に財産の評価を行うのが相当であるところ、起業者による買取り等の申出に基づく売却予定価額は、贈与税の課税時期における時価としての客観的な交換価値が顕在化したものとまでは認め難く、また、評価通達により定められた評価方式で評価した場合の価額が買収予定価額に比べ著しく低額となることをもってしても特別の事情が存するとはいえないことに加え、当審判所の調査によっても、本件土地の評価に当たり、財産評価基本通達に定める評価方法を適用することが著しく不合理であるとする特別な事情があるとは認められないことからすれば、本件土地の価額は、評価基達によって評価した価額とするのが相当である。」旨裁決している。
本件相続株式を含むO社の全株式については、本件相続開始日現在において本件株式譲渡契約が締結に至っていないことから、本件基本合意をもって売買契約中であったとはいえない。そして、本件基本合意が本件相続の後も本件相続人らとの間でそのまま存続するか否か自体、本件相続開始日において不透明な状況であったこと及び本件基本合意には本件株式譲渡契約の締結及び譲渡予定価格について本件被相続人及びV社を法的に拘束するものではないことが定められていたことなどからすれば、本件基本合意に基づく譲渡予定価格は、本件相続開始日現在にける本件相続株式の時価としての客観的な交換価値が顕在化していたとまでもいえない。
そうすると、本件基本合意をもって租税負担の公平に反する事情の一部であるということは到底いえず、そのことは、相続財産となり得る財産の売却交渉が相続の前後にまたがっている納税者と相続開始後に売却交渉を開始した納税者との比較を待つことなく明らかであると考える。
(5)相続開始後の相続財産の売却価格を評価額に反映させないことは評価通達の趣旨等に反するか
オ また、評価通達は、総則6項が適用される場合を除き、公開株式のように個別性が低く客観的な価格が容易に算定され又は判明するような相続財産でない限り、不動産など個別の評価において、あらかじめ定められた一定の方法で算出された価格をもって当該相続財産の価格と評価することとしており、当該方法によって算定された価格ではなく、相続開始後に行われた当該財産の具体的な取引価格を参照したり、類似の取引事例を考慮して当該財産を評価したりする方法は採用していない。仮に、課税庁が相続開始後の取引といった個別事情を考慮するとなれば、相続開始日と売却時期がどの程度接近していれば当該売却の事実を考慮するのか、通達評価額と売却価額の間にどの程度の差があれば総則6項に基づく個別評価をするかといった点などが問題になるところ、これらについての基準はなく、課税庁が個別的にその適否を判断することにならざるを得ない。しかしながら、そのようなこと自体、課税庁による恣意的判断が介入したり、他の事例との間で不合理な差異が生じたりする余地があって、評価通達の趣旨や平等原則の要請に反するというべきであり、適用の有無の別やその具体的方法の差異について、納税者間に不均衡又は不利益が生ずる可能性を否定することができない。
これを納税者側から見ると、相続税の申告前に、相続後に全部又は一部の相続財産を通達評価額とは異なる額で売却した場合において、当該通達評価額に従って算出した額で申告をすべきかどうか、いかなる場合にこれと異なる額で申告すべきかなどが一切明らかでないこととなるし、同様に、相続税申告後相続財産を売却した場合に、その売却額に従って算出した額で修正申告をすべきかどうかもあきらかではない。また、納税者側が、通達評価額に依って申告をした場合には、事後的に課税庁の判断で通達評価額とも売却額とも異なる額を前提とした予測可能性のない更正処分を受ける危険を負わなければならない。総則6項という極めて抽象的な規定を除けば、法令にも評価通達その他の通達にもかかる事態が具体的に想定されているとは解し難い点も併せて考えれば、納税者側が租税回避行為をしていたような場合は別として、納税者がかかる不安定な地位に置かれ、不利益を受けるのは、申告納税制度や評価通達の趣旨に照らし、強い疑問が残るものといわざるを得ない。
☞ 相続税法は、相続税の課税価格は相続によって取得した財産の価額の合計額であるとし(相法11条の2①)、相続によって取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとしている(相法22)。そして、右にいう「取得の時」とは、具体的には被相続人の死亡の日をいい、「時価」とは、客観的な交換価値、すなわち不特定多数の独立当事者間の自由な取引において通常成立すると認められる価額をいうものと解されている。したがって、相続税の課税価格に算入されるべき価額は相続時における当該財産の時価と解すべきであるから、時価の算定上、原則として相続開始後に行われた相続財産の具体的な取引価格を参照したり、類似の取引事例を考慮して当該財産を評価したりする方法を採用することは、そもそも許されない。
それに加え、評価通達1《評価の原則》(2)は、「財産の価額は時価によるものとし、……その価額はこの通達によって評価した価額による」と定めており、取引価額などが明らかでない場合にのみ補充的に評価通達を適用すべきでものとは定められていない。そして、評価通達では、個々の財産の評価は、売買実例価額による方法(評基通169)、調達価額又は取得価額による方法(評基通136)、及び再調達価額による方法(評基通97)など、一定の定められた方法により評価することとしている。
そうすると、課税庁が相続財産の評価に当たり相続開始後の取引といった個別事情を考慮し、相続開始後の相続財産の売却価格を評価額に反映させること自体、相続税法22条や評価通達が予定していないことから、上記判示のとおり申告納税制度や評価通達の趣旨に反し許されるものではないと解される。
また、上記の判示は、課税庁が評価通達は、「客観的な交換価値を端的に評価し得る場合にはそれによることが最も望ましいという考えを前提にしていることからすれば、相続開始時において、売買当事者間の主観的事情を離れた当該株式の客観的な交換価値を反映した取引価格が明示されていることなどから当該株式の客観的な交換価値と評価し得る価格が明らかになっているという事情がある場合には、特段の事情がある」旨の主張を受けて行われたものである。
この点に関しては、非上場株式の評価について評価通達に定める方法によらず、その取引価格を基に評価することが許されるか否かについて争われた訴訟において東京地裁平成17年10月12日判決は、大要「他により高額の取引事例が存するからといって、その価額を採用するということになれば、評価通達の趣旨を没却することになることは明らかである。したがって、仮に他の取引事例が存在することを理由に、評価通達の定めとは異なる評価をすることが許される場合があり得るとしても、それは、当該取引事例が、取引相場による取引に匹敵する程度の客観性を備えたものである場合等例外的な場合に限られるものというべきであるから、本件売買実例は、実質的に見れば、わずか3つの取引事例というのにすぎず、この程度の取引事例に基づいて、主観的事情を捨象した客観的な取引価格を算定することができるかどうかは、そもそも疑問であるといわざるを得ない(なお、この種の主張は、他の訴訟において課税庁自身がしばしば主張しているものであることは当裁判所に顕著である。)。」旨判示している。
そうすると、譲渡予定価格又は本件売却価格は、上場株式の取引に匹敵する程度の客観性を備えた取引事例を基に決められたわけではなく、当事者の交渉によって決められたにすぎないことから、本件相続株式の客観的な交換価値を反映した取引価格であるとはいえない。したがって、課税庁の主張は、その前提を欠き失当であるといわざるを得ない。
なお、課税庁は、審査請求段階(令和2年7月8日裁決・TAINSコードF0-3-692)では「本件基本合意により本件相続株式の価値が顕在化しており、本件通達評価額と譲渡予定価格との間には著しいかい離がある」ことをもって総則6項の適用理由としてきた。しかしながら、その後の最高裁令和4年判決を受け、単に著しいかい離があることをもって総則6項の適用を維持することが困難となったことから、このような無理な主張を展開せざるを得なかったのではなかろうかと考える。
(6)小括
カ 以上の点を考慮すれば、本件のように相続財産となるべき株式売却に向けた交渉が相続開始前から進行しており、相続開始後に実際に相続開始前に合意されていた価格で売却することができ、かつ、当該価格が通達評価額を著しく超えていたという事実をもってしても、直ちに納税者側に不当ないし不公平な利得があるという評価をすることは相当でなく、総則6項を納税者の不利に適用するに当たっては、上記オで説示したような不均衡や不利益等を納税者に甘受させるに足りる程度の一定の納税者側の事情が必要と解すべきである。例えば、被相続人の生前に実質的に売却の合意が整っており、かつ、売却手続きが完了することができたにもかかわらず、相続税の負担を回避する目的をもって、他に合理的な理由もなく、殊更売却手続を相続開始後まで遅らせたり、売却時期を被相続人の死後に設定しておいたりしたなどの場合であるとか、最高裁令和4年判決の事例のように、納税者側が、それがなかった場合と比較して相続税額が相当程度軽減される効果を持つ多額の借入れやそれによる不動産等の購入といった積極的な行為を相続開始前にしていたという程度の事情が必要なものと解される。
☞ 本判決における判断過程(上記(1)から(5))からすれば、本件のような事案について総則6項が適用できないと判断したことは相当であると考える。また、本判決は、納税者の不利に総則6項を適用できる場合として2点例示しているが、いずれも本件の事案に即したものであると解される。
Ⅲ 本判決の意義等
本判決は、冒頭でも述べたとおり課税庁が控訴したことから確定はしていない。今後、控訴審において課税庁がどのような主張を展開するかわからないが、①本件は、非上場株式を相続しながら通達評価額を大幅に超えるような売却による利益を得ることができなかった他の納税者と比較してその租税負担に看過し難い不均衡があるとは認められないこと、②本件基本合意による譲渡予定価格は、上場株式の取引に匹敵する程度の客観性を備えた取引事例を基に決められたわけではないこと、及び③相続開始後の相続財産の売却価格を評価額に反映させること自体、相続税法22条や評価通達が予定していないことなどからすれば、少なくとも原審での本件基本合意等をもって総則6項の適用が許されるという主張だけでは、難しいのではないかと考える。
本判決は、あくまでも本件の客観的事実関係の下での非上場株式等の価額の評価について総則6項の適否を判断した事例判決ではあるが、次に掲げる三点について今後の同項の適否を考える上で参考となる有意義な判決であると思料される。
1 本判決は、非上場株式の評価を巡る総則6項の適用の可否に関して最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って審理することを明らかにした。この点については、従来、最高裁令和4年判決が総則6項の適用の可否について直接判断したものではなく、また、不動産の評価に関し相続税の負担軽減行為が認められた事案であったことから、当該事案と事情を異にする事案について総則6項の適用リスクを考える際、同判決の判断枠組みに沿ったところで検討してよいか否か疑義があったところである。
しかしながら、本判決は、最高裁令和4年判決が実質的に特段の事情がある場合に総則6項を適用することを肯定しているものと解し、同判決の判断枠組み、すなわち、財産の評価について通達評価額によることが他の納税者との間の租税負担の均衡を害することになる事情の有無によって、総則6項の適用の可否を判断することを明らかにした。したがって、総則6項の適用リスクについては、最高裁令和4年判決の判断枠組みに従って検討することができるようになったといえる。
2 相続税の申告を受任した場合、相続人から相続財産の一部を相続税の申告期限までの間に売却したいという相談を受けることがあるが、その売却価額が相続財産の通達評価額より著しく高額であるときなどは、総則6項の適用が頭をよぎり、相続税の申告期限後に売却してはどうかなど否定的な回答をしていた方も多いのではなかろうか。
しかしながら、本判決によって、被相続人等による相続税の負担軽減行為を欠く場合には、①被相続人が相続開始前から売却交渉を進めていた財産について、相続開始後に相続人が当該財産の売却をしたとき、又は②相続開始後に相続人等が遺産分割や納税資金の確保等のために相続財産の売却交渉を始め、相続税の申告期限までに売却をしたときであっても、総則6項の適用リスクを考える必要がなくなったといえる。
3 本判決は、平等原則違反を理由に本件更正処分等を取消した。評価通達の適用に関し平等原則違反を理由に課税処分が取り消された事例は、本判決が初めてのものではなかろうか。
平等原則は、租税法の基本原則である租税公平主義に基づくもの、すなわち、「憲法14条1項に由来するもので、課税の上で、同様の状況にあるものは同様に、異なる状況にあるものは状況に応じて異なって取り扱われるべきことを要求するもの」(金子宏「租税法(第24版)」89頁・有斐閣)である。
総則6項の発動については、最高裁令和4年判決が是認されたことを受け、税務調査においてその適用を示唆されることが多くなったような感があったが、本判決により、当面、被相続人等による相続税の負担軽減行為を認定できないような場合には慎重にならざるを得ないのではないかと考える。
香取 稔 (かとり みのる)
国税庁資産課税課において相続税の審理(通達の制定等)に従事した後、東京地方裁判所行政部調査官、東京国税局課税第一部資産評価官、同資料調査第2課長、高松国税不服審判所長を経て、現在、税理士・埼玉学園大学院客員教授(経営学研究科)。
(主な著作)
・「令和5年改訂版 相続税重要項目詳解」 大蔵財務協会 2023年
・「新判 事例で学ぶ土地・株式等の財産評価」 清文社 2023年
・「マンション節税と相続税のシミュレーション」(共著) ぎょうせい 2023年
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























