解説記事2024年03月04日 解説 「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の解説(2024年3月4日号・№1017)
解説
「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の解説
金融庁企画市場局企業開示課開示企画調整官 上利悟史
金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 牧野一成
はじめに
2023(令和5)年12月22日、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和5年内閣府令第81号。以下「改正府令」という。)が公布され、本年4月1日から施行されることとなった。本改正は、2022(令和4)年6月13日に公表された金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告(脚注1)(以下「DWG報告」という。)における提言を踏まえ、有価証券報告書の開示事項の一つである「重要な契約」に関する開示の拡充を図るものである。
本稿は、本改正についての解説を行うものであるが、その内容については各開示書類において共通する部分が多いことから、以下では、主に企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「開示府令」という。)及び同府令に基づいて提出される有価証券報告書について解説を行う。また、本改正に伴い、「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「開示ガイドライン」という。)の改正もされたが、この内容についても、必要な範囲で触れることとしたい。
本稿において意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解である。
Ⅰ 改正の背景及び概要
開示府令では、本改正前においても、企業が重要な契約を締結している場合、有価証券報告書等の【経営上の重要な契約等】にその概要を記載することが求められていた(開示府令第三号様式記載上の注意(13)において準用する同第二号様式記載上の注意(33)a等)。また、借入金や社債等に付された財務上の特約のうち、投資判断に重要な影響を及ぼすと認められるものについては、財務諸表への注記(追加情報の注記等)が求められている。
しかし、このような規定にもかかわらず、我が国における重要な契約や財務上の特約の開示状況は、同様の制度を有する諸外国と比較して不十分であるとの指摘がされていた。その背景としては、開示対象が「投資判断にとって重要な契約」であることが十分に実務に浸透していないことや、明示的に開示が求められていなければ開示不要との受止めの下、企業が開示に消極的になっている面があるといったことが指摘されている。このような状況を踏まえ、DWG報告では、企業・株主間のガバナンスに関する合意、企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意及びローン契約(金銭消費貸借契約)と社債に付される財務上の特約の3つの類型を取り上げて、開示すべき具体的な対象やその開示内容について提言を行った。
本改正は、DWG報告における上記提言を踏まえたものであり、その概要は、図表のとおりである。本改正では、企業・株主間のガバナンスに関する合意、企業・株主間の株主保有株式の処分・買増し等に関する合意及び財務上の特約の3類型を有価証券報告書等において「重要な契約等」(脚注2)として開示すべきことを明確化するとともに、財務上の特約について、新たな臨時報告書の提出事由を追加したものである。
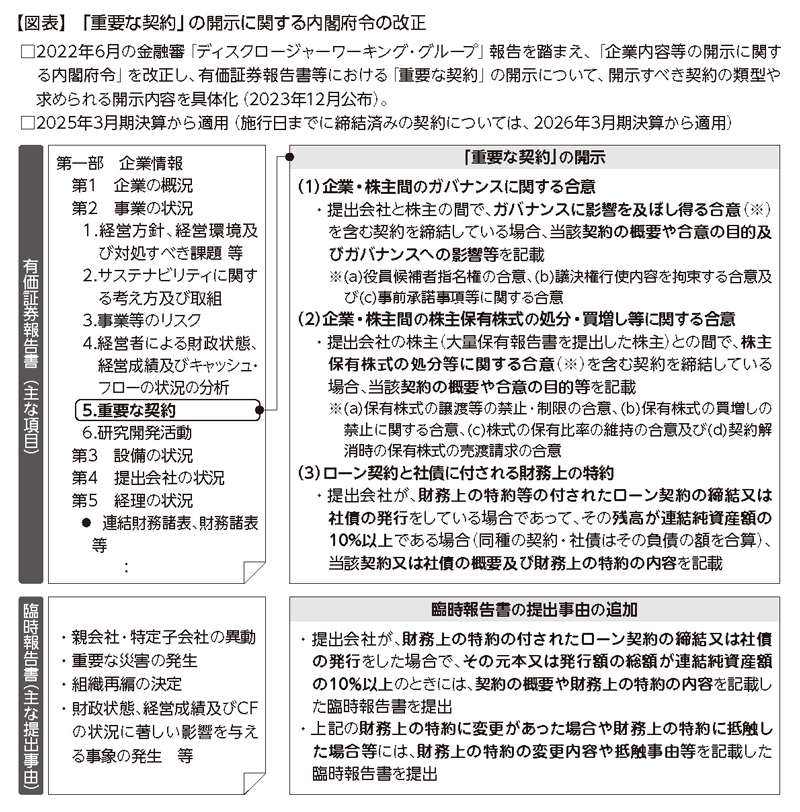
以下、それぞれの類型ごとに、開示対象及び開示内容等について解説を行う。
Ⅱ ガバナンスに関する合意(開示府令第三号様式記載上の注意(13)において準用する同第二号様式記載上の注意(33)f等)
1 改正の趣旨
企業と株主の間で、企業の役員の指名権を株主に認める合意や、企業による一定の行為(新株発行や組織再編等)について株主の事前承諾を求める合意といった、企業のガバナンスに関する合意が締結されることがある。これらの合意は、一般に、当該企業のガバナンスや支配権への影響が大きく、投資判断に重要な影響を及ぼすことが見込まれるものであるため、「重要な契約」として、適切な開示を求めるものである。
2 改正内容
本改正では、提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあっては、当該提出会社又はその連結子会社)が、提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除く。)との間で以下の合意を含む契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結している場合に、当該契約を「重要な契約」として開示すべきこととしている。
・当該提出会社の役員について候補者を指名する権利を当該株主が有する旨の合意
・当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意
・当該提出会社の株主総会又は取締役会において決議すべき事項について当該株主の事前の承諾を要する旨の合意
上記契約を締結している場合には、提出会社は、有価証券報告書等の「重要な契約等」欄において、当該契約の概要(当該契約を締結した年月日、当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所(脚注3)並びに当該合意の内容を含む。)、当該合意の目的、取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程及び当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由)を具体的に記載することを定めている。なお、今般の改正により開示すべき事項は、契約の「概要」であり、守秘性の高い情報を含め、その内容を詳細に開示することまで求めるものではなく、投資判断に対する重要性に応じて投資者の理解を損なわない程度に要約して記載することも考えられる(下記Ⅲ「株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」についても同じ)。また、記載すべき事項の全部又は一部を有価証券報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該事項の記載を省略することができる。
3 留意点
本改正では、一定の合意を含む契約の開示を求めるものであるが、ここでいう「合意」とは、法的拘束力を有するものに限られる。したがって、法的拘束力を伴わない単なる口約束などは開示対象から除かれるものの、他方で、契約書等の書面が作成されていない口頭の合意であっても、合意に至るまでの経緯や合意の内容等(脚注4)の諸般の事情から法的拘束力を持つと認められる場合には、開示の必要があることに留意する必要がある(下記Ⅲ「株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」の開示についても同じ)。
また、上記のとおり、「重要性の乏しい」合意・契約は、本改正による開示対象から除かれる。その重要性の判断にあたっては、当該合意が提出会社のガバナンスや支配権、その他の株主に与える影響を踏まえて個別具体的に検討されるべきであるが、例えば、ガバナンスに対する影響が限定的であるもの(例:通常の事業過程で締結されたものであり、かつ、事前承諾の対象となる行為が一部に限定されているもの(株主とのライセンス契約の中で訴訟提起に当たっては相手方の同意を要すると合意することなど))や、少数株主の保護の必要性が乏しい場合(例:合意の相手方以外の株主が特定かつ少数で、その全員が合意の内容を認識している場合等)については、「重要性の乏しい」場合に該当することが多いと考えられる。
Ⅲ 株主保有株式の処分・買増し等に関する合意(開示府令第三号様式記載上の注意(13)において準用する同第二号様式記載上の注意(33)g等)
1 改正の趣旨
企業と株主との間で締結される、当該株主が保有する株式に関する合意(譲渡制限や買増しの禁止、保有比率の維持等を内容とするもの)は、その株式保有の規模や合意内容等に応じ、市場に影響を与え、投資判断に一定の影響を及ぼすことが見込まれる。そこで、これらの合意のうち、特に市場に与える影響が大きいものについては、「重要な契約」として、開示を求めることとした。
2 改正内容
本改正では、提出会社が、大量保有報告書を提出している株主との間で締結している契約(重要性の乏しいものを除く。)を締結している場合には、当該契約を「重要な契約」として開示することとしている。
・当該株主による当該提出会社の株式の譲渡その他の処分について当該提出会社の事前の承諾を要する旨の合意
・当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合を超えて当該提出会社の株式を保有することを制限する旨の合意
・当該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に、当該株主がその株式保有割合に応じて当該株式を引き受けることができる旨の合意
・当該契約が終了した場合に、当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出会社の株式を当該提出会社(当該提出会社が指定する者を含む。)に売り渡すことを請求することができる旨の合意
そして、上記契約を締結している場合には、当該契約の概要(当該契約を締結した年月日、当該契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに当該合意の内容を含む。)、当該合意の目的及び取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程を具体的に記載することを定めている。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を有価証券報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該事項の記載を省略することができる。
3 留意点
上記のとおり、「重要性の乏しい」合意・契約は本改正による開示対象から除かれる。その重要性の判断にあたっては、当該合意が市場やその他の株主に与える影響を踏まえて個別具体的に検討されるべきであるが、例えば、市場における当該株式の流動性に対する影響が限定的であるもの(例:組織再編等の交渉に際し一時的に相手方の保有する株式の買増しを制限する旨の合意を締結するなど、未公表の重要事実に関連して暫定的な合意を締結する場合(脚注5))や、少数株主の保護の必要性が乏しい場合については、「重要性の乏しい」場合に該当することが多いと考えられる。
Ⅳ 財務上の特約
1 本改正の趣旨
資本市場が、事業のリスク等に応じた資金配分を行い、金利等を通じた価格発見機能を発揮する上で、社債やローンの基本条件、特に財務上の特約が適切に開示されることは極めて重要と考えられる。特に財務上の特約については、その抵触が他の債権者のキャッシュ・フローに影響を与え、経営陣の裁量を制限するとの観点からも開示の重要性が高い。また、抵触前段階から財務上の特約が適切に開示されることで、市場全体としての予測可能性が高まり、企業と投資家の間の円滑なコミュニケーションにも資すると考えられる。
本改正は、以上の趣旨を踏まえ、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約及び社債のうち、特に重要性の高いものについて、開示を求めるものである。
2 臨時報告書における開示
(1)契約締結時・社債発行時の開示
本改正は、開示すべき「財務上の特約」を「当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを条件として当該提出会社が期限の利益を喪失(脚注6)する旨の特約」として定めている。
そして、提出会社が、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(脚注7)を締結し又は社債を発行した場合であって、その元本の額(発行額)(脚注8)が当該提出会社の連結純資産額の10%以上である場合には、臨時報告書を提出することが求められる(連結子会社との間で契約を締結した場合又は連結子会社に対し社債を発行した場合を除く。開示府令19②十二の二。連結子会社について、同19②二十)。
この臨時報告書には、財務上の特約の内容のほか、契約締結(社債発行)の年月日、当該契約の元本額(発行価額)、弁済期限(償還期限)及び契約(社債)に付された担保の内容を記載する必要があり、「財務上の特約の内容」については、抵触事由の基準となる財務指標の内容やその数値、財務上の特約に抵触した場合の効果等を記載することが考えられる(脚注9)。また、金銭消費貸借契約の場合は、その相手方の属性についても記載する必要があり、「相手方の属性」については、個人名や個社名の開示まで求めない趣旨であって、「個人」や「事業会社」のほか、相手方が金融機関である場合にはその種別(都市銀行、地方銀行、協同組織金融機関等)を記載することが考えられる(脚注10)。
なお、残高の額が最近事業年度末の連結純資産額の10%以上である既存の契約や社債に対し、新たに財務上の特約が付されることになった場合も、同様に臨時報告書を提出する必要がある。
(2)契約内容等の変更及び財務上の特約の抵触時
本改正では、提出会社が締結し又は発行した、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変更、財務上の特約の内容の変更(当該財務上の特約に定める事由及び当該事由の発生があった場合の効果に照らして軽微なものを除く。)又は財務上の特約に定める事由の発生(特約への抵触)があった場合(脚注11)に、臨時報告書の提出を求めている(開示府令19②十二の三。連結子会社について、同19②二十一)。
この臨時報告書には、当該契約及び社債の概要(締結日、元本額、弁済期限及び担保の内容、契約の相手方の属性)のほか、弁済期限や財務上の特約の内容に変更があった場合にはその内容及び変更が生じた年月日を、財務上の特約への抵触があった場合には、その内容、抵触が生じた年月日及びその状況を解消し、又は改善するための対応策を記載する必要がある。我が国の金融実務においては、財務上の特約の抵触が生じた場合であっても、直ちに期限の利益を喪失させることなく、金融機関側において期限の利益の喪失を免除する措置(ウェイブ)が取られることがあるが、このような措置に関する合意が金融機関側との間で成立している場合には、その旨を「対応策」として記載することが考えられる。
3 有価証券報告書における開示(開示府令第三号様式記載上の注意(13)において準用する同第二号様式記載上の注意(33)h等)
提出会社が財務上の特約その他当該提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす可能性のある特約が付された金銭消費貸借契約の締結又はこれらの特約が付された社債の発行をしている場合であって、その金銭消費貸借契約に係る債務又は社債の期末残高が当該提出会社の連結純資産額の10%以上に相当する額であるときは、有価証券報告書等の「重要な契約等」欄において、当該財務上の特約の内容、契約締結(社債発行)の年月日、当該契約(社債)の期末残高、弁済期限(償還期限)及び契約(社債)に付された担保の内容を記載する必要があり、金銭消費貸借契約に関しては、その相手方の属性についても記載する必要がある(連結子会社が上記に該当する金銭消費貸借契約を締結し又は社債を発行している場合も同様。)。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を有価証券報告書の他の箇所において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該事項の記載を省略することができる。
なお、期末残高の算出に当たっては、複数の金銭消費貸借契約(社債)に同種の特約が付されている場合にあっては、各金銭消費貸借契約(社債)に係る債務の期末残高を合計する必要がある。「同種の特約」とは、貸し手の異同を問わず、基準となる財務指標及びその値が同一であるものをいうが、基準となる財務指標又はその値が異なる場合であっても、その差異の内容及び程度に照らして実質的に同種と認められるものについては、これを「同種の特約」として取り扱うことができる(開示ガイドライン5−17−7)。
Ⅴ 施行時期
本改正に係る内閣府令は、2024(令和6)年4月1日から施行され、以下のとおり適用される(なお、開示ガイドラインについては、同日より適用)。
1 「重要な契約」の有価証券報告書等への記載(上記Ⅳ2以外)
2025(令和7)年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から適用される(改正府令附則3①)。ただし、施行日(2024年4月1日)前に既に締結された契約については、契約の見直しや開示への対応に時間を要することに鑑み、2025(令和7)年3月31日以前に開始する事業年度に係る有価証券報告書等までは、その記載を省略することができる(同附則3②)。例えば3月決算会社であれば、2025年4月1日から開始する事業年度である2026年3月期の有価証券報告書から、施行日前に締結されていた契約も含めて記載することが求められる。
2 財務上の特約に係る臨時報告書の提出(上記Ⅳ2)
2025(令和7)年4月1日以後に提出される臨時報告書から適用される(改正府令附則2①)。ただし、施行日前に既に締結された契約について、弁済期限や財務上の特約に変更があった場合には、2026(令和8)年3月31日までは、臨時報告書の提出義務が免除される(同附則2②)。
おわりに
本改正は、「重要な契約」として開示すべき対象や内容を明確化することで、投資判断にとって重要な情報の提供を推し進め、企業と投資家との間の円滑なコミュニケーションを強化することを目指すものである。今後、本改正の趣旨を踏まえ、企業において、実質的かつ積極的な開示が進むことを期待したい。金融庁としても、「重要な契約」の開示に関する好事例集の公表等により本改正を踏まえた開示の具体例を示すなど、より実質的な開示の充実に向けた取組みを続けてまいりたい。
脚注
1 「金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」−中長期的な企業価値向上につながる資本市場の構築に向けて−」(令和4年6月13日)
(https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220613.html)
2 本改正では、開示項目名を「経営上の重要な契約等」から「重要な契約等」に改めている。これは、開示されるべき契約が典型的な経営上の契約に限られないことを明確化する趣旨であり、開示事項それ自体の変更を意図したものではない。
3 なお、当該契約の相手方が個人である場合における住所の記載に当たっては、市町村までを記載しても差し支えない(Ⅲ「株主保有株式の処分・買増し等に関する合意」についても同じ)。
4 例えば、提出会社側に諾否の事由が認められていない場合や、合意内容に反した場合に損害賠償等の法的責任を負うことが予定されている場合には、口頭の合意であっても、法的拘束力を有するものと考えられる。
5 開示ガイドライン5−17−6参照
6 「期限の利益の喪失」には、当然に期限の利益が喪失する場合(当然喪失)だけでなく、相手方の請求により期限の利益が喪失する場合(請求喪失)も含む。
7 ここでいう「金銭消費貸借契約」には、特定融資枠契約に関する法律第2条第1項に規定する特定融資枠契約(いわゆるコミットメント・ライン契約)は含まれない(開示ガイドライン5−17−2)。特定融資枠契約自体はあくまで融資枠の設定であり、具体的な金銭の動きを伴うものではないからという考え方に基づくものであり、同契約に基づいて具体的な金銭消費貸借が成立し、その額が基準を上回った時点で臨時報告書の提出義務が生じる。
8 プロジェクト・ファイナンスやアセット・ファイナンスのように、特定の資産の全部又は一部及び当該資産から生じる収益のみを返済原資とし、当該資産以外の資産及び当該収益以外の収益に遡及しない旨の合意がある金銭消費貸借契約(いわゆるノンリコース・ローン)については、当該金銭消費貸借契約の元本額が基準を上回るものであっても、当該資産又は収益の評価額等に照らして想定される損失の額が当該基準を下回ることが明らかである場合には、臨時報告書の提出は要しないものとする(開示ガイドライン5−17−3)。
9 財務上の特約の内容が複雑である場合などは、投資者の理解を損なわない程度に要約して記載することも可能である(開示ガイドライン5−17−4)。
10 金融庁のホームページに掲載されている各金融機関の免許の区分(https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)が参考になる。
11 特定の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができなかった場合に、例えば相手方との間で期限の利益を喪失させるか否かについての協議を行うなど、直ちに期限の利益を喪失しないような措置が契約又は社債の条件において予定されている場合には、基準を維持できなくなった時点ではなく、当該措置が採られなくなった時点で、「事由の発生」として臨時報告書の提出義務が生じる。ただし、このような場合であっても、当該金銭消費貸借契約又は社債について財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができなかった場合には、その後に提出される有価証券報告書において、その旨及び期限の利益を喪失させない措置が採られたことを記載することが考えられる(開示ガイドライン5−17−5)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























