解説記事2024年03月04日 特別解説 会計監査人の交代と監査報酬額の推移(2024年3月4日号・№1017)
特別解説
会計監査人の交代と監査報酬額の推移
はじめに
前回まで2回にわたって会計監査人の交代に関する調査分析と交代理由や経緯の紹介を行ったが、会計監査人交代の理由の中では、前任の会計監査人が監査報酬額の大幅な増額提案を行ったことを契機にしたものが最も多かった。
前任の会計監査人による監査報酬額の大幅な増額提案のみが会計監査人交代の理由ではないことは言うまでもないが、会計監査人の交代により、監査報酬額は実際にどのように変化したのであろうか。また、後任の会計監査人(交代後の監査法人)が4大監査法人、準大手監査法人、及び中小規模監査事務所であること等によって、どのような違いがあるのであろうか。本稿では会計監査人交代の前後での監査報酬額の推移を調査分析するとともに、監査報酬額の増額要請や継続監査期間の長期化と並んで会計監査人を交代する理由として挙げられる、会計上の不祥事(不正、粉飾決算等)や過年度財務諸表の訂正、さらには訂正後の財務諸表の監査に伴う追加報酬額等についてもあわせて調査することとしたい。
なお、本稿で「4大監査法人」とは、EY新日本、あずさ、トーマツ及びPwCあらた(※)の4監査法人のことをいい、「準大手監査法人」とは、太陽、仰星、京都(※)、東陽、及び三優の5監査法人のことをいう。そして、「中小規模監査事務所」とは、4大監査法人及び準大手監査法人以外の監査法人を指し、個人の公認会計士事務所も含まれる。
(※)PwCあらた有限責任監査法人とPwC京都監査法人は2023年12月1日付で合併し、PwC Japan有限責任監査法人となった。ただ、本稿の調査時点は合併前のため、従来どおり、PwCあらた(4大監査法人)と京都(準大手監査法人)を別々の監査法人として集計、分析している。
今回の調査対象とした企業
今回の調査対象とした企業は、2019年6月21日以降、2023年6月期までに会計監査人の交代を行い、臨時報告書を提出してその旨を開示した565社である。
本調査の場合、企業が会計監査人に支払った監査報酬額について、前任の会計監査人と後任の会計監査人の両方(2期分)調査する必要があるため、前回までの会計監査人の交代事由等の調査分析と比較すると、調査対象企業数が少なくなっている。
今回の調査分析では、各社の有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「監査の状況」「監査報酬の内容等」に記載されているデータを基にしており、本稿で各社の「監査報酬額」としているのは、特に断りがなければ、「監査公認会計士等に対する報酬額」のうち、「監査証明業務に基づく報酬額(提出会社と連結子会社との合計)」である。
会計監査人の交代前後での監査報酬額の動向の分析
(1)全体的な動向
調査対象とした全565社について、会計監査人が交代した年度の前後での監査報酬額を比較すると、表1のとおりであった。
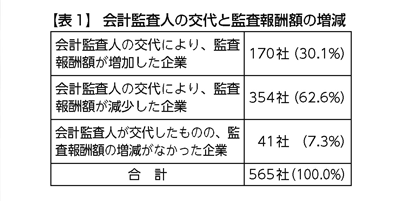
565社のうち、6割を超える354社において監査報酬額が減少していた。これは監査報酬額が増加した企業の2倍を超える水準であった。
「監査報酬額の増額要請」が会計監査人交代の最大の理由に挙げられていることを裏付ける結果となったといえよう。
次に、監査報酬額の増減比率別に企業の分布を一覧にすると、表2及び表3のとおりであった。
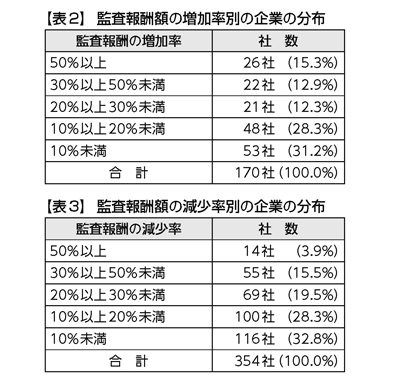
監査報酬額の増加・減少の比率を見ると、増加、減少共に「10%未満」が最大のボリュームゾーンになってはいるものの、特に減少率の側では、減少率が30%を超えるような事例も約2割を占めていた。増加、減少の比率が50%を超えるような事例は、前期、又は当期の監査報酬額に会計上の不祥事(粉飾決算等)が発生したこと等による過年度財務諸表の訂正、そしてそれに伴う監査工数の大幅な増加(監査の一部やり直しや追加監査手続の実施等)が含められていたような場合が多かった。
(2)前任の会計監査人/後任の会計監査人の類型別の分析(増減率)
次に、前任の会計監査人(企業との監査契約を解除した監査法人)と後任の会計監査人(新たに企業と監査契約を締結した監査法人)の類型別の分布を示すと、表4のとおりであった。
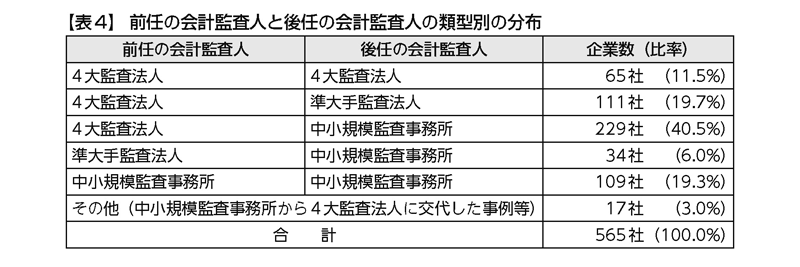
4大監査法人から準大手監査法人や中小規模監査事務所へ監査契約が移っていくという大きな流れがあり、4大監査法人が契約を解除した上場企業の監査を準大手監査法人や中小規模監査事務所が引き受けてゆく事例が過半(約60%)を占めていたが、中小規模監査事務所に監査を依頼していた上場企業が別の中小規模監査事務所に監査契約先を切り替えた事例も全体のおよそ20%弱あった。一方で、中小規模監査事務所、あるいは準大手監査法人から4大監査法人に監査契約先を切り替えるような、いわゆる「大きな流れとは逆向き」の事例は非常に少なかった。
さらに、表4のそれぞれの類型ごとに、会計監査人の交代の前後での監査報酬額の増減の状況を示すと、次のとおりであった。
① 前任の会計監査人、及び後任の会計監査人がいずれも4大監査法人の場合
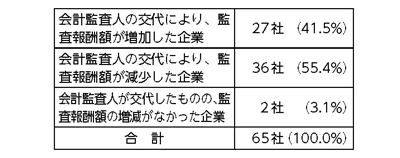
この類型の最大の特徴は、我が国を代表する超大企業やエクセレント・カンパニーが目立つことであり、例えばキヤノン、味の素、大和ハウス工業や大塚ホールディングス、積水化学工業等が当てはまる。監査報酬の支払額が1億円を超える企業も多く、キヤノンや東京センチュリーは、会計監査人が交代したことによって、監査報酬額が約80百万円減少した。
一方で、監査報酬額が大幅に増加したような事例も相当数見られた。
② 前任の会計監査人が4大監査法人、後任の会計監査人が準大手監査法人の場合
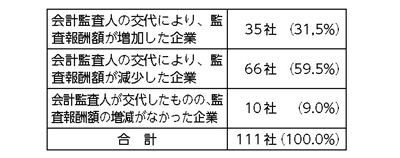
準大手監査法人の中では、最大手の太陽有限責任監査法人(太陽)による積極的な監査契約の獲得が目立った。本カテゴリーの111社のうちの過半を超える60社について、太陽が後任の会計監査人となっていた。
監査報酬額が減少している事例が増加している事例を大きく上回ってはいるが、監査報酬額の増減がなかった事例も含めれば、4割強の事例の監査報酬額が減少していなかったともいえる。
4大監査法人による中堅・新興上場企業の監査契約解除の動きが続いている中で、準大手監査法人が占める地位が相対的に上昇し、監査報酬提示額を前任監査人よりも引き下げなくても、契約の獲得に支障がないような状況になってきているのかもしれない。
③ 前任の会計監査人が4大監査法人、後任の会計監査人が中小規模監査事務所の場合
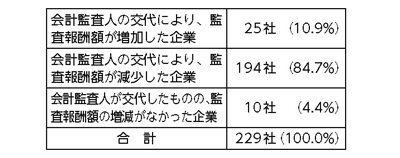
4大監査法人から中小規模監査事務所に監査契約が移った場合には、監査報酬額が減少した事例の割合が特に大きく、85%に迫る数値であった。また、監査報酬額減少の絶対額の面から見ても、このカテゴリーが最大であった。そして、このカテゴリーで目立つのは、会計上の不祥事やそれに伴う過年度決算(過年度財務諸表)の訂正監査に多額の監査報酬が支払われていたことである。このような企業は、会計上の不祥事や決算、財務諸表の訂正等が起こったことを契機に会計監査人が交代しており、当初は4大監査法人が監査を行っていたが、中小規模監査事務所に移り、さらには中小規模監査事務所の中で転々としているような事例や、危うく「監査難民」となりかかったところを一時会計監査人への就任等によってつなぎつつ、後任の会計監査人探しに奔走していると思われるような事例も中には見受けられた。
④ 前任の会計監査人が準大手監査法人、後任の会計監査人が中小規模監査事務所の場合
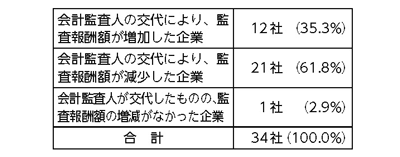
前任の会計監査人が準大手監査法人で、後任の会計監査人が中小規模監査事務所の場合には、前記③の大手監査法人から中小規模監査事務所への移動の場合に比べると、監査報酬額の減額一辺倒であった傾向に歯止めがかかり、会計監査人が交代することにより、監査報酬額が増加する事例も3分の1強(34件のうちの12件)見られた。②の4大監査法人から準大手監査法人に会計監査人が交代した事例と似たような傾向であると言えるであろう。
⑤ 前任の会計監査人、後任の会計監査人がいずれも中小規模監査事務所の場合
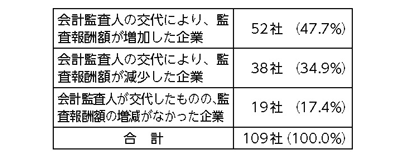
前任、後任の会計監査人がいずれも中小規模監査事務所の場合には、監査報酬額が増加した事例、減少した事例、及び増減がなかった事例とまんべんなく分布していたが、監査報酬額が増加した企業が減少した企業よりも上回る結果となった。
監査報酬額の増減とは直接関係しないが、このカテゴリーでは、金融庁から行政処分を受けた中小規模監査事務所の被監査会社が他の中小規模監査事務所に会計監査人を変更した事例や、かつて監査を担当していた社員が監査法人を脱退したことにより、企業側が会計監査人の変更を迫られたような事例が複数見られた。
⑥ それ以外の場合
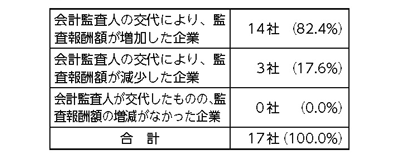
このカテゴリーには、中小規模監査事務所から準大手監査法人や4大監査法人、準大手監査法人から他の準大手監査法人や4大監査法人に会計監査人が交代したような事例が分類される。「監査報酬額が下がりやすい流れ」とは逆方向であるため、当然の結果として監査報酬額が増加した事例がほとんどを占めた。
過年度決算の訂正等に対して支払われた監査報酬
これまでにも多くの事例を紹介してきたが、粉飾決算等の会計上の不祥事に起因する過年度決算の訂正やそれに伴う監査は、極めて多額の監査報酬の支払いを伴い、また、会計監査人が交代する大きな契機ともなりうる。
ここでは、「監査公認会計士等に対する報酬」に過年度決算や財務諸表の訂正に伴って会計監査人に追加報酬を支払った旨を開示した企業とその支払額とを表5で紹介することとしたい(これまでにすでに言及した企業は除く。)。
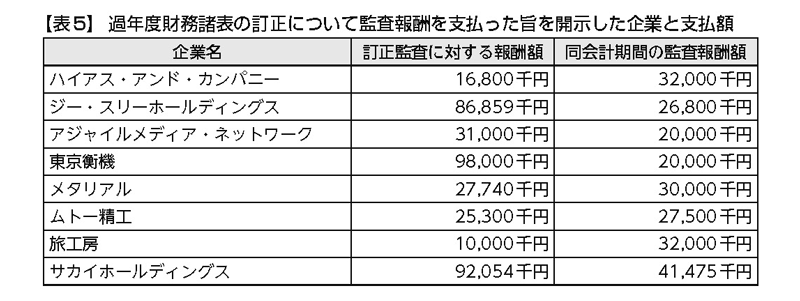
なお、表5の各社は、本誌No.963(2023年1月23日号)にてすでに調査対象としている企業348社を除いた217社を母集団として抽出したものである。
「監査公認会計士等に対する報酬」に、過年度決算の訂正に係る監査報酬を支払った旨のみを開示していた(支払金額は開示していなかった)事例や、当該開示そのものを全くしていない事例、さらには、過年度財務諸表の訂正監査を実施したが、会計監査人の交代は行わなかった事例(=今回の調査の対象外)も存在すると思われるため、表5がすべての事例を網羅出来ているわけではないことを付言しておきたい。それを差し引いても、財務諸表の訂正やそれに伴う監査の件数の多さには驚かされる。
会計上の不祥事等により過年度の財務諸表を訂正する場合には、過去数年分に遡った訂正が必要となることも多く、また、特定の勘定科目のみならず、財務諸表全体に影響するような大掛かりな粉飾決算の場合には、検証すべき数値・書類や追加することが必要な監査手続は膨大となり、当然監査報酬額も大きく跳ね上がることになる。表5を見ると一目瞭然であるが、ほとんどの企業で年間の監査報酬額を大きく上回る追加的な支出が生じていた。
さらに、このような企業については、会計監査人に支払う追加報酬に加えて、第三者委員会の委員に支払う報酬や調査費用等、さらには東証に支払う違約金等も必要となる場合が多い。そして、当該不祥事や財務諸表の訂正によって失われる信用やブランド力、不毛かつ後ろ向きな作業の連続による役職員のモチベーションの低下等は、現金による支出額とは比べ物にならないほど大きいことは言うまでもないであろう。会計上の不祥事や財務諸表の訂正(修正再表示)の代償は、企業にとって極めて大きいのである。また、会計監査人である監査法人にとっても大きなダメージであり、最悪の場合には、被監査企業との間の信頼関係が崩壊して、会計監査人を辞任(あるいは被監査会社の側から解任される)ということにもなりかねないであろう。企業、従業員、及び会計監査人の誰をも不幸にするような会計上の不祥事が、今後少しでも減ってゆくことを期待したい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























