解説記事2020年02月17日 税理士のための相続法講座 第55回 相続法改正(10)―配偶者居住権(2020年2月17日号・№823)
税理士のための相続法講座
第55回 相続法改正(10)―配偶者居住権
弁護士 間瀬まゆ子
1 はじめに
今回のテーマは本年4月1日に施行される配偶者居住権です(※)。相続法改正で新設された制度であり、その評価や小規模宅地の特例の適用の有無等を中心に税理士の関心も高いところかと思います。本稿でも、配偶者居住権の基本的な内容を確認していきます。
※同日以後に開始した相続に適用されます。但し、相続開始が同日後でも、同日より前にされた遺贈には適用されません。
2 配偶者短期居住権
相続法改正により、配偶者の居住権を確保するための方策として、以下の2つの制度が新設されました。
① 配偶者短期居住権
② 配偶者居住権
このうちの配偶者短期居住権は、被相続人の生前に被相続人所有の建物に居住していた配偶者の居住権を、相続開始後の短期間に限り保護しようとする制度です。
実は、配偶者短期居住権のような制度がなくとも、従前も判例により、被相続人所有の建物に住んでいた相続人(ここは配偶者に限られません。)の保護は図られていました。すなわち、被相続人とその相続人との間に使用貸借契約が成立していたと裁判所が推認し、遺産分割が終了するまでの間は当該相続人が無償で居住を続けることを認めていたのです(最三小判平成8年12月17日民集50巻10号2778頁)。
しかしながら、この判例理論は当事者の合理的意思解釈に基づくため、被相続人が反対の意思を表示していた場合(例えば、被相続人が当該建物を第三者に遺贈していたような場合)には適用されないという問題があります。
そこで、配偶者の保護の観点から、配偶者に限って、被相続人の意思にかかわらず、相続開始後の短期間従前の住居に住める権利を認めることとしたのです(新民法1037条)。
ただ、配偶者短期居住権の評価額は零であり、課税にも影響がありません。したがって、税理士の実務にも関係しないところかと思いますので、本稿では配偶者短期居住権についての詳細な説明を割愛します。
3 配偶者居住権の概要
被相続人の建物について配偶者居住権が設定された場合、建物の完全な所有権が、建物の使用収益権(配偶者居住権)と配偶者居住権の負担付の所有権に分かれることになります。同様に建物の敷地についても、配偶者の敷地利用権とその負担の付いた所有権に分離することになります。
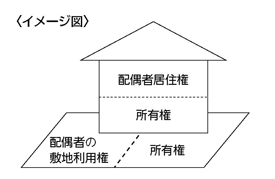
このように配偶者が取得する権利を限定的な権利とすることで、自宅の完全な所有権を取得する場合に比べ、配偶者が取得する権利の評価額が下がり、その結果、自宅以外の遺産からも配偶者が分配を受けられる可能性が高まります。これが、新法で配偶者居住権が新設された趣旨です。
【後妻の生活を確保するための配偶者居住権】
被相続人Aが亡くなった。相続人は先妻の子Bと後妻のC。相続財産は自宅土地建物(5,000万円)と預金3,000万円。Cとしては、何としても自宅を確保したいが、一方で老後の生活資金にも不安がある。
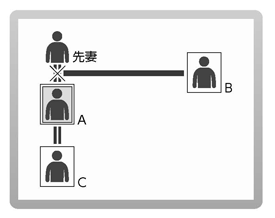
この事例で、Cが自宅を取得しようとすると、以下のとおり、1,000万円の代償金をBに支払う必要が生じます。
Cの相続分=(5,000万円+3,000万円)×法定相続分1/2=4,000万円
4,000万円-5,000万円=△1,000万円
しかし、Cに1,000万円の自己資金があるか問題ですし、仮にあったとしても、預金が減る分その後の生活が苦しくなってしまうでしょう。
この場合に、仮にCが配偶者居住権を取得し、その配偶者居住権(と敷地利用権)の評価額が2,500万円であるとするとどうでしょう。以下のとおり、配偶者居住権を取得したとしても、相続分が1,500万円残ります。したがって、預金から1,500万円の配分を受けられることになります。
4,000万円-2,500万円=1,500万円
そうなれば、自宅は確保できたもののお金がなく老後の生活に困ってしまうという事態を避け得ることになりそうです(この場合、Bは配偶者居住権の負担付きの自宅2,500万円と預金1,500万円を取得することになります。)。
ただ、実際には、上記のような先妻の子と後妻が相続人という「教科書的」な事例において、遺産分割により配偶者居住権を設定できる場面はそう多くない気がしています(被相続人が遺言により配偶者居住権を遺贈しておく事例はあるかもしれませんが。)。というのも、先妻の子(B)の方から見ると、配偶者(C)がどの程度長生きするかは分からず、自分が完全な所有権を取得できるとしても、それは30年、40年後になるかもしれないのです。加えて、その時点では不動産の価値が暴落しているかもしれません。そのため、Bの立場であれば、遺産分割の時点で不動産を売却し、その売却代金を受け取ることを希望する人も多く、協議がまとまらないケースも多く出てくるのではないかと筆者は推測しています(上記の例であれば、不動産を売却すれば、その代金5,000万円の半額2,500万円と預金1,500万円の合計4,000万円をBが取得できることになります。)。
このように配偶者と他の相続人が対立する場面では必ずしも使い勝手が良くないように思われる配偶者居住権ですが、実は後継ぎ遺贈のような使い方も可能と言われており、そちらの方が利用頻度は高くなるかもしれません。
【後継ぎ遺贈目的の配偶者居住権】
DとEの夫婦には子供がいない。自宅の不動産はDが親から継いだものである。Dは自分の死後もEが自宅に住み続けるようにしてあげたいと思う一方、Eの死後は甥のFが権利を承継してほしいと思っている。
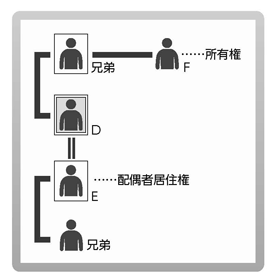
上記のケースで、仮にDが先に亡くなり、Eが自宅を相続すると、Eの相続の際には、Dの血族たる兄弟や甥姪ではなく、Eの兄弟の方に相続の権利が行ってしまうことになります。そこで、Eの後は甥に相続させると予め決めておきたいというニーズが生じてくるのです。いわゆる後継ぎ遺贈の場面です。
このような後継ぎ遺贈は、従前の民法では実現困難と言われていました。ですが、上記のケースでEに配偶者居住権、Fに所有権を遺贈しておけば、同じ効果を生じさせることができそうです。
この点、信託法上の受益者連続型信託を用いるという選択肢もあり得ます。ですが、信託は一般の方には理解のしづらい仕組みです。受益者が交代する際に受益権に対する課税が生じるという問題もあります。これに対し、配偶者居住権の方がシンプルですし、Eの死亡時に相続税が課税されることもありません。したがって、配偶者居住権を用いた後継ぎ遺贈の方が今後広がるかもしれません。
ただ、配偶者居住権の場合にも、所有者となるFが固定資産税を納税する必要がありますし(通常の必要費(新民法1034条1項)としてEに求償できますが、それも手間です。)、所有者としての責任も生じ得ますので、専門家として相談を受けた際にはそういったマイナスの面の説明も必要でしょう。詳細については別稿で述べます。
なお、先ほどの先妻の子と後妻のケースでも、夫が生前に遺言を残しておく方法は考えられます。この場合、先妻の子の遺留分の請求を封じるという効果も生じ得ます。ただ、両者の関係が悪い場合、同じ建物(及びその敷地)に対して利害を有する関係が何十年も続くことになる配偶者居住権は、双方にとってストレスにもトラブルの種にもなるでしょうから、あまりお勧めはできません。
その他、二次相続の際の相続税を軽減するために配偶者居住権を利用するケースもあり得るでしょう。
【節税のための配偶者居住権】
Gが亡くなった。相続人は配偶者H、長女Iと次女J。相続財産は自宅不動産と、Jが居住しているマンション。Hは借家住まいのIに将来的には自宅を承継させたいと思っている。
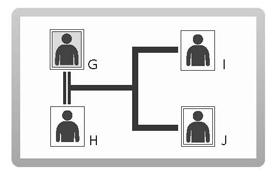
この事例で、Hが自宅を取得し、Hの相続時にIに相続させるということももちろん可能です。しかし、自宅の評価額が高かったり、その他の資産もあると、Hの相続時に相続税が課税される可能性があります。これに対し、Hが配偶者居住権、Iが配偶者居住権付きの所有権を取得するように遺産分割すれば、配偶者の死亡により配偶者居住権が消滅した場合には課税がないとされているため、少なくとも配偶者居住権については二次相続時の課税が無くなります。そのため、配偶者居住権を用いた節税が可能と思われるのです(一時相続時の相続税は増える可能性がありますが)。
また、配偶者居住権を用いる方法には他のメリットもあります。仮にHからIに自宅を相続させる方法をとると、HがIに相続させる遺言を残していたとしても、IがJから遺留分の請求をされてしまう可能性があり、結局Hが自宅を手放さざるを得ない状況に陥る可能性もあります(※)。また、Gの相続時にIではなくHが自宅不動産を取得するという方法も考えられますが、そのような方法をとると、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減という税務上の特典を享受できなくなる可能性があります。また、たとえ子供との関係が良好な場合であっても、「子供の名義の家に住まわせてもらうのは嫌だ。自分の名義にしておきたい。」と思う配偶者も実は少なくありません。最初から子(I)に相続させてしまうと、そのような配偶者(H)の思いに反してしまうことにもなりかねません。
※配偶者の死亡により建物の所有者が完全な所有権を取得した場合、相続による取得ではないため、遺留分の問題は生じないと考えます。ただ、仮に配偶者の生前に配偶者が配偶者居住権を放棄しその対価も得ていない場合、その時点の配偶者居住権の価額をもって特別受益があったと認定される可能性はあります。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















