解説記事2024年04月08日 ニュース特集 詳報 R6外形標準課税改正(2024年4月8日号・№1022)
ニュース特集
「公布日基準」への影響懸念も、公布日は令和6年3月30日に
詳報 R6外形標準課税改正
周知のとおり、令和6年度税制改正では外形標準課税が見直され、「減資への対応」「100%子法人等への対応」が図られている。改正事項の中には、駆け込みによる外形標準課税逃れ防止策として「公布日」を基準とするものがあるが、今年は3月31日が日曜日であったため、公布日が4月1日とされた場合の影響が懸念されていたところ(本誌1011号参照)、結果的には、3月28日に改正法案が成立し、3月30日の官報(号外)により公布された。
今回の外形標準課税の改正は、公布日による影響にとどまらず、附則による読み替え、経過措置の適用の有無など、詳細な検討が必要になる部分が多い。
本特集では、改正地方税法に基づき、外形標準課税の改正の内容について詳報する。
駆け込みでの減資を想定し、経過措置で対応
主に資本金を1億円以下に減資する手法により外形標準課税の適用対象法人数が大幅に減少していることは長年問題視されてきたが、令和6年度税制改正では、「減資への対応」として、適用対象法人の範囲について、現行基準(資本金1億円超)は維持しつつ、補充的な基準が追加されることになった。具体的には、当分の間、その適用事業年度の前事業年度に外形標準課税の対象法人であって、適用事業年度に資本金が1億円以下で、かつ、資本金と資本剰余金の合計額が10億円を超える法人は、外形標準課税の対象とされた(地法附則8の3の3)(図1参照)。
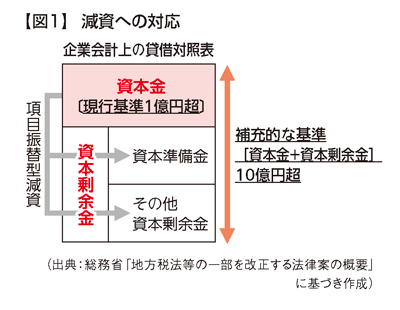
この改正は、令和7年4月1日に施行され、同日以後に開始する事業年度から適用される。
また、駆け込みでの減資による外形課税逃れを防止するため、適用初年度については経過措置が設けられている(R6改正地法附則7②)(図2参照)。具体的には、上記「前事業年度に外形標準課税法人であったかどうか」との要件について、「前事業年度」という部分を「公布の日を含む事業年度の前事業年度から適用初年度の前事業年度までのいずれかの事業年度」とし、そのいずれかの事業年度において外形標準課税法人であったかどうかにより外形標準課税の適用の有無を判断することになる(図2の①のケース)。ただし、公布日の前日に資本金の額が1億円以下で、その後、適用初年度の前まで外形標準課税の対象外であった場合は、この経過措置の適用対象から除かれる(図2の②のケース)。
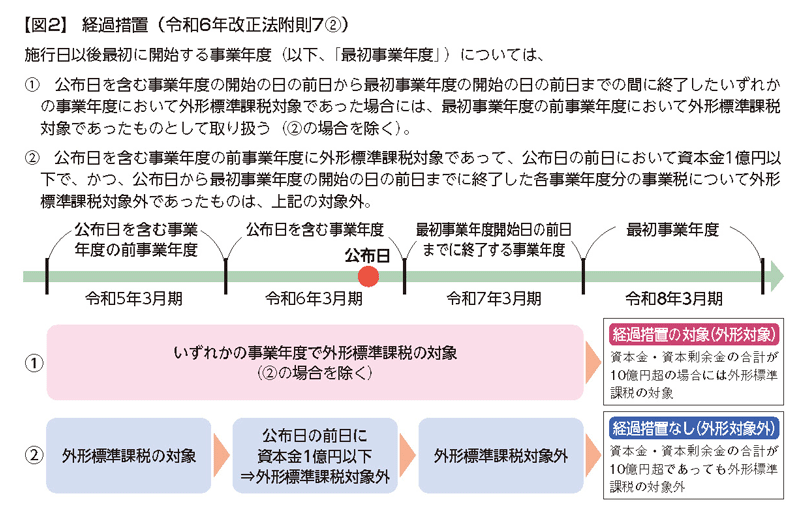
つまり、令和5年3月期までは外形標準課税対象であった法人が、公布日後に減資をして1億円以下になったとしても、適用初年度以降、「資本金+資本剰余金」が10億円超であれば外形標準課税の対象になる。
なお、改正税法の公布日は例年「3月31日」であるところ、今年は3月31日が日曜日であったため、万が一公布日が4月1日になった場合には、外形逃れ防止策に影響が出ることが懸念されていたが、結果的には、3月28日に改正法案が成立し、3月30日土曜日の官報(号外)により公布された。したがって、3月決算法人の場合の適用関係は、図2のとおりとなる。
「子法人等への対応」では親法人の外形対象判定に要注意
「100%子法人等への対応」としては、資本金と資本剰余金の合計額が50億円を超える外形標準課税法人(特定法人)の100%子法人等のうち、資本金が1億円以下で、資本金と資本剰余金の合計額が2億円超のものが、新たに外形標準課税の対象とされることとなった(地法72の2①一ロ)(図3参照)。
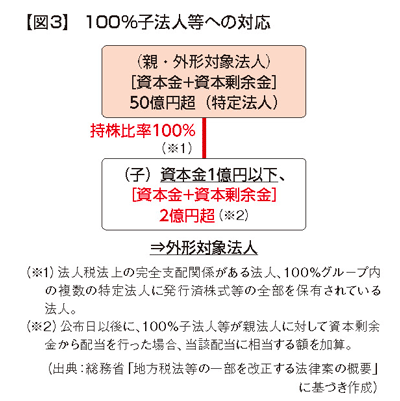
ここで注意しなければならないのは、100%子法人等が外形標準課税の適用対象かどうかを判断するためには、親法人の「資本金+資本剰余金」が50億円超かどうかだけでなく、親法人が外形対象法人であるかどうかも確認しなければならない点だ。つまり、適用対象となるかどうかの判定においては、上記「減資への対応」も考慮しなくてはならず、親法人の資本金が1億円以下であっても、その親法人が前事業年度に外形対象法人で、かつ、「資本金+資本剰余金」が10億円超の場合は、その子法人等は外形標準課税の対象になるということだ。
この改正は、令和8年4月1日に施行され、同日以後に開始する事業年度から適用される。
「100%子法人等への対応」についても、駆け込みによる外形標準課税逃れへの対策が講じられている。具体的には、公布日以後に100%子法人等が特定法人に対して“資本剰余金を原資とする配当(資本配当)”を行う場合には、その資本配当により「減少した資本剰余金等」を払込資本の額に加算して2億円超の判定を行うこととされた(地法72の2①一ロ)。
なお、今回の改正により新たに外形標準課税の対象となる法人に対しては、税負担の激変を緩和する措置が設けられている。具体的には、外形標準課税の対象となったことにより従来の課税方式で計算した税額を超えることとなる額のうち、図4に定める控除金額を、図4に定めるそれぞれの対象事業年度に係る法人事業税額から控除するというもの。この激変緩和措置により、外形標準課税が段階的に行われることになる(地法附8②)。
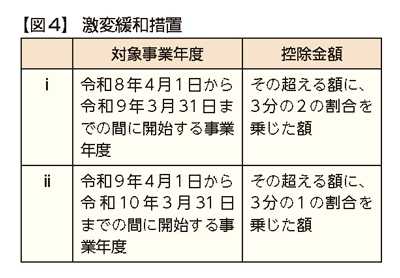
また、上記改正の適用除外措置も設けられている。具体的には、産業競争力強化法の改正を前提に、特別事業再編計画(仮称)(令和9年3月31日までに認定を受ける必要あり)に基づくM&Aにより100%子会社となった法人等については、上記改正にかかわらず、買収から5年経過する事業年度まで外形標準課税の適用対象外とされる(図5参照)。ただし、現行基準(資本金1億円超)及び上記「減資への対応」により外形標準課税の対象となる場合には、この特例措置の適用対象外となるので注意が必要だ。
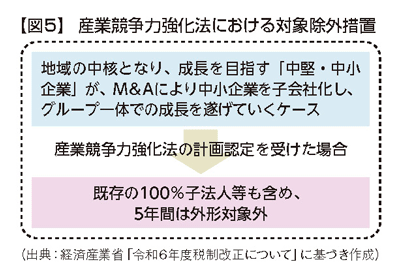
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























