解説記事2020年02月24日 ニュース特集 CbCR2020レビュー公開討議草案の全容(2020年2月24日号・№824)
ニュース特集
MFの統一、Table1の項目追加や事業体毎の記載、国単位での連結ベースの集計など論点に
CbCR2020レビュー公開討議草案の全容
2015年に公表された行動13(移転価格文書化)BEPS最終報告書には、国別報告書(Country by Country Report =CbCR)について「2020年」に見直しの検討を行う旨が明記されていたところだが、OECDは2月6日(木)、CbCRの2020年レビューに関する公開討議草案(ディスカッションドラフト=DD)を公表した。2020年レビューの後には国内で税制改正が行われ、その際には基本的にOECDで合意された改定版テンプレートが国内法に移植されることになるだけに、本レビューに対する日本企業の関心は高い。
今回のDDは全68頁に及び、3章に分かれ18の論点、合計43の質問が並ぶ膨大なものとなっているが、本誌の分析によると、必ずしもそのすべてが日本企業にとって重要なものではない。実務的に企業への影響が大きいのは、まず、BEPS最終報告書で定められたマスターファイル(MF)の様式を超える要求をする各国の状況を問う論点3だろう。各国ごとにMFをカスタマイズすることなく、本社で作成した一本のMFを全世界で利用できるようになれば、企業の事務負担は大幅に軽減されるのは間違いない。
このほか、Table1の内容を「国ごと」ではなく「事業体ごと」に記載することについて意見を求める論点12、Table1の数値を合計(aggregate)ではなく連結(consolidated)ベースとすることについて意見を求める論点13、Table1の記載項目を増やすことについて意見を求める論点14も、結論次第では企業の事務負担を大幅に増やすことにつながるだけに、その結論が注目される。
本特集では、各論点の重要性にも触れながら、全18論点について解説する。
第1章 行動13の実施一般
BEPS最終報告書のテンプレートから大きく逸脱したMFを要求される事例も
第1章「行動13の実施一般」は3つの論点からなる。このうち論点1はBEPSミニマム・スタンダードであるCbCRの包摂的枠組(Inclusive Framework=IF)加盟国における実施状況一般について問うもの、論点2はCbCRの適切かつ効果的な利用について問うものである。「条約方式に反している」「守秘義務が守られていない」「不適切な追加質問がある」「課税のツールとして直接利用されている」といった場合には、納税者として声を上げていくことになろう。企業からは、ベトナム、ルーマニアについて子会社方式のリスクがあるとの指摘もある。
第1章で最も重要なのが論点3だ。本論点はCbCR以外の行動13項目について問うもの。特にマスターファイル(MF)は、ミニマム・スタンダードではないものの、企業においては、各国の様式統一に対する期待が高い(特にインドについては、BEPS最終報告書のテンプレートから大きく逸脱したMFを要求するとの指摘がある)。DDでは、「OECD移転価格ガイドライン第5章付録Ⅰに掲げられた文書とは異なる、あるいはその文書を超えたMFを要求している法域についてコメント求める」とある。DDの準備過程では、MFを質問項目から外してはどうかとの意見もあった模様だが、関係国の主張により残されたという経緯がある。各国ごとにMFをカスタマイズすることなく、本社で作成した一本のMFを全世界で利用できるようになれば、企業の事務負担は軽減されることになる。加えて、MFの提出時期を統一すべきとの声もある。国によっては日本よりも早くMFを提出しなければならないケースもあるようだ。
第2章 CbCRの適用範囲
為替変動でCbCRの作成が必要な連結総収入金額が「1000億→900億」も
第2章「CbCRの適用範囲」では、新たにCbCRの作成義務を負う日本の企業グループが増えるかどうかが注目ポイントとなる。
まず論点4は、一の事業体が国外に1つ以上のPEを有する場合、CbCR制度上、多国籍企業「グループ」といえるかどうかを問うもの。あくまでレアケースであり、日本企業はほぼ無視してよい論点だろう。論点5は富裕層等の個人(又は同一の行動をとる複数の個人)を頂点とするグループに係るCbCRの作成義務の判定であり、これも日本企業とは関係のない論点と言ってよい。
論点6以降は、CbCRの作成義務を新たに負うこととなる日本の企業グループの増加につながる可能性がある。
論点6は、連結総収入金額750百万€という閾値を引き下げてはどうかというもの。既にCbCRを作成している大規模な多国籍企業には影響がないが、連結総収入金額がギリギリ1,000億円未満のレンジにある企業グループは、閾値の引下げによって新たにCbCRの作成義務を負う可能性があるため注意する必要がある。なお、デジタル課税における「第1の柱」の利益A及び「第2の柱」の所得合算ルールは、CbCRと同じ750百万€の閾値を超えた企業グループへの適用が検討されているため、CbCRにおける閾値引下げは、デジタル課税議論にも飛び火する可能性がある。
論点7は、ユーロ以外の通貨を採用する国において、BEPS最終報告書で定められた為替レート(2015年1月の為替レートを基礎に750百万€から自国通貨へと引き直すとされていた)からの変動を踏まえ、750百万€からの自国通貨換算額を引き直すことを問うもの。具体的な引き直しの手法としては、随時見直す案、5年に一度見直す案、為替レートの変動率が一定以上の場合(例えば5%や10%)に5年に一度見直す案など複数案が挙がっている。直近の為替レートは1€=約120円であり、750百万€=約900億円となっている。仮に直近の為替レートで引き直しを行った場合、閾値は現在の1,000億円より100億円下がることになる。この結果、日本でもCbCRの作成を求められる企業グループが増加する可能性がある。
直前会計年度が12か月に満たない場合の“12か月換算”、強制化も
論点8は、CbCRの作成義務の有無を判定する連結総収入金額を判定する会計年度を問うもの。現状では、直前会計年度の連結総収入金額が750百万€を超過する場合、当期においてCbCRの作成義務が生じることとなるが、年度によって作成義務が生じたり生じなかったりするのは安定性がないとの理由から、直前会計年度1期で見るのではなく、「直前2期の実績」で判定する案、「直前4会計年度のうち2以上の期の実績」で判定する案、「直前4会計年度の平均」で判定する案が示されている。
論点9は、非経常の利益(特別利益)を連結総収入金額に含めるべきというもの。現状、各国によって異なる特別利益の取り扱いを統一しようという趣旨である。論点10は、投資活動による所得(利子・配当所得)を連結総収入金額に含めるべきというもので、これも、各国によって異なる取り扱いを統一する趣旨である。なお、日本のCbCRにおいては、総収入金額は「売上高のほか、受取利息及び有価証券利息、受取配当金、有価証券売却益、為替差益、引当金戻入益、持分法による投資利益、固定資産売却益、負ののれん発生益などの科目により、連結財務諸表に計上した全ての収益の額はこれに含まれる」とされている(措通66の4の4−1)。したがって、非経常の利益(特別利益)や投資所得を連結総収入金額に含めるべきとされたとしても、日本企業への影響はさほどないものとみられる。
論点11は直前会計年度が12か月に満たない場合等の取扱いを提案するもの。事業年度の変更により、直前会計年度の連結総収入金額が750百万€に満たなくなるケース(例えば12月決算法人が6月決算法人に変更となる場合、変更後の7月1日から始まる事業年度の直前会計年が1月1日~6月30日の半年間となるため、連結総収入金額は750百万€を割り込むといったケース)においてCbCRの提出が不要とされるのは政策目的に合致していないとの理由から、直前会計年度が12か月に満たない場合は12か月分に引き直すことが提案されている(同様に、12か月超の場合も12か月分に引き直すことになる)。なお、日本では現在このような調整は必要とされていないが、国税庁は、企業が自主的に12か月に引き直してCbCRを作成した場合にはこれを受け入れることとしている(「移転価格税制に関する文書化制度(FAQ)」問7)。
第3章 CbCRの内容
「事業体ごと」方式の課題も紙幅を割いて記載、OECDの本音は「国ごと」方式?
第3章「CbCRの内容」には重要論点が多く含まれている。
まず論点12では、Table1の内容を「国ごと」ではなく「事業体ごと」に記載することについて意見を求めている。ある法域において多国籍企業グループの構成事業体が多い、又は異なる事業活動に従事している場合、国ごとの数値を記載すると、その数値がTable2における構成事業体の属性の情報とどのように対応しているのかが分かりにくいとの問題がある。事業体ごとの集計であればその問題は緩和されるという。
ただ、「事業体ごと」方式についてDDは、想定される便益以上に、紙幅を割いて企業や税務当局において予想される課題(challenge)を指摘している。まず企業にとっては、事業体ごとのデータの収集はシステム開発含め、追加の手間となる。また、税務当局もデータの解析にあたり困難に直面する。税務当局にとっては入手できるデータが増加するのは良いこととはいえ、ある事業体に係る資産や従業員は、他の事業体の活動に関連するかもしれないし、1つの事業体が複数の事業を行っている場合には、当該事業体の情報がその複数の活動の何に対応しているのかを判定するのはやはり容易ではない。また、ある国におけるグループの活動全体を見てBEPSリスクの有無を判定する場合には、事業体ごとのデータだけでは不十分であり、結局それらを再集計して国ごとのデータに引き直す必要があるかもしれない。関連者からの収入金額が相殺されないという問題も残ったままである。
このような便益と課題に関する記載分量の差からすれば、事業体ごと方式をOECDが推奨しているようには見えないが、BEPS行動13議論の際にも論点になった項目であり、本DDにおける最重要論点の1つであることは間違いない。企業からは、そもそもCbCRはハイレベルなリスク評価が目的だったはずであり、事業体方式への移行は課税のためのデータの直接利用につながりかねず、やりすぎとの声が出ている。
日本以外の国の多国籍企業グループの多くは国単位での「連結方式」に賛成
論点13はTable1の数値を国単位での合計(aggregate)ではなく連結(consolidated)ベースとすることについての意見を求めるもの。
連結方式を採用した場合、同一法域内における関連者向けの収入金額及び資本金の額が相殺消去され、その法域における多国籍企業グループの活動をより正確に描写できるようになる。これにより、現行の合計方式によるデメリット、すなわち利益率(税引前当期利益の額/収入金額合計)や資本利益率(税引前当期利益の額/資本金の額)が収入金額や資本金の額の重複カウントにより低く見えてしまう等の問題に対処できることになる。また、連結方式を採用することにより、多国籍企業グループがある法域で複数の事業を複数の事業体を通じて行う場合と、複数の事業を1の事業体の中の複数の事業部門で行う場合とで、数値の比較可能性がもたらされることになる。
OECDによれば、多くの企業グループが連結方式を推しているとのことだが(合計方式よりも分かりやすい、又は合計方式に比べて著しく困難ではないとの理由による)、日本の企業グループとしては国ごとの連結方式には強い違和感があるところ(さらに言えば、受け入れ困難とする企業もある)。DDでも、連結方式のデメリットとして追加の事務負担が掲げられている。
この問題は、ある意味でデジタル課税の第2の柱、所得合算ルールにおける国ごとブレンディングの議論にも類似したものであり、企業としては警戒が必要であろう。論点12と並び、第3章における最重要論点の1つと言えそうだ。
“税会不一致項目”の明確化のため、Table1に繰延税金の情報を記載する案
論点14は、Table1の記載項目を増やすことについてどう考えるかを問うもの。
BEPS行動13の際も、関連者間の利子、使用料、役務提供の対価の受け払いを含めてはどうかとの議論があったが、最終的には論点から落とされたという経緯がある。今回、これらを対象とすることの是非が再び検討されることになる。
なお、BEPS行動13の際は、これら金額の受取額(received)又は支払額(paid)とされていたが、今回は受け払いに係る所得(income)又は費用(expense)とされた。キャッシュの受け払いではなく、会計上の発生額を意味することを明確化する狙いがある。
加えて今回のDDでは、研究開発費用の支出額を含めることの是非が提案された。研究開発は価値創造の源泉であり重要な情報というのがその理由であるが、「研究開発費の発生場所=当該研究開発から生み出された無形資産の実質的な所有の場所」とは必ずしも言えない中で、情報がミスリーディングなものとなるとの懸念も示されている。
さらに、繰延税金の情報を記載することについての提案もされている。現在のTable1からは税務と会計の不一致項目(とりわけ欠損金の繰越控除などの一時差異)が読み取れず、税引前当期利益の額と税額による実効税率の分析等、リスク評価のハードルとなっていたというのがその理由である。新しいTable1の記載項目として繰延税金の欄を新規に作成する案と、発生税額の定義に繰延税金を含める案の両方がある。こちらも企業にとってはDDにおける最大のポイントの1つであろう。
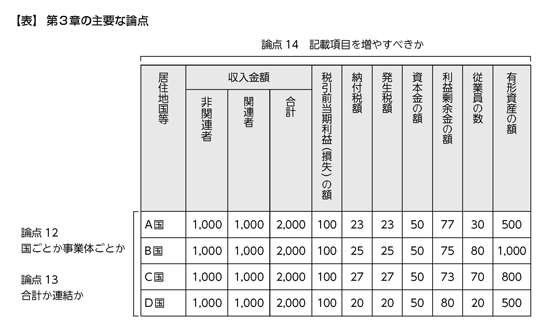
同一法域内の構成事業体に持ち分を保有される事業体は切り分けて記載も
論点15は、どの国においても税務上の居住者ではない構成事業体の扱いに関するもの。現状、これらの事業体は「stateless」として1行でまとめられているが、その内訳としては「A:透明な事業体のうち、同一法域内の構成事業体に持ち分を保有されるもの」「B:透明な事業体のうち、他の法域の構成事業体に保有されるもの」「C:透明な事業体ではないが、どの国でも税務上の居住者の要件を満たさないもの」の3類型があるとし、Aのみ切り分けて別途の記載を求める案、ABCのいずれについてもTable2と紐づけ情報を記載する案、ABCの類型を基礎に、その持分を有する者等が実際に課税されているかどうかを確認したうえで情報を記載する案、そもそも事業体ごとにデータを記載する案の4つが示されている。DDでは、多国籍企業の多くはAタイプの事業体を有している模様としており、仮に該当する場合は対応が必要な項目と言える。
論点16は、XMLスキーマで必要とされる情報(例えば納税者番号)をCbCRのテンプレートに盛り込み、記載を確実に担保することについての提案である。
論点17は、Table2について標準的な産業コードを導入すべきか、その場合、どの産業コードが有用かについて問うものである。
論点18は、記述欄のTable3について(税務当局の経験によると、納税者はあまりこの欄を利用していない模様)、あらかじめ使用する会計基準、データの情報源、重要な組織再編の有無、還付税額が納付税額ではなく収入金額に計上されている場合その旨、利益剰余金の額がマイナスの事業体がある場合はその旨等、納税者がYES/NOをチェックできる欄を最初から設けることについて問うものである。
CbCR2020レビュー後の税制改正は必至、改定版テンプレートを国内法に移植
本DDに対するコメントの締め切りは3月6日(金)とされており、同月17日(火)にはパリで公聴会が開催される。
CbCR2020年レビューの後には、必ず国内での税制改正が行われることになる。基本的にはOECDで合意された改定版テンプレートが国内法に移植されることになるだけに、OECDにおける議論の行方が注目される。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















