解説記事2024年05月20日 ニュース特集 実例に基づくケーススタディ「土地を巡る資産税の実務」(2024年5月20日号・№1027)
ニュース特集
借地権消滅地の一体譲渡、使用貸借地の評価、信託受益権の共同相続……etc.
実例に基づくケーススタディ「土地を巡る資産税の実務」
資産税の実務に最も多く絡んでくると言っても過言ではないのが土地だ。本特集では、税理士等の専門家でも取扱いに迷う実際に発生した事例を取り上げる。
具体的には、①更地とこれに隣接する借地権が設定されていた土地を一体として譲渡した場合、譲渡収入金額は各土地の実勢価格、あるいは面積比率のいずれによって按分するべきか、②妻が夫の所有する土地を使用貸借により借り受けてアパートを建て、賃貸事業を営んでいたところ、まず妻に相続(1次相続)が開始し、夫が本件建物を相続したものの、その後、夫についても相続(2次相続)が開始したといったケースでは、相続税評価にあたり、本件土地を「自用地」と見るべきか、あるいは「貸家建付地」と見るべきか、③被相続人が、生前に自宅及び賃貸用不動産を信託財産とする信託契約を締結しており、遺産分割により2人の相続人がそれぞれ「自宅に係る受益権」「賃貸用不動産に係る受益権」を取得するケースで、第一段階として受益権全体を両者が共有で取得し、第二段階として各受益権を取得したと考えた場合、相続税に加え贈与税が課税されるのか−−という3つの事例について解説する。
事例1
更地と借地権を消滅させた土地を一体譲渡した場合の収入の按分方法
土地の実勢価格に基づき按分することの合理性は
株式市場同様、土地の価格も都心を中心に高騰している。ある程度の広さの土地はマンション用地としてマンションディベロッパー等から高いニーズがあるが、マンション用地となり得るような大きさの土地となると、その一部が借地となっているケースも多い。この場合、更地部分と隣接する借地権が設定されていた土地の譲渡(両土地を一体として譲渡)収入金額の按分方法が問題となる。
例えば、甲が数十年前から所有していた自用地であるA土地(更地、面積2,000㎡)と同土地に隣接する借地権が設定されたB土地(面積1,000㎡)があったとしよう。そして、マンションディベロッパーX社が、甲よりA土地及びB土地全体(3,000㎡)を取得して分譲マンションの建設を計画しているとする。この計画を遂行するためには、B土地に設定された借地権が障害となる。そこで、甲はB土地に係る借地権を5,000万円の対価を支払って消滅させた後、A土地及びB土地を一体とし、X社に5億円で譲渡する契約を締結したとする。
所得税法上、借地権を消滅させて譲渡したB土地に係る譲渡所得は、所得税基本通達33−11の2《借地権を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の収入金額の区分》及び38−4の2《借地権を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得の取得費》に基づき短期譲渡所得(旧借地権部分)と長期譲渡所得(旧底地部分)とに区分して計算することになる。このため、5億円の譲渡収入金額をA土地とB土地にいかに按分するかは重要な意味を持つ。
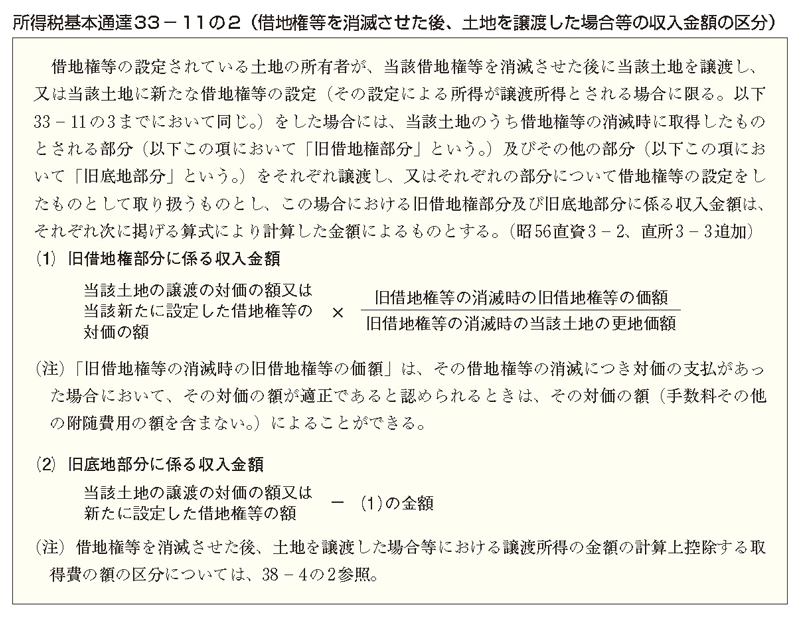
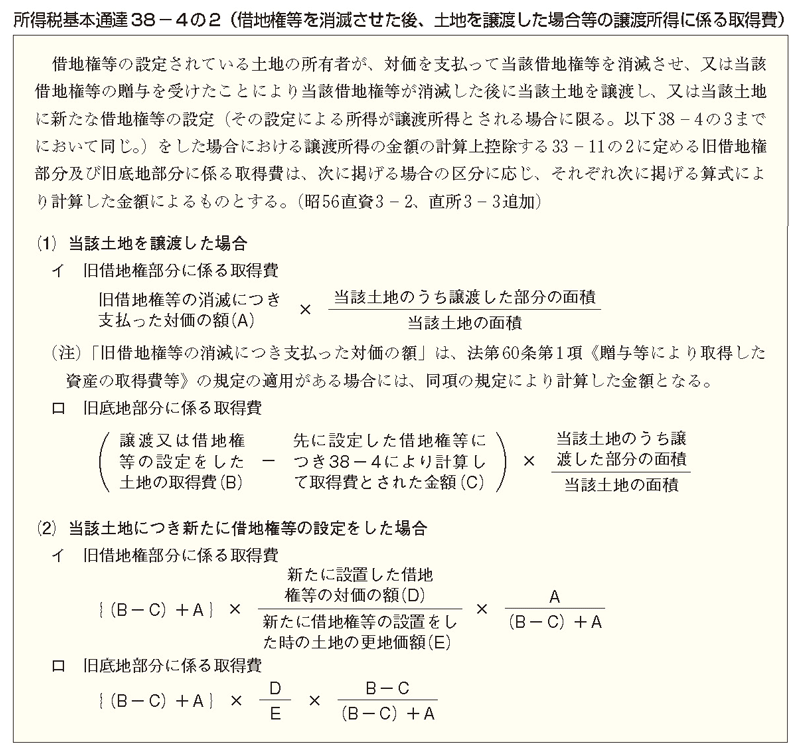
按分方法の一つとして考えられるのが、譲渡前の各土地の実勢価格による方法だ。例えばA土地は幅員12mの公道に面しているものの、B土地はA土地の裏手にあり無道路地であった場合、B土地の実勢価格は低くなる。
仮にA土地の実勢価格を3億円、B土地の実勢価格を1億円とすると、①当該譲渡収入金額(5億円)に占める本件借地権の消滅の対価の額が明らかであること、②A土地は、X社がマンションを建築するために必要不可欠な土地であり、A土地を取得できなければ当該譲渡契約は成立しなかったことを考慮すれば、当該譲渡収入金額(5億円)をそれぞれの土地の実勢価格に基づき按分することにも合理性があるように見える。
両土地の譲渡収入を各土地の「面積比率」によって按分するのが相当
しかし、当該譲渡契約は、X社が、A土地及びB土地全体を利用して分譲マンションを建設する目的で締結したものである上、当該譲渡契約においては、当該土地全体が売買の目的物とされており、建築するマンションも両土地全体を利用することになる。
このように、マンションは“両土地全体”を利用して建設され、また、両土地の譲渡契約においても両土地全体が売買の目的物とされていることから、両土地の譲渡収入金額を各土地の「面積比率」によって按分するのが相当ということになる。
すなわち、譲渡収入金額(5億円)をA土地及びB土地に区分するにあたっては、それぞれの土地の「面積比率」によって按分するべきであり(平成10年6月26日公表裁決参照)、譲渡前の各土地の実勢価格に基づき按分するのは誤りということだ。
事例2
夫から使用貸借の土地で妻が賃貸業、妻・夫の順に死亡時の土地評価
使用貸借通達3から、夫が建物を相続でも敷地利用権は妻に従属との考えも
土地の相続税評価にあたり、土地を「自用地」と見るべきか「貸家建付地」と見るべきか判断に迷うことがある。
例えば、妻(乙)が夫(甲)の所有する土地(本件土地)を使用貸借により借り受けてアパート(本件建物)を建て、賃貸事業を営んでいたところ、まず乙に相続(1次相続)が開始し、甲が本件建物を相続したものの、その後、甲についても相続(2次相続)が開始したといったケースだ。
この点、使用貸借通達3《使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合》では、使用貸借に係る土地を相続又は贈与により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、その土地の上に存する建物等が貸し付けられていたとしても「自用のものであるとした場合の価額」とされている(下掲参照)。
使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合(使用貸借通達3)
使用貸借に係る土地又は借地権を相続(遺贈及び死因贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(死因贈与を除く。以下同じ。)により取得した場合における相続税又は贈与税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等又は当該借地権の目的となっている土地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、すべて当該土地又は借地権が自用のものであるとした場合の価額とする。 |
これは、使用貸借により借り受けた土地に建物が建てられて、その建物が賃貸借により貸し付けられている場合の賃借人の敷地利用権は、建物所有者(土地の使用貸借権者)の敷地利用権から独立したものではなく、建物所有者の敷地利用権に従属し、その範囲内で行使されるにすぎないと解されているからだ。
この取扱いを本件に当てはめれば、1次相続前においては、乙が使用貸借により本件土地を借り受けていた以上、本件建物の賃借人の敷地利用権は乙の敷地利用権に従属し、その範囲内で行使されていたことになり、甲が本件建物を相続しても、その状況は変わらないのではないか、とも考えられる。
民法上、使用貸借は借主の死亡で効力消滅、2次相続に係る土地は貸家建付地に
しかし、民法上、使用貸借は借主の死亡によりその効力を失うとされていることから(民法597条3項)、甲が乙から本件建物を相続した段階で、乙の本件土地に係る使用借権、すなわち敷地利用権は消滅するため、本件建物の賃借人の敷地利用権は直接、本件土地に及ぶものと解することができる。
このように、民法上、使用貸借は借主の死亡によりその効力を失うとされていることを踏まえると、2次相続に係る本件土地は、貸家建付地として評価するのが相当ということになる。
なお、貸家とその敷地を所有する夫が貸家だけを妻に贈与し、その敷地を使用貸借としていた場合において、当該貸家の賃貸人に異動がない段階で夫に相続が開始した場合にも、当該敷地は貸家建付地として評価される。
事例3
信託受益権を分割して共同相続人がそれぞれ取得した場合の課税関係は
信託法上、受益権を質的に異なる複数のものとすることも可
被相続人甲が、生前に自宅及び賃貸用不動産を信託財産とする信託契約を締結しており、遺産分割により2人の相続人がそれぞれ「自宅に係る受益権」「賃貸用不動産に係る受益権」を取得するケースがあり得るが、このようなケースを、“第一段階”として受益権全体を両者が共有で取得し、“第二段階”として各受益権を取得したと考えた場合に懸念されるのは、相続税に加え贈与税が課税されるのではないかということだ。
例えば、被相続人甲が、生前に以下のような信託契約(なお、当該信託契約では、信託の終了事由として甲の死亡は挙げられていない)を締結していたとしよう。
・委託者:甲
・受託者:丙
・受益者:甲
・信託財産:自宅及び賃貸用不動産(信託財産に関する受益権を「本件受益権」という)
被相続人甲の相続人は「乙」及び「丙」の2人だが、遺産分割により当該信託財産のうち自宅に関する権利(本件受益権①)は甲が、賃貸用不動産に関する権利(本件受益権②)は丙がそれぞれ取得した場合、第一段階として、相続の開始により乙及び丙が本件受益権を共有で取得し、第二段階として、遺産分割によって乙が本件受益権①を、丙が本件受益権②を取得することになる。ここで懸念されるのが、相続税に加え贈与税が課税されるのではないかということだ。
そこでまず信託法を確認すると、同法149条《関係当事者の合意等》では、委託者・受託者・受益者の合意等による信託の変更を認めている。例えば、信託の変更により受益権を質的に異なる複数のものとすること、つまり、本件受益権である自宅及び賃貸用不動産に関する権利を本件受益権①と本件受益権②とに分けることもできる。
相続税の範疇で課税関係完結、相続税及び贈与税の二段階課税はなし
そして、相続した受益権を遺産分割前にこのように変更したからといって、遺産共有(遺産未分割)の状況は変わるものではない。この点は、遺産分割前に相続した土地を分筆した後、遺産分割によって共同相続人がそれぞれ取得する場合と比較すれば明らかだ。
また、仮に本件信託契約で信託の終了事由として甲の死亡が挙げられ、かつ、帰属権利者が乙及び丙とされていた場合において、当該帰属権利者が遺産分割によって自宅と賃貸用不動産とに分けて取得した事例と比較しても明らかと言える。
以上を踏まえると、信託法149条の規定により本件信託の受益権の質的変更を遺産分割前までに行い、遺産分割によって各相続人がそれぞれの受益権を取得、すなわち、乙が本件受益権①を、丙が本件受益権②を取得すれば、相続税の範疇で課税関係は完結する。すなわち、相続税及び贈与税の二段階の課税はないということになる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























