解説記事2024年05月20日 解説 四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等(2024年5月20日号・№1027)
解説
四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等
金融庁企画市場局企業開示課開示業務室長 齊藤貴文
金融庁企画市場局企業開示課課長補佐 小作恵右
金融庁企画市場局企業開示課専門官 伊藤洋平
金融庁企画市場局企業開示課係長 尾崎祐二
金融庁企画市場局企業開示課 齋藤 舜
はじめに
令和5(2023)年11月20日、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第79号。以下「改正法」という。)が成立した。
これにより、令和6(2024)年4月1日より、金融商品取引法上の四半期報告書制度が廃止され、四半期開示制度は証券取引所規則に基づく四半期決算短信に「一本化」されるとともに、第2四半期については、四半期報告書に代えて半期報告書の提出が求められることとなる。
改正法の施行に伴い、令和6(2024)年3月27日、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和6年内閣府令第29号。以下「整備府令」という。)等が公布されたほか、企業会計審議会は「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に係る意見書及び監査に関する品質管理基準の改訂に係る意見書」(以下「意見書」という。)の公表を行い、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に改訂するとともに、監査に関する品質管理基準の改訂(以下「改訂品質管理基準」という。)を行った。
本稿は、これらの改訂等の経緯及び内容について解説を行うものであるが、意見にわたる部分については、筆者らの個人的見解である。
なお、以下では、改正前の金融商品取引法を「旧法」、改正後の金融商品取引法を「新法」、整備府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令を「新開示府令」、改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則を「新財務諸表等規則」、改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則を「新連結財務諸表規則」、改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令を「新監査証明府令」という。
一 監査人によるレビューの基準
1 背景・経緯
金融商品取引法に基づく四半期報告書制度については、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告において、
・法律上の四半期開示義務(第1・第3四半期)を廃止して四半期決算短信に「一本化」すること、
・上場企業は、開示義務が残る第2四半期報告書を金融商品取引法上の半期報告書として提出し、その半期報告書については、これまでと同様、第2四半期報告書と同程度の記載内容と監査人のレビューを求めること、
・非上場企業は、上場企業に義務付けられる枠組みを選択可能とすること、
・速報性の観点等から、四半期決算短信については監査人によるレビュー(以下「一本化後の四半期決算短信におけるレビュー」という。)を一律には義務付けず、企業の判断に委ねること
などの方向性が示されたことを踏まえ、金融商品取引法の規定の見直しを行い、改正法が成立した。
こうした中、四半期開示の見直しに伴う監査人のレビューに係る必要な対応について、令和5(2023)年4月に開催した企業会計審議会総会の議論を踏まえ、同年9月から、企業会計審議会監査部会において審議を開始した。
(準拠性に関する結論と適正性に関する結論の異同)
年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う中間財務諸表その他の期中財務諸表(以下「期中財務諸表」という。)に対するレビュー(以下「期中レビュー」という。)については、種々異なる需要が想定されるところである。
例えば、幅広い利用者に共通するニーズを満たすべく一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(脚注1)に準拠して作成された期中財務諸表(以下「一般目的の期中財務諸表(脚注2)」という。)に対して、経営者が採用した会計方針が企業会計の基準に準拠し、それが継続的に適用されているかどうか、その会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかに加え、期中財務諸表における表示が利用者に理解されるために適切であるかどうかについて判断した結論(以下「適正性に関する結論」という。)を表明することがある。この判断には、期中財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかの評価と、期中財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価が含まれる。一方で、期中財務諸表が当該期中財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されているかどうかについての結論(以下「準拠性に関する結論」という。)を表明することもあるが、この場合には、財務諸表が全体として適正に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価は行われない(脚注3)。なお、四半期レビュー基準では、四半期財務諸表についての適正性に関する結論の表明のみが規定されている。このほか、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された期中財務諸表(以下「特別目的の期中財務諸表(脚注4)」という。)に対して結論を表明することもある。
こうしたことから、企業会計審議会においては、四半期レビュー基準について、新法における中間財務諸表に対するレビューに加えて、一本化後の四半期決算短信におけるレビューも含め、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの全てに共通するものとする方向で改訂の検討を進めることとし、令和5(2023)年12月の公開草案に対する意見募集(脚注5)を経て、令和6(2024)年3月に四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂等を行った。
2 四半期レビュー基準の期中レビュー基準への主な改訂点とその考え方
今般の四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂の概要は図表のとおりである。四半期レビュー基準では、旧法における四半期財務諸表に対するレビューのみが対象であったが、期中レビュー基準では、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う様々な期中レビューを対象にしている。以下、主な改訂点について解説を行う。
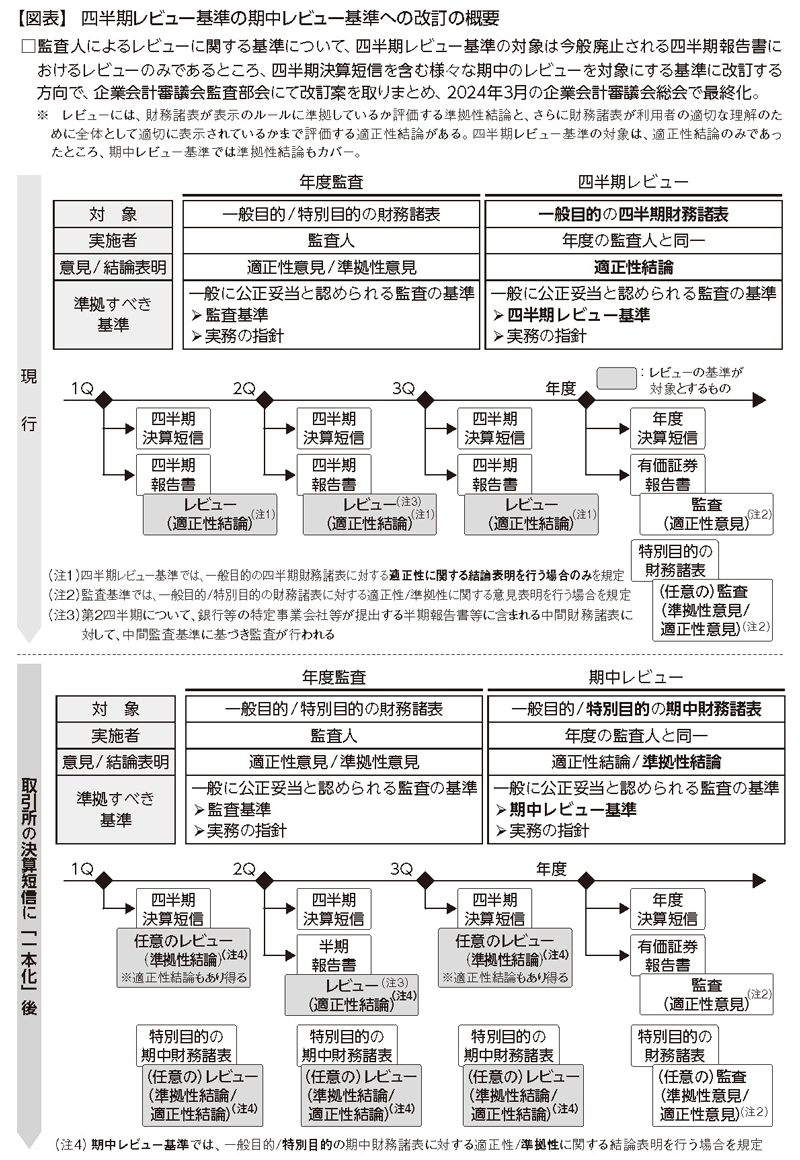
(1)基準の名称変更、用語の置き換え
本改訂においては、期中財務諸表の種類や結論の表明の形式を異にするレビューも含め、年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの全てに共通するものとして、四半期レビュー基準を期中レビュー基準に名称変更するとともに、基準の中で用いる用語についても、例えば、「四半期財務諸表」を「期中財務諸表」に、「四半期レビュー」を「期中レビュー」に改めるなど、用語の置き換えを行っている。
(2)準拠性に関する結論表明の導入や特別目的の期中財務諸表に対する結論表明の位置付けの明確化
本改訂においては、四半期レビュー基準で規定している適正性に関する結論の表明の形式に加えて、準拠性に関する結論の表明の形式を期中レビュー基準に導入し、併せて、レビュー実務における混乱や期中財務諸表利用者の誤解等を避けるため、特別目的の期中財務諸表に対する結論の表明の位置付けを明確にすることとした。
その際には、一般目的の期中財務諸表と特別目的の期中財務諸表のそれぞれについて適正性に関する結論の表明と準拠性に関する結論の表明とがあり得ることを踏まえつつも、監査基準の枠組みとの整合性にも十分配意(脚注6)し、かつ、四半期レビュー基準の趣旨を踏まえ、新法における中間財務諸表に対するレビューのような一般目的の期中財務諸表を対象とした適正性に関する結論の表明を基本(脚注7)とすることとした。
具体的には、以下のとおり改訂等を行っている。
① 期中レビューの目的の改訂
「第一 期中レビューの目的」において、一般目的の期中財務諸表又は特別目的の期中財務諸表を対象とした準拠性に関する結論の表明が可能であることを明確にした(第一 期中レビューの目的 第2項)。
② 実施基準の改訂
特別目的の期中財務諸表には多種多様な期中財務諸表が想定されることから、「第二 実施基準」において、監査人は、特別目的の期中財務諸表の期中レビューを行うに当たり、当該期中財務諸表の作成の基準が受入可能かどうかについて十分な検討を行わなければならないことを明確にした(第二 実施基準 第2項)。
なお、「第二 実施基準」における記述についても、一般目的の期中財務諸表を対象とした適正性に関する結論の表明を基本とした記述としているが、監査部会での議論(脚注8)を踏まえ、意見書の「前文」において、
・「期中レビューの実施に当たっては、準拠性に関する結論の表明の場合であっても、適正性に関する結論の表明の場合と同様に、期中レビュー手続を実施し、結論の表明の基礎となる証拠を得なければならないことから、「第二 実施基準」が当然に適用されることに留意が必要である」こと、
・「継続企業の前提に関する手続についても、準拠性に関する結論の表明の場合であっても、適正性に関する結論の表明の場合と同様である」こと、
・「特別目的の期中財務諸表の期中レビューを行うに当たっては、当該期中財務諸表が特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成されていることに留意する必要がある」こと
を明確にすることとした。
このほか、「期中財務諸表に対する期中レビューの結論を表明する場合のほか、期中財務諸表を構成する貸借対照表等の個別の財務表や個別の財務諸表項目等に対する期中レビューの結論を表明する場合についても、期中レビュー基準が適用される」ことも明確にしている。
③ 報告基準の改訂
「第一 期中レビューの目的」において、適正性に関する結論に加えて準拠性に関する結論にかかる記述を付記したことを踏まえ、「第三 報告基準」において、適正性に関する結論の表明について特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される期中財務諸表の場合を付記するとともに、これに加えて、準拠性に関する結論の表明について規定し、監査人が準拠性に関する結論を表明する場合には、作成された期中財務諸表が、当該期中財務諸表の作成に当たって適用された会計の基準に準拠して作成されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかについての結論を表明しなければならないこととした(第三 報告基準 第1項)。
なお、準拠性に関する結論の表明については、別途の報告基準を改めて規定するのではなく、適正性に関する結論の表明を前提としている報告基準に準じることとしているが、特別目的の期中財務諸表の利用者の誤解を招かないようにするために、「第三 報告基準」において、特別目的の期中財務諸表に対する期中レビューの場合の追記情報を規定した(第三 報告基準 第14項)。すなわち、特別目的の期中財務諸表に対する期中レビュー報告書を作成する場合には、期中レビュー報告書に、会計の基準、期中財務諸表の作成の目的及び想定される主な利用者の範囲を記載するとともに、期中財務諸表は特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成されており、他の目的には適合しないことがある旨を記載しなければならないこととした。また、期中レビュー報告書が特定の者のみによる利用を想定しており、当該期中レビュー報告書に配布又は利用の制限を付すことが適切であると考える場合には、その旨を記載しなければならないこととした。
3 監査における不正リスク対応基準との関係
期中レビューについては、年度監査と同様の合理的保証を得ることを目的としているものではないことから、意見書の「前文」において、「監査における不正リスク対応基準は期中レビューには適用されない」ことを明確にすることとした。
なお、四半期レビュー基準に基づく実務と同様に、「期中レビューの過程において、期中財務諸表に不正リスク対応基準に規定している不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合等には、監査人は、必要に応じて、期中レビュー基準に従って、追加的手続を実施することになる」ことも明確にした。
4 監査に関する品質管理基準の主な改訂点とその考え方
監査に関する品質管理基準は、監査基準と一体として適用されるほか、中間監査、四半期レビュー及び内部統制監査について準用され、それ以外の監査事務所の業務については、参照されることが望ましいとされてきた。
四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に伴い、監査に関する品質管理基準の一部の改訂を行い、期中レビューについて監査に関する品質管理基準が準用されるように改めることとした。
二 監査人によるレビューに関連する整備府令
監査人によるレビューに関連する整備府令の主な改正点について、解説を行う。
(1)中間(連結)財務諸表に対する期中レビューと中間監査の区分等
新法では、四半期報告書の提出義務が廃止されたことに伴い、これまで四半期報告書提出会社以外の有価証券報告書提出会社に義務付けていた半期報告書の提出を、全ての有価証券報告書提出会社に対して義務付けることとし、提出会社の種類に応じ、提出すべき半期報告書の記載内容について定めている。
新財務諸表等規則等では、新法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間(連結)財務諸表を「第一種中間(連結)財務諸表」(新財務諸表等規則第1条第1項第2号、新連結財務諸表規則第1条第1項第2号)、新法第24条の5第1項の表の第2号又は第3号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間(連結)財務諸表を「第二種中間(連結)財務諸表」(新財務諸表等規則第1条第1項第3号、新連結財務諸表規則第1条第1項第3号)として区分している。
上記区分を受けて、新監査証明府令においても、第一種中間(連結)財務諸表には期中レビュー、第二種中間(連結)財務諸表には中間監査を行うこととし、期中レビューを要する中間(連結)財務諸表と中間監査を要する中間(連結)財務諸表を区分している(新監査証明府令第3条第1項)。
また、一般に公正妥当と認められる監査の基準に該当するものとして規定されている企業会計審議会が公表した基準のうち、「四半期レビュー基準」を「期中レビュー基準」に改めることとした(新監査証明府令第3条第4項)。
(2) 有価証券届出書において四半期に係る財務情報を記載する場合における期中レビューの取扱い
今般の改正で四半期報告書の提出義務が廃止されたことに伴い、金融商品取引法の規定に基づく四半期財務諸表等は作成する必要がなくなったため、新開示府令では、有価証券届出書において四半期財務諸表等の記載を求めないこととした(新開示府令第2号様式等)。
一方で、上場会社は、引き続き、取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を記載した四半期決算短信を公表する必要があり、資金調達に当たって、四半期に係る財務情報を記載した有価証券届出書を提出する実務の継続を望む意見もあることから、四半期に係る財務情報を任意で有価証券届出書に記載できることとした。そして、四半期に係る財務情報を有価証券届出書に記載する場合には、期中レビューの有無の記載を求めることとし、期中レビューが行われている場合には当該期中レビューに係る期中レビュー報告書の添付を求めることとした(開示ガイドライン5−21−2)。
なお、四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表について監査人の期中レビューを受けていない場合であっても、有価証券届出書を提出することを目的として、当該四半期財務諸表に対して、監査人から期中レビューを受けることは可能であるが、期中レビュー手続を行うためには一定の時間を要するため、監査人との間で、予め資金調達を想定したスケジュールの共有等を行うことが重要となると考えられる(脚注9)。
三 一本化後の四半期決算短信における期中レビューの留意事項
1 期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項
一本化後の四半期決算短信におけるレビューは一律には義務付けず、企業の判断に委ねることとされている。こうした中、期中レビュー契約の締結を行わず、期中レビュー報告書の発行も求められない中で、企業から期中レビュー手続を実施して欲しいという要望が生じた場合、期中レビューの結論表明を目的とする期中レビュー手続に該当するような手続は実施できないことに留意する必要がある。この場合に実施可能な手続は、年度監査の一環として実施される監査手続が考えられるが、企業と監査人との間で十分にコミュニケーションを行うことが重要である(脚注10)。
2 後発事象に対する期中レビュー手続
後発事象については、期中レビュー基準の「第二 実施基準」において、「監査人は、期中財務諸表において修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない」とされている。
取引所の規則等では、重要な後発事象の注記は企業の任意とされているため、四半期財務諸表等において重要な開示後発事象の注記を行わないことを選択した場合、監査人は期中レビュー基準に従って準拠性に関する結論を表明する(脚注11)に当たって、基本的には上記の質問以外の手続を実施することは求められていない。しかし、開示後発事象がないことによって、財務諸表の利用者の誤解を招くと監査人が判断するような重大な場合(脚注12)には、経営者に伝達し協議した上で、期中レビュー報告書において、その他の事項として記載するかどうかを検討することに留意する必要がある。
四 施行時期・適用時期等
新法では、四半期報告書等に関する規定は、令和6(2024)年4月1日を施行日としている(改正法附則第1条第3号)が、次の経過措置が設けられている。
四半期報告書の提出義務は、施行日から廃止されるが、施行日前に開始した四半期については、施行日以後も、引き続き旧法の規定に基づく四半期報告書の提出義務を負う(改正法附則第2条第1項)。
また、新法の規定に基づく半期報告書は、施行日以後に開始する事業年度から提出が義務付けられる(改正法附則第3条第1項)。そして、施行日前に事業年度が開始する四半期報告書提出会社については、旧法の規定が適用されることから、当該事業年度に係る半期報告書の提出は求められない。
しかし、このような四半期報告書提出会社のうち、施行日前に事業年度が開始し、かつ、施行日以後に第2四半期が開始する会社(12月決算会社、1月決算会社及び2月決算会社)については、施行日を含む事業年度から、半期報告書を提出する必要がある(改正法附則第3条第2項)。
期中レビュー基準及び改訂品質管理基準は、上記と同様に、令和6(2024)年4月1日以後開始する期中財務諸表に係る会計期間の期中財務諸表に対する期中レビューから適用する。
これにかかわらず、改正法附則第3条第2項に規定する、新法第24条の5第1項の表の第1号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表の期中レビューについては、期中レビュー基準及び改訂品質管理基準を適用する。
なお、決算期によって四半期報告書提出会社の施行時期が異なるが、新法に基づく開示に係る期中レビューや、施行後に開始する一本化後の四半期決算短信におけるレビューには、期中レビュー基準が適用されることになる。
おわりに
期中レビュー基準では、新法における中間財務諸表に対するレビューに加えて、一本化後の四半期決算短信におけるレビューも含めて、年度の監査人が行う期中レビューの全てを対象にすることで、期中レビューが一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って実施されることが明確になり、監査人によるレビューや開示情報の信頼性の確保につながっていくことが考えられる。
金融庁においては、金融商品取引法上の四半期報告書を廃止し、取引所の規則に基づく四半期決算短信へ一本化するに当たって、東京証券取引所や日本公認会計士協会等と連携しながら、投資家に必要な情報が提供されるための環境整備及び制度の円滑な移行に資する環境整備を進めていく。
なお、一本化後の四半期決算短信におけるレビューについては、取引所の規則等により、原則任意とされており、準拠性に関する結論が導入されることとあわせて、企業会計審議会の議論においても、例えば、開示情報に対する信頼性の程度は下がるのではないか、監査証明業務そのものの重要性を低下させるのではないかなどといった懸念する意見があった。
この点について、取引所の規則等において、会計不正等により、財務諸表の信頼性確保が必要と考えられる場合は期中レビューが義務付けられることとされている。
また、一本化後の四半期決算短信におけるレビューは、一律には義務付けず、企業の判断に委ねることとされた。今後の企業による開示情報の速報性と信頼性のバランスを確保した取組にも期待したい。
監査証明業務は、財務諸表の信頼性を確保する上で欠かすことのできない重要なものであり、金融庁としても、その重要性について、引き続き様々な利害関係者の理解を促してまいりたい。
脚注
1 期中レビュー基準における「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」は、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則に基づき金融庁長官が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとして告示指定した企業会計の基準に限られるものではなく、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として実務の中で取り扱われる企業会計の基準も含まれるものと考えられる。
なお、企業会計基準委員会が策定した四半期会計基準については、財務諸表等規則及び連結財務諸表規則に基づき金融庁長官が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとして告示指定した企業会計の基準の対象からの除外という事実のみをもって、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準として実務の中で取り扱われなくなることは想定されていない。(「「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」等の一部改正案に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2024年3月29日公表)No.1-4)
また、企業会計基準委員会が公表した「企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」等の公表」において、「金融商品取引法上は四半期報告書制度が廃止されるが、上場会社においては引き続き取引所規則に基づき第1・第3四半期決算短信の報告が行われるため、今後、期中財務諸表に関する会計基準等の開発が行われるまでの間、四半期会計基準等は適用を終了しないことを予定している」とされており、この点にも留意が必要である。
2 新法における中間財務諸表は、一般目的の期中財務諸表として位置付けられる。また、一本化後の四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等は、パブリックコメントを通じて策定された取引所の規則等を介して、実質的には「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」に準拠して作成し、一般投資家向けに開示されているものであるとされていることから、一般目的の期中財務諸表であると考えられている。
なお、2024年3月12日開催の企業会計審議会総会において、堀江監査部会長より「改正後の金融商品取引法上の中間財務諸表は一般目的の期中財務諸表として位置づけられ、一本化後の四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等も、あくまでも一般目的の期中財務諸表として整理されるものと承知している」旨の発言があった。
また、日本公認会計士協会「期中レビュー基準報告書第2号実務ガイダンス第1号 東京証券取引所の有価証券上場規程に定める四半期財務諸表等に対する期中レビューに関するQ&A(実務ガイダンス)(以下、「期中レビューに関するQ&A」という。)」においても、「第1・第3四半期財務諸表等は、(中略)一般目的の財務報告の枠組みとなる。」とされている。
3 準拠性に関する結論を表明するに当たって、監査人は、経営者が採用した会計方針が、会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか、期中財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかについて形式的に確認するだけではなく、当該会計方針の選択及び適用方法が適切であるかどうかについて、会計事象や取引の実態に照らして判断しなければならないことにも留意が必要である。
4 これまでの実務における特別目的の期中財務諸表の一例として、上場会社等でない生命保険会社が四半期報告モデル(生命保険協会が作成したモデルで、四半期連結財務諸表規則の注記の一部を省略したもの)に準拠して任意に作成した四半期財務諸表などが挙げられる。
5 公開草案について、2023年12月21日から2024年1月24日までの間、パブリックコメント手続が行われた。その結果、公開草案については、4の個人及び団体から延べ9件の意見が提出された。企業会計審議会において、寄せられた意見を踏まえ公開草案から字句修正を行い、改訂・公表を行った。(https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20240327-2/20240327.html)
6 四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂に当たっては、平成26(2014)年改訂監査基準を参考にした。(https://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140225-2.html)
7 期中レビュー基準における記述についても、一般目的の期中財務諸表を対象とした適正性に関する結論の表明を基本とした記述にすることとしつつ、一般目的の期中財務諸表又は特別目的の期中財務諸表を対象とした準拠性に関する結論の表明が可能であることを付記することとした(四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)に対するコメントの概要及びコメントに対する考え方(2024年3月27日公表)No.6-8)。
8 第54回監査部会(2023年9月5日開催)及び第55回監査部会(2023年12月14日開催)において、委員等から「一本化後の四半期決算短信でも、継続企業の前提に関する注記の開示を求めることとされているが、監査人に継続企業の前提の対応を求めるのに準拠性に関する結論で良いのか」、「準拠性を想定したような実施手続になっていない」、「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準以外の会計基準、財務報告に準拠するケースを想定した実施手続となっていない」等との意見があった。
9 「令和5年金融商品取引法等改正に係る政令・内閣府令案に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」(2024年3月27日公表)No.18-20、32
10 日本公認会計士協会「第1・第3四半期決算短信に添付される四半期財務諸表等に対する期中レビュー契約を締結しない場合の留意事項(お知らせ)」(2024年4月5日公表)
11 四半期決算短信に含まれる四半期財務諸表等は、有価証券上場規程等に基づき、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び財務諸表等規則に準拠して作成されることになる(有価証券上場規程施行規則 別添9 四半期財務諸表等の作成基準 第4条参照)。四半期財務諸表等の作成基準第4条第1項では、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び財務諸表等規則に準拠して作成することが要求されており、適正性に関する結論の表明が想定される一方で、同第4条第2項では、同第1項の記載の一部の省略が認められている等のため、準拠性に関する結論の表明が想定される。
12 例えば、会社が存続できなくなるような状況に陥っているが、会社が当該状況を開示後発事象として注記しておらず、監査人が財務諸表の利用者の誤解を招くと判断するような重大な場合が挙げられる(日本公認会計士協会の期中レビューに関するQ&A Q5 後発事象)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























