解説記事2024年06月10日 ニュース特集 税制改正前のLED照明管等の節税スキームも税務調査で否認(2024年6月10日号・№1030)
ニュース特集
審判所は「事業所得」か否かを8つの諸要素に照らして判断
税制改正前のLED照明管等の節税スキームも税務調査で否認
ドローンや建築用足場資材、LED照明管などの少額減価償却資産を利用した節税スキームについては、令和4年度税制改正で封じられることになったが、税制改正前に実施された節税スキームであっても税務調査で否認されていることがわかった。本誌が入手した裁決事例によれば、会社役員が取得した建築用足場資材、クラシックカー、LED照明管について、賃貸借契約を締結し、これにより生じた所得を事業所得として確定申告を行ったが、その後の税務調査により、雑所得に該当するとして更正処分が行われている。審判所も、各賃貸業務は有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、企画及び遂行の大部分を他者に依存していることから、請求人が自己の危険と計算による企画遂行したものとは認められないとして、原処分を支持する判断を示している。審判所は、事業所得に該当するか否か、8つの諸要素に照らして詳細に判断を行っており、今後の実務の参考にできそうだ。
令和4年度税制改正で貸付けの用に供した資産が除外
令和4年度税制改正では、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度及び一括償却資産の損金算入制度について、対象となる資産から貸付けの用に供した資産が除外されることになった(ただし、主要な事業として行われるものは除く)。いわゆる“ドローン節税”などともてはやされた節税スキームを封じるものである。
この節税スキームは、当期の利益を圧縮する目的として、自らが行う事業で使用しない少額な資産を大量に取得し、その取得した資産を貸付けの用に供することにより、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等を適用して当期の損金に算入し、賃貸料・売却益を当期以後の複数年度の益金に算入することとする損金と益金の計上時期の相違を利用したもの。ドローン以外にも、建築用足場資材、LED照明管などが多く利用されていた。
主要な事業であれば適用可
この改正は、令和4年4月1日から施行されているため、現在は、主要な事業として行う貸付け以外は実施することができない。
しかし、これらの節税スキームについては、税制改正が行われる前の過去の申告分が税務調査で否認されているケースがあるので十分に留意したい。
事業所得に該当するか否かは最終的には社会通念によって判断
本誌が入手した裁決事例(関裁(所)令5第3号)では、建築用足場資材、クラシックカー、LED照明管を利用した取引について税務調査で否認され、その後の審査請求でも納税者の請求が棄却され、原処分が支持されている。
本件は、会社役員である請求人が、建築用足場資材、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務から生じた所得が事業所得に該当するとして所得税等の確定申告をしたところ、原処分庁が雑所得に該当するとして更正処分を行ったことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。例えば、LED照明管のレンタル事業では、請求人がW社からLED照明管を購入し(少額減価償却資産として一括して購入代金の全額を損金の額に算入)、それをH社にレンタルするというものである(図表1参照)。H社はさらにX社などにLED照明管をレンタルし、管理等はH社が行っていた。
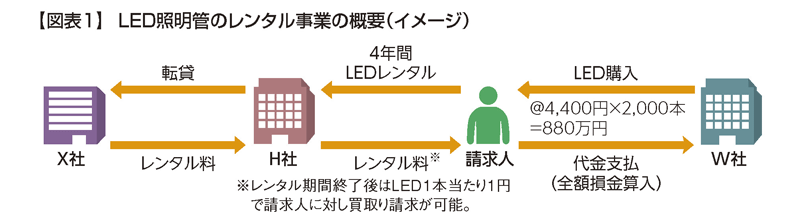
請求人は、事業所得又は雑所得のいずれに該当するかについては、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められるかで検討すべきであり、各賃貸業務は社会通念に照らしても「事業」といえることは明らかであるなどと主張した。
8つの諸要素を総合的に判断
審判所は、ある経済的行為による所得が事業所得に該当するか否かは、最終的には社会通念によって判断すべきものであるとし、その判断に当たっては、①経済的行為の営利性、有償性の有無、②継続性、反復性の有無、③自己の危険と計算による企画遂行性の有無、④経済的行為に費やした精神的、肉体的労力の程度、⑤人的、物的設備の有無、⑥経済行為をなす資金の調達方法、⑦その者の職業、経歴及び社会的地位、⑧生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が存するか否か等の諸要素を総合的に検討すべきであると解されるとした。
有償性、継続性及び反復性は認められるが…
その上で、審判所は、各賃貸業務から生じる所得が事業所得か否かに関する諸要素を踏まえて判断を行っている(図表2参照)。
それによると、LED照明管を賃貸する業務については営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が認められるものの、建築用足場資材及びクラシックカーを賃貸する業務については初期投資額を回収することは困難であり、営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性は認められないとした。
また、各賃貸業務のいずれについても、有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、企画及び遂行の大部分を他者に依存していることから、請求人が自己の危険と計算による企画遂行したものとは認められないとしたほか、請求人は、各賃貸業務に係る業務内容の決定や賃貸資産の維持管理にほとんど関与しておらず、請求人が費やした精神的・肉体的労力の程度は低いなどとし、諸要素に関する検討結果からすると、各賃貸業務から生じる所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当するとの判断を示し、請求人の請求を棄却している。
8つの諸要素は今後の実務の参考に
前述したとおり、現在は、建築用足場資材やLED照明管などを利用した節税策を実施することはできない。しかし、主要な事業として行う貸付けは別だ。今後は、事業所得とする上で「主要な事業」に該当するか否かで争われる場面がでてくる可能性もありそうだ。その際には、前述の8つの諸要素から事業所得か否かについて検討した審判所の判断は大いに参考になるだろう。
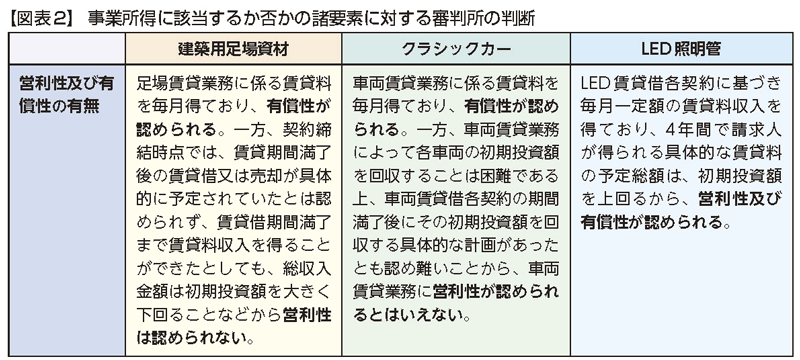
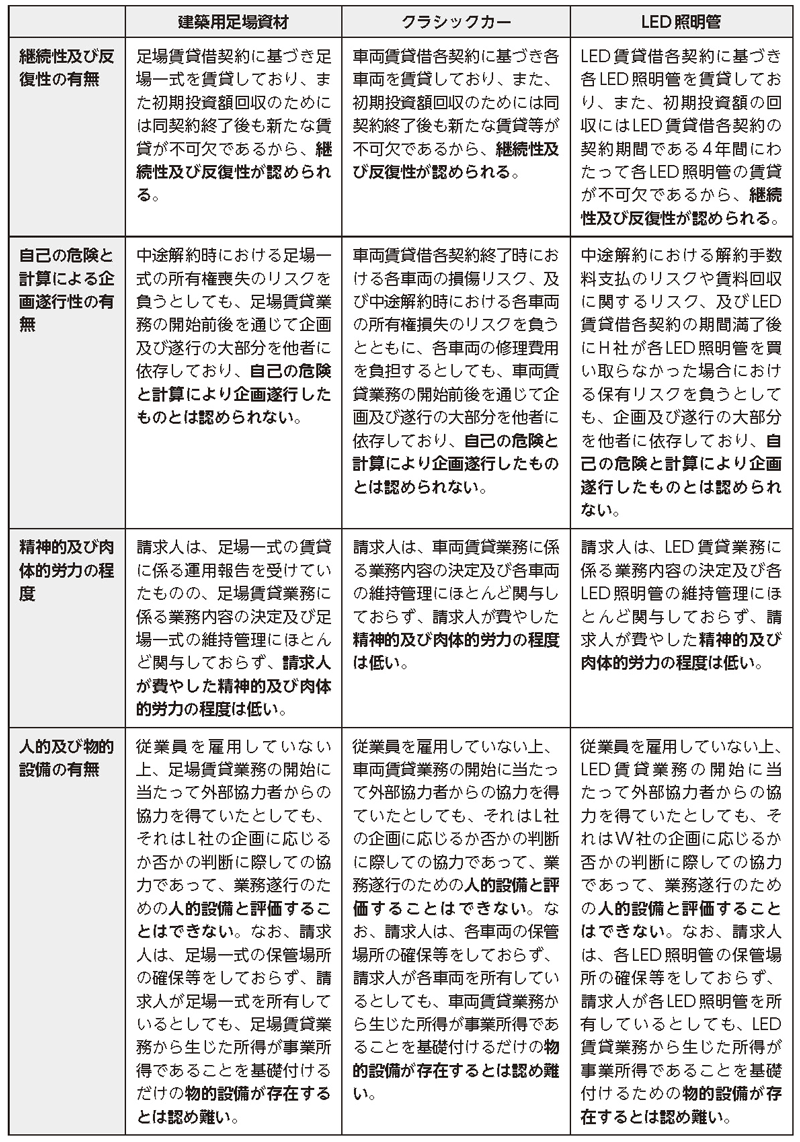
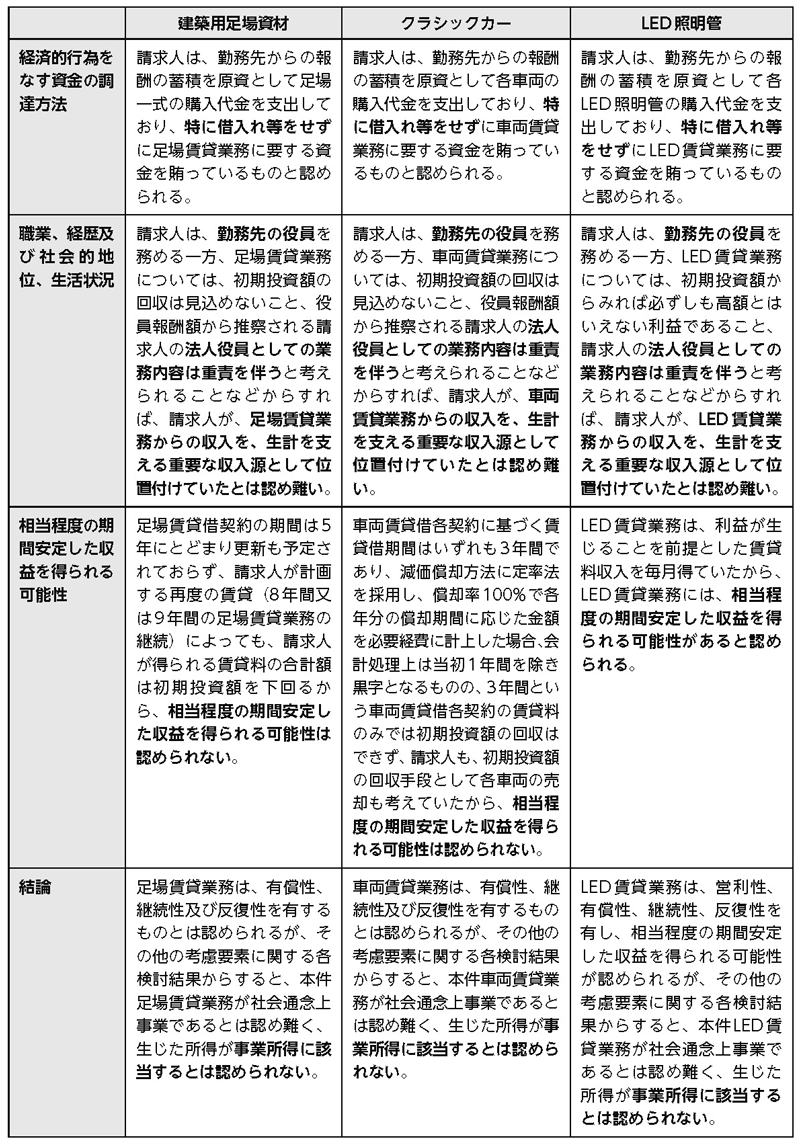
「帳簿書類を保存していれば事業所得」は一般論にすぎず
国税庁は令和4年10月7日に所得税基本通達を一部改正し、事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するとした上で、帳簿書類の保存がない場合(収入金額が300万円を超え、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には雑所得等に該当する旨を明記している(所基通35−2(注))。
この点、請求人は、事業所得に該当するか判断するに当たって、他に得ている収入と比較することについては、帳簿書類の保存の有無や事業規模で事業所得該当性を判断すべきことを原則とする本件通達の定めと整合しないと主張したが、審判所は、所得税基本通達35−2の注書きは、帳簿書類を保存している場合は事業所得に区分される場合が多いという一般論を踏まえたものであって、事業所得と雑所得の区別を社会通念に従って判断するという原則を変更するものではないと指摘している。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























