解説記事2024年09月02日 特別解説 日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した差異の調整表(表示と認識・測定)(2024年9月2日号・№1041)
特別解説
日本企業が日本の会計基準からIFRSに移行した際に開示した差異の調整表(表示と認識・測定)
はじめに
わが国の企業に対して、国際財務報告基準(IFRS)を任意に適用して連結財務諸表を作成・公表することが認められてから10年以上が経過し、250社を超える日本企業がIFRSを任意適用するまでになった。これまでわが国の会計処理や表示の基準を適用していた日本企業がIFRSに移行する場合、IFRS第1号「国際財務報告基準の初度適用」第23項に基づいて、企業は、従前の会計原則からIFRSへの移行が、報告された財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローにどのように影響したのかを説明しなければならない。これは、従前の会計原則に従って報告されていた資本から、IFRSに準拠した資本への調整表(以下、「調整表」という。)と呼ばれ、ここでは、利用者が財政状態計算書及び包括利益計算書に対する重要な修正を理解できるようにするのに十分な詳細を示さなければならないとされている(IFRS第1号第25項)。この「重要な修正」には、のれんの償却/非償却や有給休暇引当金の計上に代表される、IFRSとわが国の会計基準との間の差であるいわゆる「GAAP差異の修正(認識と測定に係る修正)」と、特別損益項目としての区分表示の可否などの「財務諸表の表示科目の差異の修正」の2種類があり、いずれも調整表で説明が加えられている。本稿では、IFRSを任意適用して有価証券報告書(四半期報告書を含む)を作成・提出した企業」(以下「IFRS任意適用日本企業」という。)の各社が、IFRSを初めて適用した期に作成した調整表を題材として、どのような項目が「財務諸表の表示科目の差異の修正」や「認識と測定に係る差異の修正」として説明されているかを調査分析した。本稿では、その結果を実際の開示例を参照しつつ紹介することとしたい。
今回調査対象とした企業
今回の調査の対象とした企業は、日本の会計基準又は米国会計基準からIFRSへ任意で移行し、2024年3月期の有価証券報告書までに調整表を作成して開示したIFRS任意適用日本企業の279社である。なお、開示例は、なるべく直近の決算期に係るもの(2024年3月期、及び2023年12月期など)を中心に取り上げている。
IFRS任意適用日本企業が初度適用時に開示した主な表示組替の内容
IFRS任意適用日本企業が、IFRSの初度適用時に調整表で開示した連結貸借対照表及び連結損益計算書の表示科目の主な組替を、開示件数が多い(開示件数が50件以上のもの)順に示すと、表1のとおりであった。
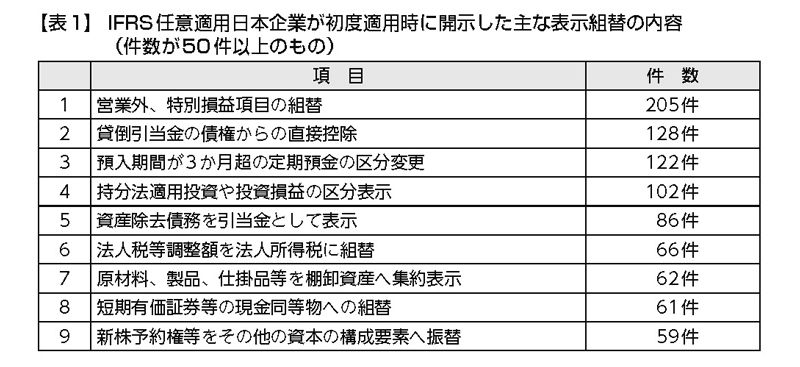
わが国でもよく知られている「営業外・特別損益項目の組替」に関する相違点の開示が圧倒的に多く、以下、「貸倒引当金の債権からの直接控除」、「預入期間が3か月超の定期預金の区分変更」や「持分法適用投資及び持分法投資損益の区分表示」といった項目が続いている。
IFRS任意適用日本企業が初度適用時に開示した認識・測定にかかる主な差異の内容
次に、IFRS任意適用日本企業がIFRSを初度適用する際に、日本基準とIFRSとの差異として説明していた認識・測定に係る項目を、企業数が多い(開示の件数が70件以上のもの)順に列挙すると、表2のとおりであった。IFRSと我が国の会計基準との代表的な差異としてよく挙げられる有給休暇引当金(未払有給休暇)の計上やのれんの非償却については、ほとんどのIFRS任意適用日本企業が開示を行っていた。
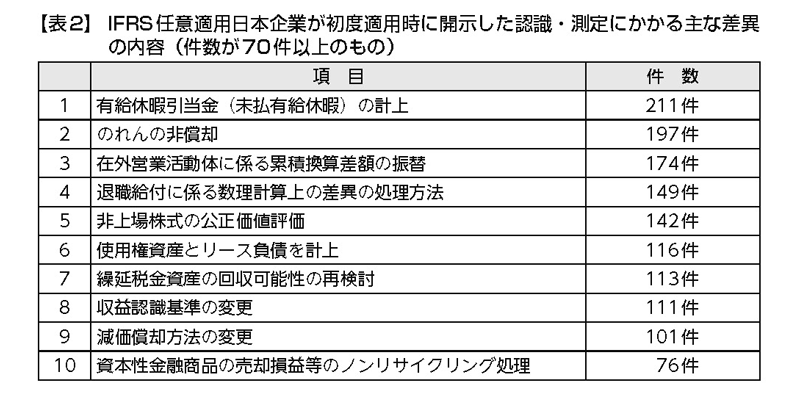
認識・測定に係る主な差異に関する説明のうち、特徴的なものの紹介
これまでは、表1や表2に列挙された差異項目について、直近の事例を用いつつ、その内容について簡単に説明を加えてきたが、ここ数年はIFRSを適用して新規上場する企業や、これまではあまり見られなかった、特殊な業種に属するIFRS任意適用企業等が出てきていることから、本稿では、件数としては多くないものの特色のある、IFRSと日本の会計基準との間の表示や認識・測定等に係る差異の説明事例を取り上げてみたい。本稿で紹介する事例は次の3件である。
1.ライフネット生命保険(2024年3月期第一四半期)
2.メルカリ(2024年6月期第一四半期)
3.INPEX(2023年12月期)
1.ライフネット生命保険(2024年3月期第一四半期)
ライフネット生命保険(株)は、国内の独立系生命保険会社であり、東証グロース市場に株式を上場している。保険外交員をなくした直販のネット生保として創業された。出口治明氏、岩瀬大輔氏など著名な関係者も多く、これまでに数多くの画期的な取組みを行って、生命保険業界のイノベーターとしての役割を果たしてきた。会計基準の面においても、生命保険会社の先頭を切って、2023年度からIFRS及びIFRS第17号「保険契約」を適用している。
ライフネット生命保険は、調整表において次のような開示を行った。
(4)保険契約資産及び保険契約負債
日本基準において、保険業法及び保険業法施行規則に基づき、以下の保険契約準備金を積み立てています。
・支払備金
期末時点において支払義務が発生しているもののうち支払いが行われていないもの、又は、まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由が既に発生しているものと認められるものについて保険業法の規定に基づいて算出された金額
・責任準備金
期末時点において、保険契約上の責任が開始している契約について、保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、算出方法書に記載された方法に従って計算した責任準備金のうち保険料積立金については、大蔵省告示に定める方式により計算しています。
責任準備金のうち危険準備金については、保険業法施行規則に基づき、保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて、所定の積立基準額以上を繰入計上し、積立限度額の範囲内で積み立てています。
また、保険契約に再保険契約を付した場合において、支払備金及び責任準備金の積立額のうち、再保険を付した部分に相当する金額を計上しないこととしています。
IFRSでは、保険契約グループの帳簿価額を、残存カバーに係る負債と発生保険金に係る負債の合計としており、残存カバーに係る負債は、将来の期間において契約に基づき提供されることとなるサービスに係る履行キャッシュ・フロー及び報告日の残存CSM(契約サービスマージン)で構成されています。
発生保険金に係る負債は、まだ支払われていない発生保険金及び費用に係る履行キャッシュ・フローで構成されています。
また、IFRSでは保険契約に再保険契約を付した場合においても、上記の残存カバーに係る負債と、発生保険金に係る負債について、金額の一部を控除する処理は行っていません。
(5)再保険契約資産及び再保険契約負債
日本基準において、再保険貸借は再保険協約に基づき計上しています。
また、新契約の一部(以下、出再契約)を対象として修正共同保険式再保険を行っており、出再契約にかかる新契約費の一部は再保険収入に含まれる出再手数料として収益計上し、未償却出再手数料として再保険貸に資産計上され、その後一定の期間において費用である再保険料を含む再保険収支に基づいて段階的に償却しています。
IFRSでは、再保険協約に基づいてカバーを受ける際に、再保険契約グループごとに再保険契約負債を認識し、再保険者から回収した金額若しくは回収見込み額を再保険契約資産として認識しています。
また、修正共同保険式再保険契約については、IFRS第17号における保険契約の定義を満たさないため、IFRS第9号に基づき会計処理を行っています。
(12)価格変動準備金
日本基準において、株式等の価格変動による損失に備えるため、保険業法の規定に基づき価格変動準備金を計上しています。IFRSでは、IAS第37号「引当金、偶発債務及び偶発資産」の負債の定義を満たさないため、価格変動準備金を計上していません。
(1)保険収益及び保険サービス費用
日本基準において、保険料及び保険金等支払金については、保険業法及び保険業法施行規則に基づき、以下の通り計上しています。
・保険料
契約応当日が到来している契約のうち、保険料の収納があったものについて、当該金額により計上
・保険金等支払金
保険約款に基づく支払事由が発生し、当該約款に基づいて算出された金額を支払った契約について、当該金額により計上、IFRSでは、保険契約に基づいてカバーを提供するにつれて、保険契約グループごとに保険収益を認識しています。
保険約款に基づき支払事由が発生している保険金請求金額(まだ支払事由の報告を受けていないものの支払事由がすでに発生していると認められるものを含む)及び、発生したその他の関連費用を保険サービス費用として認識しています。
また、当社グループは、保険料のうちの保険獲得キャッシュ・フローの回収に関連する部分を、時の経過に基づいて規則的な方法で各期間に配分しています。当社グループは、配分した金額を保険収益として認識し、同額を保険サービス費用として認識しています。
(2)再保険損益
日本基準において総額で区分掲記している「再保険収入」、「再保険料」について、IFRSでは再保険契約グループごとに再保険サービス費用を認識し、再保険者から回収した金額若しくは回収見込額を差し引いて再保険損益として表示しています。
なお、日本基準において、再保険収入及び再保険料については、再保険協約に基づき計上しています。
また、新契約の一部(以下、出再契約)を対象として修正共同保険式再保険を行っており、出再契約にかかる新契約費の一部は再保険収入に含まれる出再手数料として収益計上し、未償却出再手数料として再保険貸に資産計上され、その後一定の期間において費用である再保険料を含む再保険収支に基づいて段階的に償却しています。
IFRSでは、再保険協約に基づいてカバーを受ける際に、再保険契約グループごとに再保険サービス費用を認識し、再保険者から回収した金額若しくは回収見込額を差し引いて再保険損益として表示しています。
また、修正共同保険式再保険契約については、IFRS第17号における保険契約の定義を満たさないため、IFRS第9号に基づき会計処理を行っています。
2.メルカリ(2024年6月期第一四半期)
(株)メルカリは、フリマアプリ「メルカリ」を運営する企業であり、東証プライム市場に株式を上場している。本業に加え、Jリーグのチームである「鹿島アントラーズ」を子会社に持つなど、スポーツビジネスにも注力している。
メルカリは、調整表において、次のような開示を行った。
利用者から預託を受けた暗号資産
日本基準では利用者から預託を受けた暗号資産について、流動資産に区分掲記していた「その他」及び流動資産に区分掲記していた「その他」に含めて処理を行っておりましたが、IFRSではこれらの暗号資産については連結財政状態計算書上、資産として認識しておらず、対応する負債についても認識しておりません。
また、「重要な会計上の判断、見積り及び仮定」において、次のような開示を行っている。
(3)株式会社メルコインが利用者から預託を受ける暗号資産について
当社の連結子会社である株式会社メルコインは、「資金決済に関する法律」に基づく暗号資産交換業者として、暗号資産取引等の事業を展開しております。一方、IFRSにおいては暗号資産の取引等に係る明確な基準が存在しないことから、当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の要求事項に基づき、「財務報告に関する概念フレームワーク」及び類似の事項を扱う基準を参照し、株式会社メルコインの暗号資産交換業者として保有する暗号資産に係る会計方針を決定しております。
株式会社メルコインの保有する暗号資産の大半は、暗号資産交換業者として利用者から預託を受けた暗号資産であり、下記の事項を総合的に勘案した結果、当社は当該暗号資産に対する支配を有していないと判断しております。このため、これらの暗号資産については連結財政状態計算書上、資産として認識しておらず、対応する負債についても認識していません。
3.INPEX(2023年12月期)
(株)INPEX(旧社名:国際石油開発帝石)は、国内外で石油・天然ガス等の権益を持つ大手石油開発企業であり、東証プライム市場に株式を上場している。
INPEXは、調整表において、次のような開示を行った。
日本基準では「無形固定資産」、「生産物回収勘定」及び「生産物回収勘定引当金」として表示していた石油及び天然ガスの探鉱、評価、開発及び生産活動に係る資産については、IFRSでは「石油・ガス資産」に振替えております。
(1)共同支配事業に対する投下資本
日本基準では「生産物回収勘定」に含めていた生産分与契約のプロジェクトに係る投下資本については、IFRSでは、共同支配事業の資産及び負債に対する権利及び義務を示すため、当該共同支配事業の資産及び負債のうち当社グループの持分相当額を測定し、適切な勘定科目に含めております。
(m)石油・ガス資産
日本基準では契約形態に応じて異なる会計処理を行っておりましたが、IFRSでは石油及び天然ガスの探査及び評価に係る支出は成功成果法を用いて会計処理し、開発井及び関連する生産設備に係る支出は石油・ガス資産として認識した上で生産高比例法により減価償却しております。
(c)石油・ガス資産の減価償却
日本基準では契約形態に応じて異なる会計処理を行っておりましたが、IFRSでは石油及び天然ガスの開発井及び関連する生産設備に係る支出及び資産除去債務に対応する資産除去債務資産は石油・ガス資産(開発・生産資産)として認識し、生産開始後、確認埋蔵量及び推定埋蔵量の合計数量に基づいて、生産高比例法により減価償却しております。
(e)探鉱費
日本基準では契約形態に応じて異なる会計処理を行っておりましたが、IFRSでは石油及び天然ガスの探査及び評価に係る支出は成功成果法を用いて会計処理し、支出の一部を石油・ガス資産(探鉱・評価資産)として認識しております。
終わりに
我が国においてIFRSの任意適用が認められて10年以上が経過し、新たにIFRSの適用を公表し、本稿で取り上げた調整表を作成する企業の数は年間10社から15社程度で落ち着きを見せている。任意適用が認められた当初は、大手商社や製薬会社や輸送用機器、情報・通信など、IFRS任意適用日本企業の業種が比較的限られていたが、ここ1、2年は多種多様なサービス業や、本稿でも取り上げた鉱業、生命保険業などでも適用事例が見られるようになってきた。それにともなって、調整表で説明される項目も、のれんの非償却や有給休暇引当金の計上といった、どの業種の企業にも共通のおなじみの項目ばかりではなく、業種特有の会計処理の相違を説明したものが増えてきている。また、設立からまだ日が浅い、IFRSを任意に適用して上場したような企業においては、ストック・オプションの会計処理の取扱いの違いに言及するような事例も見られる。
また、国際会計基準審議会(IASB)は、2024年4月9日にIAS第1号「財務諸表の表示」を置き換えるIFRS第18号「財務諸表における表示及び開示」を公表した。この基準書の適用は2027年1月1日以降開始する事業年度であるため、まだ先であるが(早期適用は可能)、今後、「調整表」において、財務諸表の表示に関する我が国の基準とIFRS第18号との間の差異が説明される日が遠からず来るものと思われる。IFRS第18号の公表を受けて、我が国の財務諸表の表示や開示の方法が今後どのようになってゆくのか、IFRSとの間の相違点が残るのかどうかといった点についても、合わせて注目して見守りたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























