解説記事2024年10月14日 巻頭特集 PGM事件・東京地裁 令和6年9月27日判決(2024年10月14日号・№1047) ~組織再編成に係る行為計算否認規定の適用事案における初の納税者勝訴判決~
巻頭特集
詳細解説
~組織再編成に係る行為計算否認規定の適用事案における初の納税者勝訴判決~
PGM事件・東京地裁 令和6年9月27日判決
島田法律事務所 弁護士 井村 旭 (元東京国税局 国際調査審理官)
Ⅰ はじめに
令和6年9月27日、東京地方裁判所は、PGMグループのPGMプロパティーズに対する法人税法132条の2に基づく課税処分の適否が争われた訴訟において、PGMプロパティーズの主張を認め、処分を取り消す判決(以下「本判決」という。)を下した。本件は、税務当局の「伝家の宝刀」と呼ばれる法人税法132条の2適用事案ということもあり、審査請求の時点から、PGM事件と呼ばれ注目を集めていた。本件以前に法人税法132条の2に基づく課税処分が争われた事案としては、ヤフー・IDCF事件及びTPR事件があるが、いずれも下級審判決を含めて納税者が勝訴したものはなく、本判決は初の納税者勝訴判決である。
筆者はかつて、本誌において、法人税法132条の2に関する一連の課税事案を検討させていただいた経緯もあり(脚注1)、本判決についてもコメントの機会を頂戴した。本稿は、判決後間もない時期におけるものであることに鑑み、事案の概要及び裁判所の判断の要旨の紹介(後記Ⅱ・Ⅲ)に力点を置きつつも、後記Ⅳにおいて本判決の意義について若干の検討を加えたい。
なお、本稿中意見にわたる部分は筆者の個人的見解であり、筆者が現在所属し、又は過去に所属した組織の見解を示すものではない。
Ⅱ 事案の概要(図参照)
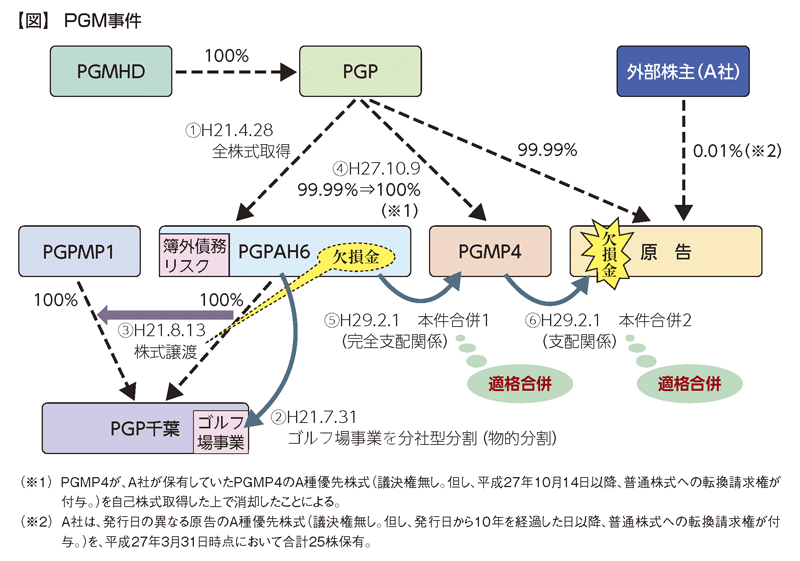
原告(PGMプロパティーズ株式会社)は、ゴルフ場の保有を主要な事業とする株式会社であって、平成16年12月頃から平成30年9月30日まではPGMホールディングス株式会社(以下「PGMHD」という。)を、同年10月1日以降はパシフィックゴルフマネージメント株式会社を持株会社とする企業グループ(以下「PGMグループ」という。)の構成法人の一つである。
①PGMグループのパシフィックゴルフプロパティーズ株式会社(以下「PGP」という。)は、平成21年4月28日、大手商社から、ゴルフ場運営会社であるPGPAH6株式会社(以下「PGPAH6」という。)の全株式を取得した。しかし、PGPAH6では元代表取締役の業務上横領事件等が発生しており、これに関連した債権者からの損害賠償債務等の簿外債務(以下「本件簿外債務」という。)が存在するリスクがあることから、②PGPは、平成21年7月31日、PGPAH6からゴルフ場経営及びこれに付帯し、又は関連する一切の事業(以下「本件ゴルフ場事業等」という。)だけを分社型分割(物的分割)で切り出し、新設子会社であるPGP千葉株式会社(以下「PGP千葉」という。)に承継させ、その対価としてPGP千葉の株式(以下「PGP千葉株式」という。)を取得し、PGPAH6(本件ゴルフ場事業等以外の事業)は、簿外債務の管理や債権者対応等のために存続することになった。その後、③PGPAH6は、平成21年8月13日、PGMグループのPGMプロパティーズ1株式会社(以下「PGMP1」という。)に、PGP千葉株式を全て譲渡(以下「本件株式譲渡」という。)し、この本件株式譲渡によって、PGPAH6には多額の株式譲渡損が生じ、その結果、PGPAH6は、平成22年3月期において、57億6984万7905円の欠損金(以下「本件未処理欠損金額」という。)を抱えることとなった。
平成27年3月31日時点において、PGPは、原告及びPGMプロパティーズ4株式会社(以下「PGMP4」という。)の発行済株式の99.99%を保有していたが、残りの各0.01%の発行済株式(原告のA種優先株式(議決権はないが、発行日から10年を経過した日以降、普通株式への転換請求権が付与されているもの。)及びPGMP4のA種優先株式(議決権はないが、平成27年10月14日以降、普通株式への転換請求権が付与されているもので、以下「本件PGMP4優先株式」という。))は、いずれもPGMグループに属さない外部株主(以下「A社」という。)が保有していた。
④PGMP4は、平成27年10月9日、A社から本件PGMP4優先株式を10万円で取得(以下「本件優先株式取得」という。)した上で消却した。これにより、PGPは、PGMP4の発行済株式の全部を保有することとなった。
その後、⑤平成29年2月1日、PGMP4を合併法人、PGPAH6を被合併法人とする適格吸収合併(以下「本件合併1」という。)、次いで⑥同日、原告を合併法人、PGMP4を被合併法人とする適格吸収合併(以下「本件合併2」といい、本件合併1と総称して、以下「本件各合併」という。)が行われた。
本件各合併の日の前日である平成29年1月31日時点で、PGMP4及びPGPAH6の発行済株式の全部をPGPが保有し、また、原告の発行済株式のうち99.99%をPGPが保有していたため、本件合併1は、完全支配関係(法人税法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)2条12号の7の6)のある法人間で行われる合併(同法2条12号の8イ)として、本件合併2は、支配関係(同条12号の7の5)のある法人間で行われる合併(同法2条12号の8ロ)として従業者引継要件及び事業継続要件を充足する形で、それぞれ適格合併とされた。
原告は、適格合併が行われた場合に適用される法人税法57条2項及び81条の9第2項2号イ(以下「法人税法57条2項等」という。)の各規定により、PGPAH6の有する本件未処理欠損金額を原告の連結欠損金額とみなして、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結事業年度(以下「本件連結事業年度」という。)の法人税の連結確定申告及び平成28年4月1日から平成29年3月31日までの課税事業年度(以下「本件課税事業年度」という。)の地方法人税の確定申告をしたところ、東京上野税務署長が、法人税法132条の2の規定により、本件未処理欠損金額を原告の連結欠損金額とみなすことを認めず、本件連結事業年度の法人税の更正処分をするとともに、これを前提に本件連結事業年度の法人税の過少申告加算税賦課決定処分並びに本件課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分(これらの各処分を総称して、以下「本件各更正処分等」という。)をした。
原告は、本件各更正処分等の取消しを求めて審査請求を行ったが、いずれも棄却されたため、国を被告として、東京地方裁判所に訴えを提起した。
本件の争点は、本件各更正処分等の適法性であり、具体的には、本件各合併が法人税法132条の2にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(以下「不当性要件」という。)に該当するか否かである。
Ⅲ 裁判所の判断の要旨
請求認容。
1 不当性要件に係る判断枠組み
「法人税法132条の2……にいう「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」とは、法人の行為又は計算が組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用することにより法人税の負担を減少させるものであることをいうと解すべきであり、その濫用の有無の判断に当たっては、①当該法人の行為又は計算が、通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど、不自然なものであるかどうか、②税負担の減少以外にそのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか等の事情を考慮した上で、当該行為又は計算が、組織再編成を利用して税負担を減少させることを意図したものであって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるもの又は免れるものと認められるか否かという観点から判断するのが相当である(最高裁平成28年判決(引用者注:最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(ヤフー事件最判))等参照)。」
「株式会社が合理的な事業目的のある組織再編成を行うに当たり、通常は想定されない手順や方法ではなく、実態と乖離した形式を作出するものでもない、不自然性の全く認められない複数の手順や方法の中から最も税負担の少ないものを採ったとしても、そのことから直ちに組織再編税制に係る各規定を租税回避の手段として濫用したものということはできない……。」
2 組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的
「平成13年度税制改正により導入された組織再編税制の基本的な考え方は、実態に合った課税を行うという観点から、原則として、移転資産等についてその譲渡損益の計上を求めつつ、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、この考え方に基づき、組織再編成において、移転資産に対する支配が再編成後も継続していると認められるものについては、経済実態に実質的な変更がないことから、移転資産の譲渡損益の計上を繰り延べることとしたものである。……組織再編成に伴う未処理欠損金額の取扱いについても、基本的に、移転資産等の譲渡損益に係る取扱いに合わせて従前の課税関係を継続させることとするか否かを決めることとされて……いる。」
「このように、小委員会(引用者注:税制調査会法人課税小委員会)において示された組織再編税制の基本的な考え方は、飽くまで、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、この観点から、移転資産等に対する支配が組織再編成後も継続しているものについて、譲渡損益の計上を繰り延べるというものであって、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からにすぎない。」
「以上によれば、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の趣旨及び目的は、組織再編成により資産を移転する前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるというものであり、経済実態に実質的な変更がないか否かを判断するなどのために、法人税法2条12号の8及びこれを受けた法人税法施行令4条の3等において、適格合併と判定するための具体的な要件が定められているものと認められる。」
「租税法律主義の原則に照らすと、租税法規はみだりに規定の文言を離れて解釈したり拡張適用したりすべきではない……。これは、租税法規の解釈に関する我が国の伝統的な通説及び確立した判例であって、組織再編税制も、これを踏まえて立法されたものと認められる。……法人税法及びこれを受けた法人税法施行令の規定上、支配関係適格合併及び共同事業適格合併においては、従業者引継要件及び事業継続要件等が必要とされているのに対し、完全支配関係適格合併については、これら従業者引継要件及び事業継続要件等のいずれについても必要とされていない。また、法57条2項等の規定をみても、完全支配関係のある法人間の合併について、事業の継続がない場合には一律に適用がない旨をうかがわせる文言はない。」
「これらの事情によれば、組織再編税制の立法に当たっては、……完全支配関係があり対価要件を満たす法人間の合併の場合には、基本的に、合併の前後で経済実態に実質的な変更がなく、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないことから、支配関係適格合併及び共同事業適格合併とは異なる、より緩和された適格合併の要件があえて定められ、従業員(原文ママ。引用者注:「従業者」の誤記と思われる。)引継要件及び事業継続要件が必要とされなかったと解するのが相当であ」る。
「したがって、完全支配関係適格合併の場合において、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」が法人税法57条2項等の適用の「前提」となっているとか、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」がない完全支配関係適格合併に上記規定を適用することはその本来の趣旨及び目的に反するなどと解することはできない。」
3 本件における不当性要件該当性の検討
(1)PGMグループのビジネスモデル等
裁判所は、不当性要件該当性の検討に先立ち、以下の事実を認定している。
「PGMグループにおいては、経営危機に陥るなどしたゴルフ場運営法人を買収して規模を拡大させ、多数のゴルフ場を本部で集中管理し、ゴルフ用品等を一括購入するなどしてスケールメリットを追求するとともに、買収により増え続ける子会社の数を合併により削減することにより、経営の合理化・効率化を追求するというビジネスモデル(引用者注:以下「本件ビジネスモデル」という。)……の下、事業を営んでいる。なお、ここでいう経営の合理化・効率化とは、単に、一括購入による調達費用の削減や税務申告コストの削減等にとどまらず、経営に係る意思決定や監査の迅速化・合理化・効率化を包含するものである。」
「PGMグループは、本件ビジネスモデルに基づき、本件各合併の10年以上前から、買収によってPGPの子会社の数がある程度増える都度、グループ内での吸収合併を繰り返し、最終的には原告にこれらの会社を吸収合併させることによって、ゴルフ場の保有機能を原告に集約させつつ、PGPの子会社の数を削減するための合併を繰り返していた。このような合併に当たり、ゴルフ場事業を営んでいない法人も合併の対象となったほか、合併に伴って被合併法人から合併法人へ未処理欠損金額が引き継がれない合併も複数あった。」
「平成18年から令和元年までの約15年間で、PGMグループの経理・財務部員及び法人数は、それぞれ3分の1程度に減少し、また、同グループにおける監査報酬・税理士報酬の累計削減金額は、上記約15年間で7734万円であった。」
(2)PGPAH6を合併することについて
「PGMグループにおいて、PGPAH6を同グループ内の既存法人に吸収合併することとしたのは、本件簿外債務に係る新たな債権者が現れる可能性が低く、本件簿外債務に係る債権はおおむね時効により消滅しており、本件簿外債務に係るリスクが顕在化する可能性は低減していると評価し、PGPAH6を本件ビジネスモデルに基づく組織再編成の対象から除外して残存させておくべき特段の必要性はないと判断したことによるものと認められる。」
「PGMグループにおいては、本件ビジネスモデルの下、繰り返し合併を行い、子会社の数を削減することにより、経営に係る意思決定や監査の迅速化等を包む経営の合理化・効率化を継続的に追求しており、これにより大幅な費用の削減が実現されていること……からすると、平成29年に行われたPGMグループの組織再編成において、前記……のような判断の下、PGPAH6を残存させず、PGMグループ内の既存法人に吸収合併することには、合理的な理由となる事業目的が十分に存在するといえる上、何ら不自然なものではない。」
(3)本件各合併に係るスキームについて
ア 本件各合併が二段階で行われていることについて
「会社法上、吸収合併は、単一の存続会社と単一の消滅会社との間で行われるものと整理されていることから、2社以上の消滅会社と単一の存続会社との間で一体のものとして吸収合併を行う場合であっても、各消滅会社と存続会社との間で各別に吸収合併が行われるものと整理され、吸収合併契約も消滅会社ごとに各別のものとして存在することとなっており、このような複数の吸収合併を実質的に一体のものとして行うため、実務上、同日付けで複数の吸収合併を実施する場合には、例えば、第一合併の効力発生を停止条件として第二合併を実行するなど、各吸収合併に順序を付し、その効力発生に条件を付けるという方法が採られている。」
「そして、課税実務上も、このような整理及び合併の実務を踏まえ、三社合併が行われた場合、適格合併に当たるか否かの判定は、当該三社合併に係る個々の合併ごとに行うこととされ、三社合併に係る個々の合併に順序が付されている場合には、私法上は原則としてその順序に応じ個々の合併の効力が生ずることとなるから、税制上もその順序どおり合併が行われたものとして、適格合併に当たるか否かの判定を行うこととされている……。」
「したがって、本件各合併が二段階で行われたからといって、必ずしも、通常は想定されない手順や方法が採られたということはできない。」
「しかも、……①本件各合併のスキームを採れば、PGPに対しては、PGMP4の1社分の株式についてのみ、原告の株式を割当て交付すれば足りるのに対し、②仮に、本件合併1を経ずに、PGPAH6及びPGMP4をそれぞれ被合併法人とし、原告を合併法人とする各合併を実施した場合には、原告とPGPAH6との合併比率及び原告とPGMP4との合併比率をそれぞれ計算した上で、PGPに対してPGMP4とPGPAH6の2社分の株式について、原告の株式を割り当てることが必要となると認められ、この点において、一定の事務の煩雑さがあることは否めない……。」
「これらのことからすると、原告が直接PGPHA6(原文ママ。引用者注:「PGPAH6」の誤記と思われる。以下同じ。)を吸収合併するのではなく、PGMP4がPGPHA6(原文ママ)を吸収合併した上で、原告がPGMP4を吸収合併したのは、客観的にみて、効率的な事務の遂行に資するものであったと評価することができる。」
「したがって、本件各合併のスキームについて、通常は想定されない手順や方法を採るものであるとか、通常(本来)とは異なり、あえてう遠な手順や方法を採るものであるなどと評価することはできない。……むしろ、一般に採られている合理的な手順・方法の一つと認められる。」
「また、PGPAH6とPGMP4はいずれもPGPの完全子会社であり、完全支配関係があるから、本件合併1は、完全支配適格合併(原文ママ。引用者注:「完全支配関係適格合併」の誤記と思われる。)に当たると認められるのであって、そこに実態と乖離した形式の作出はみられない。被告の主張のうち、PGPAH6からPGMP4に事業が引き継がれないこと(ひいてはPGPAH6から原告に事業が引き継がれないこと)を捉えて本件各合併につき実態と乖離した適格合併の形式を作出した旨をいう部分は、完全支配関係適格合併の場合において、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」が法人税法57条2項等の適用の「前提」となっているものではない上……、PGPAH6の合併には合理的な事業目的が存在するのであり……、かつ、本件合併1の前後で経済実態に実質的な変更がないことからすると、採用することができない。」
「しかも、本件各合併のスキームは、①課税上のメリットがなく、かつ、事務効率化のメリットもない(事務の煩雑さがある)手順・方法(原告が直接PGPHA6(原文ママ)を吸収合併する場合)と、②課税上のメリットがあり、かつ、事務効率化のメリットもある(事務の煩雑さが生じない)手順・方法(本件各合併の場合)のうち、後者を採用したというものであるから、事務効率化のメリットを数値化したり、課税上のメリットと事務効率化のメリットの大小や目的の主従関係を比較したりして検討するまでもなく、営利企業にとって合理的な経済活動と評価できるものであって、何ら不自然なものではない。」
イ 本件各合併に先立ち、PGMP4をPGPの完全子会社としたことについて
「PGMP4は、適法な手続に従って本件PGMP4優先株式を取得……及び消却することにより、PGPの完全子会社となったものであって、何らかの仮装をしたり虚偽の概観を作出したりしたものでないのはもとより、それ自体、通常は想定されない手順や方法に基づくものでも、実態とは乖離した形式を作出したものでもなく、何ら不自然なものではない。」
また、PGMHDは、資金調達のため、平成26年2月25日付けで銀行との間でシンジケートローン契約(以下「本件シンジケートローン契約」という。)を締結していたが、本件シンジケートローン契約においては、PGMHDが、同契約の締結日以降、同契約上の全ての債務の履行を完了するまでの間、契約締結日現在における連結子会社に対する直接又は間接の議決権割合を100%に維持することを確約するとの条項(以下「本件コベナンツ条項」という。)が付与されていた。この点を踏まえ、裁判所は以下のとおり判示している。
「A社が本件PGMP4優先株式を保有しているままでは、平成27年10月14日以降……、A社がPGMP4に対し、その取得を請求できる権利を行使し、その取得と引換えに普通株式がA社に交付される結果、本件コベナンツ条項に違反する状態が生じ、PGMHDが本件シンジケートローン契約上の期限の利益を失うというリスク……が存在していた。そうすると、本件優先株式取得等は、かかるリスクを抜本的に解消するための合理的な方法であったと認められる……のであって、合理的な理由となる事業目的が存在したと認められる。」
ウ 原告における税務上の影響の考慮について
「PGMグループが本件各合併のスキームを採用するに当たり、本件未処理欠損金額の原告への引継ぎを重視したことは否定し難い……。」
「しかしながら、……株式会社が一定規模以上の取引をするに当たり、税務上の影響を全く考慮しないことは考え難く、そのような考慮をすることはむしろ当然」である。
「本件各合併に係るスキームは、通常は想定されない手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなどといった、不自然なものでは全くないのであるから、そのスキームの採用に当たり、本件未処理欠損金額の原告への引継ぎを重視したとしても、このことをもって、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものということはできない……。」
(4)まとめ
「以上を総合すると、PGMP4がPGPAH6を吸収合併し(本件合併1)、その効力発生を停止条件として、原告がPGMP4らを吸収合併する(本件合併2)という本件各合併について、その各部分を個別に見た場合においても、その全体を見た場合においても、「通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づくもの」でも「実態とは乖離した形式を作出したりするもの」でもなく、何ら不自然なものとはいえないし、かかるスキームを採用して合併を行うことの「合理的な理由となる事業目的その他の事由」が存在することからすると、組織再編税制に係る各規定の本来の趣旨及び目的から逸脱する態様でその適用を受けるものとは認められない。」
4 小 括
「したがって、本件各合併は、組織再編税制に係る法人税法57条2項等の各規定を租税回避の手段として濫用することによって法人税の負担を減少させるものとはいえず、「法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるもの」(同法132条の2)に当たるということはできないから、これに該当することを前提に行われた本件各更正処分等は、いずれも違法である。」
Ⅳ 検 討
1 本判決の意義
法人税法132条の2については、ヤフー事件最判(脚注2)及びIDCF事件最判(脚注3)が、法文上「法人税の負担を不当に減少させる結果となるもの」と表現される不当性要件に関する判断基準を明らかにしたが、その判断基準の個別事案への具体的な適用については不明確さが残る状況にあった。そのような不明確さを生じさせていた一つの要因が、上記最判の後に登場したTPR事件東京高判(脚注4)の「完全支配関係にある法人間の適格合併……においても、被合併法人から移転した事業が継続することを要するものと解するのが相当である」といった判示であったが、本判決は、前記Ⅲ・2において、「完全支配関係適格合併の場合において、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」が法人税法57条2項等の適用の「前提」となっているとか、「合併による事業の移転及び合併後の事業の継続」がない完全支配関係適格合併に上記規定を適用することはその本来の趣旨及び目的に反するなどと解することはできない。」等と判示し、TPR事件東京高判の上記判示とは決別しているように思われることに最大の意義がある(この点については下記2において詳述する。)。
また、不当性要件については、①「当該法人の行為又は計算が……不自然なものであるかどうか」、及び②「そのような行為又は計算を行うことの合理的な理由となる事業目的その他の事由が存在するかどうか」等の事情を考慮することが必須とされているところ(脚注5)、その当てはめが、法人税法132条の2適用の適否の結論を左右することになる。本判決は、法人税法132条の2に基づく課税処分に対する初の取消判決であるところ、裁判所が、法人税法132条の2の適用を否定する文脈としては初めて上記の必須考慮事情の具体的当てはめを示しており、この点は、今後納税者が法人税法132条の2の適用可能性を検討するに際して参考になるといえる(この点については下記3において詳述する)。
2 法人税法57条2項等の趣旨・目的について
本判決は、ヤフー事件最判が示した不当性要件の判断基準である制度濫用基準に従うことを前記Ⅲ・1において示している。制度濫用基準は、組織再編税制全体やその個別規定の趣旨・目的との関係において当事者がこれを逸脱しているかについて判断を行うという考え方であるところ、本判決は、続く前記Ⅲ・2において、適格合併が行われた場合における未処理欠損金の取扱いを定めた法人税法57条2項等の趣旨・目的の検討を行っている。
法人税法57条2項等の趣旨・目的の検討に際して、本判決が主に依拠しているのは、税制調査会法人課税小委員会の「会社分割・合併等の企業組織再編成に係る税制の基本的考え方」(脚注6)(以下「基本的考え方」という。)である。もっとも、この基本的考え方は、「企業グループ内の組織再編成」(第二・一・1)において、「組織再編成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別する観点から、資産の移転が独立した事業単位で行われること、組織再編成後も移転した事業が継続することを要件とすることが必要である。」との考え方を示しており、この部分を完全支配関係適格合併の法定された要件との関係でどのように位置づけるかが、判断の分かれ目となっている。
すなわち、TPR事件東京高判に依拠したと思われる国側の主張は、組織再編税制は、組織再編成による資産の移転を個別の資産の売買取引と区別するために、資産の移転が独立した事業単位で行われること及び組織再編成後も移転した事業が継続していることを想定しているものと解され、これは完全支配関係適格合併においても当てはまり、事業継続要件等の要件をあえて設けてはいないものの、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提にされているというものであった。
これに対し、本判決は、基本的考え方において示されている組織再編税制の趣旨の根幹は、組織再編成の前後で経済実態に実質的な変更がない場合には、その譲渡損益の計上を繰り延べて従前の課税関係を継続させるという点にあることや、基本的考え方が上記の引用箇所に続け、「ただし、完全に一体と考えられる持分割合の極めて高い法人間で行う組織再編成については、これらの要件を緩和することも考えられる。」と述べていることといった、基本的考え方の全体の文脈の分析を通じて、「資産の移転が独立した事業単位で行われること」と「組織再編成後も移転した事業が継続すること」が必要とされたのは、「個別の資産の売買取引と区別する観点」からにすぎないと解釈した。また、租税法律主義に照らした文理解釈の原則(脚注7)について、「租税法規の解釈に関する我が国の伝統的な通説及び確立した判例であって、組織再編税制も、これを踏まえて立法されたものと認められる。」として、その重要性を説くとともに、組織再編税制にもその適用がある旨を確認することで、完全支配関係適格合併において、事業継続要件等の要件が求められていないことの意味を重視する姿勢を示しているといえる。これらの事情等をもとに、完全支配関係適格合併については、個別の資産の売買取引との区別も問題とならないことから、支配関係適格合併及び共同事業適格合併とは異なる、より緩和された適格合併の要件があえて定められ、従業者引継要件及び事業継続要件が必要とされなかったと解するのが相当として、合併による事業の移転及び合併後の事業の継続が当然の前提にされているという国の主張を理由のないものと判断した。
TPR事件東京高判が示した完全支配関係適格合併においても事業の継続が求められるとの考え方については、租税法学界及び実務界において批判的な論調が大半を占めていたと思われ(脚注8)、本判決がこの考え方を否定したことについては、筆者も賛成の立場である。特に、不当性要件判断の必須の考慮事情の一つである「行為・計算の不自然性」については、「通常は想定されない組織再編成の手順や方法に基づいたり、実態とは乖離した形式を作出したりするなど」といった該当性が肯定される場合の例示はあるが、「不自然」という概念の外縁は必ずしも明確ではない。TPR事件東京高判の考え方は、完全支配関係適格合併において事業の継続が認められないことを、「不自然性」を基礎づける重要な要素と位置付けるものであり、「不自然性」という概念の外縁を、法令上の根拠なく不当に広げるものであったと思われる。
但し、本判決が、法人税法57条2項等の趣旨・目的を検討し、完全支配関係適格合併における「事業の継続」必要論を否定するに際して、基本的考え方の個別の記載を、その全体の文脈等にも照らして、いわば法令のように解釈し、重視しているように思われる点については、違和感が全くないわけではない。
確かに、ヤフー事件最判の調査官解説では、組織再編税制に係る規定の趣旨・目的の把握に際しては、基本的考え方や国会の議事録等を確認すべき旨が述べられており(脚注9)、基本的考え方を確認すること自体は否定されるべきではない。しかしながら、あくまで法令そのものではない基本的考え方の個別の記載について解釈を行い、そこから組織再編税制に係る個別規定の趣旨・目的を把握するという手法は、納税者の立場から見ると、個別規定の趣旨・目的の把握を困難にさせ、その予測可能性を害する恐れがあるように思われる(脚注10)。また、(紙幅の都合上、前記Ⅲにおいては引用していないものの、)本判決は、原告が証拠提出した、平成13年度税制改正により組織再編税制が導入された際に大蔵省(財務省)主税局課長補佐として立法作業に関与したOB税理士が作成した意見書も理論の補強材料とされているように思われ、この点も同様に、納税者の予測可能性という観点からは疑問が残る点である(脚注11)。
このような観点からすると、筆者としては、本判決が、完全支配関係適格合併における「事業の継続」必要論を否定した判示のうち、租税法律主義に照らした文理解釈の原則から完全支配関係適格合併において、事業継続要件等の要件が求められていないことの意味を重視する姿勢を示し、結論を導いている点を主に支持したい。
3 不当性要件の当てはめについて
本件で不当性要件の該当性が検討された行為は「本件各合併」であるが、不当性要件における必須の考慮事情の充足の有無の判断にあたっては、①そもそも未処理欠損金の引継ぎを目的としたもので事業目的を欠くものではないか(前記Ⅲ・3(1)、同(2)、同(3)ウ)、②二段階合併というスキームは、通常は想定されない手順や方法、又は実態とは乖離した適格合併の形式を作出するもの(適格作り)であり、不自然ではないか(前記Ⅲ・3(3)ア)、③本件各合併に先立ち、PGMP4をPGPの完全子会社としたことは、通常は想定されない手順や方法、又は実態とは乖離した適格合併の形式を作出するもの(適格作り)であり、不自然ではないか(前記Ⅲ・3(3)イ)といった点が主に検討されている。
まず、不当性要件における一つ目の必須の考慮事情である「行為・計算の不自然性」との関係で問題となるのは上記②及び③である。
上記②については、本件の裁決(脚注12)に関連して、三社合併について二段階の形を取ることは、一回的に行う三社合併との比較において、会社法の実務としても、国税庁の文書回答事例における取扱い(脚注13)としても、不自然ではない旨の見解が実務界から示されており(脚注14)、本判決は、これらの見解と概ね同様の見解を採用したと考えられる。その判断に際し、本判決が、合併比率の算定や合併対価としての株式の割当てといった具体的な事務負担に触れることで、二段階合併の事務効率化のメリットを客観的に評価している点、また、(本件ではその検討をするまでもないということではあるものの、)事務効率化のメリットの数値化や、課税上のメリットと事務効率化のメリットの大小や目的の主従関係を比較するといった方法に触れている点は、今後納税者が、同じ目的を達成する複数のスキームが考えられる際、当該スキームを選択することが不自然ではないと判断し、その判断を記録・証拠化するに際して参考になる視点と思われる。
上記③については、PGPによるPGMP4の完全子会社化が、いわゆる「適格づくり」として税務上の考慮から行われたというよりも、本件シンジケートローン契約における本件コベナンツ条項に違反するリスクを抜本的に解消するという事業上の目的を主たる目的として行われたという事実認定によって、不自然性の否定という判断が導かれている。かかる事実認定に際しては、完全子会社化と本件各合併との時間的間隔、PGMグループにおける組織再編成に係る一連の検討の時期、本件シンジケートローン契約の締結時期、A社が保有する本件PGMP4優先株式の転換請求権の発生時期と完全子会社化の時期との関係といった、各事実の時間的関係性に照らした判断が重視されている。
次に、不当性要件における二つ目の必須の考慮事情である「そのような行為・計算を行うことの合理的な理由となる事業目的等の有無」との関係で問題となるのは上記①である。
上記①の判断については、本件各合併に係る事業目的を、原告の属するPGMグループのビジネスモデルの文脈において捉えている点が注目される。すなわち、本件各合併を個別に捉えてその事業目的をミクロ的視点で分析するのではなく、PGMグループのビジネスモデルというマクロ的視点から分析しているのである。そして、そのPGMグループのビジネスモデルについては、本件各合併以前から長期に亘り実施されてきたもので、実際に人員・法人・経費等の削減の効果をもたらし、経営に係る意思決定や経営の合理化・効率化を実現していることが客観的に認められたことで、そのビジネスモデルの一環として実施されている本件各合併は十分な事業目的を有する行為と評価されることに繋がっている。そして、そのような行為を営利法人としての株式会社が実行するに際し、税負担について考慮することはむしろ当然であって、そのことは不当性要件の充足を基礎づけないとされる。
本判決の上記の考え方は、同じく納税者の勝訴判決であるユニバーサルミュージック事件最判(脚注15)が、「本件借入れ」を「企業グループにおける組織再編成に係る一連の取引の一環」として行ったものとして位置付けて、法人税法132条1項の不当性要件の判断を行い、その一連の取引には、税負担を減少させることの考慮があったことを認めつつも、その他に認められる事業目的に照らせば、不当性要件を満たさないとした考え方と一定の類似性を見出すことができると考えられる。
このようなユニバーサルミュージック事件最判及び本判決の考え方に照らせば、納税者としては、不当性要件の該当性の検討に際し、問題となり得る行為を個別に捉えるのではなく、その前後の行為を含む目的の共通する一連の行為の中で問題となり得る行為を捉え、その行為の事業目的等を整理することが、納税者にとって有利な結論を導くことに繋がることを示唆しているといえる。
Ⅴ 最後に
本判決は、第一審判決であり、国としては控訴を行うことが予想されるが、TPR事件東京高判の「事業の継続」必要論を否定し、また、法人税法132条の2適用事案に関する初の納税者勝訴判決ということでその意義は大きい。加えて、本判決は、同じくTPR事件東京高判の「事業の継続」必要論を背景に課税処分が行われ、現在訴訟継続中とされる二つの事案(脚注16)にも一定の影響を及ぼす可能性があること、更に、本判決が、「株式会社が一定規模以上の取引をするに当たり、税務上の影響を全く考慮しないことは考え難く、そのような考慮をすることはむしろ当然」と述べている点は、現在、行為計算否認規定の適用検討事案の調査に当たる税務当局への牽制を含むようにも思われることからすると、その意義は更に大きなものとなる可能性がある。
脚注
1 佐藤修二=井村旭「対談・行為計算否認を中心とした東京国税局における調査の最新トレンド」本誌第1023号4頁。
2 最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁。
3 最判平成28年2月29日民集70巻2号470頁。
4 東京高判令和元年12月11日金融・商事判例1595号8頁。
5 徳地淳=林史高「判解」最判解民事篇平成28年度84頁(該当頁109頁)。
6 https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/1996-2009/gijiroku/soukai/2000/a02kai_2.html
7 最判平成22年3月2日民集64巻2号420頁(ホステス源泉徴収事件)等参照。
8 例えば、吉村政穂「繰越欠損金の引継ぎと組織再編成に係る行為計算否認規定の適用」税務事例研究第177号1頁、渡辺徹也『スタンダード法人税法〔第3版〕』(弘文堂、2023)307~308頁、谷口勢津夫『税法基本判例Ⅰ』(清文社、2023)239頁、片平享介「判批」本誌第811号、平川雄士「立法趣旨論再考−最判令3.3.11から近時の法132条の2による否認事例を考える−」租税研究2021年10月号109頁等。但し、TPR事件東京高判の判示の適用場面を限定しようとする見解として、伊藤剛志「適格合併による未処理欠損金の引継ぎと法人税法132条の2~TPR事件東京高裁判決の合理的解釈の試み~」租税研究2023年12月号132頁も参照。
9 徳地=林・前掲(注5)113頁。
10 現に、TPR事件東京高判と本判決は、いずれも基本的考え方に依拠して法人税法57条2項の趣旨・目的を把握しているが、裁判所においても、完全支配関係適格合併において事業の継続が求められるか否かという点に関し、結論を異にしているのであり、これは納税者の予測可能性を害する状態にあることを示している。
11 TPR事件東京地判(令和元年6月27日判タ1486号72頁)及び東京高判について、このような指摘をするものとして、吉村・前掲(注8)8~14頁参照。
12 令2年11月2日裁決(東裁(法)令2第30号)。なお、裁決の内容については、佐藤=井村・前掲(注1)16~18頁を参照。
13 平成21年1月27日付け平成21・01・23経局第1号「三社合併における適格判定について(照会)」に対する国税庁回答。
14 太田洋=伊藤剛志『企業取引と税務否認の実務~税務否認を巡る重要裁判例の分析~〔第2版〕』(大蔵財務協会、2022)176~177頁等。
15 最判令和4年4月21日民集76巻4号480頁。
16 令和4年8月19日裁決(大裁(法・諸)令4第5号)及び令和5年3月23日裁決(東裁(法)令4第101号)に係る事案であり、事案の詳細については、佐藤=井村・前掲(注1)19~22頁を参照。
井村 旭 (いむら あきら)
2012年 慶應義塾大学法学部法律学科中退(飛び級)、2015年 同大学大学院法務研究科(法科大学院)修了、2016年 弁護士登録。2021年から23年まで東京国税局(調査第一部調査審理課 国際調査審理官)にて勤務し、現在、島田法律事務所に所属。
税務当局対応を含む税務案件、税賠案件、M&A、一般企業法務、争訟等に従事。
近時の著作として、「重加算税における『納税者』要件の検討」(東京税理士界2024年6月号・第809号)、「税務調査における意見書~課税庁を説得するための内容とは」(税務弘報2024年7月号)、「伝家の宝刀による斬り捨て回避の指針~ヤフー事件」(ビジネス法務2024年8月号)(共著)等。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























