解説記事2024年10月28日 ニュース特集 施行間近のフリーランス法、一人税理士等の「士業」も対象(2024年10月28日号・№1048)
ニュース特集
令和6年11月1日以後に締結した取引が対象
施行間近のフリーランス法、一人税理士等の「士業」も対象
いわゆるフリーランス法が令和6年11月1日から施行される。税理士などの「士業」にとっては関係のない話にも思われるが、同法のフリーランスには業種の限定はなく、個人であって従業員を使用していない税理士等であれば、同法の適用対象となるので留意したい。一人税理士に業務委託を行うクライアントについては、書面等による取引条件の明示や60日以内のできる限り短い期間での報酬の支払いなどが求められる。逆に、税理士事務所などが個人事業者や一人法人などに業務委託を行う場合にもフリーランス法の対象となる。フリーランス法に違反し、所管省庁の勧告に従わない場合には、50万円以下の罰金に処せられることもあるので気をつけたい。今回の特集では、施行が間近に迫ったフリーランス法の概要を紹介することとする。
フリーランスに業種の限定なし
フリーランス法とは、正式には「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」と呼ばれる法律のこと。令和5年4月28日に国会で成立し、同年5月12日に公布。令和6年11月1日から施行されることになった。
以前にも増して働き方の多様化が進み、フリーランスという働き方も普及しているが、最近では、デジタル社会の進展に伴い、ギグワーカーなど、新しいフリーランスの働き方も増えてきているようだ。フリーランスが増える中、問題となっているのが報酬の不払いや支払遅延などのトラブルである。一人の個人として受注業務を受けるフリーランスは、組織である発注事業者から業務委託を受ける場合において、取引上、弱い立場に置かれることが多いからだ。
このような状況を受け、フリーランス法は、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引の適正化と就業環境の整備を図ることを目的として創設されたものである。以下、同法の概要についてみてみることにしよう。
対象は事業者間取引
まず、フリーランス法は、従業員を使用せず、一人の「個人」としての業務委託を受ける「特定受託事業者」と、従業員を使用して「組織」として業務委託をする「特定業務委託事業者」との間の業務委託に係る取引に適用される。「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供を委託する行為のこと。事業者間(BtoB)における委託取引が対象であるため、一般消費者からの委託は対象外であり、また、物品等の「売買」についても対象外となる。
なお、「従業員を使用」とは、週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいう。このため、仮に従業員を雇っていても同要件を満たさない従業員であれば「特定受託事業者」に該当し、フリーランス法の適用対象となる(図表1参照)。
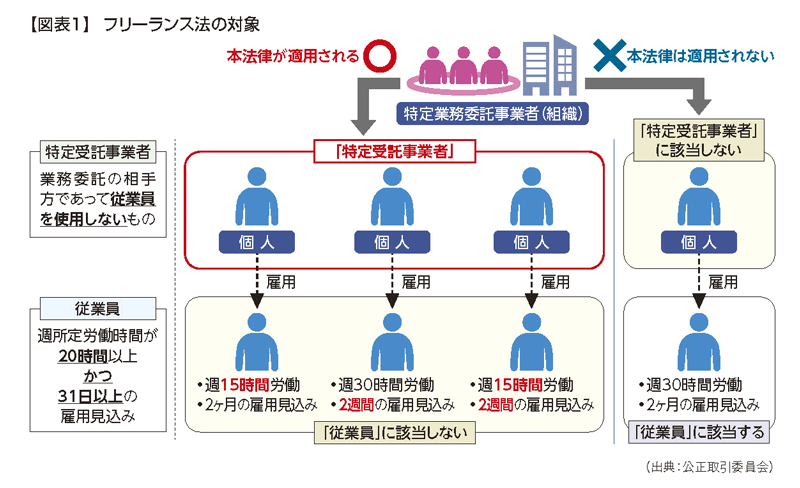
同居親族は「従業員」に該当せず
また、「特定受託事業者」には業種の限定はなく、税理士や弁護士といった「士業」であったとしても、①個人であって、従業員を使用しないもの、②法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準する者)がなく、かつ、従業員を使用しないもののいずれかに該当するものであれば、「特定受託事業者」に該当することになる。
なお、同居親族(居住と生計が同一の親族)のみを使用している場合には、「従業員を使用」していることにはならない。事務職員として同居親族を税法上の青色事業専従者として従事させているケースもあると思われるが、この場合は従業員を使用していることにはならず、一人税理士や個人事業者等はフリーランス法の適用対象ということになる。
執行役員等はフリーランス法の適用対象外
会社によっては、会社法上の役員ではないものの、執行役員を設置しているところがあるが、会社と執行役員との関係は、業務委託契約となっていることが多いようだ。この場合、フリーランス法の対象となるのか疑義が生じるところだが、公正取引委員会によれば、株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、委任型の執行役員との契約関係は、会社内部における関係にすぎず、これらのものは会社にとっての「他の事業者」とはいえないため、フリーランス法上の「業務委託」には該当しないとしている。
発注側は取引条件の明示等が必要に
次に規制内容だが、発注側の従業員の有無や業務委託期間でその内容が異なるものの(図表2参照)、すべての事業者に共通するのは取引条件の明示だ。個人に業務委託する場合には、従業員の有無を問わず、すべての事業者に対して書面等による取引条件の明示の義務が求められる。個人事業者や一人社長(法人)であっても該当するので留意したい。
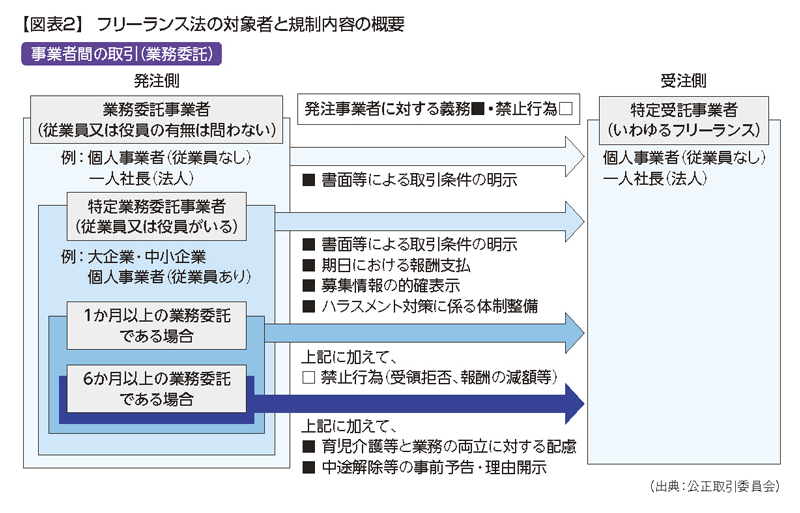
また、特定業務委託事業者(従業員あり)に対しては、書面等による取引条件の明示に加え、期日における報酬支払、募集情報の的確表示、ハラスメント対策の義務を課しており、さらに1か月以上の業務委託に関しては、①受領拒否、②報酬の減額、③返品、④買いたたき、⑤購入・利用強制、⑥不当な経済上の利益の提供要請、⑦不当な給付内容の変更及び不当なやり直しが禁止される。また、6か月以上の業務委託については、育児介護等と業務の両立に対する配慮や、中途解除等の事前予告・理由開示が求められる。
なお、フリーランス法の適用対象となる取引は令和6年11月1日以後に締結したものからとなる。したがって、既存の契約については対象外となり、契約更新時に改めてフリーランス法が適用されることになる。
命令違反の場合は50万円以下の罰金
フリーランス法に違反する事実がある場合には、フリーランスは、所管省庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)に対しその旨を申し出ることができ、所管省庁は、申出の内容に応じ、報告徴収や立入検査を行い、指導・助言のほか、勧告を行うことになる。勧告に従わなければ、命令・公表が行われ、命令違反の場合は50万円以下の罰金となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























