解説記事2024年10月28日 税務マエストロ お問合せの多いご質問(Part5)(2024年10月28日号・№1048)
税務マエストロ
お問合せの多いご質問(Part5)
#303
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
毎月更新されていた「お問合せの多いご質問」であるが、国税庁への問合せも一段落したのであろうか、8月と9月は新問の追加がなかったようだ。今回は、令和6年6月26日の更新で追加された問 、7月26日の更新で追加された問
、7月26日の更新で追加された問 と問
と問 の内容について検討する。
の内容について検討する。
なお、国税庁のインボイスQ&Aに追加された問も含め、「お問合せの多いご質問」のうち、 ~
~ までの問は本誌No.1033(2024.7.1号)にて解説しているので参照されたい。
までの問は本誌No.1033(2024.7.1号)にて解説しているので参照されたい。
ところで、(個人的な感想ではあるが)問 (フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)の【答】を読んで理解(納得)できた人はどの程度いるのだろうか……。
(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)の【答】を読んで理解(納得)できた人はどの程度いるのだろうか……。
筆者は【答】に書かれている日本語が消化できず、なかなか解説が執筆できなかった。
こういった事情もあり、問 の<ポイント>に記載する解説は決して完全なものではない。ただ、筆者なりに頑張って可能な限りわかり易く整理したつもりである。読者の皆様に、多少なりとも参考になれば幸いである。
の<ポイント>に記載する解説は決して完全なものではない。ただ、筆者なりに頑張って可能な限りわかり易く整理したつもりである。読者の皆様に、多少なりとも参考になれば幸いである。
問 (フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
(フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除)
私は古物営業法上の許可を受けて古物営業を営んでいる個人事業者です。フリーマーケットアプリやインターネットオークションを通じて商品を仕入れることもありますが、その際、取引の相手方が匿名の場合があります。この場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、どうしたらよいでしょうか。
また、固定資産など自ら使用する物品として仕入れるような場合や、古物商以外の者が仕入れるような場合に、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除することができる経過措置の適用はできるのでしょうか。
<ポイント>
1 古物商特例とは?
古物営業法上の許可を受けた古物商が、非登録事業者から販売目的で古物や準古物を買い受けた場合には、法定事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることが認められている(消令49①一ハ(1))。
(注)金、銀、白金といった貴金属の地金やゴルフ会員権などの古物に準ずる物品や証票は準古物に該当する(消規15の3、消基通11-6-3)。
2 帳簿の記載事項
(1)商品の仕入総額(税込)が1万円以上の場合
古物営業法では、原則として、商品の仕入総額(税込)が1万円以上の場合には、相手方の確認を行った上でいわゆる「古物台帳」に取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢を記載することとされていることから、古物台帳への記載をもって、消費税における帳簿の記載要件を満たすものとして取り扱うことができる。
ただし、消費税法で帳簿への記載が義務付けられている「帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるいずれかの仕入れに該当する旨」については、古物台帳への記載は義務ではない。よって、総勘定元帳などの会計帳簿には、「古物商特例適用」といったような記載が必要となるようだ(インボイスQ&A問110(参考))。
(2)商品の仕入総額(税込)が1万円未満の場合
古物営業法では、商品の仕入総額(税込)が1万円未満の場合には、古物台帳の記載は不要とされている。ただし、自動二輪車、家庭用コンピュータゲーム、CD・DVD、書籍の買い受けなどについては、相手方の本人確認や帳簿への記帳義務が課されている。
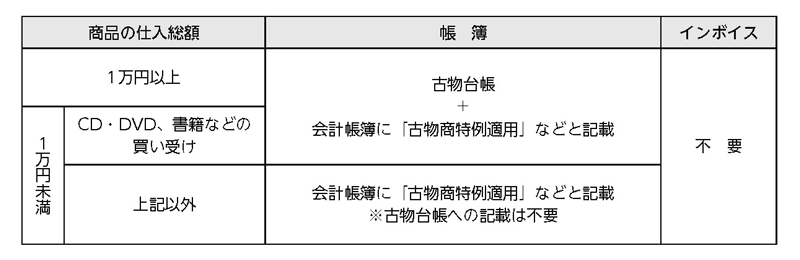
3 フリマアプリ等による仕入商品に対する古物商特例の適用について
(1)適格請求書発行事業者から商品の仕入れを行った場合
フリマアプリ等により商品を仕入れる場合には、物品の譲渡を行う事業が不特定かつ多数の者を対象とするものであることから、簡易インボイスの交付を受けることになるものと思われる。また、出品者とフリマアプリ等の運営事業者が共に適格請求書発行事業者であり、媒介者交付特例の適用要件を満たすような場合には、運営事業者が、出品者に代わって簡易インボイスの交付を行うことも認められる。
(2)非登録事業者から商品の仕入れを行った場合
古物商が、非登録事業者からフリマアプリ等により商品の仕入れを行った場合において、仕入総額が1万円未満の場合には、帳簿に「古物商特例適用」などと記載することにより、古物商特例の適用を受けることができる。
ただし、仕入総額が1万円以上の場合には、古物台帳へ法定事項を記載する必要があることから、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要がある。
(3)個人事業者から商品の仕入れを行った場合
適格請求書発行事業者である個人事業者から家事用資産を仕入れるようなケースでは、メッセージ機能等により「適格請求書発行事業者としての譲渡である場合は登録番号を教えてください。連絡がない場合には、消費者としての譲渡と考えさせていただきます。」と確認を行った上で、何らの連絡がない場合には、仕入先を非登録事業者として取り扱うことができるようである。
4 フリマアプリ等による仕入商品に対する80%(50%)経過措置の適用について
古物商が仕入れる古物については、古物営業法上、本人確認や古物台帳への記帳義務が生じることから、結果として、仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場面は想定されない。そのため、80%(50%)経過措置が適用されることはない。
(1)古物商以外の者が仕入れる古物の取扱い
古物商以外の者がフリマアプリ等で古物を仕入れた場合において、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合には、80%(50%)経過措置の適用を受けることが認められているようである。
(2)準古物を仕入れる場合の取扱い
仕入総額が1万円以上の準古物の仕入れで、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないような場合には、80%(50%)経過措置の適用を受けることができることとしている。
「準古物については、古物営業法の対象外であることから、対価の総額が1万円以上の場合でも同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められません。」と問 の(注)4に記載されていることがその理由(根拠)であると思われる。
の(注)4に記載されていることがその理由(根拠)であると思われる。
(3)区分記載請求書等の記載要件
80%(50%)経過措置の適用を受けるために保存が義務付けられている区分記載請求書等に記載すべき「書類の作成者の氏名又は名称」及び帳簿に記載すべき「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」は、「フリマアプリ等の名称及び当該フリマアプリ等におけるアカウント名」として差し支えないとのことである。
(注)フリマアプリ等の取引画面を区分記載請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録として保存する場合には、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)に準じた方法による必要がある。
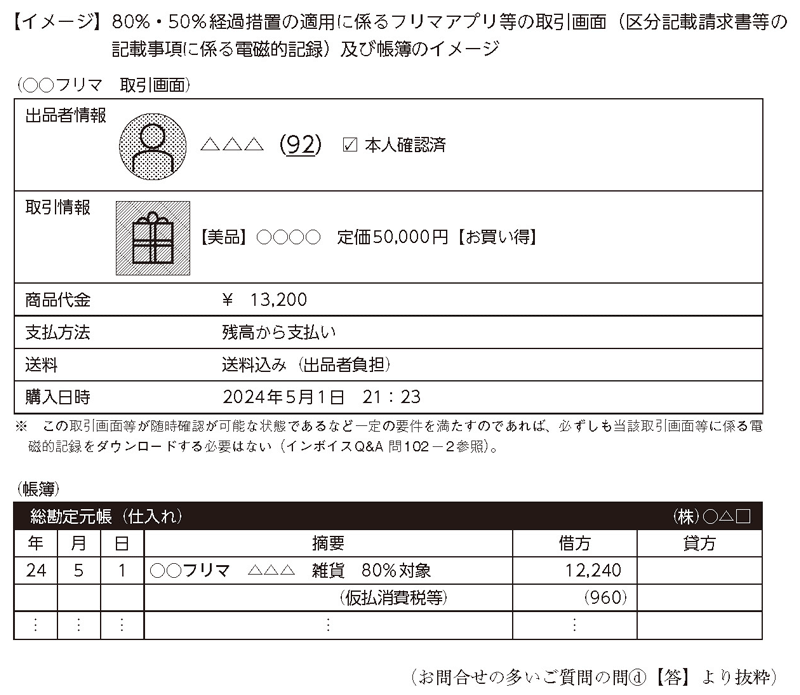
5 準古物の取り扱い(疑問点)
第213回国会 財政金融委員会 第5号(令和6年2月28日)会議録には、パチンコ業界における景品取引所の特殊景品の買い取りについて、田村貴昭委員からの質問が記録されている。
古物営業法に従えば、景品買取り所は、犯罪被害品の流通を防止するために、窓口をガラス張りにするなど、お客の顔を見て取引ができる環境をつくることが義務付けられている。これは、対面によって、相手の態度、しぐさなどを見て確認するためのものと説明されている。さらに、1万円以上の買い取りについては、本人確認や運転免許証などのコピーの保存、帳簿の記載などが必要とされているのであるが、特殊景品を換金するお客さんに対し、このような条件をクリアすることは現実問題として不可能である。
景品取引所の特殊景品は、風営法により価格の上限が「9,600円+消費税」と定められていることから、パチンコの特殊景品は価格要件をクリアすることになるようだ。
田村貴昭委員が警察庁に対し、5千円の古物を6個、総額3万円で買い取る場合の本人確認などの必要性について質問したところ、和田政府参考人からは古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合には、その物品の対価を全て足し合わせた額で判断するのに対し、古物に該当しないものを買い取る場合は、古物営業法の規制は及ばないと回答している。特殊景品は金地金を使っていることから準古物に該当する。準古物である特殊景品には古物営業法は適用されないため、1万円未満の景品を何万円換金しても、本人確認や古物台帳への記帳は必要ないことになるのだろうか……。
問 の【答】では、フリマアプリ等による準古物の仕入総額が1万円以上の場合で、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないようなケースでも、80%(50%)経過措置の適用を受けることができることとしている。この取扱いは、パチンコの景品取引所においては適用されず、景品取引所はお客さんからの仕入れについて、インボイスなしでその全額を仕入税額控除の対象としてよいのであろうか……?
の【答】では、フリマアプリ等による準古物の仕入総額が1万円以上の場合で、メッセージ機能等を用いて確認を行ったとしても仕入先の住所、氏名、職業及び年齢の確認ができないようなケースでも、80%(50%)経過措置の適用を受けることができることとしている。この取扱いは、パチンコの景品取引所においては適用されず、景品取引所はお客さんからの仕入れについて、インボイスなしでその全額を仕入税額控除の対象としてよいのであろうか……?
古物商特例の対象となる古物には、古物営業と同等の取引方法により買い受ける準古物が含まれる(消令49①一ハ(1)、消規15の3)。「古物営業と同等の取引方法」とは、古物営業法の規定に基づき相手方の住所、氏名等の確認等を行うとともに、業務に関する帳簿等への記載等を行うなど、古物商が古物を買い受ける場合と同等の取引方法にあることをいうものとされている(消基通11-6-3)。
ただし、準古物には古物法は適用されないことから、対価の総額が1万円以上の場合であっても同法上は本人確認や古物台帳への記帳は求められず、また、買取価格の合計額による1万円判定も不要となる。結果として、景品取引所は、古物営業法上の許可を受けることにより、個々の買取価格が1万円未満の特殊景品を古物商特例の対象とすることができることになるのだろうか?
準古物については、古物法が適用されないのにも関わらず、古物営業法上の許可を受けることにより、古物商特例が適用できるということに妙な違和感を感じている。
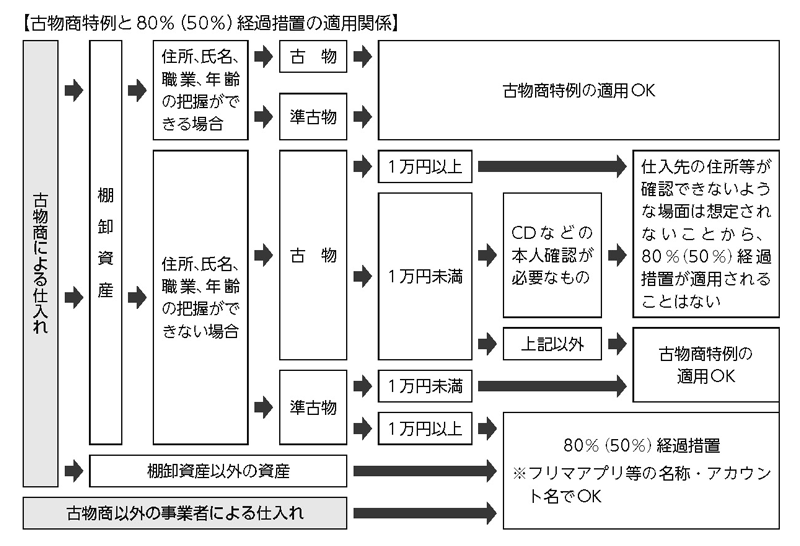
問 (地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録)
(地方公営企業法適用の特別会計に移行する際の適格請求書発行事業者の登録)
上下水道の特別会計を有する地方公共団体ですが、この度、地方公営企業法適用の特別会計に移行することとなりました。移行前の特別会計で適格請求書発行事業者の登録申請を行い登録番号の付番を受けていましたが、移行に当たっては当該登録番号も移行されるのでしょうか。
<ポイント>
1 旧特別会計から新特別会計へ移行する場合の取扱い
水道事業、交通事業や衛生事業など、地方公共団体が特別会計を設けて行う事業については、その特別会計ごとに一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定を適用することとされている(消法60①)。
また、国税庁ホームページ(地方公共団体の特別会計が地方公営企業法の規定を適用する特別会計に移行した場合の消費税の課税関係について)によると、上下水道の特別会計を地方公営企業法適用の特別会計へ移行する場合には、全ての出納は地方公営企業法の適用日の前日をもって打ち切られる(打切決算)こととなる(地方公営企業法施行令第4条第1項)。
よって、新特別会計への移行に当たっては、旧特別会計は廃止され、別人格である新たな特別会計が設置されたものとして取り扱われることになる。
2 登録番号の取扱い
適格請求書発行事業者の登録は、登録を受けようとする事業者ごとに行うものである。
地方公共団体の特別会計が、地方公営企業法の規定を適用する特別会計に移行する場合、通常、旧特別会計は廃止され、新たな特別会計が設置されることとなるのであるから、旧特別会計においては「事業廃止届出書」の提出が必要となり、それに伴い旧特別会計の登録番号は失効することとなる。
よって、新特別会計は改めてインボイスの登録申請を行い、登録番号の付番を受ける必要がある。
3 登録の効力
新たに特別会計を設置した場合には、設置日以後に登録申請を行うこととなるのであるが、特別会計の設置日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書をその課税期間の末日までに提出した場合、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされる特例が設けられている(インボイスQ&A問11)。
この場合において、設置日の属する課税期間の初日から登録通知があるまでの期間については、次のような対応方法が考えられる。
・事前に適格請求書等の交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後に適格請求書等を交付する。
・取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めて適格請求書等を交付し直す。
・取引先に対して、通知を受けるまでは、登録番号のない請求書等を交付し、その請求書等との関連性を明らかにした上で、適格請求書等に不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする。
問 (複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付)
(複数年をまたぐ取引に係る適格請求書の交付)
当社は、1年を超える期間にわたって毎月保守を行う役務を提供しています。このように課税期間をまたぐような長期間にわたる課税資産の譲渡等について、対価の前受け時にまとめて適格請求書を交付しても良いのでしょうか。
<ポイント>
インボイスの記載事項である取引年月日については、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめてインボイスを作成する場合には、当該一定の期間を記載することになる。
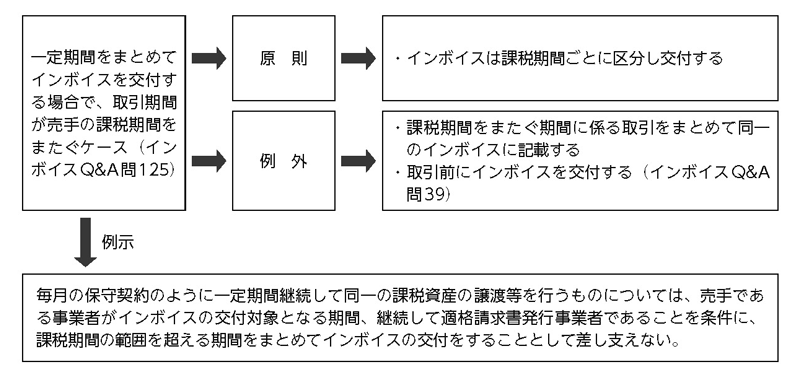
<留意点>
・個人事業者は1月1日から12月31日までの期間、法人は事業年度が課税期間となるので、どちらも最長1年間となる。課税期間の範囲を超える期間につき、まとめてインボイスを交付した場合において、当期の課税期間に係る消費税額等の記載が明確に区分されていない場合には、売上税額の積上計算を行うことはできない。
・課税期間の範囲を超える期間につき、まとめてインボイスを交付した後に、その記載事項に変更が生じることとなった場合には、修正インボイスを交付する必要がある。
・課税期間の中途で適格請求書発行事業者でなくなった場合には、既に交付したインボイスについて、適格請求書発行事業者でなくなった期間部分を区分して区分記載請求書等として再交付するなどの対応が必要となる。
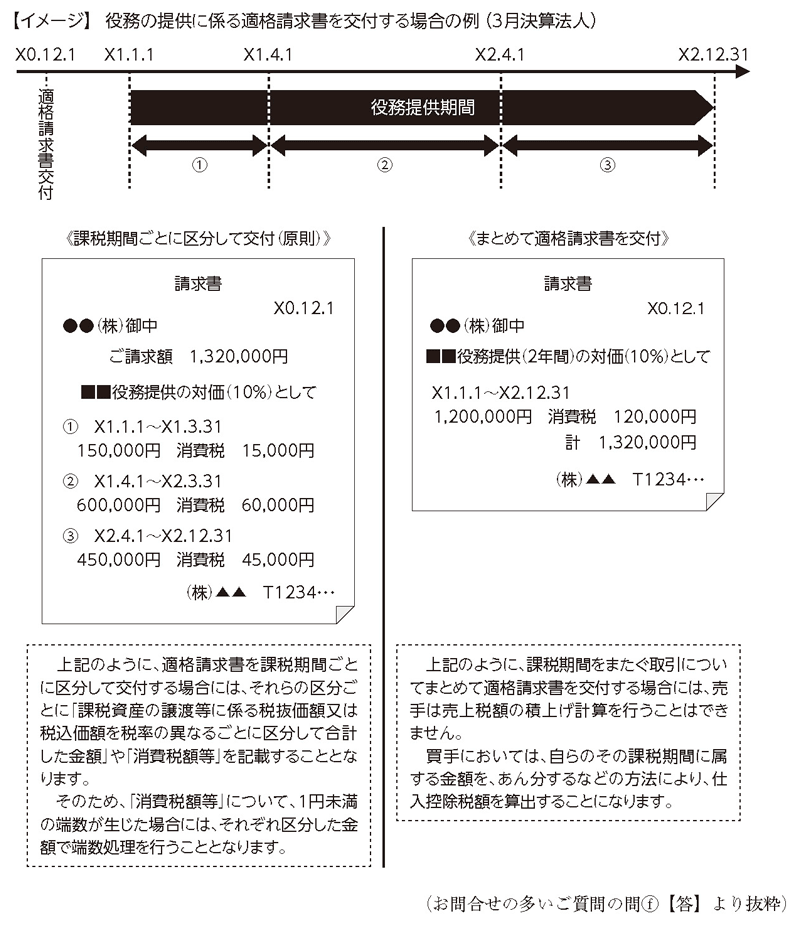
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























