解説記事2024年11月11日 新会計基準解説 企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要(上)(2024年11月11日号・№1050)
新会計基準解説
企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の概要(上)
企業会計基準委員会 ディレクター 村瀨進吾
企業会計基準委員会 専門研究員 福江東晶
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、2024年9月13日に、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下「リース会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(以下「リース適用指針」という。また、以下合わせて「リース会計基準等」という。)を公表し、また、併せて関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針(以下合わせて「本会計基準等」という。)の改正を公表した(脚注1)。本稿では、リース会計基準等の概要のうち、借手と貸手で共通の取扱い及び借手の会計処理について紹介する。
なお、本会計基準等の公表に合わせて、2024年9月13日に日本公認会計士協会(JICPA)より実務指針等が改正されている(脚注2)ため、併せてご確認いただきたい。また、文中の意見に関する部分は筆者の私見であり、ASBJの見解を示すものではないことをあらかじめ申し添える。
Ⅱ 本会計基準等の公表の経緯
我が国においては、2007年3月にASBJが企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」(以下「企業会計基準第13号」という。)及び企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第16号」という。また、以下合わせて「企業会計基準第13号等」という。)を公表し、リースに関する我が国の会計基準は当時の国際的な会計基準と整合的なものとなった。
そのような中、2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」という。)が公表され、また、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりFASB Accounting Standards Codification(FASBによる会計基準のコード化体系)のTopic 842「リース」(以下「Topic 842」という。)が公表された。IFRS第16号及びTopic 842では、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされている。IFRS第16号及びTopic 842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性があった。
これらの状況を踏まえ、ASBJは、財務諸表作成者及び財務諸表利用者から幅広く意見を聴取した上で、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとし、検討を行った。本会計基準等は、2023年5月に公表した企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等に対して寄せられた意見を踏まえて検討を行い、公開草案の内容を一部修正した上で公表するに至ったものである。
Ⅲ リース会計基準等の概要
1 開発にあたっての基本的な方針
ASBJは、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上するリースに関する会計基準の開発にあたって、次の基本的な方針を定めた。
(1)借手の費用配分の方法
借手のリースの費用配分の方法として、IFRS第16号では、すべてのリースを借手に対する金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る金利費用を別個に認識する単一の会計処理モデル(以下「単一の会計処理モデル」という。)が採用されている。これに対して、Topic 842では、オペレーティング・リースの借手が取得する権利及び義務は、残存する資産に対する権利及びエクスポージャーを有さず、オペレーティング・リースを均等なリース料と引き換えにリース期間にわたって原資産に毎期均等にアクセスする経済的便益を享受するものと捉えて、従前と同様にファイナンス・リース(減価償却費と金利費用を別個に認識する。)とオペレーティング・リース(通常、均等な単一のリース費用を認識する。)に区分する2区分の会計処理モデルが採用されている。
リース会計基準等では、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用する。
(2)IFRS第16号と整合性を図る程度
借手の会計処理に関してIFRS第16号と整合性を図る程度については、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRSを任意適用して連結財務諸表を作成している企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となる会計基準とする。そのうえで、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮した方策を検討する。
一方、貸手の会計処理については、IFRS第16号及びTopic 842ともに抜本的な改正が行われていないため、次の点を除き、基本的に、企業会計基準第13号の定めを踏襲する。
① 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」(以下「収益認識会計基準」という。)との整合性を図る点
② リースの定義及びリースの識別
2 リース会計基準等の適用範囲
(1)範囲
リース会計基準等は、契約の名称などにかかわらず、次の①から③に該当する場合を除き、リースに関する会計処理及び開示に適用する(リース会計基準第3項)。
① 実務対応報告第35号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い」の範囲に含まれる運営権者による公共施設等運営権の取得
② 収益認識会計基準の範囲に含まれる貸手による知的財産のライセンスの供与(ただし、製造又は販売以外を事業とする貸手は、当該貸手による知的財産のライセンスの供与についてリース会計基準を適用することができる。)
③ 鉱物、石油、天然ガス及び類似の非再生型資源を探査する又は使用する権利の取得
上記にかかわらず、無形固定資産のリースについては、リース会計基準を適用しないことができる(リース会計基準第4項)。
(2)個別財務諸表への適用
リース会計基準等では、連結財務諸表と個別財務諸表の会計処理を同一とすることとしている。リース会計基準等を連結財務諸表のみに適用すべきか、連結財務諸表と個別財務諸表の両方に適用すべきかを検討するため、ASBJでは次の項目について審議を行った。
① 国際的な比較可能性
② 関連諸法規等(法人税法、分配規制、自己資本比率規制、民法(賃貸借)及び法人企業統計)との利害調整
③ 中小規模の企業における適用上のコスト
④ 連結財務諸表と個別財務諸表で異なる会計処理を定める影響
審議の結果、リース会計基準等の適用に関する懸念の多くは、個別財務諸表固有の論点ではないと考えられ、連結財務諸表と個別財務諸表の会計処理は同一であるべきとする基本的な考え方及び方針を覆すに値する事情は存在しないと判断した。
この点、公開草案に寄せられたコメントの中には、上記①から④の項目に関連し、リース会計基準を連結財務諸表と個別財務諸表の両方に適用することを懸念する意見があった。当該懸念に対して再度検討を重ねた結果、上記の判断を変更する結論には至らなかった。
3 リースの定義及びリースの識別
(1)リースの定義及びリースの識別の判断
リース会計基準等では、リースの定義に関する定めについて、IFRS第16号の定めと整合させて、借手と貸手の両方に適用することとしている。具体的には、「リース」について、原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分と定義している(リース会計基準第6項)。
また、リースの識別の判断に関する定めについては、基本的にIFRS第16号の定めと整合させて、借手と貸手の両方に適用することとしている。リースの識別に関する定めは企業会計基準第13号では置かれていなかった定めであり、リース会計基準等の適用によってこれまで企業会計基準第13号により会計処理されていなかった契約にリースが含まれると判断される場合があると考えられる。具体的には、主に次の定めを置いている(リース会計基準第25項及び第26項並びにリース適用指針第5項から第8項)。
① 契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む。
② 特定された資産の使用期間全体を通じて、次のいずれも満たす場合、当該契約の一方の当事者(サプライヤー)から当該契約の他方の当事者(顧客)に、当該資産の使用を支配する権利が移転している。
(ア)顧客が、特定された資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受する権利を有している。
(イ)顧客が、特定された資産の使用を指図する権利を有している。
なお、IFRS第16号のリースの識別に関する細則的なガイダンスや設例については、国際的な比較可能性が大きく損なわれるか否かを主要な判断基準として、取捨選択してリース会計基準等に取り入れている。リース会計基準等に取り入れていないものとして、例えば、次のものがある。
① 資産が契約に明記されない場合でも黙示的に定められることによって特定され得るとの定め
② 使用期間全体を通じて使用から得られる経済的利益に影響を与える資産の使用方法に係る意思決定の例示
また、リースの識別の判断に関する理解のために、前頁の図表1のとおり、リースの識別に関するフローチャートをリース適用指針の[設例1]に示している。
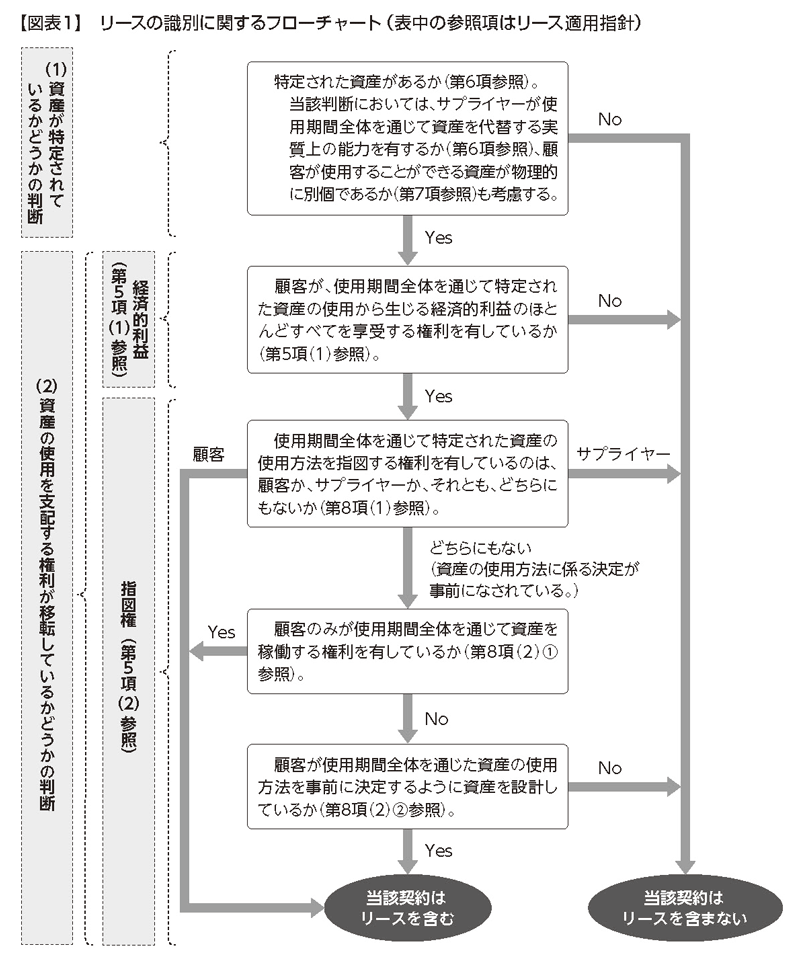
(2)リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分
借手及び貸手は、リースを含む契約について、原則として、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とに分けて会計処理を行う(リース会計基準第28項)。ただし、次の例外の定めを置いている。
① リースを構成する部分とリースを構成しない部分の区分の例外
借手は、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと又は性質及び企業の営業における用途が類似する原資産のグループごとに、リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを分けずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分として会計処理を行うことを選択することができる(リース会計基準第29項)。
貸手は、リースを含む契約についてリースを構成しない部分が収益認識会計基準の適用対象であって、かつ、次の(ア)及び(イ)のいずれも満たす場合には、契約ごとにリースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせて取り扱うことができる。この場合、リースを構成する部分がリースを含む契約の主たる部分であるかどうかにより、リース会計基準に従って会計処理を行うか又は収益認識会計基準に従って会計処理を行うことになる(リース適用指針第14項及び第15項)。
(ア)リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分の収益の計上の時期及びパターンが同じである。
(イ)リースを構成する部分がオペレーティング・リースに分類される。
② 契約における対価の金額の配分
契約における対価の金額について、リースを構成する部分とリースを構成しない部分への配分については、次のとおり行う。
借手は、契約における対価の金額についてそれぞれの部分の独立価格の比率に基づいて配分する。また、借手は、契約における対価の中に、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含まれる場合、当該金額を契約における対価の一部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分する(リース適用指針第11項)。
貸手は、契約における対価の金額についてそれぞれの部分の独立販売価格の比率に基づいて配分する。このとき、契約における対価の中に、借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額、あるいは、原資産の維持管理に伴う固定資産税、保険料等の諸費用(以下「維持管理費用相当額」という。)が含まれる場合、当該配分にあたって、次の(ア)又は(イ)のいずれかの方法により会計処理を行う(リース適用指針第13項)。
(ア)契約における対価の中に借手に財又はサービスを移転しない活動及びコストについて借手が支払う金額が含まれる場合に、当該金額を契約における対価の一部としてリースを構成する部分とリースを構成しない部分とに配分する方法
(イ)契約における対価の中に維持管理費用相当額が含まれる場合に、当該維持管理費用相当額を契約における対価から控除し収益に計上する、又は貸手の費用の控除額として処理する方法
ただし、上記(イ)の方法においては、維持管理費用相当額がリースを構成する部分の金額に対する割合に重要性が乏しいときは、当該維持管理費用相当額についてリースを構成する部分の金額に含めることができる。
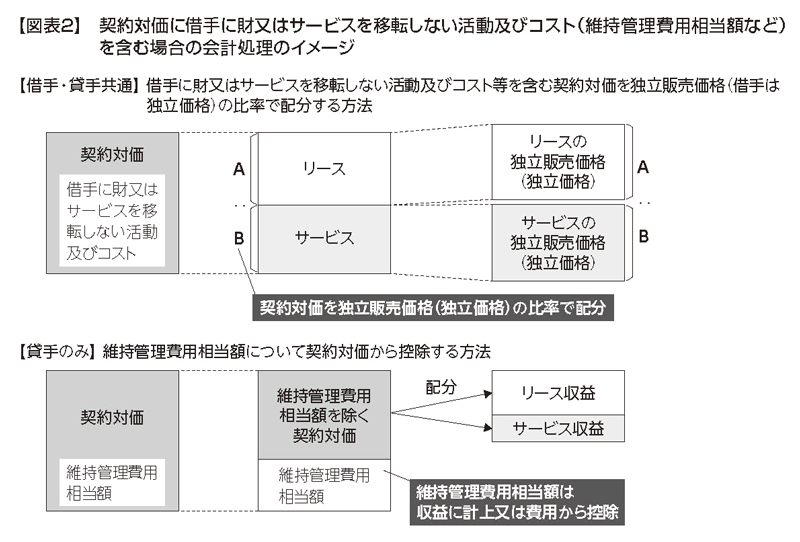
4 リース期間
(1)借手のリース期間
借手のリース期間については、借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間に、借手が行使することが合理的に確実であるリースの延長オプションの対象期間及び借手が行使しないことが合理的に確実であるリースの解約オプションの対象期間を加えて決定する(リース会計基準第31項)。借手のリース期間の決定方法については、IFRS第16号の定めと整合的な取扱いとしている。
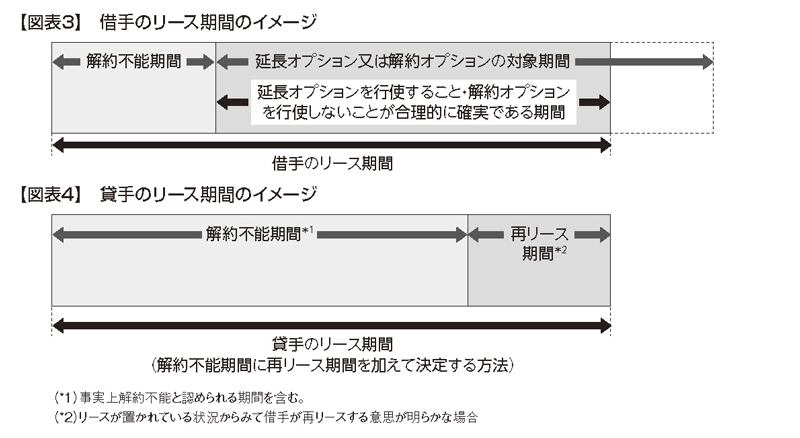
借手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該権利は借手が利用可能なオプションとして、借手は借手のリース期間を決定するにあたってこれを考慮する。貸手のみがリースを解約する権利を有している場合、当該期間は、借手の解約不能期間に含まれる(リース会計基準第31項)。
借手は、借手が延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって、経済的インセンティブを生じさせる要因を考慮する(リース適用指針第17項)。
この点、借手が特定の種類の資産を通常使用してきた過去の慣行及び経済的理由が、借手のオプションの行使可能性を評価する上で有用な情報を提供する可能性がある。ただし、一概に過去の慣行に重きを置いてオプションの行使可能性を判断することを要求するものではなく、将来の見積りに焦点を当てる必要がある。合理的に確実であるかどうかの判断は、諸要因を総合的に勘案して行うことに留意する必要がある。
借手のオプションの行使可能性に関する「合理的に確実」は、蓋然性が相当程度高いことを示している。この点、IFRS第16号には「合理的に確実」に関する具体的な閾値の記載はないが、米国会計基準会計基準更新書第2016-02号「リース(Topic 842)」の結論の根拠では、「合理的に確実」が高い閾値であることを記載した上で、米国会計基準の文脈として、発生する可能性の方が発生しない可能性より高いこと(more likely than not)よりは高いが、ほぼ確実(virtually certain)よりは低いであろうことが記載されている。
(2)貸手のリース期間
貸手のリース期間については、次のいずれかの方法を選択して決定する(リース会計基準第32項)。
① 借手のリース期間と同様に決定する方法
② 借手が原資産を使用する権利を有する解約不能期間(事実上解約不能と認められる期間を含む。)にリースが置かれている状況からみて借手が再リースする意思が明らかな場合の再リース期間を加えて決定する方法(解約不能期間に再リース期間を加えて決定する方法)
上記①の方法はIFRS第16号と整合的な方法であり、上記②の方法は企業会計基準第13号のリース期間の定めを踏襲した方法である。
5 借手のリースの会計処理
(1)リース開始日の使用権資産及びリース負債の計上額
企業会計基準第13号では、リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法によるとしていた。
リース会計基準等では、IFRS第16号の定めと同様に、借手は、使用権資産について、リース開始日に算定されたリース負債の計上額にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用及び資産除去債務に対応する除去費用を加算し、受け取ったリース・インセンティブを控除した額により算定することとしている(リース会計基準第33項)。
また、リース負債の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース開始日において未払である借手のリース料からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除し、現在価値により算定する(リース会計基準第34項)。
使用権資産の計上額については、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上することとしたため、企業会計基準適用指針第16号における貸手の購入価額又は見積現金購入価額と比較を行う方法を踏襲しておらず、借手のリース料の現在価値を基礎として算定することとしている。
① 借手のリース料
借手のリース料は、IFRS第16号の定めと同様に、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払であり、次のもので構成される(リース会計基準第35項)。
(ア)借手の固定リース料
(イ)指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料
(ウ)残価保証に係る借手による支払見込額
(エ)借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額
(オ)リースの解約に対する違約金の借手による支払額(借手のリース期間に借手による解約オプションの行使を反映している場合)
② 指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料
「借手の変動リース料」とは、借手が借手のリース期間中に原資産を使用する権利に関して行う貸手に対する支払のうち、リース開始日後に発生する事象又は状況の変化(時の経過を除く。)により変動する部分をいう。借手の変動リース料には、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料とそれ以外の借手の変動リース料がある(リース会計基準第21項)。具体的には次のものが考えられる。
(ア)指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料(例えば、消費者物価指数の変動に連動するリース料)
(イ)原資産から得られる借手の業績に連動して支払額が変動するリース料(例えば、テナント等の原資産を利用することで得られた売上高の所定の割合を基礎とすると定めているようなリース料)
(ウ)原資産の使用に連動して支払額が変動するリース料(例えば、原資産の使用量が所定の値を超えた場合に、追加のリース料が生じるようなリース料)
上記(ア)のリース料について、IFRS第16号においては、当該リース料は借手の将来の活動に左右されないものであり、将来におけるリース料の金額に不確実性があるとしても、借手はリース料を支払う義務を回避することができず、負債の定義を満たすことから、リース負債の計上額に含められている。リース会計基準においても、国際的な会計基準との整合性も踏まえ、当該リース料をリース負債の計上額に含めることとした。
この(ア)のリース料には、市場における賃料の変動を反映するように当事者間の協議をもって見直されることが契約条件で定められているリース料が含まれる(リース適用指針第24項)。
一方、上記(イ)及び(ウ)のリース料について、IFRS第16号においては、借手の将来の活動を通じてリース料を支払う義務を回避することができることから、リース料の支払が要求される将来の事象が生じるまでは負債の定義を満たさないとの考え方もあるため、リース負債の計上額に含められていないとされている。リース会計基準においても、これらのリース料が本来的に負債として認識すべきものかどうか国際的に十分なコンセンサスが得られていない状況にあること及び国際的な比較可能性の観点を考慮し、これらのリース料をリース負債の計上額に含めないこととした。
また、借手の変動リース料には、形式上は一定の指標に連動して変動する可能性があるが実質的には支払が不可避であるもの又は変動可能性が解消されて支払額が固定化されるものがある。これらのリース料の経済実態は借手の固定リース料と変わらないことから、借手の固定リース料と同様にリース負債の計上額に含めることとなる。例えば、リース開始日においては原資産の使用に連動するが、リース開始日後のある時点で変動可能性が解消され、残りの借手のリース期間について支払が固定化されるようなリース料等が該当すると考えられる。
借手は、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料について、リース開始日には、借手のリース期間にわたりリース開始日現在の指数又はレートに基づきリース料を算定する(リース適用指針第25項)。ただし、借手は、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料について、合理的な根拠をもって当該指数又はレートの将来の変動を見積ることができる場合、リース料が参照する当該指数又はレートの将来の変動を見積り、当該見積られた指数又はレートに基づきリース料及びリース負債を算定することを、リースごとにリース開始日に選択することができる(リース適用指針第26項)。
一方、借手は、リース負債の計上額に含めなかった借手の変動リース料については、当該変動リース料の発生時に損益に計上する(リース適用指針第51項)。
③ 現在価値の算定に用いる割引率
借手がリース負債の現在価値の算定のために用いる割引率は、次のとおりである(リース適用指針第37項)。
(ア)貸手の計算利子率(脚注3)を知り得る場合、当該利率による。
(イ)貸手の計算利子率を知り得ない場合、借手の追加借入に適用されると合理的に見積られる利率による。この利率には、例えば、次のような利率が含まれる(リース適用指針BC66項)。
(i)借手のリース期間と同一の期間におけるスワップレートに借手の信用スプレッドを加味した利率
(ii)新規長期借入金等の利率(借手のリース期間と同一の期間の借入れを行う場合に適用される利率)
(2)短期リースに関する簡便的な取扱い
「短期リース」は、IFRS第16号と同様に、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースと定義している(リース適用指針第4項(2))。
当該短期リースについて、借手はリース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することを認めている(リース適用指針第20項)。
この短期リースに関する簡便的な取扱いは、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合に貸借対照表において表示するであろう科目ごと、又は、IFRS第16号と同様に、性質及び企業の営業における用途が類似する原資産のグループごとに適用するか否かを選択することができる。
(3)少額リースに関する簡便的な取扱い
少額リースについても、借手はリース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することを認めている。少額リースとは、次の①と②のいずれかを満たすリースである(リース適用指針第22項)。
① 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース
② 次の(ア)又は(イ)を満たすリース
(ア)企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース
(イ)新品時の原資産の価値が少額であるリース
上記②(ア)の「企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1件当たりの金額に重要性が乏しいリース」とは、企業会計基準適用指針第16号において定められていたリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下であるかどうかにより判定する方法を踏襲することを目的として取り入れたものである。また、リース契約1件当たりの金額の算定の基礎となる対象期間は、原則として借手のリース期間とするが、当該借手のリース期間に代えて、契約上、契約に定められた期間(以下「契約期間」という。)とすることができる。加えて、リース契約1件当たりの金額の算定にあたり維持管理費用相当額の合理的見積額を控除することができる。なお、この適用にあたっては、リース契約1件ごとにこの方法を適用するか否かを選択することは想定しておらず、リース契約1件当たりの金額を判定する際に複数の契約を結合することまでは想定していない(リース適用指針第23項並びにBC43項及びBC44項)。
上記②(イ)の「新品時の原資産の価値が少額であるリース」は、IFRS第16号と同様の方法を認めることを目的として取り入れたものである。当該方法は、IFRS第16号の結論の根拠で示されているIFRS第16号の開発当時の2015年において新品時に5千米ドル以下程度の価値の原資産のリースを念頭においている(リース適用指針BC45項)。
(4)借地権の設定に関する権利金等
リース会計基準等では、借地権の設定に係る権利金等は、使用権資産の取得価額に含め、原則として、借手のリース期間を耐用年数とし、減価償却を行うこととしている。ただし、旧借地権の設定に係る権利金等又は普通借地権の設定に係る権利金等のうち、次の①又は②の権利金等については、減価償却を行わないものとして取り扱うことを認めている(リース適用指針第27項)。
① リース会計基準等の適用前に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等を償却していなかった場合、リース会計基準等の適用初年度の期首に計上されている当該権利金等及びリース会計基準等の適用後に新たに計上される権利金等の双方
② リース会計基準等の適用初年度の期首に旧借地権の設定に係る権利金等及び普通借地権の設定に係る権利金等が計上されていない場合、リース会計基準等の適用後に新たに計上される権利金等
また、経過措置として、借手のリース期間を耐用年数とし減価償却を行う会計処理を選択する借手がリース会計基準の適用初年度の期首に計上されている旧借地権の設定に係る権利金等又は普通借地権の設定に係る権利金等を償却していなかった場合、当該権利金等を使用権資産の取得価額に含めた上で、当該権利金等のみ償却しない取扱いを認めている(リース適用指針第127項)。
借地権の設定に係る権利金等について減価償却を行う場合、借手のリース期間の終了時に残存価額があると認められるときには借手のリース期間の終了時における残存価額を見積った上で残存価額を控除した金額により減価償却を行うことが考えられる。ただし、借地権の承継が行われる可能性を見込むことや借手のリース期間の終了時に予想される売却価額を見積ることができない場合には、残存価額をゼロとすることも考えられる(リース適用指針BC54項)。
(5)利息相当額の各期への配分
リース会計基準等では、企業会計基準第13号等におけるファイナンス・リース取引に関する定め及びIFRS第16号の定めと同様に、リース開始日における借手のリース料とリース負債の計上額との差額は、利息相当額として取り扱い、当該利息相当額を借手のリース期間中の各期に配分する方法は、原則として利息法によることとしている(リース会計基準第34項及び第36項並びにリース適用指針第38項及び第39項)。
ただし、使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合(脚注4)は、次のいずれかの方法を適用することを認めている(リース適用指針第40項)。これらの簡便的な取扱いは、企業会計基準適用指針第16号に定められていた簡便的な取扱いを踏襲したものである。
① 借手のリース料から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法
② 利息相当額の総額を借手のリース期間中の各期に定額法により配分する方法
上記①の方法においては、使用権資産及びリース負債は、借手のリース料をもって計上し、支払利息は計上せず、減価償却費のみ計上する。
(6)使用権資産の償却
リース会計基準等では、使用権資産の償却について、基本的に企業会計基準第13号等におけるリース資産の償却と同様の会計処理を定めている。
まず、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるリースに係る使用権資産の減価償却費は、原資産を自ら所有していたと仮定した場合に適用する減価償却方法と同一の方法により算定し、この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間とし、残存価額は合理的な見積額とすることとしている(リース会計基準第37項)。
また、契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるリース以外のリースに係る使用権資産の減価償却費は、定額法等の減価償却方法の中から企業の実態に応じたものを選択適用した方法により算定し、この場合、原則として、借手のリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとすることとしている(リース会計基準第38項)。
(7)リースの契約条件の変更
「リースの契約条件の変更」とは、リースの当初の契約条件の一部ではなかったリースの範囲又はリースの対価の変更をいい、例えば、1つ以上の原資産を追加若しくは解約することによる原資産を使用する権利の追加若しくは解約、又は、契約期間の延長若しくは短縮をいう(リース会計基準第24項)。
リースの契約条件の変更に関する取扱いについては、IFRS第16号の主要な定めとしてリース会計基準等に取り入れている。
借手は、リースの契約条件の変更が生じた場合、次のいずれかを行う(リース会計基準第39項)(脚注5)。
① 変更前のリースとは独立したリースとして会計処理を行う。
② リース負債の計上額の見直しを行う。
(ア)上記①の会計処理を行う場合
リースの契約条件の変更が1つ以上の原資産を追加することにより原資産を使用する権利が追加されリースの範囲が拡大され、かつ、借手のリース料が範囲が拡大した部分に対する独立価格に特定の契約の状況に基づく適切な調整を加えた金額分だけ増額される場合、借手は、当該リースの契約条件の変更を独立したリースとして取り扱い、当該独立したリースのリース開始日に、リースの契約条件の変更の内容に基づくリース負債を計上し、当該リース負債にリース開始日までに支払った借手のリース料、付随費用等を加減した額により使用権資産を計上する(リース適用指針第44項)。
(イ)上記②の会計処理を行う場合
一方、独立したリースとしての会計処理が行われないリースの契約条件の変更については、借手は、リースの契約条件の変更の発効日に、次の(i)及び(ii)の会計処理を行う(リース適用指針第45項)。
(i)リース負債について、変更後の条件を反映した借手のリース期間を決定し、変更後の条件を反映した借手のリース料の現在価値まで修正する。
(ii)使用権資産について、次のことを行うことによって、上記(i)のリース負債の見直しに対応する会計処理を行う。
・リースの契約条件の変更のうちリースの範囲が縮小されるものについては、リースの一部又は全部の解約を反映するように使用権資産の帳簿価額を減額する。このとき、使用権資産の減少額とリース負債の修正額とに差額が生じた場合は、当該差額を損益に計上する。
・他のすべてのリースの契約条件の変更については、リース負債の修正額に相当する金額を使用権資産に加減する。
(8)リースの契約条件の変更を伴わないリース負債の見直し
借手は、リースの契約条件の変更が生じていない場合で、次のいずれかに該当するときには、該当する事象が生じた日にリース負債について当該事象の内容を反映した借手のリース料の現在価値まで修正し、当該リース負債の修正額に相当する金額を使用権資産に加減する(リース会計基準第40項及びリース適用指針第46項)。
① 借手のリース期間に変更がある場合
② 借手のリース期間に変更がなく借手のリース料に変更がある場合
上記①の借手のリース期間に変更がある場合には、(ア)借手の統制下にあること及び(イ)延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかの借手の決定に影響を与えることのいずれも満たす重要な事象又は重要な状況が生じたときに、借手のリース期間について延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかについて見直し、借手のリース期間を変更し、リース負債の計上額の見直しを行う(リース会計基準第41項)。また、借手は、延長オプションの行使等により借手の解約不能期間に変更が生じた結果、借手のリース期間を変更するときには、リース負債の計上額の見直しを行う(リース会計基準第42項)。
上記②の場合の例としては、原資産を購入するオプションの行使についての判定に変更がある場合、残価保証に基づく支払見込額に変動がある場合、指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に変動がある場合などが挙げられる(リース適用指針第47項)。
脚注
1 本会計基準等の全文については、ASBJのウェブサイト
(https://www.asb-j.jp/jp/accounting_standards/y2024/2024-0913.html)を参照のこと。
2 JICPAによる実務指針等の改正については、JICPAのウェブサイト
(https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240913kjq.html)を参照のこと。
3 貸手の計算利子率とは、貸手のリース料の現在価値と貸手のリース期間終了時に見積られる残存価額で残価保証額以外の額(以下「見積残存価額」という。)の現在価値の合計額が、当該原資産の現金購入価額又は借手に対する現金販売価額と等しくなるような利率をいう(リース適用指針第66項)。
4 使用権資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過の借手のリース料の期末残高が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合をいう(リース適用指針第41項)。
5 ただし、リースの契約条件の変更に複数の要素がある場合、これらの両方を行うことがある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























