解説記事2025年01月13日 特別解説 上場会社監査事務所登録制度と監査法人(2025年1月13日号・№1058)
特別解説
上場会社監査事務所登録制度と監査法人
上場会社監査事務所登録制度の法制化
上場会社監査の担い手の裾野の拡大といった会計監査を取り巻く環境変化を踏まえ、上場会社等の財務書類について監査証明業務を行う監査法人等に対する登録制度の導入などを内容とする「公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和4年法律第41号。以下「改正法」という。)」が、2022年5月18日に公布された。
日本公認会計士協会では、2007年度から、上場会社と監査契約を締結している監査事務所の監査の品質管理の状況の一層の充実強化を図り、資本市場における財務諸表監査の信頼性を確保するため、「上場会社監査事務所登録制度」を自主規制として導入していたが、上記の改正法を踏まえ、これまでに自主規制として培ってきた知見・ノウハウを活用していくことを念頭に、2023年4月1日から、上場会社等監査人登録制度を運営している。
この制度では、監査法人又は公認会計士が、上場会社等の財務書類に係る監査証明業務(金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第193条の2第1項及び第2項の監査証明に係るものに限る。)を行うときは、上場会社等監査人名簿への登録を受けなければならないこととされている。
また、上場会社等監査人名簿への登録にあたっては、日本公認会計士協会の会議体である「上場会社等監査人登録審査会」の審議が行われることとなる。
今般の法改正により、上場会社等は、その財務計算に関する書類及び内部統制報告書について、上場会社等監査人名簿に登録を受けた公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないこととなった。
このため、上場会社等は、監査法人又は公認会計士と財務書類に係る金商法の監査証明業務の契約を締結するにあたっては、当該監査法人又は公認会計士が、上場会社等監査人名簿に登録されているかどうかあらかじめ確認が求められることになる。
上場会社等監査人登録制度の概要
上場会社等監査人登録制度は、
① 上場会社等の監査を行う監査事務所(監査法人又は公認会計士)を法律上の名簿(公認会計士法(昭和23年法律第103号。以下「法」という。)第34条の34の2の「上場会社等監査人名簿」をいう。)に登録し、
② 登録を受けた監査事務所(以下「登録上場会社等監査人」という。)に対して“高い規律付け”を求め、
③ 登録上場会社等監査人が、上場会社等の監査を行う監査事務所として“高い規律付け”を果たしているかどうかを日本公認会計士協会が確認し(以下「適格性の確認」という。)、
④ 必要に応じて、登録上場会社等監査人の登録の取消しなどを行うことを通じて、会計監査の信頼性確保に寄与することを目的とした制度である。
登録の申請が承認された監査事務所は、上場会社等監査人名簿に登録され、登録上場会社等監査人となる。上場会社等監査人名簿は日本公認会計士協会に備え置かれ、公衆の縦覧に供されている(ウェブサイト上でも閲覧可能)。
登録上場会社等監査人には、法令上、監査法人のガバナンス・コードの受入れと情報開示の充実のための取組みの実施が求められることになる。
日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人に関する情報を、ウェブサイト「登録上場会社等監査人情報」において公表しており、閲覧できる主な情報は、次のとおりである。
ア.登録上場会社等監査人の概要情報(名称・所在地・連絡先・代表者名・専門要員数・上場会社等の監査契約数)
イ.『透明性報告書』又は『監査品質に関する報告書』を通じた経営管理の状況等(施行規則第95条)及び「監査法人の組織的運営に関する原則(監査法人のガバナンス・コード)」の適用状況(施行規則第96条)に関する情報
ウ.品質管理レビューの実施状況(原則として直近2回分)
エ.金融庁又は日本公認会計士協会からの懲戒処分等を受けた場合には、当該懲戒処分等を受けた旨及びその理由
2023年3月31日までの制度において、自主規制としての上場会社監査事務所名簿又は準登録事務所名簿に登録されていた監査事務所は143事務所(監査法人:133、共同事務所:2、個人:8)あった。本稿の執筆時点(2024年11月)では、上場会社等監査人として登録されているのが121事務所、上場会社等監査人としてみなし登録されているのが11事務所である。
本稿では、上場会社等監査人として登録されている121事務所について情報を調査・分析した。本稿で紹介する情報は、日本公認会計士協会のウェブサイトに掲載されている「登録上場会社等監査人情報」から入手したものである(各事務所の「登録上場会社等監査人の概要」及び掲載されている直近の説明書類)。
監査事務所の決算期の分布等
上場会社等監査人の有限・無限責任監査法人の内訳は、有限責任監査法人が20法人、無限責任監査法人が101法人であった。
そして、各事務所の決算月の分布は、表1のとおりであった。

3月決算の会社の監査が終了する6月末日を決算期末とする監査事務所が最も多く、次いで3月決算が多かった。決算期は幅広く分布していたが、4月決算と10月決算の監査事務所はなかった。
監査事務所に所属する人員数の規模別の分布
各監査事務所に所属する人員数(社員及び職員の合計。常勤所属者と非常勤所属者両方を含む。)別の分布を示すと、表2のとおりであった。
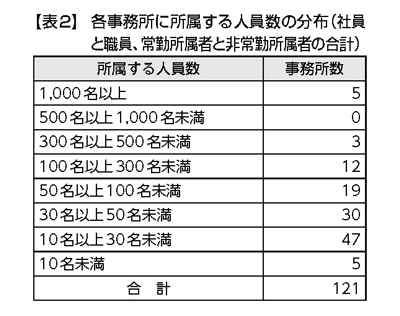
所属する人員数が500名以上1,000名未満の監査事務所が皆無であることが、我が国の監査市場の最大の特徴と言えるかもしれない。後述する表4に所属する人員数が多い監査事務所(上位10法人)を掲載しているが、業界3位のEY新日本と4位のPwCジャパン、PwCジャパンと5位の太陽、そして太陽から6位の仰星との差がそれぞれ大きく開いている状態となっている。所属人員の多い監査法人の業務が規模に比例して高品質であるとは限らないが、4大法人と準大手監査法人、準大手監査法人と中小規模監査法人の間に入るような「中堅規模の監査法人」の育成が我が国の課題と言われて久しい。準大手監査法人筆頭の太陽の所属人員数は1,000名を超え、仰星、三優、東陽という他の準大手監査法人も300人台、中小監査事務所でも、アヴァンティアやアークは200名に迫る勢いで成長を続けているが、4大監査法人との間の規模の差はまだ大きい。
さらに、監査事務所の常勤所属者と非常勤所属者を、監査事務所の類型別に集計すると、表3のようになった。
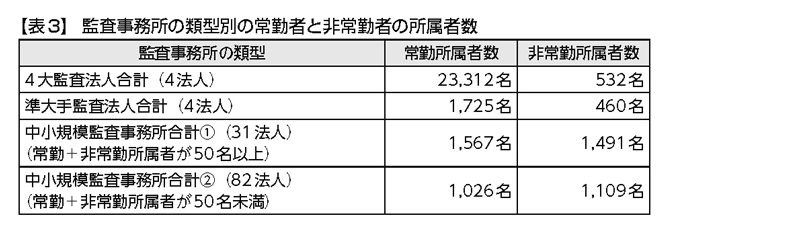
なお、4大監査法人とは、EY新日本、あずさ、トーマツ及びPwCジャパン(旧あらた+京都)の4法人をいい、準大手監査法人とは、太陽、仰星、三優及び東陽の4法人をいう。
雑駁な単純計算ではあるが、4大監査法人の場合は業務のほとんどを常勤所属者で実施しているのに対して、頭数でいうと、準大手監査法人では業務の2割程度、中小規模監査事務所では半分近くを非常勤所属者に頼っていることが見て取れる。当然のことながら、非常勤職員が所属する監査法人の業務にかけている時間数は多様であり(繁忙期に限定して補助的な業務に従事している場合が多いと思われる。)、各事務所ともに、主査業務等の各監査業務の主要な部分は常勤者が担っていると思われるが、中小規模監査事務所では、非常勤者への依存度が高くならざるを得ない状況であると考えられる。
次に、所属する人員数が多い監査事務所の上位10法人を列挙すると表4のとおりであった。
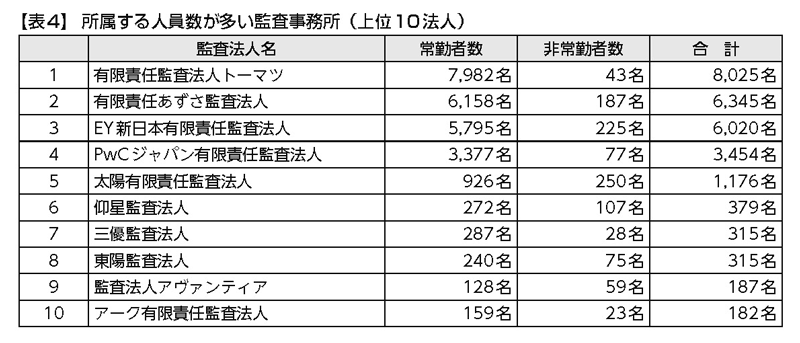
所属する社員(パートナー)数の分布
監査法人とは、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明を組織的に行うことを目的として、公認会計士法第34条の2の2第1項によって、公認会計士が共同して設立した法人をいう(公認会計士法第1条の2第3項)。そして、監査法人は、社員になろうとする5名以上の者によって設立され(このうち、少なくとも5名は公認会計士であることを要する。)(第34条の7第1項)、原則として公認会計士を社員とし(ただし、登録を受けた公認会計士以外の者も社員となりうる)(第34条の4第1項)、公認会計士である社員が4名以下となった状態を法定解散事由とする(第34条の18第2項)法人である。
公認会計士でない社員(=特定社員)の割合は、25%以下でなければならない(34条の4第3項、同施行規則第19条)。
なお、監査法人における「社員」とは出資者であり、通常の事業会社等でいうと「役員」に近い立場であることに留意が必要である。事業会社等における「社員」に相当する立場の者は、監査事務所では「職員」あるいは「専門職員」などと呼ばれることが多い。
ここでは、上場会社監査事務所に所属する社員(パートナー)数の分布を見てみたい。上場会社監査事務所に所属する社員数の分布を一覧にすると、表5のとおりとなった。
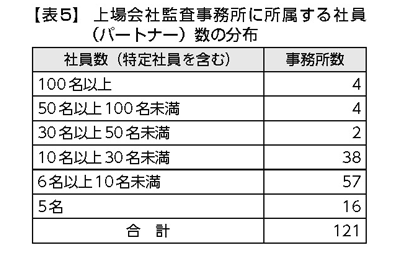
30名以上の社員(パートナー)を有する監査事務所はわずか10事務所に過ぎず、社員数が法定要件の下限の5名という監査事務所も少なくない。
次に、社員数が多い上場会社監査事務所(上位10事務所)を一覧にすると、表6のとおりであった。
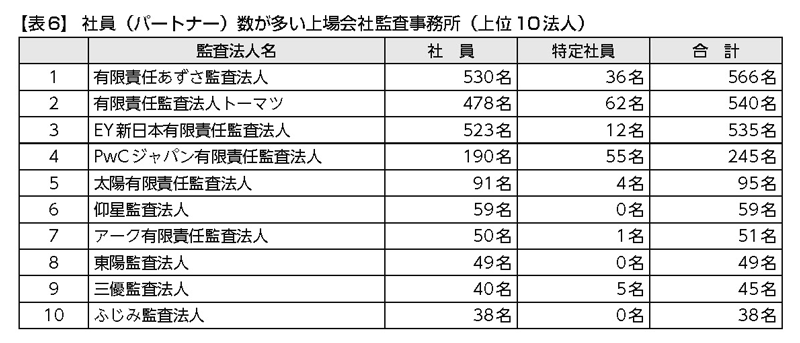
10位のふじみ監査法人は、2023年10月に名古屋監査法人、青南監査法人及び双研日栄監査法人の三法人が合併をして、新たにスタートした監査法人である。
監査事務所の被監査上場会社及びそれらを含む被監査顧客数の分布
次に、監査事務所ごとの被監査上場会社数の分布と、上場会社を含む被監査顧客数合計の分布を一覧にして見てみたい。なお、被監査顧客数には会社のほか、学校法人や労働組合等も含んでいる。
まず、監査事務所ごとの被監査上場会社数(金融商品取引法・会社法の監査業務数)の分布を一覧にすると、表7のとおりであった。
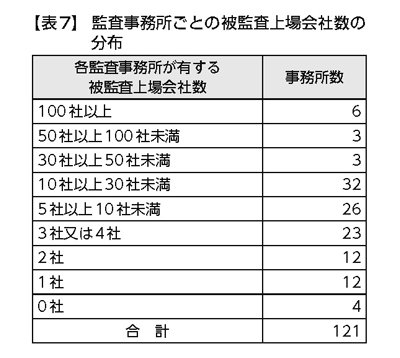
被監査上場会社数が30社以上の監査事務所は、上場会社監査事務所全体の1割に満たず、上場会社監査事務所全体の4割強(121法人のうちの51法人)の被監査上場会社数が5社未満であった。このことから、少なくない上場会社の監査業務を、きわめて小規模な監査法人が担っている現状を読み取ることができる。
次に、上場会社の監査業務(金商法・会社法の監査業務)数について、監査事務所の類型(規模)ごとにシェアを示すと、表8のとおりであった。なお、決算期が異なる各事務所の説明書類から抽出した数値を単純に合算しているため、数値の厳密さは十分ではない。あくまでも「参考程度」「ひとつの目安」とお考えいただきたい。
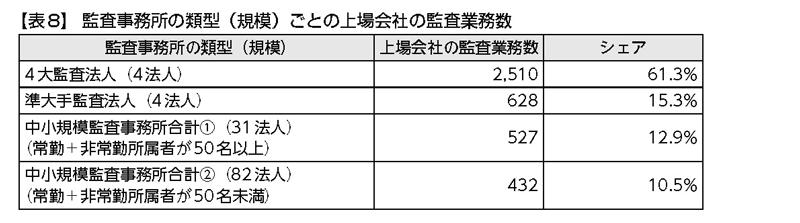
上場会社の監査市場における中小規模監査事務所の存在感は着実に大きくなってきてはいるが、まだまだ4大法人による寡占の状態が続いているといえよう。
さらに、被監査上場会社数が多い上場会社監査事務所のランキング(上位10法人)を示すと、表9のとおりであった。
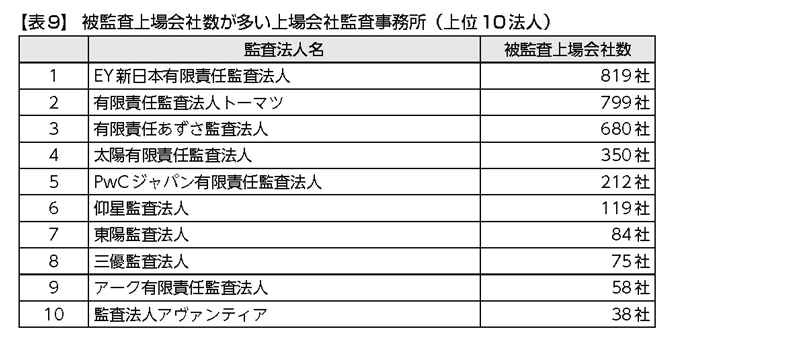
4大法人と準大手監査法人が上位8事務所を占めているが、アーク有限責任監査法人や監査法人アヴァンティアの近年の成長も著しい。
さらに、上場会社を含む、各事務所の被監査顧客全体の数の分布を示すと、表10のとおりであった。
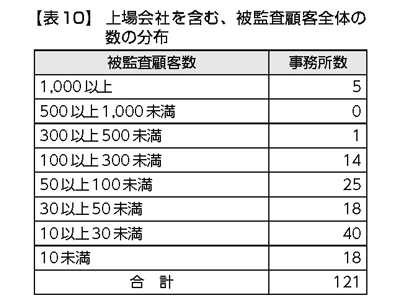
被監査顧客数が100未満の監査事務所が全体の8割強(121事務所中101事務所)を占めており、10未満の監査事務所も15%を占めていた。
上場会社監査事務所の業務収入の分布(監査業務及び非監査業務の合計)
次に、上場会社監査事務所121事務所の業務収入(監査業務収入と非監査業務収入の合計)の分布を示すと、表11のとおりであった。
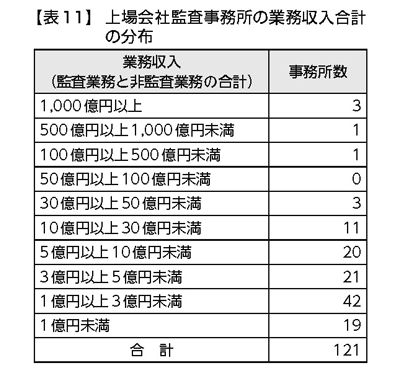
業務収入が10億円を超える監査事務所は19事務所であり、上場会社監査事務所全体の2割に満たなかった。
次に、監査事務所の類型(規模)別に監査業務収入、非監査業務収入と非監査業務収入が全体に占める比率をまとめると、表12のとおりであった。
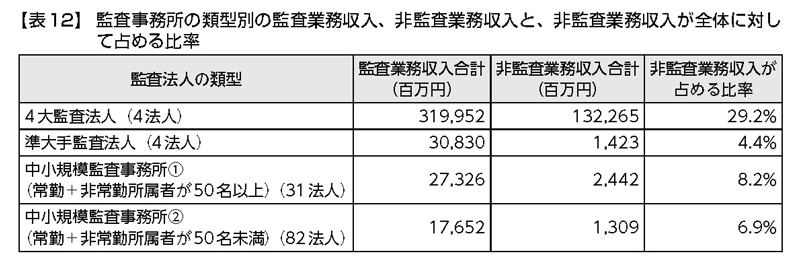
多様な人材を要して監査業務から非監査業務まで手広く手掛ける4大法人に対して、中小規模監査事務所は監査業務に注力する度合いが高くなっており、とりわけ、準大手監査法人の監査業務への注力ぶりが目に付く。特に準大手監査法人トップの太陽は、監査業務収入17,424百万円に対して、非監査業務収入は567百万円にとどまっていた。
最後に、業務収入が多かった上場会社監査事務所の上位10事務所を一覧にすると、表13のとおりであった。
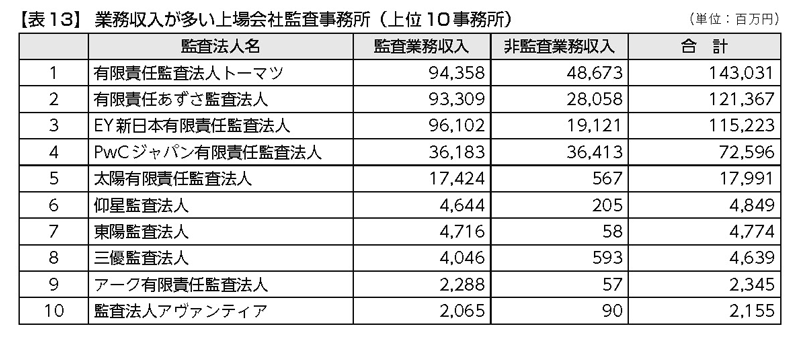
監査法人業務収入ランキングのトップ10のうち、PwCあらたとPwC京都が合併してPwCジャパンとなったため、空いた10位にアヴァンティアが新たに顔を出す形となった。
参考資料
日本公認会計士協会(JICPA)ホームページ 上場会社等監査人登録制度 及び登録上場会社等監査人情報
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























