解説記事2025年01月20日 ニュース特集 Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(Ⅱ)(2025年1月20日号・№1059)
ニュース特集
防衛特別法人税は企業全体の6%
Q&Aで読み解く令和7年度税制改正大綱(Ⅱ)
自民党税制調査会及び公明党税制調査会は令和6年12月20日、令和7年度税制改正大綱を決定。その後、同月27日には政府が「令和7年度税制改正の大綱」を閣議決定している。本特集では、所得課税及び資産課税を中心とした第一弾(本誌1057号4頁参照)に引き続き、法人課税などを中心に令和7年度税制改正大綱のポイントをQ&A形式で解説する。
特例税率の見直しの対象は中小企業全体の0.1%
Q
中小法人等の軽減税率の特例(15%)については、適用期限が令和9年3月31日まで2年延長される一方、特例税率の見直しが一部行われるとのことですが、どの程度影響がありますか。
A
令和7年度税制改正では、中小法人等の軽減税率の特例が一部見直され、所得10億円超の中小法人等は17%と2%引き上げることとしている。見直しの影響額は1社あたり+16万円としている。また、グループ通算制度の適用を受けている法人については、特例税率の対象から除外する。見直しの対象は、現行の特例税率の適用者の0.3%、中小企業全体の0.1%とされているため、多くの中小企業にとっては影響がない。
ただし、中小法人等の軽減税率の特例については、リーマンショックの際の経済対策として時限的に設けられた措置であることを踏まえ、令和9年度税制改正においてもその存続の可否を含めて検討が行われることになりそうだ。
B類型の設備に建物追加も要件のハードルは高い
Q
中小企業経営強化税制では、「売上高100億円超を目指す」中小企業に対して、インセンティブ措置としてこれまで認められていなかった建物を対象設備に追加されるとのことですが、中小企業であれば同税制の対象になると考えてよいのでしょうか。
A
売上高100億円超を目指す投資計画が、経営規模拡大要件を満たすものである場合に、その計画に基づいて行う工場のラインや店舗等の生産性向上に係る設備投資について、B類型(収益力強化設備)の対象資産に建物を追加するというもの。経済産業省によれば、同じB類型でも「経営規模拡大設備」と呼んでいる。
今回の改正は、所得が10億円超と高い中小企業の特例税率が見直される一方で、新たな投資減税を活用することで、特例税率の見直しを大きく上回る減税メリットを享受できるものとなっている。したがって、すべての中小企業が対象になるのではなく、経営力向上計画の認定を申請する事業年度の直前の事業年度の売上高が10億円超90億円未満等の中小企業が対象となる。
そのほか、給与等の支給額を増加させるものでなければならず、①賃上げ率2.5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却15%又は税額控除1%、②賃上げ率5%以上の計画の場合は、建物に対する特別償却25%又は税額控除2%となる。表1にもあるとおり、いくつかの適用要件があり、適用を受けるメリットは大きいものの、そのハードルは高いものとなっている。
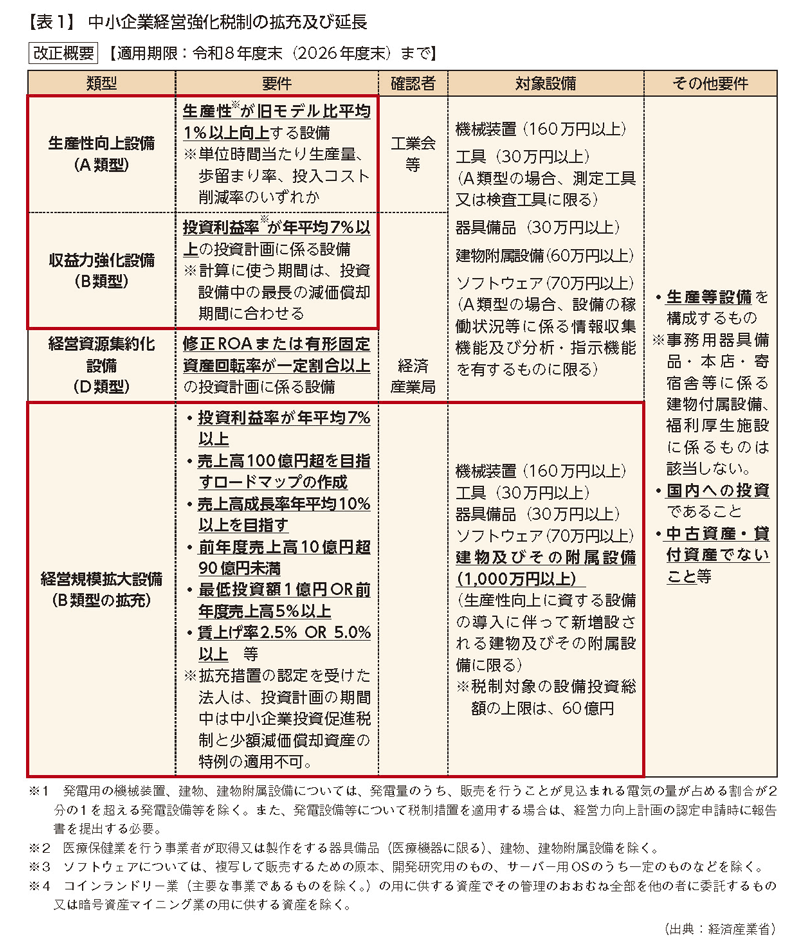
なお、現行の収益力強化設備(B類型)についても、これまで通り要件を満たせば適用することができる(令和9年3月31日まで)。ただし、投資利益率が年平均5%という要件については、年平均7%に引き上げられることになるため、留意したい。
固定資産税の特例は1.5%以上の賃上げ表明が必須に
Q
生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置については、適用期限の延長はありますか。
A
令和5年度税制改正で創設された投資利益率5%以上の投資計画に記載された①機械装置(160万円以上)、②測定工具及び検査工具(30万円以上)、③器具備品(30万円以上)、④建物附属設備(60万円以上)を対象(認定経営革新等支援機関が確認)として、課税標準を最初の3年間価格の2分の1とするもの。ただし、賃上げ方針を先端設備等導入計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、最大で5年間、課税標準が3分の1に軽減することができる。
令和7年度税制改正では、適用期限を2年延長するが、1.5%以上の賃上げ表明を先端設備等導入計画に掲載することが求められることになる。これを踏まえ、課税標準は、①1.5%以上の賃上げ表明の場合は3年間価格の2分の1に軽減、②3%以上の賃上げ表明の場合は5年間価格の4分の1に軽減することとされている。
地域未来投資促進税制の通常枠の特別償却は35%に
Q
地域未来投資促進税制(地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度)は、地域経済の実情に応じ、その発展・成長に特に資する分野に対する10億円以上の設備投資について新たな措置(特別償却50%又は税額控除5%)が追加された上、適用期限が3年延長されるとのことですが、そのほかの見直しはありますか。
A
地域未来投資促進税制は、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大6%)を受けることができるというもの。通常枠(特別償却40%又は税額控除4%)のほか、労働生産性の伸び率5%以上かつ投資収益率5%以上などの要件を満たすことで、特別償却50%又は税額控除5%に引き上げられる。令和7年度税制改正では、上乗せ措置について、創出される付加価値が1億円以上、かつ、自治体が指定する地域の経済発展・成長に特に資する分野に該当する事業であって、設備投資額が10億円以上を新たな類型として追加する(表2参照)。
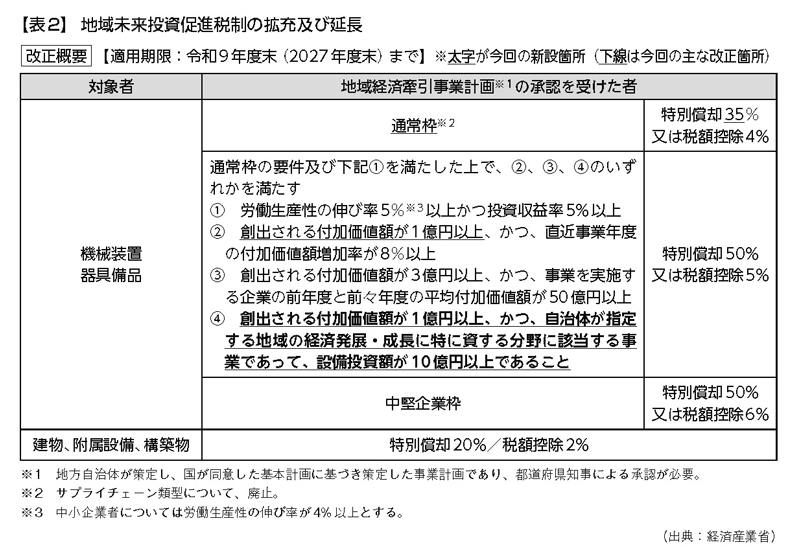
ただし、いくつか厳しい方向で現行制度を見直す改正も予定されているので留意したい。例えば、通常枠に関しては、特別償却は40%となっているが、35%に引き下げられる。また、上乗せ措置の要件の1つである「直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上」については、「創出される付加価値額が1億円以上」との要件が追加されることになっている。
企業グループ内再編もOK
Q
中小企業・小規模事業者の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の拡充が行われるとのことですが、具体的にどのような見直しが行われるのですか。
A
次世代への経営引き継ぎを促す観点から、中小企業が、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた経営力向上計画にしたがい、事業譲渡により取得した不動産に係る不動産取得税については一定の軽減措置が講じられ、令和6年度税制改正により適用期限が2年(令和8年3月31日まで)延長されたところだ。
今回の見直しでは、適用対象に企業グループ内の法人間で行われる一定の事業譲渡についても対象に加えることとしている。企業の更なる成長に向けて、親会社の強みの横展開、シナジー効果の発揮、経営の効率化といった効果が見込まれるグループ化の取組みを促すとしている。
延払基準をやめた場合の賦払金の残額を10年均等で
Q
リース会計基準の改正に伴い、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例が廃止されるとのことですが、激変緩和措置などは講じられるのでしょうか。
A
令和9年4月1日以後に開始する事業年度等から新たなリース会計基準が適用されることになった。国際的な会計基準との整合性の観点から、ファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースについて資産及び負債に計上することになる。
令和7年度税制改正では、会計基準を踏まえて税制が改正されるか否かが注目すべき点の1つであったが、本誌1054号でお伝えしたとおり、税制については改正されず、オペレーティング・リースは、現行どおり費用処理が可能となっている。申告調整等の企業のコストは増えるものの、税負担についてはこれまでどおりで決着している。
ただし、リース会計基準において、現行の貸手の第2法(受取リース料を各期において売上高として計上し当該金額からリース期間中の各期に配分された利息相当額を差し引いた金額を売上原価として処理する方法)の会計処理が廃止になったことを踏まえ、税制についても、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例は廃止されることになった。
この点については、リース事業会社の税負担が大きいことから、令和9年度3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準によって収益及び費用の額を計算できるとともに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度において、延払基準をやめた場合の繰延リース利益額を5年均等で収益計上する旨の経過措置が講じられる(法人税及び所得税)。
また、消費税に関しては、貸手は、各課税期間において開始したリース取引に係るリース料の総額に対して消費税が課されるが、消費税を借手に転嫁できずに資金負担が求められ、大きな影響があることから、令和12年3月31日以前に開始する事業年度において行ったリース譲渡について、延払基準によって収益及び費用の額を計算できるとともに、令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、延払基準をやめた場合の賦払金の残額を10年均等で資産の譲渡等の対価の額とする経過措置を講じるとしている。
防衛特別法人税の課税対象は約6%
Q
新たに防衛特別法人税が創設されるとのことですが、どの程度の企業に影響があるのでしょうか。
A
令和7年度税制改正では、所得税の増税時期決定は先送りされたものの、防衛特別法人税(仮称)については、法人税額に対し税率4%の新たな付加税を課すものとして、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになった。
ただし、課税標準となる法人税額から500万円を控除することとされているため、財務省によると、対象となるのは企業全体の6%程度としている。
公益信託制度に「承認特例」が追加
Q
令和6年度税制改正では、公益信託制度について、寄附金控除、譲渡所得課税非課税の特例(一般特例に限る)など、公益法人と概ね同様の優遇措置が手当てされています。令和7年度税制改正では、どのような見直しが行われますか。
A
公益信託制度については、令和6年5月、「公益信託ニ関スル法律」(大正11年法律第62号)を全部改正した「公益信託に関する法律」(令和6年法律第30号)が公布され、令和8年4月より施行される予定となっている。公益信託の税制優遇に関しては、新しい公益信託法において認可基準等を法定し、公益法人と共通の枠組みで認可・監督する制度としたことを踏まえ、令和6年度税制改正において、これまで信託財産として受け入れる財産を金銭に限る等、一定の要件を満たしたもののみが優遇を受けていた税制を見直し、新しい公益信託法によって認可を受けたすべての公益信託が公益法人並みの税制優遇を受ける制度となった。また、公益法人等に金銭以外の財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税措置の「一般特例」について、公益信託もその対象に追加された。
ただし、昨年度の改正では、「一般特例」のみ認められ、「承認特例」が認められていなかったことから、令和7年度税制改正では、公益信託制度が公益法人と共通の枠組みで認可・監督される制度であることを踏まえ、譲渡所得等非課税の「承認特例」の対象として追加することとしている。これにより、承認申請の手続きが大幅に簡素化されることになる。
固定資産税等の納税通知書の電子送付は令和9年4月から開始へ
Q
地方税関係通知のうち、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車税種別割の納税通知書等については、納税者の求めに応じ、地方自治体がeLTAX(地方税のオンライン手続のためのシステム)を経由して電子的に副本を送付することができることになるとのことですが(本誌1052号参照)、いつから適用されることになりますか。
A
まず、電子的送付を行う地方税関係通知の範囲は、固定資産税、都市計画税、自動車税種別割、軽自動車税種別割における納税通知書(課税明細書、更正決定通知書及び税額変更通知書を含む)及び納付書等のこれに附属する通知となる。納税者が納税通知書等(正本)に付された地方税統一QRコード(eL−QR)を読み取り、電子送付希望の申出をした場合に、電子的に送付されることになる。
適用に関しては、法人に対して送達する納税通知書等は令和9年4月1日以後に送達するものから、個人に対して送達する納税通知書等は令和10年4月1日以後に送達するものからとされている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
情報がありません
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

















