解説記事2025年03月31日 税務マエストロ インボイスの取扱いに関するご質問(2025年3月31日号・№1068)
税務マエストロ
インボイスの取扱いに関するご質問
#306
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
令和7年2月25日に国税庁から「インボイスの取扱いに関するご質問」が公表された。「更新」と書かれているので、「お問合せの多いご質問」からタイトルを変更しただけのようである。看板だけ付け替えて、しばらくはこのフォーマットで掲載を続けるということなのであろう……。今回は、「インボイスの取扱いに関するご質問」の内容を検証する。
国税庁の資料について
「お問合せの多いご質問」は、インボイスQ&Aが改訂されるまでの繋ぎ情報としての側面があると考えている。次の改訂までの新規のQ&Aを「お問合せの多いご質問」として不定期に更新し、一定の時期にインボイスQ&Aに組み込んでいくという作戦である。
現に、「お問合せの多いご質問」にストックされていた①から までの内容は、令和6年4月8日に改訂されたインボイスQ&Aに追加又は追記した上で削除されている。今回は、問の番号が「
までの内容は、令和6年4月8日に改訂されたインボイスQ&Aに追加又は追記した上で削除されている。今回は、問の番号が「 ……」から「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ……」とローマ数字に変更されているのだが、インボイスQ&Aを改訂し、「お問合せの多いご質問」にストックされていた
……」から「Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ……」とローマ数字に変更されているのだが、インボイスQ&Aを改訂し、「お問合せの多いご質問」にストックされていた の内容をインボイスQ&Aに追加又は追記するつもりはないようだ。それとも、しばらくしてからインボイスQ&Aも改訂するつもりなのであろうか……?
の内容をインボイスQ&Aに追加又は追記するつもりはないようだ。それとも、しばらくしてからインボイスQ&Aも改訂するつもりなのであろうか……?
ところで、五月雨式に公表されている国税庁の資料であるが、実に統一性がとれていない。よって、現時点でどのような資料が公表されているのかということは、しっかりと整理しておかなければならない。
国税庁が公表している資料には、「お問い合せの多いご質問」のほか、「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」、「インボイス制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」、「公表サイトに関するよくある質問」、「適格請求書発行事業者公表サイトの運営方針」など、紛らわしい名称の資料が乱発されている。このほかにも、財務省から「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」なるものも公表されているので、これらの情報を一覧にして整理していただかないと、収拾が付かないような気がしている。ついでに言えば、内容のイメージが重複してしまうような中途半端なタイトルは一掃して、もう少しセンスの良いタイトルにしていただきたい。
……と、愚痴はこれくらいにして、実務家にとって重要性が高いのは、令和6年4月に改訂されたインボイスQ&Aのほか、下記の情報ではないかと思われる。本誌における解説記事を参考に、確認と整理をしていただきたい。
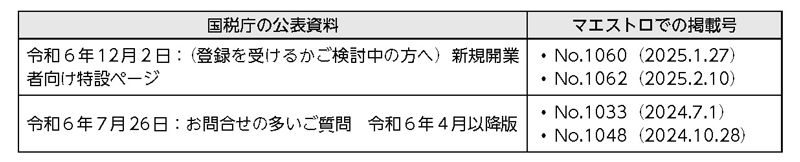
インボイスの取扱いに関するご質問
問Ⅰ(現金主義を適用する事業者における仕入税額控除のタイミング)
私は、現金主義を適用しており、課税仕入れを行った時期をその仕入れに係る費用の額を支出した日としています。ある取引につき、費用の支出を行ったものの適格請求書の受領が翌年になってしまいましたが、現金主義により、費用の支出を行った課税期間において仕入税額控除の適用を受けることはできますか。
<ポイント>
現金主義の特例の適用を受ける個人事業者は、資産の譲渡等及び課税仕入れを行った時期について、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることが認められている(消法18、消令40、消規12)。
そこで、発生主義による課税仕入れ等の時期と現金主義による仕入税額控除の時期が異なるような場合でも、インボイスの保存を条件として、仕入税額控除を認めることとしたものである。
ところで、【答】では「……事後に交付される適格請求書を保存することを条件として、当該支出した日の属する課税期間において仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。」と説明しているが、実務の世界では、請求書に基づいてまずは買掛金を計上し、支払期限に買掛金の支払いをするのである。適格請求書が事後(支払後)に交付されるのは、前払金につき、課税仕入れが行われた場合だけであるから、この解説はいささかピントがずれているように思われる。
なお、前払金を仕入税額控除の対象とした翌課税期間において、前払額と実際の課税仕入高が異なる場合には、その差額は翌課税期間の課税仕入高に加減算することにより調整する(インボイスQ&A問96)。
また、法人税(所得税)の申告において、短期前払費用の取扱いにより、支出時に仕入税額控除の適用を受ける場合についても、インボイスの保存を条件に、仕入税額控除が認められている(インボイスQ&A問98)。
参考 現金主義会計とは?
1 適用要件
前々年の不動産所得の金額及び事業所得の金額の合計額が300万円以下の個人事業者が、所得税法67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)により所得計算をしている場合に限り、消費税計算においても現金主義会計によることが認められている。
2 選択基準
上記1のとおり、現金主義会計の特例は、所得税において特例制度の適用を受けていることが要件となるが、強制されるものではない。よって、所得税の申告で特例制度の適用を受け、消費税では発生主義によることも認められる(消法18、消基通9−5−1)。
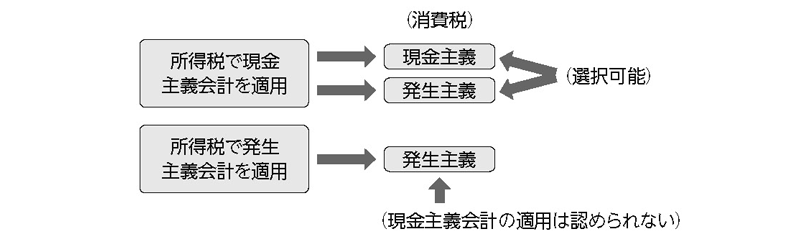
3 発生主義へ変更することとなった場合の処理
現金主義会計から発生主義会計へ変更することとなった場合には、変更する直前の課税期間において、次のような処理をすることになる。
(1)資産の譲渡等に係る売掛金の取扱い(消令40①一、消規12②~④)
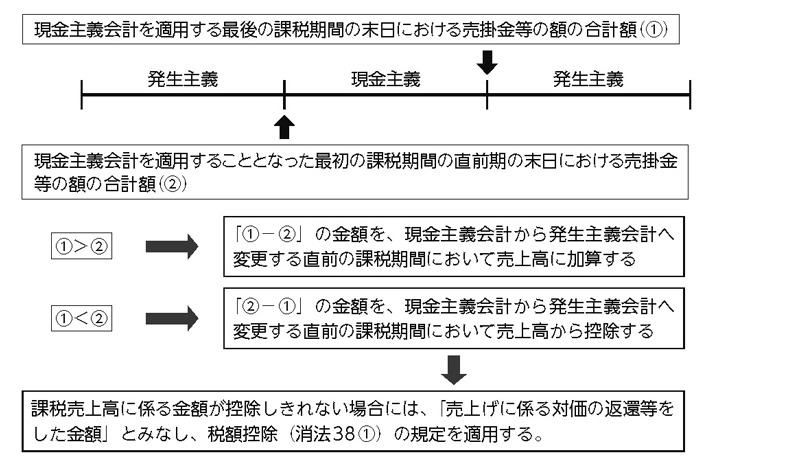
(2)資産の譲渡等に係る前受金の取扱い(消規12①一、②~④)
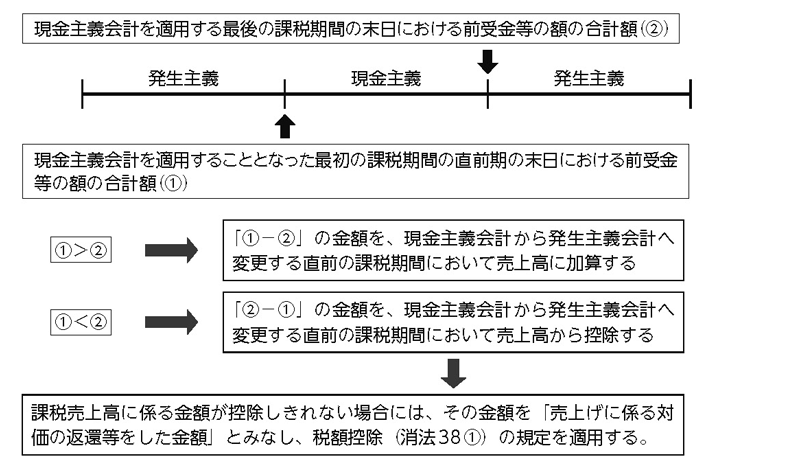
(3)課税仕入れに係る買掛金の取扱い(消令40①二、消規12⑤~⑥)
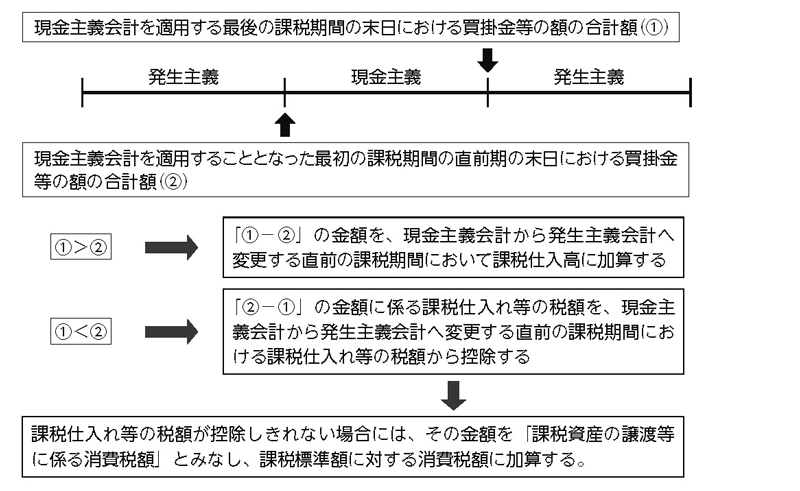
(4)課税仕入れに係る前払金の取扱い(消規12①二、⑤~⑥)
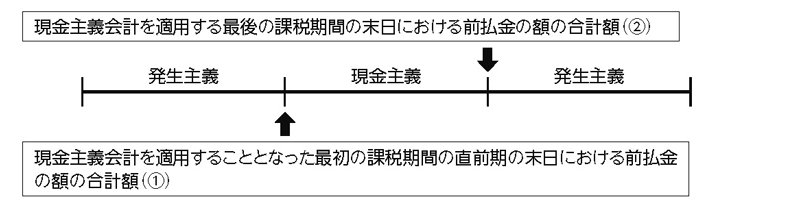
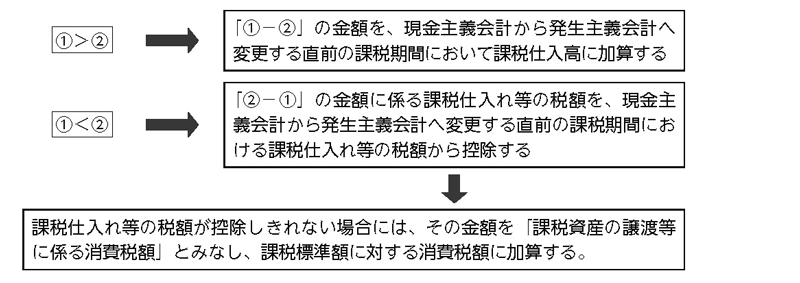
4 事例(現金主義会計と納税義務(2割特例)の判定)
x1年に開業し、現金主義会計により所得税の申告をしている個人事業者が、x3年から発生主義に変更することにした。これに伴い、x2年の年末における売掛金200万円は、x3年の売上高として計上している。
この場合におけるx5年の納税義務(2割特例)の適用判定は、基準期間であるx3年の課税売上高が1,000万円以下(900万円)であることから免税事業者となり、インボイスの登録をしている場合には2割特例の適用を受けることができる。
なお、x2年の末日における売掛金200万円は、消費税法ではx3年ではなく、x2年の売上高(入金額)600万円に加算することとなる。結果、x2年の課税売上高は1,000万円以下(600万円+200万円=800万円)となり、x2年を基準期間とするx4年についても免税事業者となることができる。
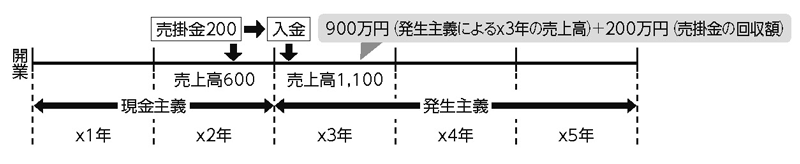
問Ⅱ(任意組合の構成員が帳簿へ記載すべき課税仕入れの相手方の氏名又は名称)
当社は、複数の取引先と任意組合を組成し事業を行っています。任意組合の課税仕入れについては、幹事会社が課税仕入れの相手先から受領した適格請求書の原本を保存し、当社を含めた構成員は幹事会社から精算書のみを受領しています。当社が仕入税額控除の適用を受けるに当たり、帳簿に「課税仕入れの相手方の氏名又は名称」をどのように記載すればよいでしょうか。
<ポイント>
任意組合の課税仕入れについては、幹事会社がインボイスの保存をすることを条件に、構成員はインボイスのコピーや精算書の保存により仕入税額控除が認められている(インボイスQ&A問93)。
この場合において、構成員は幹事会社に確認の上、帳簿に法定要件を記載することが義務付けられているが、幹事会社において課税仕入れ毎に相手方の氏名、名称、登録番号などが管理されており、構成員が必要に応じ確認できるような場合には、構成員は、帳簿に幹事会社の名称及び幹事会社を経由して行った課税仕入れである旨の記載をすればよいこととされた。
ただし、80%(50%)経過措置の対象となる課税仕入れについてはその旨の記載が必要となる。
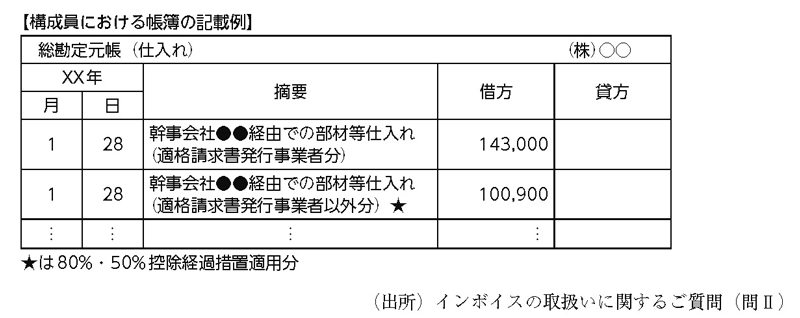
問Ⅲ(任意組合の組合員のうち事業の損益の配賦を受けない者の取扱い)
私は、任意組合の業務執行組合員であり、当任意組合には世界中に組合員が存在しています。これらの組合員の中には日本で活動を行っておらず、かつ、日本における事業の損益の配賦を直接又は間接にも受けていない組合員が含まれています。
そうした者についても適格請求書発行事業者としての登録を受け、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出しなければ、当任意組合は任意組合の事業としての適格請求書の交付を行うことはできないのでしょうか。
<ポイント>
任意組合等は、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出することによりインボイスの発行が認められている。
ただし、下記の①及び②に該当する組合員については、届出書制度の対象とする必要はない。
①日本で課税資産の譲渡等を行っていないこと
②日本における事業の損益の配賦を直接又は間接にも受けないこと
なお、上記の組合員が日本における事業の損益の配賦を受けることとなる場合には、下記の届出書を速やかに提出する必要がある。
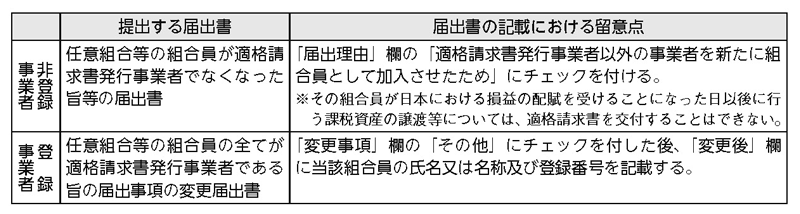
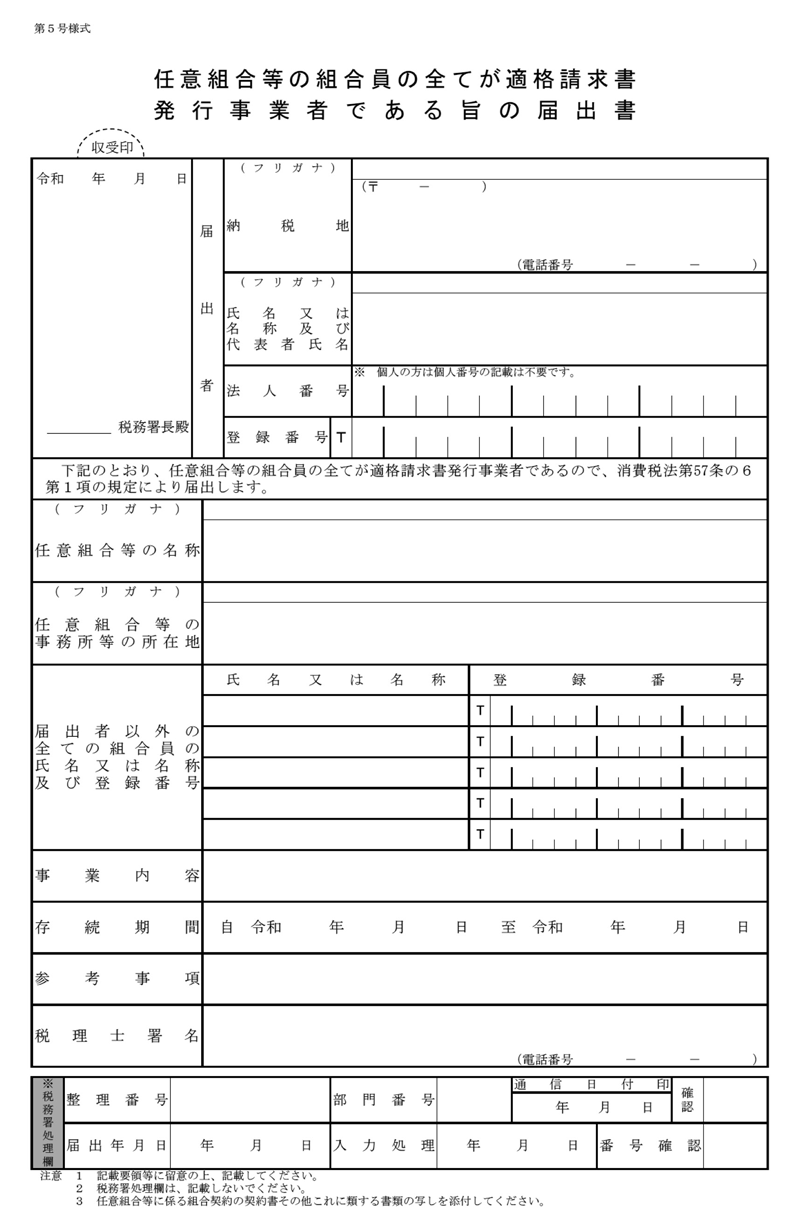
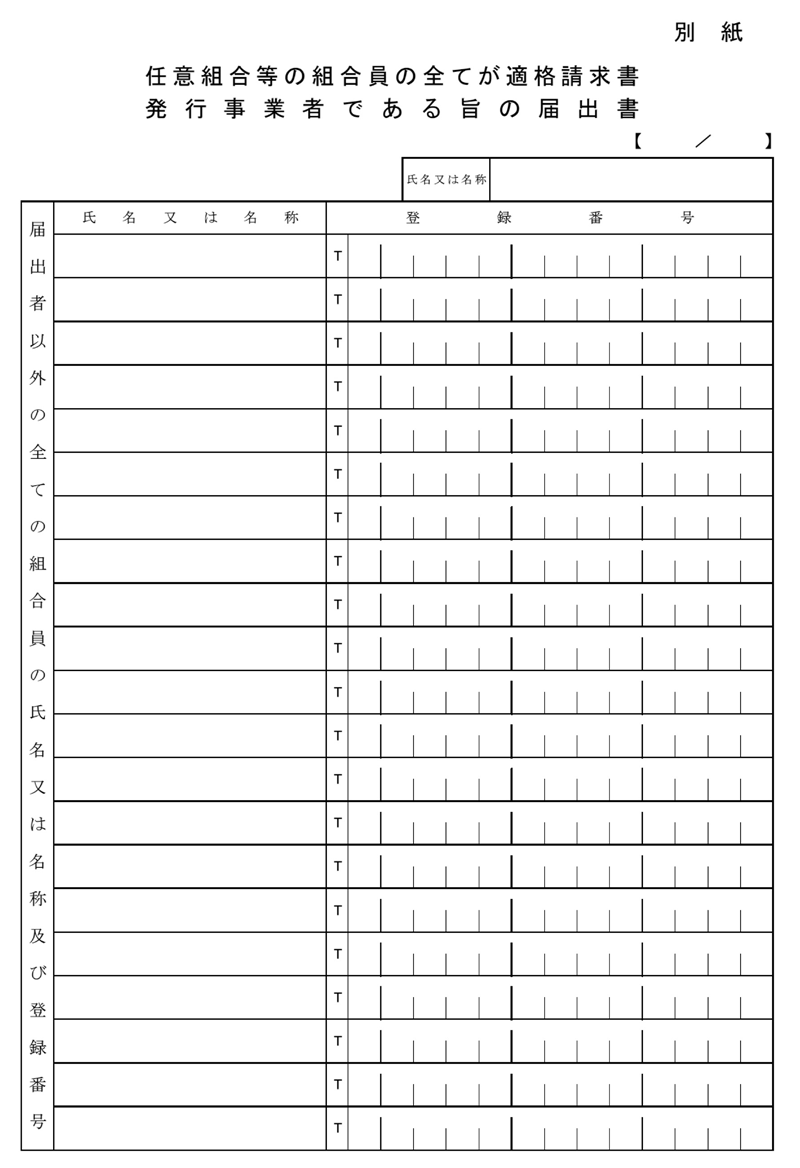
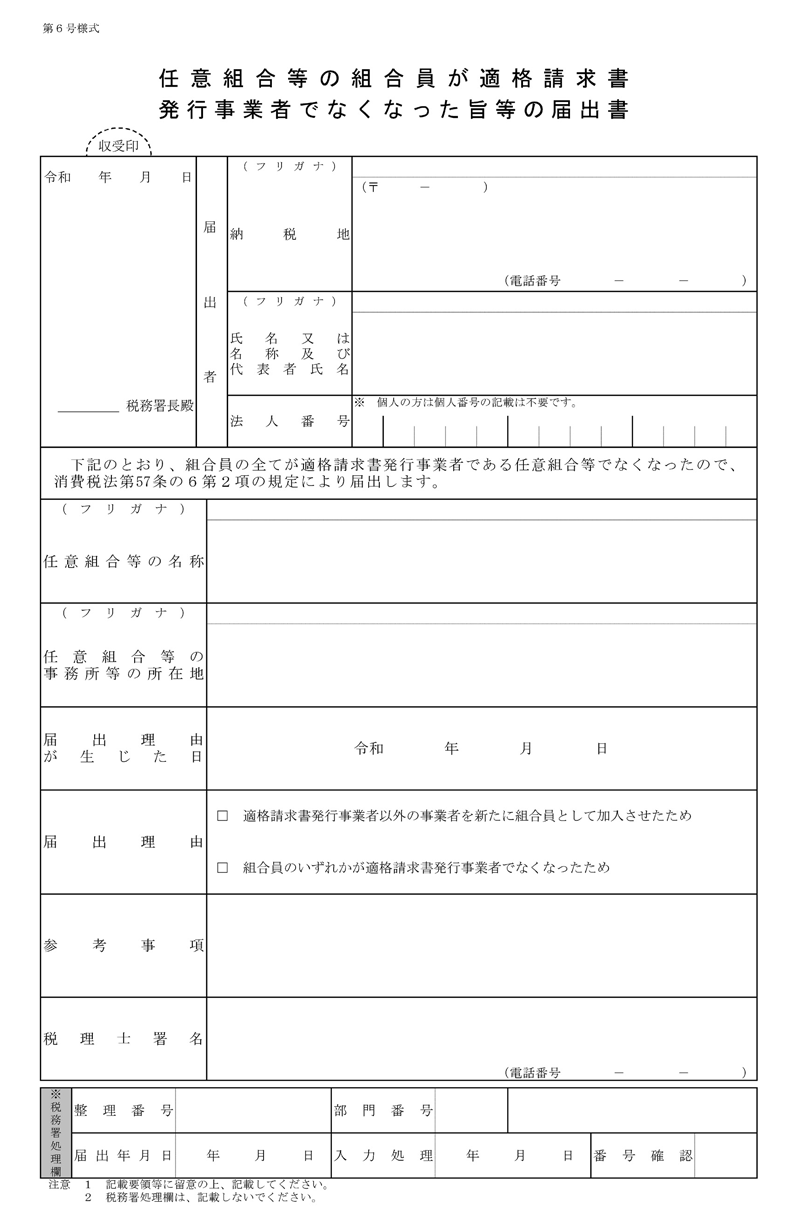
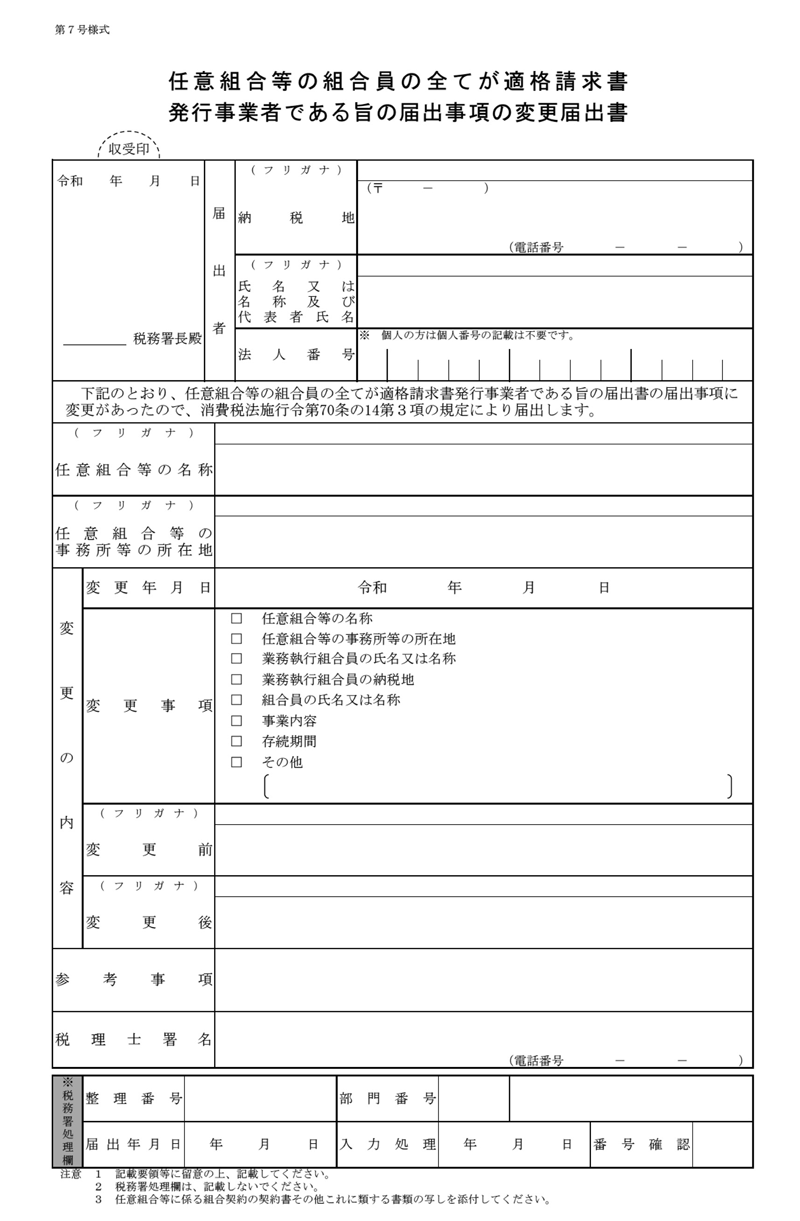
問Ⅳ(適格請求書の記載事項のインターネットでの公表)
当社では、交付する領収書において、当社のホームページのURLを案内しておき、当該URLに適格請求書の記載事項の一部である適格請求書発行事業者の名称及び登録番号、適用税率を表示した上で、当該領収書を受領した事業者においていつでも確認可能な状態にしてあります。このような方法により、適格請求書の記載事項を満たすことは可能ですか。
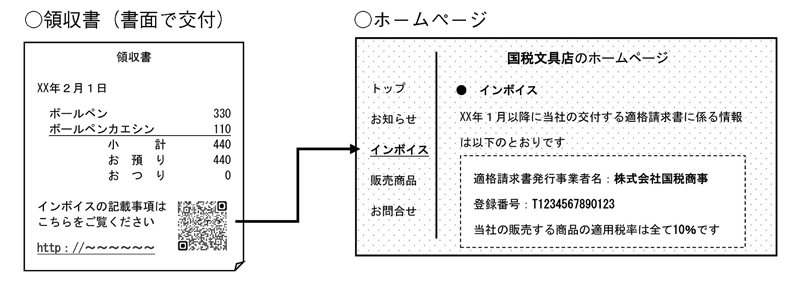
<ポイント>
インボイスは、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はないので、書類相互の関連が明確で、その取引を正確に認識できる方法で交付されていれば、複数の書類や書類と電磁的記録の全体により、適格請求書の記載事項を満たすことになる(インボイスQ&A問72)。
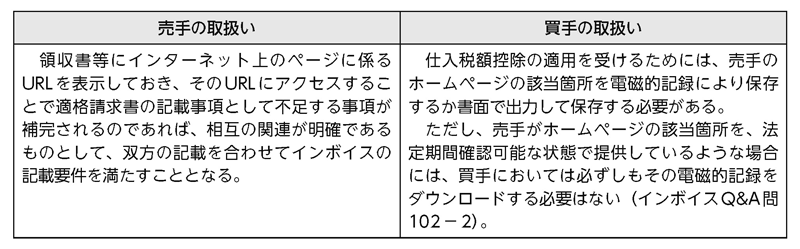
記事に関連するお問い合わせ先
記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























