解説記事2025年03月31日 解説 「会社法の改正に関する報告書」の解説(2025年3月31日号・№1068)
解説
「会社法の改正に関する報告書」の解説
経済産業省経済産業政策局産業組織課 課長補佐 川﨑靖之
一.はじめに
1 経 緯
経済産業省は、本年1月17日、「会社法の改正に関する報告書」(以下「報告書」という。)を公表した。
本報告書は、昨年9月に立ち上げた、「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会」(座長:神田秀樹 東京大学名誉教授)(以下「研究会」という。)における議論を踏まえて取りまとめを行ったものである。
本稿では、趣旨や背景、研究会においてなされた議論も紹介しつつ、報告書の概要を解説する。紙面の都合上、一部の項目については概要を記載するにとどめているが、その詳細については報告書本体を参照いただきたい。
2 検討の背景・報告書の全体像
昨今、企業を取り巻く経営環境は更に複雑化しており、経営陣は難しい舵取りを迫られている。企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していくためには、サステナビリティを経営に織り込むことが不可欠となっており、インフレ環境の下において、従業員の賃上げや取引先・サプライチェーンとの適正価格取引等、ステークホルダーに対する適正な利益配分の要請が一層高まっている。同時に、今後、サステナビリティ関連情報(気候変動関連、人的資本関連等)の開示の要請もますます高まることも予想される。また、2023年3月には東京証券取引所より「資本コストや株価を意識した経営」の実現が要請される等、資本コストや資本収益性を十分に意識した上で、事業ポートフォリオの最適化や成長投資を行っていくことの重要性が資本市場の視点からも高まっている。
こうした経営環境において、日本企業が経営資源を積極的に成長投資に振り向け、高い付加価値を創出し、「稼ぐ力」を強化していくためには、社会課題やステークホルダーについても考慮しつつ、自社の競争優位を生み出す価値創造ストーリーを構築し、それを確実に実行していくことが必要であり、そのためには株主・投資家との対話を通じて、その内容を磨き上げ、信頼関係を築いていくことが重要となる。その上で、多くの上場企業が積極的な成長投資を持続的に行っていくためには、各企業が自社の競争優位を生み出す価値創造ストーリーの構築と実行を支える経営基盤を整備していく必要があり、コーポレートガバナンスはこうした経営基盤の一つである。
そして、政府においては、このような経営者の判断を株主等から後押しするための環境整備(企業経営・資本市場一体改革)を進めることが求められている。その一環として、企業の「稼ぐ力」の強化に向けて、企業経営者が大胆なリスクテイクを行い、成長投資を実行していくことを後押しする観点から、企業活動の基盤である会社法制についても、企業の価値創造ストーリーを実行するための選択肢の拡大や、企業と株主の意味のあるエンゲージメントの促進(対話の実質化・効率化)等に資する制度見直しを早期に図ることが重要と考えられる。
加えて、日本企業の企業経営や企業を取り巻く資本市場の今後の変化も踏まえつつ、自社に最適なコーポレートガバナンス体制に密接に関係する機関設計の在り方や、株主総会の在り方についても、両者を一体的な論点としてとらえて更なる検討を深めていくことが必要である。
そこで、報告書では、第2章において価値創造ストーリーを実行するための企業の選択肢の拡大に資する事項について、第3章においては機関設計の在り方について、そして第4章においては企業と株主のエンゲージメントを実質化・効率化に資する事項について、それぞれ改正の方向性を提示している。
二.価値創造ストーリーの実行
企業が構築した価値創造ストーリーを実現し、「稼ぐ力」の強化につなげていくためには、これらのストーリーやそれに基づく具体的な成長戦略を、円滑に実現することを可能とするソフトインフラを整備することも重要である。
例えば、上場株式の流動性を活用するという観点から、従業員や子会社の役職員に対する自社株式の無償交付を可能とすることや、自社株式を対価とするM&Aの活用をより広範囲にかつ簡易な手続で実施可能とすることは、価値創造ストーリーを実行する上で不可欠な成長投資の手段を多様化するという意義を有する。
また、上場会社を完全子会社化する際に通常必要となる手続(キャッシュ・アウト)を、より機動的に可能にすることで、上場企業間の大規模な買収を通じた攻めの成長投資、更には業界再編を活性化することが期待できる。加えて、上場を維持することの長短を踏まえ、自社の成長戦略として非上場化を選択した企業が円滑にそれを実行する手段を整備するという意義も認められる。
また、成長投資に必要な資金調達の手段を多様化することも重要である。現状、国内の民間非金融法人企業が利用するデットファイナンスのうち、8割以上を借入が占めており、社債の利用は約1割と低水準にとどまっているが、バーチャルの方法による社債権者集会の迅速な開催を可能とすることは、社債市場の活性化に寄与するものと考えられる。
そして、業務執行取締役や執行役が会社との間で責任限定契約を締結できるようにし、業務執行取締役等が個人で負担するリスクの予見可能性を高めることは業務執行取締役等の適切なリスクテイクを促進するうえで有意義と考えられる。
そのような観点から、第2章では従業員・子会社の役職員に対する株式の無償交付、株式対価M&A、キャッシュ・アウト、社債権者集会のバーチャル化、責任限定契約について改正の方向性を提示している。本稿では、これらのうち、従業員・子会社の役職員に対する株式の無償交付及び責任限定契約について取り上げることとしたい。
1 従業員・子会社の役職員に対する株式の無償交付
人的資本への投資が生み出すイノベーションによって社会課題を解決し、それに見合った利益を実現することは、企業の「稼ぐ力」を強化し、中長期的に企業価値を向上させていく上で非常に重要な要素である。とりわけ、従業員に対して株式を付与することは、企業価値や株価に対する意識を高める効果や、帰属意識の醸成効果が期待でき、人材の価値を引き出しながら企業価値を高めていく上で有意義と考えられる。
日本企業においても従業員に対して株式を付与する企業数は増加傾向にあるものの、欧米諸国と比較すると、依然として低水準にある。グローバルな人材の獲得競争の中で、日本企業が競争力を高めていくためには、通常の賃上げに加えて、上場株式の流動性を活用し、従業員に対する株式の付与を拡大していくことは重要である。
現行法上、従業員や子会社の役職員(以下「従業員等」という。)に対する株式の無償交付は認められていない。そのため、現行法下で従業員等に株式を付与する場合は、従業員が金銭債権を現物出資するという技巧的な方法(以下「現物出資構成」という。)によらざるを得ず、会計上の処理等において実務上の負担が生じているとの指摘がある。
このような問題意識から、一般社団法人日本経済団体連合会による「役員・従業員へのインセンティブ報酬制度の活用拡大に向けた提言」(2024年1月16日)では、従業員等に対しても株式の無償交付を認めることが提言されており、研究会においても、従業員等への株式の付与の重要性や、現物出資構成についての実務上の負担を指摘する意見が多く見られたところである。このような議論を踏まえ、報告書では、従業員等への株式の付与を拡大していくために、従業員等に対する株式の無償交付を可能とすることを提言している。
また、従業員等に株式を無償交付した場合には、1株当たりの価値が下落(株式価値の希釈化)し、既存株主の利益が害されるおそれがあり得るため、無償交付に際しては株主総会決議を必要とすべきとの指摘も存在することから、研究会ではこの点についても検討を行った。研究会では、「従業員に株式を付与した場合には労働意欲の向上等の効果が得られるため、株式価値の希釈化は生じない」といった意見や、「既に現物出資構成により株式付与を行っている企業が一定数存在する以上、無償交付に株主総会決議が要件とされた場合は、新制度が利用されないのではないか」といった意見が見られた。このような議論を踏まえ、報告書では、無償交付に際しては株主総会決議を不要とすることが望ましい旨を指摘している。
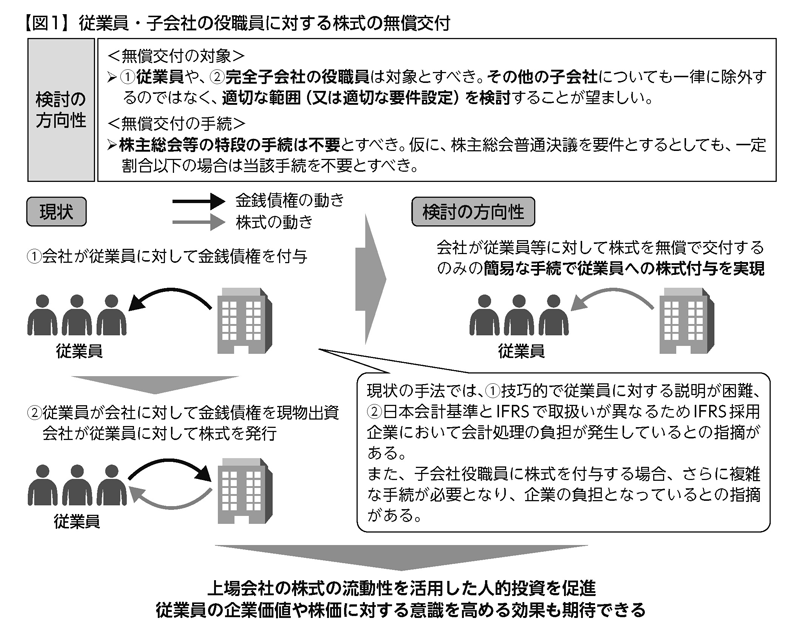
2 責任限定契約
企業を取り巻く外部環境が複雑化している中、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するためには、そうした外部環境を成長機会として捉え、中長期目線での攻めの成長投資を行っていく必要がある。そのためには、既存路線の単なる継続や延長線上の対応ではなく、大胆な経営改革を行うことも重要な意味を持ち、各企業のコーポレートガバナンス体制や、その基盤となる法制度はこのようなリスクテイクを後押しするものである必要がある。
現行法上、業務執行取締役・執行役(以下「業務執行取締役等」という。)の任務懈怠責任の全額を免除するためには総株主の同意が必要とされている。また、悪意や重過失がなく、任務懈怠責任の一部を免除するにすぎない場合も、都度、事後的に株主総会の特別決議等の手続を経ることが必要とされている。そのため、業務執行取締役等において、悪意や重過失なく負担した任務懈怠責任についても、免除されるか否かについて予見可能性が認められない状況となっている。責任限定契約(会社に対する任務懈怠責任を予め一定額に限定する契約)は悪意や重過失なく任務懈怠責任を負担した場合の責任上限額を定めるものであり、業務執行取締役等が個人で負担するリスクの予見可能性を高めるものと考えられるが、現行法上、業務執行取締役等は責任限定契約を締結することができない。研究会では、このことが業務執行取締役をリスク回避的とし、大胆な経営戦略の実現の妨げになっているとの指摘がなされたところである。
このような議論を踏まえ、報告書では、経営者の適切なリスクテイクを可能とし、大胆な成長戦略の実現を後押しするという観点から、業務執行取締役等も責任限定契約を締結できるようにすることを提言している。
三.機関設計
各企業における機関設計(監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社)は各企業におけるコーポレートガバナンス体制の基盤となるものであり、機関設計制度は、各企業が最適なコーポレートガバナンス体制を実現することを可能とし、後押しするものであることが必要である。
指名委員会等設置会社は、取締役会の監督機能を重視する企業になじむ機関設計と考えられている。しかし、社外取締役が取締役の過半数を占める場合でも、指名・報酬委員会の決定を覆すことができない点で、そのような企業においても使いにくい制度となっているとの指摘が見られるところである。すなわち、現行法上、指名委員会等設置会社における取締役候補者の指名権限や、取締役・執行役の報酬の決定権限は、それぞれ指名委員会・報酬委員会に帰属し、取締役会はその決定を覆すことはできないこととされているが、取締役会の中の一機関である指名委員会ではなく、取締役会自体が取締役候補者の指名権限を有するべきであるとの指摘である。
そもそも、指名委員会等設置会社の制度創設時は、社外取締役の適任者が少なかったことに鑑みて、社外取締役が過半数を占める取締役会と同等の監督機能を果たすことができるよう、社外取締役が過半数を占める委員会に指名・報酬の決定権限を帰属させたものであった。しかし、2024年10月時点において、指名委員会等設置会社を採用する上場企業のうち、取締役会の過半数を社外取締役が占める企業の割合が80%存在する中、制度策定時の趣旨は妥当しないとも考えられ、例えば、一般社団法人日本取締役協会は、そのような観点から、指名委員会等設置会社に関する制度見直しの提言を行っている。
他方、そのような問題は実務上の工夫で解決が可能であり改正の優先度は高くないため、拙速に制度の一部のみを改正するのではなく、近年の社会経済環境の変化を踏まえて、機関設計制度全体について見直していくべきとの指摘も存在する。例えば、モニタリングモデルを志向する企業において使いやすい機関設計制度を整備するのであれば、委員会の権限のみを見直すのではなく、株主総会と取締役会の権限配分の在り方、ひいては株主権の在り方等との関連性も意識しながら制度全体について見直しを検討するべきであるといった意見も見られるところである。
そこで研究会では、指名委員会等設置会社における委員会の権限の優先的な見直しの要否について検討を行った。
研究会では活発な議論がなされたものの、以下のとおり、優先的な見直しの要否について意見の一致が見られなかったため、報告書では双方の意見を記載した上で、優先的な見直しの要否については引き続き検討していく必要がある旨を指摘している。
【優先的に見直すべきとの意見の例】
指名委員会等設置会社の数自体は多くないものの、指名委員会等設置会社への移行を検討する際に、指名委員会に指名の最終決定権限があることがその障壁となっているという企業の事例はよく聞くところであり、優先的に議論すべきである。
【優先的な見直しは不要とする意見の例】
一部の取締役のみが参加する委員会が取締役候補者の決定をすることについて問題が生じているのであれば、議論の仕方や、委員会での議論が適切に取締役会に報告されていないこと等に起因する問題、すなわち(制度の問題ではなく)運用上の問題ではないか。
四.エンゲージメント(対話の実質化・効率化)
「稼ぐ力」を強化していくためには、株主・投資家とのエンゲージメントを通じ資本市場からの意見・評価を受け止めた上で、価値創造ストーリーを磨き上げ、投資家を含む社会からの信頼を獲得していくことも重要である。
このような建設的なかつ実効的な対話を実施するためには、企業と株主の双方から必要かつ十分な開示を行うとともに、対話に際して非効率が生じている事項があればそれを解消し、より建設的かつ実効的な対話に企業・株主の人材や時間を割くことができるようにすることは重要であると考えられる。
具体的には、企業が、実質株主に関する情報を正確かつ効率的に把握できるようにすることは、企業と株主の信頼関係の醸成を促進し、企業から株主に対して対話を申し入れることが容易になるという点で重要である。また、事業報告及び計算書類と、有価証券報告書を一体の書類として同時に開示(以下「一体開示」という。)し、開示書類の作成作業を効率化・合理化することにより、非財務情報等の開示の質を高めることに人材や時間を活用できるようになる可能性がある。
また、企業と株主の対話の場として考えられてきた株主総会について、非効率を指摘する声も見られるところであり、その実態を踏まえて手続の効率化・合理化を進めることは、建設的・実効的なエンゲージメントを総体として後押ししていく上でも有意義であると考えられる。
このような観点から、第4章では実質株主の情報開示、一体開示、バーチャルオンリー株主総会、株主提案権、書面決議、株主総会の在り方について改正の方向性を提示している。本稿では、これらのうち、実質株主の情報開示、一体開示及び株主総会の在り方について取り上げることとしたい。
1 実質株主の情報開示
企業が株主とのエンゲージメントを行うためには、株式の議決権の指図権限を有する実質株主が誰であるかを把握することが重要である。例えば、企業規模が小さく、機関投資家側からは対話を打診されないような企業において、(民間のサービスである実質株主判明調査を利用して取得した)実質株主情報を活用することで、企業側から対話を打診している事例も見られる。
しかし、現行制度上、大量保有報告制度の適用対象となる場合を除き、企業が実質株主を把握する制度が存在しない。また、大量保有報告制度に基づき開示されている情報は、企業がエンゲージメントの際に利用する情報としては、その閾値(5%)や、その実効性(提出遅延が多い等)の観点から課題が指摘されているところである。そこで、企業によっては民間のサービスを利用して実質株主判明調査を行っている(経済産業省が実施した委託調査によれば50%以上の上場企業が定期的に実質株主判明調査を行っている。)が、把握できる株主の範囲等について課題が指摘されているところである。
このような状況や研究会における議論を踏まえて、報告書では企業が実質株主や名義株主に対してその保有状況や実質株主に関する情報について質問した場合には、その質問に対する回答を義務づける制度を会社法上措置することを提言している。
また、研究会では、実効性の伴った制度とすることが重要であるとの指摘も見られた。例えば、質問に対して回答しない株主や、意図的に虚偽の回答を行う株主に対する制裁が過料にとどまる場合は(特に海外の投資家に対して)実効性が伴わないおそれがあるので、その議決権を停止することを可能とすべきとの意見が多く見られたところである。そこで、報告書では、違反の程度や態様等も踏まえて、少なくとも一定の場合には違反した株主の議決権を停止することが可能な制度とすることが望ましい旨を指摘している。
加えて、研究会では、企業・株主の双方において過度な負担が発生しないよう、実質株主の把握プロセスを効率的にすることが重要であるとの意見も見られた。具体的には、研究会第2回で株式会社ICJより紹介されたドイツにおける制度を参考にするべきとの意見が見られたところであるが、海外の諸制度も参考にしつつ、実務上の運用の在り方についても更なる検討が進められることが強く期待される。
2 一体開示
企業が開示・提供する会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報は株主とのエンゲージメントを行う上での基盤となるものであり、企業が株主とのエンゲージメントを、中長期的な企業価値の向上に資するような建設的・実効的なものとするためには、そうした情報を、分かりやすく有用性の高い形で開示することが重要である。日本企業は、会社法に基づく事業報告及び計算書類(以下「事業報告等」という。)、金融商品取引法に基づく有価証券報告書(以下「有報」という。)、株式会社東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書等、様々な形式でこれらの情報を開示している。これらのうち、事業報告等と有報の記載事項は大部分において重複しているにもかかわらず、法制度上は、両書類は別個のものであり、このため、両書類を別個に作成し、別日に開示する実務が定着している。その結果、一部の企業や株主において負担が生じている可能性がある。
そのため、経済産業省はこれまで、企業の情報開示の効率化と投資家の情報取得の質の向上の両立を図る観点から、法務省・金融庁と連携し、一体書類の記載例の公表や、一体的開示のFAQの公表等、一体的開示や一体開示(事業報告等と有報を一体の書類として同時に開示すること)の実現を可能とする取組を進めてきたが、現時点で一体開示を行った企業は存在しない。そこで、一体開示を志向する企業がそれを任意に行うに当たって、どのような事項が、制度上・実務運用上の課題・障壁となっているかについて検討を行った。
研究会では、制度上の課題として、一体開示を行った場合に、一体書類のうち、どの部分が事業報告等に該当するかが不明確であり、その結果、責任(監査役等の監査範囲、虚偽記載があった場合の責任等)が不明確になるといった制度上の課題(制度の解釈上の課題も含む)や、総会スケジュールの後ろ倒しが必要になると言った実務運用上の課題が指摘された。
他方で、「企業によっては一体開示により企業側の事務負担はさほど軽減されない」との意見や、「一体開示を行った場合に、企業と株主の対話が促進されるようにするためには、株主総会の相当期間前に一体書類の開示がなされることや、投資家が有報の内容に加えて開示後の対話内容も踏まえた実質的な議決権行使が行われることが重要である。」といった意見も見られたところである。これらの意見も踏まえ、報告書では、問題の出発点に立ち返り、建設的で実効的な企業と株主の対話を促進するという観点から、企業は、いつ、どのような情報を、どのような形式で開示し、それを踏まえて、企業と株主の間で、いつ、どのように対話(株主総会プロセスを通じた対話を含む。)を行っていくべきか、それを後押しするための制度設計はどのようにあるべきか、という開示と対話の在り方の全体について今後検討をより深めていくことが期待される。
3 株主総会の在り方
上場会社における株主総会についても非効率性が指摘されており、例えば、事前の議決権行使によって決議の帰趨が見えているような場合であっても、多額の費用をかけて、厳格な手続に則り、株主総会を開催することの必要性を疑問視する声がある。研究会でも、(手続違反による株主総会決議取消リスクを懸念し)株主総会の開催に向けて周到な準備をするために、多くの人員と費用を割くことを余儀なくされている状況を改善するべきとの意見は多く見られたところである。
そもそも、株主総会において厳格な手続が必要とされているのは、株主総会に意思決定機関としての側面に加えて、会議体としての側面があるためと考えられている。ここでいう会議体とは、主として意思決定に向けた審議の場を意味している。
しかし、会議体の構成員である株主が極めて多数に及ぶ上場会社においては、株主総会が意思決定に向けた審議の場としては実質的に機能していないケースが多いとの指摘がある。現に、取締役の選任等の株主総会決議事項に関する意思決定に向けた審議は、実質的には、年間を通じた情報開示や、企業と株主との対話、及びそれを踏まえた事前の議決権行使によって果たされており、株主総会議案の帰趨は(株主総会当日の質問・説明内容等にかかわらず)株主総会当日以前に決していることも多い。また、株主総会当日に株主よりなされる質問には、議案の内容に直接関係しないものが含まれることも多く見られるというのが実情である(全国株懇連合会の調査に寄れば、株主総会において質問を受けた上場企業のうち、少なくとも56.7%の企業が、議案に関係のない質問を受領している。)。
確かに、株主総会における質疑プロセスは、個人株主を含む株主との対話・コミュニケーションの場としての役割としても機能している。しかし、このようなコミュニケーションを株主総会内で行う必然性はなく、株主総会の外でそのような場を措置することも可能であり、その方がより建設的な対話が可能となるのではないかといった意見も研究会で見られたところである。
このような議論を受けて、報告書では、会議体としての機能を果たすために認められている規律の意義・在り方を見直したうえで、現行の株主総会の実態に沿った形で、株主総会の手続を効率化、合理化するよう、さらに検討を深めていくことが望ましい旨を提言している。具体的な見直しの方向性については、報告書案においても複数の考え方を提示しているものの、それらに限定されることなく、望ましい株主総会の実現に向けて、今後更に闊達な議論が行われることが期待される。
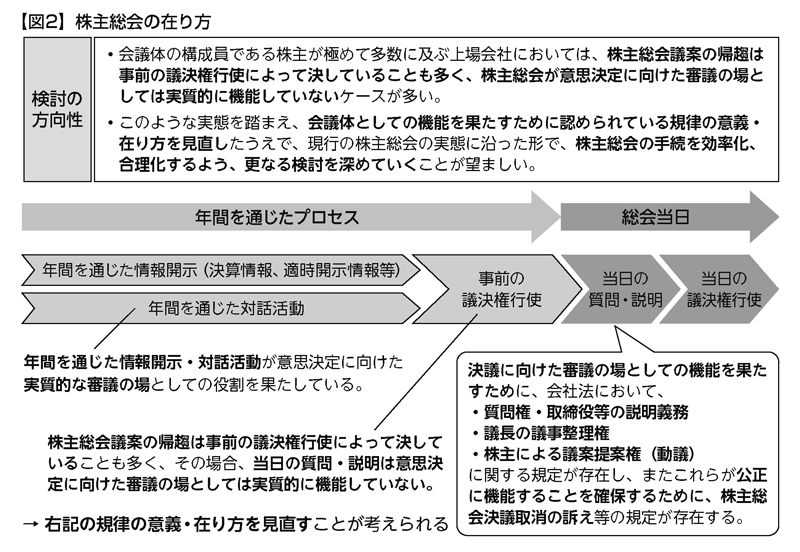
五.その他
その他、研究会では、調査者制度の見直しや、長期保有株主の優遇に関する事項等についても検討が行われた。内容の詳細は、報告書本体をご参照いただきたい。
六.おわりに
企業活動の基盤である会社法は、企業や企業を取り巻く外部環境の変化を正確に捉まえ、各時代において、各企業が価値創造ストーリーを構築・実行することを後押しするとともに、各企業が抱える課題の解決に資するものとなるよう適時に見直していくことが求められている。
報告書では、このような観点から、主として今般の会社法の改正において期待される事項を取りまとめている。本年2月10日に、法務大臣から法制審議会に対して会社法改正の諮問が行われ、今後、法制審議会会社法制部会においてその検討が進められることが予定されているが、経済産業省としては、報告書で示された内容を踏まえ、成長投資を通じた企業の「稼ぐ力」の強化に向けて、引き続き、会社法の改正に向けた議論に貢献してまいりたい。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























