解説記事2025年05月19日 未公開裁決事例紹介 国税庁の暗号資産の情報は法令解釈の変更に該当せず(2025年5月19日号・№1074)
未公開裁決事例紹介
国税庁の暗号資産の情報は法令解釈の変更に該当せず
審判所、新情報追加も納税義務の環境整備が目的
〇国税庁が公表した令和4年12月22日付の「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」において追加された「非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は所得税の課税対象とされていない」との解釈が、国税通則法施行令6条1項5号に規定する国税庁長官の法令の解釈が更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことに該当するか争われた裁決(東裁(所)令5第111号)。国税不服審判所は、本件情報は暗号資産取引に関して納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図ることなどを目的として公表されたものであり、国税庁長官の法令の解釈が更正等に係る裁決又は判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたものとは認められないことから、更正の請求ができる場合に該当しないとの判断を示した。
主 文
審査請求を棄却する。
基礎事実等
(1)事案の概要
本件は、審査請求人(以下「請求人」という。)が、非居住者であった期間に行った暗号資産の譲渡により生じた所得に係る申告は不要であったとして所得税等の更正の請求をしたところ、原処分庁が、当該更正の請求は、更正の請求ができる期間を経過した後にされた不適法なものであるとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたのに対し、請求人がその全部の取消しを求めた事案である。
(2)関係法令(略)
(3)基礎事実及び審査請求に至る経緯
当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
イ 請求人は、勤務先の社命により、平成28年6月20日に中華人民共和国に出国し、平成29年中は所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者であった。
ロ 請求人は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)について、日本の暗号資産交換業者である×××××××に保有する暗号資産を譲渡したことにより雑所得が生じたとして、確定申告書に別表1の「確定申告」欄のとおり記載して法定申告期限までに申告した。
ハ 請求人は、国税庁が公表した令和4年12月22日付「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」(以下「本件情報」という。)における、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていない旨の記載内容に基づき、令和5年4月2日、平成29年分の所得税等について、別表1の「更正の請求」欄のとおり、雑所得の金額を×××とすべき旨の更正の請求(以下「本件更正請求」という。)をした。
ニ 原処分庁は、令和5年8月29日付で、本件更正請求は、通則法第23条第1項に規定する更正の請求を行うことができる期限の経過後に提出されているとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分(以下「本件通知処分」という。)をした。
ホ 請求人は、令和5年9月10日、本件通知処分に不服があるとして、審査請求をした。
争点および主張
本件更正請求は、通則法第23条第2項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当するか否か。具体的には、本件情報の公表が、本件公表に該当するか否か。(編注:争点についての主張は表のとおり)
【表】争点についての主張
| 請 求 人 | 原処分庁 |
| 原処分庁所属の担当職員は、平成29年当時の国税庁長官の法令解釈に基づいて、非居住者である請求人が行った暗号資産の譲渡により生じた所得について申告と納税が必要であると回答を行った一方、本件情報において、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていないとの国税庁長官の新たな解釈が公表された。この公表は、重大な法令の解釈変更に当たり、本件公表に該当すると認められるべきである。そして、請求人は、本件情報を令和5年4月2日に知り、同日に本件更正請求をした。 したがって、本件更正請求は、通則法第23条第2項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当する。 |
通則法施行令第6条第1項第5号が掲げる理由は、国税庁長官の法令の解釈が裁決又は判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことによるものであり、本件において、これに該当する事実は認められず、ほかに、通則法第23条第2項に規定する更正の請求をすることができる場合に該当する事実は認められない。 |
審判所の判断
(1)認定事実
請求人提出資料、原処分関係資料並びに当審判所の調査及び審理の結果によれば、以下の事実が認められる。
イ 国税庁は、暗号資産に関する税務上の取扱い等に係る情報について、別表2のとおり、①平成29年12月1日付で「仮想通貨に関する所得の計算方法等について(情報)」によりFAQを公表し、②平成30年11月21日付で「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)」を公表し、その後、更新又は改訂の都度、各情報を国税庁ホームページに掲載した(以下、別表2の①ないし⑦(⑦は本件情報)の各情報を併せて「本件各情報」という。)。
なお、本件各情報のうち、②ないし⑦については、「暗号資産(仮想通貨)に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」が別添とされており、当該FAQに問答が記載されている。
ロ 本件各情報のFAQには、暗号資産に関する税務上の取扱いについて税目ごとに寄せられた一般的な質問等を取りまとめたものである旨の記載があり、また、別表2のとおり、問答の追加又は法律改正による呼称変更等を理由として改訂等が行われているため、本件各情報は、暗号資産取引に関して納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図ることなどを目的として公表されたものであると認められる。
ハ 本件情報(別表2の⑦)のFAQには、上記のとおり、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていない旨の回答が記載されているところ、この回答は本件情報より前に公表された本件各情報(別表2の①ないし⑥)には記載されておらず、本件情報において追加されたものである。
(2)検討
イ 本件情報における、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていない旨の回答は、上記のとおり、本件情報において追加されたものであるところ、同ロのとおり、本件情報は、暗号資産取引に関して納税者自身による適正な納税義務の履行を後押しする環境整備を図ることなどを目的として公表されたものであって、国税庁長官の法令の解釈が更正又は決定に係る裁決又は判決に伴って公表されたものとは認められない。そうすると、本件情報が公表されたことが、本件公表(すなわち、「国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴って変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたこと」)に該当するとは認められない。
ロ したがって、本件情報の公表が本件公表に該当するとは認められないから、本件更正請求は、通則法第23条第2項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当せず、ほかに、同項に規定する更正の請求をすることができる場合に該当する事実は認められないから、同項による更正の請求ができる場合に該当しない。
(3)請求人の主張について
請求人は、上記の「請求人」欄のとおり、原処分庁所属の担当職員は、平成29年当時の国税庁長官の法令解釈に基づいて、非居住者である請求人が行った暗号資産の譲渡により生じた所得について申告と納税が必要であると回答を行った一方、本件情報において、非居住者が日本の暗号資産交換業者に保有する暗号資産を譲渡することにより生ずる所得は、所得税の課税対象とされていないとの国税庁長官の新たな解釈が公表され、この公表は、重大な法令の解釈変更に当たり、本件公表に該当すると認められるべきであるから、本件更正請求は、通則法第23条第2項第3号に規定する更正の請求をすることができる場合に該当する旨主張する。
しかしながら、原処分庁所属の担当職員が、非居住者である請求人が行った暗号資産の譲渡により生じた所得について申告と納税が必要であるとの回答をしたと認めるに足りる証拠はなく、仮に、原処分庁所属の担当職員が当該回答を行ったとしても、上記(2)のとおり、本件情報は、国税庁長官の法令の解釈が裁決又は判決に伴って公表されたものと認められないから、本件情報の公表が本件公表に該当するとはいえない。
したがって、請求人の主張は採用できない。
(4)請求人のその他の主張について
請求人は、上記の「請求人」欄に記載の主張以外にも、通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項は、還付金等に係る国に対する請求権(以下「還付請求権」という。)は、その請求をすることができる日から5年間行使しないことによって、時効により消滅する旨規定し、通則法施行令第6条第1項第5号とは別に請求人が原処分庁に対して、原処分庁の重過失や不作為によって納付してしまった金額の還付を請求する根拠となるものであり、請求人が国に対して還付金等の請求をすることができることになった日、すなわち本件においては原処分庁の誤った指示によって所得税等を納付した日である平成30年4月20日から本件更正請求をした日まで5年を経過していないため、還付請求権を引き続き有している旨主張する。
しかしながら、通則法第74条は、還付請求権を発生させる根拠規定ではなく、各税法の規定により確定した還付金等である公法上の金銭請求権が既に存在する場合の規定であり、還付請求権は確定税額が過大であっても、そのことから法律上当然に発生するわけではなく、更正の請求などに基づき減額更正がされ、確定税額が是正されることによって初めて発生するものと解するのが相当である。そうすると、請求人は、減額更正を受けるなどして確定した税額が是正されていないことから還付請求権を有しているとはいえず、その主張は前提を欠き、採用できない。
(5)本件通知処分の適法性について
上記(2)のロのとおり、本件更正請求は、通則法第23条第2項第3号に規定する更正の請求ができる場合に該当しない。
また、本件通知処分のその他の部分については、請求人は争わず、当審判所に提出された証拠資料等によっても、これを不相当とする理由は認められない。
したがって、本件通知処分は適法である。
(6)結論
よって、審査請求は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり裁決する。
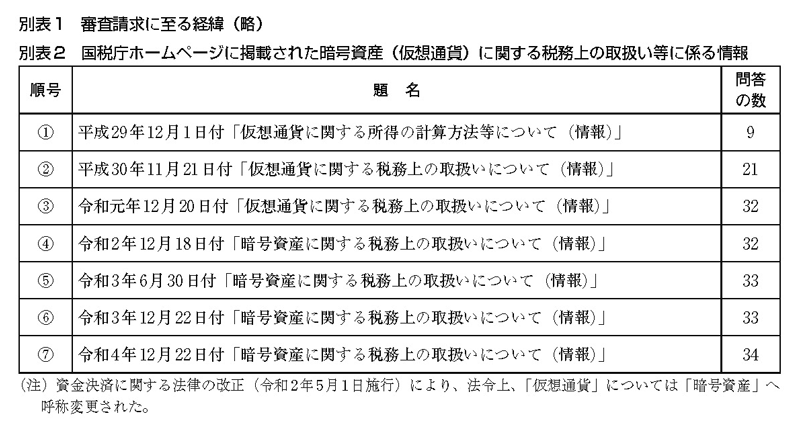
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























