解説記事2025年06月02日 ニュース特集 会社法改正における検討課題とその方向性(2025年6月2日号・№1076)
ニュース特集
法制審での検討がスタート
会社法改正における検討課題とその方向性
法制審議会総会が2月10日に開催され、鈴木馨祐法務大臣が株式の発行の在り方や株主総会の在り方など、会社法の見直しの要否を検討するよう諮問がなされ、検討がスタートした。今回の改正は、政府が令和6年6月21日に閣議決定した「規制改革実施計画」において、株式の無償交付について、会社法上、上場会社の取締役等だけでなく、企業が優秀な人材を確保しやすくする観点から、従業員等に対する無償交付を可能とするほか、株式交付について活用範囲拡大、手続の簡素化を通じてスタートアップ等による活用を促進するなど、株式対価M&Aの活性化に向けた会社法の改正を検討する旨が盛り込まれたことを踏まえたもの。諮問では、①株式の発行の在り方、②株主総会の在り方、③企業統治の在り方等に関する規律の見直しの要否を検討することとされている(図表1参照)。本特集では、法制審議会で検討課題に取り上げられる項目を中心にその概要と方向性について解説する。
【図表1】主な検討事項
①株式の発行の在り方 |
株式の無償交付、株式総会決議の有無が論点に
株式の発行の在り方でまず検討課題に挙げられるのが株式の無償交付の対象範囲の見直しだ。令和元年の会社法の改正により、上場会社の取締役又は執行役を対象として、株式の無償交付をすることができることとなったが(会社法202条の2)、昨今では、国内外の優秀な人材を確保する観点などから従業員及び子会社の取締役等に対しても株式を付与する動きが広がっているという。
ただし、従業員等は株式の無償交付の対象外であるため、実務上は金銭債権を従業員等に付与した上で、従業員等に募集株式を割り当て、引受人となった従業員等に金銭債権を現物出資財産として給付させることにより、株式の発行又は自己株式の処分をするという取扱いがなされている。このように企業の事務負担等が大きいとの指摘があり、今回の会社法改正では、従業員等に対しても株式の無償交付を可能にする方向で検討が行われる(図表2参照)。
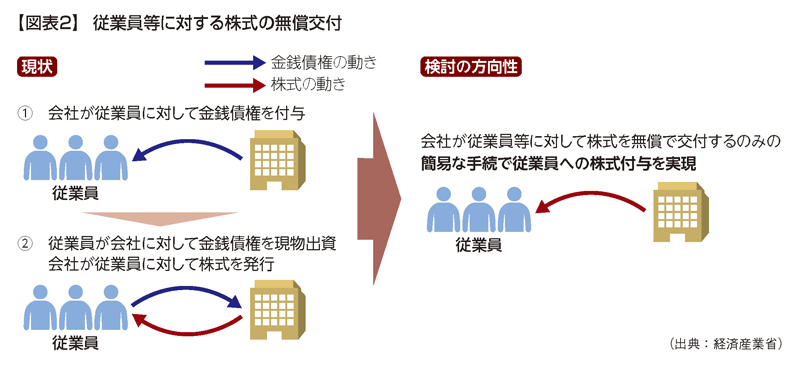
問題となるのは株式総会決議の有無だ。従業員等に株式を無償交付した場合、1株当たりの価値が下落し、既存株主の利益が害されるおそれがあり得るため、株式公開決議を必要とすべき意見がある一方、株式の無償交付は、広い意味では職務執行の対価といえるものであり、有利発行に該当することは想定し難いとし取締役会決議のみで交付可能とすべきとの意見がある。株式総会決議が要件となった場合には、従業員等への株式の無償交付が実現したとしても、新制度が利用されないのではないかといった懸念の声もある。
完全子会社に限定するか否かがポイント
また、株式の無償交付の対象者の範囲をどこまでにするかも問題となる。実務上、株式会社とその子会社は一体的に経営されていることから、株式会社の従業員のみならず、その子会社の役員及び従業員も対象者に含めるべきとのニーズがあるとされている。ただし、子会社の取締役及び従業員は親会社に対して直接的に便益の提供をするものではないことや、親会社の利益を優先して子会社の少数株主の利益を害するという不適切なインセンティブとなり得ることなどから、完全子会社の場合に限るとの考え方も示されており、今後の議論のポイントになりそうだ。
完全子会社化する以外も株式交付制度の利用が可能か
令和元年の改正会社法により、完全子会社とすることを予定していない場合であっても、株式会社が他の株式会社を子会社とするため、自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができる株式交付制度が創設された(会社法2条32号の2、774条の2~774条の11、816条の2~816条の10)。今回の会社法の改正では、株式交付制度を利用することができる範囲を拡大することや、手続を簡素化することが検討される。
現行の株式交付制度の対象については、国内の株式会社の議決権の過半数を取得する場合に限られており、これ以外に子会社化する場合のほか、外国会社や持分会社を子会社にする場合は対象外となっている。このため、対象範囲をどこまで拡大するかが論点となる(図表3参照)。
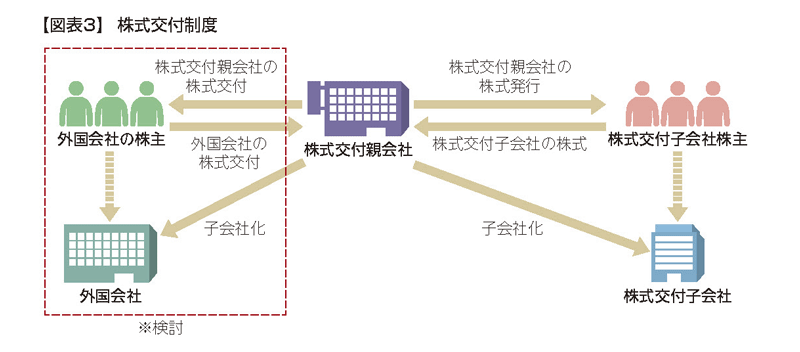
反対株主の株式買取請求権を不要に
現行、株式交付親会社の既存株主の保護については、株式交換と同様の規律とされており、株式交付親会社の反対株主には、株式買取請求権が認められている。しかし、反対株主の株式買取請求権の行使により株式交付親会社において不測の金銭の支出が発生する可能性があり、これが株式交付制度を利用する上で障害になっているとの指摘がある。この点については、上場会社であれば市場での売却機会を有していることから株式買取請求権を認めないとする考え方や、会社が他の会社の株式を取得し、株式の発行又は自己株式の処分をする場合には、債務の承継がされるわけではなく、会社の財務状況に重大な影響を及ぼす危険はない上、原則として株主総会決議を要するため株主が有する会社の支配権や株式の財産的価値が害されるおそれも低いとし、反対株主の株式買取請求権を認めないとする考え方があるとしている。
また、株式交付制度も、株式交換制度と同様、株式交付親会社における債権者保護手続が必要とされている。ただし、債権者保護手続は、1か月程度の期間が必要となる手続であり、やはり株式交付制度を利用する際の障害とされており、廃止すべきとの指摘がある。このため、例えば、組織再編行為の対価が不当であると財産の流出が生じ得る場合については、会社の財産の流出は通常の取引においても生じ得るものであり、不当な財産の流出のおそれがあるにすぎない場合には、債権者を害するおそれが大きいとはいえず、債権者保護手続を必要とはしないとの考え方が示されている。
現物出資制度の検査役の調査を不要に
現物出資制度の見直しも今回の改正の検討課題に挙がっている。会社法上、株式会社は、現物出資(金銭以外の財産の出資)がされる場合には、原則として、募集事項の決定の後遅滞なく、現物出資財産の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならないとされている(会社法207条1項)。このような検査役の調査制度については、スタートアップに対する知的財産権等の現物出資の支障になっているとの指摘がある。また、会社法上の現物出資財産に係る不足額填補責任については、募集事項の決定時に現物出資財産が適正に評価された場合であっても、募集株式の引受人が株主となった時までに現物出資財産が値下がりしたときは、不足額填補責任が発生し得るため、このことが実務上のリスクとなっているとの指摘がある。このため、現行の現物出資制度を見直す方向となっている。
具体的には、検査役の調査を省略できる場合として、株主総会の特別決議により現物出資財産の価額を定めたときや、取締役が現物出資財産の評価の方法、評価額が相当である理由を説明するときなどが検討される。また、不足額填補責任を負うリスクを避けるために現物出資制度の利用が躊躇されているとの指摘に関しては、例えば、立証責任の転換がされた過失責任とすることや、立証責任の転換のない過失責任とすること、取締役と通じて著しく不公正な条件で募集株式を引き受けた場合に限り責任を負うとすることなどが考えられるとしている。
非上場会社も含めバーチャル株主総会の開催可能に
株主総会関係では、非上場会社も含めバーチャル株主総会に関する規律を設けるかどうかが大きな論点となる。株主総会を開催するためには、株主総会の「場所」を定めなければならないとされ(会社法298条1項1号)、この「場所」は、株主が質問し説明を聴く機会を確保するため、物理的に入場することができる場所でなければならないと解されている。このため、現行の会社法では、ハイブリッド型バーチャル株主総会を開催することは可能であるが、バーチャルオンリー株主総会を開催することは難しいとされている。
コロナ禍においては、令和3年の産業競争力強化法の改正により、一定の要件を満たし、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた上場会社については、会社法上の特例としてバーチャルオンリー株主総会を開催することが可能となっている。法務省によれば、令和6年末時点で、この特例に基づいてバーチャルオンリー株主総会を開催した会社は70社、開催を可能とする定款変更を行った会社は459社にのぼっているという。このため、法務省は、一定の実務上のニーズがあるとして検討を行うとしている。
検討の対象は、バーチャルオンリー株主総会及びハイブリッド出席型バーチャル株主総会(物理的な場所における株主総会の開催に加え、株主総会の場所にいない株主が、インターネット等を用いて株主総会に出席することができる株主総会)としている。なお、ハイブリッド型バーチャル株主総会(物理的な場所における株主総会の開催に加え、株主総会の場所にいない株主が、株主総会に出席せずに、インターネット等を用いて株主総会の議事を傍聴できる株主総会)については、株主総会への出席を伴わないものであり、特段の規律を設ける必要はないとしている。
具体的な要件としては、①場所の定めのない株主総会とすることができる旨の定款の定めがあること、②通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること、③株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること(バーチャルオンリー株主総会のみの要件)などとする方向で検討が行われる見込みだ。②に関しては、方針に加えて、通信障害に対する対策が講じられた通信方法を使用するほか、通信障害が生じた場合に代替する通信方法を用意することが考えられる。また、事後的に株主総会の議事が適正かつ確実に行われたことを検証することができるよう、株主総会の議事における通信の内容を記録した電磁的記録を作成し、株主総会の日から数年間、その電磁的記録を保存することが求められることになりそうだ。また、③に関しては、インターネット等を使用することに支障のある株主の希望により、必要となる機器を貸し出しすることや、電話も認めること、株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨(会社法298条1項三号)を定めることが検討される。なお、株主全員の同意を得た場合には、これらの措置を定めないことができるとされる。
そのほか、同じく「場所」を定める必要がある社債権者集会(会社法719条1号)についても、バーチャルオンリー社債権者集会に関する規律を設けるかどうか検討が行われる。
企業は実質株主に関する情報の提供を請求可能に
金融庁に設置された金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」で検討課題に挙がった実質株主確認制度も大きな改正項目の1つである。
現行制度上、名義株主は、会社法上の株主名簿や有価証券報告書等の大株主の状況の開示により、企業や他の株主が把握する制度が整備されている一方、実質株主は、大量保有報告制度の適用対象となる場合を除き、企業や他の株主がこれを把握する制度は存在しない。多くの企業が株主判明調査をしているが、コストや時間を要する上、全ての実質株主が判明するわけではない。実質株主の確認ができれば、より投資家との対話を促進できると期待されている。このため、同WGが令和5年12月25日に公表した報告書では、「まずは早急に、機関投資家の行動原則としてその保有状況を発行会社から質問された場合にはこれに回答すべきであることを明示することを、またその後、そのような回答を法制度上義務付けることを、それぞれ検討すべきである」と明記された。これを受け、「スチュワードシップ・コードに関する有識者会議」がスチュワードシップ・コードの改訂案を公表。改訂案では、「機関投資家は、投資先企業との間で建設的に対話を行うために、投資先企業からの求めに応じて、自らがどの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべき」とするとともに、「投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表すべき」旨が明記され(コード指針案4−2)、近々決定される予定だ。
情報提供を怠れば議決権を一部停止など
ただし、スチュワードシップ・コードはあくまで自主規制であり、法的拘束力はない。このため、株式会社が実質株主に関する情報の提供を請求することができる制度を創設する。実質株主については、実質株主確認制度の趣旨を株式会社と株主との間の建設的な対話の促進であることを前提にした場合には、「株式に係る議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する者」が相当であるとしている。なお、情報の提供を怠った者への制裁も設けられる。過料や議決権の一部停止などが検討される。
現状は株主総会前に決議が決している場合も事前準備などが必要
そのほか、株主総会関係では、「事前の議決権によって株主総会の決議があったものとみなす制度の創設」も検討課題に挙がっている。上場会社では事前の書面又は電磁的方法による議決権行使によって決議の成否の大勢が決していることがほとんどである。しかし、会社法との関係では、株主総会を現に開催し、質問や動議に適切に対処しなければ決議の取消事由になり得るため、多大な労力をかけて株主総会に向けた準備や当日の対応を行っているのが現状であり、このような状況を改善する目的がある。
再度、株主提案権の議決権数要件の見直しも
また、株主提案権の議決権数の要件見直しの要否も検討される。株主提案権の要件のうち議決権数(300個以上の議決権)の要件については、株式数が多い株式会社や投資単位が小さい株式会社においては、保有比率がごくわずかの株主にも株主提案権が認められることになり、株主提案権が濫用される懸念があるとの指摘がなされている。
ただし、この点は、令和元年の会社法改正における法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会でも検討されたものの、最終的には、株主が提出することができる議案の数の制限に関する規定の新設によって株主提案権の濫用的な行使はある程度排除することができるほか、議決権数の要件の見直しを基礎付けるだけの立法事実がないことなどを理由に見送られた経緯がある。このため、まずは、300個以上の議決権を有するものの議決権の100分の1以上の議決権は有していない株主による株主提案権の行使が濫用的であることなどを裏付けるデータがあるかどうかなどから検討される模様だ。
指名委員会による取締役選任議案の権限を取締役会へ
企業統治の在り方等に関して挙げられるのは指名委員会等設置会社制度の見直しだ。同制度は、平成14年の商法改正により導入された委員会等設置会社制度を前身とするものだが、現在まで実質的な見直しは行われておらず、改善を求める声がある。問題は、①各委員会の委員の過半数は社外取締役でなければならないが(会社法400条3項)、取締役の過半数が社外取締役とはされていないことや、②指名委員会は株主総会に提出する取締役選任・解任議案の内容を決定する権限を有しており(会社法404条1項)、取締役会が指名委員会の決定を覆すことができないとされていることだ(図表4参照)。
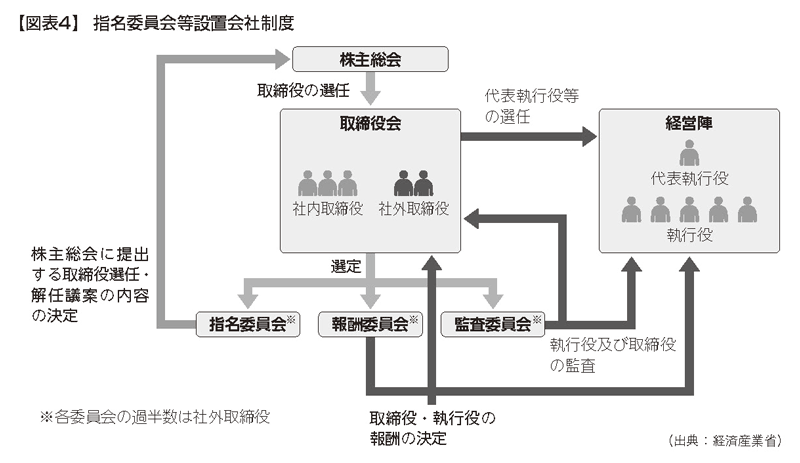
このような制度設計となったのは、平成14年当時は社外取締役の適任者が少ないことが指摘されており、取締役の過半数を社外取締役とした場合には要件を満たす株式会社が少なくなるといった懸念を踏まえたものである。しかし、令和6年7月時点では、プライム市場上場会社の20.3%において、取締役の過半数が独立社外取締役になっており、また、指名委員会等設置会社の80%において取締役の過半数が社外取締役となっているなど、上場会社における社外取締役の選任状況は大きく変化している状況だ。このため、取締役の一部のみで構成される指名委員会のみが取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を有することは、特に取締役の過半数が社外取締役である場合には合理性が乏しいとの指摘がなされている。このような指摘を踏まえ、例えば、取締役の過半数が社外取締役である場合には、取締役の選任に関する議案の内容を決定する権限を取締役会に付与することなどが検討される。
そのほか、グローバルな人材確保の観点から、業務執行取締役である取締役との責任限定契約の締結を認めるかが検討課題となる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























