解説記事2025年06月30日 巻頭特集 要件事実論の租税実務への活かし方(後編)(2025年6月30日号・№1080)
巻頭特集
対談
要件事実論の租税実務への活かし方(後編)
−具体的裁判事例を元に
北海道大学大学院法学研究科教授 元国税審判官 佐藤修二
弁護士・元国税審判官 向笠太郎
租税実務における要件事実論の意義について語っていただいた前編に続き、後編では、その応用編として、所得の帰属が争われ、一審で敗訴した国が控訴を断念するという納税者側の“圧勝”に終わったバークレイズ銀行事件(東京地判令和4年2月1日税資272号順号13665)を、要件事実論の観点から分析していただく。
実質的な所得者が誰であるかという実質所得者課税の原則が争われる場合には様々な事実関係が現れ、事案として複雑化しやすいといえる。そして、事実関係が複雑になればなるほど、何を主張立証すればよいのかが分かりにくくなりがちだ。このため、要件事実論を踏まえるとどのような整理ができるのかをしっかりと理解しておくことが重要となる。本稿ではバークレイズ銀行事件を通して、納税者がどのような事実を主張立証すべきかを明らかにする。
2.要件事実論の応用−所得の帰属が争われたバークレイズ銀行事件を素材に
佐藤:具体例を交えながらご説明いただいたことで、要件事実論のイメージが具体的になってきたかと思います。ここからは応用編ということで、所得の帰属が争われた、向笠先生が本誌に評釈(脚注13)を書かれたこともあるバークレイズ銀行の事件(東京地判令和4年2月1日税資272号順号13665)を、要件事実論によって分析していただきたいと思います。本件は、長島・大野・常松法律事務所の吉村浩一郎先生らが代理して一審で勝訴し、国側が控訴せずにそのまま確定した事件です。鮮やかに勝ちすぎたせいか、それほど世の中に知られていないような気がするので、ちょうど向笠先生も評釈を書かれたことでもあり、改めて光を当ててみたいと思った次第です。所得の帰属が争われる訴訟では、様々な事実関係が現れますので、要件事実論による整理が役に立つのではないかと想像しています。
向笠:佐藤先生がおっしゃるように、実質的な所得者が誰であるかという所得の帰属が争われる場合は、様々な事実関係が現れます。そのため、要件事実論を踏まえるとどのような整理ができるのか、というのを理解しておくことが重要であると考えます。そこで、まず、実質所得者課税の原則について簡単に触れ、この原則についての要件事実の分析を行った後、バークレイズ銀行事件を題材に、具体的な検討を行いたいと思います。
なお、ご紹介くださいましたとおり、バークレイズ銀行事件につきましては、以前に本誌にて評釈を書かせていただきました。その時は、要件事実の観点からの分析はあまり行いませんでしたので、今回は、その視点も織り交ぜつつ改めてご紹介いたします。ただ、一方で、どうしても以前の評釈と重なる部分もありますが、その点はご了承ください。
それでは、まず、実質所得者課税の原則について簡単に見てみたいと思います。所得税法をはじめとする多くの租税実体法では、実質所得者課税の原則を規定しており、例えば、所得税法12条は、「資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。」と規定しています。
この実質所得者課税の原則については、①課税物件の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判定すべきとする法律的帰属説と、②課税物件の法律上(私法上)の帰属と経済上の帰属が相違している場合には、経済上の帰属に即して課税物件の帰属を判定すべきとする経済的帰属説があります(脚注14)。そして、①の法律的帰属説は、課税庁による執行を不必要に複雑化させず、また、納税者の予測可能性を高めることにも資するということから、通説とされていますし、下級審裁判例も、基本的には法律的帰属説に立っているといえます(脚注15)。バークレイズ銀行事件でも、後ほどご紹介しますとおり、裁判所は法律的帰属説に立つことを明示しています。
この法律的帰属説に立つことを前提に、納税者が、真実の法律関係からすれば実質所得者は自分以外の別人である、と反論する場合の要件事実について、「課税当局が、契約書上の所得の帰属者である甲に対して更正処分及び無申告加算税賦課決定処分を行ったところ、甲が、実質所得者は乙であるとしてこの各処分を争う」という例(図3参照)で考えてみたいと思います。
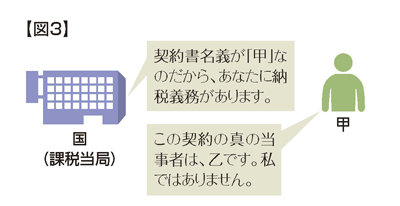
この例の場合、課税処分は納税者にとって不利な事情ですので、国側が、契約書という証拠によって、納税者が甲であることの主張立証を行い、甲に対する更正処分等という法律効果が発生したことを主張する必要があります(脚注16)。これに対し、甲としては、契約書上の記載は確かに甲であるが、真の契約者が乙であると反論すると思われます。この甲が主張するであろう事実は、国側の主張立証する事実と両立する内容であり、また、その主張立証が奏功しますと、乙が所得税法12条の要件を満たしていることを主張でき、その結果、甲に対する適法な更正処分等という法律効果が発生しないという法律効果が生じているという主張が認められることになります。したがいまして、真の契約者が乙であることを基礎付ける事実については、甲が主張立証責任を負います(以上、図4参照)。
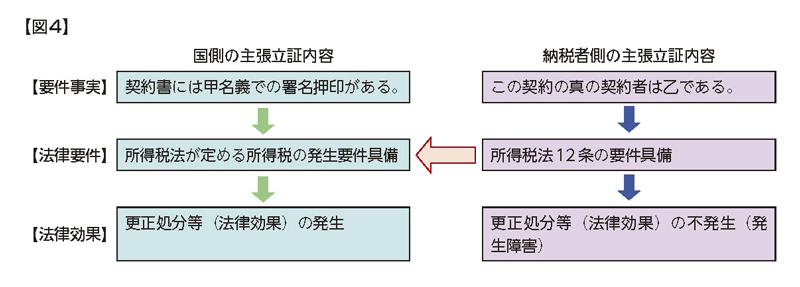
このように、実質所得者課税の原則が争われるケースにおいて、納税者側が、実質所得者は自分以外の別人であると反論するのであれば、それを基礎付ける事実を主張立証していく必要がある、ということになります。
佐藤:実質所得者課税の原則が問題となる場合、納税者は、真実の法律関係を基礎付ける事実を主張立証する必要があるということですね。では、納税者は、具体的に、どのような事実を主張立証すればよいのでしょうか。
向笠:実質所得者課税の原則について法律的帰属説に立ったとしても、最終的には個々の事案ごとに様々な事実を見て判断していくしかありません。今の設例のように、事実関係が単純であれば比較的分かりやすいと思いますが、事実関係が複雑になればなるほど、何を主張立証すればよいのかが分かりにくくなっていくように思います。
そこで、バークレイズ銀行事件を通して、納税者がどのような事実を主張立証すべきかを見てみたいと思います。
まず、バークレイズ銀行事件の概要をご説明します。この事件は、関係当事者が非常に多く、スキームも複雑ではありますが、可能な限り簡潔にしますと、以下のとおりです。なお、原告であるバークレイズ銀行を「X」とします。また、①から⑤までの取引関係については、概要図(図5参照)も併せてご参照ください。
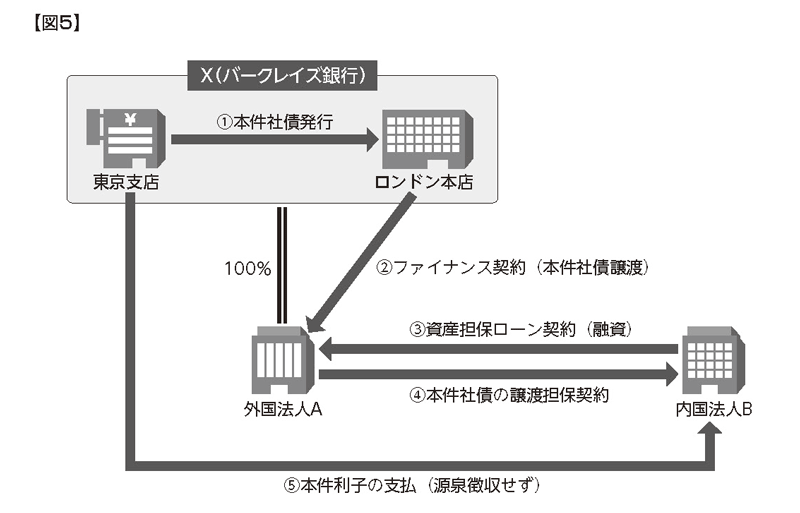
① 外国法人であるXの東京支店(以下「東京支店」という。)は、その事業資金を調達するために、英国ロンドン市にあるXの本店(以下「ロンドン本店」という。)に対して社債(以下「本件社債」という。)を発行した。
② ロンドン本店は、本件社債の発行と引換えに東京支店に支払う資金を調達するため、ルクセンブルクで設立されたXの完全子会社であるA社との間でファイナンス契約(以下「本件ファイナンス契約」という。)を締結し、A社に対して本件社債を25億ポンドで譲渡した。
本件ファイナンス契約には、本件社債の買入価格を定期的に調整するため、以下のような定めがある。なお、「平準化LIBOR金額」とは、本件社債の利払日においては25億ポンドに対してLIBORの利率を乗じた金額で、本件ファイナンス契約終了日においては25億ポンドである。また、「平準化返済金額」とは、本件社債の利払日においては、東京支店が本件社債について支払う金額に相当する金額で、本件ファイナンス契約終了日においては当該支払日時点の本件社債の公正価格である。
| 平準化LIBOR金額>平準化返済金額 | ロンドン本店がA社に超過分相当金額を支払う。 |
| 平準化LIBOR金額<平準化返済金額 | A社がロンドン本店に超過分相当金額を支払う。 |
③ A社は、Xグループと従前から取引関係にあった内国法人B社との間で、本件社債の対価額である25億ポンドを調達するために資産担保ローン契約を締結し、B社から融資を受けた。
④ A社は、B社との間で譲渡担保契約を締結し、③の資産担保ローン契約に基づくB社からA社への貸付金(融資)について担保を提供することを目的として、本件社債をB社に譲渡した。
なお、以下では、本件社債の譲渡に係る②から④に係る各契約を「本件各契約」といい、本件社債の発行及び譲渡に関する取引の全体を「本件資金調達取引」という。
⑤ 本件社債の利子(以下「本件利子」という。)は、東京支店からB社の口座に支払われているところ、Xは、本件利子の各支払に際して源泉徴収をしなかった。
⑥ そうしたところ、管轄の税務署長が、本件利子の収益を実質的に享受している者はA社であり、本件利子の各支払は外国法人に対する利子の支払に当たるとして、本件利子についての源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び各不納付加算税賦課決定処分(以下「本件各処分」という。)を行った。
⑦ これに対してXが、本件利子の収益を実質的に享受している者はB社又はロンドン本店であるとして、本件各処分の取消しを求めるとともに、本件各処分に基づいてされた源泉所得税の本税、不納付加算税及び延滞税の各納付は法律上の原因なく行われたものであるとして、被告国に対し、過納金として53億4717万6776円の還付及びその還付加算金の支払を求めた。
以上が事案の概要ですが、Xが本件資金調達取引を行った理由を少し補足します。
裁判所の認定によりますと、まず、Xが行っていた従前の資金調達方法では、日本の課税額に係る外国税額控除を十分に受けられず、それによって繰り越された部分が多額となっていたところ、その部分を活用できるようにするには、社債を発行し、その社債を英国外の第三者が保有する方法によることが適切であると考えられたようです。ただ、第三者がロンドン本店から直接社債を購入すると、日本の会計上、第三者において本件資金調達取引をパス・スルーできなくなってしまうことから、別の法人がロンドン本店から社債を購入した上で、その第三者が別の法人に対して購入資金の貸付けを行い、その貸付けに係る担保として社債を譲り受けることにしたようです。そして、ここでいう「別の法人」がA社であり、「第三者」がB社となります。
本件の具体的な争点は、本件利子の実質所得者(所得税法12条)がロンドン本店とA社のいずれであるかです(図6参照)。なお、B社が本件利子の実質所得者ではないこと、及びロンドン本店が本件利子の実質所得者である場合にはXに本件利子に係る源泉徴収義務が生じないことは、当事者間に争いがありませんでした。
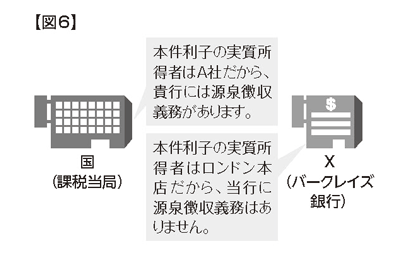
続いて、判決内容をご紹介します(脚注17)。まず、裁判所は、所得税法12条が実質所得者課税の原則について規定しているとした上で、「その趣旨は、課税物件の法律上(私法上)の帰属につき、その形式と実質が相違している場合には、実質に即して帰属を判断すべきとするものと解され」るとして、法律的帰属説に立つことを明示しています。
そして、「本件の課税物件である本件利子の実質所得者を判断するに当たっては、本件利子に係る経済的損益の帰属先のほか、本件資金調達取引全体の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況など諸般の事情を総合的に考慮すべきものと解される。」という判断枠組を提示しています。なお、1つ目の「本件利子に係る経済的損益の帰属先」を考慮事情とするのは、経済的帰属説に親和性があり、法律的帰属説と相反するようにも見えます。しかし、裁判所は、実質所得者の判断に際して総合考慮するに当たり、「その一つの事情として経済的損益の帰属等を考慮することが許容されないものとは解され」ない、と述べています。
その後、「本件各契約においては、東京支店から本件B社口座に支払われた本件利子につき、それらに相当する金額を、B社はA社に対して担保余剰金額として、A社はロンドン本店に対して平準化返済金額としてそれぞれ支払う義務を負うこととされ、本件利子に係る経済的な損益は、その支払義務の名目を変化させつつも、法的な支払義務を通じて最終的にロンドン本店に帰属するものとなっている」こと、「本件各契約においては、本件ファイナンス契約の終了時において、ロンドン本店はA社に対して平準化LIBOR金額として25億ポンドを、A社はロンドン本店に平準化返済金額として本件社債の公正価格を支払う義務を負うとされていることなどが認められ、これらの事実に照らせば、本件資金調達取引は、ロンドン本店から本件社債が譲渡された後における本件社債の公正価格や為替の変動に伴う損益を含む本件社債等に関する損益の全てがロンドン本店に帰属するようその仕組みが構築されていること」、「本件資金調達取引は、本件本支店間融資取引の経済的実質を変えず、原告グループにおける財務効率を改善させることを目的として作り上げられたものであるところ、A社やB社の財務状況には一切悪影響を与えず、一定の手数料収入のみを取得させることを不可欠の要素としていたこと、本件各契約の関係者の財務諸表においても、本件社債及び本件利子についてはロンドン本店の資産又は収益として計上され、A社の資産又は収益としては計上されていないことが認められるなど、本件資金調達取引が行われるに至る経緯や関係者の認識としても本件社債等に係る損益につきロンドン本店に全て帰属させることを想定していた」こと、「本件各契約締結後の本件資金調達取引の実施状況をみても、【中略】本件利子の各利払日とB社からA社に対する担保余剰金額の支払日との間に若干の時間差が生じたことに伴う修正措置を講じつつも、本件各契約が予定する損益状況に実質的な影響が生じないように本件各契約の関係者間における各種支払等がされていたことが認められる」こと、といった事実を認定の上、「以上のとおり、本件資金調達取引においては、本件利子に係る収益を含む本件社債等に関する経済的な損益につき、法的な権利義務関係を通じて、最終的にロンドン本店に帰属するという仕組みを採用していることのほか、本件社債等に係る損益を全てロンドン本店に帰属させることが本件資金調達取引を実施する不可欠の要素であることは、本件資金調達取引を行う関係者間における一貫した共通認識であって、本件資金調達取引の実際の実施状況もこれに沿う形で行われているものである。かかる本件利子の経済的損益の帰属先も含めた本件資金調達取引の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況に鑑みれば、本件利子に係る収益については、実質的にロンドン本店が支配するものであり、B社あるいはA社が当該収益を支配するものではないというのが、本件資金調達取引の関係者間の真実の法律関係であると認めるのが相当であり、ロンドン本店が本件利子の実質所得者であるというべきである。」として、Xの主張を認めました。
先ほど佐藤先生からご説明がありましたとおり、この判決は控訴されず、X勝訴で確定しています。
佐藤:それでは、このバークレイズ銀行事件についての解説をお願いします。
向笠:この事件において、裁判所は、法律的帰属説に立つことを明らかにした上で、以下の4つの考慮事情を総合考慮して実質所得者がロンドン本店であると判示しました。
① 本件利子に係る経済的損益の帰属先
② 本件資金調達取引全体の仕組み
③ 本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識
④ 本件資金調達取引の実施状況
この4つの考慮事情をよく見ますと、本件利子に係る経済的損益の帰属先に関するもの(①)と、本件資金調達取引の内容(②~④)に分類できるように思います。そこで、この分類した2つの事情のうちどちらがより重要な要因かを考えてみます。
仮に①の方がより重要であると考えますと、それは、経済的帰属説を意味することになりかねません。先ほどご紹介しましたように、本件で裁判所は法律的帰属説に立つことを明言していますが、そのような裁判所が①をより重視しているようには思えません。考慮事情の1つとして「経済的損益の帰属等を考慮することが許容されないものとは解され」ないとしているのは、あくまで、一つの事情に過ぎないことを強調しているのではないかと思われます。
したがいまして、本件でポイントとなったのは②~④であり、要するに、本件資金調達取引の内容であって、①についても、あくまで、取引内容把握のための事情として扱われているものと考えます(脚注18)。
そして、取引内容の全体像を踏まえて真実の法律関係を解明するという手法は、バークレイズ銀行事件と近い時期に出た大阪高判令和4年7月20日税資272号順号13735でも見ることができます。この事件では、親が所有し、第三者に駐車場として貸していた土地について、親子間で使用貸借契約を締結し、それに伴い駐車場収入も子に移転したところ、この駐車場収入が親と子のいずれに帰属するかが争われました。原告であり、納税者である親(脚注19)は、この駐車場収入が子に帰属すると主張していましたが、裁判所は、親子間での取引全体を見て、親が実質所得者であると判断し、その結果、納税者側が敗訴しました。
佐藤:ありがとうございます。真実の法律関係を明らかにするには、取引内容がポイントということですね。バークレイズ銀行事件で挙げられている4つの考慮事情は、民法的にパラフレーズすると、取引の基礎をなす契約の構造、契約当事者の認識がキーになっているように思われ、法曹実務の基盤たる民法に基づく判断基準として、共感できるものです。バークレイズ銀行事件判決の示したこのような判断基準は、いろいろな事案で適用できると思うのですが、いかがでしょうか。
向笠:ありがとうございます。バークレイズ銀行事件に限らず、課税処分の前提として取引内容を正しく把握することが重要ですので(脚注20)、その点からしますと、おっしゃるとおり、この4つの考慮事情というのは、民法に基づく判断基準として適切妥当であるように思います。一方で、バークレイズ銀行事件では、国際的な金融取引という事実関係の特色に即した形で取引内容が主張・立証され、裁判所もそれに即して4つの考慮事情を挙げた上で認定をしたと考えられます。したがいまして、他の事例では、その事例の具体的事実関係に即した形で取引内容について主張立証し、真実の法律関係を明らかにすることが重要といえます。
ただ、取引内容をやみくもに主張立証しても、必ずしも真実の法律関係を明らかにできるわけではありません。「このような取引内容からすれば、●●といえ、したがって、真実の法律関係は■■である。」のように、取引内容からどのような事情を導き出せるかを考える必要があると思います。つまり、「●●」に当たる部分は何か、真実の法律関係を導き出すためのエッセンスは何か、ということです。そこが明らかになれば、どのような視点で取引内容を明らかにしていけばよいのかが見えてくると思います。
この点、バークレイズ銀行事件では、「かかる本件利子の経済的損益の帰属先も含めた本件資金調達取引の仕組み、本件資金調達取引に至る経緯あるいは関係者の認識、本件資金調達取引の実施状況に鑑みれば、本件利子に係る収益については、実質的にロンドン本店が支配するものであり、B社あるいはA社が当該収益を支配するものではないというのが、本件資金調達取引の関係者間の真実の法律関係であると認めるのが相当であり、ロンドン本店が本件利子の実質所得者であるというべきである。」としています。つまり、本件利子に係る収益を誰が支配しているか、ということから、最終的に実質所得者を判断しています。ただ、「支配」というだけでは、取引内容について何を主張立証すればよいかがまだ明確とは言えませんので、もう少し具体的に言えないかを考えてみます。
ここで参考になるのが、牛枝肉問屋である原告の買受人に対する貸倒債権について、原告が消費税法39条1項による貸倒れに係る仕入税額控除の適用を主張できるとした大阪地判平成25年6月18日税資263号順号12235です。
この事件で、裁判所は、まず、消費税法13条についても法律的帰属説が妥当であるとしています(脚注21)。そして、その上で、「本件牛枝肉取引を含むA場における牛枝肉の取引において、【中略】制度上およそ原告が売買代金回収のリスクを負わない仕組みが構築されているものとはいえず、本件牛枝肉取引においても原告が本件各買受人からの売買代金回収のリスクを負うものであって、委託者(出荷者)は同リスクを何ら負わないこと、原告と買受人との間の牛枝肉の売買代金の合意(売買契約の締結)についても、委託者(出荷者)は特段の関与はしていないこと、買受人に対する瑕疵担保責任を負うのも原告であって委託者(出荷者)ではないことに照らせば、本件牛枝肉取引において、原告が、その法的実質として、単なる名義人として課税資産(本件牛枝肉)の譲渡を行ったものにすぎないということはできず、したがって、原告は、課税資産(本件牛枝肉)の譲渡を行ったものとして、本件牛枝肉取引に係る本件各債権について、消費税法39条1項の貸倒れに係る消費税額の控除の適用を受けるものと解するのが相当である。」と判示しています。
このように、裁判所は、様々な事情を総合考慮して取引全体の内容を明らかにし、原告が売買代金回収リスクを負っていることから、原告が実質的に課税資産である牛枝肉の譲渡を行った、と判断しています。つまり、取引から生じるリスクを誰が負っているのかということを重視していると見ることができます。
確かに、ほとんどの取引においてリスクは存在しており、そして、実質的な契約当事者がそのリスクを負うのが通常であると思われます。そうだとすれば、真実の法律関係はどのようなものか、実質的な当事者は誰か、を考えるに当たり、問題の取引から生じるリスクを誰が負っているかを考えるのが重要であるように思います(脚注22)。
バークレイズ銀行事件においても、様々な事情を総合考慮して本件資金調達取引の内容を明らかにした上で、為替変動に伴う損益を含む本件社債等に関する損益の全てがロンドン本店に帰属すると判示しています。これは、言い換えれば、ロンドン本店が為替変動リスクを含む本件社債に関するリスクを負っていることを示しているといえると思われます。
また、本件資金調達取引は、元々Xグループで行われていた本支店間融資取引の方法に検討が加えられた結果採用されたものであり、そのため、第三者であるB社や、Xグループとはいえ本支店間融資取引に直接関係のないA社がリスクを負わないよう配慮されていました。すなわち、引用は省略しましたが、裁判所の認定によれば、まず、社債を第三者が保有する場合、「当該第三者にとっては、Xグループ内の資金調達に係る取引に参加し、社債の保有等に係るリスクを負担することになるなどの問題」があったことから、Xグループにおいては、「当該第三者に何らの不利益が及ばない仕組みを採用すること」が検討されていました。また、A社においても、「本件資金調達取引に参加するか否かを決定するに当たって、ルクセンブルクでの法制の下で、その参加がA社の財務実績に悪影響を及ぼさず、A社の利益に資するか否かという観点から検討が加えられ、本件資金調達取引に参加したとしても、本件資金調達取引に内在するリターン及びリスクに伴う影響を受けることがない旨」が確認されていました。
このように、本件資金調達取引は、取引から生じるリスクをA社やB社が負わない一方で、ロンドン本店がそのリスクを負う形で構築されていたと見ることができます。
したがいまして、バークレイズ銀行事件がいう本件利子に係る収益の支配、の具体的意味としては、「その取引によってリスクを負う者が誰であるか」、ということであり、この事件では、①から④の総合考慮により、リスクを負うのがXのロンドン本店であることの立証ができた、ということになるのだと思います。なお、本判決がいう「収益の支配」の具体的意味が「誰がリスクを負うのか」と解するのは、少し不自然に見えるかもしれませんが、収益を支配しているからこそリスクを負っているのであり、両者は裏腹の関係にあるといえるので、そこまで不自然ではないと考えます。
以上でご説明した内容を、要件事実の視点も踏まえておさらいしたいと思います。まず、バークレイズ銀行事件では、本件利子の実質的帰属者がA社とロンドン本店のいずれであるかが問題となっており、それがA社ということであれば、本件各処分が適法となります。したがいまして、国側は、本件利子の収益を実質的に享受しているのがA社であることを基礎付ける事実の主張立証責任を負っています。
これに対してロンドン本店が本件利子の実質的帰属者であれば、本件各処分が不適法となりますので、そのことを基礎付ける事実である①から④までの考慮事情を踏まえた各根拠事実については、Xが主張立証責任を負っています(図7参照)。このような状況にあって、Xにおいて、ロンドン本店が本件資金調達取引から生じるリスクを負っており、ひいては本件利子について実質的帰属者であることを主張立証できたことで、X勝訴に繋がったのだと思います。
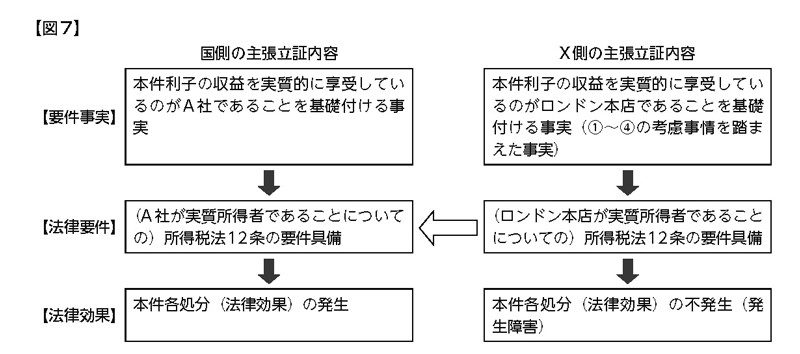
なお、バークレイズ銀行事件では、国側も実質所得者課税の原則に基づく主張立証を行っており、先ほどの契約書の名義人に対して課税を行おうとした例(5頁)とは少し異なっています。しかし、X側からすれば、実質所得者が別にいるということを主張立証する必要がある、という点では変わりません。
佐藤:それでは、バークレイズ銀行事件についてのまとめをお願いします。
向笠:バークレイズ銀行事件をはじめ、紹介した裁判例からしますと、実質所得者課税の原則が争いとなるケースでは、納税者側が、実質所得者が納税者以外の第三者であることを主張する必要があり、そのためには、取引の全体像を明らかにすることで、その取引で発生するリスクを誰が負うか、という事情がポイントといえます。したがいまして、誰がリスクを負うか、という点を明らかにすることを意識しながら、取引内容に関する事実を主張立証していくのが重要であると考えます。言い換えれば、問題となる取引について、誰がリスクを負っているのかが明らかとなるように事実を主張立証していくのが重要、ということであると思います。
3.補論:消費税(インボイス制度)と競争法
佐藤:最後に、本論と離れますが、向笠先生は、『免税事業者との取引条件見直しの実務 独禁法・下請法・フリーランス法への対応』(中央経済社、2024)という本も著しておられ、好評と伺っています。私も、本誌に書評を書かせていただきました(脚注23)。このテーマは実務上も重要だと思いますので、書籍のご紹介かたがた、実務上どのようなことに留意しなければならないかなど、ざっくばらんに教えていただければ幸いです。
向笠:どうもありがとうございます。ご紹介くださいました書籍は、仕入先が免税事業者であることでインボイス制度導入後に仕入税額控除ができない状況に置かれる事業者が、その免税事業者との間で取引条件を見直す際の留意点を解説するものです。消費税法だけでなく、独占禁止法(脚注24)、下請法(脚注25)やフリーランス法(脚注26)といった競争法に関する知識も重要となりますので、私の後輩で、公正取引委員会での勤務経験のある石川哲平弁護士と一緒に執筆しました。
佐藤先生には、刊行直後のタイミングで書評のご執筆という非常に強力な援護射撃をしていただき、大変お世話になりました。この場をお借りして、改めまして深く御礼申し上げます。
この書籍の内容は先ほどのとおりなのですが、もう少し詳しくご説明させていただきます。消費税法の改正により、2023年10月1日からインボイス制度が導入されましたが、導入前の段階から、仕入先が免税事業者のままである場合、事業者がその仕入先に対し、仕入税額控除ができなくなることを理由に、一方的に取引価格を引き下げたりするのではないか、という懸念が指摘されていました。そのため、財務省や公正取引委員会等が連名で2022年1月19日に公表した「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(脚注27)のQ7では、仕入先である免税事業者との取引について、取引価格の引下げ、取引停止や登録事業者となるような慫慂、といった行為類型ごとに、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直す場合の留意点が説明されています。
書籍では、この「Q&A」の考え方を踏まえ、具体例を用いながら、独占禁止法の優越的地位の濫用や下請法の規制対象となり得る場合を解説しています。また、この「Q&A」が公表された時点ではフリーランス法は施行されていませんでしたが、「Q&A」の考えを敷衍し、フリーランス法の規制対象となり得る場合も解説しています。
ここでは詳しい説明をするのが難しいのですが、ポイントは、取引関係上立場の強い事業者が、免税事業者である仕入先に対し、「仕入税額控除ができなくなるから」といった一方的な理由で取引条件を見直すことは許されず、見直しを行うには、仕入先の事情も考えながら真摯に協議を行う必要がある、ということです。例えば、インボイス制度導入前のものですが、共同組合が免税事業者である組合員に対し、当該組合が共同受注する運送事業を配分した際の運送代金を精算するに当たり、依頼主から入金される代金から別途消費税相当額(10パーセント)の手数料を差し引いた金額を支払うことが独占禁止法上問題ないか、という当該組合からの相談に対し、公正取引委員会は、「取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、免税組合員との十分な協議を行うことなく、組合の都合のみで、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を一方的に設定した場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。」と回答しています(脚注28)。
念のため申し上げますと、事業者が、仕入先がインボイスを発行できないことにより仕入税額控除ができなくなるという負担を一方的に負う理由も必要もなく、「Q&A」も、仕入先との間での取引条件の見直し自体は否定していません。問題は、その方法でして、仕入先に「仕入税額控除ができなくなる分の取引価格を引き下げます。」と一方的に伝えたり、「取引価格の引下げに応じないのなら、御社との取引は打ち切ります。」と無理やり引下げに応じさせたりするのは許されません、ということです(脚注29)。
佐藤:事業者が、仕入先との間で取引条件を見直したいと考えるのはよく分かりますが、見直しを考えた事業者の多くは、インボイス制度導入時に仕入先との間で既に交渉を行っているのではないでしょうか。逆に言えば、その時点で交渉をしていない事業者は、取引条件の見直しを考えておらず、したがって、今後、仕入税額控除ができないことを理由とする取引条件見直しという問題はあまり起きないのではないでしょうか。
向笠:先生のご指摘のとおり、免税事業者との取引条件見直しに関するご相談は、インボイス制度導入前後に多くありましたが、現在は少し落ち着いているように思います。もっとも、インボイス制度には経過措置があり、2025年6月現在は、免税事業者との取引であっても、仕入税額相当額の80%を控除できることなっています。これが、2026年10月1日からは仕入税額相当額の50%の控除となり、さらに、2029年9月30日には経過措置期間が終了し、10月1日以降の免税事業者との取引は、仕入税額控除ができなくなります(消費税法平成28年改正法附則52条、53条)。
| 2023.10.1~2026.9.30 | 仕入税額相当額の80%が控除可能 |
| 2026.10.1~2029.9.30 | 仕入税額相当額の50%が控除可能 |
| 2029.10.1~ | 仕入税額控除不可 |
仕入税額控除が80%できていたのが50%になってしまう、さらに、仕入税額控除が一切できなくなってしまう、というのは、事業者にとってインパクトが大きいと思いますので、これらのタイミングで、仕入先との取引条件をどうするか、という問題が再び生じるのではないかと考えています。したがいまして、その際に競争法違反を問われないようにするためにも、引き続きこの問題について意識しておくのが大事であると思います。
佐藤:良く分かりました。ご関心のある読者の皆様には、詳しくはぜひ書籍を手に取ってみていただきたいですね。向笠先生には、今後も税務の幅広い分野で、弁護士としての視点を生かして活躍されることを期待しています。今回は、多岐にわたるお話をいただき、誠にありがとうございました。
脚注
13 向笠太郎「判批」本誌1002号13頁。
14 金子宏『租税法〔第24版〕』(弘文堂、2021年)182頁。
15 佐藤英明『スタンダード所得税法〔第4版〕』(弘文堂、2024年)310頁。
16 真正に成立したと認められる契約書等がある場合、「特段の事情」がない限りその記載どおりの事実を認定すべき、とされている(処分証書の法理。最判昭和45年11月26日集民101号565頁等)。この例でも、国が契約書を提出した場合、「特段の事情」がない限り、その契約書の内容どおりの契約が成立したとされることになり、真の契約者が乙であること(=実質所得者乙であること)を裏付ける事実が「特段の事情」ということになる。本稿では、処分証書の法理についてはこれ以上立ち入らないが、関心のある方は、司法研修所編『改訂 事例で考える民事事実認定』(法曹会、2023年)25頁等を参照されたい(なお、裁判所ウェブサイトには、同書の3訂版(2025年)が掲載されている(https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/shihoukensyujyo/3teijirekan-honbun.pdf。最終閲覧日:2025年6月18日)。)。
17 判旨引用部分のうち、関係者(関係法人)については本稿の表記に合わせている。その点はご了承願いたい。
18 伊藤剛志「判批」ジュリスト1577号10頁。
19 細かい話であるが、親は、第一審の口頭弁論終結後に亡くなったため、子や養女が訴訟承継をしている。
20 佐藤修二編著『対話でわかる租税「法律家」入門』(中央経済社、2024)78頁以下。
21 消費税法13条についても、法律的帰属説が通説とされているようである(金子・前掲注14・183頁、浅妻章如「判批」ジュリスト1495号137頁)。
22 望月爾「判批」新・判例解説Watch租税法No.187・4頁、阿部雪子「判批」ジュリスト1592号148頁。
23 佐藤修二「書評 『免税事業者との取引関係見直しの実務 独禁法・下請法・フリーランス法への対応』」本誌1049号39頁。
24 正式名称は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」である。
25 正式名称は、「下請代金支払遅延等防止法」であるが、「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」の成立により、令和8年1月1日からは「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に変更予定である。
26 正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」である。
27 2022年3月8日付で改正版が公表されている。
28 公正取引委員会「独占禁止法に関する相談事例集(令和3年度)」相談事例7。
29 公正取引委員会「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」(令和5年5月)。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業。2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授。2022年~現在 北海道大学大学院法学研究科教授。著書に、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、 『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『対話でわかる租税「法律家」入門』(編著、中央経済社、2024)など。
向笠太郎 (むかさ たろう)
2009年上智大学法科大学院修了。10年弁護士登録。18年から22年まで東京国税不服審判所において任期付公務員(国税審判官)として勤務し、現在は、弁護士法人日本クレアス法律事務所所属。最近の著書、論文としては、本文掲記のもののほか、「名義株の判断方法−裁判例の分析を中心に」税経通信2025年7月号28頁、『景品表示法の法律相談〔第3版〕』(共著、青林書院、2025年)、「グループ通算制度についての一考察−個別的否認規定の不当性要件を考える−」本誌1067号17頁(2025年)、「租税分野における私法関係(契約関係)の重要性−南御堂参道事件を題材に−」本誌1026号12頁(2024年)等がある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















