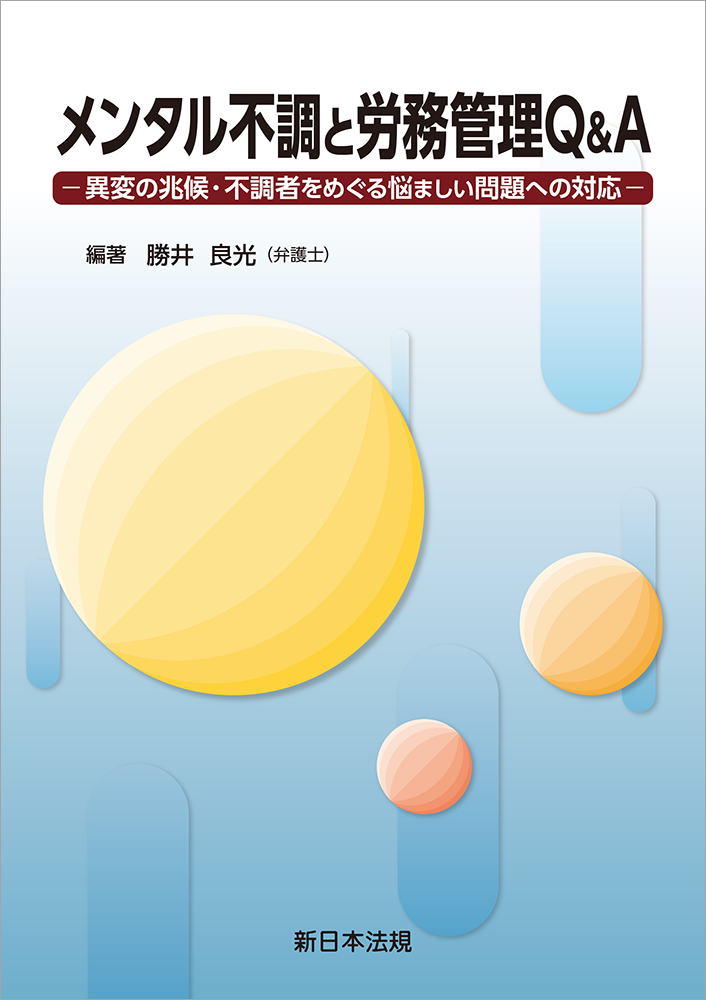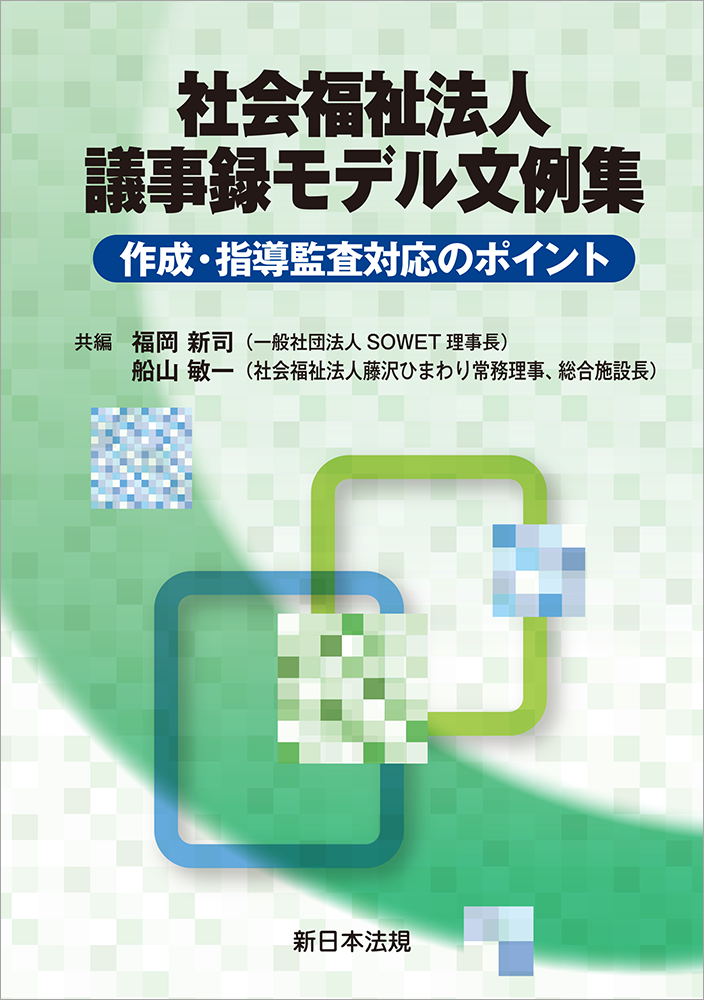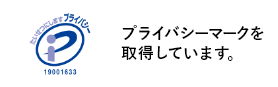解説記事2025年08月11日 ニュース特集 非上場株式の相続税評価をめぐる最近の裁決事例(2025年8月11日号・№1086)
ニュース特集
固定資産税等の負債計上の可否などで争い
非上場株式の相続税評価をめぐる最近の裁決事例
非上場株式の相続税評価額は、評価会社の規模などにより類似業種比準価額方式や純資産価額方式により評価されることになるが、その具体的な評価方法をめぐって相続人の申告が税務署により否認されるケースも多々見受けられるところだ。本特集では、非上場株式の評価方法をめぐり相続人の申告が否認された最近の裁決事例を2件紹介する。最初の事例は、純資産価額方式をめぐり評価会社が直前期末より後かつ課税時期より前に支払った固定資産税等を直前期末において評価会社の負債として計上できるか否かなどが争点となった事例(東裁(諸)令6第8号)である。もう1つの事例は、類似業種比準価額方式をめぐり評価会社が比準要素数1の会社に該当するか否かが争点となった事例(東裁(諸)令6第12号同13号)である。最初の事例では、国税不服審判所が税務署側の主張を斥けたうえで評価会社の負債計上を認める判断を示している点が注目される。
直前期末後かつ課税時期前に支払った固定資産税等の取扱いが問題に
課税時期(相続開始日)以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いの金額は、非上場株式の評価に係る1株当たりの純資産価額の計算上は負債に含まれることになる(評価通達186(2))。
財産評価基本通達186(純資産価額計算上の負債)
前項(185(純資産価額))の課税時期における1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算を行う場合には、貸倒引当金、退職給与引当金、納税引当金その他の引当金及び準備金に相当する金額は負債に含まれないものとし、次に掲げる金額は負債に含まれることに留意する。
(1)及び(3)(略)
(2)課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税の税額のうち、課税時期において未払いの金額
最初に紹介する裁決事例で争点となったのは、評価会社が直前期末(令和2年5月末)より後かつ課税時期より前に支払った固定資産税等の税額を直前期末において評価会社の負債として計上することができるか否かであった(図表1参照)。
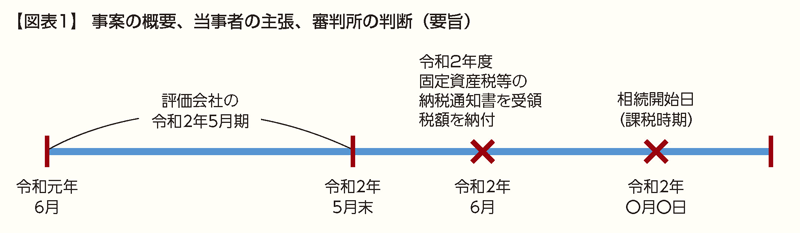
| 納税者側 (請求人) |
令和2年6月に納付された固定資産税等の税額は課税時期と擬制される評価会社の直前期末(令和2年5月末)において未払いのものに該当する。1株当たりの純資産価額を評価会社の直前期末の資産及び負債に基づき計算する場合には、令和2年6月に納付した固定資産税等の税額は負債に含まれる。 |
| 税務署側 (原処分庁) |
未払いであるか否かは課税時期において判断すべきであり、課税時期において支払済みの固定資産税等の税額は評価会社の負債に計上できない。固定資産税等の税額は課税時期である相続開始日以前の令和2年6月にその全額が納付されているから固定資産税等の税額は負債に含まれない。 |
| 審判所 | 本件における評価会社が直前期末(令和2年5月末)において未払いであった固定資産税等の税額は負債に含めて計算するのが合理的である。1株当たりの純資産価額の計算上、固定資産税等の税額は評価会社の直前期末において負債に含まれる。 |
事実関係をみると、評価会社は、令和2年度分の固定資産税等について令和2年6月に納税通知書の交付を受けた後に同月中に納付した。なお、その税額は評価会社の令和2年5月期の貸借対照表等に負債として計上されていなかった。
相続人は、評価会社に係る1株当たりの純資産価額の計算において相続開始日における仮決算を行わず、直前期末(令和2年5月末)の資産及び負債に基づき計算して固定資産税等の税額を負債の部に計上して評価会社に係る株式の評価を行った。これに対し税務署は、固定資産税等の税額は「課税時期において未払いの金額」(評価通達186(2))に該当せず評価会社の負債に計上できないなどとして、相続税更正処分等を行った。
これを不服として審査請求をした相続人は、令和2年6月納付の固定資産税等の税額は課税時期と擬制される評価会社の直前期末(令和2年5月末)においては未払いのものに該当するから負債に含まれると主張した。これに対し税務署側は、固定資産税等の税額は課税時期である相続開始日より前の令和2年6月にその全額が納付されているから評価会社の直前期末の負債には含まれないと主張した。
審判所、直前期末の負債に含まれると判断
審判所は、相続開始日において仮決算をしている場合には同日における資産の額は直前期末の資産である現金預金の額から固定資産税等の税額に相当する分が減少することから、直前期末において未払いの固定資産税等の税額を負債に含めて計算しないと仮決算を行って計算する場合と均衡を欠くことになることなどを指摘した。
また、賦課期日がその年の1月1日である固定資産税等について、納税通知書の発付の日によって負債として取り扱うか否かが異なるのは相当ではないとした。
これらを踏まえ審判所は、本件における評価会社が直前期末において未払いであった固定資産税等の税額は負債に含めて計算するのが合理的であると判断したうえで、1株当たりの純資産価額の計算上、本件における固定資産税等の税額は評価会社の直前期末において負債に含まれると結論付けている。
子会社(債務超過)に対し有する債権を減額評価できるか否かが争点に
最初に紹介した裁決事例でもう1つ争点となったのは、評価会社がその子会社に対して有する債権の一部が相続開始日において「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」(評価通達205)に該当するか否かであった(図表2参照)。
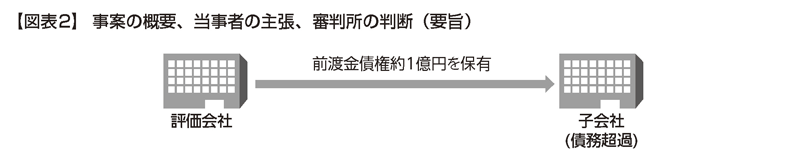
| 納税者側 (請求人) |
子会社は債務超過であり、その収益力から評価会社に対する債務を返済することが客観的に想定されないと判断すべき場合に当たるから、評価通達205による評価減が認められる。 |
| 税務署側 (原処分庁) |
子会社は経済的に破綻していることが客観的に明白で、回収の見込みがない又は著しく困難であると確実に認められるものであったとはいえないから、評価通達205による評価減は認められない。 |
| 審判所 | 子会社は相続開始日において評価通達205の(1)ないし(3)の事由と同程度に経済的に破綻していることが客観的に明白であり、回収の見込みがないか又は著しく困難であると確実に認められるとはいえない。評価会社が保有する子会社に対する前渡金債権の金額は、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」(評価通達205)に該当しないから、評価減は認められない。 |
事実関係をみると、評価会社は、相続開始日の直前期末である令和2年5月期において子会社に対する債権として前渡金約1億円(支払期限の定めはなく無利息)を有していた。
相続人は、1株当たりの純資産価額の計算において、前渡金債権の一部は評価通達205の要件(その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき)に該当するとして、相続税評価額を約3,000万円(帳簿価額は約1億円)として評価会社に係る株式を評価した。これに対し税務署は、子会社に倒産等の事実がないため前渡金債権は評価通達205の要件に該当しないとして、評価通達204により帳簿価額約1億円で評価するなどの相続税更正処分等を行った。これを不服とした相続人は、審査請求において、評価会社の子会社は債務超過であり、事業を継続しているがその収益の状況からみて評価会社に対する債務を返済することができないことは明らかであるなどと指摘したうえで、子会社の直前期末の資産の価額から同直前期末の負債(評価会社に対する負債を除く)の金額を控除した額を超える部分は回収が不可能あるいは著しく困難であるとして「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」(評価通達205)に該当すると主張した。
評価通達205による減額は認められず
審判所は、子会社が相続開始日の前後を通じて事業を継続し、事業収益を計上していたことや、債務超過の状態が続いていたものの前渡金債権に対する前受金債務以外の債務の支払いが遅滞し又は停止していたなどの事実もなく、子会社の負債の大部分である前受金債務は直ちに返還を要するものではなかったことなどを指摘した。
この点を踏まえ審判所は、子会社は相続開始日において評価通達205の(1)ないし(3)の事由と同程度に経済的に破綻していることが客観的に明白であり、回収の見込みがないか又は著しく困難であると確実に認められるとはいえないため、評価会社が保有する子会社に対する前渡金債権の金額は、「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」(評価通達205)に該当しないと結論付けた。
比準要素数の判定をめぐり1株当たり利益金額が0円か否かが争点に
比準要素数1の会社とは、直前期末に1株当たりの配当金額(直前期末以前2年間の平均、以下同じ)、利益金額、純資産価額(帳簿価額)のいずれか2つがゼロで、かつ、直前々期末の1株当たりの配当金額(直前々期末以前2年間の平均、以下同じ)、利益金額、純資産価額(帳簿価額)のいずれか2つ以上がゼロの会社のことである(評価通達189の(1))。
取引相場のない株式の発行会社が小会社の場合は類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用方式(類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L))により評価することができるが、評価通達179の(3)では類似業種比準方式で乗じるLの割合は0.5とされている。一方で、比準要素数1の会社の場合はLの割合が0.25と低く設定されていることから純資産価額方式の要素が大きくなる。(評価通達189−2ただし書)。次に紹介する裁決事例で争点となったのは、非上場株式である本件株式に係る評価会社(小会社に該当する)が比準要素数1の会社に該当するか否かという点である(図表3参照)。
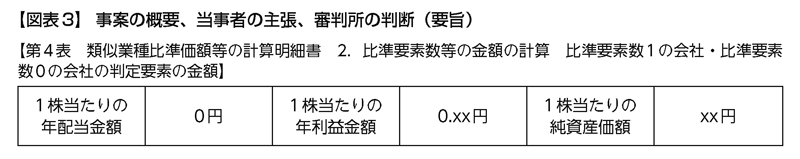
| 納税者側 (請求人) |
評価会社の1株当たりの利益金額は「0.xx円」であり少額であったとしても利益金額が存在するから「0円」ではない。1株当たりの純資産価額は「xx円」であり「0円」ではないから評価会社は比準要素数1の会社には該当しない。 |
| 税務署側 (原処分庁) |
記載方法等通達の定めにより評価明細書第4表の各欄の金額は表示単位未満の端数を切り捨てることになり、1株当たりの年利益金額の表示単位は「円」であるからその端数を切り捨てると「0円」になる。1株当たりの年配当金額・年利益金額が「0円」なので比準要素数1の会社に該当する。 |
| 審判所 | 評価明細書第4表の「1株当たりの利益金額」の「比準要素数1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄の単位は「円」であるから円未満の端数は切り捨てることとなる。本件株式に係る同欄の計算式によって算出される金額は1円未満の金額であることから、その金額の円未満の端数を切り捨てると0円となる。本件株式に係る評価会社は比準要素数1の会社に該当する。 |
事実関係をみると、請求人は本件株式に係る評価会社について1株当たりの利益金額及び純資産価額がゼロではないから比準要素数1の会社に該当しないとして、併用方式の適用に際してL=0.5とする割合により本件株式を評価して相続税の申告を行った。
これに対し税務署は、1株当たりの配当金額と利益金額はいずれも「0円」であるから比準要素数1の会社に該当するとしてL=0.25として併用方式を適用する相続税更正処分等を行った。これを不服とした請求人は、評価会社の1株当たりの利益金額は「0.xx円」であり少額であったとしても利益金額が存在するから「0円」ではないと指摘して、1株当たりの純資産価額も「0円」ではないから評価会社は比準要素数1の会社には該当しないと主張した。
円未満切捨てで比準要素数1の会社に該当
審判所は、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について(記載方法等通達)」(令和元年9月18日課評2−41ほかによる改正前のもの)が評価明細書第4表の各欄の金額の単位を様式に定め、第4表記載方法等の1のなお書で「この表の各欄の金額は各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨を定めている点について、1株当たりの利益金額が極めて少額で0に近い場合は0である会社と同視してその会社の株式を評価することに合理性が認められると指摘。また、画一的な基準として1株当たりの利益金額について1円未満であるか否かにより判定することも一般的な合理性が認められると指摘した。これらを踏まえ審判所は、評価明細書第4表の「1株(50円)当たりの利益金額」欄の「比準要素数1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄の単位は「円」であることから、円未満の端数は切り捨てることとなるという判断を示した。そのうえで審判所は、本件株式に係る同欄の計算式により算出される金額は1円未満の金額であることから、第4表記載方法等の1のなお書の定めにより円未満の端数を切り捨てるとその欄の金額は0円となると認められるとして、本件株式は比準要素数1の会社の株式に該当するからL=0.25として併用方式を適用する相続税更正処分等は適法であると結論付けた。
通達改正により「各欄の表示単位未満の端数を切り捨てる」旨の記載場所が変更
2番目に紹介した裁決事例における「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の記載方法等について」(令和元年9月18日課評2−41ほかによる改正前のもの)では、その記載方法等についての「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」の1のなお書において、「この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨が定められていた。
この点に関し現在では、令和5年9月28日課評2−76ほかによる通達改正により、「この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨の定めは「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の記載方法等について」の冒頭のまた書の部分に記載されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -