解説記事2025年08月11日 税務マエストロ 消費税法36条の問題点(2025年8月11日号・№1086)
税務マエストロ
消費税法36条の問題点
#310
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
消費税法36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の適用については、消費税法12条の4(高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例)の創設やインボイス制度の導入に伴い、数回の改正を経て現在に至っている。本稿では、この棚卸資産に係る消費税額の調整規定が抱える問題点について考察する。
Ⅰ 免税事業者が課税事業者になった場合の税額調整
消費税には会計や所得税、法人税のような費用収益対応の概念がない。仕入控除税額の計算にあたっては、期首の在庫や期末の在庫、売上原価は一切関係させず、当該課税期間中の課税仕入れ等の税額を基に仕入控除税額を計算するのは周知のとおりである。
しかし、免税事業者が課税事業者になるような場合には、免税期間中に仕入れた棚卸資産は仕入税額控除の対象とはしていない。これを課税事業者になってから販売した場合には、その売上げについてだけ消費税が課税されることとなってしまい、継続して課税事業者である事業者と比べ、不利な扱いを受けることとなってしまう。
そこで、免税事業者が課税事業者となった場合には、売上げに対する消費税とのバランスをとるために、免税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を、仕入控除税額の計算の基となる課税仕入れ等の税額に加算することを認めることとした。
この棚卸資産に係る消費税額の加算調整は、基準期間や特定期間における課税売上高が免税点を超えたことにより強制的に課税事業者となる場合の他、免税事業者が「課税事業者選択届出書」を提出したことにより課税事業者となる場合、インボイスの登録により課税事業者になる場合、相続や吸収合併、吸収分割があった場合の納税義務免除の特例規定により、年又は事業年度の中途から課税事業者となる相続人や合併法人、分割承継法人についても適用される(消法36①)。
Ⅱ 棚卸資産の範囲と取得価額・調整税額の計算
1 棚卸資産の範囲
税額調整の対象となる棚卸資産とは、棚卸をすべき資産で次に掲げるものをいう(消法2①十五、消令4)。
① 商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
② 半製品
③ 仕掛品(半成工事を含む。)
④ 主要原材料
⑤ 補助原材料
⑥ 消耗品で貯蔵中のもの
⑦ 上記①~⑥に掲げる資産に準ずるもの
消費税の法令に規定されている棚卸資産の範囲は、法人税の法令に規定する棚卸資産の範囲とまったく同一の定義になっている(法法2①二十、法令10)。
会計上においても、販売用の資産に関する取扱いとしては、財務諸表等規則ガイドライン15−5において商品とは「販売の目的をもって所有する物品」と規定されている。
注意したいのは、消費税の世界では、あくまでも「課税仕入れに係る棚卸資産」に限り、税額調整の対象とされるということである。例えば、山林を開発し、宅地に造成して販売するような場合には、その造成した宅地は棚卸資産には該当するものの、「課税仕入れに係る棚卸資産」ではないことから、その造成費用については税額調整の対象とすることはできないことになる。
これに対し、宅地を造成して建売住宅を建築し、販売するような場合には、その建売住宅(土地付建物)は課税仕入れに係る棚卸資産であるから、建物の建築費は勿論のこと、宅地の造成費用についても税額調整の対象に取り込むことができるのである。
では、建売住宅の敷地を造成したものの、建物の建築に着工する前に決算日を迎えたような場合の宅地の造成費用はどうなるのであろうか……?
販売用の宅地であれば、上記のように「課税仕入れに係る棚卸資産」には該当しないことから、その造成費用は税額調整の対象とはならないことになる。しかし、その宅地が建売住宅の敷地として使用されるものであるならば、たとえ建物が建築されていなくとも、その造成費用は「課税仕入れに係る棚卸資産」として税額調整の対象とされるべきである。
また、建物の建築途中で決算日を迎えたような場合には、その建築途中の建物は仕掛品であり、免税期間中に課税仕入れが行われている材料費などについては当然に税額調整の対象として何ら問題はない。
2 金地金は棚卸資産に該当するか?
(1)裁決事例
金地金が棚卸資産に該当するか否かについて争われた裁決事例がある(裁決事例集J 135−5−06:令和6年4月25日裁決)。
請求人は、金地金の売買を反復継続して行うものではないから、金地金の売買は請求人の営業に当たることはなく、棚卸資産には該当しないものと主張した。
これに対し、審判所は、会計処理のみにより形式的に判断するのではなく、資産(金地金)と事業目的との関係などの客観的な事実に基づき、売却目的で保有する資産なのかどうかを実質的に判断すべきであるとした。そして、請求人が行う金地金の売買に係る取引額につき、下記のような事実があることを理由に、その事業目的に係る業務過程で売却することを目的として本件金地金を保有していたものと認められるから、この金地金は棚卸資産に該当するものとし、課税事業者が免税事業者になる場合の期末棚卸資産の税額調整規定(Ⅳ)を適用することとした。
① 本件取引が請求人の事業規模に照らして大きなものであり、請求人の事業に及ぼす影響が大きいこと。
② 請求人における金地金の売買は、補助ないし付随的な活動とは言えないこと。
③ 定款に明示的に掲げられた事業目的そのものではないとしても、事業目的から離れたところで行われているものとは言えないこと。
④ 本件金地金は、請求人の事業目的に係る取引の客体にほかならないと認められること。
⑤ 本件金地金の取得から売却に至る経緯及び本件金地金を取得するための借入金を返済するためには本件金地金を売却する必要があったこと。
(2)企業会計上の取扱い
請求人の主張によれば、企業会計上、金地金のように市場価格の変動による利益を得ることを目的として取得する資産が棚卸資産に該当するかどうかは、経営者の意図だけでこれを判定すると恣意的になる可能性があることから、売却益を目的とする大量の取引を行っていると認められる客観的状況を備えているかどうかにより、下記①又は②により判定するとされている(棚卸資産会計基準第16項が準用する金融商品会計基準における売買目的有価証券に関する取扱い・金融商品会計に関する実務指針第65項及び第268項)。
① 金地金の売買を業としていることが定款の上から明らかで、かつ、トレーディング業務を日常的に遂行し得る人材から構成された独立の専門部署によって金地金が保管・運用されているか。
② 金地金の売買を頻繁に繰り返しているか。
(3)判断
本誌No.1056(2024.12.23)9頁では、下記①と②について、本裁決の問題点を指摘している。
① 金地金のようにトレーディングを目的として取得する資産について、取引額が大きいことを主たる理由として「棚卸資産」に該当すると解することは、少なくとも企業会計における一般的な理解とは異なるように見えること。
② 租税回避目的の存在を理由に消費税法36条5項の「棚卸資産」の意義を広く解したのであれば、その是非が問題になる可能性があること。
本件記事にも記述されているが、武富士事件(平成23年2月18日最高裁判決)のように、法の解釈では限界がある事案については立法によって対処するべきである。請求人が主張するように、企業会計では、金地金のようなトレーディングを目的とした資産を棚卸資産とするケースは非常に限定的に解釈している。請求人である不動産管理・賃貸業者が保有する金地金が棚卸資産に該当するという裁決には無理があるように思えてならない。
3 現住建造物は棚卸資産に該当するか?
中古の賃貸マンションを入居付で購入し、空き室を可能な限り減らした上で売却するというビジネスモデルにつき、個別対応方式を適用する場合の取得物件の用途区分が問題となった事案がある。令和5年3月6日、最高裁第一小法廷において本件判決が下され、原告の株式会社ムゲンエステート及び株式会社エー・ディー・ワークスはいずれも敗訴して結審した。
本件判決とは争点が異なるので特段問題になることはなかったが、そもそも賃貸中の建物が棚卸資産に該当するかどうかということは、いったい何を基準に判断するのであろうか。決算書の表示方法で決定されるというような単純なものではないであろうし、賃貸していた期間の長短により決定するというものでもないように思われる。棚卸資産として計上した物件であっても、買い手が見つからずに何年も在庫物件として保有するようなことは決して珍しいことではない。
固定資産として計上し、減価償却をしている賃貸物件を売却した場合には、棚卸資産ではないことは論を俟たないであろうが、決算書の表示や減価償却の有無により棚卸資産と固定資産を区分するのもいささか無理があるように感ずるところである。
4 棚卸資産の取得価額と調整税額(消令54①、②)
(1)購入資産と自社製品
計算の基となる棚卸資産の取得価額には、引取運賃や荷役費、販売準備費用などの付随費用が含まれるので、簿記会計あるいは所得税、法人税の規定に基づいて計算した棚卸資産の取得価額に7.8/110(6.24/108)を乗じて調整税額を計算すればよいことになる(消基通12−7−1~12−7−3)。
自社製品の在庫などについては、材料費、経費などの額に付随費用を加算した合計金額に7.8/110(6.24/108)を乗じて計算する。なお、棚卸資産の取得価額に加算する付随費用や材料費、経費などの額は、当然のことながら課税仕入れに係る支払対価の額に限られる。
(2)輸入貨物
棚卸資産が輸入貨物の場合には、帳簿価額ではなく、その課税貨物の課税標準である金額に、引取りに係る消費税及び地方消費税並びに付随費用を加算した合計金額に7.8/110(6.24/108)を乗ずることとされているので、結果、引取りに係る消費税額と付随費用に7.8/110(6.24/108)を乗じて計算した金額との合計額が調整税額ということになる。輸入仕入高が消費税計算に関係しないように、棚卸資産に係る調整税額についても、その棚卸資産の帳簿価額(仕入高)は消費税計算に影響を及ぼさないということである。
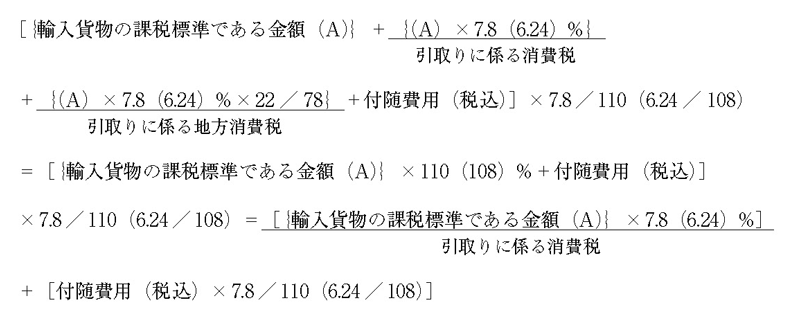
ところで、消費税法30条1項(仕入れに係る消費税額の控除)では、仕入控除税額の計算の基となる課税仕入れ等の税額について、「……保税地域からの引取りに係る課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額の合計額を控除する。」と規定しており、当該消費税額の計算に用いる課税標準については何も書かれていない。課税貨物につき課された又は課されるべき消費税額については、税関から交付されるインボイスに記載された消費税額がそのまま課税仕入れ等の税額となるのであるから、課税標準についての記載がないのはある意味当然である。
これに対し、同法施行令54条1項2号イでは、課税貨物に係る消費税額について、上記算式のように、「輸入貨物の課税標準である金額+引取りに係る消費税額+地方消費税額」を基に計算することとしている。消費税法36条1項で「……政令で定める金額に110分の7.8(108分の6.24)を乗じて算出……」と規定してしまったがために、結果として施行令において無駄な算式を書かざるを得なくなったものと思われる。
消費税法36条1項と同法施行令54条1項を下記のように改正して法令のスリム化を図ることはできないのであろうか……(下線の部分が削除・追加箇所)。
消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)
第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者が、同項の規定の適用を受けないこととなつた場合において、その受けないこととなつた課税期間の初日(第10条第1項、第11条第1項又は第12条第5項の規定により第9条第1項本文の規定の適用を受けないこととなつた場合には、その受けないこととなつた日)の前日において消費税を納める義務が免除されていた期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの(これらの棚卸資産を原材料として製作され、又は建設された棚卸資産を含む。以下この条において同じ。)を有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額として政令で定める金額(第3項及び第5項において同じ。)をその受けないこととなつた課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす。
:
消費税法施行令第54条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産の取得価額)
法第36条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産 次に掲げる金額の合計額に110分の7.8(当該課税仕入れに係る棚卸資産が他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係るものである場合には、108分の6.24)を乗じて算出した金額
イ 当該資産の課税仕入れに係る支払対価の額
ロ 引取運賃、荷役費その他当該資産の購入のために要した費用の額
ハ 当該資産を消費し、又は販売の用に供するために直接要した費用の額
二 保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するもの イの金額と、ロ及びハの金額の合計額に110分の7.8を乗じて算出した金額との合計額
イ 当該課税貨物の引取りに係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)
:
(以下省略)
5 製品などの取得価額に含まれる消費税額はどのように把握するか?
仕掛品や製品の取得価額の内訳は、材料費や外注費、労務費、経費などで構成されている。計算の基となる棚卸資産の取得価額には、労務費のように課税仕入れとならない費用は含まれないのであるから、原価の構成割合などの合理的な基準を用いて、課税仕入れに係る支払対価の額を各自算出しなければならないことになる。労務費も含めた原価の額に7.8/110(6.24/108)を乗じて調整税額を計算することはできないので注意しなければならない。
Ⅲ 適用対象事業者と適用要件
棚卸資産に係る税額調整の規定は、免税事業者が課税事業者になった課税期間について適用されるものである。ただし、新たに課税事業者となった課税期間において簡易課税制度や2割特例の適用を受けようとする場合には、当然のことながらこの規定は適用されない。
また、この規定の適用を受けようとする場合には、棚卸資産の明細を記録した書類を確定申告期限から7年間保存することとされている(消法36②、消令54③、⑤)。
ところで、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間における課税仕入れ等の税額は80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間における課税仕入れ等の税額は50%を課税仕入れに係る消費税額とみなすこととされている(平成28年改正法附則52④、53④)。
では、免税事業者であった期間中の課税仕入れに係る棚卸資産についても、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れについては、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間における課税仕入れ等の税額は80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間における課税仕入れ等の税額は50%を調整税額の対象とする必要があるのかということであるが、免税事業者が課税事業者になった場合の保有棚卸資産の税額調整は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に認められている80%(50%)控除の経過措置に関わらず、その全額を税額調整の対象とすることが認められている。
免税期間中の課税仕入れに係る棚卸資産について、申告義務がないにも関わらず、適格請求書発行事業者から仕入れたものと適格請求書発行事業者以外の事業者から仕入れたものに区分することは非現実的である。また、棚卸資産に係る税額調整の規定は、棚卸資産の明細を記録した書類を確定申告期限から7年間保存することが適用要件とされているのであり、インボイスの保存まで要求しているものではない(消法36②)。
こういった理由から、適格請求書発行事業者以外の事業者からの課税仕入れに係る棚卸資産について、平成28年度のインボイス制度創設時には適用することとされていた80%(50%)控除の経過措置(平成28年改正法附則52④、53④)について、令和4年度の改正により、その全額を税額調整の対象とすることに変更したものと思われる(新平成28年改正法附則52④、53④)。
Ⅳ 課税事業者が免税事業者になる場合の期末棚卸資産の税額調整
基準期間における課税売上高が免税点以下となったことにより免税事業者になる場合、「課税事業者選択届出書」を提出している事業者が「課税事業者選択不適用届出書」を提出して免税事業者になる場合、適格請求書発行事業者が「登録取消届出書」を提出して免税事業者となる場合には、課税期間末に保有する棚卸資産は免税事業者となってから販売するものであり、その売上げについては消費税は課税されないことになる。
しかし、その期末棚卸資産を仕入れたのは課税事業者のときであり、その棚卸資産については、販売の有無に関係なく、課税仕入れの時点で仕入税額控除の対象とされることになる。
そこで、売上げに対する消費税とのバランスをとるために、本則課税を適用している事業者が翌課税期間から免税事業者になる場合には、課税期間末日に保有する棚卸資産のうち、免税事業者となる直前の課税期間中に仕入れたものについては仕入税額控除を制限することとしたものである(消法36⑤)。
ただし、免税事業者となる課税期間の前課税期間において簡易課税制度や2割特例の適用を受けている場合には、当然のことながらこの規定は適用されないことになる(消基通12−7−4)。
ところで、消費税法36条5項(課税事業者が免税事業者になる場合の期末棚卸資産の税額調整)を読んでいくと、「事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において……」と書いてある。続きを読めば課税事業者が免税事業者になる直前の課税期間で期末棚卸資産の税額調整をすることはわかるのであるが、いきなり「……消費税を納める義務が免除されることとなった場合……」と書いてしまったら文脈が繋がらないのではないだろうか?「……消費税を納める義務が免除されることとなる場合……」と書かなければいけないように思うのであるが……。
また、課税事業者が翌課税期間から免税事業者になるケースでは、その課税事業者である最後の課税期間中に仕入れた棚卸資産だけが税額調整の対象とされるのであり、その課税期間より前の課税期間で仕入れたもののうち、在庫として保有するものについてまで調整をする必要はない。
例えば、3月決算法人が課税期間を3ヶ月単位に短縮しているような場合であれば、最後の課税期間である1~3月課税期間中に仕入れた棚卸資産のうち、3月末時点で在庫として保有しているものだけが税額調整の対象とされることになるのである。
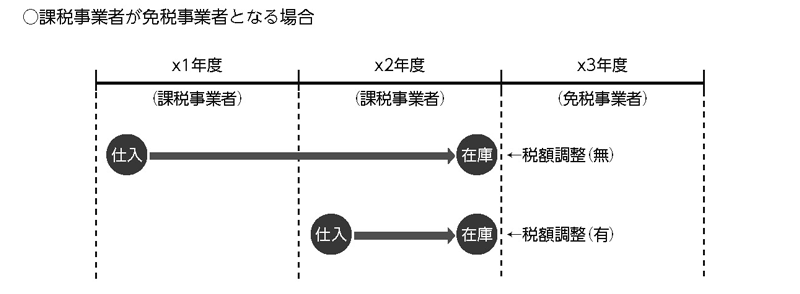
(注)x1年度中に仕入れた棚卸資産のうち、x2年度の課税期間の末日において保有するものがあったとしても、これについてはx1年度の課税期間においてすでに税額控除は完結しているのであるから調整をする必要はない。
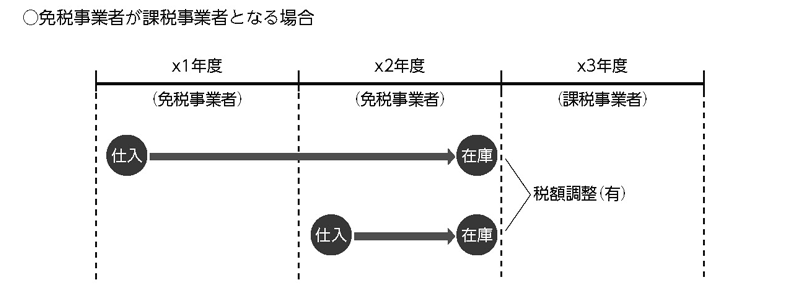
Ⅴ 隔年で納税義務が発生する場合の税額調整はどうなるか?
下図のように、隔年で納税義務が発生するようなケースでは、棚卸資産の税額調整はどうなるのであろうか? 以下、事例別に検証することとする。
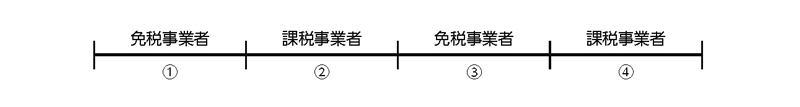
| 事 例 | 内 容 |
| ②の期首において保有する棚卸資産については期首棚卸資産の税額調整をすることとなるが、この棚卸資産を②の期末においても保有する場合、②の課税期間において、期末棚卸資産の税額調整が必要か否か? | ②の課税期間において、期首棚卸資産の税額調整をしたものが期末においても現存する場合であるが、この棚卸資産は②の課税期間中に仕入れたものではない。 期首棚卸資産の税額調整については、消費税法36条1項で「……仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす」と規定しているのであり、「その課税期間中に課税仕入れを行ったものとみなす」と規定しているわけではない。したがって、期首棚卸資産に係る消費税額を課税仕入れ等の税額に加算していたとしても、このうち、期末に在庫として保有する部分について、その消費税額を課税仕入れ等の税額から控除する必要はない。 |
| ②の期首において保有する棚卸資産について、②の課税期間において期首棚卸資産の税額調整を適用したものが④の期首においても現存する場合、④の課税期間において、再び期首棚卸資産の税額調整を適用することができるか? | ②の期首において保有する棚卸資産については、②の課税期間において期首棚卸資産の税額調整を適用することになる。この棚卸資産が②の期末においても現存する場合には、上記事例のとおり期末棚卸資産の税額調整はする必要がない。 これがさらに繰り越されて④の期首においても現存する場合であるが、この棚卸資産については②の課税期間においてすでに税額調整の対象としているものであり、理屈から考えると、④の課税期間において再び期首棚卸資産の税額調整を適用する余地はないように思われる。しかし、この棚卸資産は①の免税期間中に仕入れたものであり、これを課税事業者となった④の課税期間の期首において保有するわけであるから、消費税法36条1項の規定の適用により、④の課税期間において再び税額調整の対象とすることが可能となる。 消費税法には、これを認めないとする旨の規定は存在しないのである。 |
| ②の課税期間中に仕入れ、②の期末において保有する棚卸資産については期末棚卸資産の税額調整をすることとなるが、この棚卸資産を④の期首においても保有する場合、④の課税期間において、期首棚卸資産の税額調整が可能か否か? | ②の課税期間中に仕入れ、②の期末において保有する棚卸資産については期末棚卸資産の税額調整をすることになる。しかし、この棚卸資産は免税期間中に仕入れたものではないので、これを④の期首において保有する場合であっても、④の課税期間において、期首棚卸資産の税額調整の対象とすることはできないことになる。 消費税法36条5項では、「……仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする」と規定しているのであり、「翌課税期間において課税仕入れを行ったものとみなす」と規定しているわけではないので、本事例のケースでは、再度税額調整の対象に取り込む余地はないということになるのである。 |
Ⅵ 高額特定資産に該当する棚卸資産に対する3年縛りの適用(令和2年度改正)
消費税法第12条の4(高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除の特例)では、「……簡易課税制度又は2割特例の適用を受けない課税期間中に高額特定資産の仕入れ等を行つた場合……」と規定している。つまり、本則課税の適用期間中に高額特定資産を取得した場合に限り、3年縛りの規定が適用されることになるのである。
これに対し、消費税法第36条(納税義務の免除を受けないこととなつた場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)では、「棚卸資産に係る調整税額を、課税事業者となった課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額とみなす……」と規定しており、「課税事業者となった課税期間において課税仕入れを行ったものとみなす」といったような規定ぶりにはなっていない。
したがって、税額調整の対象となる期首棚卸資産が高額特定資産に該当したとしても、旧法の下では3年縛りの規定は適用されないことになる。そこで、令和2年度改正により、高額特定資産に該当する棚卸資産について、免税事業者が課税事業者となった場合の税額調整措置を適用する場合には、当該棚卸資産に係る課税仕入れについても3年縛りの規定を適用することとしたものである(消法12の4②、37③四、平成28年度改正法附則51の2④)。
1 調整対象自己建設高額資産の取扱い
免税期間中に自己建設した棚卸資産については、建設等に要した費用の額《原材料費や経費となる課税仕入高(税抜)》の累計額が1,000万円以上となったもの(調整対象自己建設高額資産)についてだけ、3年縛りの規定を適用することとしている。
したがって、免税期間中の課税仕入高が1,000万円未満の仕掛工事や完成工事などの棚卸資産について「免税→課税」の税額調整措置を適用する場合には、3年縛りの規定は適用されない(消基通1−5−29)。
(注)調整対象自己建設高額資産の建設等に要した費用の額には、原材料として使用する調整対象固定資産や自己保有の建設資材等も含まれる(消基通1−5−31)。
(1)拘束期間
調整対象自己建設高額資産については、「免税→課税」の税額調整措置を適用した課税期間の翌課税期間から、次の期間までの各課税期間について、本則課税が強制適用となる。
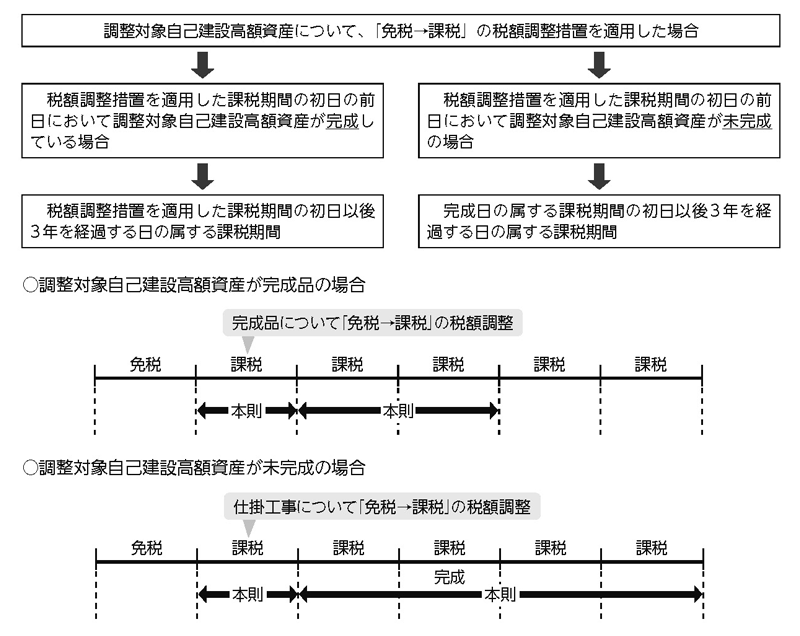
(2)3年縛りとの関係
免税期間中の課税仕入高が1,000万円未満の仕掛工事などに「免税→課税」の税額調整措置を適用する場合には、3年縛りの規定は適用されないが、課税事業者となった後の課税期間において、本則課税の適用期間における課税仕入高の累計が1,000万円以上となった場合には、ここで「自己建設高額特定資産」の仕入れを行ったこととなる。
よって、この課税期間から3年縛りの規定が適用されることとなることに注意する必要がある(消基通1−5−29(注))。
○3年縛りとなるケース( 課税仕入高の累計≧1,000万円)
課税仕入高の累計≧1,000万円)
税額調整をした②の翌期(③)から完成日の属する課税期間(④)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間(⑥)まで、本則課税が強制適用となる。
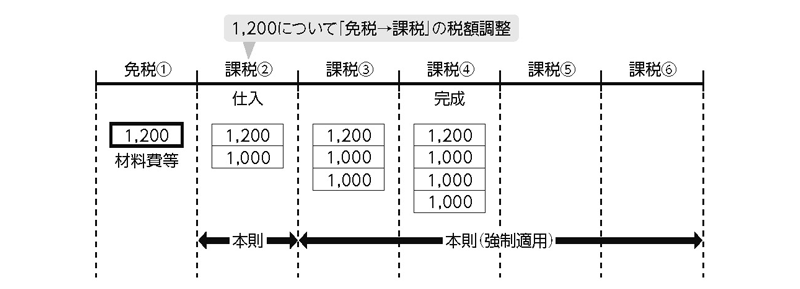
○3年縛りが適用されないケース( 課税仕入高の累計<1,000万円)
課税仕入高の累計<1,000万円)
免税期間中に発生した仕掛工事は1,000万円未満であり、調整対象自己建設高額資産には該当しない。また、課税事業者となってからの課税仕入高の累計も1,000万円未満(900万円)であり、自己建設高額特定資産に該当しないため、3年縛りの適用はない。
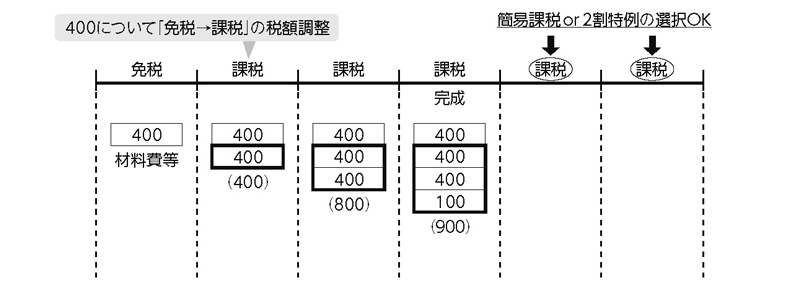
○3年縛りとなるケース( 課税仕入高の累計≧1,000万円)
課税仕入高の累計≧1,000万円)
免税期間中に発生した仕掛工事は1,000万円未満であり、調整対象自己建設高額資産には該当しない。ただし、課税事業者となってからの課税仕入高の累計額が1,000万円以上(②+③=1,200万円)となるため、③期において、仕掛工事は自己建設高額特定資産に該当することになる。
結果、③の翌期(④)から完成日の属する課税期間(④)の初日以後3年を経過する日の属する課税期間(⑥)まで、本則課税が強制適用となる。
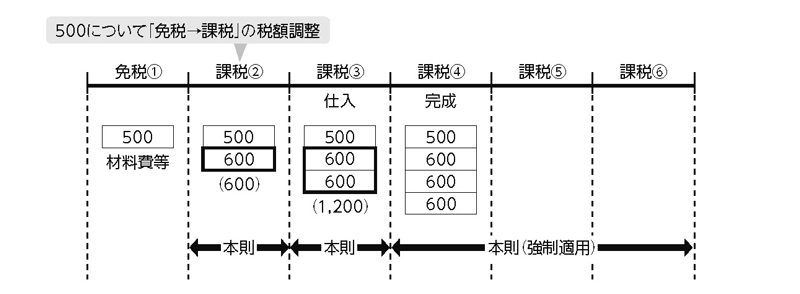
2 居住用賃貸建物との関係
居住用賃貸建物に該当する棚卸資産について「免税→課税」の税額調整措置を適用する場合には、次の日を仕入日として調整税額を計算することになる(消令53の3)。
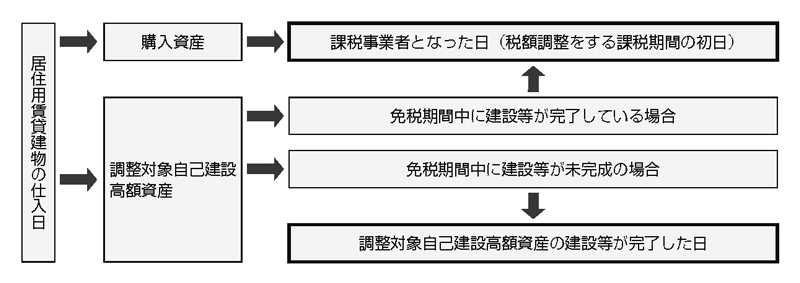
居住用賃貸建物に該当する棚卸資産については、「免税→課税」の税額調整措置を適用したとしても、結果として仕入税額控除はできない。ただし、調整期間中に課税賃貸用に供した場合又は売却した場合には、課税賃貸割合又は課税譲渡等割合により調整税額を計算し、取り戻し控除が認められることになる。
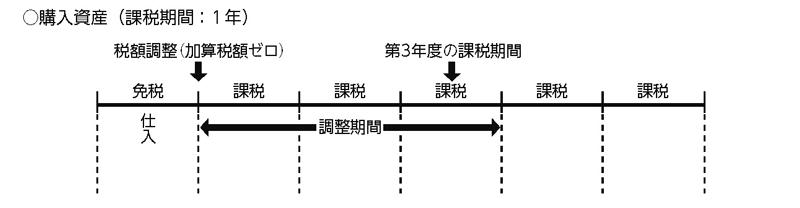
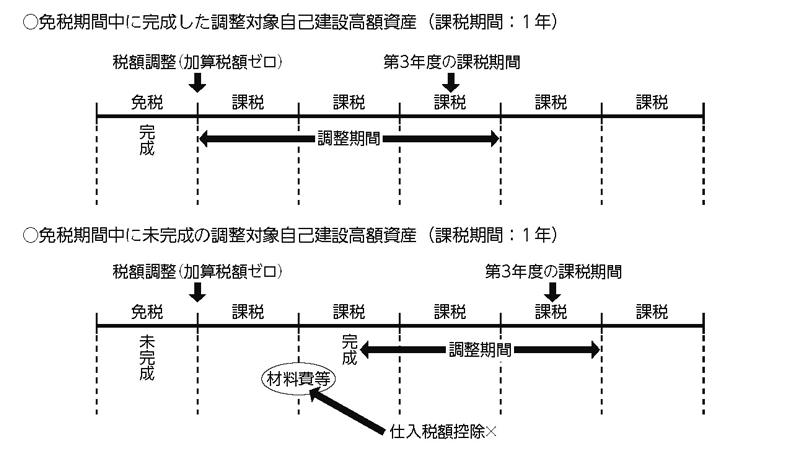
Ⅶ みなし登録期間前後における棚卸資産の税額調整
被相続人(適格請求書発行事業者)の登録の効力は相続人に承継されないので、事業を承継した相続人が登録を受けるためには、あらためて登録申請書を提出する必要がある。
適格請求書発行事業者である被相続人の死亡に伴い、相続人が事業を承継した場合には、その相続人がインボイスを交付することができないとなると、事業の継続に支障を来すことになりかねない。そこで、みなし登録期間中はその相続人を適格請求書発行事業者とみなすこととしているのである(消法57の3③)。
不動産賃貸のケースであれば、店舗や事務所などの賃借人サイドからみた場合、家主である被相続人が死亡し、遺産分割も確定していない状況ではインボイスの交付を受けられるかどうかがわからない。そこで、みなし登録期間中は相続人を適格請求書発行事業者とみなすことにより、賃借人の仕入税額控除の権利を保障することにしたものと思われる。
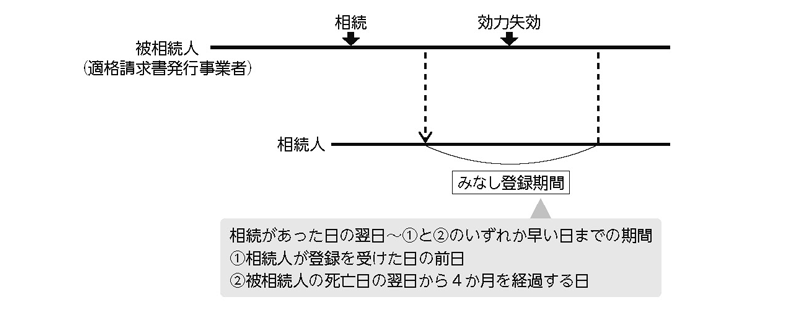
なお、相続人が事業を営んでいる場合には、みなし登録期間中は、相続人オリジナルの売上高についても申告義務があることに注意する必要がある。
インボイスの登録をしていない相続人が相続発生前から駐車場の賃貸をしているような場合であれば、相続人に登録の意思がなくとも、みなし登録期間中は、その賃貸収入について申告の必要があるということである。
1 相続人が免税事業者の場合の棚卸資産の税額調整
相続人が免税事業者の場合には、みなし登録期間の初日から課税事業者になることから、みなし登録期間の初日の前日において保有する免税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を、課税仕入れ等の税額に加算することができる(消令70の8①)。
ただし、相続人が簡易課税制度や2割特例の適用を受ける場合には、当然のことながら棚卸資産の税額調整はできない。
(注)非登録事業者から仕入れた棚卸資産であっても80%(50%)経過措置を適用する必要はない(新平成28年改正法附則52④、53④)。
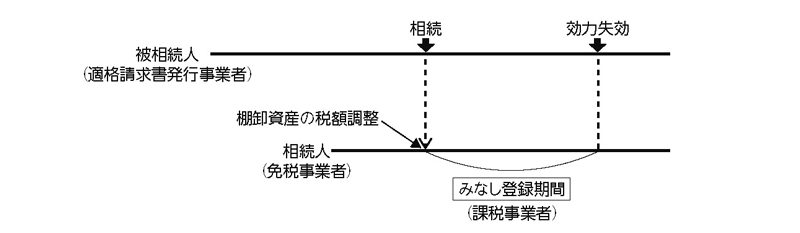
2 相続人が免税事業者になる場合の棚卸資産の税額調整
免税事業者であった相続人がみなし登録期間中にインボイスの登録申請をしなかった場合には、みなし登録期間の末日の翌日から再び免税事業者となることができる。この場合には、みなし登録期間の末日の属する課税期間中に仕入れた棚卸資産のうち、みなし登録期間の末日において保有している棚卸資産に係る消費税額は、課税仕入れ等の税額から控除しなければならない(消令70の8②)。
ただし、相続人が簡易課税制度や2割特例の適用を受ける場合には、当然のことながら棚卸資産の税額調整をする必要はない。
(注)非登録事業者から仕入れた棚卸資産については80%(50%)経過措置を適用して調整税額を計算する(平成28年改正法附則52④、53④)。
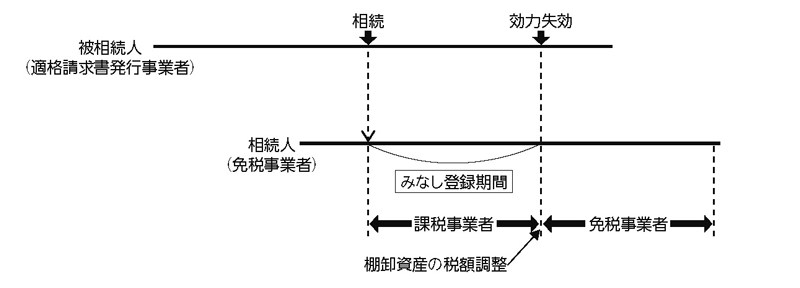
※みなし登録期間の初日の前日において保有する免税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を課税仕入れ等の税額に加算することができる(1参照)。
3 みなし登録期間が1月1日をまたがる場合
消費税法施行令第70条の8第2項に規定する消費税法第36条第5項の読替規定は下記のようになっている。
適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整(消令70の8②)
事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなった場合において、第57条の3第3項に規定するみなし登録期間の末日において当該みなし登録期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該みなし登録期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
この読替規定に基づき、x1年10月31日に相続が発生した場合について考えてみたい。読替規定の後半には、「……当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。」と書かれている。
つまり、x2年1月1日~2月28日期間中に取得した棚卸資産だけが減額調整の対象となるのであり、x1年11月1日~12月31日期間中に取得した棚卸資産は、みなし登録期間の末日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれていないため、減算調整の必要はない。
x1年11月1日~12月31日期間中に取得した棚卸資産は、みなし登録期間中に取得した棚卸資産ではあるものの、x1年分の申告で仕入税額控除が完結しているものである。
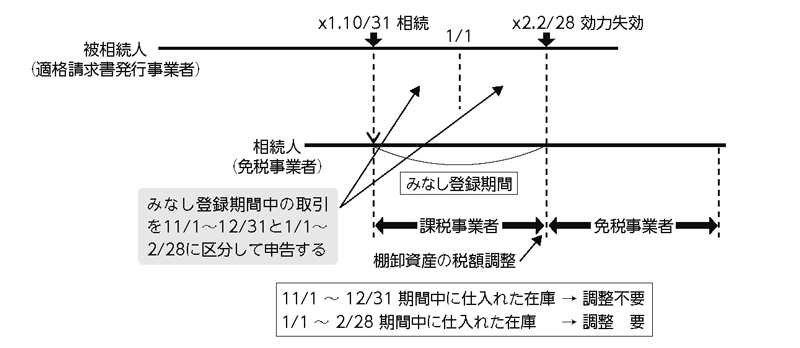
※みなし登録期間の初日の前日において保有する免税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額を課税仕入れ等の税額に加算することができる(1参照)。
ただ、読替規定の前半で、「みなし登録期間である11月1日~2月28日までの間に購入した棚卸資産を有しているときは……」と前置きしておきながら、後半で「1月1日~2月28日までの期間中の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれない……」と書くのは日本語として文章が繋がらないように思えるのである。
また、消費税法第36条第5項で「事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、同項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日において当該前日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは……」と規定していることを考えれば、消費税法施行令第70条の8第2項は、下記のように下線の箇所を追加するべきではないだろうか?
適格請求書発行事業者の事業を承継した相続人の棚卸資産に係る消費税額の調整(消令70の8②)
事業者が、第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されることとなつた場合において、第57条の3第3項に規定するみなし登録期間の末日において、当該みなし登録期間の末日の属する課税期間中に国内において譲り受けた課税仕入れに係る棚卸資産又は当該みなし登録期間の末日の属する課税期間における保税地域からの引取りに係る課税貨物で棚卸資産に該当するものを有しているときは、当該課税仕入れに係る棚卸資産又は当該課税貨物に係る消費税額は、第30条第1項(同条第2項の規定の適用がある場合には、同項の規定を含む。)の規定の適用については、当該みなし登録期間の末日の属する課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額に含まれないものとする。
この記事に関するご意見・お問合せは ta@lotus21.co.jp にお寄せください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























