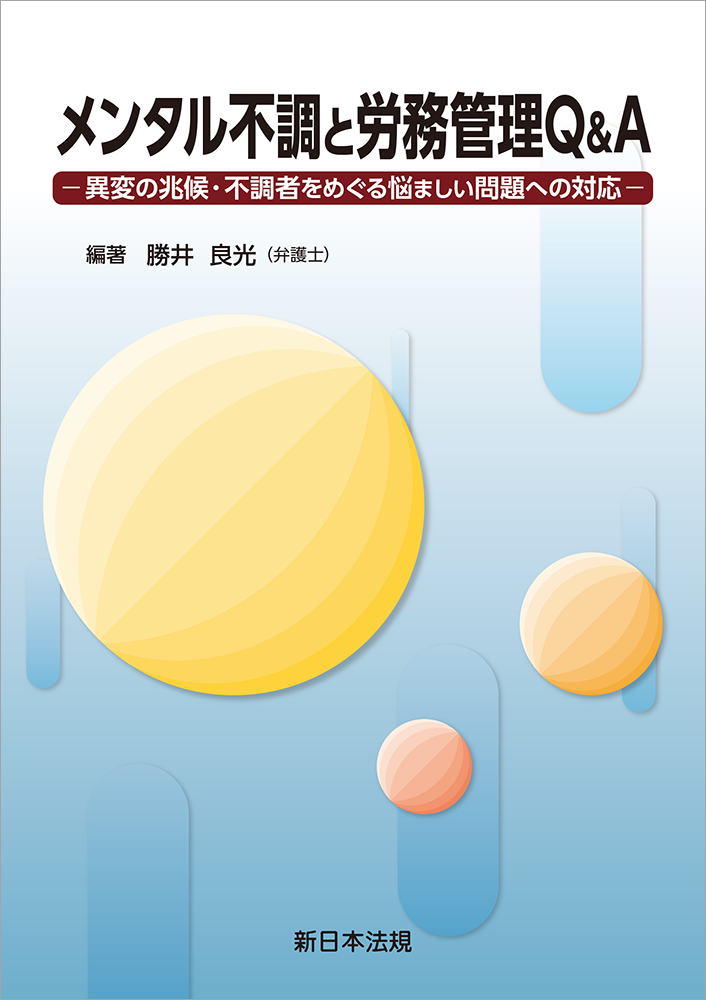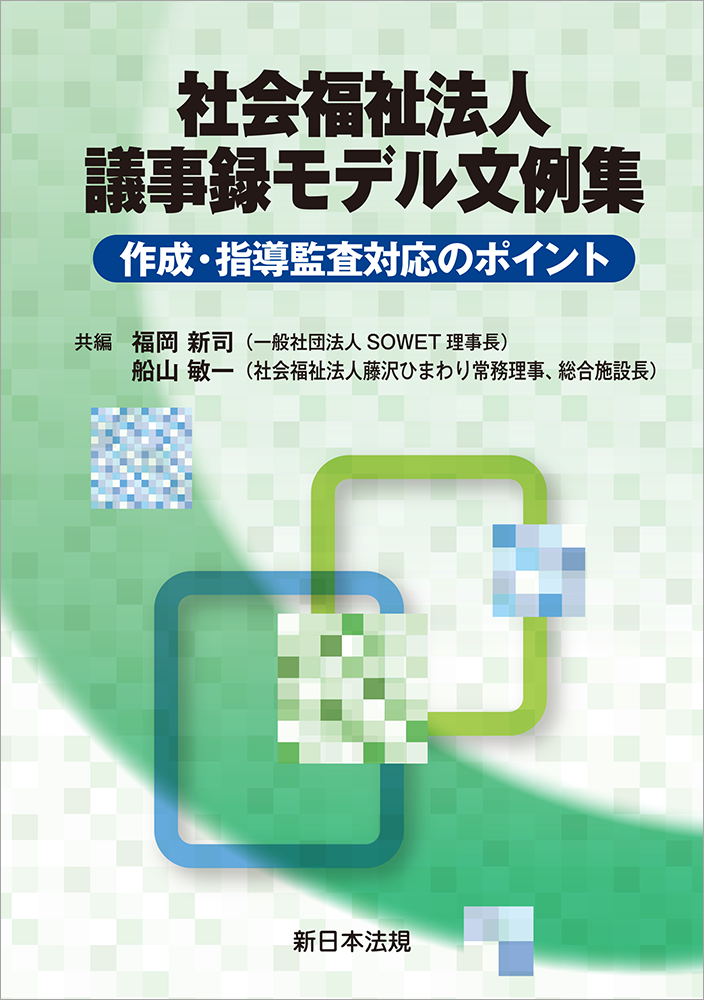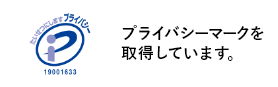解説記事2025年08月11日 未公開判決事例紹介 非上場株式の相続税評価、国の総則6項適用は適法(2025年8月11日号・№1086)
未公開判決事例紹介
非上場株式の相続税評価、国の総則6項適用は適法
東京高裁、原判決を取消し国勝訴
本誌1080号40頁で紹介した相続税更正処分等取消請求控訴事件の判決について、一部仮名処理した上で紹介する(なお、原審の判決は1077号26頁掲載)。
〇非上場株式の相続税評価を巡り争われた控訴審判決。東京高等裁判所(鹿子木康裁判長)は令和7年6月19日、総則6項を適用して純資産価額方式を採用した課税処分は適法との判断を示し、原判決の国の敗訴部分を取り消した(令和7年(行コ)第51号)。
主 文
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
2 上記の部分につき、被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
(以下において略称を用いるときは、別途定めるほか、原判決に同じ。)
1 事案の概要は、3頁1行目末尾に行を改めて次のとおり加えるほかは、原判決「事実及び理由」第2の1に記載のとおりであるから、これを引用する。
「原審が、本件訴えのうち、本件各通知処分の取消しを求める請求及び本件相続税の税額等を本件各更正の請求に係る税額等とする各更正処分をすることの義務付けを求める請求に係る部分を却下し、本件各更正処分のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消請求をいずれも認容したところ、控訴人がその敗訴部分を不服として控訴した。なお、原判決中被控訴人らの訴えを却下した部分に対しては、被控訴人らから控訴がされていないので、その部分は当審の審判の対象となっていない。」
2 「関係法令等の定め」、「前提事実」、「課税の根拠及び計算について」並びに「争点及び争点に関する当事者の主張」は、7頁10行目の「口座を」を「口座に」に改め、14頁21行目の「当たって、」の次に「非」を加え、後記3を付加するほかは、原判決「事実及び理由」第2の2ないし5に記載のとおりであるから、これを引用する。
3 当審における当事者の補足的主張
(1)争点1(本件各更正処分価額が本件株式の客観的交換価値を上回り、本件各更正処分が相続税法22条に違反するか否か)について
(控訴人)
本件株式を評価通達185に定める純資産価額方式により評価した場合の価額は1株当たり3443円となり、本件報告書により評価した場合の価額は1株当たり3488円となる。これらの価額は、本件被相続人がX社から第三者割当を受けた際の払込価額である1株当たり3536.875円及び被控訴人らがX社に対して本件株式を譲渡した際の価額である1株当たり3736円をいずれも下回る価額であることからも、上記価額はいずれも客観的な交換価値としての時価を上回らないというべきである。
(被控訴人ら)
本件株式は非上場株式であり、本件相続開始時のX社の株主は、既存の株主2名に加え相続により株式を取得した者6名、計8名がそれぞれ10ないし20パーセント前後を保有する状況にあったから、本件株式の価額を評価するに当たっては、非流動性ディスカウント及びマイノリティ・ディスカウントが行われるべきであった。
本件報告書は、本件相続前の本件被相続人の保有割合(68.92パーセント)を前提としており、本件相続開始時の本件株式の時価を評価したものではない。
(2)争点2(本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか否か)について
ア 通達評価額によると被控訴人らの相続税の負担が著しく軽減されるか否かについて
(控訴人)
本件新株発行等による相続税の負担軽減は、評価通達における課税価格の算定の仕組みを利用し、本件被相続人が保有する現預金を本件株式に転換させ、X社の資産構成の調整や配当を実施することに起因するものであって、実質的に本件被相続人の財産そのものの増減によるものではないから、本件新株発行等の前後で、被控訴人らの本件相続等における担税力に実質的な変化はなかった。したがって、本件新株発行等が行われなかったとした場合の課税価格の合計額及び納付すべき相続税額の合計額と評価通達に定める方法で評価した場合の結果としてのそれを対比した、著しい租税負担の軽減があるか否かを検討すべきである。
本件において、軽減される納付すべき相続税の合計額は9億7000万円超と極めて多額である上、軽減の割合も約48.1パーセントに及んでいるから、評価通達の定める画一的な評価方法によると被控訴人らの相続税の負担が著しく軽減されると評価すべきである。
なお、原判決は、被控訴人らが、本件相続税につき、相続税法18条による相続税による加算がされることになる行為もしていることを考慮事情としてあげているが、租税負担軽減の有無の判断において考慮すべき事情ではない。また、評価通達が相続財産の区分に応じて評価方式の選択を認めている場合であっても、当該区分に基づいた選択を画一的に許容して納税義務者が選択した評価方式によって評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があると認められるときは、評価通達が定める方法によらない評価を行うことに合理的な理由があるというべきであり、その判断において、納税義務者が選択しなかった評価方式を考慮する必要はない。
(被控訴人ら)
控訴人が主張する本件株式の時価を前提としても、被控訴人らが納付すべき相続税額の軽減割合は5割未満にしかならないから、納税者一般の素朴な公平感覚に照らし、租税負担の著しい軽減があるとはいえない。
軽減される相続税の額については、所有する遺産の価値が高ければ高いほど相続税額が高額になるのは当然のことである。所有する遺産の額が高い被相続人は、生前には高額の所得税、固定資産税その他の納税をしてきたのであるから、相続税のみを取り上げて他の事例と比較することに意味はない。
イ 本件新株発行等が租税負担の軽減を意図して行われたものか否かについて
(控訴人)
被控訴人Aは、本件相続の開始の2か月前の時期に、本件証券会社との間で本件相続税の軽減を目的とした相談を行い、その相続結果に基づき、被控訴人らは、本件被相続人の保有する現預金を、相続税の課税価格が圧縮される本件株式に転化させるとともに、本件配当を行うことにより、本件株式について、評価通達に定める方法により評価した場合の価額が最も低くなるよう企図し、本件相続の後には、所得税の負担を免れつつ本件株式を現預金に復元することを計画した。
具体的には、本件新株発行における払込価額は1株当たり少なくとも3537円であったところ、本件出資を行い株式保有特定会社に該当しないことになったことにより、1株当たりの価額は2650円となり、本件配当を行い比準要素数1の会社に該当しないことになったことにより、1株当たりの価額は1858円となった。
(被控訴人ら)
本件被相続人及び被控訴人Aは、平成22ないし23年にS社の経営支配権争いに巻き込まれた経験から、S社の経営支配権を維持するために、S社創業家の資産管理会社であるX社において資金をプールすることとし、X社において新株発行をし、本件被相続人の出資により調達した資金を用いて流動性の高い資産を運用すること等を構想・計画していた。
本件被相続人は、長年の相場低迷で保有する上場株式を処分できない状態にあったが、アベノミクスによる株価上昇を受け、平成25年に入って手仕舞いの機会を得た。被控訴人Aは、同年夏に上記構想・計画について具体的な準備を行うことが可能になったことから、本件証券会社に赴き上記構想・計画の仕上げの相談を行ったが、その時に初めて大きな租税軽減効果があることを知らされた。その意味で、租税軽減効果の認識と上記構想・計画との間に因果関係はない。
本件被相続人は、同年夏までは格別弱った様子もなく、体力知力とも十分な状態にあったから、周囲も同年の内に本件被相続人が亡くなるとは考えていなかった。資金プールの時期が相続開始の約2か月前という時期になったのは、たまたまというほかない。
したがって、本件新株発行等は、租税回避を主な目的とするものではない。
第3 当裁判所の判断
1 当裁判所は、本件訴えのうち、本件各更正処分のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消請求は、いずれも理由がないと判断する。その理由は、以下のとおりである。
2 争点1(本件各更正処分価額が本件株式の客観的交換価値を上回り、本件各更正処分が相続税法22条に違反するか否か)について
(1)相続税法22条は、相続等により取得した財産の価額を当該財産の取得の時における時価によるとするが、ここにいう時価とは当該財産の客観的な交換価値をいうものと解される。そして、評価通達は、上記の意味における時価の評価方法を定めたものであるが、上級行政機関が下級行政機関の職務権限の行使を指揮するために発した通達にすぎず、これが国民に対し直接の法的効力を有するというべき根拠は見当たらない。そうすると、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されないというべきである(令和4年最判参照)。
そこで検討すると、本件各更正処分価額は、①純資産価額方式による評価額(甲1の1ないし7。1株当たり3443円)及び②●●●●●●●監査法人による本件報告書(甲7)における評価額(1株当たり3488円)のうち、より評価額が低い上記①の評価額を採用したものである。上記①及び②の各評価額の算定方法に不合理な点は認められないところ、上記①及び②の各評価額が近似していることは、各評価額の合理性を裏付けるものというべきである。
また、X社が平成25年8月9日に本件新株発行をした際の本件被相続人の払込価額は1株当たり3976円(本件更正登記によって変更された発行済株式総数を前提に本件新株発行により発行された株式数を101万7856株としても、1株当たり3537円となる。)であり(引用に係る原判決「事実及び理由」(補正後のもの。以下「原判決」という。)第2の3(2)ア)、被控訴人Aを除く被控訴人らが平成29年にX社に対して本件株式の全部又は一部を譲渡した際の譲渡額は1株当たり3736円であって(同(3)エ)、これらの事例からみた本件株式の実際の取引価額が上記①及び②の各評価額を上回っていることは、上記①及び②の各評価額の合理性を裏付けるものといえる。
そうであれば、より評価額が低い上記①の評価額を採用した本件各更正処分価額は、客観的な交換価値としての時価を上回るものではないと認められる。
(2)被控訴人らは、上記②の本件報告書における評価額が、非流動性ディスカウントやマイノリティ・ディスカウントをしていない点で、不合理である旨主張する。
しかし①X社の株主は、本件相続の前後を通じて被控訴人ら及びその親族であるから(原判決別表1)、X社において資産の売却等により資産を換金することが可能であること、②X社の主要資産は、現金、預金、投資有価証券等の流動性の高い金融資産から構成されているのであるから(乙18の1の2)、本件株式を換金する際に追加的なコストがかかることは想定されないこと(甲7)などに照らすと、本件株式の価額を評価するに当たり、非流動性ディスカウントをすべきものとはいえない。
また、上記のとおり、X社の株主は、本件相続の前後を通じて被控訴人ら及びその親族であって、被控訴人Aを除く被控訴人らが平成29年にX社に対して本件株式を譲渡した際の譲渡額はいずれも1株当たり3736円であって(上記(1))、当該被控訴人らの間に差は認められず、かつ、本件新株発行をした際の払込価額1株当たり3976円又は3537円と概ね一致していることによれば、被控訴人ら及びその親族は、本件相続の前後を通じてX社の支配権を有していたものと認められ、本件株式の価額の評価に当たり、マイノリティ・ディスカウントをすべきものとはいえない。これに対し、被控訴人らは、株主らが親族であるからといってその利害が一致しているとはいえないと主張して、内容証明通知書(甲88)を指摘するが、その内容は、上記判断を左右するものではない。
なお、X社が依頼したY社による平成25年8月7日付け株式価値評価報告書(修正後のもの。甲44)においても、非流動性ディスカウントやマイノリティ・ディスカウントはされていない。
したがって、被控訴人らの主張は採用できない。
(3)以上によれば、本件各更正処分価額を相続税の課税価格に算入する本件各更正処分は、相続税法22条に違反するものではない。
3 争点2(本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか否か)について
(1)租税法上の一般原則としての平等原則は、租税法の適用に関し、同様の状況にあるものは同様に取り扱われることを要求するものと解される。そして、評価通達は相続財産の価額の評価の一般的な方法を定めたものであり、課税庁がこれに従って画一的に評価を行っていることは公知の事実であるから、課税庁が、特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、上記の平等原則に違反するものとして違法というべきである。もっとも、上記に述べたところに照らせば、相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である(令和4年最判)。
(2)控訴人は、本件新株発行等により、被控訴人らの相続税の負担は著しく軽減されることになり、また、被控訴人らは、本件新株発行等が被控訴人らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待していたから、本件において、課税庁が、被控訴人らの相続財産の価額について評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとしたとしても、上記の平等原則に違反しない旨を主張する。
(3)そこで検討すると、原判決第2の3(1)ないし(3)の事実関係の下において、本件新株発行等を前提として評価通達の定める方法(被控訴人らが本件各更正の請求において選択した併用方式)により評価すると、課税価格の合計額は、21億2513万4000円、納付すべき相続税額の合計額は、相続税法18条による加算額と合わせて10億5641万2200円となる。
他方、本件新株発行等をしなかった場合(本件相続と異なり、本件被相続人が、相続開始時において、本件株式を保有しておらず、本件出資の額と同額の現金又は預貯金を有しており、かつ、被控訴人らが上記額の現金又は預貯金を均等に相続又は遺贈により取得したと仮定した場合)には、課税価格の合計額は、38億3398万8000円、納付すべき相続税額の合計額は、相続税法18条による加算額と合わせて20億3513万7100円となる。
そうであれば、本件新株発行等がされたことにより、評価通達の定める方法により評価すると、課税価格の合計額は、17億0885万4000円軽減(軽減割合は約44.6パーセント)されることとなり、納付すべき相続税額の合計額は、9億7872万4900円軽減(軽減割合は約48.1パーセント)されることとなる(以上につき、別紙「本件新株発行等の有無による相続税額の比較」参照)。上記認定の軽減される相続税の額、割合等を総合的に考慮して判断すると、被控訴人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきである。
これに対し、被控訴人らは、被控訴人らが納付すべき相続税額の軽減割合は5割未満にしかならず、所有する遺産の価値が高ければ高いほど相続税額が高額になるのは当然のことであるから、被控訴人らの相続税の負担が著しく軽減されることになるとはいえないと主張する。
しかし、被控訴人らが納付すべき相続税額の軽減割合が5割に満たないとしても、軽減される相続税の額を総合的に考慮して判断すると、被控訴人らの相続税の負担は著しく軽減されることになるというべきであり、被控訴人らの主張は採用できない。
(4)証拠(乙8)によれば、被控訴人Aは、本件相続開始の約3か月前である平成25年7月12日、本件証券会社を訪れ、もうすぐ90歳になる本件被相続人が株式売却により約40億円の預金を有しているとして、本件被相続人に係る相続税の節税対策の相談をし、同月19日には、被控訴人Aの自宅を訪れた本件証券会社の担当者に対し、①節税したい、②子世代よりは孫や被控訴人Aの妻に相続又は贈与したいとの基本的な希望を表明し、担当者がX社を活用した節税対策を説明したのに対して強い関心を示し、同月29日には、本件証券会社を再訪し、担当者から、同社が作成した資料に基づき、X社に対して20億円又は40億円の増資を行った場合には、相続税額が概算で約16億円又は10億円となる旨の説明を受け、その後も、X社が「株式保有特定会社」(評価通達189(2))及び「比準要素数1の会社」(評価通達189(1))に該当しないための方策を含め、本件新株発行等を用いた相続税減税スキーム及び相続における相続人による本件株式の現金化について、担当者と電話や電子メールを通じて連日のように協議を重ね、同年8月9日に同スキームを実行した事実が認められる。本件新株発行等に至る上記認定の経過によれば、被控訴人Aが、本件新株発行等が近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において被控訴人らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件新株発行等を行ったことは明らかというべきである。
そして、証拠(乙8、17)及び弁論の全趣旨によれば、被控訴人Aを除く被控訴人らは、本件被相続人に係る相続税対策を被控訴人Aに任せていたものと認められるから、本件新株発行等は、被控訴人Aを除く被控訴人らの少なくとも黙示的な承諾の下で行われたものというべきであり、被控訴人らは、租税負担の軽減をも意図して本件新株発行等を行ったといえる。
これに対し、被控訴人らは、本件新株発行等は、S社の経営支配権を維持するために、S社創業家の資産管理会社であるX社において資金をプールすること等を構想・計画して行われたもので、租税回避を主な目的とするものではないと主張する。
しかし、被控訴人Aと本件証券会社の担当者との間の相談内容(乙8)を占めているのは、本件被相続人に係る相続税の節税対策がほとんどであって、その中には、S社の経営支配権を維持するためにX社において資金をプールするなどという計画の存在は見受けられない一方、相続における相続人による本件株式の現金化の方策が含まれているから、被控訴人らの主張は採用できない。仮に、被控訴人Aが内心においてそのような計画を有していたとしても、そのことは、被控訴人らが租税負担の軽減をも意図して本件新株発行等を行ったとの判断を左右するものではない。
(5)以上によれば、本件においては、被控訴人らの相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことは、本件新株発行等のような行為をせず、又はすることのできない他の納税者と被控訴人らとの間に看過し難い不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるということができる。
したがって、本件において、被控訴人らの相続税の課税価格に算入される財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることには、合理的理由があると認められるから、それが租税法の一般原則としての平等原則に違反するということはできない。
4 本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の適法性について
本件相続開始時の本件株式の時価を純資産価額方式によって評価した価額(1株当たり3443円)とすることは相当というべきところ、これを基礎として計算すると、本件相続税の課税価格及び納付すべき税額は、原判決別表3のとおりとなり、本件各更正処分における被控訴人らの納付すべき税額と同額となるから、本件各更正処分は、適法である。
被控訴人Aを除く被控訴人らは、本件相続税の課税価格及び納付すべき相続税額を過少に申告していたものであり、そのことについて国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの。以下同じ。)65条4項に規定する正当な理由は認められない。したがって、被控訴人Aを除く被控訴人らに対しては、同条1項の規定により、過少申告加算税が課されるべきところ、本件各更正処分における納付すべき税額を基礎として、計算される過少申告加算税の額は、本件各賦課決定処分における過少申告加算税の額と同額であるから、本件各賦課決定処分は、適法である。
第4 結論
そうすると、本件訴えのうち、本件各更正処分のうち本件各更正の請求に係る税額等を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消請求は理由がないからいずれも棄却すべきところ、これを全部認容した原判決は失当であり、本件控訴は理由があるから、原判決中控訴人の敗訴部分を取り消した上、これをいずれも棄却することとして、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第4民事部
裁判長裁判官 鹿子木 康
裁判官 坂田 大吾
裁判官 向井 宣人
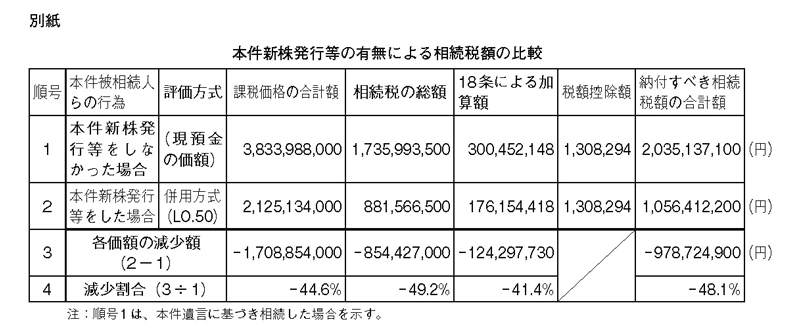
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -