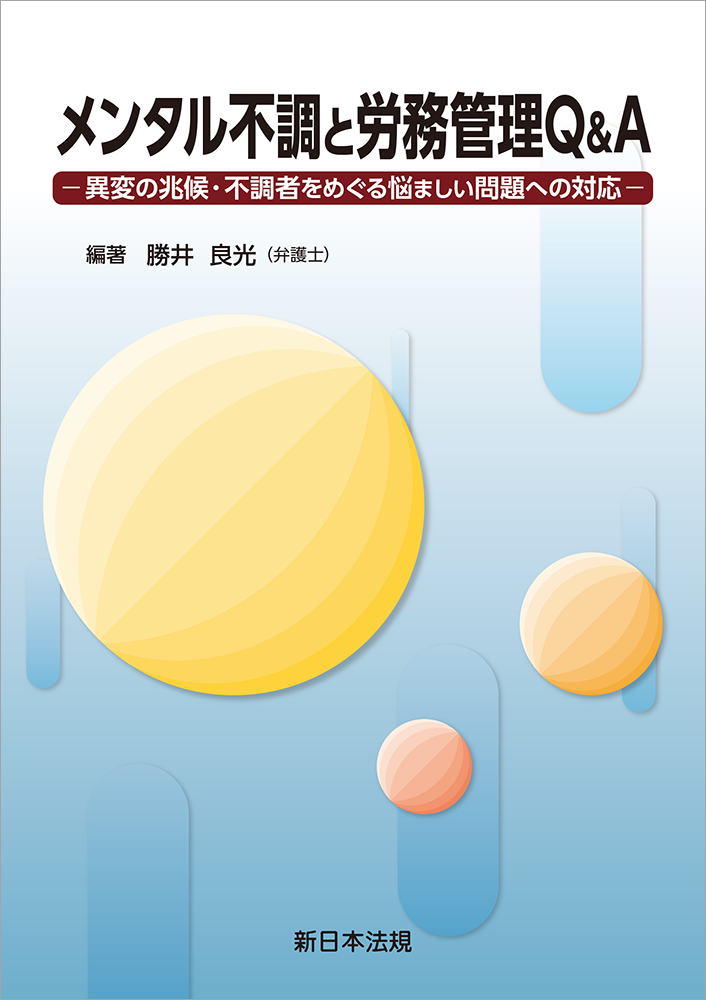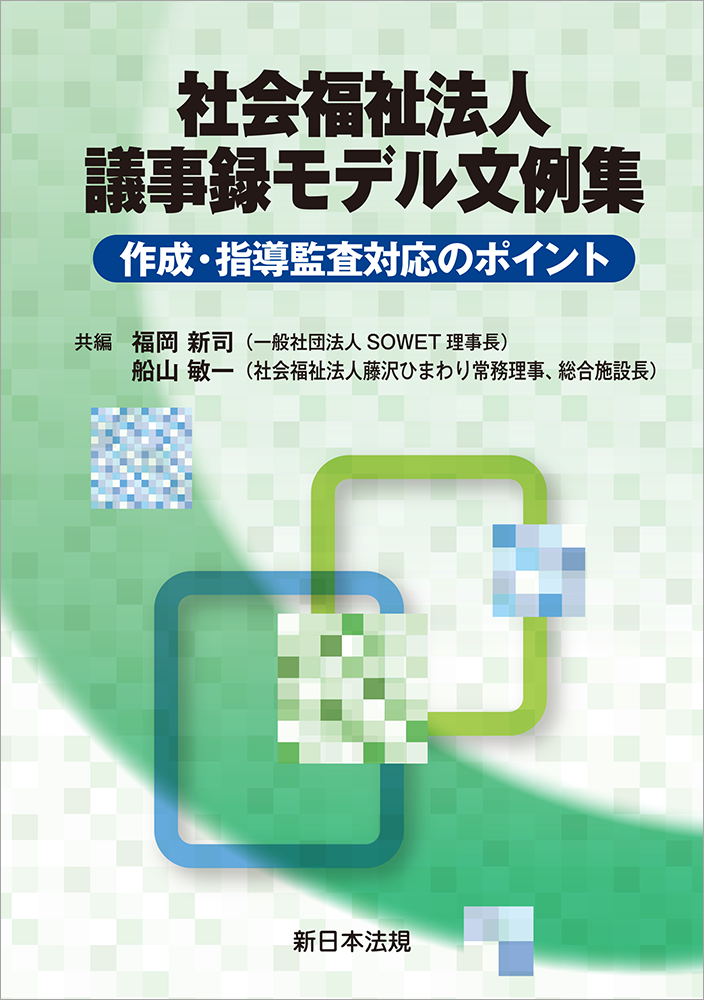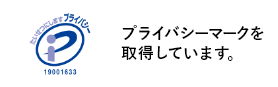解説記事2025年08月25日 最新判決研究 税理士の税務相談の範囲と損害賠償義務(2025年8月25日号・№1087)
最新判決研究
税理士の税務相談の範囲と損害賠償義務
東京地裁令和7年1月30日判決(令和5年(ワ)第154号)
筑波大学名誉教授・弁護士・税理士 品川芳宣
一、事実
(1)X(原告)は、ラーメンチェーン店を全国に展開するT社の創業者あり、同社の代表取締役である甲の妻である。また、Xは、その子らと共に出資してシンガポールに設立した資産管理会社E社の代表者であり、かつ、同社株式の約59%を保有していた。そして、令和元年6月30日時点で、T社の発行済株式総数(2375万7800株)のうち、E社が24.62%に相当する株式(585万株)を、Xは7.74%に相当する株式(184万株)をそれぞれ保有していた。
(2)X及びE社(以下「Xら」という。)は、平成31年初め頃、日星租税条約による税の負担軽減措置を受けるため、Xの保有するT株式の一部をE社に移転すること(以下「本件株式移転」という。)とし、E社は、同年1月28日、大手税理士法人であるY(被告)との間で、本件株式移転に関する業務委託基本契約及び個別業務委託契約(以下「本件契約」という。)を締結した。なお、Xは、本件契約の当事者ではなかったものの、本件契約に基づく業務の提供を受ける者として、本件契約の定めに拘束されるものとされた。
本件株式移転の目的は、E社がT社から受領する配当に対する課税について、日星租税条約10条2項(a)の適用を受けることで税率の軽減を受ける点にあり、そのためには、本件株式移転の結果として、E社がT社の議決権のある株式のうち、少なくとも25%を保有する必要があった(以下「25%要件」という。)。また、本件株式移転によってXに生じる株式譲渡益に対して所得税等の課税を受けないようにするため、本件株式移転における移転株式数がT社の発行済株式総数の5%を下回る必要があった(所法161①三、所令281①四ロ、同⑥二参照。以下「5%要件」といい、25%要件と併せて「本件各要件」という。)。
(3)Yの所属税理士Sは、令和元年7月12日、本件株式移転に関する第3回目のミーティング(以下「7月12日ミーティング」という。)において、X及びE社の担当従業員Hに対し、移転株式数のシミュレーションを記載した資料(以下「本件シミュレーション資料」という。)を交付して説明した。本件シミュレーション資料には、T社の新株予約権(以下「ストックオプション」という。)が全数行使された後に、発行済株式数が2443万8000株になることを前提として、XからE社に移転する株式数を100万株、110万株、120万株、122万株とした場合における発行済株式総数に対する移転株式数の割合及び株式移転後におけるE社が保有するT社の株式数が記載され、移転株式数120万株について青色でマーキングされていた。なお、上記シミュレーションは、いずれの場合も本件各要件を充足する結果となることを示していた。
(4)Xは、令和元年8月16日、E社に対し、自己が保有するT社の株式のうち、120万株を現物出資した。これに対し、所轄税務署長は、令和4年11月21日付で、本件株式移転における移転株式数は発行済株式総数の5.04%にあたるとして、所得税等を1億2495万円余とする決定処分と無申告加算税2496万円余とする賦課決定処分をした。また、Xは、上記所得税等に係る延滞税として880万円を納付した。
かくして、Xは、Yに対し、重大な過失により不正確・不適切な説明を受けたため損害を受けたとして、令和5年1月19日、損害金1億5872万円余とする損害賠償を請求する本訴を提起した。
二、争点及び当事者の主張
1 争 点
本件の争点は、次のとおりである。
(1)移転株式数を提案・助言すべき義務の有無及び同義務に対する違反の有無(争点1)
(2)課税リスクを説明すべき義務の有無及び同義務に対する違反の有無(争点2)
(3)Yにおける悪意又は重過失の有無(争点3)
2 Xの主張
(1)本件契約は、タックス・プランニングといわれるコンサルティング業務であり、その目的は、Yの税務専門家としての知見を得ることにより日星租税条約上の恩典を受けるとともに、本件株式移転に伴う所得税等の負担をできる限り軽減・回避する点にあった。Yは、上記目的を達成するため、本件各要件を満たすような移転株式数を提案・助言すべき義務(以下「本件提案・助言義務」という。)を負っていた。
Sは、本件提案・助言義務を負っていたことを前提に、単に関係法令等の条文に即して本件各要件を抽象的に説明しただけでなく、本件各要件を満たすために移転株式数を120万株とすることをXに提案・助言した。もっとも、この提案・助言は、T社のストックオプションが全数行使されることを前提とするものであったところ、この前提自体が不正確で不適切なものであったから、Yは本件提案・助言義務に違反した(争点1)。
(2)Yが日本及びシンガポールの税務等に精通した税理士法人であること等からすれば、Yは、5%要件を充足しない場合には、Xが多額の課税処分を受けることを認識していたか、少なくとも、容易に認識することができた。仮に本件提案・助言義務を負っていなかったとしても、Yは、移転株式数を120万株と決定しようとしていたXらに対し、ストックオプションの行使状況によっては課税を受けるリスクがあることを説明すべき義務(以下「本件説明義務」といい、本件提案・助言義務と併せて、「本件各義務」という。)を負っていた。そしてSは、本件説明義務に違反した(争点2)。
(3)Yには、本件各義務に違反したことについて、重大な過失があるから、本件契約上の責任制限の規定は適用されない(争点3)。
3 Yの主張
(1)YがXの主張する本件提案・助言義務を負っていたことは否認ないし争う。本件契約に基づくYの業務内容は、E社グループの事業承継に資するストラクチャーを策定することを目的として、その手法について提案し、主として日本及びシンガポールにおける税務について検討することであって、移転株式数を提案・助言(本件提案・助言義務)することは含まれていなかった(争点1)。
(2)Yが本件契約において求められていたのは、Xらから提供された情報を前提に、日本及びシンガポールにおける税務に関する検討を行い、説明・助言することである。そして、Yは、ストックオプションの行使状況によってはXが課税処分を受けるリスクがあることを説明すべき義務(本件説明義務)を負っていなかった(争点2)。
三、判決要旨
請求棄却。
1 争点1(本件提案・助言義務の有無及びこれに対する違反の有無)
(1)本件提案・助言義務の有無
ア Xは、本件契約について、コンサルティング業務であることを前提に、本件株式移転に伴う所得税等の負担をできる限り軽減・回避できるよう、Yにおいて本件提案・助言義務を負っていた旨主張するが、当裁判所は、Yが本件提案・助言義務を負っていなかったと判断する。その理由は、以下のとおりである。
(ア)本件契約に係る契約書を見ても、Yの受託業務について、「事業承継に資するストラクチャーを策定することを目的として、その手法について提案し、主として日本およびシンガポールの税務について検討する業務」と記載されているにとどまり、契約書上、Yの受託業務に移転株式数の提案・助言が含まれていたとはいい難い。
(イ)E社は、令和元年6月30日当時、T社の発行済株式総数(2375万7800株)の24.62%に相当する株式を保有していたから、XからE社に対して発行済株式総数の0.38%に相当する数の株式(約9万0280株)を移転すれば、25%要件を満たす状況であったと認められる。他方、移転株式数を120万株として行われた本件株式移転において、移転株式数は発行済株式総数の5.04%であったから、移転株式数を約119万0476株以下にすれば、5%要件を満たす状況であったと認められる。そうすると、本件株式移転において、本件各要件を満たす移転株式数には相当の幅があり、一義的に定まるものではなかったといえる。
以上のように、移転株式数の決定には、税務関係にとどまらない考慮要素が多分に含まれていることに照らすと、Xらは、移転株式数を主導的に決定すべき立場にあったと認められる。実際に、Hは、平成31年2月13日、Sらに対し、Yから株式移転数に関する提案・助言を得ていないにもかかわらず、株式移転数を26万株にすることを一方的に伝達するメールを送信しているのであり、このことは、Yにおいて株式移転数について提案・助言する義務がなかったことを裏付けるものといえる。
(ウ)本件各要件を満たすような移転株式数を決定するには、本件株式移転時におけるT社の発行済株式総数を把握する必要があり、その前提として、本件株式移転時までのストックオプションの行使数の見込みについての情報(例えば、ストックオプションの権利者、権利行使価額とT社株価との大小関係、ストックオプションの行使期間等)を把握することが不可欠であるところ、税理士法人であるYがこのような情報を自ら入手し得たとは認められない。そのため、仮に、Yにおいて本件各要件を満たすような移転株式数を提案・助言すべきことになっていたのであれば、XらからYに対して上記情報のうち、Xらが把握していたものが提供されるべきところ、本件全証拠によっても、このような情報提供が行われたとは認められない。
(エ)以上の事情を総合すれば、Yは、Xらに対し、本件各要件を満たすような移転株式数を提案・助言すべき義務(本件提案・助言義務)を負っていなかったと認めるのが相当である。
イ これに対し、Xは、①本件契約を締結した目的は、Yの税務専門家としての知見を得ることにより日星租税条約上の恩典を受けるとともに、本件株式移転に伴う所得税等の負担を軽減・回避する点にあったから、本件提案・助言義務を負っていたことは明らかである、②本件シミュレーション資料のうち、移転株式数を120万株とするシミュレーションにマーキングをして、移転株式数を120万株とすることをXに提案・助言したのは、Yが本件提案・助言義務を負っていたことを前提とするものである旨主張し、これに沿う証拠を提出するほか、H及びXはこれに沿う証言・供述をする。
しかし、上記①について、本件契約の目的が上記のとおりであったとしても、そのことから直ちにYが本件提案・助言義務を負っていたことが導かれるわけではないし、仮にXが本件提案・助言義務を負うことを前提とした業務を委託し、Yがこれに応じたのであれば、業務内容の重大性から、そのことが契約書等において明記されるはずである。
また、上記②についても、Hが移転株式数を120万株程度に増加させる意向を示したことを踏まえ、Xらの意向に係る部分を強調する趣旨でマーキングをしたにすぎないと見ることができるから、必ずしも本件提案・助言義務があることを前提とするものであったとはいえない。
(2)ストックオプションが全数行使されることを前提とした本件シミュレーション資料の評価
既に説示したとおり、Yは本件提案・助言義務を負っていなかったのであるが、Xは、Sが作成した本件シミュレーション資料について、T社のストックオプションが全数行使されることを前提としたこと自体が不正確で不適切であった旨主張し、これに沿う証拠を提出するので、この点についても検討する。
X及びHは、2月8日のミーティングにおいて、Sから本件各要件の判定基準について説明を受けていた上、ストックオプションが行使された場合にT社の発行済株式総数が増加することも理解していた。
ここで、25%要件の充足性を検討する際には、ストックオプションが最大限行使されること(それに伴いE社による株式保有割合が減少すること)を想定する必要がある一方で、5%要件の充足性を検討する際には、ストックオプションが見込みどおり行使されないことを想定する必要があることは明らかである。そして、Sによる上記説明の内容並びにその当時のX及びHの理解度を踏まえれば、本件各要件につき上記のような想定をする必要があることは、X及びHにおいて容易に理解できたというべきである。
しかるに、X及びHは、2月8日のミーティングの後も、Sに対し、T社株式の保有状況として、ストックオプション行使により全ての潜在株が顕在化することを前提とする数値のみを一貫して提示し続けており、しかも、そこに何らの留保・条件等も付されていなかった。
そうすると、XらとYとの間では、T社のストックオプション行使により全ての潜在株が顕在化することがYによる検討の前提となっていたと見ることができるから、本件シミュレーション資料においてストックオプションが全数行使されることを前提としたこと自体が不正確・不適切であったということはできない。
2 争点2(本件説明義務の有無及びこれに対する違反の有無)
(1)本件説明義務の有無
ア Sは、7月12日ミーティングにおいて、本件シミュレーション資料を用いながら、移転株式数を120万株とした場合のシミュレーションについて説明したところ、この説明は、本件株式移転時までにT社のストックオプションが全て行使され、発行済株式総数が2443万8000株まで増加することを前提とするものであった。ここで、令和元年6月30日時点で普通株式68万0200株分に相当するストックオプションが存在していたことを踏まえれば、ストックオプションの行使状況によっては、移転株式数を120万株としたのでは5%要件を充足せず、ひいては、Xが課税処分を受けるリスクが存在していたといえる。
また、Yは、本件契約に基づき、税務についての検討業務を受託していたところ、税理士法人であるYにとって、上記リスクの存在を認識し、Xらに説明することは、容易であったと認められる。
これらの事情を総合すれば、Yは、Xらに対し、ストックオプションの行使状況によっては5%要件を充足せず、Xが課税処分を受けるリスクがあることについて説明すべき義務(本件説明義務)を負っていたと認めるのが相当である。
イ これに対し、Yは、Xらから課税リスクについて説明・助言するよう明示的な依頼を受けていないこと、Xらが顧問税理士に確認することにより課税リスクを知ることができたことなどからすれば、本件説明義務を負っていなかった旨主張し、これに沿う証拠を提出するほか、Sはこれに沿う証言をする。
しかし、既に説示したとおり、ストックオプションの行使状況によってはXが課税処分を受けるリスクが存在していたから、Yは、受託した税務についての検討業務の一環として、上記リスクを説明すべき義務を負っていたと認めるのが相当である。課税リスクの説明・助言について明示的な依頼を受けていなかったことやXらに顧問税理士がいたことは、上記判断を左右するものではない。上記に反する限度で、上記証拠を採用することはできず、Yの上記主張を採用することはできない。
(2)本件説明義務に対する違反の有無
ア Sは、2月8日のミーティングにおいて、X及びHに対し、本件検討資料を用いて、莫大な税負担を避けるためには、5%要件を充足する必要があり、そのためには、移転株式数が発行済株式総数の5%未満である必要があることを説明した。そして、どの程度の説明を行えば説明義務を履行したと評価できるかは、相手方の理解度等に応じて異なるところ、X及びHがストックオプションの行使に伴って発行済株式総数が増加することを理解していたことに照らせば、Sの上記説明は、ストックオプションの行使状況によっては発行済株式総数が変動して5%要件を充足しない可能性があることの説明を含むものであったということができる。
また、Sは、7月12日ミーティングにおいて、X及びHに対し、本件シミュレーション資料を用いて、移転株式数を120万株とした場合の発行済株式総数に対する移転株式数の割合等を説明したところ、同資料には、記載のシミュレーションがストックオプション全数行使後の発行済株式総数を前提として計算されたものであることが明記されていた。そして、X及びHのその当時の理解度を踏まえれば、X及びHは、Sの上記説明が飽くまでもストックオプションが全て行使された後の発行済株式総数を前提とするものであって、ストックオプションの行使状況によっては5%要件を充足しない可能性があることを容易に理解することができたといえる。
以上によれば、Yは、本件説明義務を履行したということができる。
イ これに対し、Xは、Sが7月12日ミーティングにおいて、ストックオプションが全て行使されることを前提とした説明をしたところ、ストックオプションの行使状況によっては5%要件を充足せず、Xが課税処分を受けるリスクがあることについて、何ら言及・説明しなかったから、本件説明義務に違反した旨主張する。
確かに、120万株を移転した場合に5%要件を充足するとのSの説明は、本件株式移転時までにストックオプションが全数行使されること、それゆえ、ストックオプションの行使状況によっては5%要件を充足しないこともあり得ることを前提とするものであったから、その旨を改めて明示的に説明した方が丁寧で分かりやすいものであったことは明らかである。
しかし、既に説示したとおり、Sの説明内容、X及びHのその当時の理解度に加え、ストックオプションの行使状況によって発行済株式総数が変化し、それに応じて5%要件を充足しない可能性が生じることは容易に理解し得ることに照らすと、Sは、上記のような課税リスクについても説明したと評価することができる。
3 結 論
よって、その余の点について判断するまでもなく、Xの請求は理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用につき、民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
四、解説
はじめに
近年、税理士の業務上の過誤を理由とする損害賠償請求事件が多くなっている。しかも、その多くは、税理士に対しかなり厳しい専門家責任(善管注意義務)を要求する傾向にある(注1)。その中にあって、本件においては、当該税理士の業務上の免責事由を認め、税理士側が勝訴したのであるが、そのこと自体は注目される。
もっとも、本件契約のような事業承継円滑化のための業務委託契約においては、委託者側からすると、関係株式の移転等において租税負担の最少化を図ることを当然のように期待するわけであるから、本判決が判示するように、そのようなことは本件契約において明確にされていないという理由だけで受託税理士側が免責されるということにはやや首肯し難いものがある。そうは言っても、現行の税理士法の規定とその解釈等に照らし、本件のような税務相談ないしコンサルにおいて、租税負担の最少化(節税)がどの程度期待できるかということについても疑問のあるところであるので、なお、検討の余地はある。
そこで、本稿においては、それらの問題にも敷衍しながら、本判決の可否を検討することとする。
1 税理士の損害賠償責任
(1)税理士に対する損害賠償請求の法的根拠は、債務不履行(民法415)と不法行為(民法709)に求められる。すなわち、民法415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と定めている。
そして、同条2項は、「前項の規定により損害の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。」と定めている。「次に掲げるとき」は、次のとおりである。
① 債務の履行が不能であるとき。
② 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
③ 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
(2)次に、税理士と委任者(納税者)の法律関係は、一般に、民法上の委任関係であると解されており、受任者(税理士)の義務としては、①善管注意義務(民法644)、②報告義務(民法645)、③受取物引渡義務等がある。その中で、民法644条は、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」と、いわゆる善管注意義務を定めている。そして、税理士は、依頼者に対し、税法・税務の専門家として、次の三つの義務を負うものと解されている(注2)。
① 忠実義務
忠実義務とは、依頼者との合意内容を忠実に履行すべき義務である。
② 善管注意義務
依頼内容の実現にあたり、依頼者から特別に指示があったか否かを問わず、善良なる専門家として尽くすべき慎重な配慮をする義務である。注意義務の水準は、専門家に対する依頼に応えるのにふさわしい「高度」なものであり、具体的には、関連法令及び実務に通じた標準的な専門家に期待される注意義務の程度が基準になる。
③ 説明・助言義務
依頼者に対して有効な情報を提供し、依頼者が適切な判断をなし得るように配慮すべき義務である。
また、民法645条は、「受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。」と定めている。
2 税理士の使命と業務
(1)本件のような事業承継円滑化のための株式移転に関する業務委託契約(本件契約)においては、委任者(納税者)としては、当該株式移転等において租税負担の最少化を期待することは当然のことではある(注3)。しかも、X側には、顧問税理士がいながら、大手税理士法人に本件契約を締結するわけであるから、なおさらのことである。しかしながら、受任者側の税理士においては、税理士法の規則等もあって、納税者側の要請に積極的に対応するとは限らない。そこに、本件のような問題が生じる背景がある。
まず、税理士の使命については、税理士法が制定された昭和26年には、税理士法1条が、「税理士は、中正な立場において、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務を適正に実現し、納税に関する道義を高めるように努力しなければならない。」と定めていた。そして、昭和55年に改正された現行の税理士法1条では、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と定めている。
このような税理士の使命に関する税理士法1条の改正の趣旨等について、立法担当者は、次のように説明している(注4)。
「今回の改正では、税理士の社会的立場を明確にする見地から、第1条を税理士の使命に関する規定とし、その内容も、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」に改められました。
このように、税理士が「税務に関する専門家」であることを明記し、従来その解釈について議論のあった「中正な立場」を「独立した公正な立場」に改める等の改正を行った新しい使命規定は、税理士の社会的地位ないし果たすべき役割を一層明確にしたものと解されます。
また、「申告納税制度の理念にそって」は参議院の修正により追加されたものですが、この表現は、戦後のわが国税制の基本となっている申告納税制度下における税理士の重要な役割を原点にかえって強調したもので、意義深い修正として評価することができると思います。
なお、税理士は納税者の権利を擁護することを使命とする旨を明記すべきとの主張が従来からありますが、この主張の正しい意味での趣旨は、「納税義務の適正な実現を図ること」、すなわち、「過大でも過小でもなく納税する」ということの意味の中に当然含まれるものと解され、また、参議院における修正部分にはこの主張の趣旨を含むものと解することができようかと思います。」
以上のような税理士法1条の制定並びにその後の改正及び改正の趣旨に照らすと、個々の税務に係る業務委託契約において、委任者(納税者)側の意図を汲んで租税負担の最少化を図ることに消極的にならざるを得ないとも考えられる。また、そのことは、次の「税理士の業務」からも推し量られることになる。
(2)税理士の業務について、まず、税理士法2条1項は、税務代理(同項1号)、税務書類の作成(同2号)及び税務相談(同3号)を定め、本件に関する税務相談について、次のように定めている。
「税務相談(税務官公署に対する申告等、第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(〈略〉)の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。)」
しかし、一般的な意味での「税務相談」については、税務に関する全ての事項(特に、納税者にとって最大の関心事である租税負担の最少化等)についての相談ごとが含まれるものと解されるが、税理士法上の「税務相談」の定義が極めて限定的であることに留意する必要がある。このことは、税理士以外の者がコンサルタントとして各種の「税務相談」に応じることを可能にするが、その場合の「税務相談」と税理士法上の「税務相談」との区分が困難であることを意味することとなり、本件のような紛争の原因の一つともなる。
そのほか、税理士法2条2項は、税理士の付随業務として、次のことを定めている。
「税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事業を業として行うことが制限されている事項については、この限りではない。」
そのほかの税理士の業務につき、税理士法2条の2は、税理士が裁判所に出頭し陳述できることを次のように定めている。
「税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することができる。
2 前項の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正をしたときは、この限りでない。」
このような補佐人制度は、税理士が租税の専門家として法廷でも納税者の主張を代弁できるということで評価できるが、例えば、弁理士が、法廷において、弁護士と帯同せずとも出頭できること(弁理士法5)に比し、なお制限的である。
(3)そのほか、税理士の業務に関しては、その内容が複雑、多様化しており、その中で申告納税方式の下で適法と考えて納税申告を済ませても、その後、税務署長の調査・処分によって当初申告が否定されることもある。そして、納税者に対して損害を与えることもあるが、その損害が税理士の善管注意義務違反ということになると、税理士に対する損害賠償請求が生じることになる。このような損失は、当初申告税額がその後の課税処分等による適正税額よりも過少の場合も、過大の場合も、いずれにおいても生じることになる。そのために、税理士業務においては、上記のような損失を補填するための損害賠償保険制度は必須である。
ところが、日本税理士会連合会(以下「日税連」という。)が関与している損害保険会社の「税理士職業賠償責任保険適用約款」によると、過少申告から生じる追徴課税、各種加算税額、延滞税額等は保険の対象にしないことを明確にしている。すなわち、納税者のために良かれと思って奨めた節税策が課税当局の判断によって否認された場合の損失は、一切保険の対象にはならないのである。このような保険制度の趣旨について、日税連の担当部長は、次のように説明している(注5)。
「まず、修正申告により追加納付すべき税額については、当初の申告において正確な申告を行えば、本来納税者が負担すべきものであり、申告等を行った税理士が負担すべき損害ではない。
加算税、延滞税等の附帯税については、申告納税制度上の重要な役割を果たしており、税制上のペナルティー的性格を有するものであることから、これを損害として認識し保険で担保することは税制上の目的を阻害するものである。保険で担保することを認めると、法令違反や軽率な申告等を助長する恐れもあることから、納税義務の適正な実現を使命とする税理士の品位及び質の低下につながり、国民・納税者からの信頼を損ねることになる。」
しかしながら、このような説明については、そもそも、租税法の解釈・適用については、税理士と課税当局との間に見解の対立があることはしばしば生じることであり、税務調査による更正等の段階で何が「正確」であるかは判断できないはずである。それに加え、納税者の信頼に応え、当該納税者の利益になるように、合法と考えられる節税等を指導している場合に、「過少申告」が生じることが多いので、税理士の業務のあり方にも支障を生じさせることにもなると考えられる(注6)。
3 本件の課税関係
(1)Xらは、顧問税理士が存在していても、大手税理士法人のYと本件契約を締結したのは、Yが国際課税関係に強いであろうことを信頼し、T社・E社間の日星租税条約における租税負担の軽減措置を受け、かつ、Xの国内源泉所得課税を有利にすることにあった。
まず、日星租税条約10条は、両国関係者間の配当課税について、次のように定めている。
「1 一方の締結国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において租税を課することができる。
2 1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該該当の受益者である場合には、次の額を超えないものとする。
(a)当該配当の受益者が、利得の分配に係る事業年度の終了の日に先立つ6箇月の期間を通じ、当該配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25パーセントを所有する法人である場合には、当該配当の額の5パーセント
(b)その他のすべての場合には、当該配当の額の15パーセント
この2の規定は、当該配当を支払う法人のその配当に充てられる利得に対する課税に影響を及ぼすものではない。
3~6 (省略)」
かくして、本件においては、本件契約前において、T社の発行済株式総数2375万7800株のうちE社が24.62%有していたというのであるから、E社の所有割合が25%以上になるように、Xが所有しているT社株式を譲渡するようにする必要があった。
(2)他方、Xは、外国法人(注7)であるE社の代表取締役として所得税法上の非居住者(注8)であると想定されるところ、その課税関係は次のとおりである。まず、所得税法においては、非居住者の所得税の納税義務を同法161条1項に規定する国内源泉所得を有するとき等に限定的に定めている(所法5②二)。
そして、所得税法161条1項は、「この編において「国内源泉所得」とは、次に掲げるものをいう。」と定め、その3号で、「国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの」と定めている。そこで、まず、所得税法施行令281条1項は、株式の譲渡に関し、次のように定めている。
「法第161条第1項第3号(国内源泉所得)に規定する政令で定める所得は、次に掲げる所得とする。
1~3号 (省略)
4号 内国法人の発行する株式(〈略〉)その他内国法人の出資者の持分(〈略〉)の譲渡〈略〉による所得で次に掲げるもの
イ (省略)
ロ 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得
5~8号 (省略)」
次いで、所得税法施行令281条6項は、次のように定めている。
「第1項第4号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの非居住者の当該譲渡の日の属する年(以下この項及び第9項において「譲渡年」という。)における第2号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。
1号 譲渡年以前3年内のいずれかの時において、第1項第4号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資(次号及び次項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の25以上に相当する数又は金額の株式又は出資(当該特殊関係株主等が第4項第3号に掲げる者である場合には、同号の組合財産であるものに限る。次号及び次項において同じ。)を所有していたこと。
2号 譲渡年において、第1項第4号ロの非居住者を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の5以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと。」
かくして、所得税法においては、非居住者が内国法人の株式を譲渡する場合には、特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式数の100分の25以上に相当する株式を有する場合においても、当該非居住者が5%未満に相当する株式数を譲渡している限り、国内源泉所得として課税されることはないことになる。
4 本件における善管注意義務の範囲と本判決の問題点
(1)本件においては、Xらは、前記3で述べた課税関係をXらにとって一層有利に進めるために、従前からの顧問税理士が存在しながら、大手税理士法人であるYとの間で本件契約を締結したものである。そして、本件契約締結後、その所属税理士SとX及びHは、3回にわたってミーティングを行い、3回目の7月12日ミーティングにおいては、ストックオプション行使後のXからE社に対する譲渡株式数が5%未満に収まる株式数が100万株から122万株の段階ごとに示され、120万株の所が青色でマーキングされていたというものである。その1月後に、Xは、E社に対し、T社株式を120万株譲渡したが、ストックオプション行使前であったため、5%要件を充足できなくなり、合計1億5871万円余の課税処分を受けることになった。
かくして、Xは、前述のように、本訴において、本件契約がタックス・プランニングを目的とするコンサルティング業務であって、その目的がYの税務専門家としての知見を得ることにより日星租税条約上の恩典を受けるとともに、本件株式移転に伴う所得税等の負担をできる限り軽減・回避する点にあったが、Yはそのような本件提案・助言義務を怠り、かつ、本件説明義務に違反した旨主張した。これに対し、Yは、本件契約においては、上記のような本件各義務は負っていなかった旨主張した。
(2)本判決は、前述のように、まず、本件提案・助言義務の有無については、本件契約に係る契約書等において、Yの受託業務に移転株式数の提案・助言が含まれていたとは認められない旨判示した。また、Xが、①Yの税務専門家の立場から本件提案・助言義務を負っているのは明らかであるし、②本件シミュレーション資料の中で「120万株」にマーキングがしてあったのはYの本件提案・助言義務を前提にしている旨主張したことに対して、本判決は、次のとおり判示している。
「上記①について、本件契約の目的が上記のとおりであったとしても、そのことから直ちにYが本件提案・助言義務を負っていたことが導かれるわけではないし、仮にXが本件提案・助言義務を負うことを前提とした業務を委託し、Yがこれに応じたのであれば、業務内容の重大性から、そのことが契約書等において明記されるはずである。
また、上記②についても、Hが移転株式数を120万株程度に増加させる意向を示したことを踏まえ、Xらの意向に係る部分を強調する趣旨でマーキングをしたにすぎないと見ることができるから、必ずしも本件提案・助言義務があることを前提とするものであったとはいえない。」
次いで、本判決は、本件説明義務の有無について、前述のように、「Yは、Xらに対し、ストックオプションの行使状況によっては5%要件を充足せず、Xが課税処分を受けるリスクがあることについて説明すべき義務(本件説明義務)を負っていたと認めるのが相当である。」と判示したものの、結論としては、「Sの説明内容、X及びHのその当時の理解度に加え、ストックオプションの行使状況によって発行済株式総数が変化し、それに応じて5%要件を充足しない可能性が生じることは容易に理解し得ることに照らすと、Sは、上記のような課税リスクについても説明したと評価することができる。」と判示している。
(3)冒頭に述べたように、近年、納税者から税理士に対する損害賠償請求事件が多発しており、その多くが税理士に対する厳しい専門家責任(善管注意義務)を求めてきた。この点、本判決は、本件契約の履行において専門家責任を果たしているということで、納税者の請求を棄却しているので、注目されるところが大きい。
しかしながら、前記2で述べたように、現行の税理士制度が納税者の租税負担の最少化等に消極的で、かつ、「税務相談」の範囲が限定されているとはいえ、XらとY・Sとの信頼関係のあり方とそれを踏まえての本判決の考え方には、いささか疑問がある。けだし、Xらにとっては、顧問税理士が存在しながら、わざわざ大手税理士法人Yとの間で本件契約を締結するからには、Yに対する高度な税務サービスの提供を期待してのことであろうし、Yにおいても、その期待に応える義務があったはずである。そして、XらとY(S)との間に、3回にわたってミーティングが行われたところである。それに加え、本件で問題になっている「25%要件」にしても「5%要件」をクリアすることも、前記3で述べたように、それほど難しくはなかったはずである。
それにもかかわらず、第3回目のミーティング終了後約1月後に、Xは、T社株式120万株をE社に現物出資(譲渡)し、「5%要件」を誤ることになった。このような誤りは、単にXらの判断ミスにとどまらず、Y側にも税務専門家として何らかのアドバイスミスがあったものとも考えられる。
しかしながら、本判決は、Xが本件提案・助言義務については本件契約書に明記されていないとし、本件説明義務の存在を認めたもののSは当該義務を果たしている旨判示して、Xの請求を棄却している。このような判断については、税理士の専門家責任のあり方を示す一つの考え方であろうが、他の税理士損害賠償請求事件において、税理士に対して厳しい専門家責任を追及してきた多くの判決に比べ、いささか違和感がある。
(注1)東京地裁平成4年7月31日判決(判例時報1463号88頁)、神戸地裁平成5年11月24日判決(同1509号114頁)、東京高裁平成7年6月19日判決(同1540号48頁)、東京地裁平成7年11月27日判決(平成5年(ワ)第2494号)、大阪地裁平成14年7月26日判決(平成12年(ワ)第13647号)、大阪高裁平成15年6月6日判決(平成14年(ネ)第2565号)、前橋地裁平成14年6月12日判決(平成10年(ワ)第483号)、東京高裁平成15年2月27日判決(平成14年(ネ)第3787号)、千葉地裁令和3年12月24日判決(平成30年(ワ)第768号)等参照。
(注2)内田久美子他編「判例から学ぶ 税理士損害賠償責任」(大蔵財務協会 平成28年)2頁等参照。
(注3)納税者側の租税負担の最少化の要請とそれが課税庁から否認される場合の法律問題については、品川芳宣「節税と税務否認の分岐点」(ぎょうせい 令和6年)参照。
(注4)国税庁編「昭和55年改正税法のすべて」(大蔵財務協会)258頁。なお、国会審議における政府委員答弁については、前出(注3)68頁参照。
(注5)日税連総務部長「会務報告 税理士職業賠償責任保険の制度改訂について」税理士界令和5年4月15日号8頁。
(注6)前出(注3)102頁等参照。
(注7)法人税法においては、国内(この法律の施行地をいう。)に本店又は主たる事務所を有する法人を内国法人といい、内国法人以外の法人を外国法人という(法法2、一、三、四)。
(注8)所得税法においては、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人を居住者といい、居住者以外の個人を非居住者という(所法2①三、五)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -