解説記事2025年09月15日 巻頭特集 いわゆる主要目的テスト(PPT)の適用可能性について(2025年9月15日号・№1090) −国税当局がPPTを用いた課税を断念したとの報道事例を契機として−
巻頭特集
対談
いわゆる主要目的テスト(PPT)の適用可能性について
−国税当局がPPTを用いた課税を断念したとの報道事例を契機として−
北海道大学大学院法学研究科教授 元国税審判官 佐藤修二
弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士 木村浩之
国内税法上の包括否認規定というと法人税法132条、132条の2等や財産評価基本通達総則6項が思い浮かぶところだが、租税条約の適用を包括的に否認するためのルールが「主要目的テスト(Principal Purpose Test:PPT)」だ。PPTは、租税条約の恩恵を受けることが取引等の主要な目的であり当該恩恵が租税条約の趣旨に反すると判断される場合に適用されることになるが、国税当局がこのPPTを用いて課税を試みたものの、最終的に断念したとの事例が全国紙で報道され、実務家の関心を集めている。
租税条約の濫用防止を目的とするPPTは、法人税法132条等や総則6項同様に抽象的で、適用の射程が広いため、実務上の予測可能性に乏しいとの指摘もある。そこで本誌では、租税条約の専門家であり、オランダ・ライデン大学で租税条約を専門的に学んだ経験や今回の報道事案で問題となったシンガポールの会計事務所での実務経験を持つ弁護士法人淀屋橋・山上合同の木村浩之弁護士と、元国税審判官で、弁護士時代にはCFC税制を巡る著名な税務訴訟の代理人を務めた経験も有するなど国際課税の専門家であり、今回の報道記事でもコメントを提供した北海道大学大学院法学研究科の佐藤修二教授の対談を企画し、報道事例の背景やPPTの適用可能性、さらにはOECDモデル条約のコメンタリーの限界、LOB(特典制限条項)との比較など、多角的な視点から議論していただいた。
(文中、敬称略)
日本では法人税を納めず、租税条約により源泉所得税も5%に
佐藤:今回は、弁護士法人淀屋橋・山上合同の木村浩之先生に、租税条約における主要目的テストについて伺いたいと思います。主要目的テストは、Principal Purpose Testの和訳であり、頭文字をとってPPTと通称されます。本年(2025年)9月1日の日本経済新聞13面の法税務欄で、国税当局がPPTを使って課税を試みたけれども断念された、という事案が報道されました。私は、本事案について取材を受け、若干のコメントをいたしました。
ただ、PPTは、最近、日本国内の大型事案でよく使われるようになった一般的否認規定(法人税法132条、132条の2等)や評価通達総則6項と同様に、抽象的で射程の広いルールですので、どのような場合にPPTが適用され得るのかは、明らかではありません。そこで、オランダのライデン大学で租税条約を専門的に学ばれ、その成果も踏まえて『租税条約入門』(中央経済社、2017年)を上梓された上に、今回の報道事案で問題となったシンガポールで会計事務所に勤務された経験もおありの木村先生に、いろいろと伺ってみたいと考えた次第です。早速ですが、報道事例の概要について、簡単にご説明いただけますでしょうか。
木村:ご紹介いただきありがとうございます。あくまでも報道ベースですが、本件で問題となったのは、海外の投資家がシンガポールの特別目的会社(SPC)を通じて日本の特定目的会社(TMK)に出資し、TMKが日本の不動産を保有して収益を上げるというスキームのようです(図1参照)。
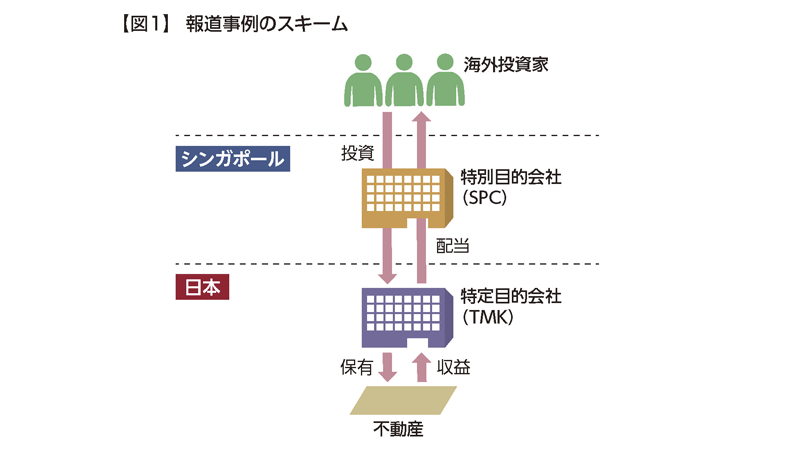
TMKは日本法人ですので、不動産からの収益は日本で法人税の課税対象になりますが、一定の要件を満たせば支払配当について損金算入が認められますので、収益と同額を配当すればTMKには課税所得が残らず、法人税はかからないことになります。これはいわゆる匿名組合(TK)を用いたスキームと同様、利益分配について損金算入が認められていることを活用したものであり、それ自体は一般的な投資スキームといえます。
問題はここからで、日本法人から外国法人であるシンガポール法人に対して支払われる配当は国内源泉所得として所得税の課税対象となり、本来であれば支払う側において20%の源泉徴収が必要となります。ところが、日本とシンガポールとの間の租税条約では、配当に対する課税は5%を限度税率とすることが定められています。そこで、スキーム全体としては、日本では法人税を納めることなく、源泉所得税も5%に抑えられる結果、日本の課税当局の立場からすると多額の税収が失われたということになります。
シンガポールとの租税条約には「二重減免」を防止する規定なし
佐藤:ありがとうございます。国内法の適用によって税負担が軽減された上で、さらに租税条約の適用によって二重に税負担が軽減されているようにも見える事例ですね。このような「二重減免」が生じることを防止する仕組みは租税条約に組み込まれていないものでしょうか。
木村:そもそも租税条約の意義ですが、これは国際投資を促進するために二重課税を排除することを主な目的として二国間で締結されるものであり、特に配当に対する課税の軽減は重要な意義を有しています。すなわち、投資先の国で収益を得た場合には、その収益に対してその国(源泉地国)で課税がなされた上で、残余の利益を配当という形で本国に還流させるわけですが、その際に追加で源泉徴収課税がなされると二重に課税がなされて税負担が大きくなってしまいます。そこで、租税条約では、配当に対する源泉徴収課税は大幅に減免されることが多いというわけです。
ただ、配当に対する源泉徴収課税の減免は、その配当の原資となった収益に対して源泉地国で課税がなされていることが前提ですので、本件のスキームのように支払配当について損金算入が認められて収益が課税対象となっていない場合には、減免を認める必要がないともいえます。通常の法人の場合は支払配当について損金算入は認められませんので、問題が生じることはないのですが、TMKのように支払配当について損金算入が認められる特別の法人の場合には問題が顕在化します。
この問題はもちろん日本の当局も認識しており、比較的新しく締結ないし改正された租税条約では、損金算入が認められる支払配当について租税条約の適用を制限するための特別規定が入れられています。ところが、シンガポールとの租税条約は比較的古いものであり、そのような特別規定を欠いたものになっています。これを利用したのが本件のスキームであるといえます。
PPTの力点は「租税条約の規定の趣旨目的」に反するかどうかにあり
佐藤:よくわかりました。シンガポールとの租税条約は個別の否認規定を欠いているということですね。
もっとも、その上で、日本もシンガポールもいわゆる多国間BEPS防止措置条約(MLI)を締結しており、一般的否認規定であるPPTが導入されていますので、この事案にPPTが適用できるのかが問題です。日経記事でも今村隆先生がコメントされていますが、PPTの適用につき、実務上参考となるのは、OECDモデル租税条約のコメンタリーくらいかと思います。日経で私もコメントしたのですが、コメンタリーでは、配当請求権が発生した後に請求権を他国の事業体に譲渡するような事例が適用事例として挙げられていて、それと本件は、雑駁に言えば似ていないこともありません。
しかし、法律家としては、配当を請求する債権が発生した後にそれをシンガポール法人に譲渡するようなケースと、今回の報道事例のように、配当を受ける法人を初めからシンガポールに設立しているケースとでは、法的な整理が違うように思って、その趣旨のコメントをした次第です。そのあたり、議論してみたいと思います。前提知識として、まずは、木村先生から、PPT及びこれに関するコメンタリーの概要をご説明いただけますでしょうか。
木村:PPTは租税条約の濫用であると認められる場合にその適用を否認するための規定ですが、その要件が包括的に定められていることが特徴的です。具体的には、取引等の主要な目的の一つが租税条約の恩恵を享受することであり、その恩恵を享受させることが租税条約の規定の趣旨目的に反する場合には、その適用を否認するとされています。ここで主要な目的という文言が用いられていることから、主要目的テストと呼ばれています。ただ、租税条約の適用によって課税の減免という恩恵を受けようとすること自体は合理的な経済活動として正当なものですから、それを目的とするからといって直ちに租税条約の濫用であると認められるべきものではありません。そこで、主要目的テストの力点は「租税条約の規定の趣旨目的」に反するかどうかにあると考えられます。
そのような観点からコメンタリーを参照しますと、コメンタリーでは事例Aから事例Mまで計13の事例が紹介されており、PPTの適用を肯定する事例と否定する事例が挙げられています。そのうちのいくつかの事例(事例F、事例Hなど)は主要な目的が租税条約の恩恵を享受することとは認められないものであり、その場合にPPTが適用されないことは明らかです。そして、租税条約の恩恵を享受することが主要な目的の一つであると認められる場合であっても、取引等に経済的な実体が伴っている事例(事例C、事例Eなど)では、なお租税条約の恩恵を享受させることがその趣旨目的に合致すると評価され、やはりPPTの適用が否定されています。これに対して、経済的な実体を伴わない事例(事例A、事例Bなど)では、租税条約の恩恵を享受させることは租税条約の趣旨目的に反すると評価され、PPTの適用が肯定されています。
PPTの適用判断とOECDコメンタリーの限界
佐藤:ありがとうございました。その上で、今回の報道事例にPPTが適用し得るかどうかについて、まずはコメンタリーを参考にして考えると、いかがでしょうか。
木村:今村教授も指摘されているとおり、コメンタリーは参考になりにくいのですが、敢えて本件との関連でいいますと、事例Mが最も参考になるかと思います。この事例では、C国の不動産投資ファンド(パートナーシップ)がR国に持株会社を設立し、その持株会社を通じて特定地域で不動産を保有する現地子会社を設立し、不動産を保有するというスキームが取り上げられています(次頁図2参照)。
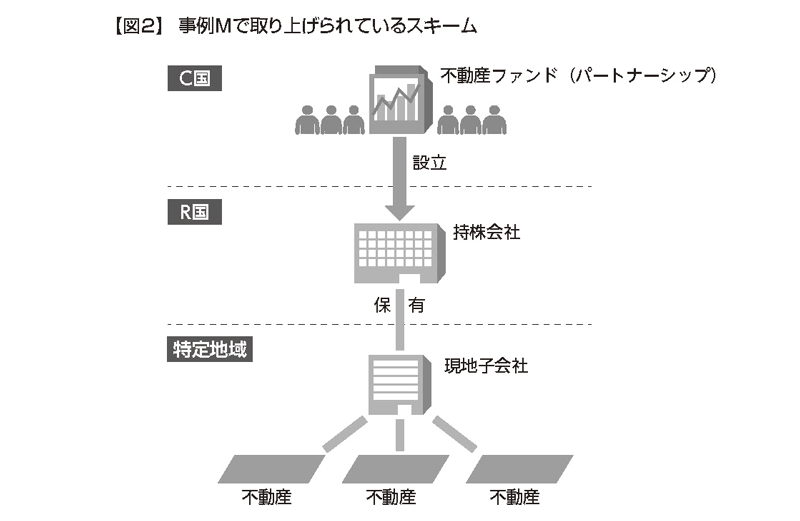
R国に持株会社を設立した理由として、R国が有する租税条約ネットワークを活用することが含まれているものの、それ以外の事業目的として、投資に関するリスクをファンドから隔離することや現地子会社の管理運営を容易にすることなどが挙げられています。このように、R国に持株会社を設立したのは租税条約の恩恵を享受することを一つの目的としているものの、それ以外にも複数の事業上の目的が認められるという事例です。
なお、この事例では、さらにR国の租税条約が投資家自らの居住地国の租税条約より有利とはいえないという事情まで付されていますので、結論としてPPTの適用が否定されることは明らかな事実関係といえます。コメンタリーが参考になりにくいというのはこのあたりに理由があり、およそ限界的な事例について回答したものではなく、ある意味で結論が明らかな事例について回答するにとどまるものであるからといえます。ただ、この付加的な事情がなかったとしても、持株会社に経済的な実体が認められる場合には租税条約の趣旨目的に反するとはいえず、PPTの適用は否定されると考えるのが筋であり、本件のスキームはこの事例に近いと考えれば、PPTの適用は否定されるという結論になるのではないかと思われます。
持株会社の設立が人為的でなければPPTの適用は困難
佐藤:ありがとうございます。冒頭述べましたとおり、木村先生は、シンガポールでの実務経験もお持ちです。シンガポールには、欧米企業や日本企業のアジア地域統括会社が置かれることも多く、私が日経でコメントしたように、シンガポールと日本との間では、さまざまな取引があると思います。その中で、敢えて今回の報道事例を取り上げてPPTを適用することについて、コメンタリーはひとまず置き、ご自身の実務感覚としてはいかがでしょうか。
木村:シンガポールは国際的な投資のハブとして法制度などの環境が整っており、投資を管理運営する人材も豊富です。そのようなことから、シンガポール法人を通じて各国に投資するというのは経済的な実体を伴ったものであることが多いといえます。
先ほど述べましたとおり、租税条約は国際投資を促進するためのものであり、経済的な実体を伴った誠実な投資活動に租税条約が適用されることはその趣旨目的に合致しています。PPTはそのような誠実とはいえない、経済的な実体を欠いた人為的なスキームに恩恵を与えることを否定するものと考えています。そこで、本件のようなスキームについては、シンガポールに持株会社を設立することが人為的なものであると認められればPPTが適用される余地はありますが、現地で投資の管理運営が実質的になされるなど、経済的な実体があると認められる場合には、その適用は難しいのではないかと考えます。
LOBとPPTは相互補完の関係
佐藤:示唆に富むお話をありがとうございました。
本件とは別の事例になりますが、木村先生と以前にご一緒した書籍『対話でわかる国際租税判例』(中央経済社、2022年)で、アイルランド法人を介在させた上でスワップ契約をするなどの手法が用いられ、租税条約の濫用が問題となった日愛租税条約事件について議論したことがあります。この事例では対象となった租税条約にPPTが入っていませんでしたが、仮にPPTが入っていたとすれば、そのような手法を用いることに事業上の合理的な目的があると認められない場合にはPPTが適用される余地はあったかもしれません。
ただ、冒頭述べましたとおり、PPTは、日本国内法で言えば、一般的否認規定や総則6項のような、納税者にとっては予測可能性を欠く規定の一種であると考えられ、あまりその適用が広く認められるべきではないように思います。PPTよりも、むしろ、特典制限条項(Limitation on Benefits, “LOB”)を活用した方が良いのではないかという意見もあり得るところですが、このあたりについて、お考えをお聞かせいただければ幸いです。
木村:LOBとPPTはいずれも一長一短であり、日本の租税条約ポリシーは、LOBとPPTを相互補完的に組み合わせるものであると理解しております。すなわち、PPTは適用要件の認定が難しいため、より客観的に判断可能なLOBを採用することには合理的な理由があるといえます。一方で、LOBは形式的な基準ですので、必ずしもすべての租税条約の濫用を捕捉できるとは限らず、実質的な基準であるPPTを組み合わせて補完するというのはポリシーとして理解できます。しかしながら、これらの否認規定が広く適用されるとすれば、租税条約の積極的な活用が阻害され、国際的な投資交流を促進するという租税条約の本来の趣旨が損なわれることになりかねないと危惧しております。まず、LOBについては、形式的な基準であるがゆえに、先ほどとは逆に、租税条約の適用を認めても問題ない事例において適用を否定してしまうおそれがあります。この点については、LOBの形式的な要件をクリアできない場合でも個別に租税条約の適用を認めるという例外規定があり、その柔軟な適用が望まれるところです。また、PPTについては、租税条約の恩恵を享受することが取引等の目的に含まれているとしても、直ちにその適用がなされるのではなく、その取引等が経済的な実体を欠いた人為的なものかどうかを慎重に判断した上で、抑制的に適用されるべきと考えます。
今後の制度設計への期待
佐藤:どうもありがとうございました。
最後に、今回、個人的に特に印象に残った点を述べますと、PPTに関するコメンタリーの記載は参考とならないという点で、日経の今村先生のコメントも木村先生のお話も一致していたことです。実務において、現状は、コメンタリーくらいしか頼れるものが無いようですが、先生方のご指摘どおり、「まあその結論になるだろう」という点に異論が出にくい事例を列挙してあるだけだとすると、悩んだ事例でどうするか考えるときの参考にならない、というのは良く分かります。日経の報道では、国税庁が指針作成を検討するという話もあり、今後の動向に注目していきたいと思います。
木村先生には、さまざまな観点から有益なお話を伺い、ありがとうございました。
木村:何らかの指針があれば納税者の予測可能性の向上に資することになりますので、国税庁が指針を作成するということは積極的に評価したいと思います。ただ、繰り返しになりますが、租税条約の積極的な活用を阻害しないためには、PPTが適用されない限界的な事例を提示する方向で、言わば納税者にセーフハーバーを与えるような指針を提供していただくことを国税庁には期待したいと思います。今回はありがとうございました。
佐藤修二 (さとう しゅうじ)
1997年 東京大学法学部卒業。2000年 弁護士登録。2005年 ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.)。2011年~14年 東京国税不服審判所(国税審判官)。2019年~22年 東京大学大学院法学政治学研究科客員教授。2022年~現在 北海道大学大学院法学研究科教授。著書に、『租税と法の接点』(大蔵財務協会、2020)、 『夏休みの自由研究のテーマにしたい「税」の話』(共著、中央経済社、2020)、『事例解説 租税弁護士が教える事業承継の法務と税務』(監修、日本加除出版、2020)、『対話でわかる国際租税判例』(共著、中央経済社、2022)、『対話でわかる租税「法律家」入門』(編著、中央経済社、2024)など。
木村浩之 (きむら ひろゆき)
弁護士法人淀屋橋・山上合同 パートナー弁護士。2005年東京大学法学部卒業、2005年~2009年国税庁(国家公務員一種)、2010年弁護士登録、2016年ライデン大学国際租税センター修了(国際租税法上級LL.M.)、2020年一橋大学法学研究科非常勤講師(担当科目:国際租税法)。主な著書に「対話でわかる国際租税判例」(編著・中央経済社・2022年)、「租税条約入門」(中央経済社・2017年)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























