解説記事2025年09月22日 法令解説 公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る政令・内閣府令改正等の解説(2025年9月22日号・№1091)
法令解説
公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る政令・内閣府令改正等の解説
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 新谷亜紀子
金融庁企画市場局企業開示課 課長補佐 金子慧史
前金融庁企画市場局企業開示課 専門官 上久保知優
金融庁企画市場局企業開示課 専門官 福田輝人
1 はじめに
金融審議会「公開買付制度・大量保有報告制度等ワーキング・グループ」報告(以下「WG報告」という)を踏まえた公開買付制度・大量保有報告制度の改正を含む「金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律」が、2024年5月22日に公布された。その後、法改正及びWG報告を踏まえ、公開買付制度・大量保有報告制度の見直しに係る関係政府令等の改正等(以下「本改正」という)が2025年7月4日に公布・公表された。
本稿では、本改正の主な内容について解説する。以下では、金融商品取引法を「法」又は「改正法」、金融商品取引法施行令を「令」又は「改正令」、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令を「改正他社株府令」、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令を「改正大量保有府令」といい、条文番号は、特に断りのない限り、改正後の規定を指す。
なお、本稿において意見にわたる部分は、いずれも筆者らの個人的見解である。
2 公開買付制度
(1)公開買付制度の対象となる取引範囲の見直し
① 適用除外買付け等の見直し
一定の類型の株券等の買付け等は、公開買付規制の適用除外とされている(適用除外買付け等)。本改正では、新たに2つの類型を適用除外買付け等に追加する等の改正を行った。
ア 金融商品取引業者による顧客からの買付け等
まず、第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者等が行う株券等の買付け等であって、「株券等の売付け等……の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為」のために行うものを適用除外買付け等に追加した(改正令第7条第1項第1号)。
「株券等の売付け等……の取次ぎに準ずる行為として内閣府令で定める行為」は改正他社株府令第2条の2の3各号に規定されており、同条各号に掲げる行為のために行う株券等の買付け等、すなわち、市場価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で顧客から行う株券等の買付け等(買付け等後の株券等所有割合が30%を超えるものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものは、適用除外買付け等に該当し、公開買付けによる必要はない。
・単元未満株式の買付け等であって、その後遅滞なく売付け等を行うために行うもの(改正他社株府令第2条の2の3第1号参照)
・株券等(単元未満株式を除く。)の買付け等であって、その後直ちに売付け等を行うために行うもの(同条第2号参照)
イ 公開買付けと同時に公開買付価格より低い価格で行う買付け等
また、公開買付けが行われる場合における次の要件の全てを満たす株券等の買付け等について、適用除外買付け等に追加するとともに、別途買付けの禁止の例外にも加えた(改正令第7条第1項第13号、第12条第6号)。これにより、かかる適用除外買付け等に該当する場合には、公開買付価格での売却が可能となる一般株主よりも低い価格で売却する旨の合意をした特定の株主からは、公開買付けによらずに株券等の買付け等を行うことが可能となる。
(a)公開買付けによる買付け等を行う者と同一の者が行うものであること
(b)買付け等の価格が公開買付価格を下回ること
(c)決済が公開買付けに係る決済と同時に行われること
(d)買付け等に係る契約締結までに、相手方に対し、公開買付けの内容を記載・記録した書面又は電磁的記録を提供したこと
(e)公開買付けに買付予定数の上限を付していないこと
(f)公開買付届出書において(d)の契約があること及びその内容を明らかにしていること
買付け等の相手方の人数について制限は設けられていないため、公開買付けが行われる場合において上記(a)~(f)の要件を満たすときは、複数の株主から公開買付価格よりも低い価格で公開買付けによらずに買付け等を行うことも可能と考えられる。もっとも、上記(d)及び(f)の要件に照らせば、各相手方との契約締結に先立ち、他の相手方との間で締結する契約の内容を記載した書面を交付し、又は記録した電磁的記録を提供していることが必要と考えられる(脚注1)。
また、上記の趣旨に鑑みれば、改正令第7条第1項第13号の買付け等として適用除外買付け等に該当するためには、当該一部の株主から買付け等を行う株券等と同一の種類の株券等が公開買付けの対象となっていることが必要と考えられる(脚注2)。
ウ その他
適用除外買付け等については、上記のほか、次の見直し等も行った。
・議決権の50%超を所有する法人等の発行する株券等の買付け等(改正前の令第6条の2第1項第4号)を適用除外買付け等から削除する。
・適用除外買付け等のうち、買付け等を行う者とその関係法人等が合わせて対象者の議決権の30%超を所有している場合における当該関係法人等から行う対象者の株券等の買付け等の一類型として、共同して議決権等を行使することを合意している親族等からの買付け等を加える(改正他社株府令第2条の4第1項第10号)。
② 僅少な買付け等
市場内取引を公開買付規制の適用対象とするに際して、制度の目的に照らして過剰な規制とならないよう、改正法では、僅少な買付け等に関する適用除外を設け、これを30%ルールの適用対象から除外している(改正法第27条の2第1項第1号)。
本改正では、その具体的な基準を、買付け等により増加する株券等所有割合が0.5%未満である場合(当該株券等の買付け等を行う者が当該株券等の買付け等を行う日前6月間において公開買付け及び適用除外買付け等以外の株券等の買付け等を行った場合を除く。)としている(改正令第7条第3項)。
また、買付け等の後の株券等所有割合が3分の2以上となる場合には、僅少な買付け等に関する適用除外の対象とはならないこととした(改正令第7条第4項)。
(2)形式的特別関係者の範囲の見直し
改正法において形式的特別関係者の基礎となる関係から「親族関係」が削除されたことを踏まえ、本改正では、買付け等を行う者の親族を形式的特別関係者の範囲から削除している(改正令第9条第1項・第3項)。また、株券等の買付け等を行う者が特別資本関係を有する法人等の役員や株券等の買付け等を行う者に対して特別資本関係を有する法人等の役員についても形式的特別関係者から削除することとした(改正令第9条第1項・第2項第2号・第3号)。
株券等の買付け等を行う者と特別資本関係にある者については、本改正後も引き続き形式的特別関係者に該当することとなる。もっとも、金融グループにおける持株会社はその傘下の運用会社等の形式的特別関係者に該当するところ、今般の法改正により30%ルールの適用範囲が市場内取引(立会内)にまで拡大することから、当該持株会社が上場会社等の議決権の30%超を有している状況下では、当該運用会社等が顧客等のための投資運用として当該上場会社等の株券等を買い付ける場合であっても、その都度公開買付けが必要になり、顧客等のための投資活動が著しく阻害されることが懸念される。そこで、投資運用業者が投資運用業として株券等の買付け等を行う場合又は信託会社等が信託財産として所有するために株券等の買付け等を行う場合であって、次の要件を全て満たすときには、投資運用業者又は信託会社等に対して特別資本関係を有する者(上記の例における持株会社等)を株券等所有割合の合算対象から除外することとした(改正法第27条の2第1項第1号、改正他社株府令第3条第2項第2号)。
① 利益相反のおそれのある行為の特定、利益相反回避措置の実施及び利益相反回避措置に関する方針の策定・公表
② 株券等の買付け等を行う者の議決権行使方針の策定・公表
③ 上記①及び②の内容及び所定の事項を記載した書類を関東財務局長に提出すること
なお、上記①~③の要件を満たしているかは買付け等の都度判定されることとなる。そのため、③の書類の提出も原則として買付け等の都度行う必要があると考えられるが、特定のファンドが一定の投資方針のもとに日常的に買付け等を行う場合等、同一の目的で同一の発行者の発行する株券等について買付け等を行う場合には、当該買付け等を行う可能性のある期間等を記載した上で、一連の買付け等について包括的に記載した③の書類の提出をすることも可能と考えられる(脚注3)。
(3)公開買付手続の柔軟化
① 剰余金の配当に伴う公開買付価格の引下げ
現行制度上、公開買付価格の引下げは、応募株主等にとって不利となり得る買付条件の変更であるため、公開買付期間中に対象者が配当を実施した場合であっても許容されていない。もっとも、公開買付期間中に配当が実施された場合には、配当基準日時点の株主は配当金を受領することができるため、公開買付価格を配当金相当額引き下げたとしても応募株主が得る実質的対価の合計は異ならず、応募株主等にとって不利とはならない。
そこで、本改正では、公開買付期間中に対象者が剰余金の配当を行った場合には、1株あたりに割り当てられる配当財産の価額に相当する金額までの範囲で公開買付価格を引き下げられることとした(法第27条の6第1項第1号、改正令第13条第1項第3号、改正他社株府令第19条第1項第3号)。
また、公開買付けの決済日より前の日を基準日とする株式分割、株式・新株予約権の無償割当て、配当を行うことが決定された場合にも、同様に公開買付価格の引下げを許容することとした(法第27条の6第1項第1号、改正令第13条第1項第4号)。
② 撤回事由の拡充
本改正では、公開買付けの撤回事由を見直し、以下の事項を撤回事由として新たに追加した(令第14条第1項第5号、改正他社株府令第26条第4項)。
(a)公開買付けの開始後にいわゆる有事導入型買収防衛策の導入が公表されたこと(同項第2号)
(b)公開買付けにより株券等の買付け等を行うことが他の法令に違反することとなること(同項第3号)
(c)公開買付けにより株券等の買付け等の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと(同項第4号)
(d)法第192条第1項に基づく緊急差止命令の申立てがなされたこと(同項第5号)
(e)上記(a)~(d)に準ずる事項で、公開買付者が公開買付開始公告等において指定した事情が生じたこと(同項第6号)
(f)当局の承認を受けたこと(同項第7号)
③ 当局の承認による規制の免除等
WG報告では、当局において引き続き体制の強化に努めていくことを前提に、公開買付けに係る各規制について、個別事案ごとに当局の承認を得ること等によって、規制が免除される制度を設けるべきとの提言が示された(WG報告9頁)。
かかる提言を踏まえ、前記②のとおり、当局の承認を受けて公開買付けを撤回できることとしたほか、当局の承認を受けた場合には、(a)全部勧誘義務の免除(改正他社株府令第5条第3項第3号)、(b)法定の期間の上限(60営業日)を超える公開買付期間の延長(改正令第13条第2項第2号ハ)、(c)公開買付期間の義務的延長の免除(改正他社株府令第22条第1項第3号)を認めることとしている。
また、上記(c)(脚注4)に関して、当局の承認を受けた場合の他、株券等の取得についての許可等を得る必要がある場合であって、当該許可等を得られたことを理由として訂正届出書を提出する場合についても、公開買付期間の延長を不要としている(改正他社株府令第22条第1項第2号)。もっとも、当該許可等に投資判断に重要な影響を及ぼす条件(脚注5)が付されている場合には、原則どおり公開買付期間を延長する必要があると考えられる。
(4)公開買付届出書等の記載事項の見直し等
本改正では、金融庁が2024年10月1日に策定した「公開買付けの開示に関する留意事項について(公開買付開示ガイドライン)」の内容も踏まえ、現行実務上、公開買付届出書の「買付け等の目的」欄に一般的に記載されている事項(例えば、公開買付けを実施するに至った経緯、対象者の意見、公正性担保措置、公開買付けに関する重要な合意等)について、これらの記載が法令上も必要であることを明確にする観点から、記載上の注意の見直しを行った(改正他社株府令第二号様式)。
また、WG報告では、公開買付けの強圧性の問題(脚注6)を巡る対応として、少なくとも部分買付け(買付予定数の上限を付した公開買付け)を実施する際には公開買付者(及び当該部分買付けに賛同する対象者)が一般株主の理解を得るよう努めることが望ましいとされ、具体的な方策としては、公開買付届出書における開示の規律を強化し、部分買付け後に生じる少数株主との利益相反構造に対する対応策や一般株主から反対があった場合の対応策についての説明責任を果たさせる措置が挙げられた(WG報告6~7頁参照)。かかる提言を踏まえ、本改正では、部分買付けを行う場合における公開買付届出書の記載事項として、新たに次の事項を追加した。
・公開買付け後の少数株主との利益相反回避措置の内容(当該措置を講じない場合にはその理由)(改正他社株府令第二号様式記載上の注意(10)d)
・一定数以上の議決権を有する株主が部分買付けに反対する場合の対応方針を定めている場合には、株主の意思確認の方法及び当該対応方針の内容(同様式記載上の注意(11)g)
また、WG報告では、公開買付届出書の提出後に大量保有報告制度の違反が発覚したような場面に備え、そのような場合には訂正命令等の是正措置を行うことができるような枠組みを整備すべきとの提言が示された(WG報告15頁)。かかる提言を踏まえ、本改正では、公開買付届出書の記載事項として新たに「大量保有報告書等の提出状況」欄を設けている(改正他社株府令第二号様式記載上の注意(35))(脚注7)。
(5)その他の見直し事項
これらの他、いわゆる間接取得が「株券等の買付け等」に該当することの明確化、公開買付届出書を参照する方式を用いる場合の公開買付説明書の記載事項の簡略化、株券等所有割合の計算において小規模所有者の合算が不要となる場合の見直し等を行った。
3 大量保有報告制度
(1)企業と投資家の対話の促進に向けた規定の整備等(脚注8)
① 共同保有者の規律に関する特例等
現行制度上、株券等の保有者との間で共同して株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している者については例外なく共同保有者に該当するが、改正法では、そのような合意をしている場合であっても、(A)当該保有者と他の保有者がいずれも金融商品取引業者等であり、(B)共同して重要提案行為等を行うことを合意の目的とせず、(C)共同して株主としての議決権その他の権利を行使することの合意のうち、個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに該当する場合には、当該他の保有者は共同保有者に該当しないという特例を設けている(改正法第27条の23第5項)。
本改正では、このうち(A)及び(C)の具体的内容を定めている。
まず、(A)については、現行法上の特例報告制度の適用対象範囲を参考に、証券会社、投資運用業者、銀行、信託会社、保険会社等とした(改正大量保有府令第5条の2の2)。
また、(C)については、以下の要件を定めている(改正令第14条の6の3)。
(a)当該発行者の株主総会又は投資主総会ごとにする合意であって、
(b)合意の対象とする議案を他の議案と明確に区別できるよう特定し、
(c)当該議案に対する賛否を定めて、当該保有者及び他の保有者が当該議案について共同して議決権を行使することを内容とするもの
(a)~(c)の要件については、改訂後の金融庁企画市場局「株券等の大量保有報告に関するQ&A」(以下「大量保有報告Q&A」という)問26で考え方を示している。
② 重要提案行為等の範囲の見直し
金融商品取引業者等が特例報告制度を利用するためには、重要提案行為等を行うことを保有の目的としないことが必要とされている(法第27条の26第1項)。この点に関し、2006年のパブリック・コメント(脚注9)において、重要提案行為等に該当するためには以下の要件を全て満たす必要があるとの解釈が示されていた。
(i)発行者(又はその子会社)に対する「提案」行為であること
(ii)提案内容が令第14条の8の2第1項各号に掲げる事項(以下「列挙事項」という)に該当すること
(iii)提案行為が発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼすことを目的とすること
しかし、重要提案行為等については、不明確又は広範な規制となっており、企業と投資家との実効的なエンゲージメントの促進のためには、更なる明確化又は限定が必要との指摘があった。
かかる指摘を踏まえ、WG報告では、企業支配権等に直接関係する行為を目的とする場合については、広く重要提案行為に該当する規律としつつ、企業支配権等に直接関係しない提案行為を目的とする場合については、当該提案行為の態様について着目し、その採否を発行会社の経営陣に委ねないような態様による提案行為を行うことを目的とする場合に限り、重要提案行為に該当する規律とすることが適当との提言が示された(WG報告12~13頁)。
本改正では、かかる提言も踏まえて、重要提案行為等の範囲を見直している。
まず、要件(ii)に関連して、列挙事項の見直しを行っており、既存の列挙事項のうち、支配人等の選解任(改正前の令第14条の8の2第1項第5号)や支店等の設置・変更(同項第6号)等を削除した。他方で、経営への影響が大きい、特定の者の役員への選任や発行者以外の第三者による買収(脚注10)を新たに列挙事項に加えている(改正令第14条の8の2第1項第4号、同項第12号、改正大量保有府令第16条第4号)。
また、大量保有報告Q&A問36において、WG報告の提言を踏まえて、要件(i)~(iii)の考え方を新たに示している。
まず、要件(i)について、発行者の経営方針等の説明を求める行為や自らの議決権行使方針や具体的な議決権行使の予定等を説明する行為等、株主・発行者間での認識の共有を図る行為であれば、要件(i)を充足しないため、「重要提案行為等」に該当しないと考えられる旨を示している。
次に、要件(ii)に関し、政策保有株式の売却、代表取締役の後継者計画・指名方針、独立社外取締役の増員、事業ポートフォリオの見直しに係る提案が列挙事項に該当するか、考え方を示している。
また、要件(iii)に関して、WG報告の提言も踏まえ、以下の考え方を示している(図表1参照)。
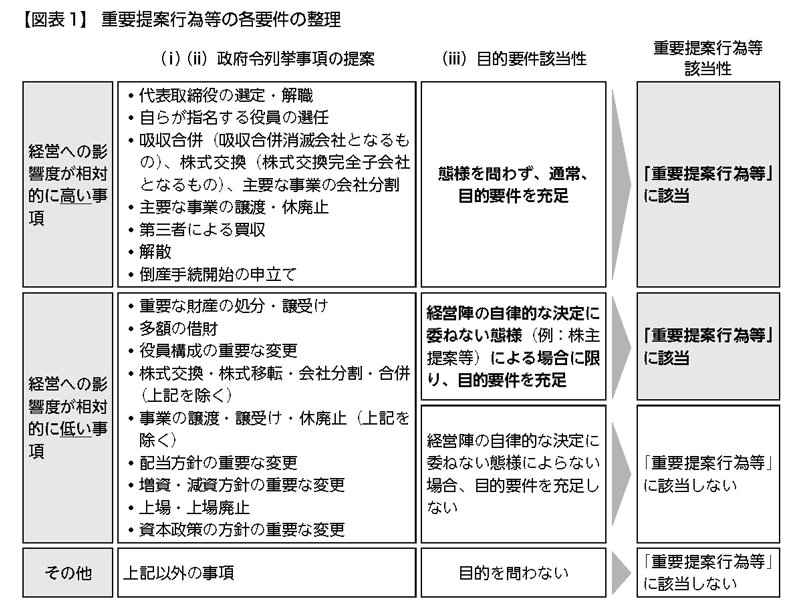
・列挙事項のうち相対的に発行者の事業活動に及ぼす影響の程度が高い事項の提案については、要件(iii)を充足する可能性が高い
・列挙事項のうち相対的に発行者の事業活動に及ぼす影響の程度が低い事項については、これを発行者との対話の場で提案したとしても、当該提案の採否を発行者の経営陣の自律的な決定に委ねない方法・態様(脚注11)により提案を行うものでない限り、要件(iii)に該当する可能性は低くなる
(2)現金決済型エクイティ・デリバティブ取引に関する規定の整備
改正法では、現金決済型のエクイティ・デリバティブ取引のロングポジションの保有者のうち、「当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者」について、大量保有報告制度上の「保有者」に該当することとされた(改正法第27条の23第3項第3号)。
本改正では、潜在的に経営に対する影響力を有しているものと評価することができるとともに、実質的に大量保有報告制度を潜脱する効果を有するものと評価することもできるようなものとして、「政令で定める目的」の具体的な内容を次のとおり定めている(改正令第14条の6第2項)。
① 株券等に係るデリバティブ取引の相手方から当該株券等の発行者が発行する株券等を取得する目的(同項第1号)
② 株券等の発行者に対して当該発行者が発行する株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有することを示して重要提案行為等を行う目的(同項第2号)
③ 株券等に係るデリバティブ取引の相手方が保有する議決権(当該株券等の発行者が発行する株券等に係るものに限る。)の行使に影響を及ぼす目的(同項第3号)
①~③の目的を有することが要件であるため、株券等に係るデリバティブ取引のロングポジションを取得した時点では、経済的な利益を享受する目的のみを有し、①~③の目的をいずれも有していない場合には、当該時点では当該株券等の「保有者」には該当しない。その後に、①~③のいずれかの目的を有するに至った場合には、その時点で当該株券等の「保有者」に該当することとなる。
現金決済型のエクイティ・デリバティブ取引について「保有者」に該当する場合、当該デリバティブ取引に係る保有株券等の数は、改正大量保有府令第3条の3各号に基づき算出されることとなる。
(3)みなし共同保有者の範囲の見直し
大量保有報告制度については、その実効性が確保されていないとの指摘や、特に近時は、共同保有者の認定に係る立証の困難性を奇貨として、複数の者が暗黙裡に協調して株券等を取得していることが疑われる事例も見受けられるとの指摘があった。
以上の点を踏まえ、WG報告では、共同保有者の認定に係る立証の困難性の問題を解決すべく、一定の外形的事実が存在する場合には共同保有者とみなす旨の規定を拡充すべきであるとの提言が示された(WG報告15頁)。
本改正では、かかる提言を踏まえて、共同保有者とみなされる関係(いわゆる「みなし共同保有者」)について、新たに以下の①~⑤の5つの類型を加えている(改正大量保有府令第5条の3)。
① 会社と、その会社の代表者及び株券等の取得・処分・管理に係る業務を執行する役員(これらの役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下「代表者等」という)との関係(同条第2号)
② 代表者等が同一の会社同士の関係(同条第3号)
③ 株券等の取得資金を供与し株券等の取得を要請した者と、当該資金の供与及び取得要請を受けた者との関係(同条第4号)
④ 株券等の取得を要請した者と、当該要請者に譲渡する目的で株券等を取得した者との関係(同条第5号)
⑤ 重要提案行為等を要請した者と当該要請に基づいて重要提案行為等を行った者との関係(同条第6号)
①及び②は、役員関係やその兼任関係に着目し、会社とその代表者等は、その保有する株券等について取得・処分や議決権行使について共同して判断がなされる蓋然性が高いと考えられることから、共同保有者とみなすものである。「これらの役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当するかは、当該趣旨を踏まえて、その者の当該会社における株券等の取得、処分又は管理に係る業務に係る意思決定を事実上行っているか等、当該業務への影響力を踏まえ、個別具体的な事案に即して判断されることになると考えられる(脚注12)。
なお、日常的に取引を行う金融商品取引業者等について、代表者等が常に共同保有者に該当すると、常時、代表者等の保有状況を確認する必要があることになり事務負担が増大し、経済活動を著しく阻害するおそれがあることも踏まえ、重要提案行為等を行う目的を有しない金融商品取引業者等(脚注13)は、①及び②の適用対象から除外している。
③については、投資運用会社等のように金銭等の拠出等を受けてその運用等を行う者等に対して要請する場合を適用対象から除外しているほか(同条第4号イ~ヘ参照)、④についても、第一種金融商品取引業者に対してその業務として株券等を取得することを要請する場合を適用対象から除外している。また、金融機関等から融資を受ける際に、当該融資に係る契約上、資金の使途が株券等の取得に限定されていることがあるが、そのような限定があることのみをもって、直ちに金融機関等が借主に対して「株券等を取得することの要請」をしていると評価されるものではないと考えられる(脚注14)。
⑤については、株主同士で意見交換を行うにとどまり、重要提案行為等を行うか否かについて各株主においてそれぞれ独立に判断しているのであれば、通常、重要提案行為等を行うことの「要請」はされていないものと考えられる(脚注15)。
(4)大量保有報告書の記載事項の見直し等
① 大量保有報告書の記載事項
本改正では、大量保有報告書の「保有目的」欄、「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄の記載内容・記載方法が必ずしも明確化されておらず、提出者によって記載ぶりが区々となっているとの指摘や、実務上大量保有報告書に記載される情報が市場の公正性、透明性の観点から必ずしも十分ではないことから、より情報開示を充実すべきとの指摘を踏まえ、これらの記載欄の記載事項の明確化等を行った。
具体的には「保有目的」欄及び「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」欄に記載すべき事項については図表2のとおり明確化等を行った(改正大量保有府令第一号様式記載上の注意(10)、(14))。
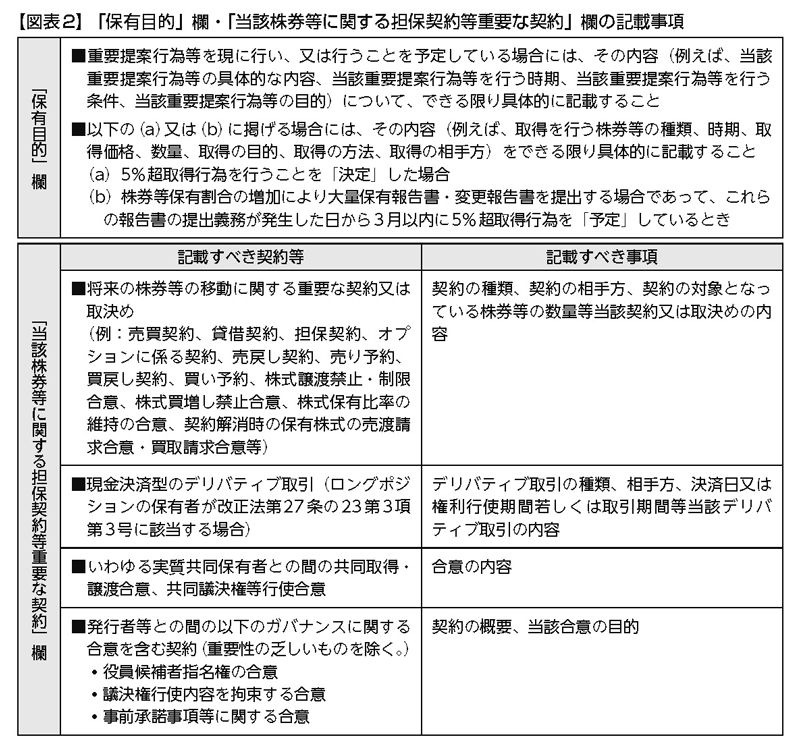
まず、重要提案行為等を現に行い、又は行うことを予定している場合(脚注16)には、その内容(例えば、当該重要提案行為等の具体的な内容、当該重要提案行為等を行う時期、当該重要提案行為等を行う条件、当該重要提案行為等の目的)について、できる限り具体的に記載する必要があることを記載上の注意で明記した(同記載上の注意(10))。重要提案行為等を行うことについて一定の蓋然性・具体性がある場合、当該提案者が重要提案行為等を行うことを「予定」している場合に該当すると考えられる。例えば、法人である提出者においては、当該行為の実施に向けた業務が行われ、当該行為を行うことが具体的に見込まれることとなった場合や、提出者において当該行為を行うことについて実質的に決定権限を有する者が当該行為を行うことを決定した場合には、提出者における形式的な最終の機関決定がなされていなかったとしても、通常、当該行為を行うことを「予定」していると評価されると考えられる。
次に、図表2の(a)又は(b)に掲げる場合には、「保有目的」欄にその内容をできる限り具体的に記載することを求めることとした(同記載上の注意(10)c)。(a)の「決定」は、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断されるべきものと考えられるが、提出者である法人においては、株券等保有割合を5%超増加させる行為(保有株券等の総数が増加しないものを除く。以下「5%超取得行為」という)を行う最終の機関決定があった場合は、「決定」をしている場合に該当すると考えられる(脚注17)。(b)については、株券等保有割合の増加を理由として提出する大量保有報告書・変更報告書の報告義務発生日時点において5%超取得行為の「予定」(脚注18)がある場合に「保有目的」欄にその内容の記載を求めるものであって、既に大量保有報告書を提出している者において5%超取得行為の「予定」が生じたにとどまる場合、その事実のみをもって変更報告書を提出する必要はない。
なお、5%超取得行為が、第一種金融商品取引業者等が「株券等の流通の円滑を図るために顧客から行う株券等の取得であって、当該株券等の取得により取得した株券等を当該株券等の取得の後直ちに譲渡することとするもの」に該当する場合、「保有目的」欄への記載は不要としている。
② 株券等保有割合の計算方法の見直し
株券等保有割合の算出に際して、取得請求権付株式や取得条項付株式の転換後の株式数が勘案されていないとの指摘を踏まえ、本改正では、取得請求権付株式・取得条項付株式について、転換後の議決権数が転換前の議決権数よりも多い場合には、転換後の株式数を株券等保有割合の分子とすることとした(改正大量保有府令第5条第1項第2号)。これに伴い、転換後の株式数と転換前の株式数との差分については、保有潜在株券等として株券等保有割合の分母に加算することとしている(改正法第27条の23第4項、改正大量保有府令第5条の2)。例えば、保有する取得請求権付株式100株(議決権1個)が普通株式200株(議決権2個)に転換できる場合であれば、図表3のようになる。
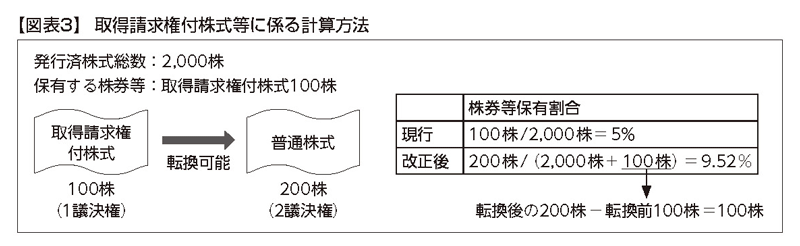
なお、取得請求権付株式・取得条項付株式の中には、転換後の株式数が市場株価等の指標に基づき変動するような設計となっているものも存在する。このような取得請求権付株式・取得条項付株式について、市場株価等の指標の変動のみを理由として保有株券等の総数や株券等保有割合が増減する場合、これらの増減のみを理由として大量保有報告書又は変更報告書を提出する必要はない(改正大量保有府令第3条第2号、第9条第2号)。もっとも、その後に別途株券等の取得・処分を行った場合には、当該取得・処分による増減だけではなく、市場株価等の指標の変動による保有株券等の数の変動も織り込んで大量保有報告書・変更報告書の提出要否を判断する必要がある。
このほか、株券等保有割合の計算上、共同保有者の保有分も合算する必要があるが、現行制度上、保有者及び共同保有者の間に引渡請求権等が存在する場合、分子では重複が控除されているにもかかわらず、分母では重複計上されており、分子と分母で計算上の不均衡が生じていた。そこで、本改正では、分母に加算する保有潜在株券等についても保有者及び共同保有者の間に引渡請求権等が存在する場合に重複控除を行うこととした(同条第6号)。
(5)その他の見直し事項
これらの他、以下の改正を行った。
・提出者の名称・所在地・代表者の変更について、変更の内容が国内においてインターネットの利用その他の方法により周知されている場合には変更報告書の提出を不要とする(改正大量保有府令第9条の2第2項第2号)
・株券等保有割合が10%を超えることとなる株券等の取得を行う目的を有している場合には、特例報告ではなく一般報告による迅速な情報開示を求めることとする(改正大量保有府令第13条第3号)
・みなし共同保有者に該当する関係から「夫婦の関係」を削除する(改正令第14条の7第1項・改正前の令第14条の7第2項)
4 施行期日等
改正法及び本改正は、2026年5月1日に施行される。もっとも、施行日前に開始した公開買付けについては、その決済が施行日後に行われる場合であっても、改正前の規定が適用される(改正法附則第2~4条、改正令附則第2条・第3条等)。他方、施行日後に開始する公開買付けについては、施行日前に公開買付けの実施予定を公表している場合であっても、改正後の規定が適用されることに留意されたい。
本改正により、みなし共同保有者の範囲が拡充されるが、本改正によりみなし共同保有者に該当することとなる者は、施行日にみなし共同保有者になったものとみなされる。そのため、施行日前から改正大量保有府令第5条の3第2~6号に掲げる関係にあった者は、施行日において新たに共同保有者になったものとして取り扱われることになる。その結果として、株券等保有割合が5%を超え、又は1%以上増加する場合には、一般報告であれば施行日を報告義務発生日として大量保有報告書・変更報告書の提出が必要となる。このほかにも、本改正により、株券等保有割合の算定方法等が変更されるところ、現行制度に基づき算出される株券等保有割合と改正後の制度に基づき算出される株券等保有割合の差については、施行時にその差に相当する株券等保有割合の増減が生じたものとみなされる。もっとも、夫婦の関係がみなし共同保有者に該当する関係でなくなることに伴い、共同保有者の減少や株券等保有割合の減少といった変更が生じるが、これらを理由とする変更報告書については提出不要としている(改正令附則第4条)。
脚注
1 金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(公開買付制度関連)」(2025年7月4日)(以下「パブコメ回答(TOB)」という)No.14及びNo.15参照。
2 パブコメ回答(TOB)No.17参照。
3 パブコメ回答(TOB)No.43及びNo.44参照。
4 現行制度上、公開買付届出書に形式上の不備があることにより訂正届出書を提出する場合を除き、訂正届出書の提出日より起算して10営業日を経過した日まで公開買付期間を延長しなければならない。
5 例えば、問題解消措置が講じられることを前提に公正取引委員会から排除措置命令を行わない旨の通知(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則第9条)を受けた場合には、当該問題解消措置の内容等によるものの、通常、投資判断に重要な影響を及ぼす条件が付されているものと考えられる(改訂後の金融庁企画市場局「株券等の公開買付けに関するQ&A」(2026年5月1日適用開始)問45参照)。
6 公開買付けの強圧性の問題については、WG報告6頁を参照されたい。
7 公開買付届出書の提出日において大量保有報告書又は変更報告書の提出義務が発生している場合であって、当該大量保有報告書又は変更報告書について、法定の提出期限、当該提出期限までに提出する予定である旨及び提出予定者を公開買付届出書に記載したときには、当該提出予定者が当該提出期限までに当該大量保有報告書又は変更報告書を提出したことのみをもって公開買付届出書の訂正届出書を提出する必要はないと考えられる(パブコメ回答(TOB)No.78)。
8 本(1)の内容に関しては、金融庁が2025年8月26日に公表した「大量保有報告制度における「重要提案行為等」・「共同保有者」に関する法令・Q&A等の整理~機関投資家と投資先企業の建設的な対話に向けて~」もあわせて参照されたい。
9 金融庁「提出されたコメントの概要とコメントに対する金融庁の考え方」(2006年12月13日)No.90参照。
10 具体的には、発行者が発行する株券等の発行者以外の第三者による取得であって、当該取得の後に当該第三者及び当該第三者とみなし共同保有者の関係にある者が合わせて当該発行者の総株主等の議決権の数の50%を超える数の議決権を有することとなるものが該当する。
11 例えば、株主提案権の行使による場合、発行者の同意を得ることなく提案内容を公表する場合(いわゆるキャンペーン)、提案内容を実行しない場合には株主提案権の行使・キャンペーン・委任状勧誘を行うことを示唆して提案を行う場合が該当し得る。
12 例えば、形式的には会社の代表権を有していない場合や株券等の取得、処分又は管理に係る業務を分掌していない者であっても、実質的にこれらの権限を有し、又は業務を分掌している場合には、これに該当するものと考えられる(金融庁「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(大量保有報告制度等関連)」(2025年7月4日)(以下「パブコメ回答(大量保有報告)」という)No.95~No.99)。
13 具体的には、改正大量保有府令第5条の2の2各号に掲げる者である。
14 パブコメ回答(大量保有報告)No.103及びNo.104参照。
15 パブコメ回答(大量保有報告)No.109参照。
16 ただし、保有者自身が改正大量保有府令第16条第4号に掲げる事項を行うことを提案するものである場合については、重要提案行為等として記載が必要となる場合からは除外しており、後述する「5%超取得行為」として記載が必要となる場合に限り、「保有目的」欄に記載されることとなる。
17 パブコメ回答(大量保有報告)No.136~No.139参照。
18 重要提案行為等の場合と同様、5%超取得行為を行うことについて一定の蓋然性・具体性がある場合には、5%超取得行為を行うことを「予定」している場合に該当すると考えられる(パブコメ回答(大量保有報告)No.147~No.153等参照)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























