解説記事2025年09月29日 SCOPE リヒテンシュタイン財団経由の株式保有にCFC税制適用(2025年9月29日号・№1092)
地裁、原告に財団の自益権・共益権ありと判断
リヒテンシュタイン財団経由の株式保有にCFC税制適用
外国子会社合算税制の適用の可否を巡り争われた事案で、東京地裁民事3部(篠田賢治裁判長)は令和7年9月12日、課税処分を適法とする判決を下した。
原告(個人)は、リヒテンシュタイン公国に設立した財団を通じてバハマ法人の全株式を保有しており、裁判では当該バハマ法人が原告に係る「外国関係会社」に該当するか否かが争われた。リヒテンシュタインの会社法には財団の株式等に関する定めはないが、東京地裁は、事実関係から、原告が財団の資本金の全額を拠出するなどして本件財団を実質的に設立したことにより、本件財団の自益権及び共益権と同視できる権利ないし地位を全部有していたとして、本件財団の発行済株式等の全部を保有していると判断した。
原告、リヒテンシュタイン財団に保有の対象となる株式等はないと主張
本件は、原告(個人)がリヒテンシュタイン公国に設立した財団(本件財団)を通じて全株式を保有するバハマ法人(本件外国法人)が、原告に係る「外国関係会社」に該当するか否かが争われた事案である。
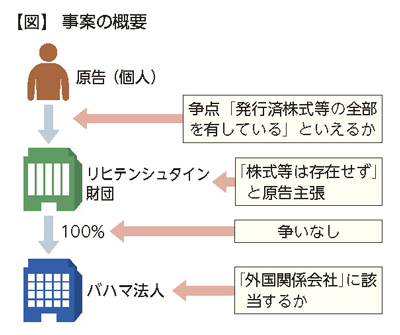
原告は、①本件財団の設立準拠法では、財団に対する財産の拠出者が保有すべき株式等に相当するものに関する規定が何ら存しないから、本件財団は持分の定めのない法人で、その保有の対象となるべき株式等はない、②したがって、原告がその全部を保有することはあり得ず、本件外国法人の発行済株式の全部を間接保有していることもないから、本件外国法人は原告に係る「外国関係会社」には該当しないなどと主張していた。
これに対し東京地裁は、外国子会社合算税制の趣旨・目的からすれば、外国法人に対する支配力の有無の判定は、形式上・名目上のものではなく、外国法人の収益や資産を実質的に支配し得る地位の有無という観点から判定されなければならないとの考えを示した。
また、諸外国の法制度が我が国の法制度と異なり得るものであることは明らかであるから、その判定基準を構成する「株式等」について、我が国における「株式」又は「出資」と完全に同じものを指すと解することはできず、外国法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位を指すものと解するのが相当であって、居住者等がこのような法的地位を取得しているか否かについては、当該外国法人の設立準拠法だけでなく、当該外国法人の定款や会社規則等の具体的事情を総合的に考慮して判定すべきとした。
その上で、外国法人を支配し得る単位化された物的持分としての法的地位は、当該外国法人に対して資金を拠出したことによって得られた、自益権及び共益権又はこれらと同視できる権利ないし地位をいうものと解すべきとした。
地裁、原告が資本金を拠出、財団の実質的な設立者と認定
東京地裁は、上記の判断枠組みに基づき、原告が自益権及び共益権と同視できる権利ないし地位を有するか否かについて検討した。
東京地裁はまず、原告はD社に対し、D社を信託設立者として本件財団を設立するよう指示するとともに本件財団の定款、規則を承認し、本件財団に対する資本金3万スイスフランを払い込んだと認定した。
そして、原告は生存中、本件財団の「第一受益者」として、本件財団の資産及びその収入を享受する権利を独占的に有しており、しかも、原告のこの地位は、本件財団の実質的な設立者として、その設立を指示し、資本金の全額を拠出した原告が承認した草案に基づいて制定された本件財団定款及び本件財団規則によって得られたものであると指摘。その上で、原告は、本件財団の資本金の全額を拠出するなどして本件財団を実質的に設立したことにより、本件財団の自益権と同視できる権利ないし地位を全部保有していたものと認められるとした。
さらに東京地裁は、原告は、本件財団の特別組織の唯一の構成員として、本件財団の資産の管理について、単独で責任を負い、制約を受けることなく裁量で行うことができる地位を有しており、また、本件財団の管理運営を行う財団評議会を指導する地位を有しているほか、財団評議会の構成員の解任につき拒否権を有していると認定。原告は、本件財団の資本金の全額を拠出するなどとして本件財団を実質的に設立したことにより、本件財団の共益権と同視できる権利ないし地位を全部保有していたものと認められるとした。
原告は、①リヒテンシュタインの財団では、出資者で構成される自らの経済的利益のために財団の経営に関与するような機関は存在せず、財団の設立者は、設立のための財産を拠出することが定められているものの、それによって出資に応じた利益配当請求権等の経済的利益を有することや経営に参加する権利を有することが定められているものではない、②本件財団において、受益者が何らかの経済的利益を受けるものではないし、本件財団における「特別組織」は、単に財産の管理をするものであって経営に参加するものではないから、その権利内容は共益権とは明らかに性質が異なるなどと主張したが、上記の理由に基づきそれらの主張はすべて排斥された。
なお原告は、本件財団から一切の経済的な利益を受けていないなどとも主張したが、東京地裁は、実際に財産の給付を受けたか否かは関係なく、また、将来においても受けることができないという追加条件を財団評議会が受領したのは2019年であるから、当時の原告の権利・地位を変動させるものとは認められないとしている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























