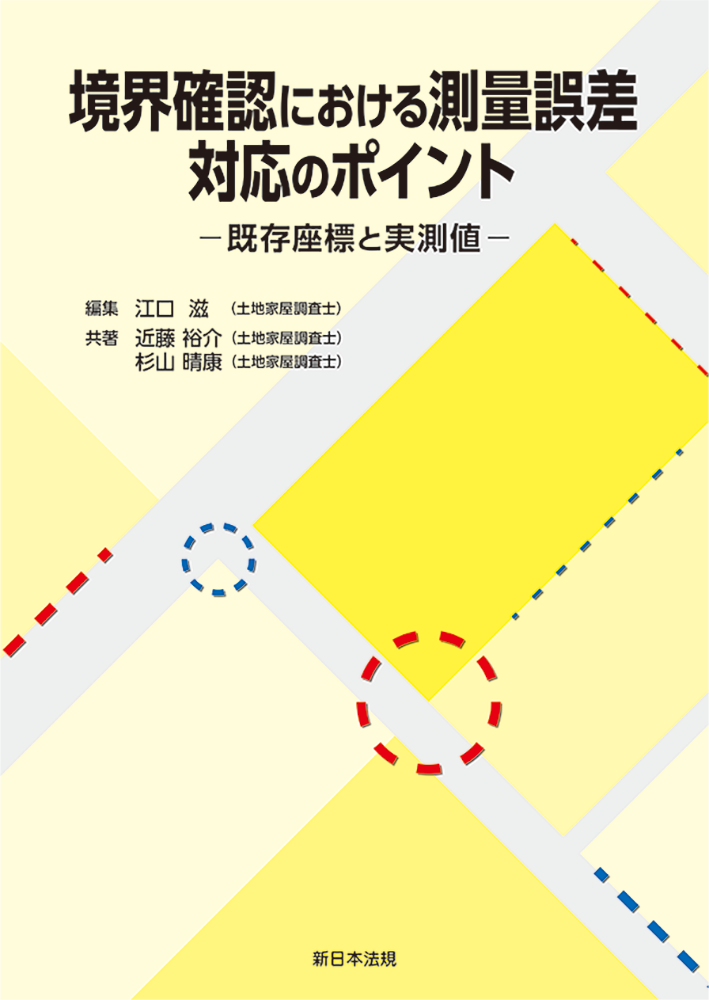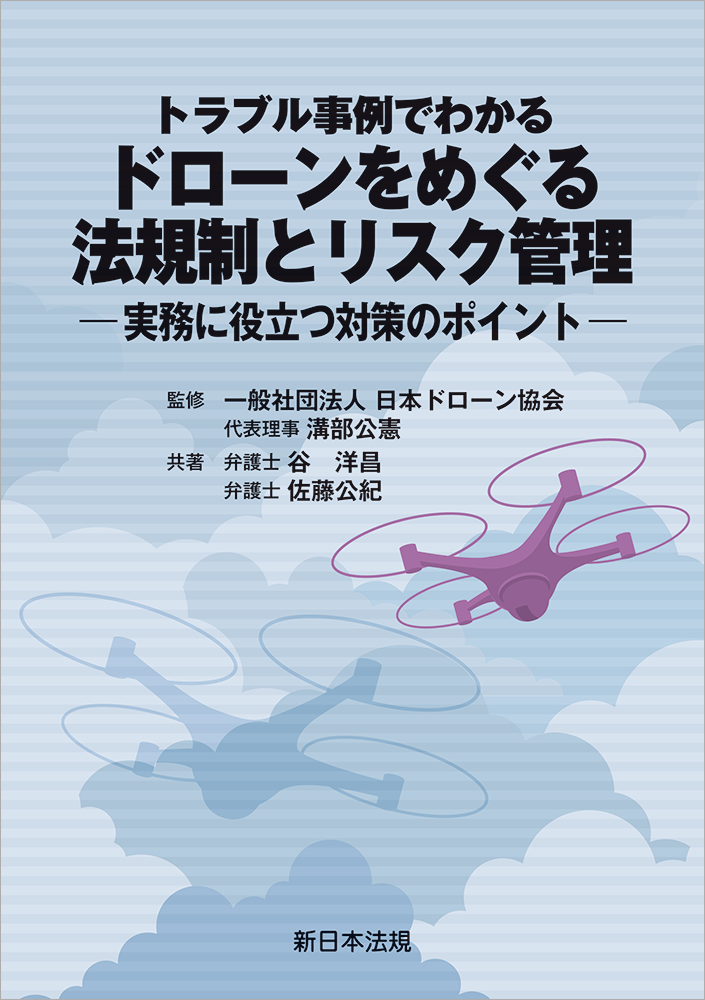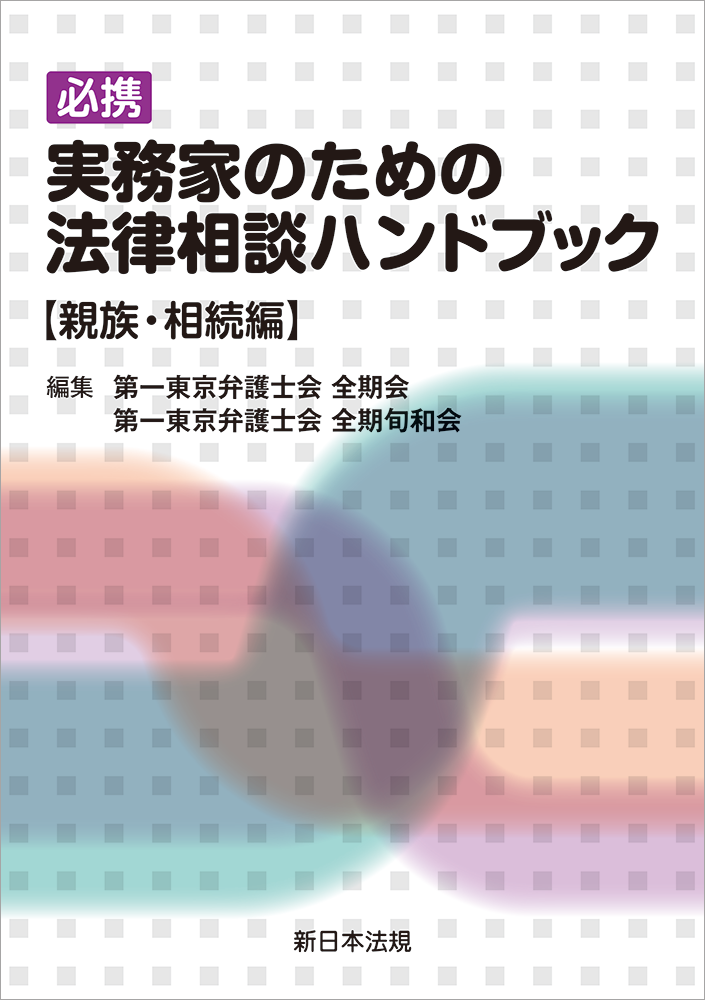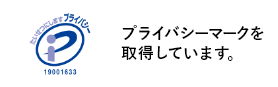解説記事2025年11月03日 解説 株主の同族会社に対する低利息貸付は経済的合理性を欠くとして所得税法157条1項を適用して未発生の利息収入(雑所得)を認定した課税処分を支持した裁決の検証(その2)(2025年11月3日号・№1097)
解説
株主の同族会社に対する低利息貸付は経済的合理性を欠くとして所得税法157条1項を適用して未発生の利息収入(雑所得)を認定した課税処分を支持した裁決の検証(その2)
中央大学名誉教授 税理士 大淵博義
(3)所得税法157条1項により個人(株主)に収入金額を認定した本裁決と現実の課税実務との齟齬・矛盾についての検証(承前)
③ 同族会社の行為計算の否認規定の解釈からの齟齬
同族会社の行為計算の否認規定の否認対象とされる行為計算は、法人税法はもとより所得税法及び相続税法においても「同族会社の行為又は計算」である。その個人(株主)やその他関係者の行為又は計算が否認の対象となるものでないことは、この「同族会社の行為又は計算」の文言から当然である(脚注17)。
ところが平和事件判決は、同族会社の行為ではなく「個人(株主)と同族会社の行為を一体」とみて、その行為(無利息貸付)が一般的には通常行われない不自然なものであると認定した。
しかしながら、それが経済取引として不自然か否かを判断するに当たって、当事者の関係等を捨象すること自体が異常不合理である。もはや平和事件判決及びそれと同様の本裁決は、先例としての価値を見い出すことはできない、と認識せざるをえない。
しかるに、所得税法157条1項及び相続税法64条1項の課税実務及び従前の判例は、営利法人である同族会社にとって利益を増加させる合理的な行為計算を否認し、株主等の所得税又は相続税を否認しているのが、現在の同族会社の行為計算の否認規定の解釈が錯綜し混乱している元凶である(脚注18)。
同族会社の行為計算の否認規定の創設経緯からは、「同族会社から株主等に対する利益の移転」による租税回避に対する「一大鉄槌であって」(脚注19)、株主等から同族会社に対する利益移転を問題としたものでないことは、すでに述べたところである。課税庁及び裁判所に反省を求めたい(脚注20)。
④ 借地権設定の課税実務との齟齬
個人(株主)の所有地に同族会社が借地権を設定する場合、その両者の関係から、権利金の授受も行わず、また、相当の地代の授受も行われない場合がある。この場合、同族会社には借地権の受贈益課税(権利金相当額)が行われるが、地主の個人(株主)には権利金の認定課税もなく、相当地代の認定課税も行われないのが課税実務である。
さらに、この両者が「借地権の無償返還の届出書」を税務署長に提出すれば、同族会社の借地権の受贈益課税も行われない。つまり、これによれば、借地権設定により地主と借地権者の双方に課税関係は発生しないというのが定着した課税実務であることは周知の事実である。
そうであれば、かかる取扱いの課税実務は、地主の個人(株主)は土地使用権を無償で同族会社に提供しているにもかかわらず、その対価の地代は受領していない個人(株主)は所得税の課税の問題は生じないというのが現行の課税実務である。
本裁決は、かかる周知の課税実務との齟齬の比較検討を捨象した結果、過去の誤った先行判決の問題点の検証も反省もなく、その判決を無防備に採用したのであろう。それでは、権利救済機関としての国税不服審判所の責務を放擲したと批判されてもやむを得ないであろう。
(4)個人(株主)に対して収受していない利息収入を認定した基本的出発点の誤謬
ア 個人(株主)の同族会社に対する過大管理料支払いの否認と転貸方式による過少賃貸料否認を同一視した基礎的誤謬の波紋
ここまでは、所得税法157条1項による個人の無利息貸付等の事例の収入認定の是非をめぐる問題である。かかる無償又は過少な収入金額を適正収入とする認定課税は、すでに述べたように、以前は否認の対象とはしていなかったところである。
それは、条文は「同族会社の行為又は計算」とされていること、加えて、法人とは異なり自然人たる個人の自由性という属性の視座からの極めて常識的な判断が前提にあったからである。
しかして、この時代に国税庁で10年間訴訟事務に従事していた筆者は、租税回避行為の否認事案を検討したことはほとんどなかったのである。
平成2年7月に転勤により国税庁の訴訟担当を離れてから、個人(株主)が同族会社に支払うマンションの過大管理料の必要経費否認事案の平成元年の東京地裁判決が言渡されたことを知ったのである。
しかし、その過大管理料の過大部分が否認されることは、「事実認定の実質主義」により、所得税法37条の必要経費該当性が否認されることは当然のことであるから、その当時はあまり興味を持っていなかったというのが現実である(脚注21)。
その後に地主の個人(株主)がマンションを同族会社に低額で賃貸、その同族会社は第三者に適正賃料で賃貸するというサブリース事件が発生した。これは、同族会社がテナントから収受した賃料収益と個人(株主)が同族会社から収受した賃料収入との差額(以下「差額収入」という。)は、個人(株主)の収入金額が同族会社に移転しているということである。この場合に、個人(株主)が同族会社に移転した賃料相当額の差額収入は、同族会社にとって経済的合理性のある行為計算であるから(脚注22)、本来、同族会社の行為計算の否認規定の趣旨目的からすれば、すでに検討したことから明らかなように、差額収入相当額を個人(株主)の収入とフィクションすることは所得税法157条1項の予定するところではない。
イ 管理会社の同族会社とサブリースの同族会社とは法的、経済的実体が異なるにもかかわらず、これを同一視した判断ミス
ところが、このサブリース方式(以下「転貸方式」という。)の同族会社の実際(実体)は、管理会社方式の同族会社と同様であるという誤った認識の下で、議論されたようである。その結果、管理会社方式の場合の過大管理料の必要経費が否認できる以上、この転貸方式の場合の収入金額も認定できるという誤解を生じさせたと思われる。
ところで、前記の過大部分の管理料が不動産所得の必要経費に該当しないことは当然のことであるが、この場合の否認の根拠は、①事実認定の実質主義による過大認定と所得税法37条の解釈適用、②所得税法157条1項による否認、の二つである。
この場合、その適用の優先順位は①によることは当然のことである。なぜならば、②は同族会社に対する支出に限定された租税回避行為につき課税庁にのみ更正権の発動を容認する特別の規定であるからである。これに対して、①は個人が過大経費等を支払った場合の全てについて、過大部分を対価性のない「贈与」と認定して、個人が過大経費等を支払った場合、相手方が同族会社に限らず、その全ての支払が否認の対象となる。
したがって、②による同族会社に限定した特別な否認規定を採用すべきではなく、①の一般原則の実質主義の適用と必要経費の解釈適用によることが合理的であることはいうまでもない。
過大管理料の否認の根拠を、①の実質主義に求めた課税処分であれば、その管理料の過大部分の支払いは個人(株主)から同族会社に対する贈与と認定されるが、その贈与の認定は、課税庁に極めて厳格な証明が求められる(脚注23)。
他方で、②の同族会社の行為計算の否認規定にその根拠を求める場合には、10社程度の類似法人の平均管理料を超える金額は過大管理料として否認され、それを判決は認めているのが実際である。
このような現状から、同族会社の行為計算の否認規定は課税庁の立証責任を緩和する規定という論者がいるが、そうであれば、同族会社に限定して、同族会社の行為計算の否認規定により不平等課税の税務執行が行なわれているという憲法違反の問題が復活するであろう。
過大管理料の否認を対価性のない贈与と認定するためには、事実認定の実質主義による認定であるから厳格な証明が求められるところ(脚注24) 、それを所得税法157条1項の租税回避行為の否認として捉えたのが、課税庁の第1のミスジャッジである。
ウ 個人(株主)の同族会社に対する貸付の賃貸料収入につき管理会社方式の管理料に基づいて認定した誤謬
さらに、所得税法157条1項により、前記転貸方式の個人(株主)から同族会社に対する低額賃貸について、同条の否認規定により適正賃料を認定する課税処分は行われていなかったのである。その課税実務が変更されるに至ったのは、所得税法157条1項を適用して過大管理料の必要経費性を否認する課税処分が先行して行われたことに基因している。
すなわち、課税庁は、同族会社の転貸方式の業務の実体は、管理会社と同様の業務内容であるという主張を展開したところ、裁判所が簡単にこれを容認して判決が言い渡され、その後も全てが納税者敗訴に終わっている(脚注25)。
しかしながら、この方式の場合には、同族会社は転貸家主の地位にあり、テナント募集の宣伝コスト、空室リスク等、家主等のリスクを負うことになり、家主の賃貸物件の管理業務とはその費用支出の性格が異なることを捨象したミスを犯している。
したがって、管理会社方式と転貸方式の法的、経済的実体の相違を捨象し同視した上で、本件同族会社の類似法人の管理会社の受取管理料に基づいて、家主の同族会社に対する適正賃料を算定したこと自体が誤謬である。それが課税庁の第2のミスジャッジである。
以上のように、個人(株主)の過大管理料否認の課税事例が先行していたこと、その後、株主から同族会社に対する3,455億円の巨額な無利息貸付の平和事件の課税問題が発生したもので、課税庁は、上記サブリースの賃貸料収入の認定課税に係る先例判決を踏まえた上で判断したものであろう(脚注26)。その結果、所得税法157条1項を適用して、収入していない利息を収入したものとフィクションして利息収入の認定課税が行われたものと推測している。
仮に、過大管理料の否認につき、所得税法157条1項ではなく、「事実認定の実質主義」により否認していれば、転貸方式の個人(株主)の同族会社に対する低額貸付の課税は回避できたのではないかと考えている。
課税当局、国税不服審判所及び司法は、ここで指摘した論点について、その大半の論点の検証を等閑視しているといわざるを得ない。
今後も、この問題点に関する課税当局の対応及び争訟における対応を注視したいと考えている。
(5)所得税法157条1項による人的役務の無償提供等と同項適用の実相とその問題点
以上、役務提供の課税処分の内容とその矛盾を紹介して検証したが、それによれば、これまでの所得税法157条1項による収入金額の認定事例は、①本裁決と平和事件判決の金銭の無利息等による貸付と、②転貸方式による個人(株主)の同族会社に対する低額賃料の貸付における適正賃料の認定課税という二つの事例である(脚注27)。
残る役務提供は、人的役務の提供に係る事例である。その典型的なものは、同族会社における役員が株主である場合、その役員が同族会社に無償又は低額な役員報酬により役員の職務に従事している場合である。
この場合には、同族会社の役員が株主である場合に限定して、かかる無償提供等を行った場合には、同族会社にとっては経済的合理性を有する行為であるにもかかわらず、金銭又は不動産等の物の貸付けが否認されている現状との平仄から、課税庁はその無償等の役員の役務提供につき、その役員に適正な役員報酬を認定課税するということにならざるを得ないであろう。
ところが、役員が無報酬又は低額報酬で役員の労務を提供している場合、所得税法157条1項を適用して、収受していない適正報酬を認定し役員報酬(給与所得)として課税対象とすることは、今までのところ行われてはいない。しかし、税務執行の課税の平等原則を堅持するという視座からも、また、ここで紹介した個人(株主)の役務の無償提供の課税当局、裁決及び税務判決の整合性からも、所得税法157条1項を適用して役員報酬の認定課税をすべきということになるのであろうか。
しかしながら、当該役員が非株主であれば、同様の無報酬等による役員の役務提供は所得税法157条1項は適用できないから、給与所得の認定課税は不可能ということになるであろう。
換言すれば、そもそも、同族会社の株主の役員が無報酬等の場合には、その認定課税を行うが、非株主の役員の場合には課税しないという現実的法益は説明不能である。それ自体論理的に矛盾、破綻しており、税法上の理論としては成り立たない解釈と考えている(脚注28)。
そして、このことは、給与所得の認定に係る源泉徴収所得税は、いかにして徴収するのか、また、その徴収義務は生じないと考えるのか、という問題に発展する。それは、すでに論じたように、「同族会社の行為計算の否認規定」(所法157①)は、同族会社から個人(株主)に対する利益の移転であるから、同族会社に対する無報酬等での役員業務の提供は、当該役員(株主)から同族会社に対する利益移転であることに照らせば、当該利益享受者の同族会社が源泉所得税の徴収義務者にはなり得ないのである。
かかる結論は「同族会社の行為又は計算」により、その株主(個人)の「所得税が不当に減少する」場合という条文からすると、すでに論じたように、その規定は、少数の株主で支配されている同族会社であるが故に行われやすい不自然、不合理な行為による同族会社から個人(株主)に対する不当な利益移転を否認するものである。したがって、役員(株主)の無償等の人的役務の提供につき所得税法157条1項を適用することは、所得税法が考慮の埒外と位置付けている事例を否認することであり、許されないと解すべきである。
すなわち、本件の私法上の取引は低率による貸付により「同族会社の所有者である株主(役員)からその同族会社に対する支援(贈与)」であり、それを否認すること自体、私法上も税法上も論外ということである。
3 「同族会社の行為計算の否認」の意義
(1)狭義の「講学上の租税回避行為」の意義と否認の意味
本裁決及び平和事件判決の問題点、疑問点に焦点を当て、そのことの問題点をより明確化するために、課税実務による租税回避の否認法理との間の齟齬等に焦点を当てたことから、上記のような構成による論考となった。そのために、租税回避とその否認とは何かという基本的な論点の検討が手薄になったことを反省しているが、紙幅との関係もあってやむを得ないものと考えている。
そこで、最後に、ドイツ租税法に由来する我が国の伝統的な租税回避の定義及びその否認の意味について考えてみたい。その上で、本裁決等がこの定義に反するものであり、そもそも租税回避行為の否認には適合しないことを論証したいと考えている。
<清永敬次京都大学名誉教授説に関して>
清永先生は「講学上の租税回避行為」の意義について、次のように適切に整理されている(脚注29)。
「税法上、①通常のものと考えられている法形式(取引形式)を納税者が選択せず、これとは異なる法形式を選択することによって、②通常の法形式を選択した場合と基本的には同一の経済的効果ないし法的効果を達成しながら、③通常の法形式に結び付けられている租税法上の負担を軽減又は排除するという形をとる。」(番号・下線は筆者)。
この意味は、①不自然、不合理な行為(異常な法形式)を選択することにより、②通常の法形式によって得られる法的、経済的成果を得ていながら、③その法的、経済的成果に沿う租税負担を回避することをいう、というものである。したがって、「不当に減少する」というのは、取引により発生している経済的成果に相応する租税負担を回避していることを不当減少というのである。
同氏は、正常な法形式を選択した場合の経済的成果に対して、相応の課税がなされ、他方、異常な法形式を採用した場合には租税負担が減免することの不平等課税を解消するために租税回避行為の否認がなされることを明言されていることに留意すべきである。
そして、その租税回避行為の否認とは、異常な法形式の選択を正常な行為計算に引き直して、課税関係を形成するというものである。ここで重要な点は、現実に顕現されている法的、経済的成果を変更するのではなく(脚注30) 、その現実の当該成果を得るための合理的な法形式に引き直して課税関係を形成するということである。
これを図解で示すと、次頁図のようになる。
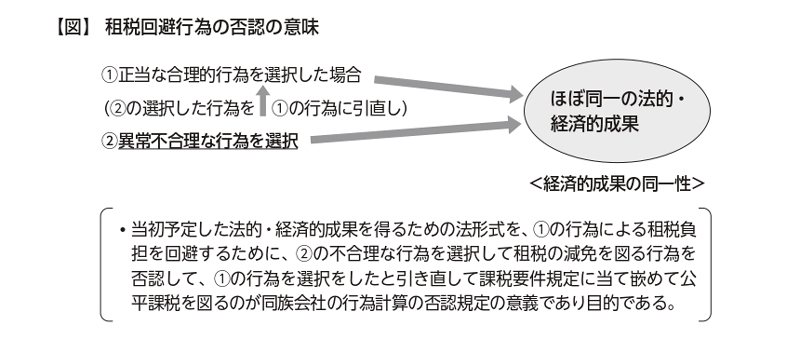
これによれば、本裁決の事例は、請求人が選択した行為は低率貸付であり、その利息収入(経済的成果)を得ているのに対して、課税庁が採用した通常の適正利率の貸付による利息収入(経済的成果)とは全く異なるという事例である。このことは、上記②の両者(請求人の低率貸付と課税庁が引直した適正利率貸付)の法的、経済的成果は、「基本的には同一の経済的効果ないし法的効果を達成している」という租税回避の要件を充足するものではない。そもそも、租税回避行為には該当しない事例ということである。
もっとも、個人(株主)が所有する同族会社の借入に際して、銀行借入の通常利息の支払による損失軽減のために、その法人の所有者である株主が低利息又は無利息貸付を行う行為が、異常、不合理ということになるはずもないことは自明であろう。しかも、本裁決のように、その貸付行為を一体としてみて(全体としてみて)、独立当事者間取引基準という法人の行為の合理性の判断基準を採用することの不合理性も明らかである。
このことは、そもそも、個人(株主)と同族会社の特異な関係を捨象して取引の正常性を判断すること自体、一般の社会通念に反することを認識すべきである。本裁決をはじめとした税務判決等の判断では、この最も重要かつ基礎的な論点が等閑視されていたことの歪みが、今、現実に顕現されているということである。
<金子宏東大名誉教授説に関して>
金子先生は、以前、租税回避行為の意義に関して次のとおり述べておられる。
「私法上の選択可能性を利用し、①私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を選択することによって、②結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、③通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除することをいう。」
この理解は、清永説と同様である。それが、ヤフー事件最高裁判決後に金子説は租税回避行為を二つの類型に分類されて説明されている(脚注31)。
第一の類型が上記の租税回避行為であり、第二の類型は、租税軽減の特例制度の趣旨目的に反するような事実関係を作出して、租税減免規定の適用を受けるケースを租税回避行為に含めることとしている。
なお、上記の第一の類型も微妙に文言が修正されている。修正後の租税回避行為の意義は次のとおりである。
「合理的又は正当な理由がないのに通常用いられない法形式を採用することによって、通常用いられる法形式に対応する租税負担の軽減又は排除を図る行為である。」(脚注32)
ここでの修正後の表現の相違は、この改定前の「租税回避行為の意義」につき、上記の説明の「②結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら」という部分が削除されたことである。
そのことが、改定前の金子説を変更したものか否かは、必ずしも明確ではない。「通常用いられる法形式に対応する租税負担の軽減排除」というのが、本裁決のように、個人(株主)の同族会社への無利息貸付等の行為が異常不合理であるとして、これを通常の法形式である適正利率による貸付に引き直すという理解に立っているとも解されるからである(脚注33)。
しかしながら、その改定後の説明後に、従前から例示として取り上げている長期間の地上権設定の事例は、その実体は資産の譲渡に等しいことを上げていることから、ここでの二つの行為(法形式)の法的経済的成果はほぼ同一であることが前提とされていることに鑑みれば、金子説は従前の清永説と軌を一にしていると解することができる。
結 語
ここでは、租税回避行為否認の態様が、比較的最近において、従前の課税実務では行われなかった否認事例が発生したことから、その拡大を回避するために、多角的な視座からの問題提起を行ったところである。
その結果、残された課題は、法人税法の否認事例では殆ど問題にされていなかった、法人税と所得税等の二重課税問題回避のためのいわゆる「対応的調整」の問題である。この点についての検討は、紙幅の関係から、今回は省略するが、結論部分のみ簡潔に述べておきたい。
過大管理料の否認は、事実認定の実質主義により、個人(株主)から同族会社に対する贈与、同族会社は受贈益として課税されるから、対応的調整は不要である。
ただ、転貸方式の場合には、ここで論じたように、個人(株主)の収入の認定課税は許されないというべきであるが、現在の税務執行を改めないのであれば、個人(株主)が通常の賃料を取得したとフィクション(擬制)して所得課税することとの対応として、その認定した賃料相当額は、同族会社の低額賃料に加算した通常の賃料の額の損金算入が認められるべきである。
それは、個人(株主)の認定賃料相当額につき、個人の所得税課税と法人税課税との二重課税の状態を是正するためには不可欠な「対応的調整」というべきである。みなし賃料の取得をフィクション(擬制)して課税する以上、法人税の所得計算では適正賃料を支払ったとフィクション(擬制)して「正常な行為計算に引き直す」ことが不可欠であると解する。
しかしながら、ここで指摘した個人(株主)と同族会社の所有者との特異な関係を考慮して、株主(所有者)による同族会社に対する無償等の役務提供は、現行所得税法の下では、考慮の埒外に措いていると認識すべきである。現在の税務執行及びそれを支持している裁決、税務判決に対して対応の改変を願いたいと考えている。
現在の税務執行は、同族会社の行為計算に限定して課税しているが、それはもはや不公平課税であることを理解し、課税対象とはしない税務執行を採用すべきであることを提唱したい。
しかし、現在の税務執行が租税正義というのであれば、そのことを証明した上で、所得税法に個別の規定を措定して、所得税法59条1項のような時価の2分の1未満等の緩和措置を設けて対処するのが、平等課税の上で不可欠なことである。
ところで、最後に述べておきたいことがある。それは、平成18年度税制改正において、いわゆる「対応的調整」が創設されたとされているが、その条文の意味が理解されないまま、現実の税務執行に生かされていないという現状にある。すなわち、本裁決でも個人(株主)の同族会社に対する低利息貸付が異常不合理として利息収入が認定課税されたにもかかわらず、同族会社に対してその認定利息の損金算入の減額更正(対応的調整)はなされていないようである。この点の「対応的調整」の財務省主税局担当者の解説書(『改正税法のすべて(平成18年版)』(大蔵財務協会・227~228頁)によれば次のとおりである。
「所得税法第157条第1項(同族会社の行為計算の否認又は計算の否認等)の規定の適用により所得税の更正があった場合に、税務署長は、法人税についても、この制度の適用により課税標準等を計算できることが明確化されました(法132③)」
これを本件に当て嵌めれば、個人(株主)の低利息貸付を適正利息貸付に引き直して認定課税した以上、当該同族会社においてもそれを支払うのが「正常な行為計算」であるから、それを同族会社の支払利息として損金算入を認めるのが、当該条項の「対応的調整」の規定である。それがなされていないのは、5年内の更正の請求が認められるべきである。
多くの論点を検証している内に、多くの紙幅を要することになったが、筆者の従前の疑問点の大半を論ずることができた。
本稿は、これまでの研究に基づく中間的集大成として位置付けている。そのために、多くの紙幅をいただいた本誌編集部のご理解、ご協力に対して心から感謝しお礼を申し上げたい。
(了)
脚注
17 このことを夙に強調しておられるのが、前記田中治教授である。例えば、田中治「所得税における同族会社の行為計算の否認規定」(財)日本税務研究センター編『同族会社の行為計算の否認規定の再検討』(2007年)81頁。同『第58回租税研究大会記録』(社)日本租税研究協会(2007年)131~132頁は、「同族会社『の』行為又は計算で、それをそのまま容認すればうんぬんと書いてありますから、法は同族会社そのものの行為を問題にするのだということです。」と説かれている。現行法の文理解釈ではかかる解釈以外には考えられない。なお、大淵博義「『所得なきところに課税なし』の原則と同族会社の『行為・計算』の否認」税理40巻9号(1997年)63頁以下も参照。
18 碓井教授は、所得税法も法人税法も「同族会社の行為計算で」とされていることから、「同族会社の行為計算の否認の規定が『同族会社』という主体に着目して定められている」と解されると指摘され、その上で、「同族会社自体の意思決定が介在する余地のない場合、又は、同族会社自体の意思決定としては合理的であるという場合には、否認できないと結論づけることが可能となる。」と明解に指摘されている(碓井光明「相続税法64条1項にいう『同族会社の行為』の意義等」判例評論280号〈判例時報1037号〉159頁)。
19 山本貞作『営業収益税法釈義』自治館(昭和2年) 379頁。
20 これに対して、時代が変化しているのであるから、租税回避行為の意義も異なってよいという論考を読んだ記憶がある。そう言うのであれば、世の中のどのような変化が、これまでの伝統的な租税回避行為の意味内容を変えることになるのかを論理的に説明するのでなければ、その反論は意味をなさない。
21 ただ、それが所得税法157条1項を適用して否認することは誤りであることは認識していたが、当時、そこに気づいて反省するまでには至らなかったことから、特別の論考は発表していなかったのである。
22 その個人(株主)の行為は、同人から同族会社に対する贈与であり、税法上、何の問題もない、ということが理解されていないということである。
23 次に述べている類似会社方式によるその平均管理料を上回る部分を贈与という甘い証明では許されないということである。
24 法基通7−3−1(高価買入資産の取得価額)では、法人が不当に高価で買い入れた固定資産について、実質的に贈与したと認められる金額がある場合に、その金額を取得価額から控除した金額を取得価額とする旨の留意通達が措定されている。この通達は、同族会社の行為計算否認ではなく、事実認定の実質主義に基づく認定である。
25 最近の事例として、大阪高裁令和7年4月25日判決(本誌No.1086 40頁)は、転貸方式による低額賃料の収入認定した課税処分を取り消した大阪地裁判決を否定して、実体とはかい離したサブリースであると認定、納税者(家主)から転貸会社の同族会社への所得移転が目的と認定し所得税法157条1項の適用による当該課税処分を適法とした。しかし、ここでも、本稿で指摘した論点(問題点)の検討は皆無である。真に遺憾というほかはない。その意味では、この裁決は明らかに疑問と言わざるを得ない。
26 仄聞するところによれば、東京地裁昭和55年10月22日判決(訟務月報27巻3号568頁)が平和事件課税の先例とされたようであるが、その事例は2年分で900万円程度の認定利息であり、それも、昭和41年の政治家の「黒い霧事件」の一つの事案に関わる共和製糖事件のグループ会社の貸付の事件である。その判決によれば、国(課税庁)は「個人の経済的合理人」なる概念を持ち出して主張し、判決はそれを疑問もなく採用して、所得税法157条1項による利息認定を支持している。しかし、課税庁の主張自体、ここで論じた問題点の全てを閑却した上での主張であり、到底、先例判決としての価値は認められない。何故ならば、「個人が合理的経済人」というのであれば、法人税法と同様の制度とすべきであり、「個人対個人」、「個人対非同族会社」の無利息貸付等も課税対象とするのが課税の公平性からの道理であろう。しかしながら、現行所得税法は、かかる法制度を採用していないことについて、この判決は何ら触れるところではない。
27 個人(株主)が所有するマンションの一室を同族会社に事務所として無償貸付等した場合の否認事例は、判決等では見当たらない。
28 佐藤英明「所得税法157条(同族会社の行為・計算否認規定)の適用について」(税務事例研究Vol.21<1994.7>64頁では、役員報酬の認定課税は慎重であるべきとされているが、赤字会社の代表取締役(株主)が役員報酬を受け取っていないときは、否認の対象となり得ることを示唆されている。ところで、佐藤論文(同書41頁以下)は、ここでの種々の論点について問題提起をされ幅広い論点を検討されている。筆者とは結論が相違するものもあるが、同論文から多くのヒントを頂いた。この点の研究をされる場合には、是非、一読をお薦めしたい。ちなみに、筆者は、過大管理料の過大部分は、既述のように、法基通7−3−1(高価買入資産の取得価額)の取扱いと同様に、税法の基本原則である「事実認定の実質主義」により否認すべきであると解している。このことから、所得税法157条1項を適用している現在の課税実務及び税務判決等から生ずる佐藤論文で指摘する問題点はその相当部分が解消できると考えている。ちなみに、上記高価買入の通達は、昭和40年前の旧法人税法の下での基本通達では、租税回避行為の一事例とされていたが、その通達廃止に伴い、法人税基本通達に組み込まれたものである。その理由は、実質主義による事実認定により高価部分は寄附金とする否認が可能であるという解釈によっている。
29 清永敬次『税法(第5版)』ミネルヴァ書房(平成11年)43~44頁
30 この点に関しては、次の論説を参照されたい。渡辺伸平「税法上の所得を巡る諸問題」『司法研究報告書』第19輯1号(1967年)28頁「税法上の実質主義・租税回避防止等如何なる理由からでも、私法上全く有効に形成された法律効果自体はこれを絶対に否定できない」。中里実「3.租税訴訟に有用な理論的フレームワーク」・中里実・太田洋・弘中聡浩・宮塚久『国際租税訴訟の最前線』有斐閣(2010年)56頁・61頁「私法上の法形成を無視して課税を行うことはできない」、「私法上の取引があり、その後の課税がある。要するに、これだけです。」。
31 金子宏「租税法(第24版)」弘文堂(2021年)134頁。ちなみに、この第二類型は、ヤフー最高裁判決を踏まえたものと考えられるが、この事件は、ヤフーの社長が被合併法人の非常勤副社長(特定役員)に就任し、その3か月後にヤフーに吸収合併された事例である。かかる場合には、みなし共同事業要件を形式的には充足しているとしても、ここでの「経営者(特定役員)引継要件」が予定する共同事業とは異なるという制度の趣旨目的に鑑み、論理的解釈(趣旨目的論的解釈)によって、みなし共同事業要件の充足を否定することにより解決すべき事件と認識すべきであろう。また、第二の類型を「租税回避行為」として理解することは、ますます、租税回避行為の理解の混乱を助長するのではないかと危惧している。
32 金子前掲書134頁。
33 金子前掲書545頁では、平和事件判決の事件を図解して紹介しているが、その判決の問題点に関する所見は述べられてはいない。しかし、同書に事件内容と判決を紹介し反対意見が述べられていない以上、金子説は同判決を支持しているという評価がなされているものと考えられる。
大淵博義 (おおふち ひろよし)
1970年中央大学商学部卒業。東京国税局直税部訟務官室、東京国税局法人税課審理係、国税庁直税部審理室訟務専門官、税務大学校教授、中央大学教授を経て、現在、中央大学名誉教授。2015年税理士登録。著書に『法人税法解釈の検証と実践的展開(第Ⅰ巻)改訂増補版、(第Ⅱ巻)、(第Ⅲ巻)』(税務経理協会)、『寄附金課税の実務』(共著)(新日本法規出版)、『最新判例による法人税法の解釈と実務』(大蔵財務協会)ほか多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -