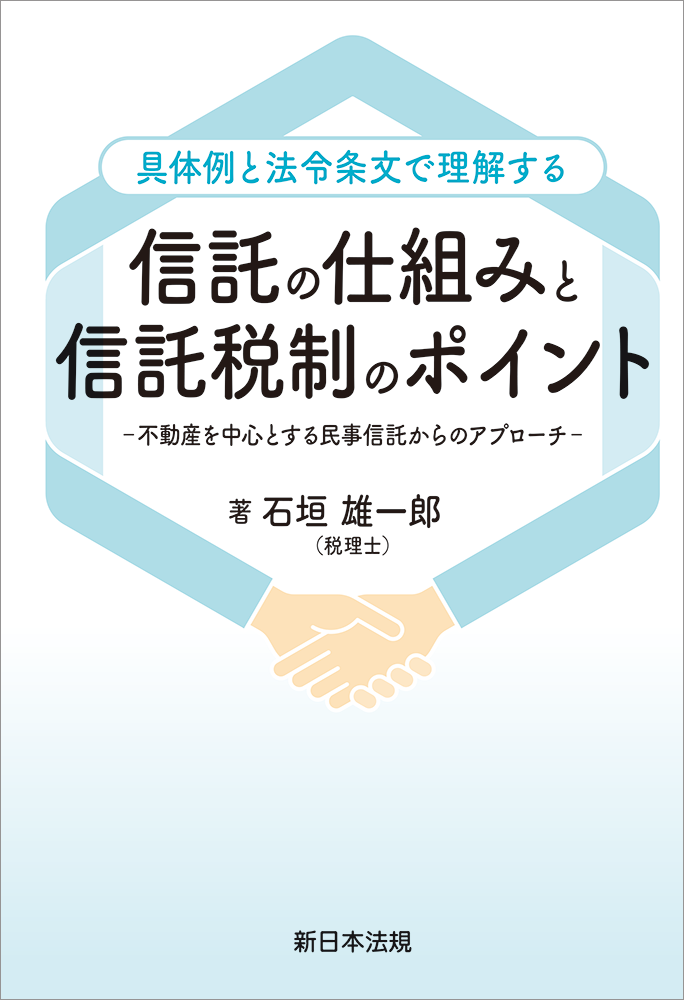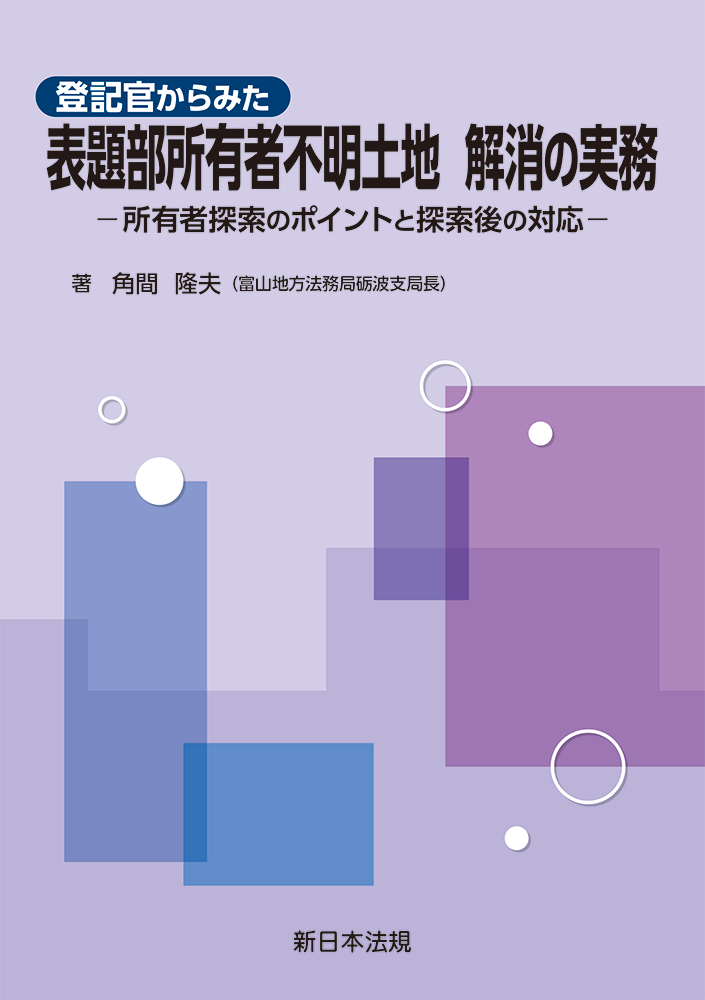税務ニュース2025年11月14日 従来型の役員退職金が損金不算入の恐れ(2025年11月17日号・№1099) 一部が業績連動なら全体を業績連動給与として指標別に損金性判定も
役員報酬の算定根拠として、業績や株価といった財務指標に加え、ESGへの対応状況など「非財務指標」を採用する上場企業が増加しているが、業績連動給与を定義する法人税法34条5項には非業績連動指標を排除する文言もないことから、非財務指標と財務指標が“混在”する役員報酬の取扱いにはかねてから疑義があったところだ。こうした中、国税庁は令和7年5月20日付で「非財務指標を組み入れた業績連動型株式報酬の税務上の取扱いについて」と題する文書回答事例を公表している。文書回答事例では、東京国税局審理課長名で「業績連動指標に加えて非業績連動指標を組み入れて支給額等が算定される給与であっても、その給与について業績連動指標を基礎として客観的に算定された部分がある場合には、その部分は損金算入業績連動給与として取り扱っても差し支えない」との見解が示されている。「その部分は損金算入業績連動給与として……」等の記述からは、文書回答事例は、法人税法34条5項では曖昧な業績連動給与の定義として、「一部でも業績連動指標が含まれていれば全体が業績連動給与に該当する(その上で、業績連動給与の損金算入要件を満たすものは損金算入業績連動給与と取り扱う)」と解釈しているものとも考えられる。
そこで問題となるのが、業績連動給与が「役員退職給与」として支払われた場合だ(実際、この文書回答事例は役員退職給与として支払われた業績連動型株式報酬についてのものである模様)。平成29年度税制改正では、業績連動給与に該当する役員退職給与は法人税法34条1項の損金算入要件を満たさない限り損金不算入とされたが、最終報酬月額に勤務期間月数を乗じてこれに功績倍率を乗ずる方法により支給額が算定される役員退職給与は業績連動給与に該当しないため、従来通り法人税法34条1項の適用対象とはならず、不相当に高額でない限り損金算入が認められる。しかし、上記解釈の結果、 一旦は“役員退職給与全体”を業績連動給与とした上で指標別に損金性を判断するならば、役員退職金の一部に業績連動要素があった場合には、これまで損金算入が可能だった非業績連動部分が損金不算入となる恐れがあろう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -