解説記事2025年11月17日 税務マエストロ インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年10月28日更新)(2025年11月17日号・№1099)
税務マエストロ
インボイスの取扱いに関するご質問(令和7年10月28日更新)
#312
税理士 熊王征秀
マエストロの解説
インボイスの取扱いに関するご質問が令和7年10月28日に更新され、新たにⅧとⅨの2題が新問として公表された。前回の更新が同年6月10日であるから、およそ4か月ぶりの更新となる。なお、前回の更新により追加されたⅤ~Ⅶの3題は、同月に改訂されたインボイスQ&A本体に取り込まれている。
今回は、令和7年10月28日の更新で追加された新問について、その内容を検証する。
問Ⅷ 令和8年10月1日前後の取引に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
当社は免税事業者と取引を行っています。例えば、令和8年9月21日から提供を受けている役務について同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う場合、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用に当たっては、80%と50%のどちらの割合を用いて計算すればよいでしょうか。また、役務の提供ではなく、商品の仕入れである場合はどうなりますか。
1 解説
非登録事業者からの課税仕入れについては、区分記載請求書等の保存を要件に、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの間は仕入税額の80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までの間は仕入税額の50%を仕入控除税額の計算に取り込むことが認められているが、令和8年10月1日にまたがる取引については、その課税仕入れの時期がいつになるかで80%(50%)経過措置の判断をすることになる。
保守点検のような役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、役務提供が完了した日になる。代金の支払日は関係しないので、たとえ未払いであっても役務提供の完了日が課税仕入れを行った日となる。
よって質問の場合には、令和8年10月20日が課税仕入れを行った日となるので、経過措置の適用に当たっては、50%経過措置により仕入控除税額を計算する。
また、商品の仕入れ(資産の譲受け)をした場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡しを受けた日となる(消基通11−3−1、9−1−1)。そのため、令和8年9月21日から同月30日までの仕入れであれば80%経過措置、令和8年10月1日から同月20日までの仕入れであれば50%経過措置により仕入控除税額を計算することになる。
なお、商品のような棚卸資産については、その種類や性質、契約内容等に応じた合理的な日に継続して売上(仕入)を計上することもできるため、引渡(着荷)基準のほか、検収基準などの方法によることも認められている(消基通11−3−1、9−1−2)。
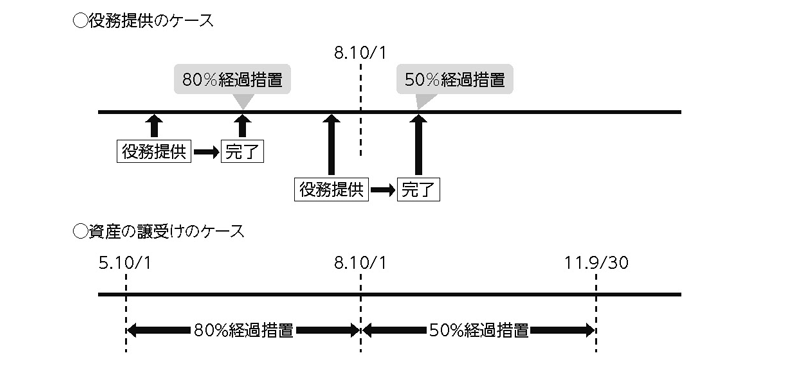
2 資産の借受けと短期前払費用との関係
資産の賃貸借による使用料については、契約又は慣習による支払日に売上(仕入)を計上することになる(消基通11−3−1、9−1−20)。ただし、いわゆる「前家賃」などについては本通達の適用除外とされているので、非登録事業者に対し、令和8年9月30日に10月分の事務所家賃を支払った場合には、契約により支払いが定められている9月ではなく、10月分の課税仕入れとして50%経過措置により仕入控除税額を計算することになる。
ところで、法人税基本通達2−2−14(短期の前払い費用)では、「前払費用」について、「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう」と定義している。そうすると、令和8年9月決算法人が10月分の家賃を支払った場合には本通達の適用により、令和8年9月決算期の損金として処理することができるとともに、80%経過措置により仕入控除税額を計算することになる(短期前払費用については次の問Ⅸを参照されたい)。
しかし、令和8年12月決算法人の場合には、令和8年9月に支払った10月分の家賃はその事業年度中に役務の提供を受けることとなるので、法人税基本通達を読む限り、短期前払費用の適用はなく、仕入控除税額の計算も50%経過措置の適用になるものと思われる。
※問Ⅷでは資産の賃貸借については何も触れられていない。
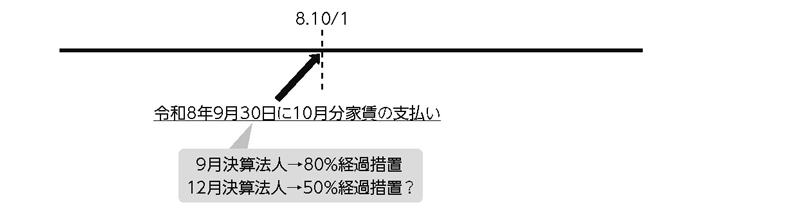
市販されている会計ソフトは、仕入先が非登録事業者であることを設定することにより、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの課税仕入れは80%経過措置、令和8年10月1日~令和11年9月30日までの課税仕入れは50%経過措置が自動適用となるよう設計されているようだ。
しかし、個人事業者と9月決算法人でない法人が令和8年9月に支払った10月分の家賃については50%経過措置の適用となるために、支払ベースで入力すると80%経過措置として仕入控除税額が過大に計算されてしまうことになる。
よって、令和8年9月支払分については、面倒でもいったん前払費用として処理した上で、10月になってから振替処理をする必要があるように思われる。
問Ⅸ 短期前払費用に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の適用
当社は、3月決算法人です。取引先との保守契約に基づき、毎年1月にその年1年間分(1月から12月分)の保守料金を支払った上で、短期前払費用として処理しています。当該取引先は適格請求書発行事業者ではないのですが、令和8年3月期の消費税の確定申告において、令和8年1月に支払う令和8年1月から12月分の保守料金の全額について、その仕入税額相当額の80%を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができますか。
1 解説
法人税(所得税)の計算では、支払日から1年以内に提供を受ける保守料などを前払いした場合には、その支払額を継続して支払日の属する事業年度(年)の経費に計上することを条件に、損金(必要経費)とすることを認めている。
消費税の計算においても、法人税(所得税)でこの「短期前払費用」の規定の適用を受けた課税仕入れについては、その支出日の属する課税期間における課税仕入れとして取り扱うことが認められている(消基通11.3.8)。
そこで、令和8年9月30日までに短期前払費用の取扱いを受ける課税仕入れを非登録事業者から行った場合には、たとえ令和8年10月以降の期間に対応する部分があったとしても、80%経過措置による仕入控除税額の計算を認めることとしたものである。
よって質問の場合には、令和8年分の保守料1年分を同年1月に支払い、短期前払費用として処理していることから、令和8年10月.12月期間分についても80%経過措置により仕入控除税額を計算することができる。
(注)インボイス制度における短期前払費用の取扱いは「インボイスQ&A問98」を参照されたい。
2 短期前払費用として処理した金額が変動した場合
翌課税期間以後に契約変更等があったため、短期前払費用として処理した金額が変動した場合には、修正申告や更正の請求ではなく、変動が生じた課税期間における仕入税額に加減算することにより調整する(インボイスQ&A問96)。
この場合の調整金額は、当然に80%(50%)経過措置を適用した仕入税額により計算することになる。
記事に関連するお問い合わせ先
記事に関するお問い合わせは週刊「T&Amaster」編集部にお寄せください。執筆者に質問内容をお伝えいたします。
e-mail:ta@lotus21.co.jp
※なお、内容によっては回答いたしかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























