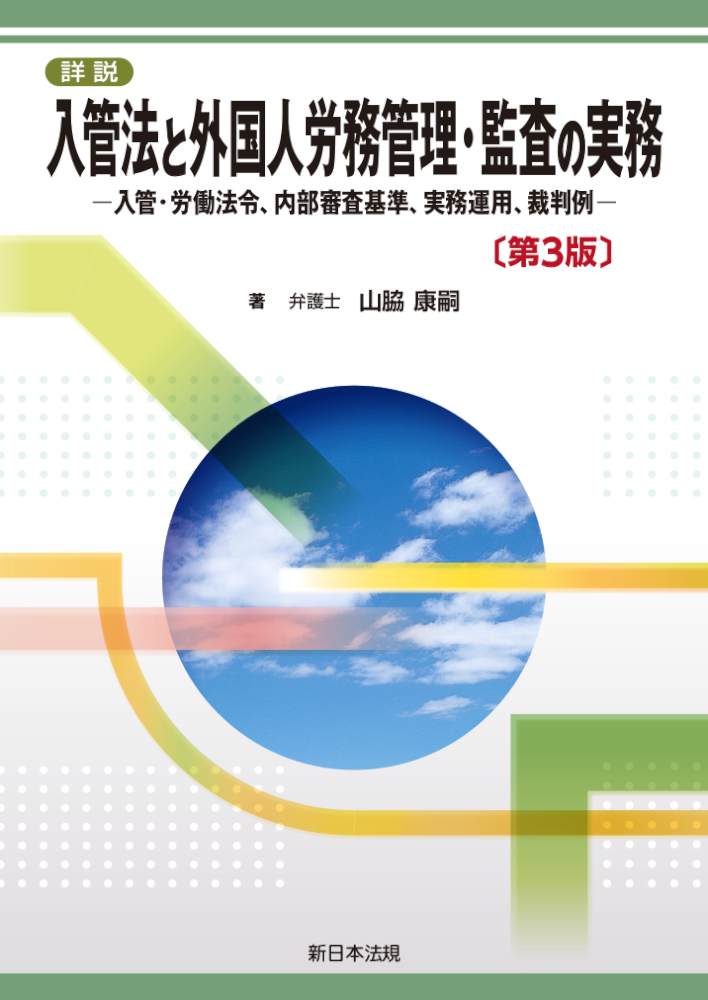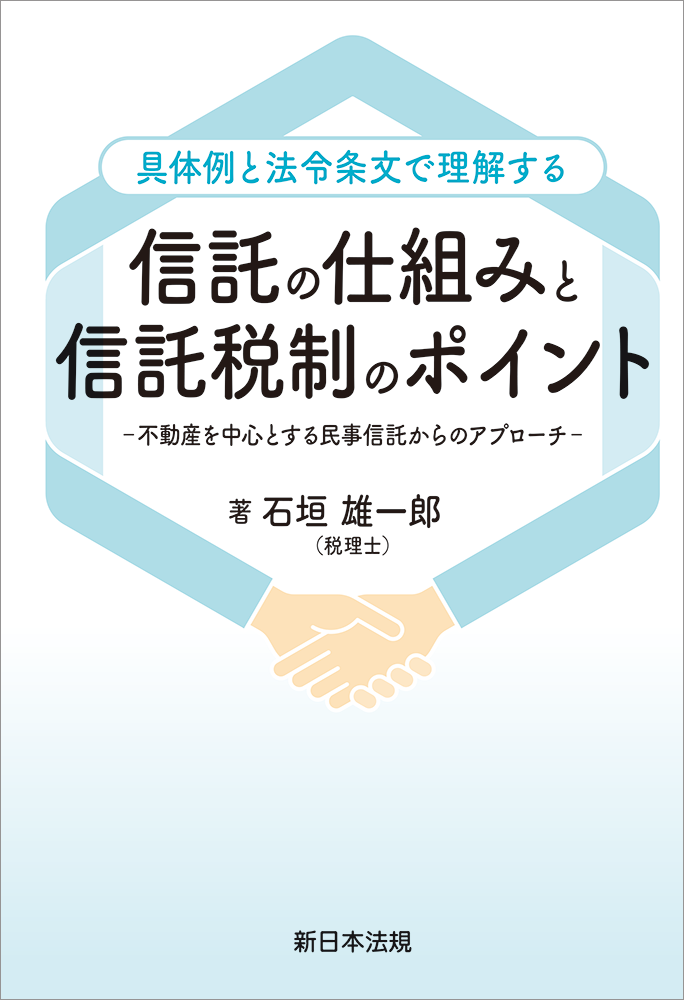税務ニュース2025年11月28日 亡元夫からの高額送金に第二次納税義務(2025年12月1日号・№1101) 地裁、生活費や学費に必要な範囲を超え無償譲渡等の処分に該当と判断
原告は別居中の夫から、夫の株式売却収入を原資とする1,000万円の送金(本件送金)を受けた。原告と夫は令和3年5月に離婚が成立し、元夫は同年6月に死亡した。処分行政庁は、亡夫の滞納国税約330万円を徴収するため、原告に対し、本件送金は国税徴収法39条に規定する無償譲渡等の処分に該当するとして、原告が1,000万円を限度として第二次納税義務を負う旨の納付告知処分を行った。
東京地裁は、①亡夫の給与収入を家庭裁判所で活用されている婚姻費用算定表に当てはめると、本件送金時に亡夫が支払うべき婚姻費用の額は月額16ないし18万円であること、②亡夫は、平成29年1月から令和3年4月までの間に合計約1,835万円の定期送金をしていた上、本件送金の2か月前に400万円及び600万円の送金をしていること、③本件送金当時、原告及び子らに、現実的に高額な子らの学費の支出を必要とする具体的な事実があったとは認められないことなどを指摘。これらの点から、本件送金は、生活費や学費等として必要な額としての範囲を超えているものといわざるを得ず、原告に異常な利益を与えるものであって、実質的にみてそれが必要かつ合理的な理由に基づくものということはできないとして、本件送金は無償譲渡等の処分に該当するとの判断を下した。
原告は、亡夫が、子らの6年制医学部への進学や海外留学を想定して本件送金をしたのであるから、必要かつ合理的な理由があると主張した。これに対し東京地裁は、原告が実際に子らのために海外留学で高額な費用を捻出しなければならなかったような事実もなく、原告が令和4年3月まで本件送金による1,000万円には手をつけなかった事実などからすると、本件送金当時、仮に原告及び子らが近く高額な学費等の支出が必要となるものと予測していたとしても、かかる予測について具体的な裏付けがあったとまでいうことはできないとして、その主張を斥けた。
また、「本件送金は将来の婚姻費用又は養育費の弁済の一部としてされたもの」との原告の主張も、原告は本件送金を受けた後も原告と亡夫が離婚する直前の令和3年4月まで定期送金を受けており、本件送金によって将来の婚姻費用支払義務又は養育費支払義務が一括して履行されたものと評価することはできないとして斥けている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -